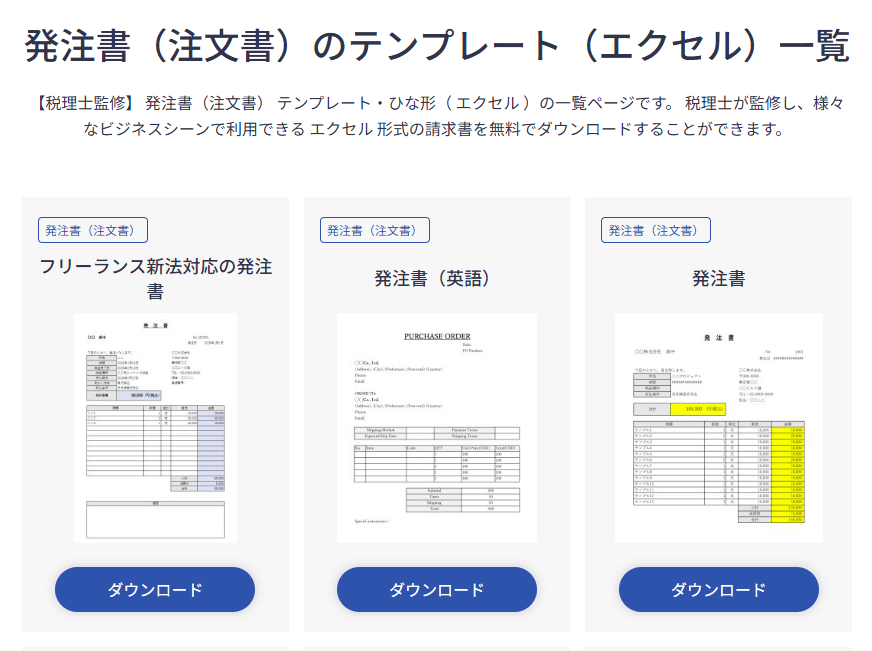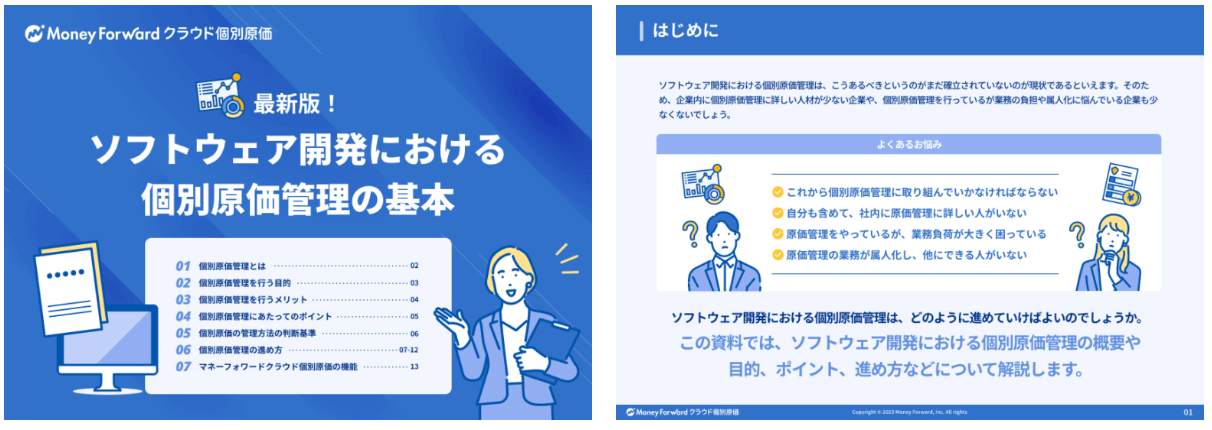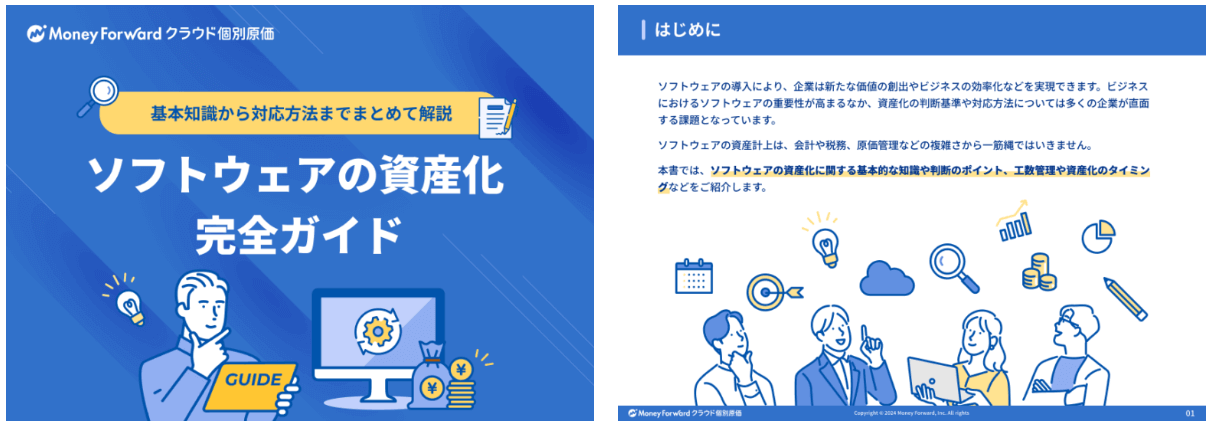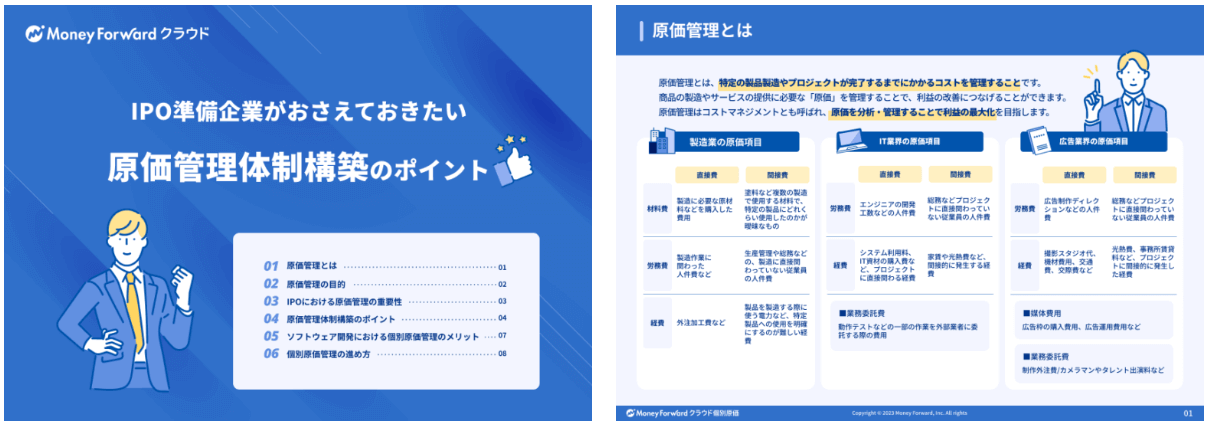- 作成日 : 2025年8月5日
発注申請が進まない理由と効率化の方法、発注書のメール例文も紹介
発注申請は、会社が物品やサービスを購入する際に、社内で必要性や予算を確認し、承認を得るための手続きです。流れを理解し、正しい申請や書類作成、メール対応を行うことで、ミスやトラブルを防げます。この記事では、発注申請の基本から、流れ、書類の書き方、メール例文、効率化の方法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
発注申請とは
発注申請は、社内で物品やサービスを購入する前に、必要性や予算を確認し、上司や担当部門の承認を得る手続きです。購買業務の起点となるこの申請がなければ、発注処理は進められません。
発注申請は、無駄な支出を防ぎ、業務に必要な品目だけを確実に手配するための管理手段です。予算内での調達を徹底し、承認ルートを明確にすることで、不正やミスを防ぎ、社内のコンプライアンスを保つ役割もあります。
発注申請書には、申請者の部署名、申請日、品目名、数量、単価、合計金額、希望納期、発注先などの項目が含まれます。多くの企業では、紙の書類ではなくワークフローシステムを活用し、申請・承認・管理を一元化しています。
発注申請を行う例
発注申請は、日常的な備品の購入から外注業務の依頼まで幅広く活用されます。以下のような業務や業界で日常的に行われています。
- 製造業:部品や原材料の調達時に
- 建設業:資材の購入や外注工事の契約時に
- IT業界:システム開発やクラウドサービスの利用契約に
- 事務部門:文具、コピー用紙、OA機器の買い替え時に
たとえば、事務所でプリンターが故障した場合、直接購入するのではなく、まず発注申請書を作成して上長の承認を得てから発注処理が行われます。これにより、会社全体のコスト管理が可能になります。
発注書と注文書との違い
発注書と注文書は、「取引先に発注(注文)の意思を示すために発行する書類」という点で同じ書類です。しかし、企業によっては、要望に合わせた加工などが必要な場合や金額が大きい場合に「発注書」を、加工が不要な商品を購入する場合に「注文書」を作成するなどして、区別するケースもあります。
発注書や注文書の作成は法律上の義務ではありませんが(下請法が適用される場合を除く)、契約トラブルを防ぐために実務上は欠かせません。 また、下請法に該当する取引では「書面の交付義務」があるため、発注書などの発行が必要となります。
発注申請のフロー
発注申請のフローは、社内での申請から実際の発注、納品、検収、支払いまでの一連の業務手順を指します。業務の正確さとコスト管理の両立のためには、発注から納品までの流れを標準化し、関係者の役割分担を明確にしておく必要があります。
発注申請の基本的な流れは以下のとおりです。
① 申請者が発注申請書を作成
まず、物品やサービスの購入を希望する社員(申請者)が「発注申請書」を作成します。申請書には以下のような情報を記入します。
- 品目名・型番・仕様
- 数量・単価・金額
- 発注先(業者名)
- 希望納期・納品場所
- 目的や使用予定
申請書は手書きやExcelではなく、社内のワークフローシステムで作成・提出されることが一般的です。申請時に見積書を添付するルールの企業もあります。
② 上長や担当部署の承認
申請書が提出されたら、次に上司や管理部門(経理・総務・購買担当など)の承認を得ます。承認フローは、購入金額や物品の種類によって段階的に変わる場合があります。
- 少額購入:上長のみ承認
- 高額購入:部門長→管理部門→役員など複数段階
この承認ステップで、予算内かどうか、業務上の必要性があるかがチェックされます。
③ 発注書の作成・送付
承認が完了したら、購買担当者が発注書を作成し、取引先に送付します。発注書は、正式な注文の意思を示す文書であり、契約の根拠にもなります。
発注書の送付手段は、メール、FAX、電子契約システムなどが一般的です。最近では、クラウド上で発注書を自動作成し、ボタン1つで送付できるシステムも増えています。
④ 納品と検収
取引先から商品が納品された後、受領担当者が「納品内容の確認(検収)」を行います。内容は以下の項目です。
- 品目と数量の確認
- 破損や不良品の有無
- 納品書との照合
検収が完了したら、納品書に押印する、もしくはシステム上で受領確認ボタンを押すなどの処理を行います。これにより、後の支払い業務に進める状態になります。
⑤ 請求書の確認と支払い
検収が終わった段階で、取引先から請求書が届きます。経理担当者は、請求書の金額と発注書・納品書の内容が一致しているかを確認し、支払い処理を行います。
このタイミングで不一致がある場合、検収や発注書を遡って確認し、取引先と調整を行う必要があります。
この一連の流れを社内でルール化し、関係部門が連携して動ける体制を整えておくことが、効率的でトラブルの少ない発注処理になります。
発注書の書き方
発注書は、企業が取引先に対して「この内容で正式に注文します」と通知する文書です。発注書には、業務に必要な内容を過不足なく記載することが重要です。
基本的には定型の様式を使う企業が多く、最近ではクラウド型の発注システムによって自動作成されるケースもあります。
発注書に記載するべき項目
発注書には最低限、以下の情報を記載します。これは取引先との契約内容の根拠にもなるため、正確な入力が求められます。
- 発注日:注文を確定した日付
- 発注番号:社内で管理する注文番号(照会時に使用)
- 取引先情報:会社名、担当者名、住所、連絡先
- 発注元情報:自社の担当者名、部署、連絡先
- 品目情報:品名、型番、仕様、数量、単価、金額
- 納品希望日・納品場所:具体的な納期と納品先を明記
- 支払い条件:締日や支払い方法(請求書払い・月末締め翌月末払い等)
- 備考欄:特記事項がある場合(例:分納不可、納品方法など)
これらの項目をもれなく記載することで、注文内容の誤解を防ぎ、スムーズな取引につながります。
発注書を書くときに注意すべき点
正しく発注書を作成するためには、以下の点に注意が必要です。
- 見積書と内容が一致しているか確認する
価格や仕様に相違があると、納品後のトラブルの原因になります。事前に見積書を確認し、同じ内容を反映させます。 - 納品日と希望納期を明確に書く
あいまいな表現(例:「できるだけ早く」)ではなく、「〇月〇日納品希望」と具体的に記載することで誤解を防げます。 - 取引先名を正式名称で記載する
通称や略称を使わず、法人格(株式会社など)を含めた正式名称を記載します。 - Wordで作成した場合はPDF化し編集不可にする
送信後に内容を書き換えられないようにするため、PDF化して送付するのが一般的です。
発注書のテンプレート
発注書を作成する際はテンプレートがあると便利です。マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。
発注申請メールの書き方と例文
発注申請メールは、申請内容をわかりやすく簡潔に伝え、発注の確認や承認がスムーズに進むようにしましょう。
件名・本文の構成・敬語の使い方まで丁寧に整えることで、ビジネス上の信頼を損なわず、確認漏れを防ぐことができます。
社内向け発注申請メールの例文
件名:発注申請(営業用ノートパソコンの購入)
本文:
総務部 ○○様
お疲れさまです。営業部の□□です。
下記の通り、ノートパソコン購入について発注申請をいたします。ご確認の上、承認をお願いいたします。
■ 発注内容
品名:ノートパソコン(型番:XYZ-456)
数量:2台
単価:95,000円
金額:190,000円(税抜)
納品希望日:2025年6月5日
納品場所:本社5階 営業部
■ 購入理由
新入社員の業務用端末として支給するため。
■ 添付資料
- 見積書(PDF)
- 発注申請書(Excel)
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
――――――――――――――――
営業部 □□
内線:1234
メール:□□@example.co.jp
――――――――――――――――
社外向け発注書送付メールの例文
件名:【発注書送付】ノートパソコン購入の件(XYZ-456/2台)
本文:
○○商事株式会社
営業部 ○○様
いつもお世話になっております。〇〇株式会社の□□です。
下記内容にて、ノートパソコンの発注をさせていただきます。発注書を添付いたしますので、ご確認をお願いいたします。
■ 発注内容
品名:ノートパソコン(型番:XYZ-456)
数量:2台
単価:95,000円
合計金額:190,000円(税抜)
納品希望日:2025年6月5日
納品場所:〇〇株式会社 本社5階 営業部
■ 支払い条件
月末締め翌月末払い
■ 添付ファイル
- 発注書(PDF)
納期や不明点がありましたら、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――
〇〇株式会社
営業部 □□
TEL:03-xxxx-xxxx
Email:□□@example.co.jp
――――――――――――――――
発注申請を効率化するポイント
発注申請がスムーズに進まない原因は、業務フローが不明確、手作業が多い、承認の滞留などが挙げられます。こうした課題は、仕組みやルールを見直し、システム化によって改善できます。申請から支払いまでを整理し直すことで、作業時間を削減し、ミスや抜け漏れも減らせます。
ワークフローシステムで承認の遅れを解消
発注申請や承認をメールや紙で行っていると、担当者不在時に滞る、過去の申請履歴が追えない、などの問題が起こります。ワークフローシステムを使えば、以下のような改善が可能です。
- 申請や承認のステータスがリアルタイムで確認できる
- 承認依頼が自動通知され、放置されにくくなる
- 全申請書類を一元管理でき、過去の記録をすぐ参照できる
クラウド型のサービスを利用すれば、初期費用やIT部門の負担を最小限に抑えながら導入できます。
発注書のテンプレート化と自動作成
発注書を毎回手入力で作成していると、作業時間がかかり、ミスも発生しやすくなります。定型フォーマットを用意し、入力欄を必要項目だけに絞れば、記入ミスや漏れが減ります。
さらに、発注申請内容をもとに発注書を自動作成できるツールを活用すると、以下のような効率化が可能です。
- 発注書PDFを自動生成し、メールに添付して送信
- 社内控えが自動で保存され、手動ファイリングが不要
この仕組みにより、発注書の作成・送付が数分で完了するようになります。
過去の発注履歴をデータベース化する
毎回同じ取引先に似た内容を発注しているのに、履歴を都度探す手間がかかる場合、過去のデータをデジタルで整理しておくと効率が上がります。
検索可能な発注履歴を整備すると、
- よく使う品目をすぐ再発注できる
- 単価や納期の比較ができる
- 過去の納品トラブルなどの記録を確認できる
発注処理が担当者の記憶やメール履歴に依存している状態は、非常に不安定です。履歴を共有できる状態にしておくことで、担当交代時にもスムーズな引き継ぎが可能になります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
入金消込をエクセルで自動化したい!関数・マクロの活用方法を紹介
入金消込は、煩雑な作業であるうえ、ミスが許されない作業のため、なんとか自動化できないかと模索中の人もいるでしょう。本記事では、入金消込をエクセルで自動化する方法を解説します。 その…
詳しくみる為替手形と約束手形の違いは?初心者にもわかりやすく解説
ビジネスにおける資金のやり取りでは、現金や振込に加えて「手形」という決済手段が長年活用されてきました。中でも「約束手形」と「為替手形」は、企業間の取引や信用の証として広く利用されて…
詳しくみる支払管理表エクセルの作り方!スプレッドシートとの違いや効率化を解説
経費や請求の支払い管理を正確に行うことは、会社の資金繰りを安定させるために重要です。この記事では、エクセルで支払管理表を作成する方法、Google スプレッドシートとの違い、さらに…
詳しくみる返還インボイスと適格請求書の金額は相殺できる?書き方や仕訳も解説
返還インボイス(適格返還請求書)は、売上に対して返品や値引きなどがあったときに、適格請求書発行事業者が発行する書類です。インボイス(適格請求書)とは記載項目が異なるため、分けて考え…
詳しくみるファクタリングを断られた!審査に通らない理由と資金調達を成功させるための対策
「ファクタリングを断られる理由が知りたい」 「ファクタリング会社の選び方を知りたい」 「審査を通過するためのポイントはある?」 上記のように、ファクタリングの審査についてお悩みの方…
詳しくみる未払金台帳とは?買掛金との違い、テンプレートを基に書き方を解説
未払金台帳は未払金を管理する台帳です。未払金とは営業外の単発的な取引から発生する費用のことです。未払金台帳をつけることで、支払のミスを防止したり、資金繰りに役立てたりできます。紹介…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引