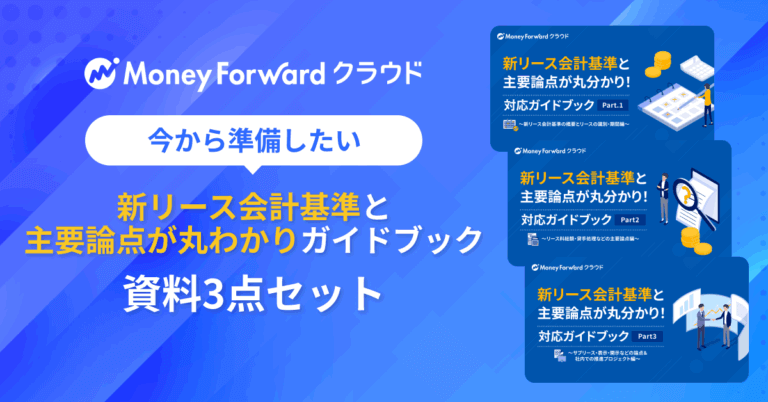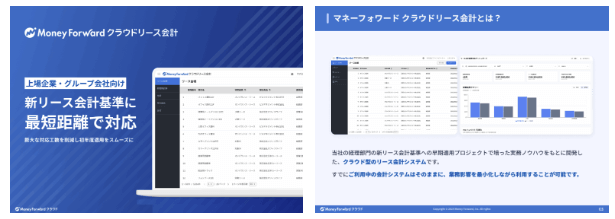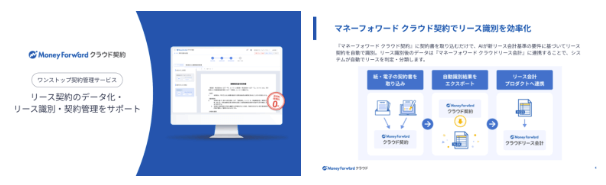- 更新日 : 2025年9月4日
ifrs17とは?ゼロから学べる保険会計の基本をわかりやすく解説
ifrs17は、2023年1月1日に適用された、保険契約の会計の処理に関する新しい基準です。ifrs17について、聞いたことはあるけれどどんな内容なのか分からない方や、難しそうだと感じている方も多いと思います。
本記事では、「ifrs17」とはどんなものなのかをゼロからわかりやすく解説します。難しい専門用語もできるだけ嚙み砕いて解説し、初心者でも読みやすい内容にしました。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
ifrs17は、保険契約の会計処理における新基準
ifrs17は、国際財務報告基準(IFRS)の1つです。
ifrs17は、保険契約の会計処理の新しい基準で、「ifrs4」と代わって2023年1月1日に適用されたものです。ifrs第17号保険契約とも呼ばれます。
国際会計基準審議会(IASB)が2017年5月17日に公表し、「最初の真に国際的な保険契約の会計基準」と位置付けています。
ifrs17が公表されるまで、保険業界には世界的に統一された会計基準はありませんでした。そのため、ifrs17は全く新しい会計基準となり、世界中のどの保険会社にとっても大きな影響が与えられたのです。
ifrs17は保険契約の会計処理を国際的に統一し、財務報告により透明性をもたせ、保険会社の業績などのわかりやすい比較を可能なものにするための新基準となっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
ifrs17の目的
ifrs17は、保険会社のわかりやすい比較をするため、保険会社の財務状況などに透明性をもたせるためという目的があります。
以下でそれぞれ詳しく解説します。
目的①保険会社の業績などをわかりやすく比較できるようにする
ifrs17の1つ目の目的は、保険会社の業績などをわかりやすく比較できるようにすることです。
従来は、企業・国・地域ごとに保険会社の会計処理は異なっており、同じ保険商品でもそれぞれ違った方法で収益や負債が計上されていました。
従来の方法に対して、ifrs17では保険契約の定義や保険負債の測定方法が統一され、企業間で統一した会計処理が適用されたため、財務諸表利用者による企業の比較や地域間の比較などがわかりやすくなったのです。
ifrs17では保険負債の測定方法は以下の3つがあり、条件によっていずれかの測定方法で測定することが求められています。
- ビルディング・ブロック・アプローチ(BBA)
- 変動手数料アプローチ(VFA)
- 保険料配分アプローチ(PAA)
ビルディング・ブロック・アプローチ(BBA)とは、ifrs17の一般的な測定方法であり、将来キャッシュフローの見積り、貨幣の時間価値の調整、リスク調整、契約上のサービスマージンの4つのビルディング・ブロックに基づいた保険負債の測定です。
変動手数料アプローチ(VFA)とは、BBAに調整を加えた測定方法であり、直接連動有配当契約に適用されます。
保険料配分アプローチ(PAA)とは、保険契約期間が1年以内であるなど、一定の条件を満たす場合に適用される、BBAの簡便法です。
目的➁保険会社の財務業績や保険負債に透明性をもたせる
ifrs17の2つ目の目的は、保険会社の財務業績や保険負債に透明性をもたせることです。
従来は、保険契約の最新状況を反映しておらず、有用な財務状況の提供がされていなかったり、貨幣の時価を考慮しておらず、保険契約の経済価値を適切に表していなかったりする場合がありました。
また、契約時に保険料収入を一括で計上していたため、実際のリスク負担やサービス提供のタイミングと収益計上のタイミングが一致しないこともありました。
それに対してifrs17では、最新の計算前提に更新されることで、企業の予測をより適切に表せたり、保険契約が現在の経済価値で測定されたりできます。
また、貨幣の時価を考慮して計算されることで、保険契約の経済価値を適切に表すことができるようになりました。
そして、収益は契約時に一括で計上するのではなく、契約期間にわたって計上する、契約サービス・マージンが導入されています。
IFRSとは世界共通の会計基準のこと
IFRS(イファース/アイファース)とは、国際会計基準審議会(IASB)が策定している国際会計基準(世界共通の会計基準)のことです。
会計基準とは、企業が財務状況を示すために作成する財務諸表の作成ルールを指します。
EU加盟国では、導入が義務付けられており、それをきっかけに世界各国での導入が広がっているのです。
以下でIFRSと日本の会計基準の違いや日本でのIFRSの導入状況について詳しく解説します。
日本の会計基準との違い
IFRSと日本の会計基準の違いを以下にまとめました。
| IFRS | 日本の会計基準 |
|---|---|
| 原則主義 | 規則主義 |
| 賃貸対照表を重視(資産負債アプローチ) | 損益計算書を重視(収益費用アプローチ) |
日本の会計基準では、数値など細かいルールを規定する規則主義が採用されているのに対して、IFRSでは考え方の原則だけ定められている原則主義が採用されています。
また、日本の会計基準では損益計算書を重視し、収益や費用を会計の中心概念として考え、収益と費用の差額を利益として算出する収益費用アプローチであるのに対して、IFRSでは、賃貸対照表を重視し、企業の資産と負債を重視の変動を基に利益を算出する資産負債アプローチが導入されているのです。
また、IFRSは日本の会計基準と違って、グローバル基準であり、定義も英語でされています。
日本のIFRS導入状況
日本ではIFRSの導入は義務化されておらず、2025年2月末時点での導入状況は以下のようになっています。
| IFRS適用済み会社数 | 279社 |
|---|---|
| IFRS適用決定会社数 | 9社 |
2025年2月末時点での日本の上場会社数は3,962社であり、日本でのIFRS導入率は1割にも満たない状況です。
参考:IFRS導入状況
IFRSを導入するメリット
IFRSを導入することで得られるメリットはたくさんあります。
ここでは、IFRSを導入するメリットを4つ紹介します。
メリット➀海外からの資金調達がしやすくなる
IFRSを導入することで、海外からの資金調達がしやすくなります。
海外の投資家からすると、日本の会計基準によって作成された財務諸表では企業の財務状況を正しく把握しにくかったり、他の企業との比較がしにくかったりします。
そのため、海外の投資家に出資をお願いする場合には、IFRSと日本の会計基準との違いを説明する必要があり、時間が大幅にかかったり、説明してもきちんと理解してもらえない可能性があるのです。
IFRSを導入し、IFRS基準の財務諸表を作成すれば、海外の投資家がスムーズに企業の財務状況を把握でき、資金調達がしやすくなるメリットがあります。
メリット➁海外にある子会社の経営状況を管理しやすくなる
IFRSを導入すれば、海外に子会社がある企業が、その経営状況を管理しやすくなるというメリットがあります。
海外に子会社をもつ企業の場合、日本の会社は日本の会計基準で、海外の子会社はIFRSでと分けると、財務諸表の作成方法などが違うため、経営状況の把握や比較が難しかったり、時間がかかったりしてしまいます。
IFRSを導入し、日本の会社と海外の子会社で同じ会計基準にすることによって、経営状況の管理や、財務情報の把握や比較がスムーズにできるようになるのです。
メリット➂国際取引の際に財務諸表をそのまま利用できる
IFRSを導入することで、国際取引の際に作成した財務諸表をそのまま利用できるメリットがあります。
日本の会計基準で作成した財務諸表は、作成の基準や方法がIFRSとは違うため、国際取引用に変更する必要があるのです。
IFRSを導入すれば、国境を越えた取引をする場合にIFRSの財務諸表をそのまま利用できるため、日本の会計基準で作成した財務諸表を国際取引用に作成し直す手間が省けます。
メリット➃企業のイメージアップにつながる
IFRSを導入することで、企業のイメージアップにつながるメリットもあります。
IFRSは国際的な会計基準であるため、「質の高い経理業務を行っている」と投資家や金融機関、取引先から評価されやすいのです。
投資家や金融機関、取引先から評価され、企業のイメージアップにもつながるでしょう。
IFRSを導入するデメリット
IFRSを導入することで発生するデメリットもあります。
IFRSを導入する際には、メリットだけでなくデメリットも把握し、損益を考える必要があります。
デメリット➀導入にコストと時間がかかる
IFRSへ移行する際には、時間とさまざまなコストがかかります。
かかるコストには、調査コストや監査報酬、システム導入、変更・更新などがあります。
企業の規模が大きいほどコストがかかる傾向があり、IFRSへの移行が完全に完了するまでもコストがかかることを踏まえておきましょう。
IFRS導入には時間もかかるため、導入が決定したら計画的に、早めに着手することが大切です。
デメリット➁事務負担が増加する
IFRSを導入することで、事務負担が増加するデメリットもあります。
IFRSを導入すると、従来とは違い、規則主義から原則主義に変更して財務諸表を作成しなければなりません。
日本の会計基準の規則主義では、数値などの細かいルールが設けられていますが、IFRSの原則主義では数値などの細かいルールはなく、考え方などの原則だけが定められています。
そのため、IFRSを導入し財務諸表を作成する際には、判断理由を注記する必要があり、事務負担が増えます。
またIFRS導入によって、計上範囲が広がり資産を時価で評価し直す業務や、IFRSに基づいた財務諸表と日本の会計基準に基づいた財務諸表の両方を作成する業務など、さまざまな業務の負担が増加するのです。
デメリット➂適用のハードルが高く難しい
IFRSの導入には、適用するハードルが高く難しいというデメリットもあります。
IFRSの規定は日本のビジネス慣行や法令にフィットしていないため、解釈が難しいのです。
IFRSに基づいた財務諸表の作成は、すべて英語で作成する必要があり、高度な英語スキルをもっていないと導入後も難しいと感じることがあるでしょう。
また、すべて英語で記載されていることに加えて定められている基準の更新も頻繁に行われることがあるため、適用や慣れるまでのハードルが高く難しいと言えます。
そのため、IFRSに詳しい人材や高度な英語力をもつ人材の確保が重要です。
ifrs17導入の流れ
ifrs17の導入のおおまかな流れは以下の通りです。
- 導入に必要な準備(システムの改修・変更/人材の確保・育成など)
- ifrs17を適用し、財務諸表を作成(試作)
- ifrs17を運用する
まずはifrs17を導入するために必要な準備を進めましょう。システムの改修・変更、ifrs17の導入に必要である、IFRSに詳しい人材や高度な英語力をもつ人材などの確保をしたり、育成したりします。
ifrs17を導入する準備が整ったら、ifrs17を適用し、財務諸表の試作をする必要があります。
財務諸表はifrs17に基づいた内容で、英語で作成しましょう。
財務諸表の試作を作成し、問題がなければifrs17の運用が始められます。
ifrs17運用後は、問題がないかこまめに確認し、問題があれば確認・改善します。
ifrs17の基本的な知識を身に付けよう
今回は、2023年1月1日に適用され、国際財務報告基準(IFRS)の1つである「ifrs17」について解説しました。
ifrs17は保険契約の会計処理を国際的に統一し、財務報告により透明性をもたせ、保険会社の業績などの比較をわかりやすくするための新基準です。
ifrs17には、保険会社の業績などをわかりやすく比較できるようにする、また保険会社の財務業績や保険負債に透明性をもたせるという目的があります。
またIFRSとは、国際会計基準審議会(IASB)が策定している世界共通の会計基準であり、EU加盟国の導入義務化をきっかけに世界各国でも導入が広がっているのです。
日本では独自の会計基準があり、IFRSとは採用している主義やアプローチ方法が違います。
IFRSを導入するには、メリットとデメリットをきちんと踏まえて計画的に導入を進めることが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
国際会計基準(IFRS)の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引