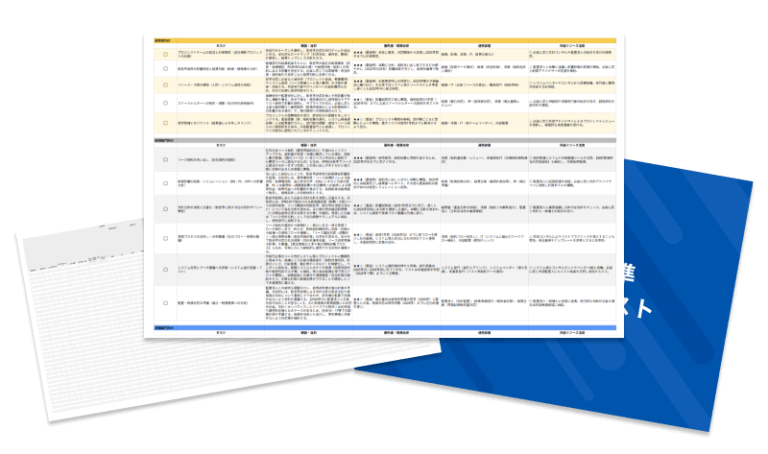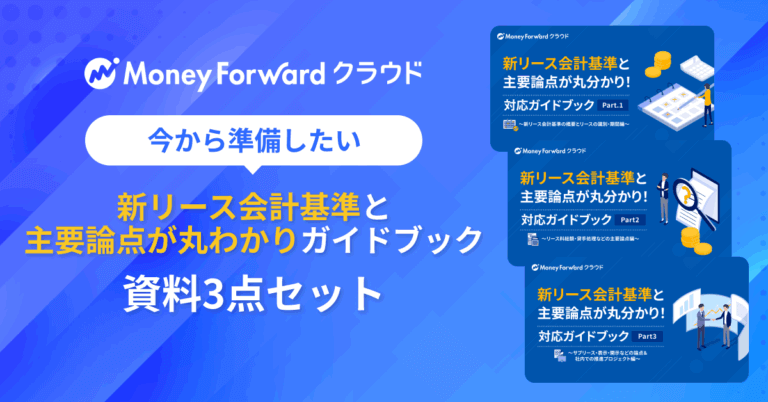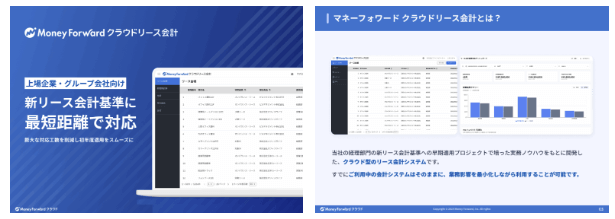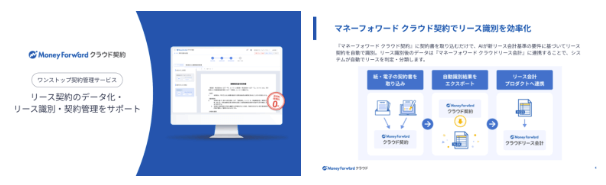- 更新日 : 2025年7月22日
リース資産とリース債務が一致しない理由とは?ズレが生じる原因を解説!
現行のリース会計基準では、ファイナンス・リースの場合には売買取引に準じた会計処理が原則とされています。
売買処理を行う場合には、リース資産とリース債務を計上しますが、これらの勘定科目については、必ずしも帳簿価額が一致するとは限りません。
ここでは、リース資産とリース債務の考え方や、これらの帳簿価額が不一致となるケースについて解説します。
目次
ファイナンス・リースの会計処理
現行のリース会計基準では、企業が行うリース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分けて会計処理を行います。
まず、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いや、ファイナンス・リースに該当する場合の会計処理について確認しましょう。
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違い
日本の会計基準では、ファイナンス・リースは実質的に売買取引と同じ経済的実態をもつリース取引と捉えるため、売買取引に準じた会計処理が原則となります。
そのため、ファイナンス・リースに該当する場合には、借手は契約開始時にリース資産およびリース債務を貸借対照表に計上し、実質的に自社で保有する固定資産と同様の仕訳を作成します。
一方、オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引のことです。オペレーティング・リースの場合には、貸手がリース物件のリスクやリターンを引き続き保持しており、借手は単に賃借料を支払って利用するだけの形態を表します。したがって、借手側の貸借対照表にはリース資産やリース債務は計上されず、単純にリース料を期間費用として計上する賃貸借取引に準じた会計処理を採用します。
なお、これらのリースの区分については、2つの要件によって判定します。以下の要件の両方を満たす場合にはファイナンス・リース、それ以外の場合にはオペレーティング・リースに該当します。
- リース期間の中途で解約できないこと(ノンキャンセラブル)
- 使用によって生じる費用を借手が実質的に負担すること(フルペイアウト)
所有権移転ファイナンス・リースの判定方法
ファイナンス・リースのなかでも、リース期間終了後あるいはリース期間の途中で、所有権が借手に移転する形態を「所有権移転ファイナンス・リース」と言います。資産の最終的な所有権が借手に確実に移るため、減価償却計算なども通常の自己所有資産と同様に扱われます。
それに対して「所有権移転外ファイナンス・リース」は、リース期間終了後には、リース物件が貸手に返却されるなど、借手に所有権が移転しないような取引形態のことです。
これらの区分の判定方法について、以下の3つのいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リースとして取り扱われます。
- リース契約上、リース物件の所有権が借手に移行する旨が定められている場合
- リース契約上、リース物件を著しく割安な価額で買い取る権利が付されており、その権利行使が確実と予想される場合
- 借手に合わせて製作された特別仕様であり、そのリース物件を第三者へリース・売却することが困難な場合
リース資産とは?
リース資産とは、ファイナンス・リース取引を締結している場合に、その取引の性質を考慮して、借手側の固定資産として貸借対照表に表示するための資産科目のことです。
そのため、リース資産として計上された金額については、他の自社所有の固定資産と同様に、減価償却によって各事業年度に費用配分します。
リース債務とは?
リース債務とは、ファイナンス・リースを結んだ場合において、借手が将来的に支払うべきリース料相当額を表します。リース債務については、資産科目として「リース資産」を仕訳計上する際の相手科目として用いられます。
リース債務は負債科目に該当し、借入金などと同じく金融負債として扱われ、リース料を支払うごとに元本が返済される形で負債残高が減少します。なお、利息相当額については、リース債務とは分けて管理し、支払利息などの費用科目として各事業年度へ計上されます。
リース資産とリース債務の算出方法
リース資産やリース債務として、資産・負債に計上する金額については、以下の3つの金額に基づいて算出します。
- 貸手の購入価額
- 見積現金購入価額
- リース料総額の割引現在価値
所有権移転ファイナンス・リースの場合には、1の金額が明らかな場合には1を採用し、1が不明な場合には、2と3のいずれか低い金額で計上します。
それに対し、所有権移転外ファイナンス・リースでは、1(1が不明な場合は2)と3のいずれか低い金額によって、リース資産とリース債務を計上します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
ファイナンス・リース(売買処理)の仕訳例
ファイナンス・リース取引について、売買取引に準じた会計処理を行う場合には、契約時やリース料支払時など、各取引時点において適切な仕訳を作成しなければなりません。
実務上は、以下のような具体例を参考に仕訳を作成しましょう。
リース開始時点
売買取引に準じた会計処理を行う場合、リース契約開始時には、借手は「リース資産」と「リース債務」を計上します。
たとえば、所有権移転ファイナンス・リースに関し、リース物件における貸手の購入価額が50万円の場合には、以下のように仕訳を作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 500,000円 | リース債務 | 500,000円 |
リース料を支払った場合
リース料を支払う場合には、リース債務の元本返済部分と利息相当額を区分して計上します。
たとえば、リース料のうち4万円が元本返済分、1万円が利息分である場合、リース料支払時の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務 支払利息 | 40,000円 10,000円 | 現金預金 | 50,000円 |
減価償却費の計上
リース資産を計上する場合には、決算整理仕訳などで減価償却計算を行います。
この場合の耐用年数については、所有権移転ファイナンス・リースの場合には経済的使用可能予測期間とし、所有権移転外ファイナンス・リースではリース期間となります。
たとえば、リース物件について、減価償却費として10万円を計上する場合には、以下のように仕訳を作成しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 100,000円 | リース資産(間接法の場合には「減価償却累計額」) | 100,000円 |
リース資産とリース債務が一致しないケースとは?
現行のリース会計基準では、「リース資産」と「リース債務」はセットで仕訳計上されますが、この2つの勘定科目は、常に帳簿残高が一致するとは限りません。
具体的には、消費税処理や減価償却、リース料の計上方法などによって、リース資産とリース債務の残高にズレが生じるケースもあります。
これらの勘定科目が一致しないケースを正しく理解して、異常点監査の精度向上に役立てましょう。
税抜経理方式の場合
消費税課税事業者の場合には、消費税の経理方法として「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2種類があります。
税込経理方式の場合には、リース資産とリース債務がともに税込価額で計上されるため、両者の計上額は一致します。一方、税抜経理方式の場合には、リース資産の消費税部分は「仮払消費税等」として別建てで計上されるため、リース資産とリース債務は一致しません。
【例】税抜100万円(税込110万円)のリース物件を計上する場合
① 税込経理方式の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 1,100,000円 | リース債務 | 1,100,000円 |
② 税抜経理方式の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 仮払消費税等 | 1,000,000円 100,000円 | リース債務 | 1,100,000円 |
上記のように、税抜経理方式の場合、リース資産の取得価額は消費税分を除いた金額で計上される一方で、リース債務は税込価額で計上します。そのため、税抜経理方式を採用している場合には、リース資産とリース債務の帳簿価額は計上時点でズレが生じることとなります。
リース料の支払いと減価償却費のペースが一致しない場合
貸借対照表に計上されるリース資産とリース債務については、それぞれ異なる観点に基づいて、帳簿価額が次第に減少します。
具体的には、リース債務が「リース料の支払い」によって段階的に減少するのに対し、リース資産は「減価償却」によって帳簿価額が逓減していきます。
したがって、リース料の支払いと減価償却が同じペースで行われる場合には、リース資産とリース債務の残高は一致しますが、これらのペースが一致しない場合には、2つの勘定科目の残高にも差異が生じることとなります。
所有権移転ファイナンス・リースの場合
所有権移転ファイナンス・リースでは、リース期間終了後にリース物件の所有権が借手に移ることが前提です。
そのような取引の特性から、リース資産の減価償却費に関しても、「リース期間」ではなく「経済的使用可能予測期間」を耐用年数として計算されます。そのため、リース期間終了後も引き続き減価償却計算が行われるケースが一般的です。
それに対してリース債務については、リース期間を通じて支払われるリース料と連動して減少するため、原則としてリース契約の終了する時点では残高がゼロになります。
したがって、所有権移転ファイナンス・リースの場合は、リース債務の残高がリース期間を通じて減少します。一方、リース資産については、リース期間にかかわらず、実際の使用可能期間を通じて減価償却するため、これらの勘定科目の残高は一致しなくなります。
所有権移転外ファイナンス・リースの場合
所有権移転外ファイナンス・リースの場合、リース資産の減価償却については、残存価額をゼロとし、リース期間を耐用年数として計算します。
そのため、リース債務の減少要因である「リース料の支払い」と「減価償却」のペースが一致するケースも多く、そのような場合には、リース資産とリース債務の残高も一致します。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リースの場合でも、「リース料の支払い」と「減価償却」のペースが不一致の場合には、リース資産とリース債務の帳簿価額にもズレが生じます。
たとえば、実際のリース期間から1ヶ月遅れてリース料を支払う場合や、初回リース料として2ヶ月分をまとめて支払うような場合には、「リース料の支払い」と「減価償却」のペースにも誤差が発生します。
支払リース料のスケジュールにかかわらず、減価償却計算はリース期間の経過に合わせて行われるため、リース料の支払方法によっては、リース資産とリース債務の残高不一致につながるケースもあるでしょう。
減損会計を適用する場合
減損会計とは、自社の固定資産の回収可能価額が著しく減少している場合に、減損損失を計上することで、その資産の帳簿価額を減額する処理のことです。
減損会計については、リース物件も対象となるため、既存のリース物件に減損の兆候があり、帳簿価額を回収可能価額まで切り下げる必要が生じた場合には、減損損失を計上しなければなりません。
たとえば、帳簿価額が100万円のリース物件について、回収可能価額が30万円であり、差額70万円を減損損失として計上する場合には、以下のように仕訳を作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 700,000円 | リース資産 | 700,000円 |
このように減損会計を適用することで、リース資産の帳簿価額は回収可能価額まで減少するのに対し、リース債務の残高に影響が及ぶことはありません。これは、リース物件の経済的な価値が下落したとしても、借手としてのリース料の支払い義務は免除されないためです。
そのため、減損会計を実施する場合には、リース資産とリース債務の帳簿価額は乖離するケースが一般的です。
新リース会計基準適用後はどうなる?
2027年4月1日以後の連結会計年度や事業年度からは、「新リース会計基準」の適用開始が予定されているため、これまでのリース会計が大幅に見直されます。
以下では、新リース会計基準の概要や変更点などを理解し、新基準の下で行うべき適切な会計処理の方法を確認しましょう。
新リース会計基準とは?
新リース会計基準では、国際的な会計基準との整合性を図るために、リースをオンバランス化して、リース取引の影響を財務諸表へ的確に反映することが求められます。
2027年4月以降の導入が予定されており、上場企業や大企業では強制適用とされる一方で、中小企業などでは任意適用となります。
新基準ではオンバランス化が原則
新基準では、リースを「資産の賃貸借」ではなく「使用権の取得」と位置づけており、リースに該当する取引はオンバランス化が原則となります。
したがって、ファイナンス・リースやオペレーティング・リースの区分にかかわらず、借手側は「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上しなければなりません。
使用権資産とリース負債は一致する?
新リース会計基準では、リース開始時点で未払いのリース料総額から利息相当額を控除して、それを現在価値に割り引くことで「リース負債」を算出します。
その一方で、資産として計上すべき「使用権資産」については、「リース負債」に対し、前払リース料や付随費用、資産除去債務などを加算し、受け取ったリース・インセンティブがあれば、それを差し引いた額となります。
そのため、「使用権資産」と「リース負債」が一致しないケースも十分に考えられるため、各企業はこれらの勘定科目を分けて適切に残高管理することが重要と言えるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
減価償却明細書とは?テンプレートを基に書き方や注意点を解説
減価償却明細書とは、企業が保有する資産の減価償却状況を一覧にした帳簿を指します。個々の固定資産の減価償却の流れを記載した固定資産台帳とは別の帳簿です。 減価償却明細書があると「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の別表を作成しやすくな…
詳しくみる空気清浄機の減価償却を解説!耐用年数や仕訳は?
家具や家電はその種類によって、国税庁が定める耐用年数が異なります。そのため「空気清浄機は減価償却できる?」「空気清浄機の耐用年数は?」と考える方も多いでしょう そこで、本記事では空気清浄機の減価償却や耐用年数などについて詳しく解説します。国…
詳しくみる有利子負債とは?勘定科目やリース債務との関係性を解説!
有利子負債とは、貸借対照表に計上される負債のうち、利息の支払いを伴うものを表します。 有利子負債の代表例としては、金融機関からの借入金や資金調達のために発行する社債などが挙げられます。 ここでは、有利子負債の概要や無利子負債との違い、有利子…
詳しくみる減価償却費は決算書にどう記載する?減価償却累計額も解説
減価償却費は、貸借対照表やキャッシュフロー計算書などの決算書に記載しなくてはいけません。具体的な書き方を直接法と間接法に分けて仕訳例を挙げて解説するので、ぜひ参考にしてください。また減価償却累計額と減価償却費の違いについても説明します。 決…
詳しくみる中古車は一括償却できる?減価償却との違いや経費計上のシミュレーションも
中古車は取得価額20万円未満であれば、一括償却資産として3年で経費化が可能です。 本記事では、一括償却制度の概要をはじめ、減価償却との違いや法人・個人事業主を問わず利用可能な要件について解説します。さらに、2年落ちや4年落ち、10年落ちとい…
詳しくみる美術品を減価償却するかどうかは100万円が分岐点
事務所の応接室に絵が飾られていたり、社屋のロビーに壷が飾られていたり、ビジネスの現場でも美術品を目にすることがあります。 美術品は事業に直接のかかわりはなく、使用するにつれて価値が減るものばかりとは限りません。しかし、税法では美術品に対して…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引