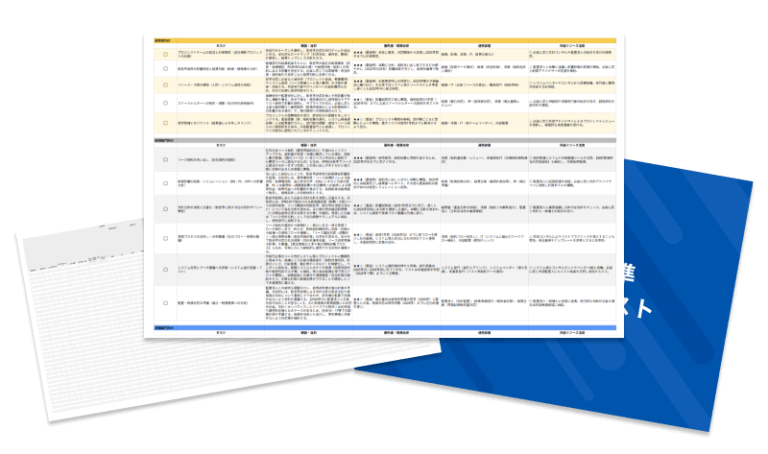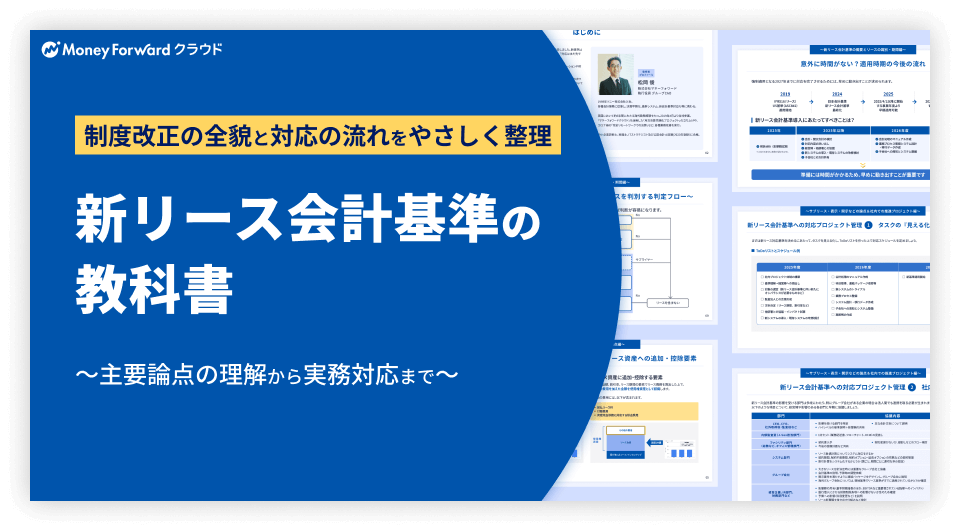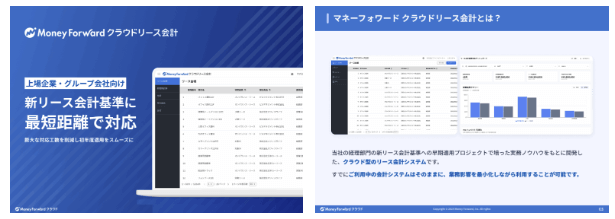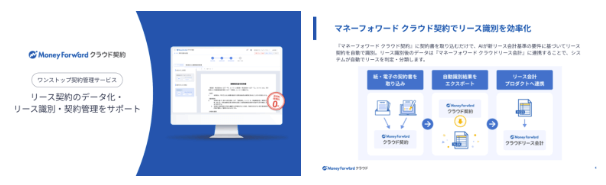- 更新日 : 2026年1月27日
新リース会計基準の対象企業とは?中小企業も?わかりやすく解説
新リース会計基準は、2027年4月より上場企業等へ原則「全リースの資産計上」を義務付ける新規則です。
契約名称にかかわらず「資産の使用を支配する権利」があればリースと定義され、オフィスや倉庫の賃貸借などもオンバランス(資産・負債計上)の対象となります。
新たなリース会計基準による影響が懸念されています。新リース会計基準は2024年9月に公表され、2027年4月1日開始事業年度から強制適用されます。対象とされる企業は、基本的に上場会社や大会社であり、中小企業については任意適用です。
この記事では新リース会計基準の適用会社のほか、新旧基準の比較や新基準の概要について解説します。
目次
新リース会計基準の適用対象企業は?
新たなリース会計基準は、基本的に「金融商品取引法に基づく財務諸表」に対して適用されます。また、会社法における大会社は、会計監査人の設置が義務付けられており、監査の対象となる計算書類(貸借対照表、損益計算書等)においても適用されます。
上場会社の場合
新リース会計基準は、上場会社に適用されます。一般に上場会社は、株式市場で株式を公開している会社ですが、ここで上場会社に含まれる会社は、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社です。
会社法では、子会社とは、その会社以外の会社等が「議決権の過半数を保有する会社」または「役員の過半数を占めている会社」あるいは「実質的な支配関係にある会社」などと定義されます。
したがって、新リース基準は、上場会社のように有価証券など「金融商品」を取り扱う会社やその子会社・関連会社について適用されます。
非上場会社(主として大会社)の場合
新リース会計基準は、会計監査人を設置する会社とその子会社に適用されます。会社法では、会計監査人を設置する企業の監査人は会計基準に基づき監査するため、新リース会計基準の適用対象です。
会社法では、大会社とそれ以外の会社の区分を定めており、「大会社」とは資本金の額が5億円以上または負債の額200億円以上が該当します。会社法第328条においては、大会社については上場・非上場に係わらず会計監査人を設置することが義務付けられています。
よって、非上場であっても大会社または任意で会計監査人を設置する会社は、新リース会計基準に従って処理をしなければなりません。
非上場会社(大会社以外の会社)の場合
上場会社や非上場会社(主として大会社)のいずれにも該当しない場合には、新リース会計基準の適用は任意となります。中小企業でも任意で会計基準を適用する会社はありますが、一般には「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいてリース取引を計上することになります。
例えば、中小企業の会計に関する指針においては、ファイナンス・リース取引を売買取引によるものとする方法のほか、賃貸借取引とすることを認めています。
したがって、これら中小企業においては、新リース会計基準の影響を受けず、従来のどおりの会計処理で問題ないとされています。
参考:
改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について|日本公認会計士協会、「中小企業の会計に関する指針」、中小会計要領について|中小企業庁、「中小企業の会計に関する基本要領」
もとから国際会計基準を適用している場合
もともと国際会計基準(IFRS)を会計基準として採用している企業においては、今回の改正以前にリース取引についても今般の対応ができているので、今回の企業会計基準の改正による影響はありません。
(国内で、2025年1月末時点で286社がIFRSを適用、または適用を決定しています。)
参考:IFRS(国際財務報告基準)への対応|日本取引所グループ
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
現行リース会計基準と新リース会計基準の違いは?
2024年9月に公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」は、現行のリース取引に関する会計基準やその適用指針とどのように違うのでしょうか?それらの大きな違いとして、次の2点が挙げられます。
なお、以下においては、今回の基準変更において大きく考え方が変わったリースの「借り手」側についてのみの記載となります。
オンバランスの拡大
現行の基準においては、オペレーティングリースは「賃貸借取引に準じた処理」でよく、貸借対照表に資産や負債として計上されませんでした。しかし、新基準においてはリースについて単一の会計処理となります。
| 現行基準 | ➡ | 新基準 |
|---|---|---|
| オペレーションリース:オフバランス | すべてのリースをオンバランス | |
| ファイナンス・リース:オンバランス |
一部、少額や短期リース等の例外はあるものの、新基準ではすべてのリースについて、オンバランス(貸借対照表に資産および負債を計上)することになりました。
新基準導入の背景には、従来の日本のリース会計基準は特に負債の認識において、国際会計基準と違っていることが懸念されてきました。オペレーティングリースによって固定資産を所有しているのと同様な効果を得て収益を上げていても、オフバランスである点が問題視されてきたのです。
世界の多くの国が国際会計基準に沿って処理をしているところ、日本は追いついていない状況でした。そこで、日本におけるリースの新基準開発においては、国際会計基準のリース会計基準である「IFRS第16号」の主要な定めを取り入れ、国際的な比較可能性ができるルールを構築しました。
参考:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会
リースの定義が変わる
新基準では、リースの定義についても大きく考え方が変わりました。新基準におけるリースの定義は、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」とされます。
出典:企業会計基準第34号 リースに関する会計基準|企業会計基準委員会
この定義だけでは判断が非常に難しいのですが、リースの識別の判断として、「特定された資産」の「使用を支配する権利」を一定期間にわたりお金を支払って得た場合にリースが含まれるとされます。即ち、次の3つの要件を満たす場合に、「リースを含む」と判断されます。
| リースの定義 | 要件 |
|---|---|
| 特定された資産 であること | 借り手によって資産が特定されている |
| 使用を支配する 権利を有すること | 借り手が資産の利用による経済的利益のほとんどすべてを得る権利 |
| 借り手が資産の使用を指図する権利 |
具体的には、契約書に「リース」の文字がなくても、実態として上の要件を満たしているかどうかがポイントです。したがって、これまで「リース」とは考えていなかった賃借不動産や機械、倉庫や車両についても実態を評価し、要件に該当すればリースとして取り扱うことになります。
参考:企業会計基準第34号リースに関する会計基準|企業会計基準委員会
リース期間が変わる
リース契約等においては、契約の延長が可能な場合がよくあります。
新基準においては、リース期間終了後に「延長オプション」が付帯している契約の場合、延長することが合理的に確実であれば、その延長分を含めた期間をリース期間とします。
したがって、リースによる固定資産の取得の場合には、解約不能期間だけでなく、合理的に考えて「延長が確実視される」期間もリース期間としなければなりません。
新リース会計基準で企業が影響を受ける内容
新リース会計基準により様々な影響が考えられます。特にリース取引となる資産の多い企業における影響として考えられることや、財務諸表への影響について概要を見てみましょう。
企業経営に与えるインパクト
店舗やオフィスなど賃貸不動産の多い企業で、新基準適用対象となった場合、現行のオペレーティングリースをオンバランスにするためには個々の契約を洗い出す必要があります。
基本的にはオペレーティングリースに関する未経過のリース料(将来支払う予定であったリース料)がオンバランスになります。
例えば、航空業などで航空機がオペレーティングリースの場合には、一機当たりの金額が巨大であるため、会計基準変更による金額のインパクトが大きいと言えます。さらに、倉庫業や物流が抱える車両がオペレーティングリースである場合も同様です。
リースの定義やリース期間の考え方が変わったことから、事業の中心がオペレーティングリースによる資産であった業種だけでなく、大々的な見直しが必要となる企業は多いと考えられます。
財務諸表面
新基準の適用によって財務諸表がどのように変わるかを見ておきましょう。
【貸借対照表への影響】(リース借り手)
.jpg)
上図のように、新基準適用により貸借対照表の総資産が増大します。
例えば、高いほど健全性も高いと言われる自己資本比率(総資産のうち純資産の占める割合)は、新基準に変わることによって低くなります。また、収益性の指標とされる総資産利益率(ROA:総資産に占める当期純利益の割合)も大きく低下することは明らかです。
このように、固定資産や資産全体を計算に含む指標は大きく変わります。
【損益計算書への影響】(リース借り手)
現行のオペレーティングリースの場合、リース期間における支払リース料は一定です。しかし、資産計上することによって「リース料」ではなく、「減価償却費+支払利息」となります。支払利息は、原則として利息法(リース負債が減るほど利息も減る)により計算するため、毎期の費用は一定ではなくなります。
会計基準が変わることにより、財務諸表への影響が大きくなりますが、その前に自社にどのように新たな会計基準を適用するかの検討は時間の限られた中で実施しなければなりません。さらに、新たな会計基準を実務に適用する際には、契約や資産の該当性、適用範囲など、詳細を十分に検討する必要があるため時間的な余裕が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新リース会計の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引