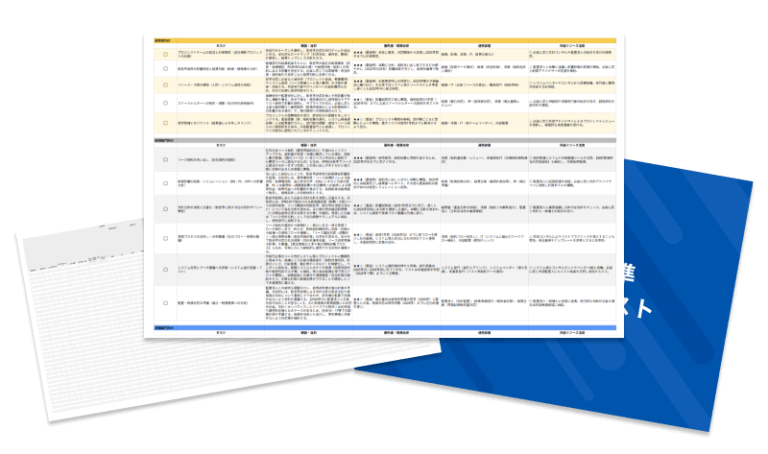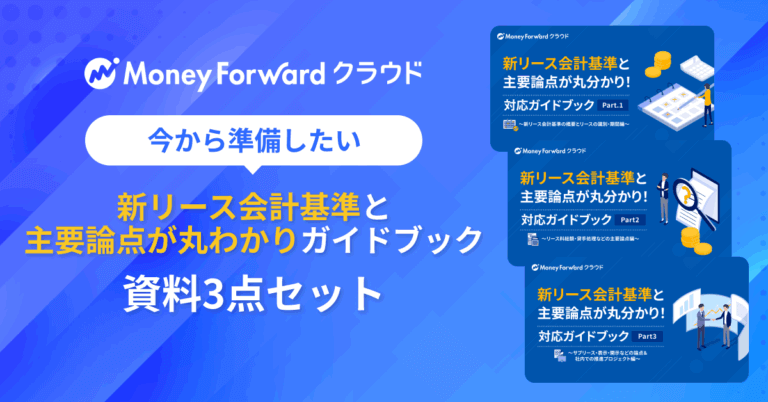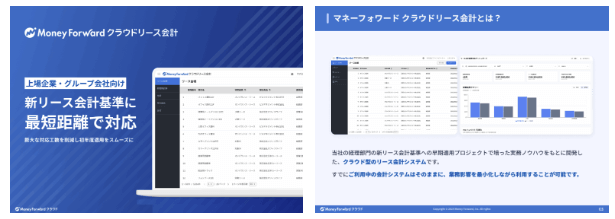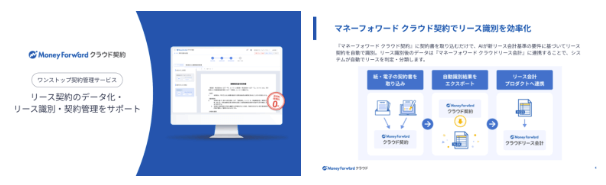- 更新日 : 2026年1月27日
リース資産を中途解約して買取した際の仕訳など
固定資産などをリースで調達する場合には、リース会計基準に基づいた処理が求められます。
リースについては、リース料の支払いや中途解約した場合の処理など、さまざまな取引が発生しやすく、その都度適切な仕訳を作成しなければなりません。
ここでは、中途解約した場合の会計処理を含め、リース取引における仕訳例や、新リース会計基準による変更点を解説します。
目次
リース資産を中途解約して買取した際の仕訳方法
リース契約期間の途中で借手がリース資産を解約するケースは少なくありません。
たとえば、借手の事情でリース物件が不要になった場合や、契約条件を変更してリースから購入へ切り替える場合などが一般的です。
このように、リース契約を打ち切る場合には、途中解約に伴う損害金などの支払いが発生します。また、「リース資産」や「リース債務」が貸借対照表に計上されている場合には、これらの資産や負債科目の取崩しが必要です。
規定損害金や違約金の支払いが必要
リース契約では、中途解約による規定損害金や違約金が設定されていることが一般的です。具体的には、中途解約時に支払う規定損害金や違約金に関して、解約時点における残りのリース期間でのリース料相当額をまとめて支払う旨が定められているケースが多いでしょう。
これは、貸手であるリース会社が資産を購入して貸し出しているリース資産について、リース期間中に中途解約が発生した場合には、当初想定していた利息やリース料の収益を得られなくなることを補填する性質があるためです。
借手はリース契約を中途解約する場合には、契約時点であらかじめ定められた損害金や違約金を支払うことで、リース期間満了前に契約を打ち切ることが可能です。中途解約したあとは、そのリース資産を自社名義で買い取ったり、他のリース物件の契約に切り替えたりするなど、自社のニーズに適した経営判断を行うことができます。
なお、ファイナンス・リース取引の場合には、中途解約不能の「ノンキャンセラブル」契約であることがひとつの要件とされています。しかし、中途解約できる場合でも、残りのリース料の総額を違約金として支払う義務のある場合には、この要件を満たすものと判断されます。
ファイナンス・リース(売買処理)の場合
現行の会計基準では、リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分けられます。
さらにファイナンス・リースについては、リース期間終了時またはリース期間中に借手へ所有権が移転する「所有権移転ファイナンス・リース」と、それ以外の「所有権移転外ファイナンス・リース」に分類します。
いずれのファイナンス・リースについても、売買取引に準じた会計処理が原則とされており、借手側は「リース資産」および「リース債務」を貸借対照表に計上する必要があります。
このような売買処理を行うファイナンス・リースについて、中途解約による規定損害金や違約金を支払う場合には、貸借対照表に計上された「リース資産」や「リース債務」の消込処理を行います。
【例:中途解約によって、違約金として30万円を支払った場合(リース資産の帳簿価額:50万円、リース債務残高:20万円と仮定します。)】
①リース資産の除却処理
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産除却損 | 500,000円 | リース資産 | 500,000円 |
②リース債務の取崩し
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務 リース債務解約損 | 200,000円 100,000円 | 現金預金 | 300,000円 |
なお、たとえば中途解約後にそのリース資産(機械装置)を40万円で買い取った場合には、以下のように仕訳を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 機械装置 | 400,000円 | 現金預金 | 400,000円 |
所有権移転外ファイナンス・リース(賃貸借処理)やオペレーティング・リースの場合
現行の会計基準では、中小企業などの場合、所有権移転外ファイナンス・リースについては、原則の「売買処理」ではなく、「賃貸借処理」に準じた会計処理も認められています。
また、オペレーティング・リース取引については、賃貸借処理が原則となるため、これらのリース取引に関しては、貸借対照表に「リース資産」や「リース債務」を計上する必要がありません。
このような賃貸借処理を行うリース取引について、中途解約によって未払いのリース料や違約金を支払う場合には、以下のように仕訳を作成します。
【例:中途解約によって、未払いのリース料30万円と違約金10万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース解約損 雑損失 | 300,000円 100,000円 | 現金預金 | 400,000円 |
また、リース資産を返却せずに買い取る場合は、新たな売買取引が発生したものとみなして、売買取引の仕訳を計上しましょう。
買い取る場合の会計処理については、「ファイナンス・リース(売買処理)の場合」と同様です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
リース資産でその他によくある仕訳例【ファイナンス・リース取引(売買処理)の場合】
ファイナンス・リース取引を売買取引に準じて会計処理を行う場合には、「リース資産」や「リース債務」のオンバランス処理が必要です。
具体的には、以下のような流れで仕訳処理を行うケースが一般的です。
リース開始時
リース契約を締結し、リースが開始したタイミングで、借手はリース資産とリース債務を計上します。
なお、この際の計上額として、貸手の購入価額が明らかな場合は、貸手の購入価額とリース料総額の現在価値のいずれか低い金額とします。不明な場合には、リース料総額の現在価値と見積現金購入価額のいずれか低い金額を採用します。
参考:企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」|企業会計基準委員会
【例:貸手の購入価額が200万円のリース契約を締結した場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 2,000,000円 | リース債務 | 2,000,000円 |
リース料支払時
リース料を支払った場合には、リース債務の返済部分と利息相当額を区分して仕訳を計上します。
【例:リース料として、元本返済分7万円、利息分1万円の計8万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務 | 70,000円 10,000円 | 現金預金 | 80,000円 |
決算時
決算時には、リース資産の減価償却費を計上します。
なお、減価償却計算における耐用年数は、所有権移転外ファイナンス・リースの場合にはリース期間、所有権移転ファイナンス・リースの場合には経済的使用可能予測期間とします。
【例:リース資産について、減価償却費として40万円を計上する場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 400,000円 | リース資産(間接法の場合は「減価償却累計額」) | 400,000円 |
リース期間終了時
最後のリース料を支払った段階でリース債務がゼロとなり、リース期間終了後は、リース資産の返却または自社所有の固定資産への振り替えを行います。
【期間満了によって、帳簿価額30万円のリース資産(器具備品)を自社所有の固定資産として振り替える場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 300,000円 | リース資産 | 300,000円 |
減損会計を適用する場合
リース資産の回収可能価額が帳簿価額を下回り、減損会計を適用する場合には、その差額を減損損失として計上しなければなりません。
【例:帳簿価額が60万円のリース資産につき、回収可能価額が40万円に下落した場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 200,000円(※) | リース資産 | 200,000円 |
(※)60万円(リース資産の帳簿価額)-40万円(回収可能価額)=20万円
リース資産でその他によくある仕訳例【所有権移転外ファイナンス・リース取引(賃貸借処理)の場合】
中小企業の場合など、所有権移転外ファイナンス・リースであっても、例外的に賃貸借処理を選択することが認められるケースもあります。
ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を行う場合には、以下のように仕訳を作成するケースが一般的です。
リース開始時
賃貸借処理を選択している場合には、「リース資産」と「リース債務」を計上する必要はないため、リース開始時の会計処理は不要です。
リース料支払時
賃貸借処理を選択する場合には、借手は毎月リース料を支払うたびに、その支払額を費用として計上します。
【例:リース料として5万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 50,000円 | 現金預金 | 50,000円 |
なお、「支払リース料」については、「賃借料」などの勘定科目を用いるケースも多いです。
決算時
所有権移転外ファイナンス・リースについて、賃貸借取引に準じて会計処理を行う場合には、貸借対照表に「リース資産」を計上していないため、減価償却費などの決算整理仕訳は不要です。
ただし、リース料のうち、未払いや前払いとなっている金額があれば、経過勘定として前払費用や未払費用の計上を行うケースもあります。
リース期間終了時
賃貸借処理によって会計処理を行う場合には、リース契約が終了した際にも、リース資産の除却やリース債務の精算手続きは必要ありません。
再リース料を支払う場合
リース期間が終了したあと貸手に対して再リース料を支払うことで、リース期間満了後も引き続きリース資産を使用し続ける場合も多いです。
再リース契約によって、再リース料を支払う場合にも、通常のリース料と同様に費用計上を行います。
【リース期間が満了し、再リース料として3万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 30,000円 | 現金預金 | 30,000円 |
減損会計を適用する場合
所有権移転外ファイナンス・リースについて、賃貸借取引に準じて会計処理を行う場合でも、そのリース資産は減損会計の対象資産に含まれます。
したがって、市場環境や技術革新などによって、リース資産の価値が著しく減少した場合には、減損損失を計上することとなります。
ただし、賃貸借処理の場合には、「リース資産」として貸借対照表に資産計上されていないため、未経過リース料の現在価値を帳簿価額とみなして減損損失を計上します。
また、「減損損失」の相手科目としては、「リース資産減損勘定」という負債科目を用います。
参考:企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」|企業会計基準委員会
【例:未経過リース料の現在価値が50万円のリース物件について、回収可能価額が10万円となり、差額40万円を減損損失として計上する場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 400,000円 | リース資産減損勘定 | 400,000円 |
なお、減損会計によって計上された「リース資産減損勘定」については、リース契約の残存期間にわたって定額法で取り崩し、支払リース料と相殺します。
リース資産でその他によくある仕訳例(オペレーティング・リース取引の場合)
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース以外のリース取引のことで、以下のように賃貸借処理に基づいて仕訳を計上します。
リース開始時
オペレーティング・リース契約は、資産や負債の計上をしないため、リース開始時点での仕訳処理は不要です。
リース料支払時
リース期間中にリース料を支払った場合には、支払額を「支払リース料」として費用計上します。
【例:リース料として1万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 10,000円 | 現金預金 | 10,000円 |
決算時
賃貸借処理の場合には、資産計上されたリース資産が存在しないため、減価償却費の計上は不要です。
リース期間終了時
オペレーティング・リースの場合、リース期間が終了した際には、リース対象資産は貸手に返却され、特に会計処理は必要ありません。
ただし、リース期間が終了し、再リース契約を締結する場合には、支払った再リース料を費用計上します。
【リース期間終了後、再リース料として5万円を支払った場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 50,000円 | 現金預金 | 50,000円 |
新リース会計基準適用後はどうなる?
2027年4月1日から「新リース会計基準」の本格導入が予定されており、リース会計の抜本的な見直しが行われます。
特に、新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引のオンバランス化が義務付けられるなど、リース取引に関する会計処理が大幅に変更されます。
新リース会計基準の概要やポイントを正確に理解し、新基準開始に向けて計画的な準備を進めましょう。
新リース会計基準とは?
新リース会計基準とは、リース取引に関する会計処理を定めたルールのことです。2027年4月1日以降に開始する連結会計年度や事業年度にて適用されることとなり、上場企業や大企業などは強制適用となります。
新リース会計基準では、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分にかかわらず、借手側は「使用権資産」と「リース負債」としてオンバランス化することが原則的な処理とされています。
このような変更の背景には、IFRS第16号などの国際的な会計基準との整合性を図る狙いがあり、財務諸表としての透明性や比較可能性を高めることが主な目的とされています。
オンバランス化が大原則
新基準の下ではリースの概念が見直され、現行の会計基準のような「資産の賃貸借」ではなく、「使用権の取得」という考え方が新たな基準となります。
そのため、契約の名称などにかかわらず、対価と引き換えに特定の資産の使用を支配する権利が借手に移転する場合には、リース取引に該当してオンバランス化の対象となります。ただし、リース期間が12ヶ月以内の「短期リース」やリース料総額が小さい「少額リース」については、従来どおりの費用処理を認める簡便法も設けられています。
このような新リース会計基準が適用されることで、不動産賃貸借契約などもオンバランス化の対象となる可能性が高まります。
これまで賃貸借処理を行っていた取引を貸借対照表に計上することにより、企業の財務指標や会計処理の業務負担に多大な影響を及ぼす可能性も懸念されます。新基準の導入に向けて、各企業は入念な事前準備が必要不可欠でしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所有権移転ファイナンス・リースとは?会計処理・仕訳例を解説!新リース会計基準でどうなる?
現行の会計基準では、「所有権移転ファイナンス・リース」は売買取引に準じた方法で会計処理を行います。 ただし、今後導入が予定されている「新リース会計基準」では、リースの定義や会計処理…
詳しくみる耐用年数とは?償却資産別や中古資産の年数、減価償却の計算方法も解説
減価償却費を算出するには、固定資産の「耐用年数」が必要です。しかし、耐用年数は償却資産の種類によって細かく設定されており、建物や車両、工具などそれぞれ異なります。 そのため、確定申…
詳しくみるソフトウェアは一括償却資産に計上できる?要件や判定方法などを解説
ソフトウェアの取得価額が20万円未満のときは、一括償却資産の勘定科目で計上できます。一括償却資産として計上した場合は、3年間で減価償却が可能です。本記事では、ソフトウェアが一括償却…
詳しくみるパソコンは固定資産に計上すべき?取得価額ごとの勘定科目や注意点も解説
業務用に購入したパソコンは、固定資産として経費計上できますが、取得価額によって扱いが異なる点に注意が必要です。 本記事では、取得価額ごとの勘定科目の違いや固定資産に計上する際の注意…
詳しくみる無税償却とは?有税償却との違いや種類、要件、メリット、活用事例を解説
無税償却とは回収できなくなった金銭債権を、税金がかからない形で処理する手続きのことです。税務上は損金として扱え、課税対象となる所得から不良債権を差し引けます。 本記事では、無税償却…
詳しくみる償却資産申告書を提出しないとどうなる?時効や提出不要となるケースも解説
償却資産申告書は、提出しないと罰金をはじめ、さまざまな罰則を受けなければなりません。本記事では、償却資産申告書の概要をはじめ、提出が遅れてしまったときの対処法や提出を免除してもらえ…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引