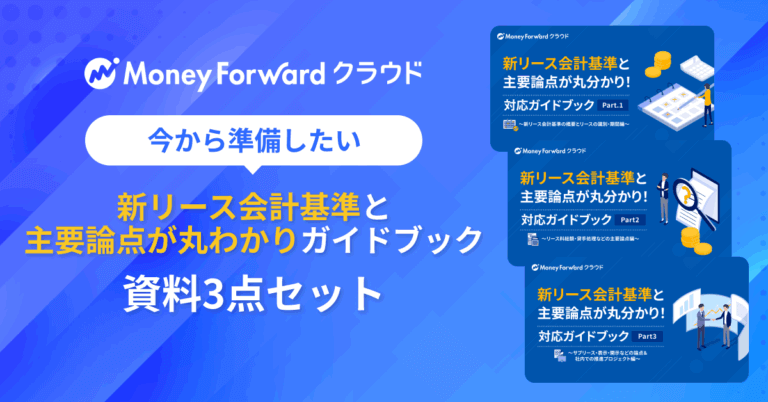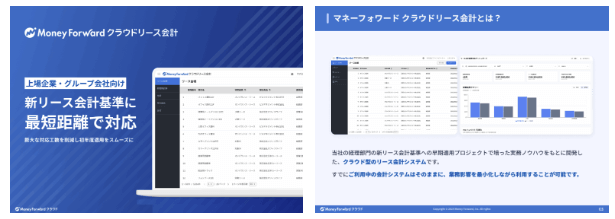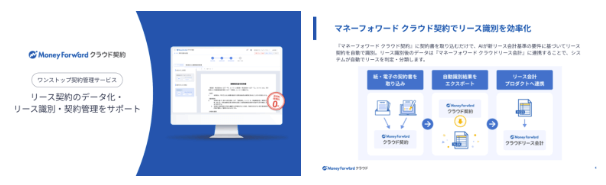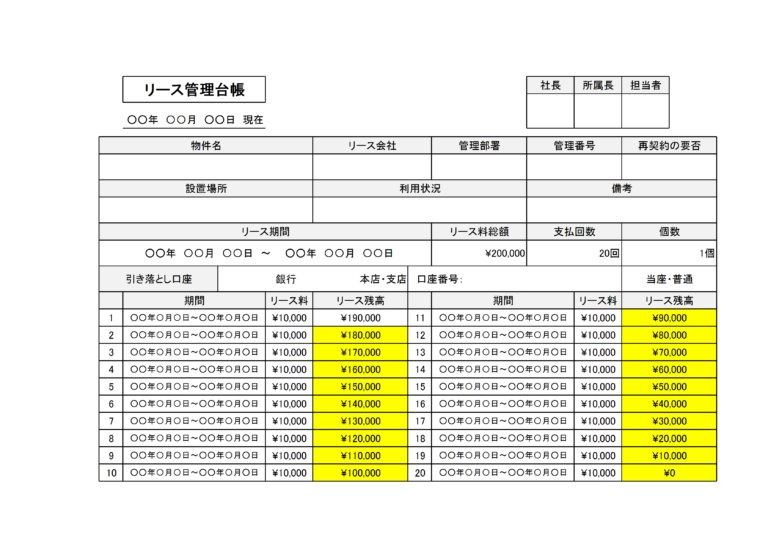- 更新日 : 2026年1月20日
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いをわかりやすく解説!
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがよくわからず、どちらを利用するべきなのか悩んでいる方も多いでしょう。
どちらもリース契約ではありますが、それぞれに特徴があります。本記事ではそれぞれのメリットやデメリット、会計基準での判定や会計処理について詳しく紹介します。
目次
ファイナンス・リースとは?
ファイナンス・リースとは、貸し手が借り手の代わりにリースする商品を購入し、借り手に貸す取引のことをいいます。通常の賃貸借やレンタルのように、すでに貸し手が保有している商品から借り手が選んで借りるのではありません。借り手が選んだものを貸し手が購入し、リース料の中から購入代金などを回収します。
「リース」という名称ではありますが、借り手側にとっては、リース会社を仲介して商品を分割で購入することと同じです。ファイナンス・リースには、以下の2つの特徴があります。
- ノンキャンセラブル
- フルペイアウト
ノンキャンセラブルでは、通常のリースとは異なりリース期間の途中で解約できません。解約時に相当な違約金を払う必要があり、事実上解約できないケースも該当します。フルペイアウトとは、リース物件を所有する場合に得られる経済的利益を借り手が享受でき、さらに生じる費用を負担する必要があることをいいます。
つまりファイナンス・リースでは実質的に商品を所有していることと同じ状態です。リースという形態ではあるものの、実質的に商品を分割払いで購入していることからファイナンス(分割払い)・リースと呼ばれています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
ファイナンス・リースのメリット・デメリット
ファイナンス・リースのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
ファイナンス・リースのメリット
ファイナンス・リースのメリットは、一括で購入することなく機械設備などの資産を利用できる点です。そのため手元のキャッシュを使わなくてよく、事業の資金繰りへの影響がありません。さらに借入ではないため融資枠を使うこともなく、いざという時の調達余力は残しておくことが可能です。
リース契約でありながら、実質的にその資産を購入したことと同じ経済的効果を得られます。またオペレーティング・リースと比べると比較的リース期間が長く、契約内容次第ではリース期間終了後も引き続き資産を利用できる場合もあります。
ファイナンス・リースのデメリット
ファイナンス・リースのデメリットは、途中で解約できない点です。もしリース契約した資産が期待通りではなかったとしても、途中で変更することはできません。ファイナンス・リースを利用する際は、本当に必要な資産かどうか慎重に見極める必要があります。
またファイナンス・リースを利用した場合、支払総額は一括購入するよりも割高になります。手元キャッシュを残しておける効果はありますが、長い目で見れば一括購入のほうがお得です。
オペレーティング・リースとは?
オペレーティング・リースは借り手が金銭を支払い、貸し手から資産をレンタルする取引のことをいいます。ファイナンス・リースと違って単に借りるだけの契約なため、期間が終了すれば資産は返却しなければなりません。
資産を所有しているわけではないため、資産に故障などがあった場合は貸主が修理を行います。イメージとしてはレンタカーや、レンタルCDと考えればわかりやすいでしょう。会計や税務上では、オペレーティング・リースを「ファイナンス・リース以外のリース取引全般」と定義しています。
オペレーティング・リースのメリット・デメリット
オペレーティング・リースのメリット・デメリットを見ていきましょう。
オペレーティング・リースのメリット
オペレーティング・リースのメリットは、ファイナンス・リースに比べ、リース料金総額を抑えられる点です。また途中で借り換えを行うこともできるため、常に最新の設備を利用できます。1年間という短い期間でのリース契約もできたり、中途解約ができたりするなど、柔軟な契約も可能です。
オペレーティング・リースのデメリット
オペレーティング・リースのデメリットは、途中解約した際に違約金が発生することです。中途解約できることがオペレーティング・リースのメリットではありますが、いつでも自由に解約ができてしまえば貸し手はメリットを得られません。そのため解約が可能でも、違約金が発生します。
また対象の資産は多岐にわたるため、高額な物件であればリース期間が長期に及ぶこともあります。資産によっては外貨建ての取引もあるため、為替リスクにも注意が必要です。高額な資産を利用する場合は、事前に契約内容を確認しましょう。
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違い
ファイナンス・リースと、オペレーティング・リースの主な違いは、次の3つです。
- 会計処理の違い
- 支払方法の違い
- 解約可能かどうかの違い
それぞれの内容を見ていきましょう。
会計処理の違い
オペレーティング・リースの場合は、一般的な賃貸借契約と同じように会計処理を行います。リースした資産は借りているだけのため、資産には計上されません。一方でファイナンス・リースの場合は、商品の売買が行われたものとして会計処理を行います。
具体的には3種類の会計処理が必要で、まず1つ目はリース資産とリース債務の計上です。リース契約を開始した時点で、関連した資産と負債をバランスシートに計上しなければなりません。2つ目は毎月のリース料の支払いで、支払利息とリース料を、現預金を相手方として処理します。3つ目は減価償却で、減価償却費を費用として貸方には減価償却累計額として仕訳します。
支払方法の違い
両社には支払方法による違いもあります。ファイナンス・リースの場合、借り手はリース期間を通じて、対象資産を購入したのと同程度の価格を支払います。さらに資産の価格に加えて金融コストが上乗せされるため、支払総額は高額になってしまうことも多いです。
一方、オペレーティング・リースでは、借り手はリース期間中の利用に対する支払いのみです。したがって、ファイナンス・リースに比べると支払総額が抑えられます。
解約可能かどうかの違い
両社には、解約できるかどうかの違いもあります。前述のようにファイナンス・リースでは中途解約ができません。借り手は契約期間を通じて資産の利用を保証されるため、解約は資産の購入を取り消すのと同じことになってしまうためです。
一方でオペレーティング・リースは資産を一時的に利用するため、特定の条件下であれば解約できます。たとえばオフィス機器をリースで利用したあと、事業規模の縮小などがあっても解約が可能です。借り手のビジネスニーズの変化に迅速に対応できる一方で、借り手にとっては資産を効率的に管理することで、多くの借り手に再リースできます。
会計基準にもとづくファイナンス・リースとオペレーティング・リースの判定方法の違い
会計基準にもとづいてファイナンス・リースとオペレーティング・リースを判定する場合、借り手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に得られ、そのリース物件の使用に伴うコストを実質的に誰が負担するのかが重要なポイントとなります。具体的な判断基準は、以下の通りです。
- 解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件の見積現金購入価額の概ね90%以上を占めること
- 解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること
上記のいずれかの基準に該当すると、ファイナンス・リースに該当します。
オペレーティング・リースの定義は、ファイナンス・リースに該当しないリース契約とされています。オペレーティング・リースでは所有権の移転を伴わないため、借り手は資産・負債ともに計上する必要はありません。リース料は軽費として計上され、企業としてはバランスシートを毀損することなく資産を利用できるメリットがあります。
資産の買い替えや中途解約などにも柔軟に対応できるため、更新頻度の高い技術機器や、プロジェクトごとに特定の機器が必要な場合など、特定のビジネスニーズに柔軟に対応できます。
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの仕訳の違い
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの、それぞれの仕訳の違いを見ていきましょう。
ファイナンス・リースの場合
ファイナンス・リースの場合は、対象資産を購入したのと同様の処理をすることになります。そのためバランスシート上に、資産・負債ともに対象資産を計上します。以下の条件で、利用したと仮定した場合の仕訳を見ていきましょう。
- リース料総額:1,000万円(内利息100万円)
- リース資産:車両代金
- 期間:10年
- 支払方法:年間100万円
リース契約締結時の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| リース資産 | 9,000,000円 | リース債務 | 9,000,000円 | 車両代 |
リース料を払った際の仕訳はこうなります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 900,000円 | 現預金 | 1,000,000円 | 車両代 |
| 支払利息 | 100,000円 | |||
減価償却は、次のように計上します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 900,000円 | リース資産 | 900,000円 | 車両代 |
オペレーティング・リースの場合
オペレーティング・リースでは、単純に資産を借りる賃貸借契約と同じように仕訳します。先ほどと同様に下記の条件で利用したと仮定した場合の仕訳を見ていきましょう。
- リース料総額:1,000万円(内利息100万円)
- 期間:10年
- 支払方法:年間100万円
リースを締結した際は、所有権が移転するわけではないため会計上の処理は発生しません。資産にも負債にも影響を与えないのが、特徴とも言えます。リース料を支払った際に、次のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| リース料 | 1,000,000円 | 現預金 | 1,000,000円 | 車両代 |
それぞれの特徴を理解して適切なリースを利用しよう
リース契約には、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースがあります。どちらもリース契約ではありますが、定義には違いがあります。売買契約に近いのがファイナンス・リースで、レンタカーのように単純に資産を借りるのがオペレーティング・リースです。
両社それぞれに特徴やメリットがあります。たとえば、オペレーティング・リースでは契約の柔軟性が高く、資産の入れ替えなどが行いやすい特徴があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解して、ビジネスのニーズにあったリースを利用しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
オペレーティングリースの関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引