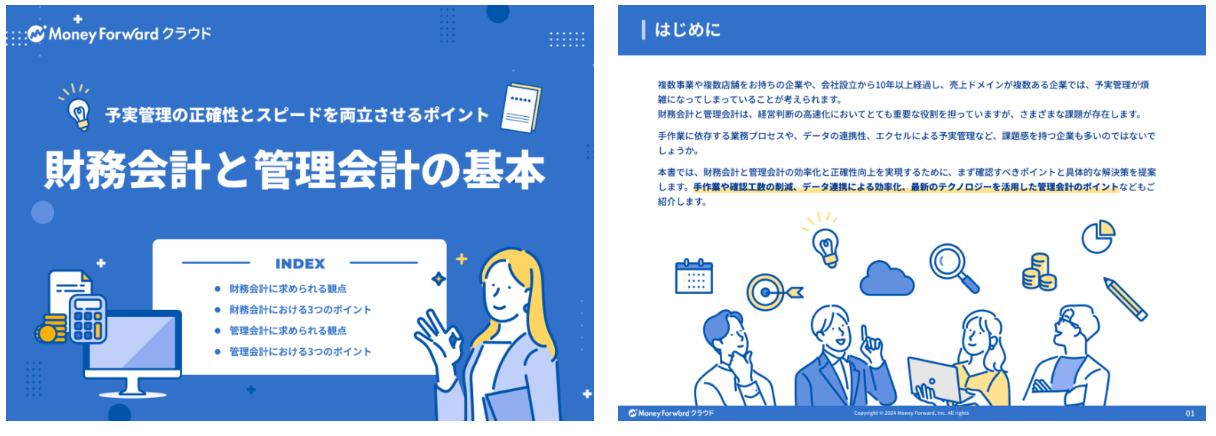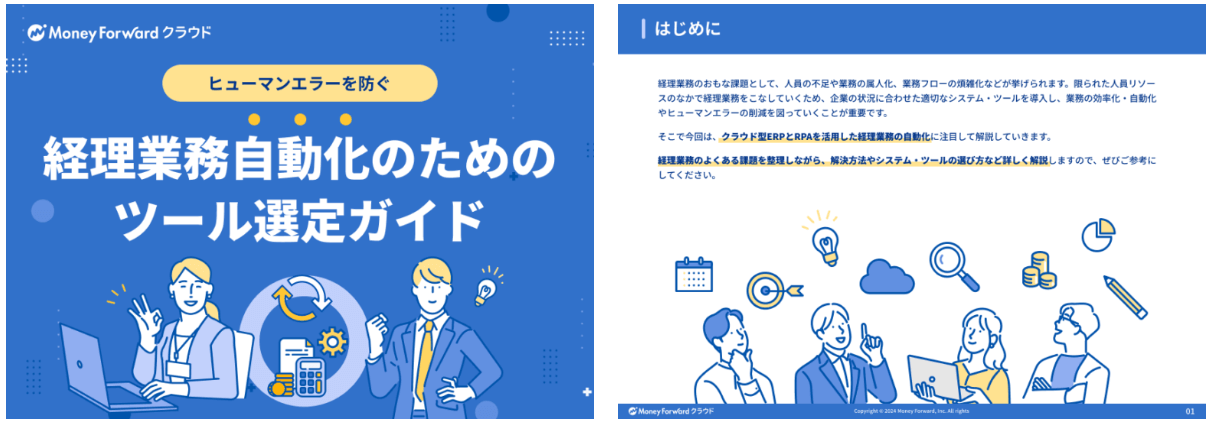- 更新日 : 2025年2月20日
IT導入補助金とは?補助対象や申請方法を解説
IT導入補助金とは、中小企業等を対象として、業務効率化、DX化のために必要となるソフトウェアやITサービスなどの導入費用の一部を補助する制度です。経済産業省などによる国の制度であるため安心して利用できます。2024年においても引き続き申請が可能です。
この記事では2024年版のIT導入補助金の概要と補助対象、申請方法などを解説していきます。
なお、IT導入補助金の詳細や実際にIT導入補助金を活用した事例など、より詳しく知りたい方のために「IT導入補助金についてまとめた資料」を用意しております。以下から無料ダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。
申請チェックリスト付きのため、IT導入補助金を活用できるかどうかお悩みの方にオススメの内容です。ぜひご活用ください。
目次
IT導入補助金とは
IT導入補助金とは、IT導入補助金とは、「中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金」です。
引用:IT導入補助金とは|IT導入補助金2024(公式サイト)
労働生産性の向上を目的としたITツールやクラウドサービスの導入をサポートする補助金で、登録された「IT導入支援事業者」の支援を受けて申請するのが特徴です。
2023年以前のIT導入補助金の活用事例には、以下のようなものがあります(※過去の導入事例については導入要件等が異なることがあります)。
- 生菓子製造業の事例:IT導入補助金を利用して、自社ECサイト立ち上げのために「EC-CUBE」を導入。新規顧客開拓により売上アップを実現した。
- 金融業の事例: IT導入補助金を活用したバックオフィスをサポートする「マネーフォワードクラウド」を導入。クラウド型サービスの導入で管理部門の作業効率が上昇したばかりでなく、テレワーク率も上昇した。
- 飲食業の事例:IT導入補助金を活用して「テンポスエアー」を導入。顧客のセルフ注文とセルフレジシステムの実現により、釣り銭の受け渡しミスがゼロとなった。さらに販促機能によって客単価の向上が実現した。
- 教育・学習支援業の事例:IT導入補助金を利用して、「Microsoft 365 Business Standard」と顧客管理システム「ZOHO CRM スタンダード」を導入。出先でのミーティングやスケジュール管理が可能になり、対面でのミーティング時間の5割削減に成功した。
- 医療業の事例:IT導入補助金を利用して、歯科治療や矯正歯科治療におけるクラウド型電子カルテの「WiseStaff-9 Plus」を導入。カルテ入力と診療の効率化が図られ、サービスの質が向上した。
IT導入補助金の補助対象
2024年版IT導入補助金においては、大まかに次の4つの枠が用意されています。
- 通常枠(A類型、B類型)
- インボイス枠(電子取引類型、インボイス対応類型)
- 複数社連携IT導入枠
- セキュリティ対策推進枠
これらのうち、複数社連携IT導入枠を除いて補助対象となる事業者は、資本金や常時雇用の従業員が一定以下の中小企業と常時雇用の従業員が一定以下の小規模事業者(個人事業主含む)です。
また、複数社連携IT導入類型は、商工団体、まちづくりや観光振興などの事業を担う団体や中小企業者、複数の中小企業や小規模事業者から成るコンソーシアム(共同企業体)が補助の対象です。複数社連携IT導入類型は、複数社から成る組織や複数社をサポートする団体のIT導入を促進するための支援となっています。
以下の表は、IT導入補助金の通常枠などの補助対象者となる中小企業者と小規模事業者の範囲の詳細を示したものです。
【中小企業者等の定義】
| 業種 | 資本金または出資金 | 従業員(常勤) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 (ソフトウェア業等、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| 上記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く
この他、医療法人、学校法人、中小企業団体や財団法人、社団法人、特定非営利活動法人においても要件を満たせば対象となります。
参考:令和6年度当初予算案関連|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
【小規模事業者の定義】
※会社役員や個人事業主は、常時使用する従業員には該当しません。
参考:通常枠 | IT導入補助金2024、「IT導入補助金2024 公募要領 通常枠」
通常枠(A・B類型)
通常枠は、中小企業や小規模事業者等が働き方改革、被用者保険拡大、賃上げなどの制度変更に対応するためのソフトウェア、サービス等の導入費用支援策です。なお、通常枠以下の補助率は最大となる率を示しています。
| A類型 | B類型 | |
|---|---|---|
| 補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
| 補助率 | 1/2 | 1/2 |
| 賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
| 補助対象 | ソフトウェア費用・最大2年分のクラウド利用料金・導入関連費用 | |
参考:令和6年度当初予算案関連|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
通常枠(A類型、B類型)は、生産性向上に役立つITツールの導入を支援するものです。
A類型とB類型の大きな違いは、プロセス数(業務の工程数)と賃上げ目標の取り扱い、そして補助額です。
A類型はITツール導入によって、「顧客対応・販売支援」「会計・財務・経営」など、7種のプロセスのうち1プロセス以上の生産性が向上する見込みがあれば利用できます。
一方、B類型は補助額が高額ですが、申請には4プロセス数以上の改善が必要です。
また、賃上げ目標について、B類型は審査時において必須となっていますが、A類型は必須ではなく審査時の加点要素となっている部分が異なります。
2024年版では、2023年10月に導入された消費税のインボイス制度を支えるためのインボイス枠が設けられました。インボイス枠は、インボイス制度に対応したITツールを積極的に推進する「インボイス対応類型」と、インボイス制度対応のITツールを取引先に無料で利用させる場合の「電子取引類型」に分かれます。電子取引類型はやや大企業向けの支援策となっています。
インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス枠のインボイス対応類型は、生産性向上・インボイス制度対応のために、「通常枠」よりも補助率をアップしてデジタル化を推進する支援策です。ハードウェアも対象となります。
| インボイス対応類型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補助額 | インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト | PC・タブレットなど | レジ・券売機など | |
| 50万円以下 | 50万円超~350万円以下 | 10万円以下 | 20万円以下 | |
| 補助率 | 4/5、3/4(※1) | 2/3(※2) | 1/2 | |
| 賃上げ目標 | 加点 | |||
| 補助対象 | ソフトウェア購入費用、クラウド利用料金(最大2年分)、導入関連費用、ハードウェア購入費用 | |||
※1 小規模事業者の補助率は4/5、中小企業の補助率は3/4
※2 ア)補助額のうち50万円以下の補助率:小規模事業者は4/5、中小企業は3/4
イ)補助額のうち50万円超の補助率 :2/3
参考:令和6年度当初予算案関連|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
具体的には、上の表のソフトウェアに加え、ハードウェアにはプリンタ、スキャナ、複合機などがあり、さらにデータ連携ツールや導入コンサルティング費用、保守サポート費用などが対象となります。
補助金のシミュレーターを利用すると大体の目安が分かります。
インボイス枠(電子取引類型)
インボイス枠の電子取引類型は、受注者である中小企業などに「無償で」アカウントを発行して利用できる受発注ソフト(インボイス対応)の導入費用の支援策です。
| 電子取引類型 | |
|---|---|
| 補助額 | インボイス制度に対応した受発注ソフト |
| 350万円以下 | |
| 補助率 | 2/3、1/2(※1) |
| 賃上げ目標 | 加点 |
| 補助対象 | クラウド利用料金(最大2年分) |
※1 中小企業・小規模事業者等:2/3 その他の事業者等:1/2
参考:令和6年度当初予算案関連|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
セキュリティ対策推進枠
セキュリティ対策推進枠は、サイバーセキュリティ対策の強化を目的とし、サーバー攻撃被害のリスクを低減するためのITツール導入費用支援策です。
| セキュリティ対策推進枠 | |
|---|---|
| 補助金申請額 | 5万円~100万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 賃上げ目標 | 加点 |
| 補助対象 | サイバーセキュリティサービス利用料金(最大2年分) |
参考:令和6年度当初予算案関連|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
サイバーセキュリティサービスとは具体的には、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されるサービスのうち、IT導入支援業者の提供によるサービスを導入する際に、そのサービス料の最大2年分を補助します。
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」については、以下をご参照下さい。
参考:サイバーセキュリティお助け隊 |独立行政法人情報処理推進機構
複数社連携IT導入類型
複数社連携IT導入類型は、サプライチェーンや商業地の複数小規模事業者等が連携してITツールを導入する取組に対し、「通常枠」よりも補助率の高い支援をするものです。
| 複数社連携IT類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助額 | (1)インボイス対応類型の対象経費(基盤導入経費) | (2)(1)以外の経費(消費動向等分析経費) | (3)事務費・専門家費(その他経費) | |||
| ソフトウェア | PC・タブレット等 | レジ・券売機等 | 50万円×事業者数 | 200万円以下 | ||
| 50万円以下 の部分 | 50万円超~ 350万円 | 10万円以下 | 20万円以下 | |||
| 合わせて3,000万円以下 | ||||||
| 補助率 | 4/5、3/4(※1) | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | |
| 賃上げ目標 | なし | – | ||||
| 補助対象 | ソフトウェア購入費用、クラウド利用料金(最大2年分※2)、導入関連費 | – | ||||
※1 小規模事業者の補助率は4/5、中小企業の補助率は3/4
※2 (2)におけるクラウド利用料金は最大1年分
参考:中小企業対策関連予算|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
参考:資料ダウンロード | IT導入補助金2024
「IT導入補助金2024公募要領 複数社連携IT導入枠 」
複数社連携IT導入類型は、サプライチェーンや商業集積地のいくつかの事業者等が連携して、面的なデジタル化やDX化の実現などを図ることを目的に、複数社連携のためのITツール導入を支援するものです。
ほかの類型と異なり単独での申請はできず、10以上の事業者で構成された事業グループ(参画事業者は中小企業者や小規模事業者等に限る。代表事業者は別途規定有り)が受けられる補助金になります。
基盤導入経費は、インボイス対応類型と同じで、会計・受発注・決済のいずれかの機能を有するITツール(オプションを含む)とハードウェア購入費用が対象となります。
消費動向等分析経費は、消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、キャッシュレスシステムなどの導入費用やクラウド利用費、ITツール導入にかかわるAIカメラやビーコンなどのハードウェア購入費用が対象です。
その他経費は、代表者が事業グループの取りまとめをするために要する経費や、外部専門家に係る費用が対象です。
複数社連携IT導入類型では、ITツール導入費から事業グループの取りまとめで必要になった事務費、外部専門家の費用や旅費などの経費に至るまで、幅広く補助することで、事業者が協力してデジタル化推進を図ることをサポートしています。
2024年版のIT導入補助金として設けられた4つの類型について、補助対象をまとめると次のとおりです。費用が補助対象となるものに〇を付けています。
| 枠 | 通常枠 | インボイス枠 | セキュリティ | 複数社 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | インボイス対応 | 電子取引 | |||
| ソフトウェア、オプション、サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハードウェア | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 事務費 | × | × | × | × | 〇 |
IT導入補助金の申請方法と事業者登録
IT導入補助金を利用するための申請方法と、補助対象の事業者をサポートするサービス事業者の登録申請について解説します。
中小企業・小規模事業者等の申請方法
ここでは、IT導入補助金2024の補助金申請の手続きの流れを説明します。
1.募集要項や制度の趣旨について確認する
IT導入補助金の公式サイトに交付規定や公募要領が掲載されます。公募要領には、補助対象の事業や補助対象経費、補助率や補助上限、交付申請のフロー、審査内容などが細かく記載されます。補助金を受けるには要件を満たす必要がありますので、ITツール導入の前にどのようなものが対象になるかなど、内容をよく確認しておきましょう。
複数社連携IT導入類型は、他とは異なり代表事業者とクループ構成員からなる共同体での事業であり、地域全体のDX実現、生産性向上を図るしくみが必要になります。そのため、連携のためのコーディネート費用や助言を行う外部専門家に係る費用等も補助対象となります。
2. IT導入支援事業者やITツールを選択する
申請の前段階として、導入するITツールの選択、導入を支援するIT導入支援業者の選定が必要です。自社の経営課題などを整理して、自社に適したツールや支援事業者を選択ましょう。
具体的なツールや業者の選定については、ITツール・IT導入支援事業者検索サイトで検索できるようになっています。
3.「gBizIDプライム」アカウント取得
補助金の交付申請では、「gBizIDプライム」のIDとパスワードが必要になります。新規のID発行には2週間程度の時間を要しますので、早めに取得しておきましょう。複数社連携IT導入類型では、代表事業者のみgBizIDプライムを取得します。
参考:GビズID|デジタル庁
4.「SECURITY ACTION」実施
補助金申請の要件を満たすには、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が創設した「SECURITY ACTION」宣言を行わなくてはなりません。これは、事業者自らが情報セキュリティ対策に取り組む姿勢を自己宣言する制度です。
IT導入補助金の申請のためには、1つ星、または2つ星での宣言が必要です。SECURITY ACTION自己宣言者サイトで使用規約を確認後、新規申し込みを行い、およそ1~2週間前後で届くロゴマークをダウンロードします。複数社連携IT導入類型では、代表事業者がセキュリティアクション宣言を行います。なお、セキュリティ対策推進枠では2つ星だと加点要素になります。
なお、以前に「SECURITY ACTION」の宣言をされた場合には改めて自己宣言の手続きは不要です。
参考:SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言|独立行政法人情報処理推進機構
5.「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」の実施
2024年のIT導入補助金においても昨年同様、中小企業庁のデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ経営チェック」の実施をする必要があります。このチェックは、自社の経営課題解決に向けて「気づき」につながるチェックであり、申請に用いたgBizIDによってチェックをします。
このチェックによって、同業種または同地域の事業者と対比しつつ、事業の課題やデジタル化の取り組み状況が確認できます。チェックの結果、課題があった場合には「みらデジリモート相談」などで中小企業診断士などの専門家に相談(無料)することができます。
ポイントとしては、gBizIDを利用して「みらデジ事業者登録」をした上で、「みらデジ経営チェック」実施後にはgBizIDとの連携しておくことです。2024年のIT導入補助金においては、このチェックが通常枠では必須であり、インボイス枠(両類型とも)とセキュリティ対策推進枠において加点されます。
6.交付申請
交付申請は、IT導入支援事業者との共同作成となります。大まかな流れは次のとおりです。
- IT導入支援事業者から「申請マイページ」の招待を受けて、基本情報を登録する。
- 交付申請に必要な情報の入力や資料の添付を行う。
- IT導入支援事業者が導入予定のITツールや事業計画を入力する。
- 「申請マイページ」上での確認が終わったら、事務局へ提出する。
複数社連携IT導入類型では、代表事業者が参画事業者の申請情報や書類を取りまとめ、「申請マイページ」にて申請します。
なお、それぞれの申請書の作成にあたって特に留意すべき点は次のとおりです。
- 自社の経営課題を自覚し、改善に向けた具体的な問題意識を持っているか?
- 改善すべき事項が、対象となるITツールの導入効果とマッチしているか?
- 労働生産性が向上する目標値を掲げているか?
例えば、通常枠の場合は1年後に3%以上の労働生産性向上が必要です。 - 加点への取り組みを行っているか?
加点項目(賃上げ、クラウド製品、サイバーセキュリティお助け隊、インボイス対応製品など)を積極的に政策に取り入れているか。
参考:中小企業対策関連予算|中小企業庁
「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2024』の概要」
7.ITツールの契約や支払い
補助金を申請するITツールの発注、契約、支払いができるようになるのは、交付決定を受けた後です。交付決定以前に契約などを行って導入したITツールは補助の対象にはなりません。
8.事業実績報告
ITツールの発注、契約、納品、支払いなどが行われたことが分かる書類を提出します。
実績報告も申請者とIT導入支援事業者との入力が必要です。
9.補助金の交付手続き
事業実績報告の審査が完了して補助金額が確定したら、「申請マイページ」で補助金の額を確認できるようになります。事務局による確認が終了した後、補助金が交付されます。
10.事業実施効果報告
実施効果報告のため、事業者は申請マイページに期限までに実施効果についての情報を入力します。
支援者であるITベンダー・サービス事業者の登録
補助事業者のサポートを担うITベンダーやサービス事業者を「IT導入支援事業者」と言います。IT導入支援事業者は、補助事業を実施するうえでの中小事業者等のパートナーとして、事業推進サポートの円滑化を担う事業者です。IT導入支援事業者として登録することで、自社製品を普及できるなどのメリットがあります。IT導入支援事業者になるには、登録申請によって採択される必要があります。
ここでは、IT導入補助金2024のIT導入支援事業者登録の手続きの流れを説明します。
1. IT導入支援事業者の登録申請
IT導入支援事業者の登録は、単独(法人)での登録、コンソーシアム(共同事業体)での登録の2種類があります。コンソーシアムの幹事社として登録できるのは、法人のみとなります。
登録要領などで登録要件を満たしていることを確認した後、IT導入補助金の事務局に登録申請を行います。事務局による審査、外部審査委員会による審査が行われ、採否の決定が行われます。
2. ITツール登録
IT事業者ポータルより、補助金交付申請の対象になる自社で取り扱うITツールの登録を行います。登録にあたっては、ITツールの仕様や機能などが分かる明確な資料などの添付が必要です。
3. 事業者へのサポートや提案など
小規模事業者や中小企業者に、登録したITツールの提案を行うとともに、見積等の依頼や問合せに対応します。
4. 交付申請・決定
補助金を申請する中小企業や小規模事業者と共同で申請書を作成し、事務局へ提出します。交付申請にともない、IT導入支援事業者は申請マイページの招待申請を事務局に申請しなくてはなりません。IT事業者ポータルへの入力後、内容を補助事業者に確認してもらい、承認を受けたのちに、事務局へ申請の宣誓を行い提出します。
5. 補助事業の実施(ITツールの納入)
交付の決定後に、補助金の対象になるITツールの契約や納入ができるようになります。
6. 事業実績報告
ITツールの導入完了後は、補助事業者は事業実績報告をしなければなりません。
事業実施とは、契約・申込、納品、支払の一連の手続きを言います。IT導入支援事業者は、補助事業者が実績報告を行えるようサポートします。
7. アフターサポート
IT導入支援事業者は、ITツール納入後も継続的なアフターサポートが求められます。特に導入したITツールを解約・利用停止した場合には速やかに事務局へ報告するように促します。
8. 事業実施効果報告
報告内容の入力は補助事業者が行います。実施効果が満たない場合もあり得ます。例えば、通常枠のB類型において、給与支給総額の増加目標が未達、事業場内最低賃金の増加目標が未達などの場合には、補助金の全部または一部の返還となります。
参考:資料ダウンロード | IT導入補助金2024
「IT導入支援事業者 登録要領」、「IT導入支援事業者登録の手引き」
IT導入補助金申請のスケジュール
IT導入補助金2024の申請は、以下のスケジュールで行われます。こちらでは1次及び2次分のみの掲載としますが、順次更新されます。
| IT導入支援事業者の登録申請 | 2024年2月16日(金)~終了時期は後日案内予定 | |
|---|---|---|
| ITツールの登録申請 | ||
| 通常枠の申請締切 | 第1次 2024年3月15日 | 第2次 2024年4月15日 |
| インボイス枠(インボイス対応類型) | 第1次 2024年3月15日 | 第2次 2024年3月29日 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 第1次 2024年3月15日 | 第2次 2024年4月15日 |
| セキュリティ対策推進枠 | 第1次 2024年3月15日 | 第2次 2024年4月15日 |
| 複数社連携IT導入枠 | 第1次 2024年4月15日 | – |
インボイス枠(インボイス対応類型)は他の枠よりもエントリーの機会が多く設けられています。複数社連携IT導入類型を含め下記公式サイトのスケジュールは随時更新されますので、申請時期や交付決定日をよく確認しましょう。
スケジュールの詳細は公式サイトよりご確認ください。
ITツールを取り入れるならIT導入補助金を活用しよう!
IT導入補助金は、小規模事業者や中小企業のITツールの導入費用を補助する制度です。生産性向上に寄与するITツールの導入をした事業者が利用できる通常枠のほか、毎年通常枠とは別に、補助率の高い枠が設けられることもありますので、募集要項を注意深く確認しておきましょう。
また、補助金の交付は、交付決定後にITツールを導入する事業者が対象です。ITツールの導入を検討中の事業者は、IT導入補助金を活用したITツールの導入ができないか、まずは検討することをおすすめします。
マネーフォワード クラウド 販売パートナー募集について
マネーフォワード社ではマネーフォワードクラウドをお取り扱いいただける販売パートナーを募集しております。
マネーフォワードクラウドERPの提案を通じて、貴社ビジネスを成長させませんか?パートナープログラムには、紹介手数料型の紹介パートナー、仕入販売を行う再販売パートナーの2種類を用意しております。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
標準原価とは?実際原価との違いや計算の流れを解説
標準原価とは、製品の製造に伴う材料費、労務費、間接経費について、科学的・統計的に算定する原価のことです。標準原価を実際にかかった費用と比較することで、製造の問題を把握し、解決につな…
詳しくみる税務調査は税理士に依頼するべき?メリットや注意点・選び方を解説
税務調査は、企業や個人の確定申告内容を調査するために実施されるものです。税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があります。「税務調査の通知が来たけれど、どのように対応すればよいの…
詳しくみるオペレーティングリースとは?新リース会計基準も解説
オペレーティングリースは、会計処理上、資産の賃貸借として認識される取引です。現行のリース取引会計基準では、リース取引をオペレーティングリースとファイナンスリースに区分して処理するこ…
詳しくみる島根で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
島根県で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中…
詳しくみる逓増(ていぞう)定期保険とは?節税になる理由や期間満了前の解約についても解説!
多くの法人が活用する逓増(ていぞう)定期保険は、一定期間を超えると死亡保障金額が徐々に増えていくタイプの定期生命保険です。 保険料の一部が損金として計上できるため、条件を満たせば節…
詳しくみる北九州市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
北九州市(福岡県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引