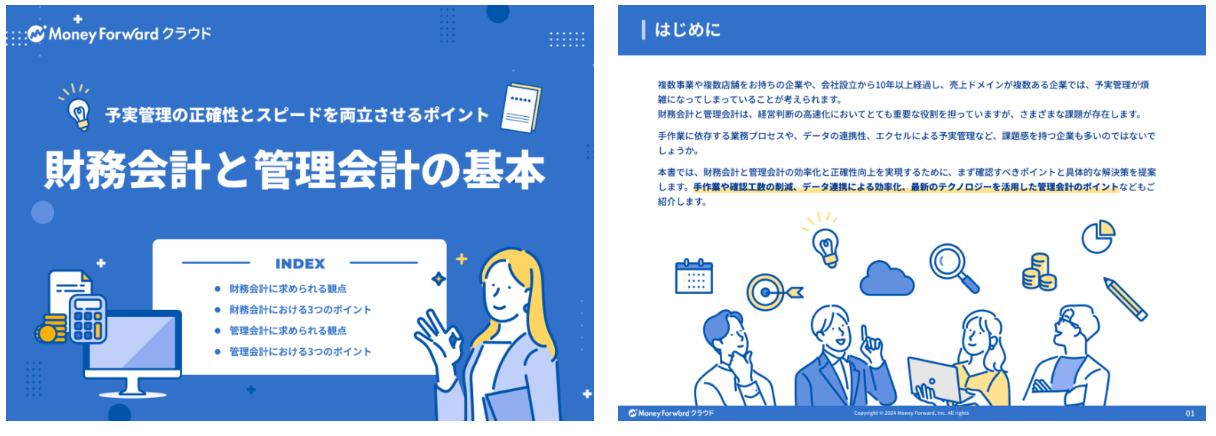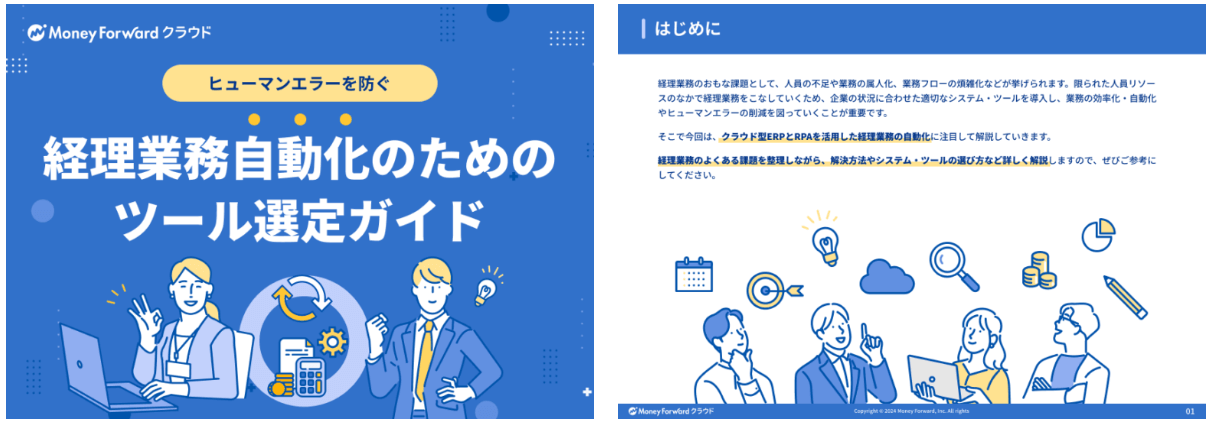- 更新日 : 2025年9月4日
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」とは
IFRS S1号は、サステナビリティ関連財務情報の開示に関する事項を定めた国際会計基準です。企業が持続可能性に関するリスクや機会を財務報告に適切に反映することで、投資家やステークホルダーから信頼を得やすくなります。本記事では、IFRS S1号の概要や適用時期、S2号との違い、日本語訳の入手方法についてご紹介します。
目次
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」とは
IFRS S1号とは、財務情報のうちサステナビリティ関連の情報を開示する際に用いる国際会計基準です。投資家やステークホルダーが企業のリスクや機会を正確に把握できるよう、開示の全般的な指針を示しています。
IFRS S1号の目的
IFRS S1号の主な目的は、企業のサステナビリティ関連のビジネス機会とリスクを財務情報と整合性を保ちながら開示することです。その企業が直面する環境・社会・ガバナンス(ESG)要素を含めたリスク・リターンを、投資家や金融機関などのステークホルダーが正しく評価できるよう、情報の質と比較可能性を高める指針を示しています。
これにより、企業は長期的な価値創造や持続可能な経営戦略を広く理解してもらいやすくなるのです。
IFRS S1号の適用範囲
IFRS S1号の適用範囲は、サステナビリティ関連情報を投資家に提供する必要がある広範な業種・企業が想定されています。特に、上場企業やグローバル事業を展開する企業は、国内外の投資家や金融機関からサステナビリティ情報の開示要請が強まるため、IFRS S1号の適用が望ましいと考えられています。
ただし、任意適用か強制適用かは各国・地域の規制当局が判断するため、市場の状況や自社の現状、方針を踏まえて導入を検討する必要があります。
IFRS S1号の適用時期
IFRS S1号は、2023年6月に最終基準が公表され、企業によっては2024年以降の会計期間から適用可能となりました。ただし、日本国内での導入は義務ではありません。
金融庁や企業会計基準委員会などが検討を進めており、最終的な適用時期や義務化の有無は今後の動向によって決まります。企業としては、サステナビリティ関連情報の開示体制を整えるために、早めの準備を進めることが望ましいです。
IFRS S1号とS2号の違い
IFRS S1号は、サステナビリティ関連財務情報全般に関する開示要求事項を定めたものです。一方、IFRS S2号は気候変動に特化し、気候リスクや機会に関する開示をより詳細に規定しています。
S1号が全体的な基準としてさまざまなESG要素を網羅するのに対し、S2号はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の考え方に基づき、気候関連の具体的情報を開示するための要件を整備している点が大きな違いです。
IFRS S1号の概念的基礎
IFRS S1号の概念的基礎は、「適正な表示」「重要性」「報告企業」「つながりのある情報」という4つの要素から形成されています。以下で、それぞれの概要を解説します。
適正な表示
「適正な表示」とは、サステナビリティ関連情報を財務情報と整合性を担保し、かつ正確に開示することです。企業は自社のリスクや機会を誤りなく反映し、財務諸表と矛盾がないようにする必要があります。また、投資家が合理的な投資判断を行える程度に十分な情報量を確保することが求められます。
重要性
「重要性」は、情報が投資家やステークホルダーの意思決定に影響を与える程度を表す概念です。IFRS S1号においては、サステナビリティ関連情報の中でも、特に財務状況や将来のキャッシュ・フローに大きな影響を及ぼす項目を優先的に開示することが求められます。
報告企業
IFRS S1号では、連結ベースでの報告が求められる場合が多く、親会社だけでなくグループ全体のサステナビリティ関連情報を整理して開示する必要があります。例えば、子会社や関連会社が排出する温室効果ガスなど、グループ全体のリスク管理が重要となります。単一企業に限定されない包括的な視点が求められるのです。
つながりのある情報
IFRS S1号は、サステナビリティ関連情報と財務情報の「つながり」が重視されます。例えば、気候変動リスクが売上やコスト構造に影響を及ぼすケースを具体的に示すなど、財務数値との関係性を明示することが求められます。これによって、投資家が企業の将来価値をより的確に判断できるようになるのです。
IFRS S1号のコア・コンテンツ
IFRS S1号では、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つをコア・コンテンツとして開示することが推奨されています。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ガバナンス
ガバナンスの開示では、サステナビリティ関連リスク・機会に対する取締役会や経営陣の監督体制が重要となります。どのような会議体でどの程度議論をしているのか、ESG課題に対する責任者や委員会の設置状況など、組織としての統制・責任分担を明確にすることが重要です。投資家やステークホルダーにとっては、リスク対応の意思決定プロセスがどれほど充実しているかを判断する材料になります。
戦略
戦略に関する開示では、企業が認識しているサステナビリティ関連リスクと機会が経営戦略や事業計画にどのように関わっているかを説明します。例えば、気候変動による原材料コストの変動や新興市場での需要増加など、具体的なシナリオ分析や将来予測を示すことが求められます。投資家やステークホルダーはこれらの情報をもとに、企業が長期的な収益力や企業価値をどのように高めようとしているかを評価します。
リスク管理
リスク管理の開示では、どのようなプロセスを通じてサステナビリティ関連のリスクを特定・評価・対応しているかを説明します。特に、気候変動リスクや資源枯渇リスク、人権リスクなど、多岐にわたるリスクをどのように優先順位づけし、具体的な対策を講じているのかを示すことが重要です。こうした取り組みが企業の財務状況や事業継続性にどの程度影響を与えるかを投資家やステークホルダーに共有する役割を果たします。
指標及び目標
指標及び目標の開示では、企業が採用する具体的なパフォーマンス指標(KPI)や、達成を目指す定量的・定性的な目標を示します。例えば、温室効果ガス排出量の削減目標や女性管理職比率の向上目標などを設定し、進捗状況を定期的に報告することが好ましいです。投資家やステークホルダーはこれらの指標を通じて、企業の取り組みが実際に成果を生み出しているかを客観的に判断できるため、透明性の高い報告が求められます。
IFRS S1号の全般的要求事項
IFRS S1号には、ガイダンスの情報源、開示の記載場所、報告のタイミング、比較情報、準拠表明といった要求事項が定められています。これらの項目を理解することで、適切な情報開示につながるので、ぜひ押さえておきましょう。
ガイダンスの情報源
IFRS S1号の開示を行う際には、既存の国際基準やフレームワーク(TCFDやGRIスタンダードなど)を参考情報として活用できます。企業はこうした公的ガイドラインを参照することで、財務情報と矛盾しない形でサステナビリティに関する重要情報を整理しやすくなります。
ただし、IFRS S1号と他のフレームワークが相反する場合には、IFRS S1号の基準を優先的に適用する必要があります。
開示の記載場所
IFRS S1号では、サステナビリティ関連情報を財務諸表と同じ報告書内で開示することが推奨されています。有価証券報告書やアニュアルレポートなど、投資家が財務情報とともにアクセスしやすい場所に記載することが望ましいです。
サステナビリティレポートなど別紙に記載する場合は、財務情報との関連性が途切れないよう、適宜クロスリファレンスを設定するなどの工夫が必要になるでしょう。
報告のタイミング
IFRS S1号は、財務報告と同じタイミングでサステナビリティ関連情報を開示することを原則としています。投資家やステークホルダーが財務情報と併せてリスクや機会を評価できるようにするためです。また、中間報告や四半期報告においても必要な情報を開示するよう求められる場合がありますが、法規制や証券取引所の規定によって異なるため、企業は該当するルールを確認することが必須です。
比較情報
IFRS S1号に基づいて情報を開示する際は、前期の数値や過去の実績と比較できるようにすることが好ましいです。例えば、温室効果ガス排出量や水使用量などの環境指標を複数年分並べて報告することで、企業の改善状況や傾向を把握しやすくなります。ただし、指標や測定方法が変更された場合は、その理由や影響を明示し、投資家やステークホルダーが適切に理解できるよう配慮が必要です。
準拠表明
企業はIFRS S1号に準拠して報告する場合、「IFRS S1号に準拠したサステナビリティ関連財務情報の開示である」ことを明確に表明する必要があります。これにより、投資家やステークホルダーは、開示内容が国際会計基準に沿ったものかどうかを簡単に判別できます。
また、他のフレームワークも併用している場合は、どの部分をどの基準に基づいて開示しているのかを整理して示すことが望ましいです。
IFRS S1号を適用するときの注意点
IFRS S1号を適用する際は、判断や測定の不確実性、誤謬(ごびゅう)の取り扱いなどに注意が必要です。以下では、代表的な3つのポイントについてご紹介します。
企業独自の判断が求められる
サステナビリティ関連情報の開示には、企業独自の判断が求められる場面が多々あります。例えば、どのリスクや機会を重要とみなし、どの程度詳細に開示するかなどは、企業の業種や事業環境によって異なります。IFRS S1号では「重要性」の原則が提示されていますが、それでも最終的な判断は企業自身に委ねられるため、組織内で合意形成を図り、根拠を明確にすることが重要です。
サステナビリティ情報の測定に不確実が伴う
気候変動など、長期的な戦略や取り組みが求められ、かつ複雑な要素が絡むサステナビリティ情報の測定には不確実性が伴います。将来シナリオの想定や、環境インパクトの算出方法などに複数の仮定が含まれるため、数字には一定の幅や誤差が生じる可能性があります。
IFRS S1号では、こうした不確実性を適切に開示し、投資家やステークホルダーがリスク評価の前提条件を理解できるようにすることが求められます。
誤謬(ごびゅう)を避ける必要がある
誤謬とは、意図しない計算ミスや表記ゆれ、開示漏れなどを指します
IFRS S1号では、財務情報と同様に、サステナビリティ関連情報においても誤謬を避けるための内部統制や検証プロセスが重要となります。例えば、温室効果ガス排出量の測定方法やデータ収集の仕組みを定期的に見直し、最新の基準や技術に沿った開示ができるかを確認する体制づくりが求められます。
IFRS S1号の日本語訳の入手方法
IFRS S1号の日本語訳については、IFRS財団の日本語版サイトなどが公開しています。翻訳がリリースされ次第、公式サイトで通知されるため、こまめに情報を確認しておきましょう。
参考:Sustainability pdf collection|IFRS
IFRS S1号はサステナビリティ情報を結び付ける重要な要素
IFRS S1号を導入すれば、サステナビリティ関連情報を財務情報と統合し、投資家やステークホルダーに正確かつ比較可能な情報の提供が可能となります。経営戦略やリスク管理、ガバナンス体制など、企業が将来どのように価値を創出し、持続可能性を高めるのかを明確に示すことで、長期的な企業価値の向上につながるでしょう。
今後、サステナビリティであることがますます求められるようになるはずです。IFRS S1号への対応は企業の信頼性と競争力を左右する重要な要素となります。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
国際会計基準(IFRS)の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引