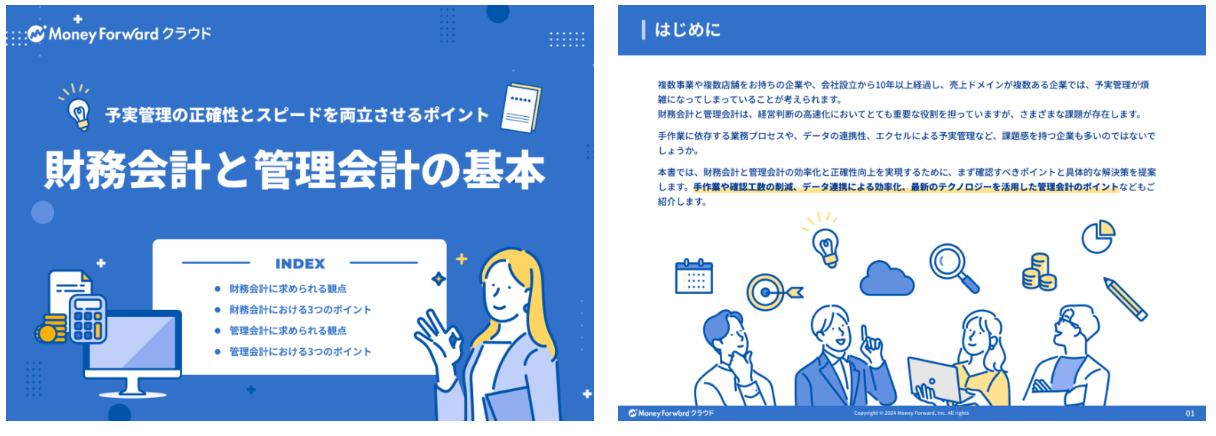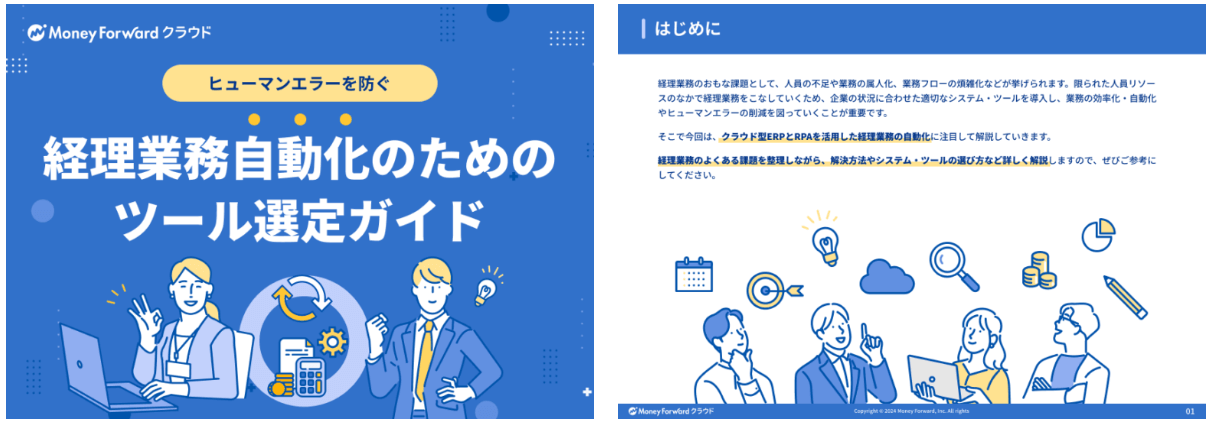- 更新日 : 2025年9月4日
IFRS(国際財務報告基準)対応の会計ソフトの選び方は?初心者にも簡単に解説
会計ソフトの中には、IFRS(国際財務報告基準)に対応したものもあります。日本基準だけでなく、IFRS対応の会計ソフトを選択するメリットはあるのでしょうか。IFRSに対応するメリットや会計ソフトの選び方、導入時の注意点について解説します。
IFRS(国際財務報告基準)とは
IFRSとは、国際財務報告基準のことです。International Financial Reporting Standardsの頭文字をとって、IFRSといわれます。国際会計基準審議会により策定された会計基準で、EU域内の上場企業ではIFRSの適用が義務付けられています。
IFRSと日本基準の違い
IFRSは、ヨーロッパを中心に適用が進んでいます。一方、アメリカや日本などでは自国基準の会計基準が根付いています。そのため、自国基準をIFRSに近づけて差異を縮小させるコンバージェンスが重視されるようになりました。日本では、財務諸表の連単の分離や中小企業などへのIFRSの影響が生じないことを前提に、日本基準を主体としたコンバージェンスが進められています。
日本基準をIFRSに近づける動きはあるものの、日本基準とIFRSではさまざまな差異が見られます。まず、日本基準とIFRSでは下記のように作成する財務諸表に違いがあります。
| IFRSの財務諸表 | 日本基準の財務諸表 |
|---|---|
|
IFRSと日本基準の財務諸表は相互に類似するものではありますが、区分や表示する項目、開示する内容などに違いがあります。例えば、日本基準の損益計算書には5段階の段階損益(売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益)の表示が求められる一方、IFRSの純損益及びその他の包括利益計算書には、段階損益の規定はありません。ただし、純損益、その他の包括利益、当期の包括利益の表示が求められています。
他にも、固定資産の範囲や償却方法、関連会社の持分法の適用、のれんの会計処理、減損の認識や戻し入れ、引当金の概念、注記で開示する事項など、さまざまな面で違いがあります。
IFRSを適用している会社
日本において、IFRSは連結財務諸表に適用できます。上場企業であるグループ会社を中心に、さまざまな企業での適用が見られます。以下の表は、日本取引所グループが公開しているIFRS適用会社の一部です。
| 企業名 | 適用時期 |
|---|---|
| 住友商事 | 2011年3月期 |
| ソフトバンクグループ | 2014年3月期 第1四半期 |
| 武田薬品工業 | 2014年3月期 |
| 三井物産 | 2014年3月期 |
| 日立製作所 | 2015年3月期 |
| 本田技研工業 | 2015年3月期 |
| アサヒグループホールディングス | 2016年12月期 |
| 住友ゴム工業 | 2016年12月期 |
| 花王 | 2016年12月期 第1四半期 |
| 三菱ケミカルグループ | 2017年3月期 第1四半期 |
| ENEOSホールディングス | 2017年3月期 |
| ライオン | 2018年12月期 第1四半期 |
| 日清食品ホールディングス | 2019年3月期 第1四半期 |
| 日本製鉄 | 2019年3月期 |
| ヤマハ | 2020年3月期 第1四半期 |
| トヨタ自動⾞ | 2021年3月期 第1四半期 |
| ソニーグループ | 2022年3月期 第1四半期 |
| 資生堂 | 2022年12月期 第1四半期 |
| 川崎重工業 | 2023年3月期 第1四半期 |
| 村田製作所 | 2024年3月期 第1四半期 |
IFRS対応の会計ソフトを導入するメリット
一般的な会計ソフトとIFRS対応の会計ソフトとの違いは、IFRSに対応して設計されていることです。日本だけでなく海外でも利用しやすく、海外子会社と会計基準を合わせられます。IFRS対応の会計ソフトには、多言語表示や多通貨会計などの海外での利用を想定した機能が含まれたものもあります。ここでは、IFRS対応の会計ソフトを導入するメリットを紹介します。
グローバル基準での財務報告ができる
IFRS対応の会計ソフトは、国際基準での財務報告書を作成するのに役立ちます。IFRSに対応することで、国際的な企業間比較に役立つ情報を投資家に提供できるのがメリットです。複数の会計基準の帳簿を作成できるソフトであれば、日本基準とIFRSなど、複数の財務諸表を管理することも可能です。
M&Aや海外展開がスムーズにできる
IFRS対応の会計ソフトは、海外に子会社や事業会社のある企業やグローバルビジネスを展開する企業を中心にニーズがあります。IFRS対応の会計ソフトをグループに導入することで、海外に拠点がある複数のグループ内企業との情報統合が容易になるためです。このように、すでに海外展開をしている企業はもちろん、M&Aによる海外企業の取得や海外展開を検討している企業にも向いています。IFRSに対応することで、海外で求められる財務情報の提供に対応しやすくなるためです。
投資家や金融機関からの評価が向上する
IFRS対応の会計ソフトの導入は、投資家や金融機関からの評価向上にも役立ちます。IFRSに対応することで、海外投資家や海外の金融機関向けに日本基準との違いを説明する必要がなくなるためです。財務状況を誤解なく提供できることから、海外からの資金調達にプラスになる可能性があります。
IFRS対応の会計ソフトの選び方
IFRS対応の会計ソフトはどのように選ぶべきか、選定のポイントを紹介します。
IFRSに準拠した財務諸表を作成できるか
IFRS対応の会計ソフトを導入する目的は、IFRSに準拠した財務諸表を開示できるようにすることです。そのため、会計処理がIFRSに対応しているだけでなく、少なくともIFRSの財務諸表を作成できる機能があることが求められます。
なお、日本企業の場合、個別の財務諸表については日本基準に準拠していることが必要です。個別財務諸表を日本基準とIFRSの2つの方法で作成したい場合は、複数の会計基準で財務諸表を作成できる機能が備わっている会計ソフトが便利です。
グループ企業の連結決算に対応しているか
日本でIFRSの適用が認められているのは、連結財務諸表です。個別財務諸表は日本基準での作成が求められることから、IFRSに対応した連結財務諸表の作成方法としては2パターン考えられます。
1つは、親会社が各連結会社から集めた個別財務諸表を組み替えて連結財務諸表を作成する方法です。もう1つのパターンとして、各連結会社がそれぞれIFRSと自国基準の個別財務諸表を作成する方法があります。
いずれの方法を採用するにせよ、グループ企業の連結決算に対応した会計ソフトを導入することで、財務諸表を連結させる労力を削減できます。
自動仕訳やデータ連携機能があるか
IFRSと日本の会計基準はさまざまな面で異なります。懸念されるのは、会計処理の変更が必要になったり、財務データの整理が必要になったり、手間がかかることでIFRSの導入がスムーズに進まないことです。
IFRSの導入の手間を少しでも軽減するために、日々の業務プロセスの負担を軽減できるIFRS対応の会計ソフトの導入が役立ちます。例えば、自動仕訳やデータ連携機能により自動で情報を取得できる機能がある会計ソフトです。
自社に合った料金プランがあるか
IFRSの会計ソフトの料金体系は、サービスによって異なります。料金体系を明示せず、要相談としているサービスもあります。クラウド型サービスの場合、月額課金制が一般的です。また、複数の料金プランを設けているサービスは、企業の規模に応じたプランを提供していることもあります。企業の規模や利用できる機能も加味して、自社に適した料金プランが選択できる会計ソフトがおすすめです。
IFRS対応の会計ソフトを導入するときの注意点
IFRSに対応した会計ソフトを導入する際に注意しておきたいポイントを紹介します。
IFRSの移行スケジュールを確認する
一般的に、IFRS対応の会計ソフトの導入は、下記の手順により行います。
IFRSに対応した財務諸表を作成するということは、業務プロセスなどにも大幅な変更が生じる可能性があるということです。導入の前に、人材の確保や導入による影響度合いを確認しておくことが重要です。移行スケジュールについては、このような予備調査も含めた期間の設定を行います。また、導入によりさまざまな変更が生じるため、それによって起こる問題や問題の解決を考慮して移行スケジュールを組む必要があります。
IFRSに対応するための社内体制を整備する
IFRSに対応するには、担当者の育成や人材の確保、システムの導入以外にもさまざまな課題があります。IFRSへの対応により勘定科目の体系や数値などにも変化が生じる可能性があるため、必要に応じて内部統制などの見直しも求められます。
例えば、決算体制の整備や進捗管理の整備、業務フローのような内部統制の文書の見直しが必要です。IFRSの影響も考慮し、予算管理などの仕組みも適宜変更する必要があります。
会計ソフトの導入コストと費用対効果を検討する
IFRSに対応することによるデメリットとして挙げられるのが、導入コストです。IFRSに対応するということは、日本基準とは異なる会計基準を把握して適切に対処する必要があるということです。
IFRSに対応するには、会計ソフトの導入だけでなく、さまざまなコストを想定しておく必要があります。例えば、IFRSに対応するための人材確保として社員教育のコストが想定されます。導入前の調査を外部に依頼する場合には調査コスト、外部の専門家からの支援を受けたい場合には外部アドバイザーに対する報酬の支払いも必要です。システム以外の導入コストも含め、IFRSの対応でどのくらいの費用対効果が得られるのか試算して、実際に導入するかどうか検討することをおすすめします。
IFRS対応の会計ソフト導入には準備が必要
IFRS対応の会計ソフトを導入することには、グローバル基準の財務情報を提供できるようになるなどのメリットがあります。しかし、IFRSは日本の会計基準とは異なる面も多いため、一般的な会計ソフトの移行と比較して、多大な準備期間が必要です。移行のメリットや費用対効果なども考慮して、IFRSに対応するかどうか十分に検討しましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
国際会計基準(IFRS)の関連記事
会計ソフトの関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引