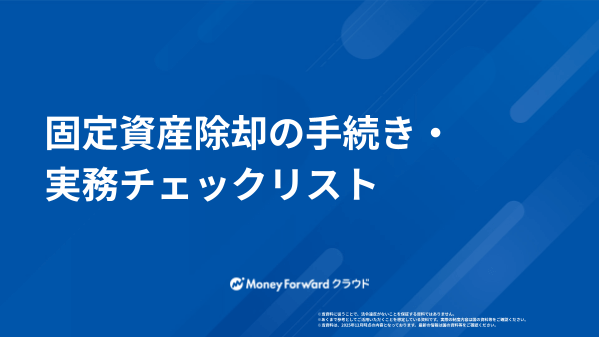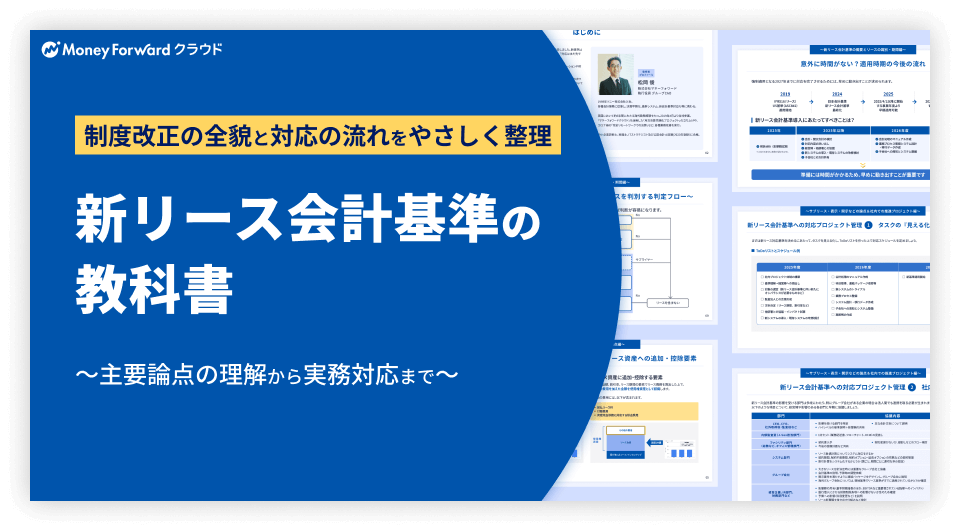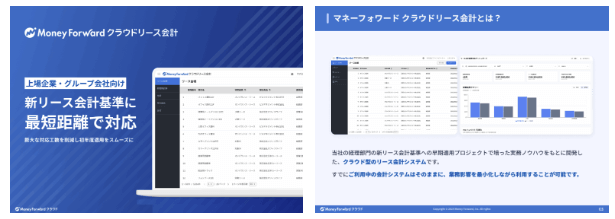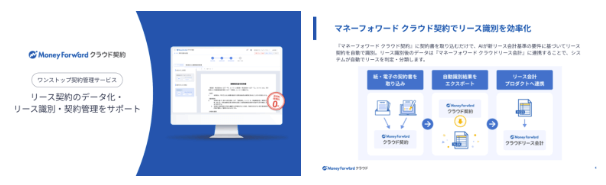- 更新日 : 2026年1月20日
資産除去債務と税務調整について
法令や契約などによって発生する固定資産の除去費用については、あらかじめ資産除去債務として財務諸表に表示する必要があります。ただし、資産除去債務に関する費用については、税務上は損金処理のタイミングが異なるため、税務調整を行わなければなりません。
ここでは、資産除去債務における会計と税務の違いや、税務調整の方法について解説します。
目次
資産除去債務とは?
資産除去債務とは、貸借対照表において負債として表示される科目であり、有形固定資産に関する将来の除去費用を現在価値に換算したものです。
まずは、資産除去債務の概要や資産除去債務を計上する場合の手順を理解して、適切な対応を徹底しましょう。
資産除去債務の概要
資産除去債務とは、将来発生することが見込まれる資産の除去費用を見積もり、それを現在価値に割り引いたうえで、負債に計上する会計処理のことです。
除去費用については、法令や契約に基づいて法律上の義務が発生するものが対象となり、アスベストの除去費用や賃貸借契約に基づく原状回復費用などが挙げられます。したがって、企業が自主的に行う除去費用は、資産除去債務に該当しません。
資産除去債務については、2010(平成22)年4月1日以降の事業年度から適用された「資産除去債務に関する会計基準」に基づいて会計処理を行う必要があります。それ以前も、電力業などの特定の業界においては、解体引当金などの形で計上されていましたが、現在では上記の会計基準に基づく統一的な会計処理が求められています。
■「資産除去債務に関する会計基準」が導入された背景
なお、資産除去債務の計上については、上場企業やその連結子会社などが主な対象です。中小企業などの場合には、必ずしも貸借対照表へ表示する必要はありません。
資産除去債務の計算方法
資産除去債務に関する会計処理を行う場合には、以下のような手順に則って計上額を計算します。
- 将来キャッシュフローの見積もり
当該有形固定資産の撤去や処分に要する費用を合理的に見積もります。たとえば、過去の実績や業者の見積金額などを参考にします。 - 割引率の決定
将来キャッシュフローを現在価値に換算するための割引率を設定します。具体的には、無リスクかつ税引前の利率を用いることとなり、利付国債の流通利回りなどを基準とするケースが一般的です。 - 現在価値への割引
見積もった将来キャッシュフローを割引率で割り引き、資産除去債務として計上すべき現在価値を計算します。
なお、将来キャッシュフローについては、以下のような情報をもとに算出します。
- 除去作業に必要な平均的な費用
- 資産取得時に見積もられた除去費用のデータ
- 類似資産の過去の除去費用実績
- 投資決定時の除去費用の見積もり
- 除去作業を行う業者からの見積もり情報
将来キャッシュフローには、直接的な除去費用だけでなく、当該資産の保管や管理など、除去するまでの関連費用も含まれます。ただし、法人税などの影響額を含めない点には注意が必要です。
また、インフレ率や予測値の乖離リスクも反映し、技術革新や法規制の変更による影響も合理的に見積りが可能な場合には、これらも計算に加味します。
なお、将来の除去費用については、月日の経過に伴い、企業の事業状況や外部環境の変化に応じて変動するケースも少なくありません。将来キャッシュフローの見積変更が生じた場合には、資産除去債務についても調整が必要となるため、企業は定期的なモニタリングが求められます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
資産除去債務の会計処理
資産除去債務を計上する場合には、固定資産の購入時に負債として表示すべき金額を計算するだけでなく、毎期の決算時にも仕訳計上を行う必要があります。
具体的には、以下の流れに沿って適切な会計処理を行いましょう。
購入時の仕訳処理
固定資産の購入時に資産除去債務を計上する場合には、将来キャッシュフローの見積額を現在価値に割り引いて負債として計上すべき金額を算定します。具体的には、資産除去債務として計上する金額と同額を有形固定資産の帳簿価額に加算します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | ×××円 | 資産除去債務 | ×××円 |
※(監修者免責)ここでは、具体的な計算方法というより、仕訳の全体像のみをシンプルに提示するため、具体的な金額は避けて作成しています。
この仕訳を計上することで、固定資産の取得価額には、実際の購入価格だけでなく将来負担すべき除去費用の現在価値が上乗せされます。資産除去債務の額が取得価額に加算されることにより、それぞれの耐用年数にわたって減価償却費として各事業年度に費用配分されます。
決算時の仕訳処理
決算時には、資産除去債務の帳簿価額に基づき利息費用を計上する必要があります。これは、時間経過とともに負債の現在価値が増加することを財務諸表へ的確に表示するためのものです。具体的な仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 利息費用 減価償却費 | ×××円 ×××円 | 資産除去債務 減価償却累計額(間接法の場合) | ×××円 ×××円 |
毎期の決算時に利息費用を計上することで、資産除去債務の帳簿価額が増加するため、時間の経過とともに増加する将来キャッシュフローの現在価値をより正確に反映することが可能です。
一方、資産除去債務に対応する除去費用として加算された有形固定資産の取得価額については、耐用年数にわたって減価償却費として費用配分されます。これにより、除去費用についても資産の使用期間全体を通じて適切に費用化できるため、期間損益計算の透明性が向上します。
除去時の仕訳処理
資産除去債務の対象となった資産を除却した場合には、資産除去債務を取り崩し、実際に発生した除去費用を現金または預金から支払います。具体的な仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 資産除去債務 | ×××円 | 現金預金 | ×××円 |
実際に固定資産を除去したことで、これまで計上してきた資産除去債務の帳簿価額と実際の支出額が相殺されて資産除去債務は消滅します。
なお、実際の除去費用が資産除去債務の残高と異なる場合には、その差額は「履行差額」として損益計算書上の収益または費用に計上されます。
資産除去債務の税務上の取扱いについて
資産除去債務は、会計基準に基づいて計上される負債科目ですが、このような会計処理と税務上の取扱いは異なります。
具体的には、会計と税務において、固定資産の除去費用に関する損金算入のタイミングに違いがあることで、法人税計算では税務調整が必要となります。
税務における損金算入時期の考え方
法人税法では、損金算入の基準として「債務確定主義」が採用されています。これは、債務が確定したと認められる時点でのみ損金算入が認められるという考え方に基づいています。
この観点から、税務上は資産除去債務について以下のように扱われます。
- 資産取得時
固定資産の取得時点では、将来発生する除去費用に関する債務が確定しているとは認められないため、税務上は損金として認められません。したがって、会計上における資産除去債務の計上による減価償却費や利息費用については、税務上は損金には該当せず、課税所得に加算する必要があります。 - 資産除去時
資産を実際に廃棄・処分した時点で、第三者に対する債務が確定します。したがって、除去費用については、除却時点で初めて税務上の損金算入が可能となります。
税務調整の方法
会計基準では、資産除去債務は将来発生が見込まれる除去費用を財務諸表に反映することを目的として、法律上の義務が発生した時点で認識します。これにより、資産除去債務に関する会計処理の一環として、決算時において減価償却費や利息費用が各期の費用として計上されます。
一方で、税務上においては実際の支出が発生する除去時点でようやく損金として認められます。このような会計と税務の差異が生じることで、法人税などを計算する場合には、以下のような税務調整を行わなければなりません。
- 別表4(所得調整)
会計上で費用計上された利息費用や減価償却費については、別表4で加算することにより、課税所得が増加します。 - 別表5(1)(帳簿価額の調整)
資産除去債務として計上された負債額や、両建て処理によって固定資産の帳簿価額に上乗せされた額については、別表5(1)で調整を行うことで、税務上は資産除去債務が計上されていない状態に戻すこととなります。
なお、資産除去債務の税務調整により、会計上認識された費用と税務上の損金が一致しないため、一時差異が発生します。この差異に基づき、税効果会計によって繰延税金資産または負債を計上することとなります。
税務調整の具体例
資産除去債務に関する税務調整について、以下では具体例を用いて、その内容を確認しましょう。
◎前提条件
■ 固定資産について
会計上の処理
建物取得時には、将来の除去費用である1,000を現在価値に割り引いて、資産除去債務として計上すべき金額を計算します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 建物 | 3,915 | 現金預金 資産除去債務 | 3,000 915(※1) |
(※1)1,000(割引前将来キャッシュフロー)÷【1+3%(割引率)】^3≒915
なお、毎期の決算時に計上する減価償却費や利息費用の内訳については下表のとおりです。
■ 各事業年度における費用の内訳
| 事業年度 | 減価償却費(※2) | 利息費用(※3) | 除去費用 |
|---|---|---|---|
| ×2年3月31日 | 1,305 | 28 | 0 |
| ×3年3月31日 | 1,305 | 28 | 0 |
| ×4年3月31日 | 1,305 | 29 | 0 |
| 合計 | 3,915 | 85 | 0 |
(※2)減価償却費:3,915÷3年=1,305
(※3)利息費用:(資産除去債務+過年度の利息費用合計)×3%によって計算
したがって、減価償却費と利息費用の合計額は「3,915+85=4,000」となり、建物の取得価額3,000に除去費用1,000を加えた金額と一致します。
税務上の処理
税務処理においては、債務確定主義に基づいて、会計による資産除去債務の計上がなかったものとして、課税所得を計算しなければなりません。
そのため、各事業年度において計上すべき損金については下表のとおりです。
■ 各事業年度における損金の内訳
| 事業年度 | 減価償却費(※) | 利息費用 | 除去費用 |
|---|---|---|---|
| ×2年3月31日 | 1,000 | 0 | 0 |
| ×3年3月31日 | 1,000 | 0 | 0 |
| ×4年3月31日 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 合計 | 3,000 | 0 | 1,000 |
(※)減価償却費:3,000÷3年=1,000
損金計上額としては、減価償却費3,000と除去費用1,000の合計4,000となり、会計処理と同額になりますが、損金算入のタイミングが大きく異なります。
会計上における資産除去債務による減価償却費の増額分や利息費用については、税務上は損金処理が認められず、実際に除去費用を支出した際にまとめて損金算入することとなります。
税務調整
法人税を計算する際には、会計にて計上された資産除去債務の仕訳処理を取り消すために、以下のような申告調整を行う必要があります。
1. ×2年3月期
➀ 別表4
- 減価償却超過額:305(加算・留保)
- 利息費用否認:28(加算・留保)
税務上は上記の2つを加算することで、資産除去債務に関連する費用を除外して所得計算を行わなければなりません。
➁ 別表5(1)
| 区分 | 期首現在利益積立金額 | 当期の増減 | 差引翌期首現在利益積立金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 減 | 増 | |||
| 建物 | ▲915 305 | ▲610 | ||
| 資産除去債務 | 915 28 | 943 | ||
別表5(1)では、当初の資産除去債務915の計上がなかったものとしたうえで、別表4で損金から除外した費用についても反映することで、資産除去債務の計上分を取り消します。
2. ×3年3月期
➀ 別表4
- 減価償却超過額:305(加算・留保)
- 利息費用否認:28(加算・留保)
➁ 別表5(1)
| 区分 | 期首現在利益積立金額 | 当期の増減 | 差引翌期首現在利益積立金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 減 | 増 | |||
| 建物 | ▲610 | 305 | ▲305 | |
| 資産除去債務 | 943 | 28 | 971 | |
3. ×4年3月期(除却年度)
➀ 別表4
- 減価償却超過額:305(加算・留保)
- 利息費用否認:29(加算・留保)
- 減価償却超過額認容:915(減算・留保)
※305×3期分=915 - 利息費用認容:85(減算・留保)
※28+28+29=85
実際に固定資産を除却したタイミングで損金計上が認められるため、これまで損金不算入として加算してきた減価償却費や利息費用をまとめて減算処理します。
➁ 別表5(1)
| 区分 | 期首現在利益積立金額 | 当期の増減 | 差引翌期首現在利益積立金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 減 | 増 | |||
| 建物 | ▲305 | 305 | 0 | |
| 資産除去債務 | 971 | 1,000 | 29 | 0 |
別表4にて減算・留保とした915+85=1,000を資産除去債務から取り崩すことで、別表5(1)における資産除去債務が消滅します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
資産除去債務の関連記事
新着記事
請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説
Point請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 A…
詳しくみる請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説
Point請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個…
詳しくみる振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説
Point振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業…
詳しくみる振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説
Point振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社…
詳しくみる振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説
Point振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 …
詳しくみる振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法
Point振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OC…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引