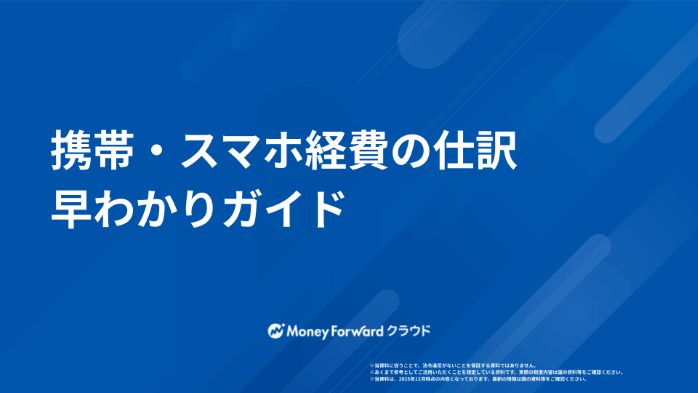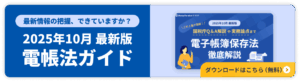- 更新日 : 2026年1月8日
スマホや携帯電話代は経費にできる?個人事業主の場合は?仕訳と勘定科目まとめ
業務に必要なスマホや携帯電話の購入費、通信料は経費にできます。また、修理代や周辺機器の購入費も同様です。本記事では、スマホ・携帯電話にかかる各費用の勘定科目、仕訳方法について詳しく解説していきます。個人事業主がプライベートでも併用するスマホを経費にするための家事按分もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
スマホや携帯電話代は経費にできる?
会社や個人事業主が業務をする上で、スマホ(スマートフォン)または携帯電話を使用するケースは多いでしょう。そのような事業関連で使用するスマホ・携帯電話にかかる費用は、経費精算することが可能です。
一般的に、法人であれば事業で使用していることが証明しやすく、経費として認められやすいです。しかし個人事業主の場合は、仕事とプライベート共用のスマホとして使用している方も多いでしょう。そのため、経費にできないケース、または全額を経費化が認められないケースもあります。
まずは法人と個人事業主に分けて、それぞれ詳細を解説していきます。
法人の場合
法人がスマホ・携帯電話を法人契約で購入・使用する場合の購入費や通信費、通話料などの費用を全額経費として精算できます。
例えば、法人契約で購入したスマホを社員に支給した場合は、事業で使用していることが証明しやすく、税務署から指摘される可能性は限りなく低いでしょう。このほかにも、事業で使用していることが証明しやすいように、取引先との連絡手段に使用するために支給したスマホの電話番号を、社員の名刺に記載するなども適しています。
個人事業主の場合
個人事業主がスマホを使用する場合、仕事とプライベートで併用することも考えられます。その場合、仕事で使用しているのは何割程度なのかを確認して「家事按分(かじあんぶん)」しましょう。家事按分をすることで、費用の一部を経費精算することが可能です。
個人事業主がスマホを利用する場合、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、特に注意しておきましょう。また、事業内容によってスマホの重要性は異なります。例えば、IT関連であれば常にインターネットで調べることがあるため、通信料(インターネット利用料)を家事按分する際は、半分程度を経費にできるかもしれません。
もちろん、プライベート用のスマホとは別に、仕事専用スマホを購入・利用する場合は全額を経費精算することが可能です。
また、個人事業主でも法人契約でスマホや携帯電話を購入・利用できます。個人事業主が法人契約をするためには、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「確定申告書」、そして「営業所の住所確認書類」が必要になるため覚えておきましょう。
スマホや携帯電話の通信料の仕訳
スマホ(スマートフォン)や携帯電話にかかる費用には、毎月継続的に発生する通信料(インターネット利用料)があります。通信料を経費として仕訳する際に使用する勘定科目は、「通信費」が一般的です。
法人契約しているスマホで毎月1万円の「通信費」が発生している場合は、以下のように仕訳しましょう。
1月分 | ||||
摘要欄には、何月分の通信費であるかも記載しておくことで、確認しやすくなります。
また、個人事業主が仕事とプライベートで併用しているスマホの通信費を支払った場合は、以下のように記入してください。
例えば10,000円の通信費を支払ったとして、事業で使用した割合はどのくらいなのか、家事按分する比率を決めます。今回は事業用60%、プライベート40%に設定しました。
1月分 (事業用60%) | ||||
スマホや携帯電話を購入した場合の仕訳
スマホ(スマートフォン)や携帯電話の本体の購入費も経費にすることが可能です。購入費が10万円未満であれば「消耗品費」、10万円以上であれば「工具器具備品」として仕訳するのが一般的です。
法人契約で購入したスマホ・携帯電話は、費用の全額を経費として精算できます。しかし、プライベートと併用するスマホ・携帯電話の場合は、家事按分をして費用の一部を経費精算しましょう。詳しく解説していきます。
10万円未満の場合
10万円未満のスマホ・携帯電話の購入費は「消耗品費」で仕訳しましょう。例えば家電量販店に行き、事業で使用するスマホを50,000円で現金購入した場合は、以下のとおりです。
法人契約でスマホ・携帯電話を購入する場合は10台、30台などある程度まとめて購入することも考えられます。そのような場合、購入費をまとめると10万円以上になりますが1台あたりの購入費が10万円未満であれば、上記と同様に仕訳しましょう。
例えば、法人契約で50,000円のスマホを10台購入した場合は、以下のように仕訳してください。
摘要欄に、スマホの購入費(消耗品費)が10台分であることを記載しておきましょう。この記載がないと仕訳ミスと判断され、改めて「工具器具備品」として計上されてしまう可能性があるため注意が必要です。
個人事業主が仕事とプライベート併用のスマホを80,000円で購入して、事業では50%使用する場合は、以下のように家事按分をして仕訳してください。
(事業用50%) | ||||
家事按分をしていることが分かるように、摘要欄には「按分比率」を記載しておきましょう。
10万円以上の場合
最近は高機能で、10万円を超えるスマホも増えてきました。10万円以上のスマホ・携帯電話を購入した場合は「工具器具備品」に計上して、耐用年数に応じた減価償却をしなければいけません。
しかし、スマホは近年になって登場したため、耐用年数の一覧表にスマホが記載されていません。一番近いものでは、「電話設備その他の通信機器」のデジタルボタン電話が6年、その他のものが10年とされています。
ただし、実際はスマホをそこまで長く利用するのは少数派でしょう。そこで、スマホを電子計算機(携帯用パソコン)と考えれば、耐用年数は4年です。そのため、「工具器具備品」に計上して減価償却する場合は4年で減価償却をするとよいでしょう。
例えば、事業で使用するスマホを120,000円で購入(法人契約)した場合は、以下のように「工具器具備品」で仕訳します。
スマホ | ||||
そして決算時には減価償却をして、以下のような仕訳をしてください。今回は120,000円を耐用年数4年で減価償却するため、1回あたりの減価償却費は30,000円です。
減価償却◯回目 | ||||
10万円以上20万円未満のスマホ・携帯電話であれば、「一括償却資産」で仕訳して3年で減価償却することも可能です。より短期間で減価償却が終わり、一事業年度あたりの経費効果も大きくできます。ぜひ活用することを検討しましょう。
スマホや携帯電話の周辺機器を購入した場合の仕訳
スマホ(スマートフォン)や携帯電話の周辺機器を購入した場合も、経費にすることが可能です。スマホ・携帯電話の周辺機器には、充電器や充電コード、USBメモリやモバイルバッテリーなどが挙げられます。当然ですが、キーホルダーのようなスマホアクセサリーなどは業務に必要ないと判断されるため、経費にはできません。
スマホを保護するためのスマホカバーをはじめ、上記のような周辺機器を仕訳する際に利用する勘定科目は「消耗品費」です。10万円を超えるような周辺機器は、基本的に見られないため「周辺機器は消耗品費で仕訳する」と覚えておくとよいでしょう。
例えば、事業で使用するスマホの保護をするために5,000円のスマホカバーを現金で購入した場合は、以下のとおりです。
スマホカバー | ||||
最近は、スマホでも使えるUSBのスタンドライトをはじめ、さまざまな周辺機器があります。事業で使うけれど本当に経費として認められるか不安という場合は、最寄りの税務署で確認することもおすすめです。
スマホや携帯電話の修理代の仕訳
業務において必要なスマホや携帯電話が壊れてしまい、修理をした際の修理代は「修繕費」として経費精算することが可能です。また、「通信費」あるいは「消耗品費」を利用することも考えられます。
勘定科目には「絶対にこの勘定科目を使用しなければならない」というルールはありません。継続的に同じ勘定科目を利用することが重要なため、過去に修理代を仕訳している場合は、そのときに使用した勘定科目で仕訳しましょう。
例えば、社員に貸与していたスマホの画面が割れてしまい、修理に出したとします。そして修理代が8,000円かかった場合の仕訳は、以下のとおりです。
修理代を経費にできないと考えている方もいるかもしれませんが、業務上必要なモノの修理については修理代を経費精算できるため覚えておきましょう。
スマホ・携帯電話にかかる各費用は経費にしよう
事業で利用するためにスマホ(スマートフォン)や携帯電話を購入した場合は、毎月発生する通信料(インターネット利用料)だけではなく、本体の購入費も経費精算することが可能です。本体の購入費が10万円未満であれば「消耗品費」、10万円以上であれば「工具器具備品」で仕訳するため注意しましょう。
法人契約をしているスマホ・携帯電話は事業に利用していることを証明しやすいですが、個人事業主の場合は仕事とプライベートで併用している方も多いです。仕事とプライベートで併用する場合は、家事按分をして費用の一部を経費精算します。無理のある家事按分は、税務署から否認されてしまう可能性があるため、質問されても答えられるように合理的な割合で家事按分をしましょう。
また、事業用口座で支払いをすることで、事業で使用していることをより説明しやすいです。最近はスマホが必須といっても過言ではないほど、必要な時代です。ぜひ本記事を参考にして、スマホ・携帯電話代を経費精算していきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
よくある質問
スマホ・携帯電話代は経費にできる?
事業に関係しているスマホ・携帯電話代は経費精算できます。ただし、個人事業主は仕事とプライベートで併用する方も多いでしょう。その場合は仕事で使う割合を決めて、費用の一部を経費にするための家事按分が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
スマホ・携帯電話代の仕訳のポイントは?
スマホや携帯電話代を仕訳する際は、必要であれば家事按分をして適切かつ合理的な金額を経費精算しましょう。料金の支払いを事業用口座にしておくことで、仕訳を忘れてしまうミスを防ぎやすくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
勘定科目 通信費の関連記事
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引