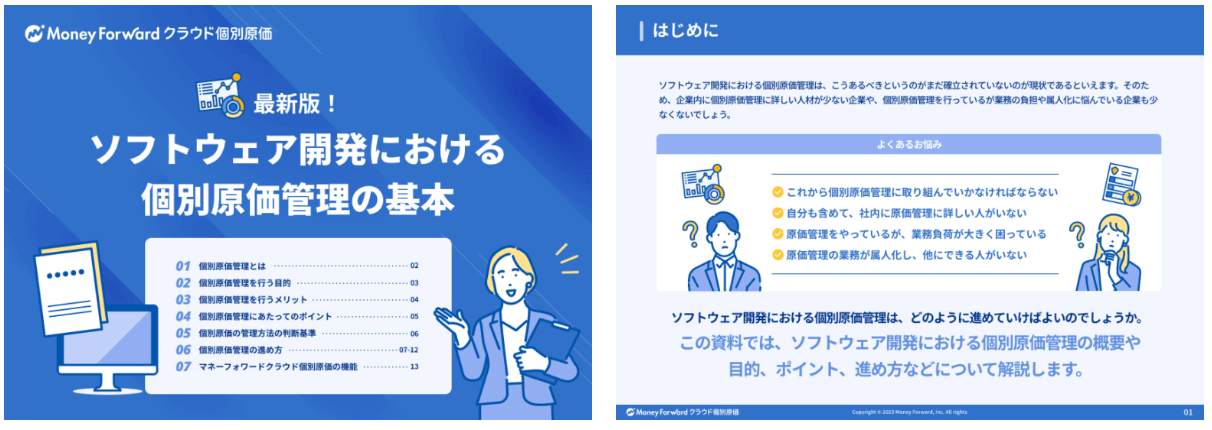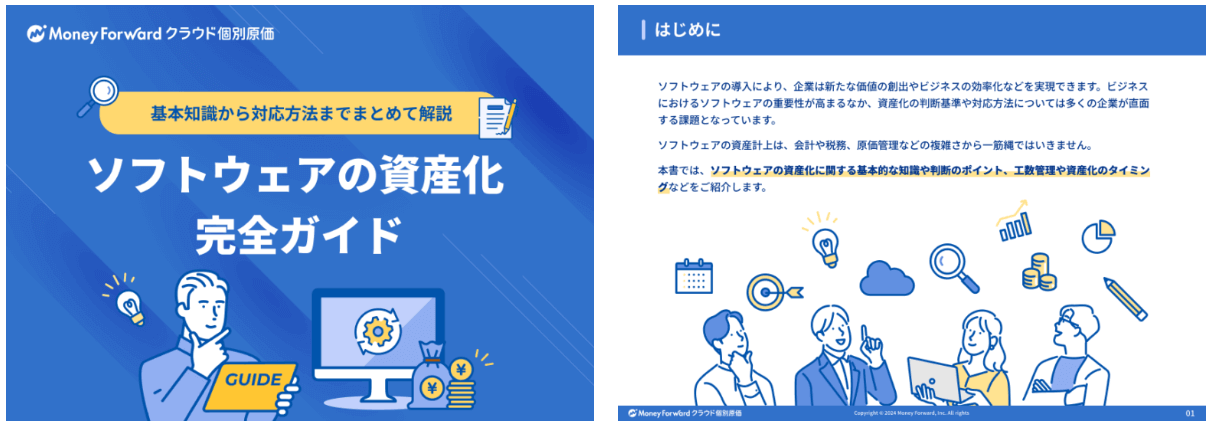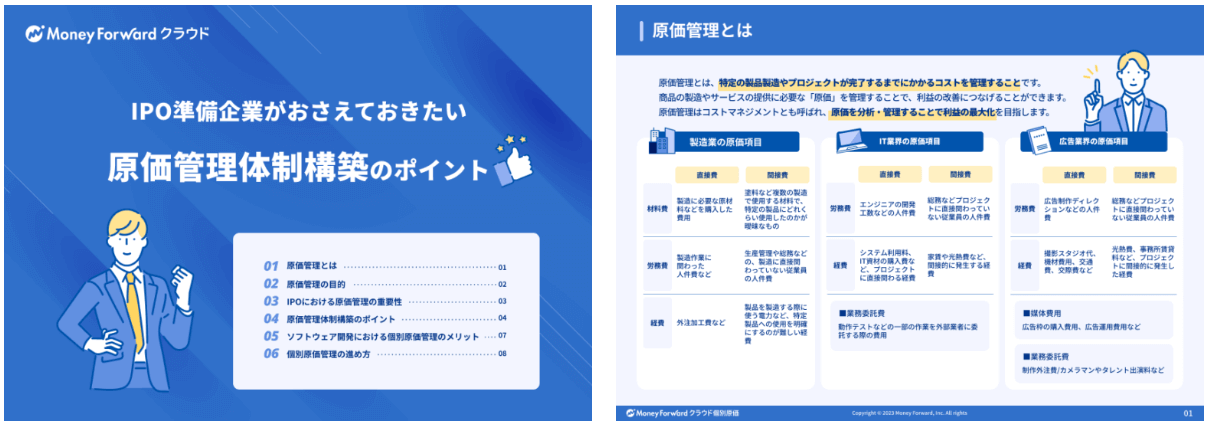- 作成日 : 2025年3月19日
【建設業向け】施工管理における原価管理とは?メリットや計算方法を解説!
施工管理において原価管理を行うのは会社の経営を左右する重要な業務です。
しかし、「管理方法が難しい」「エクセルで管理しているけど時間がかかりすぎる」という悩みを持つ施工管理者も多いのではないでしょうか。
本記事では、施工管理における原価管理を効率的に運用するポイントや方法を解説します。自社の運用ツールに悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
目次
施工管理で行う原価管理とは
施工管理で行う原価管理は、一般的な原価管理と目的の観点が異なります。
まず、原価管理とは、工事過程において人件費や材料費などの資源が不足していないか、または無駄がないかを計算して、予算内で工事を滞りなく進行できるように管理することを指します。
工事を施工する際の予算はあらかじめ決められていますが、予定通りに工事が進んでも原価割れが起きれば赤字になり、赤字が続けば経営が厳しくなります。
施工管理で行う原価管理とは、原価割れによる赤字経営にならないように予算内で施工することを目的に無駄な資源や資材を省き、適正なコストの推移を把握し、適切なコストカットを行うことを意味します。
施工管理の4大管理
施工管理には4大管理と呼ばれる主な業務が存在します。原価・工程・品質・安全に区分され、いずれも工事施工において重要な役割を果たします。
ちなみに、「施工管理」とは建設現場で施工計画の立案、現場全体への指示・指揮、現場そのものや施工業者の管理をする業務のことを指します。
「現場監督」と混同されがちですが、建設業の求人によっては、「施工管理」と「現場監督」はそれぞれ明確なちがいはなく、明確な使い分けがされていません。
ふたつは同意義で使用されている場合も多いですが、厳密には以下のような意味を有します。
| 施工管理 | 施工計画から予算・書類作成、安全事項など工事現場に関連する全ての事項を管理する。施工管理技士という国家資格がある。 |
|---|---|
| 現場監督 | 主に工事現場での作業を管理する。 |
ここでは「施工管理」に統一して呼称します。
施工管理の4大管理について解説しましょう。
①原価管理
原価管理とは、予算内および工期内で工事を完成するために必要な資材費・人件費・諸経費などの原価を管理することを指します。予算の立案やコスト設定を行い、予算オーバーにならないようにシミュレーションします。
原価管理を続けることで、過去データが参考値となり、将来的に工事計画の参考になるなど経営判断の重要な資料となりえます。
②工程管理
工程管理とは、決められた工期までに工事を完了し、建設物を完成させることを目的に作業日程を調整しながら、全体的にスケジュール管理することを指します。工程管理は期間中においてPDCAサイクルを回すことで工期に間に合わせるようにできるのがポイントです。
③品質管理
品質管理とは、その名の通り建設物の品質を落とさないために管理することを指します。発注者が要求するクオリティに即した建設物を実現させることが目的です。発注者が求めるクオリティとは、完成時点での建設物の耐震強度や材質密度などです。
また、建設物の品質基準は地方自治体や国が定めた規定によります。この水準を満たしていないといけないため工程管理との調整が重要です。
そのため設計図や仕様書に記載された規格や資材の寸法や資材そのものの品質が条件を満たしているかどうかを確認することも業務に含まれます。
品質管理では、対象項目の試験を都度実施し、高品質な建設物が長期的に保持できるように管理を行います。
④安全管理
安全管理とは、工事現場においてすべての工程が安全に施工されるように作業環境を整備することを指します。
作業員や周辺地域の住民などに影響を出さないために、あらゆる危険性を想定し、事前に対策を行う必要があります。工事に関わるすべての作業員の安全を確保し保守することが施工管理の重要な任務です。
また、安全管理の項目は以下が挙げられます。
- 機材点検
- 工法の確認
- 危険予知運動
- 作業員の健康状態の確認
- 5s活動
- ヒヤリハットの事例共有
「5s活動」とは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」のことです。安全管理は機材への注意や作業員の統括など全般的に管理します。
原価管理の役割
施工管理における原価管理の役割は工事を予算内および工期内に完了させて、利益を生み出すことです。原価管理を行うことで、予算オーバーを未然に防ぎ、会社や関係団体への損害をなくせるほか、適正なコストカットによって利益を増幅させるなどのメリットも生み出します。
原価管理の具体的な役割は以下のとおりです。
- 工事の進捗把握
- リスク管理
- 予算オーバーにならないような予算調整
- コストカットできる工程を発見・指摘
- 予算と品質に見合った資材・資源の発注と手配
- 将来的な見積もり算出
- 今後の受注価格の参考データの蓄積
以上から施工管理における原価管理は経営上で重要な役割を果たします。
施工管理が行う原価管理と経営者が行う原価管理の違い
原価管理は施工管理者と経営者の二者が担当することが多いです。
立場の違う両者が原価管理を行う理由は、目的や管轄が違うためです。
施工管理者は現場別で各工事を予算内で完遂させることを目的にしており、対して経営者は会社が担当する工事全体の収益を目的としています。どちらも業務を適切に完了させ、健全な会社経営において利益を生み出すために重要な役割を担っています。
施工管理が行う原価管理
施工管理者が行う原価管理の目的は、工事現場で必要とする材料費・人件費・経費すべての資源を管理し各工事ごとの予算内に収めるようにすることです。
施工管理者の管轄では、工事で直接的に必要な諸経費などを分析して算出し、工程や資材・機材の調達に必要かどうかを判断します。厳密に管理することで、予算オーバーや赤字などのリスクを回避し、順当な利益になるように努めています。
経営者の原価管理との決定的なちがいは、個々の担当現場に注目している点です。直接現場を見ることで、無駄な資源の削減、コストカットなどの細かい部分の課題を発見できます。
施工管理者が行う原価管理は以下のようにまとめられます。
| 目的 | 予算内に収めて工期内に完成する |
|---|---|
| 管轄 | 個々の工事 |
| 分析対象 | 管理する工事の直接費・間接費 |
| 判断 | 工程や資機材調達の判断材料 |
| 課題 | 予算オーバーなどのリスク管理 |
以上から施工管理者が行う原価管理の範囲や目的が分かりました。
経営者が行う原価管理
経営者における原価管理の目的は、施工管理者とは反対に会社全体の利益の確保および利益率の向上です。
有効な経営戦略のためには利益率を上げる必要があります。戦略を練る際には工事全体の資金状態や市場の動向を確認、分析することが必要不可欠です。
経営者の立場からは、請け負うすべての工事の原価実績を把握することで将来的な受注価格の設定および今後の経営戦略に役立つ参考データを集約していきます。
経営者が行う原価管理は以下のようにまとめられます。
| 目的 | 会社全体の損益の把握および利益の確保 |
|---|---|
| 管轄 | 会社が担当する工事全般 |
| 分析対象 | 全工事の原価実績 |
| 判断 | 将来の受注価格設定や経営戦略の立案 |
| 課題 | 工事全体の不要な支出の削減と利益率の向上 |
以上から経営者が行う原価管理の範囲や目的が分かりました。
施工管理における原価管理のメリット
施工管理における原価管理のメリットは、大きく3つが挙げられます。
利益面でのメリットでは損益分岐点を把握できたり、作業員への情報共有のしやすさから業務効率化が図れるほか、リスク回避・無駄なコスト削減に直結するコストシミュレーションが可能になるなどです。
下記では、それぞれのメリットを解説します。
損益分岐点を把握できる
施工管理における原価管理のメリットのひとつは損益分岐点が把握できるようになることです。損益分岐点とは工事の売上高と費用が一致し、利益を出し始める点を指します。
損益分岐点の算出は、工事に係るすべての費用(材料費・諸経費・労務費・外注費など)を固定費と変動費に区別し、以下の方程式に当てはめて計算します。
算出した損益分岐点から、経営者が受注した受注額が果たして利益をどれだけもたらすのかが判明します。
利益が少ない場合には、洗い出した固定費や変動費を見直し、どうやって利益を増やすかといった先の見通しがしやすくなるメリットがあります。さらに予算設定で達成売上高を把握することでリスク管理も可能です。
作業員へ状況を伝えやすい
原価管理を行うと工事の進捗具合やコストの推移がリアルタイムで判明します。工事のリアルタイムな状況が分かれば、各作業員に伝達しやすくなります。オーバーコストなどの問題点が判明すれば、原因を作業員にデータとして共有しやすいというメリットがあります。
結果として生産性の向上や無駄なコスト削減を意識できるようになり、合理的な施工工事が可能です。
コストシミュレーションできる
原価管理でコストシミュレーションが可能になることも大きなメリットです。これまでの工事案件を集約した原価管理データを活用すれば、新規案件における工事の粗利益を計算でき、着工前にリスク回避、無駄なコストカット、利益率の把握などが事前に判明します。
コストシミュレーションはさまざまなシーンで想定されます。たとえば資材や材料費が高騰し、仕入れ額が変動した場合の工事原価のシミュレーションや、工期に遅延した場合の追加費用のシミュレーションなどが挙げられます。
工事におけるあらゆるイレギュラーにも柔軟にコストシミュレーションができれば、赤字回避など適切な経営につながっていきます。
施工管理における原価管理のデメリット
施工管理における原価管理のデメリットは、システムの導入によって起こりえます。
デメリットのひとつは初期投資とランニングコストの費用が発生することです。これは建設業に限ったデメリットではありませんが、コストをかけてでも業務効率化によって利益が向上するのかは運用するまで不透明です。
もう一つのデメリットは、システムに慣れるまでに時間がかかることです。デスクワークではない建設現場ではアナログな作業が多く、経営者および管理者と、建設作業員にはシステムの運用に関して慣れるまでの時間に差異が生まれます。
システムを導入すると費用が掛かる
原価管理システムの導入にはさまざまな費用が発生します。初期投資として導入前にネットワーク環境を整備したり、システムに対応するための設備機器を増やす必要があります。
さらにシステムの運用は定額コストがかかります。ランニングコストのほかにもシステムの更新や保守の際には追加費用が発生します。自社の規模感や導入に割ける予算に合ったシステムを選択しましょう。
システムに慣れるまで時間がかかる
原価管理システムの運用はパソコンやスマートフォンで行います。ある程度のPCスキルやスマートフォン操作ができるなら問題ありませんが、建設現場での業務上、パソコンは不要なので運用自体に慣れるには時間を要する可能性が高いです。
この点に関しては、自社の従業員や委託業者へヒアリングし運用に問題がないかを判断しておくことをおすすめします。
システムを導入するなら「マネーフォワード」におまかせ!
施工管理における原価管理の基本から重要性、メリットとデメリットについて解説しました。原価管理を徹底することで現場単位でも、経営全体でも無駄なコストを発見することでコストカットにつながり、黒字経営を実現できるようになります。
さらに、より効率的で正確な原価管理をするなら原価管理システムの活用がおすすめです。システムの導入によって業務効率化も推進できるでしょう。
マネーフォワードの原価管理システムなら企業が懸念するデメリットもカバーできるシステムがあります。導入をご検討の企業はぜひ参考にしてみてください。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
軽減税率対策補助金は3種類 対象者や申請期限を解説
2019年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられます。そこで多くの事業者の頭を悩ませているのが増税とあわせて導入される軽減税率です。 軽減税率によって一部品目は消費税…
詳しくみる青色申告会に入ると税務調査は入りにくい?仕組みと実際を解説
個人事業主やフリーランスの多くが気にするのが「税務調査はどのくらいの確率で入るのか」という点です。 とくに「青色申告会に加入していると税務調査に入りにくいらしい」と耳にした経験があ…
詳しくみる法人のネットバンキング導入5つのメリット!選び方や注意点とは?
Point法人のネットバンキング導入のメリットとは? 振込手数料の大幅な削減と経理業務の効率化につながる手段です。 ネット振込の手数料は窓口の約½~⅓ 会計ソフトとのAPI連携で記…
詳しくみるIFRSの収益認識基準とは?日本基準との違いをわかりやすく解説
IFRSの収益認識基準とは、売上収入の計上に関する基準です。IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に規定されています。IFRSの収益認識の特徴や日本基準との比較、IFRSの…
詳しくみる会計システムとは?主な種類と機能について
企業の会計業務は、適切な会計処理に加え、債権債務の管理や経営に合った管理が必要など、複雑です。多くの企業では、複雑な会計処理を効率良く済ませられるようにするため、会計システムが用い…
詳しくみる“良い税理士”を見極めるたった一つのポイント 「近所」「紹介」の落とし穴も
この記事の読者の中に、税理士を探している方がいるかもしれません。中には知人の紹介やネット検索を頼りに検討している方もいるかもしれないですね。 一昔前と変わり、今はターゲットや専門分…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引