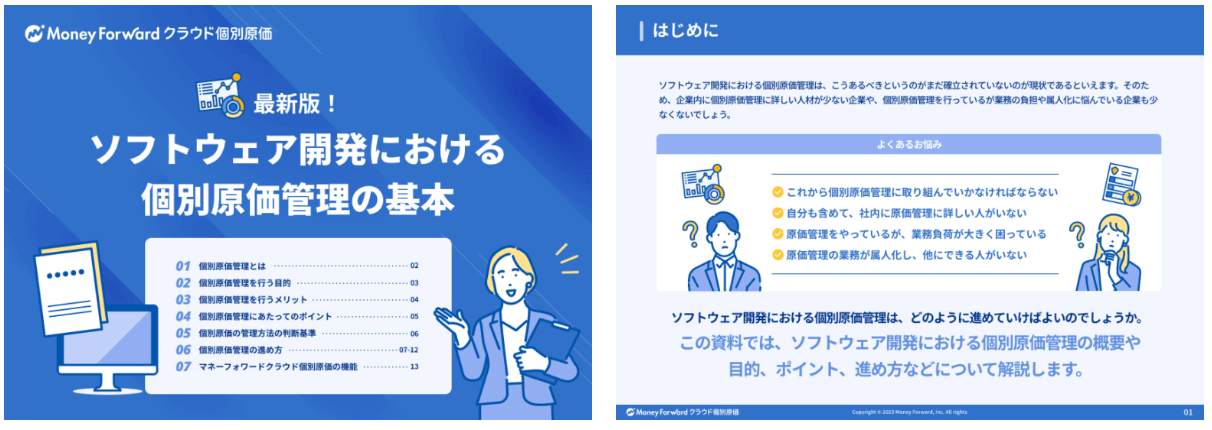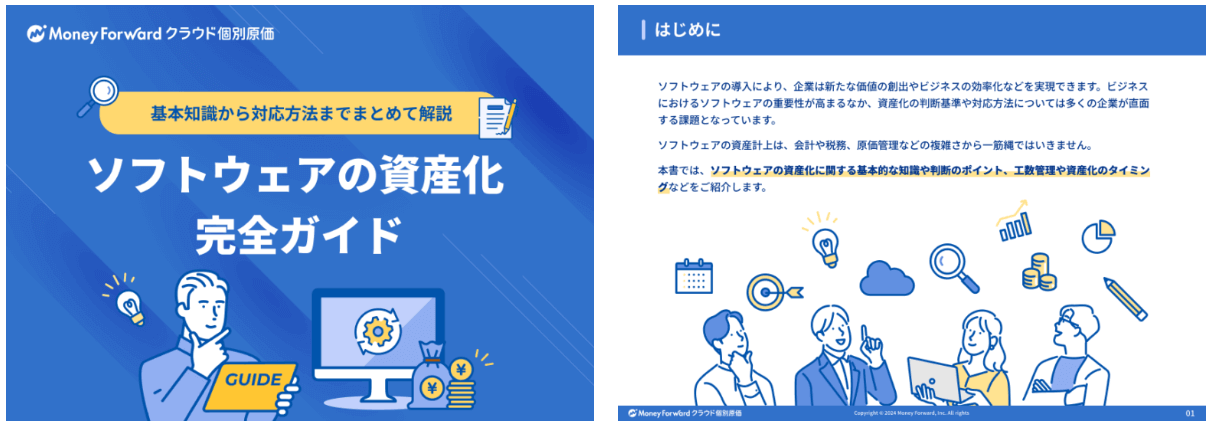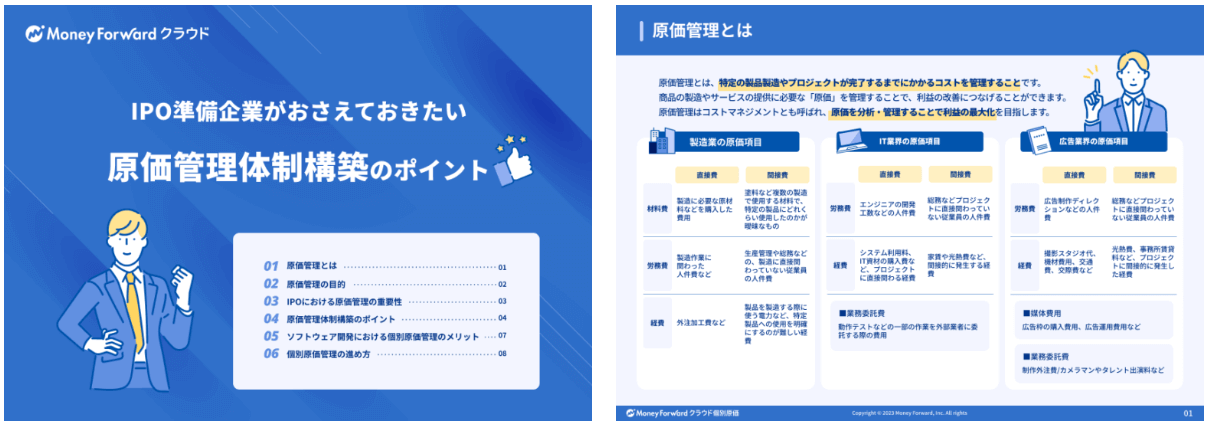- 更新日 : 2025年3月17日
原価割れとは?意味や計算方法、不当廉売として違法になる事例などをわかりやすく解説
原価割れとは、商品の販売価格が製造や仕入れコストを下回る状態を指し、企業の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。本記事では、原価割れの定義や発生する理由、戦略的な活用方法、さらには不当廉売として違法になるケースについて詳しく解説します。適正な価格設定やコスト管理を通じて、ビジネスの収益性を維持するための具体的な方法を学びましょう。
目次
原価割れとは
原価割れとは、商品やサービスの販売価格が、その製造や提供にかかったコストを下回る状態を指します。つまり、原価より安い価格で販売することで、売るほど損失が発生する状況です。通常、商品を販売することで得られる収益は、投入したコストを上回るのが理想ですが、原価割れが発生すると赤字となり、企業の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
原価割れの英語表現
原価割れを英語で表す場合は、「below cost」や「selling below cost」などの表現が一般的です。これらは、商品が原価を下回る価格で販売されていることを直接的に意味します。
原価に含まれる費用
原価割れを正しく理解するには、「原価」には何が含まれるのかを把握することが重要です。具体的には、以下のような費用が原価に含まれます。
これらの費用は、特定の製品に直接関連する直接費と、複数の製品にまたがる間接費に分類されます。たとえば、テーブルを製造する場合、木材やネジは直接費に該当し、工場全体の電気代は間接費に分類されます。
原価の算出方法
原価の算出方法にはさまざまな種類があり、目的によって異なる手法が用いられます。主な計算方法は、以下の通りです。
どの計算方法を採用するかによって算出される原価の額が変動するため、原価割れの判断基準も異なる可能性があります。例えば、直接原価計算では変動費のみを原価として計算し、固定費は考慮されません。そのため、ビジネスの状況や分析の目的に応じて原価の捉え方が変わり、原価割れの意味合いも変化することを理解しておくことが重要です。
原価割れと似ている用語の違い
原価割れと似た意味で使われる用語がいくつかありますが、それぞれの意味や使われ方には違いがあります。混同しやすいこれらの用語について、正しく理解しておきましょう。
赤字販売との違い
原価割れと赤字販売は似た概念ですが、厳密には異なります。
- 原価割れ
販売価格が原価を下回ること - 赤字販売
販売価格は原価以上であっても、その他の経費(販管費、固定費など)を含めると最終的に赤字になること
たとえば、1個1,000円で仕入れた商品を1,100円で販売しても、人件費や広告費などを考慮すると最終的に利益が出ない場合、これは「赤字販売」となります。一方で、1,000円で仕入れた商品を900円で販売すれば、直接的に「原価割れ」となります。
逆ざやとの違い
逆ざやは原価割れと似た概念ですが、特に金融商品やビジネスモデルの収益構造に関連して使われることが多い用語です。
- 原価割れ
商品やサービスの販売価格が、仕入れや製造コストを下回ること - 逆ざや
特定の取引において、支払うコストが受け取る収益を上回ること
たとえば、金融業界では、銀行が預金金利よりも貸出金利のほうが低い場合、「逆ざや」と呼ばれます。また、ゲーム機本体を原価以下で販売し、ゲームソフトや周辺機器の販売で利益を回収する戦略も「逆ざや販売」と言われることがあります。
ダンピングとの違い
ダンピングは、原価割れと関連する概念ですが、国際貿易や市場競争の文脈で使われることが多い用語です。
- 原価割れ
単に原価を下回る価格で商品を販売すること - ダンピング
特定の市場で意図的に原価割れ価格で販売し、競争相手を排除する戦略的行為のこと
ダンピングは、特に国際貿易において問題視される行為で、WTO(世界貿易機関)では不公正競争の一種として規制されています。国内市場でも、公正取引委員会によって不当廉売と認定される可能性があります。
以上のように、原価割れと類似する用語には、それぞれ異なる意味や使用用途があります。正しい理解を持つことで、ビジネスの価格戦略をより適切に判断することができます。
原価割れが発生する理由
原価割れは、通常のビジネス運営においては避けるべき状況ですが、さまざまな要因によって発生することがあります。ここでは、経営環境の変化により結果的に原価割れに陥る理由について解説します。
市場競争の激化
競争の激しい市場では、企業が価格競争に巻き込まれ、利益を削ってでも販売価格を下げざるを得ない状況が発生します。特に以下のようなケースで原価割れが起こりやすくなります。
- 競合他社との価格競争
他社が値下げを行うと、対抗するために自社も値下げせざるを得なくなり、結果的に原価を下回る価格での販売に至ることがあります。 - 新規参入企業の影響
市場に新しい企業が参入すると、シェアを奪われないように価格を下げる動きが加速し、原価割れのリスクが高まります。 - 価格の影響が大きい商品
価格が少しでも上がると売れなくなるような商品では、消費者の購買意欲を維持するために値下げを余儀なくされることがあります。
外的要因によるコストの上昇
原材料費の高騰や経済環境の変化によって、企業が意図せず原価割れに陥ることもあります。
- 原材料費や人件費の高騰
急なコスト上昇が発生しても、すぐに販売価格を引き上げられない場合、原価割れが生じることがあります。 - 為替レートの変動
輸入品を扱う企業は、為替レートの変動によって仕入れ価格が上がり、予想外のコスト増によって利益が圧迫されることがあります。 - 物流コストの増加
燃料費の高騰や輸送規制の影響で物流コストが上がると、商品の原価が膨らみ、結果的に原価割れになることがあります。
以上のように、原価割れは市場環境の変化や企業の戦略によってさまざまな形で発生します。
ビジネス戦略における原価割れの活用
原価割れは、通常予期せず発生する状況ですが、企業が意図的に活用することもあります。適切な戦略として用いれば、集客や市場シェアの拡大に役立つ場合があります。ここでは、ビジネス戦略の一環としての原価割れの活用方法を解説します。
ロスリーダー戦略
ロスリーダー戦略とは、一部の商品を原価割れ価格で販売することで集客し、他の商品で利益を補う手法です。この戦略には、以下のようなメリットがあります。
- 集客効果が高い
目玉商品を低価格で提供することで、多くの顧客が店舗やウェブサイトに訪れるようになります。 - 追加購入を促進できる
来店やサイト訪問のついでに、利益率の高い商品を購入する可能性が高まります。 - ブランドの認知度を向上できる
低価格の目玉商品が話題となり、企業やブランドの認知度が高まる効果が期待できます。 - リピーター獲得につながる
定期的にお得な商品を提供することで、顧客が継続的に利用するきっかけになります。
しかし、ロスリーダー戦略にはリスクも伴います。
- 短期的な利益が悪化する
原価割れ価格で販売するため、一時的に収益が落ちる可能性があります。 - 価格への過度な期待を生む
頻繁に低価格販売を行うと、通常価格の商品が売れにくくなり、価格競争が激化する可能性があります。 - ブランドイメージへの影響
過度な値下げは、商品の品質に対する不安を招き、ブランド価値を損なうリスクがあります。
ロスリーダー戦略を成功させるためには、利益率の高い商品の販売へとつなげる工夫が不可欠です。
市場シェア拡大のための戦略
新規市場へ参入する際や、既存市場でのシェアを拡大したい場合、一時的に利益を度外視した低価格販売を行うことがあります。この戦略には、以下のようなメリットがあります。
- 新規顧客の獲得
競争が激しい市場では、低価格で顧客を獲得し、後に通常価格へ移行する戦略が有効です。 - 競争優位の確保
先行者利益を得るために、初期段階で価格を下げ、競合が参入しにくい環境を作ることができます。 - サブスクモデルへの移行
本体を安価に販売し、継続的なサービス利用料で収益を確保する戦略。ゲーム機とゲームソフト、プリンターとインクカートリッジなど)が代表的です。
この戦略は、短期的には利益が出ない可能性がありますが、長期的に顧客基盤を築き、収益性を高めることが期待できます。
在庫処分による原価割れ販売
企業にとって、売れ残った在庫はコストとなるため、早期に処分することが重要です。原価割れ販売を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 保管コストの削減
長期間在庫を抱えると、倉庫費用や管理コストが発生します。原価割れしてでも販売することで、これらのコストを削減できます。 - 商品の陳腐化防止
特に、流行に左右される商品や、型落ち品は価値が下がる前に売り切る方が得策です。 - キャッシュフローの改善
滞留在庫を現金化することで、新たな仕入れや投資に回す資金を確保できます。
在庫処分を目的とした原価割れ販売は、短期的な戦略として有効ですが、常態化するとブランド価値を損なう可能性があるため、慎重な運用が求められます。
このように、原価割れは単なる損失ではなく、戦略的に活用することで、ビジネスにとってプラスに働く場合もあります。ただし、長期的な視点を持ち、利益確保の仕組みと組み合わせて運用することが重要です。
原価割れが不当廉売として違法になる事例
原価割れ自体は、企業の自由な価格設定の範囲内で行われる限り、必ずしも違法とは限りません。しかし、競争を不当に制限したり、市場の健全な取引を阻害したりする場合、「不当廉売」として法的な問題になることがあります。ここでは、不当廉売に該当するケースや関連する法律について詳しく解説します。
不当廉売とは
不当廉売とは、公正な競争を妨げる目的で、原価を大きく下回る価格で商品やサービスを販売する行為を指します。
不当廉売とみなされるのは、以下の3つの条件を全て満たす場合です。
1.供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること
ここでいう「供給に要する費用」とは、商品の仕入れ原価に販売費及び一般管理費を加えた総販売原価を指します。変動費を下回る価格は、「供給に要する費用を著しく下回る対価」であると推定されます。また、「継続して」とは、相当期間にわたって繰り返して廉売を行うこと、または廉売を行う事業者の営業方針等から客観的にそれが予測されることを意味します。一時的な安売りは通常、これに該当しません。
2.他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること
競争関係にある事業者の事業活動が困難になる具体的な可能性が認められることを意味します。廉売を行う事業者の市場シェア、価格の下げ幅と期間、競争事業者の経営状況などが考慮されます。
3.正当な理由がないこと
一定の状況下では、原価割れ販売が正当な理由があると認められる場合があります。例えば、季節商品や流行遅れの商品、賞味期限が迫った商品、キズ物などの在庫処分、事業からの撤退や新規参入のためのバーゲンセール 、需給関係による価格低下への対応などが該当します。大量の在庫品で、通常の販売方法では使用期限内に販売できない場合なども、正当な理由と認められることがあります。
独占禁止法による規制
公正取引委員会は、独占禁止法の規定に基づき不当廉売を規制し、公正な競争秩序を維持しています。不当廉売が認定された事業者には、排除措置命令や課徴金納付命令 などの行政処分が下される可能性があります。
特に、価格競争が激しい業界 では、不当廉売が疑われるケースが多いため、公正取引委員会の調査対象となることがあります。以下の業界では、過去に不当廉売と認定された事例があります。
1. ガソリンスタンド業界
ガソリンスタンドは価格競争が激しく、地域ごとに大幅な値引きが行われることがあります。過去には、特定の店舗が周辺価格より大幅に安い価格で継続販売したため、公正取引委員会から警告を受けた事例 があります。
2. スーパーマーケット業界
ある新規参入のスーパーマーケットが 集客目的で野菜を1円で継続販売 したところ、不当廉売の疑いがあるとして公正取引委員会から警告を受けました。
3. スマートフォン端末の「1円販売」
携帯キャリアによるスマートフォン端末の 極端な値引き販売(1円販売) が、不当廉売に該当する可能性があるとして公正取引委員会が調査を行った事例があります。このような 端末価格の過度な値引きが、競争を阻害する行為と見なされる可能性 があります。
原価割れを避けるためのポイント
原価割れが続くと、企業の利益が圧迫され、経営が不安定になるリスクがあります。そのため、事前に適切な対策を講じることが重要です。ここでは、原価割れを防ぐために有効なポイントを紹介します。
適正な原価計算の徹底
原価を正しく把握していないと、知らないうちに原価割れを起こしてしまうことがあります。正確な原価計算を行い、適切な販売価格を設定しましょう。
- 直接原価と間接原価を明確にする
材料費や人件費などの直接コストだけでなく、固定費や物流コストなどの間接コストも考慮して原価を算出する。 - 製造業では原価の見直しを定期的に行う
原材料費やエネルギーコストの変動を考慮し、定期的にコストを見直すことで原価割れを防ぐ。 - 小売業では仕入れ価格の交渉を行う
仕入れ価格の適正化を図ることで、原価を抑えつつ利益を確保しやすくする。
利益を確保できる価格設定
適正な利益を確保するためには、価格設定の工夫が必要です。競争力を維持しながら、原価割れしない価格を設定しましょう。
- 価格設定の指標を持つ
利益率の目標を設定し、それに基づいて価格を決定する。例えば、「原価の30%以上の利益を確保する」などの基準を設ける。 - 需要に応じた価格戦略を採用する
人気商品は利益率を高め、集客用の商品は原価割れしない範囲で価格を設定する。 - ダイナミックプライシングを活用する
需要に応じて価格を柔軟に調整することで、適正な利益を確保しやすくなる。
コスト削減による原価圧縮
原価を下げることで、販売価格を維持しながら利益を確保できます。コスト削減の具体的な方法を取り入れましょう。
- 仕入れ先の見直し
より安価で高品質な仕入れ先を見つけることで、原価を下げることが可能。 - 業務プロセスの効率化
製造工程や物流の見直しにより、コストの削減を図る。 - 不要なコストの削減
過剰な広告費や無駄な在庫を減らし、利益率を向上させる。
販売戦略の最適化
適切な販売戦略を採用することで、原価割れを防ぎながら売上を伸ばすことができます。
- 高付加価値商品を提案する
同じ商品でも、セット販売や特典をつけることで単価を上げることが可能。 - ターゲット層を明確にする
購買意欲の高い顧客に向けて適正価格で販売する。 - プロモーションを最適化する
値引きによる販売促進だけでなく、ポイント制度や限定販売を活用することで、利益を確保しながら集客できる。
データ分析による売上・利益の管理
原価割れを防ぐためには、データを活用しながら適切な経営判断を行うことが重要です。
- 売上・利益のデータを定期的に分析する
どの商品が利益を生み、どの商品が赤字なのかを把握し、適切な対策を講じる。 - 価格の見直しを定期的に行う
市場の変化に応じて、価格を調整し利益を確保する。 - 在庫管理を徹底する
過剰在庫を防ぎ、在庫処分による原価割れ販売を回避する。
以上のような対策を講じることで、原価割れを防ぎながら安定した経営を実現することができます。
原価割れが独占禁止法違反にならないよう注意しましょう
原価割れは、企業にとって避けるべき状況である一方で、戦略的に活用されることもあります。価格競争や在庫処分、プロモーションの一環として原価割れ販売を行うケースもありますが、不当廉売として規制の対象となる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。適正な価格設定やコスト管理を徹底し、無理のない収益モデルを構築することが、長期的な経営安定の鍵となります。今後の価格戦略に活かし、持続可能なビジネス運営を目指しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
連結会計システムとは?種類の比較やサービス例10選など紹介
連結会計システムの導入は、複雑化するグループ経営において、迅速かつ正確な意思決定の基盤となります。この記事では、連結会計システムとは何か、その主な機能から種類、そして自社に最適なシ…
詳しくみる世田谷区で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
世田谷区(東京都)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対…
詳しくみるIFRSにおける営業利益とは?2027年に定義が統一される理由や影響も解説
IFRS第18号の公表によって、IFRSでは新たに営業利益の表示が求められるようになりました。ただし、IFRSの営業利益は、同一の企業の会計情報であっても、日本基準の営業利益とは金…
詳しくみる役員退職慰労金とは?計算方法と功労加算・税金面の注意点や支給手続きを解説
取締役や監査役などの役員が退職した場合に、会社は役員退職慰労金を対価として支給することができます。 この役員退職慰労金については、支給する側にもされる側にも様々なメリット・デメリッ…
詳しくみる美容室の会計業務を解説!おすすめの会計ソフトは?
「本業が忙しく会計業務に時間をかけたくない」「毎月の仕訳入力が面倒くさい」という方向けに、この記事はクラウド型会計ソフトで会計業務を効率化するための方法を解説しています。 結論から…
詳しくみる会計ソフトの費用相場は?税理士に依頼する価格と比較!費用を安く抑える方法も!
確定申告にて「税理士には頼んだ方がいいの?」「会計ソフトは必要?」といった疑問がある方に向けて、「なるべくコスパの良い方法」を解説していきます。 結論から言うと、かかる時間も考慮し…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引