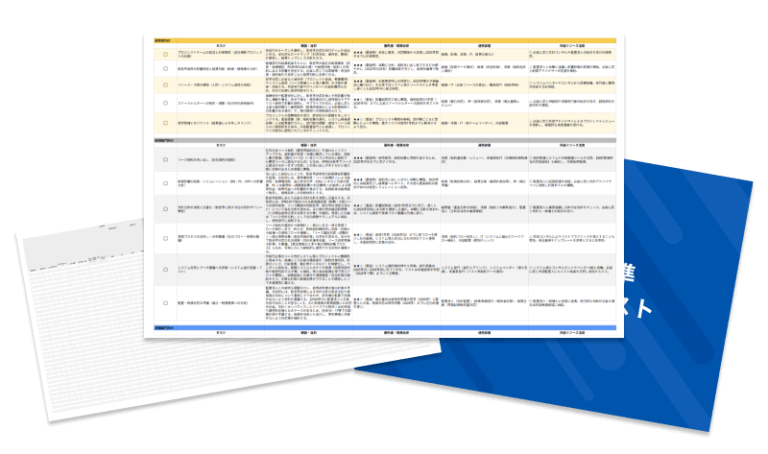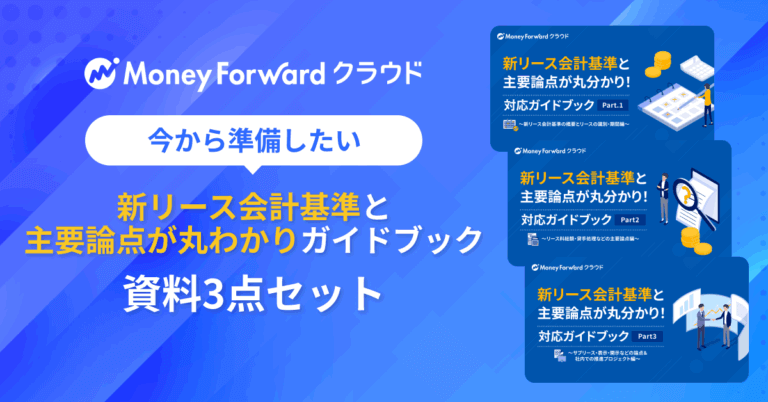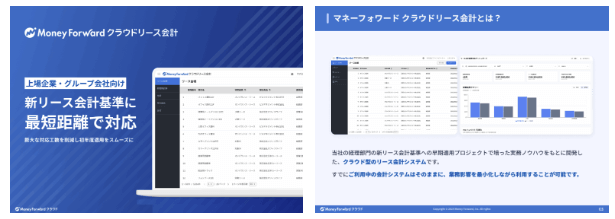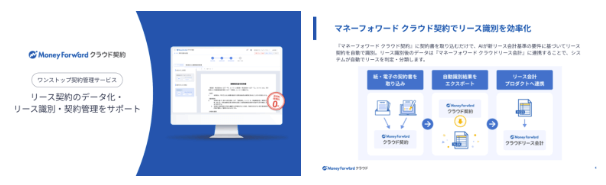- 更新日 : 2025年7月22日
リース資産減損勘定とは?リースと減損会計の関係性について解説!
固定資産に適用される減損会計については、ファイナンス・リース取引に基づくリース資産にも適用されます。
ただし、売買処理と賃貸借処理では減損損失の計上方法が異なるため、実務上はこれらの違いを理解することが重要です。
ここでは、リース資産における減損会計の方法や、新リース会計基準での変更点について解説します。
目次
リース資産は減損会計の対象?
自社所有の固定資産の価値が大幅に低下した際、帳簿価額を切り下げる「減損会計」ですが、リース取引においても適用される可能性があります。
リース契約だからといって資産の価値が下がらないわけではなく、その他の固定資産と同様に、実質的に自社で使用しているリース資産が経済的価値を損なうリスクは存在します。
まずは、減損会計の基本的な考え方とプロセスを確認したうえで、リース資産も減損の対象となる理由や実務対応の方向性について確認しましょう。
減損会計とは?
減損会計とは、自社が保有する固定資産の価値が著しく低下した場合に、その固定資産の帳簿価額を実質的な価値まで減額するために行う会計処理のことです。
市場環境の変化や技術革新によって固定資産が陳腐化した場合など、その帳簿価額が実際の回収可能価額と比べて乖離しているにもかかわらず、貸借対照表上の計上額を修正しないままでいると、利害関係者に誤った情報を与えかねません。
そこで、財務諸表の透明性や信頼性を向上させ、国際的な会計基準との整合性を確保することを目的として、「固定資産の減損に係る会計基準」という会計処理のルールが設けられています。
具体的には、企業が保有している有形固定資産や無形固定資産などについて、当初想定していた回収可能価額を著しく下回る状況となった場合に、その帳簿価額を減額して差額を減損損失として計上することになります。
減損会計のプロセス
減損会計を適用する場合には、以下のようなステップに沿って会計処理を行いましょう。
- 固定資産のグルーピングを行う
減損会計の必要性を判断するために、対象となる固定資産のグルーピングを行います。この場合のグルーピングについては、独立したキャッシュフローを生み出す最小単位によって行います。 - 減損の兆候を確認する
たとえば、稼働率の低下や市場価格の急落、技術革新などにより、資産の使用価値が大きく減少するなどの兆候があるかをチェックします。 - 減損損失を認識する
減損の兆候が確認された場合には、減損損失を認識する必要があるかどうかを検証します。具体的には、割引前の将来キャッシュフローが固定資産の帳簿価額を下回る場合には、減損処理が必要だと判断します。 - 減損損失の測定を行う
減損損失を認識した場合には、減損損失として計上すべき金額を算定します。具体的な計算方法としては、帳簿価額から回収可能価額を差し引いて生じる差額を減損損失として計上します。この場合の回収可能価額とは、資産を継続使用することで得られるキャッシュフローの現在価値と、処分費用を差し引いたネットでの売却価額(正味売却価額)のいずれか高い方の金額のことです。
リース資産も減損会計の対象
ファイナンス・リース取引の場合には、解約不能のリース取引であるうえ、借手がリース資産に関するさまざまなコストを負担することから、自己所有の資産と経済的な性質は変わりません。
したがって、このようなファイナンス・リースについても、帳簿価額と回収可能価額を比較して価値の著しい下落が認められる場合には、減損会計を適用する必要があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
リース資産の減損会計の方法
リース資産に関する減損会計については、リース取引の会計処理の方法によって仕訳の内容も異なります。
ここでは、「ファイナンス・リース(売買処理)」と「ファイナンス・リース(賃貸借処理)」「オペレーティング・リース」の区分ごとに、減損会計の適用可否や具体的な会計処理について確認しましょう。
ファイナンス・リース(売買処理)の場合
ファイナンス・リース取引については、「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」の2つに分類されます。
このうち、所有権移転ファイナンス・リースについては、リース期間終了時に、その資産の所有権が借手に移転することが確実とされるため、会計上も売買処理が義務付けられています。
それに対し、所有権移転外ファイナンス・リースでは、売買処理が原則とされているものの、中小企業などでは賃貸借処理を選択することも可能です。
ファイナンス・リースのうち、売買処理を適用している場合には、基本的には自己所有の固定資産と同様に減損会計を適用します。具体的には、ファイナンス・リースによって資産計上された「リース資産」を直接切り下げることとなります。
ファイナンス・リース(賃貸借処理)の場合
所有権移転外ファイナンス・リースにおいて、中小企業の場合やそのリースが少額リースに該当する場合には、売買取引ではなく賃貸借取引に準じた会計処理も認められています。
賃貸借処理を選択する場合には、「リース資産」や「リース債務」としてオンバランス化するのではなく、オペレーティング・リースと同様に、支払リース料をそのまま費用として計上します。
ただし、ファイナンス・リースの実態は売買取引とみなされることから、賃貸借処理を選択している場合でも、売買処理のケースと同じように減損会計の対象となり得ます。
したがって、賃貸借処理を選択していても、企業が減損の兆候があると判断した場合には、リース資産に関する回収可能価額の算定が必要不可欠です。
その結果、減損損失を計上する際には、賃貸借処理の場合には「リース資産」が計上されていないことから、減損損失を計上する際の相手科目として「リース資産減損勘定」を用いることとなります。
オペレーティング・リースの場合
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引のことです。
オペレーティング・リースの場合には、原則として貸手がリース資産を保有し、さまざまなコストやリスクを負担することから、借手は単にリース物件をレンタルしているに過ぎず、賃貸借取引に準じた会計処理を行います。
このような観点を踏まえると、借手はリース物件の実質的な所有者ではないことから、オペレーティング・リースについては減損会計を適用しません。
リース資産の減損会計の仕訳例
ファイナンス・リースに基づくリース物件に対して減損会計を適用する場合には、「売買処理」と「賃貸借処理」のいずれかによって具体的な会計処理も異なります。
以下では、それぞれのケース別の仕訳例を確認し、適切な減損会計の計上方法を理解しましょう。
ファイナンス・リース(売買処理)の場合
所有権移転ファイナンス・リースまたは所有権移転外ファイナンス・リースにより、売買処理に準じて会計処理を行う場合には、それぞれ以下のように仕訳を作成します。
リース契約時
売買処理を行うファイナンス・リース取引では、借手はリース契約の開始時点で「リース資産」と「リース債務」をそれぞれ計上します。
なお、この際には、「リース資産」ではなく、「機械装置」や「器具備品」など、通常の自社所有の固定資産と同様の勘定科目を用いることも可能です。同様に、「リース債務」も「未払金」などの科目で代用できます。
【例】所有権移転ファイナンス・リースにより、貸手の購入価額が500万円の機械装置を導入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 5,000,000円 | リース債務 | 5,000,000円 |
リース料支払い時
リース料を支払う場合には、元本返済部分と利息相当額を区分する必要があります。この場合において、元本返済部分は「リース債務」、利息相当額については「支払利息」として計上するケースが一般的です。
【例】元本返済分9万円と利息相当額1万円の計10万円をリース料として支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務 支払利息 | 90,000円 10,000円 | 現金預金 | 100,000円 |
決算時
毎期の決算時点では、資産として計上した「リース資産」に対する減価償却費を計上します。
減価償却費の計算方法については、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースでは異なりますが、前者の場合には、自社所有の固定資産と同様に償却額を算出します。
【例】リース資産に対し、年間で50万円の減価償却費を計上する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 500,000円 | リース資産(間接法の場合には「減価償却累計額」) | 500,000円 |
減損損失の計上時
リース資産の回収可能価額が帳簿価額を大幅に下回り、減損処理が必要と判断された場合は、その差額を「減損損失」として計上します。
【例】帳簿価額が100万円のリース資産について、回収可能価額が30万円まで減少し、減損会計を適用する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 700,000円(※) | リース資産 | 700,000円 |
(※)100万円(リース資産の帳簿価額)-30万円(回収可能価額)=70万円
このような仕訳を計上することによって、減損処理後のリース資産の帳簿価額は「100万円-70万円=30万円」に切り下げられます。
ファイナンス・リース(賃貸借処理)の場合
所有権移転外ファイナンス・リースのうち、賃貸借処理によって会計処理を行う場合には、「リース資産」として資産計上することなく、支払うリース料を直接費用として計上します。
賃貸借処理を行うファイナンス・リースに減損会計を適用する場合には、以下のような手順で仕訳を作成しましょう。
リース契約時
賃貸借処理の場合には、貸借対照表に「リース資産」や「リース債務」を計上する必要がないため、借手側はリース契約時点での仕訳処理は不要です。
リース料支払い時
リース契約に基づいてリース料を支払った場合、賃貸借処理では、支払ったリース料をそのまま費用として計上します。
【例】10万円のリース料を支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 |
決算時
賃貸借処理の場合には、「リース資産」を計上していないことから、決算時においても、減価償却費の計上などの会計処理は必要ありません。
ただしリース料の未払分や前払分があれば、経過勘定として前払費用や未払費用の計上を行うケースもあります。
減損損失の計上時
所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理で行う場合でも、減損会計を適用することが可能です。ただし、「リース資産」が計上されていないことから、回収可能価額と比較すべき帳簿価額を見積もる必要があります。
具体的には、そのリース資産に関する未経過リース料の現在価値を帳簿価額とみなし、減損損失を計算します。減損損失を計上する場合には、「リース資産」を減額する代わりに、「リース資産減損勘定」という負債科目を用いて仕訳を作成します。
【例】未経過リース料の現在価値が100万円のリース資産について、回収可能価額が30万円まで減少し、減損会計を適用する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 700,000円(※) | リース資産減損勘定 | 700,000円 |
(※)100万円(未経過リース料の現在価値)-30万円(回収可能価額)=70万円
減損損失計上後の会計処理
賃貸借処理を行うファイナンス・リースについて、減損会計を適用した場合には、「リース資産減損勘定」という負債が計上されることとなります。
「リース資産減損勘定」については、そのリース契約の残存期間にわたり、定額法によって取崩しを行い、その取崩し額については支払リース料と相殺します。
【例】減損会計を適用した翌年度に10万円のリース料を支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 |
【例】残存リース期間10年のうち、1年が経過した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産減損勘定 | 70,000円(※) | 支払リース料 | 70,000円 |
(※)70万円(リース資産減損勘定の帳簿価額)×1年/10年=7万円
上記の仕訳を計上することで、「リース資産減損勘定」の帳簿価額は「70万円-7万円=63万円」に減少します。
新リース会計基準適用後はどうなる?
2027年4月から開始する新リース会計基準(企業会計基準第34号)によって、リース取引に関する会計処理が大幅に変更されます。
リース資産に対する減損会計についても一部変更が生じるため、新リース会計基準の概要や減損会計上の注意点を確認しましょう。
原則としてオンバランス化が必須に
新リース会計基準では、従来のファイナンス・リースやオペレーティング・リースの区別を借手側で行う必要がなくなり、原則としてすべてのリース契約を「使用権資産」と「リース負債」としてオンバランス化します。
したがって、これまではオフバランスが認められていた所有権移転外ファイナンス・リースやオペレーティング・リースについても、貸借対照表への表示が原則となります。
新リース会計基準による減損会計の注意点
新リース会計基準によってすべてのリースがオンバランス化されることで、減損会計の対象資産も拡大します。これまで賃貸借処理をしていたオペレーティング・リースについても、新基準では「使用権資産」の減損会計を検討する余地があるでしょう。
その一方で、新基準でもオフバランスが認められる短期リースや少額リースについては、重要性が乏しいことを考慮して、減損会計の対象外とされています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
トレーラーハウスの耐用年数と減価償却費計算を解説
トレーラーハウスは、タイヤの付きのシャーシ上に乗った、小さな家のようなものです。トレーラーハウスは「車両」に分類されますが、資産としてどう扱えばよいのか、疑問を感じられる方も多いで…
詳しくみるコンテナの耐用年数と減価償却費計算を解説
荷物を運搬する用に使用されていたコンテナも、運搬だけでなく、さまざまな用途で使用されるようになってきました。活用事例のひとつとして近年増えているのが、レンタルルームや倉庫としての利…
詳しくみるパソコンは減価償却できる?計算方法や30万円未満の特例、耐用年数も解説
パソコンの減価償却は、取得価額や用途ごとに処理が異なり、判断に迷うことも多い業務です。特に法定耐用年数や特例の適用条件を誤ると、税務上のリスクが発生する可能性が否定できません。その…
詳しくみるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金は圧縮記帳の対象!対象条件や仕訳例を解説
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金は、EV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)などの導入を支援するために交付される補助金制度です。 この補助金を活用して車両を購入した場合、…
詳しくみる借地権は償却できる?減価償却の方法や会計処理、税会不一致についても解説
建物などの不動産は減価償却が認められているのに対し、借地権はどうなのか疑問に思う方もいるでしょう。結論からいうと、借地権は税務において減価償却はできません。 本記事では借地権とは何…
詳しくみるリース取引の会計処理方法は?仕訳や勘定科目のポイントをわかりやすく解説
企業の経理担当者が直面する重要な業務の一つに、リース取引の仕訳があります。リース取引の会計処理は、リースの種類によって用いる勘定科目が大きく異なり、正確な知識が求められます。 この…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引