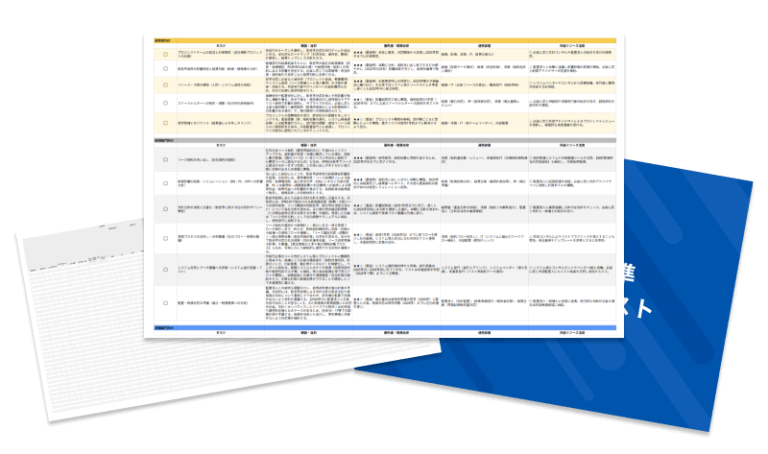- 更新日 : 2026年2月24日
【新リース会計基準】不動産関連の取引における影響・実務ポイント
現行では固定資産計上、新リース会計基準では現在価値を用いた区分処理へと変化します。
- 実質的な貸付金として敷金と明確に区別
- 新基準は額面と現在価値の差額を資産化
- 上場企業等は2027年4月から強制適用
新基準での仕訳方法は、預託額を「貸付金」と「前払家賃」に分解して計上し、差額は期間費用化します。
2027年4月から本格導入される「新リース会計基準」により、不動産賃貸借における建設協力金の会計処理が変わろうとしています。 これまでは「貸付金・預り金」として処理されることが一般的でしたが、新基準では「現在価値」を用いた評価や、仕訳の複雑化が予測されます。
本記事では、建設協力金の基礎から、現行の実務的な仕訳、そして新リース会計基準導入後に求められる変更点について、2026年1月時点の情報を基に解説します。
参考:
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」|企業会計基準委員会
企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」 | 企業会計基準委員会
目次
建設協力金とは?
建設協力金は、テナントが建物の建設資金を地主に融通するもので、実質的な「金銭消費貸借(貸付金)」としての性格を持ちます。
ロードサイド店舗や商業施設の出店において、借主(テナント)が貸主(オーナー)に建設資金を預託する建設協力金。
一般的な敷金が「債務の担保」であるのに対し、建設協力金は「資金調達の協力」が目的です。そのため、多くの契約では賃貸期間中に分割返済されたり、賃料と相殺されたりします。
建設協力金と敷金の比較
建設協力金は金融的な性質が強いため、敷金とは区別して管理する必要があります。
| 項目 | 建設協力金 | 敷金・保証金 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 建物建設資金の融通(貸付) | 賃料不払い等の債務担保 |
| 法的性質 | 金銭消費貸借に近い | 債務担保のための預託金 |
| 返還方法 | 契約期間中に分割返済・賃料相殺が多い | 退去時に一括返還が一般的 |
| 利息 | 無利息または低金利が多い | 基本的に無利息 |
| 会計処理 | 長期貸付金・借入金としての性質が強い | 差入・預り保証金として処理 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
【現行】建設協力金の仕訳例(借主・貸主)
現行基準では、借主は「投資その他の資産」、貸主は「固定負債」として計上し、1年基準(ワン・イヤー・ルール)に基づいて会計処理します。
現行の実務において、建設協力金は返済期間が長期(1年超)にわたるため、固定資産・固定負債として扱います。
借主(テナント)の仕訳例
前提:建設協力金1,000万円を預託。返済期間20年。
1. 預託時(支払い時)
支払った建設協力金は、返還期限が1年を超えるため、固定資産の「差入建設協力金」として全額を資産計上します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 差入建設協力金 | 10,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 |
摘要: 店舗建設協力金の支払い
2. 返済時(賃料相殺時)
毎月の家賃支払額と協力金の返還額を相殺し、差額のみを決済することで資産を取り崩します。
※家賃30万円のうち、5万円が協力金の返済として相殺される場合。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 300,000 | 普通預金 | 250,000 |
| 差入建設協力金 | 50,000 |
摘要: 家賃の支払い(協力金返済相殺後)
貸主(オーナー)の仕訳例
前提:建設協力金1,000万円を受入。返済期間20年。
1. 受入時(預かり時)
受け取った建設協力金は、将来返済する義務があるため、固定負債の「預り建設協力金」として全額を負債計上します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000,000 | 預り建設協力金 | 10,000,000 |
摘要: 建設協力金の受け入れ
2. 返済時(賃料相殺時)
受け取る家賃収入を計上すると同時に、建設協力金の返済分を相殺して負債を減少させます。
※家賃30万円のうち、5万円を協力金返済として相殺する場合。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 250,000 | 受取家賃 | 300,000 |
| 預り建設協力金 | 50,000 |
摘要: 家賃の受け取りと協力金の返済
新リース会計基準が不動産賃貸借に与える影響
新リース会計基準の導入により、オペレーティング・リースのオンバランス化やリース期間の見直しなど、不動産管理の実務は変更を迫られます。
2027年4月から適用される新基準では、不動産の賃貸借取引において以下のような具体的かつ広範な影響が生じます。建設協力金の処理と合わせて、取引全体の見直しが必要です。
新リース会計基準が適用される企業は?
原則として、上場企業およびその連結子会社、関連会社などが適用の対象となります。
新リース会計基準は、主に金融商品取引法の適用を受ける上場企業や大企業を対象としており、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度から強制適用されます。
一方で、上場していない中小企業については、当面の間は新基準の適用義務はなく、従来通りの「中小企業の会計に関する指針」等に基づいた処理(賃貸借処理)が認められる見込みです。
ただし、以下のケースでは中小企業であっても対応が必要になるため注意が必要です。
1. 不動産賃貸借(オペレーティング・リース)のオンバランス化
原則としてすべての不動産賃貸借契約において、「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表(B/S)に計上しなければなりません。
現行基準では、店舗や事務所の賃料は「オペレーティング・リース」として、支払いの都度経費処理するだけのオフバランス取引でした。しかし新基準ではこれらが資産・負債としてB/Sに乗ってくるため、特に多店舗展開する企業や大型施設を借りている企業では、事務負担の増加と管理項目の増大が懸念されます。
2. リース期間の判断基準の厳格化
契約書上の期間だけでなく、延長オプションや解約オプションの実質的な行使可能性を考慮してリース期間を決定します。
新基準では、延長オプションを行使することが「合理的に確実」である場合や、解約オプションを行使しないことが「合理的に確実」である場合、その期間も含めてリース期間とみなされます。「合理的に確実」かどうかの判断は、経済的インセンティブ(有利な条件など)に基づいて行われますが、不動産契約においては判断が難しく、実務上の大きな課題となっています。
3. 共益費・管理費の区分処理
原則として「賃借料(リース部分)」と「共益費(非リース部分)」を区分して会計処理を行います。
不動産契約には賃料以外に共益費や管理費が含まれます。新基準ではこれらを分解し、リース部分のみをオンバランス化するのが原則です。ただし、実務上の負担軽減のため、借手はリース部分と非リース部分を区別せず、まとめてリースとして処理することも認められています(貸手は不可)。
4. 自己資本比率の低下と財務指標への影響
バランスシートが膨らむことで、自己資本比率が悪化する可能性があります。
オペレーティング・リースがオンバランス化されると、資産と同時に「リース負債」が巨額に計上されます。これにより分母である総資産が増加するため、自己資本比率(自己資本÷総資産)は計算上低下します。金融機関からの評価やコベナンツ(財務制限条項)に抵触しないか、事前のシミュレーションが不可欠です。
5. サブリース事業へのインパクト
転貸(サブリース)を行う企業では、資産と負債が連鎖的に膨らむ可能性があります。
オーナーから借りて第三者に貸すサブリース事業では、これまでオフバランスだった取引が、借手としての「使用権資産・リース負債」の計上対象となります。事業実態は変わらずとも、B/S上の資産・負債が数倍に膨れ上がるリスクがあり、影響は甚大です。
【新基準】建設協力金の仕訳例
新基準では、建設協力金を「金融商品」として時価評価し、支払額との差額を「使用権資産」等の構成要素として処理します。
建設協力金は通常無利息または低金利であるため、将来返還されるお金の「現在価値(時価)」は額面より低くなります。この差額を実質的な「前払家賃」とみなして処理します。
借主(テナント)の新基準仕訳
- 建設協力金:1,000万円
- 現在価値:900万円(市場金利等で割引計算)
- 差額:100万円
1. 預託時(支払い時)
支払額を「貸付金(金融資産)」と「前払家賃(資産)」に分解します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 長期貸付金 | 9,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 |
| 長期前払家賃 | 1,000,000 |
摘要: 現在価値と差額(前払費用)の計上
2. 決算時(毎期の処理)
「前払分の費用化」と「貸付金の利息計上」の2つの処理が必要です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払家賃 | 50,000 | 長期前払家賃 | 50,000 |
| 長期貸付金 | 45,000 | 受取利息 | 45,000 |
摘要: 前払分の期間費用化および利息相当額の計上(例)
貸主(オーナー)の新基準仕訳
- 受入額:1,000万円
- 現在価値:900万円
- 差額:100万円
1. 受入時(預かり時)
受入額を「借入金(金融負債)」と「前受収益(負債)」に分解します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000,000 | 長期借入金 | 9,000,000 |
| 長期前受収益 | 1,000,000 |
摘要: 現在価値と差額(前受収益)の計上
2. 決算時(毎期の処理)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 長期前受収益 | 50,000 | 受取家賃 | 50,000 |
| 支払利息 | 45,000 | 長期借入金 | 45,000 |
摘要: 前受分の期間収益化および利息相当額の計上(例)
返還されない部分の取扱い
敷金や建設協力金のうち、将来返還されないことが契約で定まっている金額(償却部分など)は、金融商品ではなくリースの一部とみなされます。全額を「使用権資産」の取得価額に含めて計上し、減価償却を行います。
新リース会計基準の不動産関連取引における影響と実務の課題
新リース会計基準が適用されると、不動産賃貸借契約のオンバランス化など、企業の実務に大きな影響を与えます。株式会社マネーフォワードは、企業のバックオフィス担当者を対象に新リース会計基準に関する調査を実施しました。
契約の洗い出しとシステム対応の必要性
調査によると、新リース会計基準への対応に負担を感じている割合は合わせて約8割に上ります。その中で特に負担に感じる業務として挙げられたのは、リース契約の洗い出し・分類・整理でした。不動産の関連取引を含め、すべての契約を洗い出して適切に分類する作業が、実務における大きな課題となっています。
また、現在対応を進めている企業等に対応完了時期を質問したところ、多数を占めたのは2026年上半期中で、63.0%でした。さらに、リース契約情報の管理における主な課題は紙や手作業に頼った管理となっています。今後のリース負債の計算や残高管理に向けて、新たにシステムを入れ替えすると回答した割合は約4割でした。複雑な実務への影響を抑えるためには、早期の契約整理とシステムの活用が求められます。
出典:マネーフォワード クラウド、新リース会計基準への対応負担や課題【新リース会計基準に関する調査】(回答者:現在の勤務先で「経理部門」「情報システム部門」「総務部門」「法務部門」「経営企画部門」のいずれかに所属する方(個人事業主を除く)660名、集計期間:2025年3月11日(火)~3月17日(月))
建設協力金の適正な処理に向けて
新リース会計基準の導入により、建設協力金の会計処理は「預け金」から「金融とリースの複合取引」へと高度化します。
- 現行処理: 額面金額で「差入建設協力金(資産)」や「預り建設協力金(負債)」として計上する。
- 新基準処理:返還予定額を現在価値に割り引き、差額を「使用権資産」や「前払家賃」として処理する。
- 全体影響: 賃貸借契約がオンバランス化され、自己資本比率に影響を与える可能性がある。
特に現在価値計算は専門的な判断を要するため、適用開始前に監査法人や税理士と連携し、既存契約への影響額を試算しておくことが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新リース会計の関連記事
新着記事
- # 会計・経理業務
請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説
請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 AI-OCR…
詳しくみる - # 会計・経理業務
請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説
請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個別対応が原…
詳しくみる - # 会計・経理業務
振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説
振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業務をなくし…
詳しくみる - # 会計・経理業務
振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説
振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社内でも権限…
詳しくみる - # 会計・経理業務
振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説
振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 同行宛口座…
詳しくみる - # 会計・経理業務
振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法
振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OCRで請求書…
詳しくみる
会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引