- 作成日 : 2025年9月16日
所得税の節税はこうする!iDeCo・NISA・青色申告など全制度を解説
所得税の節税は、年収や働き方にかかわらず多くの人にとって実践できる対策の一つです。会社員であれば、年末調整だけでなく確定申告によって医療費控除や住宅ローン控除などの恩恵を受けることが可能です。個人事業主の場合は、経費の正確な計上や青色申告、共済制度の活用により大きな節税効果が見込めます。
本記事では、法律で認められた制度や控除の活用法を解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
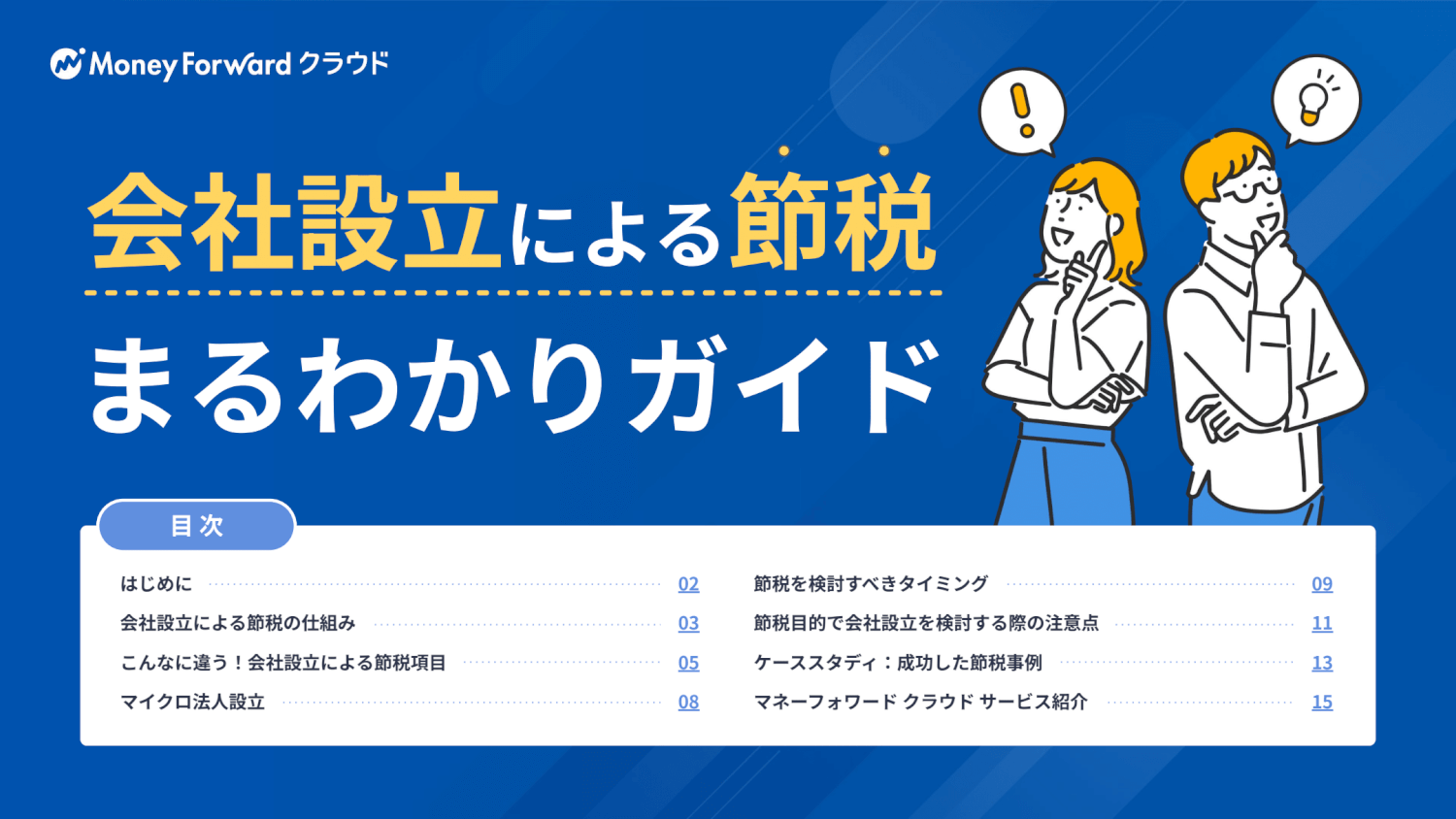
目次
所得税を節税するには
所得税の節税とは、法律で認められた制度や控除を活用し、所得税の負担を抑える方法です。「課税所得を減らす」ことと「税額そのものを減らす」ことに分類でき、それぞれに対応する制度があります。
課税所得を減らす
課税所得とは、給与収入から給与所得控除や各種所得控除を差し引いた金額で、この額に税率がかかって所得税が計算されます。令和7年分からは税制改正が行われ、サラリーマンにとって有利な変更点が多数盛り込まれました。
まず、基礎控除が一律48万円から、所得に応じて58万~最大95万円まで拡大しました。給与所得控除の最低額も55万円から65万円へと引き上げられ、負担軽減の効果が期待できます。さらに、配偶者控除や扶養控除の適用要件となる配偶者・扶養親族の所得基準は48万円以下から58万円以下へと緩和され、給与収入換算で年103万円から123万円まで対象が広がりました。
新たに、19~23歳未満の親族を対象とする「特定親族特別控除」も創設され、最大63万円の控除が可能です。
加えて、老後資金準備と節税を兼ねられるiDeCoの掛金上限も大きく見直されました。自営業者は月6.8万円から7.5万円へ、会社員は従来の月2万円前後から共通で6.2万円まで引き上げられ、加入年齢も70歳未満に拡大し、将来の資産形成を後押しします。
ただし、退職一時金に関する「5年ルール」が「10年ルール」へと変更されたため、受け取り方には注意が必要です。こうした改正を理解し、控除や制度を正しく活用することが、サラリーマンにとって効率的な節税につながります。
税額控除を活用する
税額控除は、算出された所得税そのものから一定額を直接差し引ける制度であり、同じ金額なら所得控除よりも節税効果が大きくなります。代表的な制度に住宅ローン控除とふるさと納税があります。
住宅ローン控除では、マイホーム取得時に年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から差し引けます。たとえば年末残高が3,000万円あれば、年間21万円の所得税が軽減されます。省エネ住宅等の条件を満たせば13年の控除期間が適用され、2025年入居分までが対象です。
ふるさと納税は、全国の自治体に寄附を行うことで税金が軽減される制度です。寄附額のうち自己負担2,000円を除いた金額が、翌年の所得税と住民税から控除されます。たとえば3万円を寄附した場合、2万8,000円が控除対象となり、さらに返礼品も受け取れます。
このほか、配当控除や雑損控除なども、対象となれば税額控除を通じて直接的に税負担を軽減できます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
個人事業主の所得税節税方法
フリーランスや自営業者として働く個人事業主は、自ら確定申告を行い、事業所得に基づいた税金を納める必要があります。会社員とは異なり、経費の計上や控除制度の活用次第で大きな節税が可能です。ここでは、個人事業主が実践できる代表的な所得税節税方法について解説します。
必要経費を正しく計上する
個人事業主の節税の基本は、事業に必要な支出を経費として正確に計上することです。経費とは、売上を得るためにかかった費用であり、これを収入から差し引くことで課税所得を減らせます。たとえば、自宅の一部を事業用として使っていれば、家賃や光熱費の按分、車両の燃料費、減価償却費、打ち合わせのための飲食代なども経費に含めることができます。
ただし、経費計上にはルールがあります。事業に関係ないプライベートな出費や架空の支出を経費として申告するのは、脱税に該当し、税務調査で発覚すれば追徴課税のリスクもあります。不要な支出を節税目的で増やしても、キャッシュアウトの負担がかえって重くなる可能性があります。正当な範囲で、事実に基づいた経費を適切に申告することが節税の基本です。
青色申告の特典を活用する
確定申告において「青色申告」を選択することで、節税効果は大きく広がります。青色申告のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる点です。この控除を受けるには、複式簿記による記帳と電子申告、もしくは電子帳簿保存が条件になります。紙申告や簡易帳簿の場合は、55万円または10万円の控除となります。
青色申告にはほかにもメリットがあります。青色事業専従者給与の制度を利用すれば、事業に従事する配偶者や親族に支払う給与を必要経費として計上することができます。例えば配偶者に年間100万円の給与を支払えば、その分課税所得を圧縮できます。ただし、支払う金額が業務内容に対して適正である必要があり、配偶者側には課税が発生する点には注意が必要です。
また、事業が赤字になった場合には、その赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる「純損失の繰越控除」も適用されます。事業の立ち上げ初期や経費の多い年度などで損失が出ても、翌年以降に利益が出た際に節税につなげることができます。
共済や積立による控除(小規模共済・セーフティ共済・iDeCo)
個人事業主が利用できる控除制度の中でも、共済制度は節税と資産形成の両面から活用できます。代表的なのが「小規模企業共済」です。これは個人事業主が将来の退職金に備えて積み立てる制度で、掛金(月額1,000円~70,000円)の全額が所得控除の対象となります。年間最大84万円の控除が可能であり、節税効果は非常に大きいです。
また、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」は、取引先の倒産などのリスクに備えて資金を積み立てる制度です。掛金は月5,000円から20万円まで設定でき、支払った掛金は全額を必要経費として計上できます。年間では最大240万円もの経費計上が可能で、利益が大きい年に掛金を集中することで課税所得を大きく減らせます。ただし、加入には「継続して1年以上事業を行っていること」という要件があるため、創業後すぐには加入できません。
さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)も有効です。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、最大で年81.6万円(将来的には年90万円に引き上げ予定)まで所得控除が可能です。加えて、運用益が非課税となり、受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。老後資金を準備しながら現在の税負担を軽減できるため、余裕がある場合は積極的に利用したい制度です。
法人化(会社設立)を検討する
課税所得が大きくなってきた個人事業主は、法人化(法人成り)を検討することで節税メリットが得られる場合があります。一般に、年間の課税所得が800万円~900万円を超えると、法人化の検討が現実的とされています。個人の所得税は最大で45%(住民税を含め約55%)に達しますが、法人税は中小企業であれば800万円まで15%、それを超える部分でも23.2%とされており、税率面での優位性があります。
法人化による節税効果の一つは、所得分散です。法人にすれば、役員報酬という形で自分や家族に給与を支払い、それぞれに給与所得控除を適用することで課税所得を分散させることが可能です。また、法人であれば旅費規程による出張手当、役員退職金の支給など、個人では難しい経費の計上も認められます。
さらに、法人には赤字の繰越控除が最大10年間認められており、個人の3年間と比べて長期的な節税計画が立てやすいという利点もあります。ただし、法人化には社会保険料の加入義務、法人住民税の均等割(赤字でも年間7万円前後)、決算書の作成などの事務負担が増えるというデメリットもあります。したがって、法人化のタイミングや税務戦略については、税理士などの専門家と相談の上、慎重に進めることが大切です。
会社員の所得税節税方法
会社員は、給与から源泉徴収された所得税が年末調整で自動的に処理されるため、自分で税金を計算・申告する機会が少ないのが一般的です。しかし、自分から制度を活用することで、手元に残るお金を増やす節税対策が可能です。ここでは、会社員が実践できる所得税の節税方法を解説します。
年末調整と確定申告を正しく活用する
まず、会社員の節税の第一歩は、年末調整で控除漏れを防ぐことです。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除などは、会社に提出する申告書類に記載することで適用されます。生命保険料控除は『一般生命保険料』『介護医療保険料』『個人年金保険料』の3つの区分があり、それぞれで最大4万円、合計で最大12万円の所得控除が受けられますが、申告書に記載しないと自動では適用されません。控除証明書の添付も忘れずに行うことが大切です。
また、年末調整では対応できない控除については、自分で確定申告を行うことで所得税を還付してもらうことが可能です。年間10万円以上の医療費を支払った場合には、医療費控除を使うことで課税所得を減らすことができます。さらに、ふるさと納税による寄附金控除、災害や盗難による損害があった際の雑損控除、住宅ローン控除の初年度申告なども、確定申告が必要です。日頃から領収書や控除証明書を整理しておくと、申告手続きがスムーズになります。
iDeCoで老後資金を準備しながら節税
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、会社員にとっても強力な節税ツールです。自分で拠出した掛金の全額が所得控除の対象となるため、拠出額に応じて所得税と住民税の負担が軽減されます。会社員が利用できるiDeCoの掛金上限額は、勤務先の企業年金制度の加入状況によって異なります。企業型DCのみに加入している場合は月額2万円、企業年金に全く加入していない場合は月額2.3万円が上限となります。
仮に年収600万円の会社員が年間74.4万円を拠出した場合、所得税率10%・住民税率10%として、約14万9千円の税負担が軽くなります。加えて、運用益が非課税、受取時にも退職所得控除や公的年金等控除の対象になるため、長期的な資産形成と節税の両立が可能です。老後資金を効率的に積み立てながら、今の税負担も抑えたい方におすすめの制度です。
NISAを使って将来の税負担を減らす
NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、投資によって得た利益にかかる20.315%の税金が非課税となります。2024年から新NISA制度がスタートし、年間360万円、最大1,800万円まで非課税投資枠が設けられ、非課税期間も無期限となりました。
年間120万円(毎月10万円)ずつ15年間積立投資を行い、年5%の運用成果を得られた場合、約900万円の運用益に対して本来かかる約180万円の税金をゼロにできます。直接的に所得税を減らす仕組みではありませんが、将来得られる金融所得に対する税負担を大きく減らせるため、長期的な節税効果は高いといえます。資産運用を検討している会社員には、NISAは欠かせない選択肢です。
控除制度や福利厚生も活用する
配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除など、家族構成に応じた控除を適切に申告することも節税につながります。配偶者の所得が48万円以下であれば最大38万円の控除を受けられ、扶養親族が19〜22歳の子どもであれば最大63万円の特定扶養控除が適用されます。これらは年末調整で申告できますが、控除の条件に該当するか毎年確認することが大切です。
さらに、通勤手当や出張旅費など、非課税となる手当を受けている場合、それに対応する金額は給与として課税されません。また、資格取得補助や社宅制度、従業員持株制度など、会社の福利厚生制度を利用することで、実質的な可処分所得を増やすことができます。制度の利用有無を確認し、可能な範囲で活用しましょう。
特定支出控除を検討する
会社員には「給与所得者の特定支出控除」という制度も用意されています。これは、業務上必要な支出がその年の給与所得控除額の2分の1を超えた場合に、その超過分を所得控除できる制度です。例えば給与所得控除が120万円の場合、60万円を超える業務関連支出があれば、超過分を控除対象とすることができます。
対象となる支出は、資格取得費、書籍代、職務用衣服費、自腹で支払った通勤交通費などです。ただし、適用には会社からの証明が必要であり、実際に適用されるケースは限定的です。それでも該当する可能性がある場合は、活用を検討する価値はあります。
会社員も個人事業主も制度活用で所得税の節税が実現できる
所得税の節税は、会社員・個人事業主を問わず、制度を正しく理解し適切に活用することで実現可能です。会社員は年末調整だけに頼るのではなく、医療費控除やふるさと納税、iDeCo・NISAなどを自ら選択して確定申告を行えば、手取りを増やす余地があります。一方、個人事業主は経費計上や青色申告、小規模企業共済などの制度を通じて、所得を圧縮しながら節税を進めることができます。どちらの立場でも、日々の記録と制度の正しい理解が欠かせません。将来の資金計画と連動させ、無理なく実践できる節税対策を継続的に見直していくことが、長期的な資産形成にもつながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
長崎県で会社設立する際の主な方法3選!お得に設立するには?
長崎県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる分譲マンションは法人登記できる?NG・OKの例、会社設立住所の注意点
会社設立コストを抑えるために、自宅の分譲マンションを法人登記したいと考える人もいるでしょう。しかし、自宅であっても、分譲マンションは法人登記ができない可能性があります。この記事では、分譲マンションの法人登記の注意点などを紹介します。 分譲マ…
詳しくみるIT・インターネット業の会社設立で定款に記載する事業目的の書き方
IT・インターネット業界は、今後も高い成長性を持つ分野と言えます。多くの起業家がさまざまな形で算入する業界とも言えますが、会社を設立するための手続きは他の業界にも共通しています。 この記事では、IT・インターネット業の会社設立について、特に…
詳しくみる合同会社に社長という役職はある?代表取締役との違いや選び方・報酬を解説!
合同会社は株式会社と異なる柔軟な経営スタイルを持つ法人形態です。しかし、その代表者を「社長」と呼べるのか、あるいは法的にはどのような位置づけになるのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。 本記事では、合同会社における「社長」という肩…
詳しくみるプライベートカンパニーで節税するには?法人化のメリットや注意点を解説
副業収入や不動産収益が増えたことで、個人の税負担に悩んでいる方が増えています。そこで注目されているのが、プライベートカンパニー(資産管理会社)を活用した節税です。 本記事では設立のメリット・デメリットやタイミング、手続きなどを解説します。 …
詳しくみる中野区の会社設立で事前に知っておくべき情報まとめ
中野区での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる


