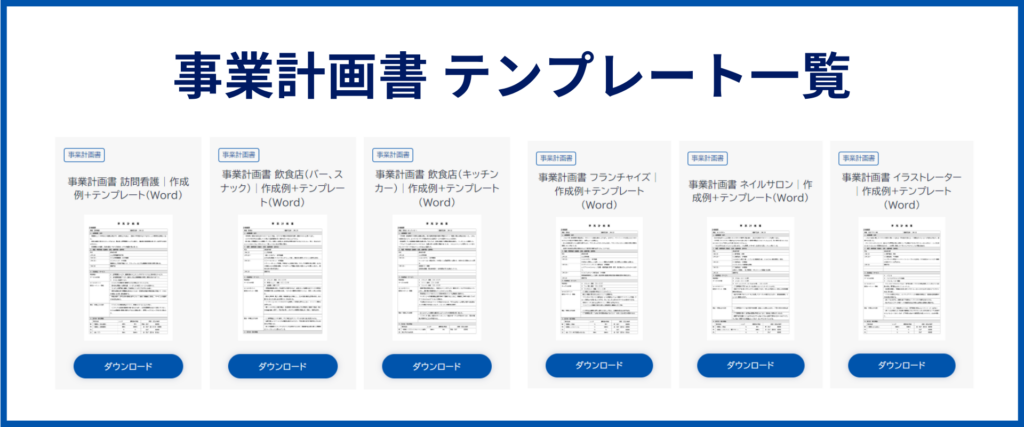- 更新日 : 2023年12月5日
クリニック経営の成功とは?マネジメントなど医療以外の対処法を学ぶ
医師や医療分野での起業に興味がある方の中には、クリニック経営に挑戦したい方も多いでしょう。医院を開業・経営するためには、黒字化のために患者数を増やしたり、看護師やスタッフをマネジメントしたりする必要があり、医療以外のさまざまな知識やスキルが必要です。今回は、クリニック経営の悩みや経営課題を解決するポイントを解説します。
目次
クリニックの経営、開業前は悩みだらけ
「地域医療に貢献したい」「1人でも多くの方の健康を守りたい」と考えている方には、クリニック経営がおすすめです。
しかし、クリニックの数は年々増加しており、生き残るのは容易ではありません。クリニック経営は決して簡単ではないことを理解したうえで、開業準備を進める必要があります。
ここでは、クリニック経営にあたってよくある悩みについて見ていきましょう。
- 集患できるか
- ドクターなどの人事マネジメントはうまくいくか
- 会計や財務・税務や行政対応がしっかりできるか
- 資金繰りで失敗しないか、事業拡大は可能か
- 自分が経営者としてやっていけるか
集患できるか?は一番の悩み
クリニック経営において多くの方が抱える悩みは、患者を集められるか、でしょう。
開業しても、集患できなければ当然売上にはつながりません。開業のためには家賃や設備費用など、多額の初期費用がかかります。収益を上げられるようになるまで時間がかかる場合も多いため、開業前から集患に向けた施策を講じることが必要です。
新規の患者を集めるだけでなく、リピートしてもらうことも欠かせません。再診率が低ければ、やがて経営は傾いてしまいます。
ドクターなどの人事マネジメントはうまくいくか
人事マネジメントも、クリニック経営の成否をわける重要なポイントです。
クリニック経営は、経営者が1人ですべての業務を行うわけではありません。ほかの医師や看護師、受付や事務職員などの協力があって、はじめてクリニック経営がうまくいきます。
人事マネジメントを行い、クリニック運営に携わるスタッフと良好な関係を築くことが求められます。
会計や財務・税務や行政対応がしっかりできるか
クリニック経営では患者を治療するだけでなく、経営者として会計や財務、税務まわり、行政対応なども行わなければなりません。経営者が1人で担当する場合は、必要な手続きや対応を正しく行うための知識が必要です。
多くの場合、会計士や税理士、社労士など外部の専門家に業務を委託することになります。その際は、自院の良きパートナーとなる専門家を見極め、契約後も丸投げすることなく、密にコミュニケーションをとることが必要です。
資金繰りで失敗しないか、事業拡大は可能か
クリニック経営に限らず、資金繰りに関する悩みは経営者にとってつきものです。
クリニック経営では機械設備にかかる費用、集客における広告宣伝費、水道光熱費、人件費、スタッフの給与・福利厚生費など、さまざまなコストが発生します。
資金繰りを考える際は、開業してから事業が軌道に乗るまでは時間がかかる点を考慮しなければなりません。初期費用だけでなく、一定期間の運転資金を確保したうえで事業を始めないと、資金繰りが悪化して倒産してしまうリスクがあります。
また、さらなる売上アップのために、提供するサービスの拡充や店舗数の増加など、事業拡大が可能かどうかについても検討が必要です。
自分が経営者としてやっていけるか
医療の技術やノウハウがあるからといって、経営者として成功するとは限りません。経営では戦略の策定やマーケティング、営業、広報、マネジメント、会計・財務管理、資金繰り管理など、さまざまな事項に関する知識が求められます。経営者が担当する業務の幅も広く、自分が経営者としてやっていけるか、不安に思う方も多いでしょう。
医療業務に追われてリソースが足りなくなると、経営が疎かになってしまいます。逆に、経営に注力しすぎると、肝心の医療業務の品質が低下し、患者の満足度が低下してしまうため、注意が必要です。
人材を採用して業務の分担を進めたり、適宜アウトソーシングを取り入れたりすることにより、多忙な中でも経営が回るよう工夫しましょう。
クリニック経営を成功に導く6つのポイント
クリニック経営に成功するためのポイントは、以下のとおりです。
- 経営理念をつくり共有する
- 何よりも患者を優先する
- スタッフが働きやすい組織づくりをする
- 地域に根ざして活動する
- ネットでも情報発信して集患を工夫する
- さらなる効率化を図る
患者やスタッフのことを考え、地域住民に選ばれ、スタッフが働きやすいと感じるクリニックづくりを徹底しましょう。
ここでは、クリニック経営を成功に導く6つのポイントについて解説します。
経営理念をつくり共有する
クリニック経営を成功させるためには、経営理念を策定し、スタッフにも共有することが大切です。
経営理念は、クリニックを経営する目的やビジョン、信念のことです。経営理念を明確化し、常に意識して行動しましょう。経営に行き詰まったり悩んだりした際にも、経営理念があれば、理念に従って適切な行動を選択できます。
さらに、スタッフ全員に共有することで、足並みを揃えられるのもポイントです。スタッフが患者への対応について判断に迷った際も、理念に基づいて判断し、対応できます。患者に対して適切なサービスを提供できるようになり、理想のクリニックを実現できるでしょう。
何よりも患者を優先する
クリニック経営は、患者がいなければ成り立ちません。そのため、コストカットや目先の利益ばかりを重視するのではなく、患者ファーストで行動する必要があります。
クリニック経営に成功するためには、患者にとって必要なサービスは何か、どのようなサービスを提供すれば喜んでもらえるか、などを常に考えて、経営に活かしましょう。患者ファーストの姿勢を示すことで、多くの患者から支持されるようになり、長い目で見ると売上アップにつながります。
スタッフが働きやすい組織づくりをする
患者だけでなく、協力してくれるスタッフのことも重視することが大切です。
スタッフにとって働きやすい組織を作ることで、スタッフのモチベーションやエンゲージメントが向上し、人材定着につながります。
労働時間が長かったり、スタッフ間のコミュニケーションがうまくいっていなかったりすると、スタッフが職場環境に不満を抱いて離職してしまう可能性が高いです。せっかく確保した人材がやめてしまうと、業務が回らなくなり、これまで教育にかけたコストも無駄になってしまいます。
新たな人材がすぐに採用できるとは限りません。求人や教育にさらにコストがかかります。
定期的にクリニックが抱える課題を洗い出し、スタッフが快適に働ける職場づくりを目指すことが重要です。
地域に根ざして活動する
クリニックの患者は、基本的には近隣住民です。多くの患者から選ばれるクリニックにするためには、地域に根ざして活動する必要があります。
自院が地域で求められている役割を自覚し、経営の参考にしましょう。
サービスを強化し、患者の役に立つクリニックにするためには、薬局や近隣の病院など、地域内での連携も欠かせません。
ネットでも情報発信して集患を工夫する
多くの患者を集めるためには、積極的な情報発信が求められます。
最近では、ネットでクリニックの情報を集め、来院する患者が多いです。ネットやSNSを活用して情報を発信し、クリニックの認知度を高める取り組みに力を入れましょう。
クリニックの様子や対応している疾患、医師のプロフィールなどをわかりやすくまとめたホームページを作成したり、診察情報を定期的に発信するためのSNSアカウントを開設したりするのが効果的です。
さらなる効率化を図る
クリニック経営では、業務効率化と生産性の向上がポイントです。
スタッフが手作業で行っている業務の中には、システムで効率化できるものも多いでしょう。Web問診システムや電子カルテ、オンライン予約サービスなどを活用することで、業務を大幅に効率化できます。無駄なコストの削減と利益率向上にもつながるでしょう。今まで事務作業にかかっていたリソースを、コア業務に集中させることも可能です。
ITシステムを活用した効率化は、患者にとっても予約が容易になることや、待ち時間が短縮されるなど、多くのメリットがあります。業務を見直し、効率化できる部分はないか模索することが大切です。
医療法人化するメリット・デメリットは?
クリニック経営の際は、医療法人を設立するという選択肢があります。医療法人化には、以下のようにメリットとデメリットがあります。
メリットとデメリットを比較検討したうえで、医療法人化するか否かを決めましょう。
メリット1. 資金調達面で有利になる
医療法人を設立することで、個人事業としてクリニックを経営する場合よりも、社会的信用度が高まります。その結果、資金調達で有利になりやすいのがメリットです。
資金調達の際、個人事業の場合は、経営者だけでなく保証人を立てる必要があります。一方、医療法人であれば、主体を医療法人、保証人を経営者にできるため、実質経営者だけで資金調達できるのもメリットです。
メリット2.税務上のメリットもある
医療法人を設立することで、医療法人から役員報酬が支払われます。個人事業の場合、報酬は経費として認められません。医療法人であれば、所得を給与として受け取れるため、給与所得控除が受けられるようになります。節税につながるのがポイントです。
また、将来クリニックを承継する場合、個人事業であれば多くの相続税がかかります。一方、医療法人であれば、法人の内部留保には相続税がかからないため、相続税負担を軽減できます。
デメリット1.法人設立には時間も手間もかかる
医療法人の設立にはさまざまなメリットがある一方、設立のために時間や手間がかかるのが難点です。
設立手続きに手間がかかるだけではありません。設立後も、医療法人については、毎年決算終了後3ヶ月以内に、都道府県知事に事業報告書を提出する必要があります。普段の業務に加え、報告書の作成やその後の複雑な運営管理に、時間や手間がかかってしまう点は見逃せません。
業務負担を軽減するために、司法書士や税理士、行政書士などに依頼することも可能です。しかし、依頼には費用がかかる点には注意しましょう。
デメリット2.解散することも難しい
医療法人には、事業の永続性が求められるため、簡単には解散できません。
医療法人は地域医療の担い手とみなされており、地域医療の永続性確保は医療法人制度の目的の1つです。そのため、後継者の育成に努め、安易な解散は避けなければなりません。
解散したい場合は、保健所への届出に加えて、別途医療法人の解散手続きが必要です。解散事由によっては、都道府県知事の認可を得る必要があります。
クリニックを経営するうえでの注意点
クリニック経営を闇雲に進めても、うまく集患できず経営に行き詰まってしまう可能性が高いです。
クリニック経営で失敗しないためには、以下の注意点を押さえましょう。
- クリニックの独自性を模索する
- 医療面でも経営面でも必要な学びを欠かさない
- 関連するビジネスへの展開も視野に入れる
- 必要なサポートは利用する
ここでは、クリニックを経営するうえでの注意点について解説します。
クリニックの独自性を模索する
クリニック経営では、競合と差別化するために、独自の方向性を模索しなければなりません。近隣のクリニックと同じようなサービスを提供するだけでは、わざわざ自院を選んでもらうことは難しいです。
専門的な治療を行っていることをアピールする、いつでも気軽に予約できるようにする、オンライン診療を取り入れる、患者の待ち時間を短縮するなど、自院ならではの魅力を増やし、積極的にアピールしましょう。
医療面でも経営面でも必要な学びを欠かさない
優れた医療技術や実績があるからといって、必ずしもクリニック経営に成功するとは限りません。前述のとおり、経営者は幅広い業務をこなす必要があります。経営をスムーズに進めるためには、マーケティングや広報など、経営に関する知識を習得することが大切です。
もちろん、医療面での学びも欠かせません。
高い技術力と充実したサービスでリピート率を高める、集患を工夫して新規の患者を増やす、財務や資金繰りなどを管理して健全な財務体質を維持するなど、経営者が果たすべき役割は多様です。経営者自らが、経営に必要な知識を積極的に吸収することが、クリニック経営成功のポイントと言えます。
関連するビジネスへの展開も視野に入れる
売上を安定させ、クリニックを成長させるためには、関連するビジネスへの展開を視野に入れることも大切です。
あるクリニックは、新型コロナウイルスの影響で、開業後の集患に苦労していました。そこで注目したのが、PCR検査です。PCR検査ができる体制を整備し、旅行会社と連携してPCR検査と陰性証明書を発行できるようにしました。その結果、PCR検査希望者が多く来院するようになり、収益につながったそうです。
ニーズのあるビジネスを見極め、素早く参入することで、万が一の事態にも耐えられるクリニックを実現できます。
必要なサポートは利用する
クリニック経営において必要な外部からのサポートは、積極的に利用しましょう。
クリニック経営専門のコンサルタントに相談することで、プロのアドバイスをもとにクリニック経営をスムーズに進められます。
特に、はじめてクリニックを開業する場合、不安や悩みは多いでしょう。クリニック経営は、医療の知識だけでうまくいくものではありません。クリニック経営に精通したコンサルタントの協力を仰ぎ、必要なサポートを受けながら経営を進めることが有効です。
また、経営者が業務をすべて抱え込む状態を作ってしまうと、経営と医療どちらもどっちつかずになってしまいます。会計士や税理士、司法書士など、必要に応じて外部のプロに業務を依頼することも大切です。
病院・クリニック開業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
効率的なクリニック経営を続けていくために
クリニック経営に成功するためには、医療技術だけではなく、経営者としての能力が求められます。患者とスタッフのことを常に考えて行動し、患者から選ばれ、スタッフにとって働きやすいクリニックづくりを進めましょう。
クリニック経営で経営者がやるべきことは多岐にわたります。業務効率化を進めたり、外部の専門家の力も借りたりしながら、地域のニーズに応えられるクリニックを実現することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
アパレルを経営したい人が増加中!立ち上げ方や向いている人を分析
「個人ブランドのアパレルショップやセレクトショップを立ち上げてみたい」若い世代を中心にアパレルショップの経営を夢見る人が少なくありません。とはいえ、アパレルショップを開業するという夢はあるものの、実際の立ち上げ方がわからないという人は多いの…
詳しくみる子会社とは?種類や設立するメリット・デメリット、会計のポイント
子会社とは、親会社に支配されている会社のことです。定義は会社法で定められており、「完全子会社」「連結子会社」などいくつかの種類があります。 今回は、子会社について詳しく解説します。子会社の設立方法や会計について知りたい方はぜひ参考にしてくだ…
詳しくみる会社買収とは?M&Aとの違いやメリット、成功する企業のポイントを解説!
会社買収とは他の会社の株式を取得して、その企業の経営権を握る行為のことです。合併の意味を持つM&Aとは示す範囲が異なり、敵対的買収や友好的買収などの種類があります。 買収の流れでは、企業調査のデューデリジェンスが重要です。今回は、会…
詳しくみる経営リスクとは?種類やリスクマネジメントの方法も紹介
経営リスクとは、企業経営で発生しうるリスクのことで、その種類は多岐にわたります。経営を成功に導くためには、経営リスクを予測し、リスクを未然に防ぎ、発生時の被害を抑えるための取り組みが欠かせません。今回は、経営リスクとは何か、種類やリスクマネ…
詳しくみる経営再建とは?企業再生の事例や手法も解説
経営状態を悪化させている原因を取り除き、企業の経営状態を健全化する取り組みを「経営再建」と呼びます。自社の経営が危機にある場合、経営者は経営再建の可能性を分析した上で、さまざまな取り組みを進めることが必要です。 この記事では、経営再建の意味…
詳しくみる公共経営・公共施設経営とは?成功事例4つも
近年、あらゆる地方自治体において公共経営・公共施設経営の取り組みが推進されつつあります。公共経営とは利益獲得を目的としない公共的組織にビジネス・マーケティングといった経営の概念や手法を取り入れるという考え方です。そして、公共施設経営は公共施…
詳しくみる