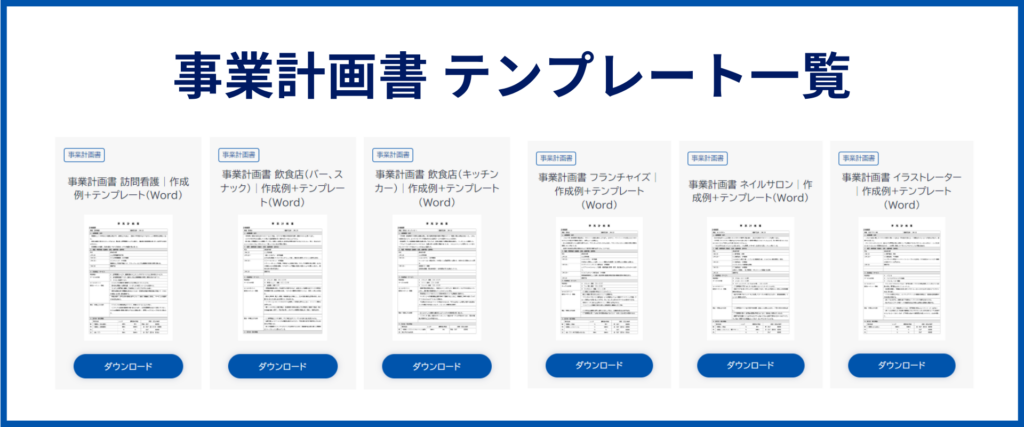- 更新日 : 2023年11月30日
デイサービス経営者の平均年収と経営が厳しい理由
デイサービス経営は、従業員の離職率が高かったり競争が激しかったりするなど、想像以上に厳しいのが現実です。実際のところ、赤字経営の施設が少なくありません。本記事では、デイサービス経営のリスクと、成功のためのポイントについて詳しく解説します。デイサービス経営者の年収に興味がある方も参考にしてください。
目次
デイサービスの経営者の平均年収は?
デイサービス経営者の具体的な年収は公表されていないため、施設規模によるおおまかな営業利益を解説します。おおよそいくらくらいの金額が手元に残るのか、参考にしてください。
施設規模によるおおまかな営業利益
定員10名のデイサービスの場合、物件を借りていると仮定すると、営業利益は350万〜400万円ほど、定員15名であれば950万〜1,000万円ほどです。定員20名の場合では、おおよそ1,500万〜1,600万円になるでしょう。
定員20名ほどの施設であれば、ビジネスとしてもやりがいを感じるのではないでしょうか。また店舗が増えると、リスク分散が可能となり経営は安定します。
ただしこれらの数値は、条件によって異なります。後述しますが、稼働率が低ければ営業利益も少なくなるため注意が必要です。自身がデイサービスを経営する場合は、営業利益を厳しめに算出しましょう。
一方、厚生労働省が公表した調査結果によると、デイサービス管理職の平均月給は約33.9万円です。デイサービス事業は高齢者を相手とする仕事であり、難しい面も多々あります。気を遣う仕事内容から、月給33.9万が妥当と感じるかどうかは個人差があるでしょう。
経営者の年収ミュレーション例
自分で会社を経営する場合、自身の年収をいくらくらいにすべきか迷う方は多いことでしょう。従業員を1,000人以上抱える規模の大企業の場合、社長は4,000万円〜6,000万円ほど、取締役であれば2,000万円〜3,000万円ほどです。会社の規模が大きくなるほど、年収も高くなる傾向にあります。
中小企業の場合、社長の年収は1,000万円〜4,000万円ほどです。会社の規模や条件により、金額にかなり幅があります。実際には年収500万円だったり、また従業員と同程度だったりとさまざまです。
デイサービス経営の場合、上に述べた営業利益と中小企業の例を参考にいくらくらいの年収になるのか、おおよそのシミュレーションができるでしょう。
デイサービス経営が厳しいと言われる理由
デイサービスは、さまざまな理由から経営が難しいと言われています。ここでは、なぜデイサービス経営が難しいのか、理由を5つ解説します。
介護報酬の改定の影響を受ける
デイサービス事業では、収益の大部分が介護保険からの介護報酬です。介護報酬が減れば、そのまま収益低下につながります。
介護保険から支払われる介護報酬は、3年毎に見直されます。次回の介護報酬改定は2024年です。国の財政悪化から社会保障費が削減されれば、介護報酬の削減もありえるでしょう。介護報酬の影響を抑えるために、保険外サービスを充実させることが必要です。
レクリエーションサービスやお泊りデイなど、さまざまな保険外サービスを取り入れ、介護報酬だけに頼らない体制を整えることが不可欠です。
従業員が定着しない
デイサービス事業では、従業員が定着しにくく離職率が高いのは悩みです。人手不足になると、充実したサービスを提供できず、利用者が減る可能性もあります。
また従業員が少なくなることで、残った従業員の負担がさらに大きくなり、離職に歯止めがかからないという悪循環に陥りかねません。デイサービス経営では、従業員の離職率を下げるために、働きやすい職場作りが重要です。
管理者が育っていない
デイサービス経営が難しい理由の一つは、管理者が育たないことです。管理者とは、従業員のケアや事業所運営をサポートする人を指します。管理者の具体的な役割は、次のとおりです。
- マネジメント:従業員の面接・採用・人員配置・育成などを行う
- マーケティング:利用者数やリピート率を増やし、経営の安定化を図る
- 行政書類の管理:3年に1度行われる実地指導のための書類を作成・管理する
このように、従業員のケアから利用者を増やすためのマーケティング、また細々とした行政書類の管理など、管理者の仕事内容は多岐にわたります。
デイサービス経営を成功させるためには、きちんと事業をサポートできる管理者は必要ですが、その管理者が育っていないことも現実です。
デイサービスの施設数増加による競争
デイサービス事業は比較的参入しやすいため、施設数が増え競争は激化しています。デイサービスは小規模でも開所でき、在庫も抱える心配はありません。
デイサービスの場所を確保できれば、初期投資もかなり抑えられます。また収益のほとんどが介護報酬という公費のため、未入などの心配もないのが魅力です。
こういった理由から施設数が増え、競争は激しさを増しています。ほかの施設との差別化を図るためにさまざまな工夫をしなければ、期待したような人数の利用者を確保するのは難しくなっています。
赤字経営している事業所の割合も高い
デイサービス事業では、赤字経営している事業所の割合が高い状況にあります。2020年度の赤字の割合は41.9%だったのに対して、2021年度は46.5%と増えています。おおよそ2つに一つの事業所で、赤字が出ているという厳しい状況です。
高齢者数は増加しているため、デイサービス経営もうまくいくと思われがちですが、実際には利用者を確保できず赤字経営をしている事業所が少なくありません。
参考:福祉医療機構「2021年度(令和3年度)通所介護の経営状況について」
デイサービス経営を成功させるためのポイント
デイサービス経営を成功させるためには、いくつかのポイントを理解しておくことが大切です。ここでは、デイサービス経営を成功させるためのポイントを4つ説明します。
介護職員処遇改善加算は算定必須
介護の現場で働く人たちの処遇を改善するために、国ではいくつかの加算を用意しています。とくに、介護職員処遇改善加算の算定は必須でしょう。介護職員処遇改善加算とは、従業員の賃金改善を図る目的で設けられています。
介護職員処遇改善加算をきちんと算定できれば、従業員の賃金アップや処遇改善が可能です。介護職員処遇改善加算を取得するためには、必要な書類を作成し申請しなければなりません。
事業所の管理者が最新の情報をしっかりとキャッチし、取得できる加算をもれなく申請することで、デイサービス経営が安定します。厚生労働省では処遇改善に関わる加算について情報を公開しているため、次のサイトで確認し、申請できる加算はないかどうかを確認してみてください。
自社デイサービスの差別化・ブランディング
デイサービス経営を成功させるためには、厳しい競争を勝ち抜く必要があります。介護といえども、ほかの業種同様に自社デイサービスの差別化やブランディングが必要です。
利用者のニーズは何か、どこにあるのか、またニーズに応えられるサービスを打ち出しているのかなど、経営者目線で考えなければなりません。ほかの事業所との差別化が図られ、周知できれば、利用者も自然と増えていくでしょう。
稼働率を上げる
経営を安定させるためには、事業所の稼働率アップは欠かせません。稼働率とは、事業所が利用できる最大人数に対して、実際に何%の利用があるのかを示すものです。稼働率が高いほど、経営が安定している状態です。
ただし稼働率を上げるために、人員を増やし、手厚いサービスをおこなうことが必ずしも経営の安定化につながるわけではありません。人員を増やせば人件費がかかり、トータルでは赤字になる場合もあります。
稼働率60%を下回ると、赤字となるケースが多いようです。まずは稼働率60%を目指しましょう。バランスを見ながら、稼働率を上げる戦略が必要です。
稼働率以外にもデイサービスの経営指標について把握する
デイサービス経営をおこなう際は、稼働率以外にもデイサービスならではの経営指標を把握する必要があります。人件費率や労働生産性、平均要介護度、利用者1人あたりの人件費、利益率、損益分岐点などについて、一つひとつ解説しましょう。
- 人件費率:売上に対する人件費の割合

2000年度の厚生労働省の実態調査によると、人件費率の平均値は63.8%でした。デイサービスの場合、60%前後が良いと言われています。
- 労働生産性:従業員一人あたりが生み出す価値
労働生産性とは、一人の従業員がどれほどの付加価値を生み出しているのかという指標です。同じ仕事量であれば、従業員が多いほど労働生産性は低くなります。従業員が多すぎると人件費がかさむため、適切な人員配置を考え、必要な人員のみを雇うようにしましょう。
- 平均要介護度:利用者の介護の平均値
要介護度とは、どれくらいの介護が必要なのかを示す指標です。要介護度が高くなるほど介護報酬も大きくなるため、平均要介護度の把握は欠かせません。ただし、要介護度が高くなると、より多くの人員が必要となるためバランスが大切です。
- 利用者一人あたりの人件費:どの程度の人的サービスがあるかの指標

利用者一人あたりの人件費を算出することで、どの程度の人的サービスが行われているのかを客観視できます。この値が小さすぎる場合、利用者数に対して人員が足りていない可能性はあります。また大きすぎる場合は、業務効率が悪いことを示しているため注意が必要です。
- 利益率:会社の最終的な収益力
利益率とは、売上から税金などを差し引いた最終的な利益力を示します。売上高に対して、5〜10%前後が良いと言われています。
- 損益分岐点:収益と費用が等しくなる点。いわゆるトントンの状態
損益分岐点は、次の計算式で求められます。

固定費とは人件費や家賃、車代などです。変動費とは、材料費や販売手数料などを指します。
損益分岐点は損失は出ていないものの、利益も出せていない状態です。デイサービスを経営する際は、いくらくらいが損益分岐点なのかを把握しながら、損益分岐点を上回る経営を目指すべきでしょう。
これからデイサービスを開業予定の方は、次の記事が参考になります。指定基準や申請方法を詳しく解説しています。
参考:デイサービス(通所介護)を開業するには?指定基準や申請方法を解説!
参考:厚生労働省 令和2年度介護事業経営実態調査結果
デイサービス・介護事業開業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
【事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例】
リスクポイントを押さえてデイサービス経営を成功させよう!
デイサービス経営は、国から認められた公共性の高い事業です。収益の大部分を介護報酬が占めるため、介護報酬を意識した経営が欠かせません。ただし、ビジネス視点での運用は不可欠です。リスクポイントを押さえて、さまざまな経営指標を確認しながら事業を展開していくことが、成功への鍵といえるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
経済産業省のグループガバナンスに関する実務指針とは?企業の取り組みを解説
グループガバナンスとは、親会社が子会社を含む企業グループ全体を統制・支援し、戦略的な成長とリスク管理を実現する仕組みです。経済産業省はこの考え方を企業経営に浸透させるため、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を公表し、持続的な…
詳しくみる経営手法はどれがおすすめ?目的別にやり方を解説
経営手法は戦略面や財務面、管理面の3つの側面において重要な要素です。経営手法には目的別にさまざまな方法があるため、自社にあった手法を選ぶ必要があります。 本記事では、経営手法の重要性や戦略・財務・管理面でそれぞれ役立つ手法を解説します。どの…
詳しくみる動物園の経営は難しい?開業に必要な許認可や費用、失敗を防ぐコツを解説
「動物園の経営に携わりたい」と思っている人もいるのではないでしょうか。本記事では、動物園は難しいのか、開業に必要な許認可や費用などについて解説します。 あわせて、動物園経営で失敗を防ぐコツや動物園経営をする際に必要な事業計画書の書き方や定款…
詳しくみるゲストハウス経営の成功のコツとは?必要費用や準備について解説!
コロナ禍で行われた入国規制の解除などによって、訪日外国人観光客の数は以前の水準に戻りつつあります。需要を見越して、ゲストハウスを経営するのも良いでしょう。今回は、ゲストハウスはどのようにして開業するのか、開業に必要な資格や許可、ゲストハウス…
詳しくみる経営哲学とは?経営理念の有名例も紹介!
企業の存在意義や方向性、価値観、行動指針などを経営者自らが示すものである経営哲学は、経営理念・企業理念などとも呼ばれ、多くの企業が策定しています。経営・組織の基軸を作り、社外からの信頼を得るため重要とされているものです。この記事では、経営哲…
詳しくみるファブレス経営とは?メリットや企業事例を解説!
ファブレス経営とは、自社で工場を保有せず、製造を外部に委託する経営方式です。半導体メーカーやアパレルメーカーなど、多くの企業が採用しています。 初期投資や製造コストを抑えられ、市場の変化に柔軟に対応できる一方、品質管理が難しいのが特徴です。…
詳しくみる