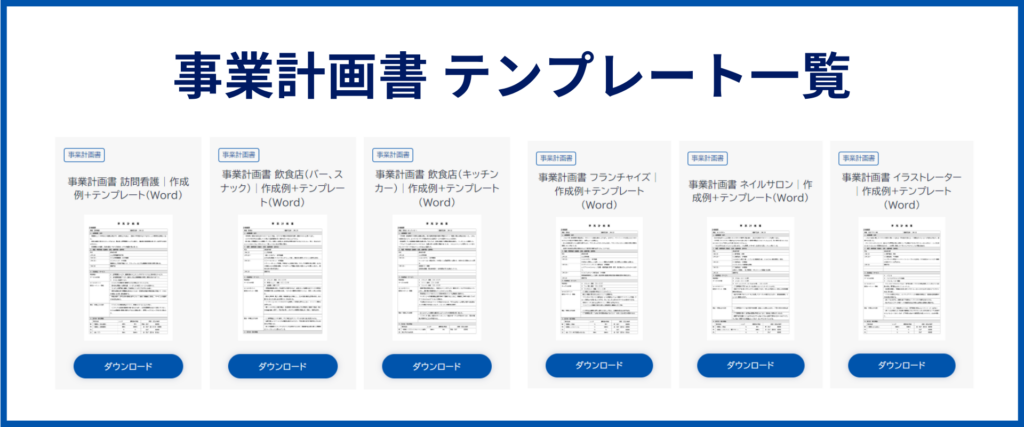- 更新日 : 2023年11月30日
ケアマネージャーの資格で開業する!居宅介護支援事業所の立ち上げ方
ケアマネージャーとして独立したいと思ったら、居宅介護支援事業所の開業がおすすめです。居宅介護支援事業所は、主任ケアマネの資格があれば一人でも立ち上げられるので、事務所を自宅兼用にできるなど参入も比較的容易といえるでしょう。
この記事では、資格の取得方法や、居宅介護支援事業所の立ち上げ方、独立のメリット・デメリットを紹介します。
目次
ケアマネージャーとして独立開業する方法はある?
ケアマネージャーとして独立開業するなら、居宅介護支援事業所の立ち上げが選択肢に入るでしょう。居宅介護支援事業所はケアマネージャー一人でも設立できる上、自宅でも開業できるなど参入しやすいのが特長です。
居宅介護支援事業所なら開業が可能
ケアマネージャー(ケアマネ)は居宅介護支援事業所の開業が可能です。居宅介護支援事業所とは、要介護認定を受けた人が自宅で生活できるよう、介護サービスなどの支援をする事業所です。
居宅介護支援事業所ではケアマネージャーが、本人と家族の心身の状況や生活環境、希望などを踏まえた上でケアプランを作成します。また、作成したケアプランを実現に移すため、介護保険サービスを提供する事業所などとの連絡や調整なども必要です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も「自宅」とされるため、やはり居宅介護支援事業所の業務対象に含まれます。
一般にケアマネージャーの勤務先は居宅介護支援事業所や介護施設などですが、最近では「独立型ケアマネ」と呼ばれる、居宅介護支援事業所を独立開業したケアマネージャーも増えています。
ケアマネージャー一人でOK・自宅でもできるなど、参入もしやすい
居宅介護支援事業所の開業は、ケアマネージャーの独立形態として適しています。まず、資格を持っていれば一人でも立ち上げ可能です。特別な設備や機器は必要ないので、設立費用もそれほどかかりません。
自宅でも開業できます。ただし、自宅で開業する場合には、事務所スペースは住居スペースと明確に分かれており、独立性が保たれていることが必要です。
同じ介護保険事業でも、老人ホームなどの立ち上げには多大なコストがかかります。それに比べて居宅介護支援事業所は参入しやすいといえるでしょう。
居宅介護支援事業所の管理者になるには
上述のように居宅介護支援事業所の開業は、ケアマネージャーの独立形態として適しています。ただし、管理者が主任ケアマネでなければなりません。
開業するなら主任ケアマネを目指そう
居宅介護支援事業所の管理者は、以前は一般のケアマネージャーでも問題ありませんでした。しかし、超高齢化社会が到来し、質の高いケアマネジメントが求められるようになっている背景から、原則として2021年度から主任ケアマネージャーに限られることになりました。
主任ケアマネージャー(主任ケアマネ)とは、ケアマネージャーの上級資格です。2006年に介護保険制度の改正が行われた際に新たに設置されました。ケアマネージャーのサポートや育成、地域の介護課題への貢献などが主な仕事内容です。
ただし、現状では、居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネではないケースが多数あります。そのため、2020年度末の時点で管理者が主任ケアマネではない居宅介護支援事業所は、2026年度まではケアマネージャーがそのまま管理を続けられるとする経過措置が設けられました。
もちろん、ケアマネージャーが管理者になれるのは既存の居宅介護支援事業所の場合に限ったことです。新規に立ち上げる居宅介護支援事業所の管理者は、主任ケアマネでなくてはなりません。
主任ケアマネになるには
主任ケアマネになるためには、主任介護支援専門員研修を受講しなければなりません。主任介護支援専門員研修の受講要件は、厚生労働省によって以下の4点が定められています。
- 専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して5年(60カ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
- ケアマネジメントリーダー養成研修修了者または⽇本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネージャーであって、専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して3年(36カ月)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
- 主任介護⽀援専⾨員に準ずる者として、現に地域包括⽀援センターに配置されている者
- その他、介護⽀援専⾨員の業務に関し⼗分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
ただし、都道府県により上記以外の要件が定められていることもあります。
研修は都道府県が実施します。「他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護⽀援専⾨員に対する助⾔、指導その他の介護⽀援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識および技術を修得すること」を目的として行われ、12日間にわたって70時間で行われるのが一般的です。受講費用は5万円程度となります。
居宅介護支援事業所の開業に必要なこと
居宅介護支援事業所の開業には、管理者が主任ケアマネであることの他にも必要なことがあります。それをここでは解説します。
法人格を有している必要がある
まず、居宅介護支援事業所の開業には法人格を有している必要があります。法人格の種類としては、株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などです。
人員・建物・設備の基準を満たす必要がある
人員や建物・設備に関しても、以下の基準を満たすことが必要です。
■人員の基準
- 常勤の管理者の配置常勤の管理者を1名配置しなくてはなりません。常勤の管理者はケアマネージャーとの兼務もできます。
- 常勤のケアマネージャーの配置居宅介護支援事業所ごとに1名の常勤のケアマネージャーを配置しなくてはなりません。ケアマネージャーは、利用者が35人またはその端数を増すごとに1名を増員します。ただし、増員のケアマネージャーは非常勤で構いません。
■建物・設備の基準
建物・設備に関しては、以下の基準を満たさなくてはなりません。
- 事業運営に必要な広さの専用の事務室を設けること
- 相談室は、利用者とその家族のプライバシーが確保できる構造となっていること
- 指定居宅サービスなどの担当者と会議を行う会議室を設けること(相談室との兼用も可)
- 事務機器や鍵付きのキャビネットなど、必要な設備・備品を設置すること
適正な事業の運営が義務付けられる
適正な事業運営を行うため、以下の運営基準の順守が義務づけられます。
- 内容と手続きの説明と同意
サービスの提供に際しては、利用者とその家族に対してあらかじめ、運営規定の概要などの重要事項を記載した書類を渡して説明を行い、同意を得なければなりません。 - 提供拒否の禁止
正当な理由なくサービスの提供を拒んではなりません。 - サービス提供困難時の対応
サービスの提供が困難と判断したケースについては、他の居宅介護支援事業所の紹介などの必要な措置を取らなければなりません。 - 受給資格などの確認
利用者の被保険者証で、被保険者資格と要介護認定の有無、要介護認定の有効期間を確かめます。 - 要介護認定申請の援助
被保険者の要介護認定申請に際しては、申込者の意思を踏まえて必要な協力をします。 - 身分を証する書類の傾向
ケアマネージャーには身分を証する書類を携行させ、初回訪問時などに利用者と家族に提示させなくてはなりません。 - 利用料金などの受領
介護サービス計画費と実際に支払いを受ける利用料に、不合理な差異が生じないようにしなければなりません。また、通常の事業の実施地域以外でサービス提供する際には、交通費の支払いを受けられます。 - 保険給付の請求のための証明書の交付
利用料の支払いを受けた場合は、利用料の金額などを記載した提供証明書を利用者に交付しなければなりません。 - 法定代理受領サービスについての報告
市町村・国民健康保険団体連合会に対して、法定代理受領サービスについての文書を毎月提出しなければなりません。 - 利用者に対するサービス計画などの書類の交付
利用者に対してサービス計画と実施状況についての書類を交付しなければなりません。 - 市町村への通知
利用者に不正などがあった場合は、遅滞なく市町村へ通知しなくてはなりません。 - 運営規定
必要とされる内容の運営規定を定めなくてはなりません。 - 秘密保持
利用者とその家族の秘密を漏らしてはなりません。
ケアマネージャーが開業するメリットとデメリット
ケアマネージャーが開業するメリットとデメリットを見ていきましょう。
主なメリット
ケアマネージャーが開業するメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。
■勤務時間を自由に決められる
開業の大きなメリットとして、まず挙げられるのは、勤務時間を自由に決められることでしょう。出勤時間や休憩時間、休日などは、全て自分の都合に決定できます。
■報酬は全て受け取れる
報酬を全て受け取れることも、開業のメリットです。事務所に勤めているときのように、会社の取り分はありません。頑張り次第では、年収を増やすことも可能でしょう。
■仕事の内容・種類を選べる
独立開業すれば、仕事の内容や種類を選ぶことが可能です。やりたくない仕事でもやらなければならない事務所勤務のときとは異なります。
主なデメリット
主なデメリットは、次の3つです。メリットと一緒に知っておきましょう。
■収入が不安定
開業のデメリットとしてまず挙げられるのは、どうしても収入が不安定になることです。勤めているときとは異なり、固定の給与がなくなるからです。
■営業・集客をしなくてはならない
事務所を開業すれば、自身が経営者となります。そのため、経営を安定させるためには、営業や集客も積極的に行わなくてはなりません。営業や集客が苦手な人にとっては、これは大きなデメリットになるでしょう。
■仕事量が増える
事務所運営にともなって、経理や顧客対応、事務所の備品管理などをしなくてはなりません。事務所運営に必要なことの全てを自分でやらなければならないため、勤務時代に比べれば、仕事量は増えるでしょう。
居宅介護支援事業所・介護事業開業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
【事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例】
介護事業の起業は万
ケアマネージャーの資格を活かすなら開業も考えてみては?
ケアマネージャーの資格を活かしたキャリアプランを考えるとき、居宅介護支援事業所の開業は一つの選択肢になります。主任ケアマネの資格があれば、居宅介護支援事業所の立ち上げを一人でも、事務所を自宅兼用にできるなど参入しやすいのが特長です。
主任ケアマネの資格を取得するためには、70時間の主任介護支援専門員研修を受講します。居宅介護支援事業所の開業にあたっては、法人格や人員、建物、設備、運営について必要な基準を満たさなければなりません。
独立すれば、勤務時間を自由に決められ、仕事の内容も選べます。チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
よくある質問
主任ケアマネの資格はどうすれば取得できますか?
一定の受講資格を持った人が70時間の主任介護支援専門員研修を受講すれば、主任ケアマネの資格が取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
居宅介護支援事業所は一人でも始められますか?
主任ケアマネの資格があれば、居宅介護支援事業所は一人でも始められます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
靴修理屋の独立・開業は難しい?開業資金や手続き、成功のコツを解説
靴修理の仕事は安定して需要があり、景気にも左右されにくく、独立開業のメリットがあります。小規模のスペースで開業でき、粗利も高めです。 本記事では、靴修理の開業方法や必要な知識・技術、開業を成功させるポイントを解説します。開業に関する不安や疑…
詳しくみる札幌市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
札幌市で開業届を提出する際は、札幌市の管轄税務署にオンラインや郵送で提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、札幌市の管轄税務署に提出しなければならない書類です。 青色申告を開…
詳しくみる徳島県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
徳島県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する徳島県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、徳島県の税務署に提出しなければならない書類です。 青色…
詳しくみる個人投資家は開業届の提出が必要?投資会社との違いや書き方を解説!
個人が所有する資産を運用して投資活動を行い、利益をあげる方を「個人投資家」と呼びます。「個人投資家」のなかには、投資活動を本業にして生計を立てている方もいますが、開業届の提出が必要な投資を行っているかの判断がつかない場合もあります。 今回は…
詳しくみる個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できる?法人との違いも解説
建設業に従事したい場合、「会社に所属して従業員として働く」「会社を設立して代表者として働く」などの方法が一般的に考えられます。 また、これらの働き方以外に、個人事業主、一人親方として働くという方法もあります。個人事業主や一人親方が経営業務の…
詳しくみる金券ショップの開業方法!個人ならフランチャイズ・独立どちらが良い?
商品券、ギフト券、ビール券、切手、収入印紙、あるいは鉄道チケットやレジャーチケットなどの販売・買取を行う金券ショップ。今ではすっかりおなじみですが、金券ショップの開業を志す人が少なくないようです。本記事では、金券ショップについて、開業・経営…
詳しくみる