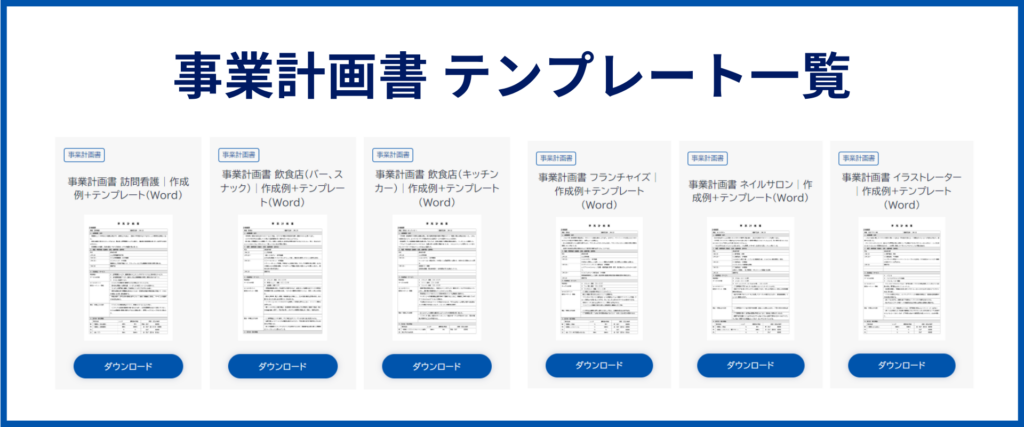- 更新日 : 2023年12月5日
民泊経営は儲かる?田舎でもOK?失敗例や年収も紹介
民泊経営が儲かるかは、エリア(首都圏か田舎か)や費用などによっても異なります。年収アップを期待するのであれば、他の宿泊施設との差別化やいかに観光客を取り込むかなどを意識しましょう。
また、種類によって必要な資格や届出が異なる点にも注意が必要です。本記事では、民泊経営が失敗しやすい理由や始め方などを紹介します。
目次
民泊経営に失敗しやすい理由
民泊経営は失敗しやすいと言われることがあります。主な理由は以下のとおりです。
- 民泊新法が定められた
- 利益を出すことや資金繰りが難しい
- エリア選定が難しい
- 他の施設と差別化ができていない
- 観光需要に左右される
それぞれの意味を解説します。
民泊新法が定められた
2017年6月に民泊新法(住宅宿泊事業法)が成立したことが、民泊経営は失敗しやすいと言われる理由です。民泊新法は3つのプレーヤー(住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者)を位置付け、それぞれに対して役割や義務などを決めています。
民泊新法によると、住宅宿泊事業をおこなう者が1年間に提供できる日数の上限は180日(泊)です。自治体によって、180日より短く設定されていることもあります。
1年間通して民泊を経営していたときと比べて経営できる日数が少ない分、十分な売上を出すことが難しくなりました。
参考:民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
利益を出すことや資金繰りが難しい
民泊経営にはさまざまな費用がかかり、すぐに利益を出すことが難しい点も失敗しやすい理由です。物件の調達やリノベーションなどに数百万円から数千万円の初期費用を必要とするときもあります。
民泊経営を始めるもすぐに結果につながらず、利益を出せなければ、資金繰りも悪化するでしょう。将来的に黒字化できる見込みがあっても、それまでのキャッシュが手元になければ運営を続けられず民泊経営に失敗してしまいます。
失敗を避けるためには、あらかじめ数か月分の運転資金を確保しておかなければなりません。
エリア選定が難しい
エリア選定が難しいことも、民泊経営に失敗しやすいと言われる理由です。日本のどこで民泊経営を始めるかによって、かかる費用や客単価、対策などが異なります。
たとえば、東京はビジネス客も観光客も取り込みやすいエリアです。その一方で、コストがかさむ傾向にあります。
一方で、京都や福岡、札幌などの場合、観光客が中心となる点が特徴です。
他の施設と差別化ができていない
他の宿泊施設との差別化ができていないと、民泊経営に失敗しやすいです。
民泊以外にも、ホテル・旅館・コンドミニアム・ユースホステルなど、さまざまな宿泊施設の選択肢があります。他の施設と比べて、料金が高い場合やサービスのレベルが低い水準にある場合、観光客はあえて民泊を選択しないでしょう。
失敗を避けるためには、料金を下げる、他の施設にはないサービスを提供するなどの方法で、差別化を図らなければなりません。
観光需要に左右される
観光需要に左右されることも、民泊経営の失敗につながります。
景気や社会情勢などによって、今まで安定的に確保していた宿泊客数が、ある日突然減少してしまうこともあるでしょう。たとえば、新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認された年(2020年)の延べ宿泊者数は、前年と比べて大幅に減少しました(-48.9%)。
参考:観光庁 宿泊旅行統計調査(令和2年・年間値(確定値))
民泊経営でどれくらい儲かる?理論年収は?
民泊経営でどれくらい儲かるかについて、公的なデータはありません。数百万円が理論年収の目安です。
たとえば、ワンルームで1泊1万円で運営した場合、180日制限を考慮すると最大でも180万円しか収入になりません。ここから日用品の補充や清掃費用、水道光熱費などを考慮すると、自分個人の手元に残る収入はさらに少なくなるでしょう。
年間で手元に300万円以上入るようにするためには、集客できるエリアを選ぶ、広い部屋の物件を選ぶなどの方法で、1泊あたりの売上を数万円にすることを目指さなければなりません。
田舎で民泊経営は儲かる?
田舎は都会と比べると土地代などが安いため、民泊経営で儲かる可能性はあります。状況によっては、180日までフルに営業せず、月に10日ほどの稼働で黒字化できることもあるでしょう。
しかし、観光客がいないエリアであれば集客が難しいため、さまざまな工夫を凝らさなければなりません。田舎の民泊経営で稼いでいる人は、その土地ならではの付加価値を上手に提供して集客しています。
郷土料理を味わう田舎暮らし体験や、農業体験・漁業体験などをセットにした宿泊の提供は、田舎の付加価値を加えた民泊経営事例のひとつです。さらに、日本らしさをアピールできるものであれば、外国人宿泊客の増加も期待できます。
民泊経営にかかる費用
民泊経営には、さまざまな費用がかかります。初期費用とランニングコストに分けて、確認していきましょう。
初期費用
民泊経営の初期費用としてかかるのは、主に以下のとおりです。
- 賃貸料(物件購入費用)
- 備品・家具・設備購入費
- 開業許可申請代行費用
まず、民泊を提供するための施設を用意しなければなりません。賃貸で物件を用意する場合、敷金・礼金・初回の賃料など100万円前後が初期費用として必要です。
備品・家具・設備購入費は、ベッドやソファなどの調達費用を指します。種類によって異なりますが、数十万円はかかるでしょう。
また、民泊経営は申請が必要です。手間や時間を考慮して、業者に代行を依頼する場合、代行費用が10万〜40万円かかります。
ランニングコスト
ランニングコストとしてかかる主な費用は、以下のとおりです。
- 水道光熱費
- 消耗品費
- 管理費
民泊施設を利用する際の水道代・ガス代などがかかります。規模によって異なりますが、月数千円から2万円程度はかかるでしょう。
また、シャンプーやボディソープなどの消耗品調達に、月数千円から1万円程度かかります。民泊施設の管理を業者に依頼する場合、宿泊料に対して15〜20%程度の管理費がかかる点にも注意が必要です。
そのほか、Wi-Fiを提供するためにインターネット環境の整備にコストがかかることもあります。
民泊経営の種類と必要な許可
民泊を始めるには、以下3種類の方法があります。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出
- 旅館業法の許可
- 特区民泊の認定
届出・許可・認定とそれぞれ許認可などの種類が異なります。
ただし、いずれも消防法に基づく対応や手続きが必要になり、消防法上の扱いは基本的に同じです。そのため、条件次第で着工届・設置届・防火管理者選任届出書・使用開始届などの提出を追加で求められることがあります。
ここから、各民泊経営の特徴や、必要な許可について確認していきましょう。
参考:総務省消防庁・住宅宿泊協会(JAVR) 民泊を始めるにあたって
住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊
住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は、都道府県知事への「届出」が必要な民泊です。所管省庁は、国土交通省・厚生労働省・観光庁が該当します。
民泊新法による民泊には、家主居住型と家主不在型の2種類に分類可能です。家主居住型は、自宅の空いた部屋を利用して旅人を招き入れる形式に対し、家主不在型は相続した実家など自宅以外で民泊を提供する形式を指します。
民泊新法による民泊は、形式的な届出で始められるため比較的早い段階から営業できる点がメリットです。ただし、自治体によって審査が異なるため注意しましょう。
住居専用地域での営業が可能な点もメリットです。自宅や相続した物件などを活用すれば、初期費用を抑えられます。
年間営業可能日数が180日に制限されている点が、民泊新法による民泊のデメリットです。1年中営業して売上を出したい人には、馴染まないでしょう。
また、家主不在型の民泊を選択した場合、住宅宿泊管理業者への委託が必要になる点がデメリットです。住宅宿泊管理業者に委託する場合、売上に対して15〜20%の手数料がかかります。
自ら、住宅宿泊管理業者になることはできますが、国土交通大臣の登録が必要です。
旅館業法の民泊
民泊を180日超営業することを検討している場合、基本的に旅館業法に基づく許可を得なければなりません(所管省庁:厚生労働省)。旅館業法による許可には「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」があります。
いずれも宿泊料を受けて人を宿泊させる営業である点は共通していますが、簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設、と定義されている点が主な違いです。一般的に、民泊は「簡易宿所営業」で許可を取得します。
旅館業法の宿泊は、1年中運営して売上を出せる点がメリットです。一方、建築基準法の用途地域の制限を受けますので、民泊新法による民泊と比べて営業できるエリアが限られている点が、デメリットとして挙げられます。
また、簡易宿泊所としての基準を満たさず、用途変更申請が必要な場合、一級建築士の資格を持つ業者に図面の作成を依頼しなければなりません。
参考:厚生労働省 民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~(平成30年6月改訂版)
特区民泊
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは、外国人旅客の滞在に適した施設の民泊サービスに対し、旅館業法の適用を除外する制度を指します。「外国人旅客の滞在に適した」とは、主に使用方法に関する外国語を用いた案内や、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供することです。
特区民泊を始めるには、「認定」を受けなければなりません。内閣府(厚生労働省)が所管しています。
民泊新法による民泊と異なり、不在時の管理業者への委託義務がない点が特区民泊のメリットです。また、旅館業法の民泊と異なり、住居専用地域での営業が可能な点も、メリットとして挙げられます。
特区民泊のデメリットは、対象エリアが限定されている点です。2023年6月30日時点で、東京都大田区・大阪市など8か所のみが該当しています。
そのほか、受け入れる客の宿泊日数が、2泊3日以上が条件とされている点も特区民泊のデメリットです。
参考:民泊制度ポータルサイト 特区民泊について
参考:内閣府 国家戦略特区 旅館業法の特例(特区民泊)について
参考:国土交通省観光庁 住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 2022年3月
民泊経営の始め方
民泊経営にあたって、3種類のうちどの方法が自分にあっているかを最初に検討しましょう。今回は、民泊新法による民泊経営を始める際の流れを解説します。
主な流れは以下のとおりです。
- 事業計画を立てる
- 設備要件を確認する
- 民泊新法による届け出をする
- ウェブなどに掲載して周知する
- 開業
民泊の種類を決めたら、まず市場調査や事業にかかる費用、売上見込みなどを盛り込んだ事業計画を立てます。事業計画書は、銀行から融資を受ける際にも必要な書類です。
続いて、民泊経営に必要な設備を備えているか確認します。場合によって、消防設備などの設置が必要です。
準備が整ったら、住宅の登記事項証明書や図面、賃借人の場合賃貸人が承諾したことを証明する書類などを揃えて、行政に届け出をします。
また、民泊経営には施設を知ってもらうことが重要です。ウェブやSNS、民泊サイトへの登録を通して周知しましょう。数か月から半年の期間を経て準備が整ったら、民泊を開業します。
参考:民泊制度 ポータルサイト 住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて
民泊・ゲストハウス開業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
民泊経営は種類選びがポイント
民泊経営を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出、旅館業法の許可、特区民泊の認定の3種類の方法があります。どの方法を選ぶかによって、営業できる場所や営業日数などが異なる点に注意が必要です。
たとえば、民泊新法による届出の場合、比較的早い段階から民泊経営を始められます。しかし、原則180日までしか営業できないため、十分な売上を出しにくい点がデメリットです。
どの種類が自分にあっているか十分に吟味して、民泊経営を始めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
経営リスクとは?種類やリスクマネジメントの方法も紹介
経営リスクとは、企業経営で発生しうるリスクのことで、その種類は多岐にわたります。経営を成功に導くためには、経営リスクを予測し、リスクを未然に防ぎ、発生時の被害を抑えるための取り組みが欠かせません。今回は、経営リスクとは何か、種類やリスクマネ…
詳しくみる経営とは?意味や定義をわかりやすく解説!
「経営」はよく耳にする言葉ですが、具体的な意味や定義について深く考える機会はあまりありません。 会社経営を失敗から遠ざけるためにも、この記事で経営の意義、経営のために必要な要素とは何か、経営者としては何が必要なのかをあらためて考えてみましょ…
詳しくみる経営判断でM&Aをする際の注意点。目的や手法、成功への道筋を解説
最近よく耳にするM&A(企業の合併や買収)ですが、中小企業においても件数は伸びてきているようです。中小企業の経営者にとってM&Aでの売却や買収などをどのように選択すればよいのでしょうか?この記事では、中小企業を想定したM&a…
詳しくみる本屋経営は難しい?政府の書店振興プロジェクトや経営アイデアまとめ
本屋の経営は難しいといわれています。売れる・儲かる本屋を経営するためには、本屋の経営難の要因を理解し、必要に応じて柔軟な経営アイデアを取り入れることが大切です。 この記事では、本屋の経営が厳しいといわれる理由や政府による書店振興プロジェクト…
詳しくみるワンルームマンション経営とは?7つの危険性・成功のポイント
ワンルームマンション経営は、サラリーマンを中心に安定した投資方法として人気があります。しかしながら実際には、期待したような利益を得られずワンルームマンション経営を断念する方もいるのが現実です。ここでは、ワンルームマンション経営が危険と言われ…
詳しくみる経営の責任は誰が負う?取締役の責任範囲や責任の取り方を解説
経営における責任を負うのは、原則として会社の取締役(役員等)です。本記事では会社法に基づき、経営判断や業務執行によって損害が生じた際に発生する法的責任の範囲や、個人事業主との違い、損害賠償請求の可否について詳しく解説します。 法人の経営に損…
詳しくみる