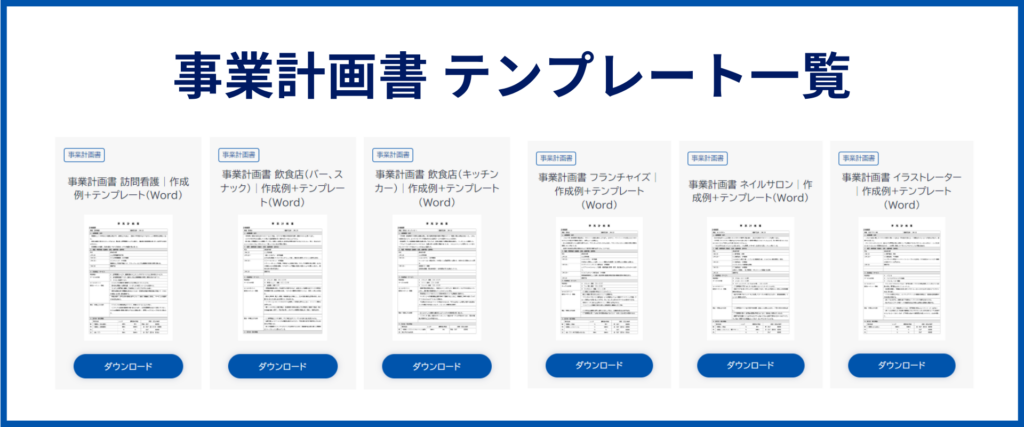- 更新日 : 2023年12月4日
アパート経営とは?土地活用に最適?メリットやリスク、費用について解説!

所有する土地に建てたアパートや、中古で取得したアパートを第三者に貸し出し、入居者から家賃収入を得る不動産事業をアパート経営といいます。株式投資とは違う、不動産への投資事業です。会社の主な事業とすることもあれば、副業的にアパート経営を行うこともあります。
今回はアパート経営のメリットやデメリット、知っておきたい利回りや経営にかかる税金、失敗を回避するためのポイントなどを解説します。
目次
アパート経営とは?
アパート経営とは新築のアパートを建設したり、中古のアパートを取得したりして、所有するアパートを賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る不動産事業の形態のことです。
通常はアパート1棟を丸々所有して、賃貸物件とします。会社で所有する場合は複数棟を所有することもありますし、すぐに使用する予定がない土地にアパートを建てて、活用することもあります。
アパート経営の仕組み
アパート経営は、第三者にアパートの1室を貸し出す事業形態です。そのため、主な収入は入居者からの家賃収入、入居時の礼金、更新時の更新料(礼金や更新料を設けないこともあります)となります。
所有権は入居者である第三者に移らないため、所有者であるアパート経営者が建物の修繕費や入退去時の経年劣化による原状回復費、火災保険料、固定資産税などを負担しなければなりません。アパート経営による収入からアパート経営にかかる費用を差し引いた額が、アパート経営の利益額となります。
アパート経営とマンション経営の違い
アパートとマンションの区分は、明確に定義されていません。
アパートとマンションは物件を扱う会社がどちらで呼ぶかを決めますが、一般的には木造で2階建て以下のものをアパートと呼び、造りがしっかりしている複数階建てのものをマンションと呼びます。
そのため建物1棟を所有する場合は、アパート経営よりもマンション経営のほうが規模は大きくなります。ただし、マンションの場合は区分所有といって、マンションの1室を所有して賃貸物件とすることも可能です。
アパート経営と株式投資の違い
アパート経営と株式投資は、投資対象が異なります。アパート経営の投資対象はアパートや土地といった不動産で、株式投資の投資対象は企業が資金調達のために発行する株式です。
株式は国際情勢や経済状況の他、企業の経営成績や財務状況なども株価に影響します。特に上場されている株式は日々売買が行われるため、値動きが激しいです。
アパート経営は株式投資とは異なり、不動産の価格が日々大きく変動することはありません。長期的に土地の価格が上昇したり、下落したりすることはありますが、土地の売買でなく賃貸業をメインにしている場合は、土地の価格変動による影響は限定的です。
アパート経営のメリットは?
アパート経営には、土地活用の面や節税面でメリットがあります。
土地を活用できる
土地は使用していなくても、所有していれば維持費が発生します。代表的なのが、固定資産税や土地計画税などの土地に課される地方税です。維持管理を委託している場合は、委託費用などもかかります。
使っていない土地を眠らせているだけでは、コストがかかるばかりです。アパート経営は、土地を有効活用する手段の一つです。
使用していない土地にアパートを建てて投資することで、家賃収入によって長期的に収入を得られるようになります。特にアクセスが良好なエリアなら、土地活用法としてアパート経営を検討するとよいでしょう。
相続税や固定資産税の節税対策ができる
土地をただ所有するより、賃貸物件として貸し出したほうが節税を図れます。例えば土地を所有していると、固定資産税や都市計画税が毎年発生します。アパートなどの賃貸物件の敷地は、200平方メートル以下の部分については6分の1(都市計画税は3分の1)などの特例措置があるので、固定資産税や都市計画税の納税額を軽減できます。
アパート経営は、相続税対策としても有効です。法人としてアパート経営を行う場合、アパートや土地は個人の財産ではないため、相続税の対象外です(ただし株式の相続には相続税が課せられます)。
会社で所有する不動産自体が対象になるわけではないため、株式相続の対策ができていれば、アパート経営は相続税対策にも有効です。
また、法人がアパート経営する場合は、不動産から得られる収入から必要経費を差し引いた所得がそのまま個人の所得とはならないため、結果的に経営者の所得税や住民税の税負担が軽減されることがあります。会社留保分と経営者の所得(給与所得)を区分できるからです。すべてを所得とせず会社に資金をプールすることで、アパートの増設といった投資にも有効活用できます。
アパート経営のデメリット・リスクは?
アパート経営はうまくいけばプラスになりますが、さまざまなリスクも伴います。代表的なのが、空室や家賃滞納による収益低下のリスクや、入居者トラブルのリスクです。リスクが重なると、アパート経営の収益が低下するおそれがあります。
空室や家賃滞納により収入が低下する
アパート経営では、新たな入居者がすぐに見つからないこともあります。空室が続くと、想定していた家賃収入を下回ってしまうでしょう。
空室が続く原因の一つとして、同じような間取りの周辺の物件と比べて家賃が高いことが考えられます。家賃を下げて入居者募集をせざるを得ない場合、家賃下落による収入減というリスクも生じます。
また、アパート経営は家賃滞納のリスクもあります。家賃滞納は空室リスクと同じように家賃収入が途絶えることが問題ですが、空室よりも厄介です。
家賃の滞納があっても、すぐに契約を解除して退去してもらうことができません。家賃滞納対策のために家賃保証のサービスを利用するとしても、コストがかかります。
入居者トラブルが発生するリスクがある
騒音やゴミ(異臭やゴミの出し方など)、ペット問題など、アパート経営では入居者間でトラブルが発生するリスクもあります。入居者間の問題とはいえ、対策を講じなければ被害が広がるばかりです。
対策が遅れるとトラブルがさらに拡大したり、周りの入居者の退去が相次いだりして、アパート経営の収益が低下することもあります。
トラブルが起こったら早急に対応する必要があること、対応にコストがかかる可能性があることなどが、アパート経営のデメリットといえるでしょう。
アパート経営に必要な資金は?
アパート経営には、どのくらいの資金が必要なのでしょうか。初期費用である建築費用とアパート経営開始後の維持費・修繕費について、簡単に説明します。
アパートの建築費用
中古アパートを取得する場合は中古物件の取得費などがかかりますが、新築の場合は建築の諸費用がかかります。建築費用の内訳は、以下のとおりです。
- 本体工事や設備費
- 測量費や地盤調査費
- 電気や給排水などの工事費
- 駐車場や空調などの付帯設備の工事費
- 不動産取得税などの各種税金など
全体の建築費用は、どのような構造の、どの程度の規模のアパートを建築するか、どの程度の設備を整えるかなどによって大きく変わります。一般的な木造アパートの建築費用の相場は、2,000万円前後です。付帯設備など本体以外の部分で費用が膨らむこともあるので、事前に資金計画をしっかり立てておきましょう。
アパートの維持費・修繕費
アパート経営で入居者を常に受け入れられるようにしておくためには、維持費や修繕費がかかります。維持費の中で代表的なのが固定資産税や都市計画税で、その他に火災保険や地震保険などの諸費用もかかります。
アパートは経年劣化するため、修繕も必要です。まず、退去時には原状回復費が発生します。入居者が故意で傷つけたものなどは借主負担になりますが、自然に消耗するような畳の劣化などは貸主(オーナー)負担です。
また、外壁塗装などの定期的な大規模修繕、空調設備など備え付けの設備の経年劣化による取り換え費用や修繕費なども発生します。特に大規模修繕費は負担が大きいため、必要な時に修繕できるように資金を積み立てておくことが大切です。
アパート経営の利回りは?
アパート経営の利回りには、表面利回り、想定利回り、実質利回りがあります。利回りとは、投資額に対するリターンのことです。
表面利回り
表面利回りは、物件の購入価格のうち年間どのくらいの割合を回収できるかを表すものです。以下の式を用いて計算します。
表面利回りが高い物件ほど物件購入額の回収が早いため、効率の良い物件といえます。
想定利回り
想定利回りは、空室リスク抜きでの物件購入価格に対する回収割合を示すものです。以下の式を用いて計算します。
リスクを考慮しない利回りであるため、物件を比較する場合など利回りをざっくり計算したい場合に向いています。
実質利回り
実質利回りは、アパート経営にかかる費用を考慮した物件取得価格に対する回収割合を示します。計算式は以下のとおりです。
アパート経営にかかる費用を加えた計算であるため、実際のリターンを想定しやすいでしょう。
アパート経営にかかる税金は?
法人がアパート経営を行う場合は、以下のような税金がかかります。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 固定資産税(都市計画税)
- 不動産取得時の税金
法人税
法人税は、法人の事業活動による所得額(法人税上の益金から損金を差し引いた額)に課せられる税金です。普通法人の法人税率は、原則的に所得額に対して23.2%(中小法人に該当する場合は年間所得800万円まで15%または18%)です。厳密には会計上の利益とは少し異なりますが、「法人がアパート経営で利益を出した分に課税される税金」と覚えておくとよいでしょう。
法人住民税
法人住民税は個人の住民税と同じように、地域社会にかかる費用の負担を広く求めるものです。その地域に住所のある事務所などに対して、都道府県と市町村がそれぞれ課税します。
法人住民税の税額は、均等割と法人税割の2つで構成されます。
法人税割の税額は、国税である法人税に対して一定割合(都道府県は1.0%、市町村は6.0%)を乗じたものです。法人税は法人の所得に対して課されるため、赤字の場合に法人税割は発生しません。
均等割は、法人の規模(資本金の額や従業員数)に応じて一律に課されるものです。均等割は法人の所得に関わらず発生するため、アパート経営が赤字であっても納める必要があります。
法人事業税
法人も地方自治体の行政サービスを受けることから、収益事業を営む普通法人などには都道府県から法人事業税が課されます。基本的には法人の所得に対して課されますが、一部の業種は収入に対して課されます。資本金が1億円を超える普通法人については、所得割に資本割や付加価値割が加算されます。
令和元年に地方法人特別税が廃止されたことで、特別法人事業税が創設されました。法人事業税の納税義務がある法人は、特別法人事業税の課税対象になります。
消費税
消費税は、さまざまな取引に幅広く課される税金です。最終的な負担者は商品やサービスなどを消費した消費者ですが、実際の納税者は事業者です。
納税義務者は、原則として年間の課税売上が1,000万円超となる事業者です。課税売上が1,000万円以下の事業者は、任意で課税事業者となることを選択しない限り、消費税の申告納税義務は免除されます。
消費税は国税ですが、消費税の納税義務者は地方税である地方消費税も併せて納付しなければなりません。
アパート経営の場合も、年間の家賃収入が1,000万円を超える場合は消費税の納税義務が発生する可能性があります。
固定資産税(都市計画税)
固定資産税は土地や家屋、事業者が所有する償却資産に課せられる地方税です。マンション経営では土地や建物を資本として事業を行うため、土地やアパート(建物)が課税対象となります。
土地や家屋は3年ごとの評価替えにより基準額が算出され、評価額に対して毎年課税が行われる仕組みです。標準税率は評価額に対して1.4%ですが、アパート経営のような賃貸物件は完全に所有権を行使することが難しいため、税額が軽減されます。
市街化区域内でアパート経営を行う場合は、固定資産税に加えて都市計画税を納める必要があります。
不動産取得時の税金
法人税や消費税、固定資産税などはいずれも毎年発生しますが、不動産取得時に限り以下のような税金を納める必要があります。
- 不動産取得税(土地の取得や家屋の新築など不動産の取得に関する税金)
- 登録免許税(所有権の登記に関する税金)
- 印紙税(物件購入時の売買契約書などの文書に必要)
アパート経営を成功させる方法は?
アパート経営には、さまざまなリスクがあります。リスクを抑えて経営を成功に導くためには、どのようなことに注目すればよいのでしょうか。アパート経営を成功させるための3つのポイントを紹介します。
賃貸用不動産は利便性やニーズも考慮する
消費者の立場で物件を探す際、何に注目するでしょうか。間取りや家賃も考慮すると思いますが、アクセス面や周辺の環境なども比較して選ぶ人が多いでしょう。
アパート経営では、利便性の高さやニーズが成功に大きく影響します。人気のないエリアだったり、ニーズにマッチしていなかったりすると、空室リスクが生じやすいです。
入居者層によって、立地のニーズは変わります。賃貸不動産としてアパートを取得または建築する際は、事前に周辺エリアのニーズを把握しておくことが大切です。
周辺エリアのニーズを知ることで期待できる入居者層や、それに合わせた条件(アクセスが良い、周辺に買い物できる環境があるなど)をイメージできるため、ニーズに合ったアパートを取得または建築しやすくなります。
細かい収支計画を立てる
利回りの計算は効率の良い賃貸不動産を見極める際に活用できますが、アパート経営におけるさまざまなリスクはあまり考慮されていません。また、利回りだけでは手元資金の推移がわからないため、事業計画を立てるのは難しいです。
アパート経営を始めるにあたっては、細かい収支計画を立てておくことが大切です。毎月発生する費用はもちろん、将来の修繕費に対する積立金なども考慮してキャッシュフロー(お金の流れ)を見ていきます。
常に満室で経営できる保証はないため、さまざまなリスクを考慮し、複数の収支シミュレーションを行うとよいでしょう。あらゆるケースを想定して適宜見直すことで、事業の安定を図れます。
契約する管理会社を見極める
アパート経営では、入居者募集や契約、退室や原状回復、トラブル対応、滞納者への催促、物件のメンテナンスなど、さまざまな管理業務が発生します。入居者募集は不動産仲介業者に委託するなど、一部を委託するケースも少なくありません。
アパート経営に関する業務の一部を委託する場合は、契約する管理会社を比較して信頼できる業者を選びましょう。管理が行き届いているかどうかは、経営の安定にも関わります。
アパート経営・開業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
・個人事業主(不動産投資)の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例
アパート経営に失敗しないよう慎重に計画を立てましょう
法人がアパート経営を成功させるためには、まずはアパート経営のメリット・デメリットや、必要な資金などを正しく把握する必要があります。その上で失敗しないように計画を立て、実行に移すことが大切です。事前にニーズを把握したり、細かい収支計画を立てたりして、アパート経営を始めましょう。
よくある質問
アパート経営とは?
所有するアパートを第三者に貸し出して、家賃収入を得る不動産事業のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
アパート経営を成功させる方法は?
利便性やニーズを考慮した賃貸不動産の取得や細かい収支計画、管理会社の見極めなどが成功にへの近道です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。