- 作成日 : 2025年9月16日
節税対策ガイド|個人事業主・会社員・法人の立場別に解説
節税は、収入を効率よく活かし、手元に残るお金を増やすための手段です。ただし、間違った方法や制度の誤解により、思わぬリスクを抱えることもあります。
本記事では、個人事業主・会社員・法人の立場ごとに実践できる節税対策をわかりやすく解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
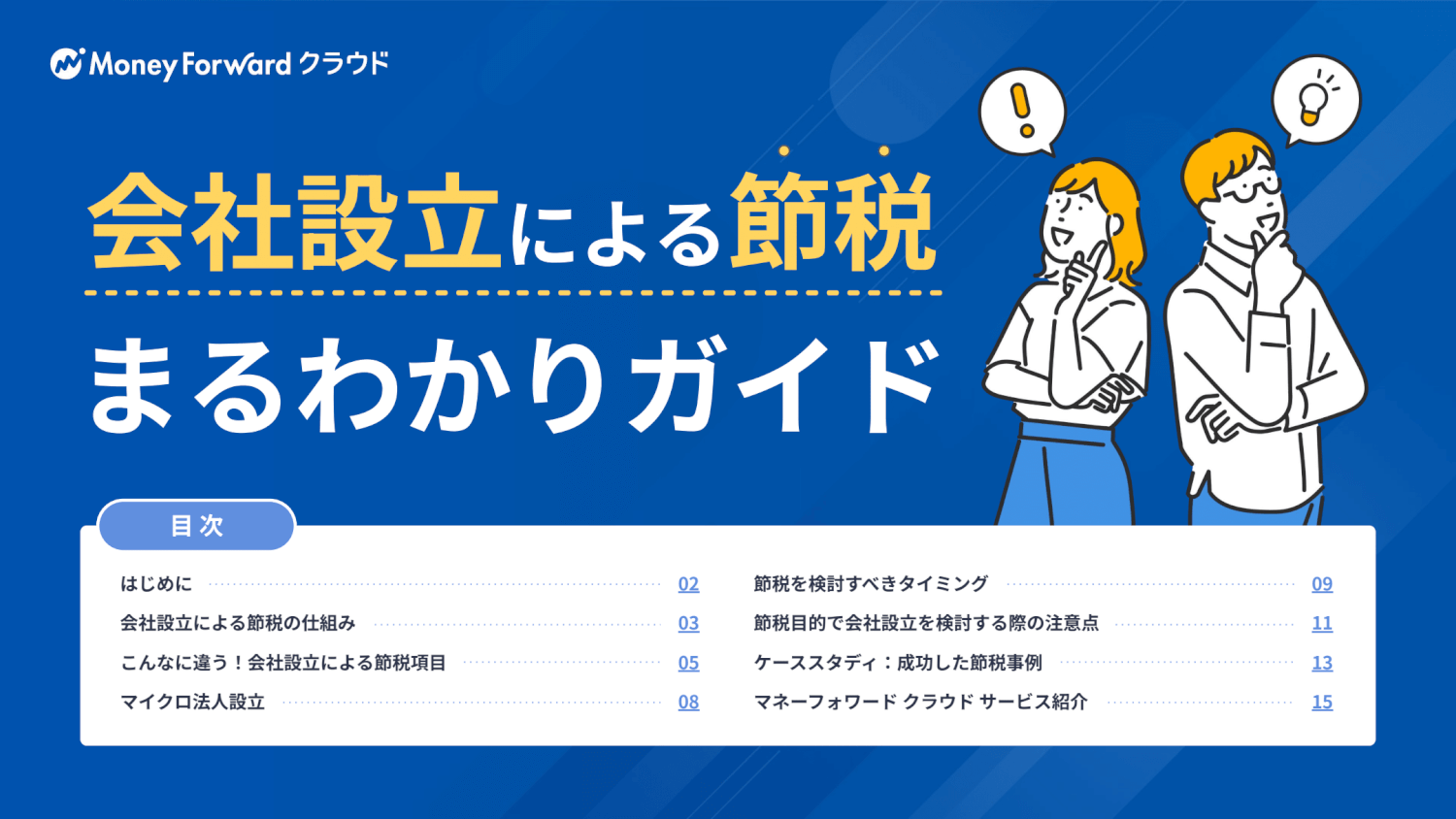
節税の基本
節税とは、税法で認められた仕組みを活用し、正当な方法で納税額を減らすことです。控除や優遇制度、経費の計上などを工夫することで、支払う税金を抑えることが可能です。一方、収入の隠蔽や架空経費の計上などによる脱税は違法であり、罰則の対象となります。
高所得者ほど税負担が重い仕組み
日本の所得税は「超過累進課税制度」を採用しており、所得が高くなるほど税率が上がります。課税所得が4,000万円を超える場合は所得税だけで45%が課されます。これに住民税(一律10%)と、所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税が加わるため、合計の最大負担率は約55.9%となります。
一方で、法人税の税率は一定であり、中小法人であれば年800万円以下の所得には15%、800万円を超える部分には23.2%が課されるという仕組みです。
このように、個人として高所得になるよりも、法人を設立して一定額を役員報酬として受け取るなどの工夫をすることで、税率面で有利になる可能性があります。節税を検討するうえで、自身の収入構造に応じた最適な方法を把握することが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
個人事業主の節税対策
個人事業主は収入や支出の管理を自ら行うため、節税効果のある制度や控除を上手に活用することが重要です。以下に、個人事業主が実践できる節税方法を紹介します。
青色申告を活用して節税
節税を考える個人事業主にとって、青色申告の導入は効果的です。所定の手続きと複式簿記による記帳を行えば、青色申告特別控除として55万円(電子申告などの条件を満たせば最大65万円)を所得から控除することができます。
年間の事業所得が500万円ある場合、65万円を差し引いて435万円が課税対象となり、その分の税負担が軽減されます。青色申告を利用するには、税務署への事前申請が必要ですが、一度申請し帳簿管理を徹底すれば、毎年の節税効果は大きなものになります。
経費を漏れなく計上して所得圧縮
個人事業主は、事業に関する支出を「必要経費」として計上することで、課税所得を抑えることが可能です。経費に含められる範囲は広く、自宅を事務所として使用している場合は家賃や光熱費、通信費などの一部も按分して経費に含めることができます。また、家族が事業を手伝っている場合には「事業専従者給与」を設定することで、支払った給与を経費に算入し、所得を分散させることができます。
ただし、事業専従者給与は税務署への届け出が必要です。これらを含め、日々の支出を記録・管理し、正確に経費として申告することで、効果的に税負担を減らすことが可能です。
将来への積立制度を活用して節税(小規模共済・iDeCoなど)
老後資金の準備と同時に節税効果も得られる制度として、小規模企業共済とiDeCoの活用が挙げられます。小規模企業共済は、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象の所得から控除される制度です。これは事業所得を計算した後の総所得金額から差し引かれる「所得控除」であり、売上から差し引く「必要経費」とは異なります。
iDeCoは個人型確定拠出年金で、掛金が全額所得控除となります。個人事業主の場合、月額上限6万8,000円まで積み立てが可能で、運用益も非課税。将来の受け取り時にも税優遇があるため、節税しながら老後資金を増やす手段として有効です。
一定以上の利益なら法人化も検討する
事業所得が一定額を超える場合は、法人化を検討することでさらに大きな節税効果が期待できます。法人税率は中小法人で年800万円以下の所得に15%、超える部分に23.2%が適用され、個人の高い所得税率と比べて低く抑えられる傾向にあります。たとえば、年収が800万円を超えるような場合には、法人化によってトータルの税負担が軽くなる可能性があります。
さらに法人化すれば、自分への報酬は「役員報酬」として支給され、これは法人の経費となるうえ、受け取る個人には給与所得控除が適用されます。給与所得控除は年収に応じて一定額が差し引かれる制度で、最大195万円の控除が認められています。
また、資本金1,000万円未満の法人であれば設立から最長2年間、消費税の納税義務が免除される特例も利用できます。ただし、法人化には設立費用、社会保険加入義務、経理の複雑化などのコストや事務負担も伴います。税制メリットとコストのバランスを見極めた上で、専門家の助言も得ながら慎重に検討することが望まれます。
会社員(サラリーマン)の節税対策
会社員は源泉徴収により給与から自動的に税金が差し引かれるため、節税の自由度は限定されます。しかし、税制上の各種控除制度を理解し活用することで、所得税や住民税を抑えることができます。
所得控除を最大限に活用する
会社員が節税を行う上で基本となるのが、所得控除の活用です。所得控除とは、課税所得を減らすために認められている項目で、適用できる控除を漏れなく申告することで、支払う税額が軽減されます。代表的なものとして、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、そして住宅ローン控除があります。
生命保険や地震保険に加入している場合、年間の保険料に応じて所得控除が受けられます。また、住宅ローン控除では、住宅ローンの年末残高の0.7%を10〜13年間にわたり所得税から直接差し引くことができ、大きな節税効果があります。
これらの控除は、原則として年末調整で処理されますが、医療費控除やふるさと納税などは確定申告が必要です。また、副業による所得が年間20万円を超える場合も確定申告が必要で、その際に青色申告を活用すればさらに控除が増えます。生活環境に照らして、控除対象となる項目を定期的に見直すことが重要です。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税は、会社員でも手軽に活用できる節税制度のひとつです。任意の自治体に寄付を行うことで、寄付金のうち2,000円を超える部分が所得税および住民税から控除されます。例えば、5万円を寄付すれば、2,000円の自己負担で4万8,000円が控除されるため、実質的な納税額が減ると同時に返礼品も受け取れるという仕組みです。
会社員は、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告をせずに控除を受けることが可能です。これは、1年間に寄付する自治体が5つ以内の場合に適用されます。6自治体以上への寄付や医療費控除などを併用する場合は、確定申告が必要です。ふるさと納税には年収や家族構成によって異なる控除上限があるため、自身の上限を把握したうえで、範囲内で賢く利用するとよいでしょう。
資産運用による節税(iDeCo・新NISAの活用)
将来の資産形成と節税を同時にかなえる方法として、iDeCoと新NISAの活用があります。iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が非常に高い制度です。
会社員のiDeCo掛金上限額は、勤務先の企業年金の加入状況によって異なります。企業年金のない会社員は月額2万3,000円、企業型DCのみに加入している場合は月額2万円、確定給付企業年金(DB)にも加入している場合は月額1万2,000円が上限となります。満額であれば年間27万6千円の所得控除が受けられます。
さらに、運用益も非課税で再投資でき、60歳以降の受取時には年金控除や退職所得控除の優遇が受けられる点も魅力です。
一方、新NISAは2024年に制度が拡充され、年間最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)の投資が非課税で可能になりました。非課税期間が無期限となったことで、長期運用にも適しています。生涯投資上限は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)で、資産形成にとって有利な制度と言えます。新NISAは直接的な所得控除にはなりませんが、運用益に本来かかる約20%の税金を非課税にできるため、長期的には大きな節税効果が期待できます。
法人(会社)の節税対策
法人には個人とは異なる節税手法が用意されており、適切に活用することで利益の最大化と安定経営の両立が図れます。この節では、法人が実践できる節税策を解説します。
経費計上の徹底と損金算入できる支出の活用
法人は、個人事業主と比べて損金(経費)として認められる支出の範囲が広く、これを活かすことが節税の基本です。従業員の給与や賞与、オフィス家賃、交際費、備品購入費、研修費など、業務に必要な支出は原則として損金に計上できます。また、業務使用が前提であれば、経営者個人のスマートフォン代や車両費も法人経費とすることが可能です。
さらに法人独自の節税策として、役員退職金や法人向け生命保険の活用があります。退職金は適正な社内規定を整えたうえで積み立てると損金算入が可能であり、受け取る際にも退職所得控除が適用されます。また、法人向け生命保険も要件を満たせば保険料を損金にでき、保障と節税の両立が可能です。ただし、税制改正により損金算入要件は厳しくなっているため、活用には最新の情報確認が必要です。
役員報酬の最適化による節税
法人では、役員報酬の額が会社の利益と法人税額に大きく影響します。役員報酬は法人にとっては損金となり、支給額を調整することで課税所得をコントロールできます。一方で受け取る側(経営者個人)には所得税・住民税がかかりますが、給与所得控除が適用されるため、一定の範囲であればトータルの税負担を抑えることが可能です。
会社が1,000万円の利益を出した場合、そのうち500万円を役員報酬として支給すれば法人税が減少し、個人は給与所得控除を受けることで課税所得を圧縮できます。このように法人と個人の税金のバランスを見極めて、全体としての節税効果を最大化することが重要です。ただし、役員報酬は期首に定めた額を1年間変更できない定期同額給与が原則であるため、慎重な設定が求められます。
設備投資や利益繰延べのタイミング調整
決算期が近づき利益が多く出そうな場合は、設備投資や前払費用の活用によって利益を繰延べ、節税を図ることが可能です。必要な備品や機器の購入を期末に前倒しすることで、その年の経費として処理でき、課税所得を減らせます。中小企業には一定の設備投資に対して即時償却や税額控除が認められる制度もあり、活用することで効果的に税負担を抑えられます。
また、短期前払費用の特例を活用すれば、翌期に提供を受けるサービスの費用でも一定の条件を満たす場合は当期の経費として計上できます。ただし、無理な前払いは資金繰りに影響するため、余裕資金がある場合のみにとどめるべきです。
加えて、利益調整手段として「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」への加入も有効です。この制度では掛金(月額最高20万円)を全額損金算入できるため、利益が出た年に積立てを行い、税負担を軽減しつつ将来のリスクに備えることができます。
税額控除制度や補助制度の活用
法人が直接的に税額を減らせる制度として、税額控除制度の活用が挙げられます。代表的なものに「所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)」があります。これは、従業員の給与を一定割合以上増額した場合に法人税の一部が控除される制度です。また、研究開発費に対する税額控除制度もあり、技術開発を行っている企業にとって有効な手段となります。
さらに、自治体によっては中小企業の設備投資に対して固定資産税の軽減措置が適用される場合もあり、地元の制度を調べることも節税に役立ちます。加えて、国や自治体が実施する補助金・助成金制度を活用することも間接的な節税につながります。たとえば、IT導入補助金や事業再構築補助金などを活用すれば、支出の一部を補填でき、残りの費用は経費計上により税負担の軽減につながります。
節税対策を行う際の注意点
節税は手元資金を増やし、将来の備えや事業の成長につなげるための有効な手段ですが、誤った方法や目的で取り組むと、思わぬリスクや不利益を招くことがあります。節税を実践する際の注意点をまとめます。
法律を守り、脱税に陥らない
節税と脱税の違いを明確に理解することが大切です。節税は法律で認められた控除や制度を活用する合法的な手段ですが、経費の水増しや売上の未申告などは脱税に該当し、発覚すれば重い罰則が科されます。
近年は、税務当局によるAIによる申告内容の分析や、インボイス制度による取引の透明化が進み、不正の発見精度が高まっています。節税はあくまで適法の範囲内で行い、堂々と胸を張れる形で実践することが重要です。
支出の目的を見失わない
節税を優先するあまり、本来必要のない支出をしてしまうのは避けるべきです。「税金対策のために経費を使う」といった考え方は、結果的に資金を減らし、本末転倒になりかねません。節税の基本は、必要な支出を通じて税負担を軽減することです。経費の一部は税金から差し引かれますが、支出した金額全体が戻ってくるわけではないため、「節税効果以上の出費」になっていないか、冷静に判断することが求められます。
最新の税制情報を確認する
節税に関わる制度や控除は、毎年の税制改正で内容が見直されます。控除額の変更、新たな優遇措置の追加、制度の廃止などが行われることもあるため、数年前の情報をそのまま鵜呑みにせず、常に最新情報を確認する姿勢が必要です。新NISAのように仕組みが大きく変わる制度では、正しい理解と活用が節税効果に直結します。信頼できる公的機関や専門家の情報をもとに、制度の変化に対応しましょう。
自分に合った節税対策を選び、正しく実践しよう
節税は、税制に則った適切な方法を選ぶことで、手元資金を有効に活用できる手段です。個人事業主・会社員・法人それぞれに有効な節税策が存在し、自身の立場や収入状況に応じて最適な方法を選ぶことが成果につながります。青色申告や各種控除、積立制度の活用に加え、法人化や投資制度も有効です。節税の本質を理解し、最新の制度を踏まえて、健全で継続的な対策を実践していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
資本金の額の計上に関する証明書とは?書き方・雛形を紹介
会社設立時に作成する書類には、さまざまなものがあります。資本金の額の計上に関する証明書も、会社設立時に代表取締役を務める人が作成する必要のある書類です。会社設立以外にも、作成が求められるケースがあります。この記事では、資本金の額の計上に関す…
詳しくみる仮想通貨の節税方法は?個人・法人別に税金対策を解説
仮想通貨取引によって利益が出た場合、税金の負担が想像以上に重くなることがあります。日本では仮想通貨の利益は雑所得として扱われ、他の所得と合算されて課税されるため、高額になるほど税率も上がります。さらに、損失の繰越や他の所得との損益通算ができ…
詳しくみる会社設立の相談は行政書士にすべき?費用やメリット、選び方まで解説
会社設立を思い立ったとき、多くの手続きや専門知識が必要となり、誰に相談すべきか悩む方は少なくありません。行政書士への会社設立の相談は、定款作成や許認可申請をスムーズに進めるための有効な選択肢のひとつです。 この記事では、行政書士に起業の相談…
詳しくみる民泊の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
民泊事業を株式会社で始める場合、定款の作成が必要になります。初めて法人設立をする方にとっては、定款の作り方や記載事項もわからないでしょう。 定款は正しく作成しなければ、効力がありません。本記事では定款の記載事項や、民泊の場合のポイントを詳し…
詳しくみる持分会社とは?株式会社との違いやメリット、設立手続きを解説!
持分会社は、株式会社と似たところもありますが、そうでないところもあります。例えば持分会社である合同会社を設立し、社員になるとどのようなメリットがあるのでしょうか? この記事では、社員における有限責任社員、無限責任社員の区別やそれぞれの責任の…
詳しくみるFXで会社設立する方法とは?節税対策など法人化のメリットも解説!
FXで会社を設立するためには、株式会社設立や合同会社設立などの方法があります。法人化することで、経費による節税対策ができる点や損益通算できる点などがメリットです。 ただし、法人化すると口座のお金を自由に使えない点に気をつけなければなりません…
詳しくみる


