- 作成日 : 2025年9月16日
フリーランスの節税対策まとめ|経費・控除から法人化まで解説
フリーランスとして働く上で、税金の仕組みを正しく理解し、効果的な節税対策を行うことは、安定した事業運営と手元資金の確保に直結します。所得税・住民税・消費税といった基本的な税負担に加え、売上や業種に応じた追加の税金が発生することもあります。こうした負担を軽減するには、経費や所得控除の活用に加え、青色申告や各種制度、さらには法人化といった選択肢も視野に入れることが大切です。
本記事では、フリーランスの方におすすめの節税方法を解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
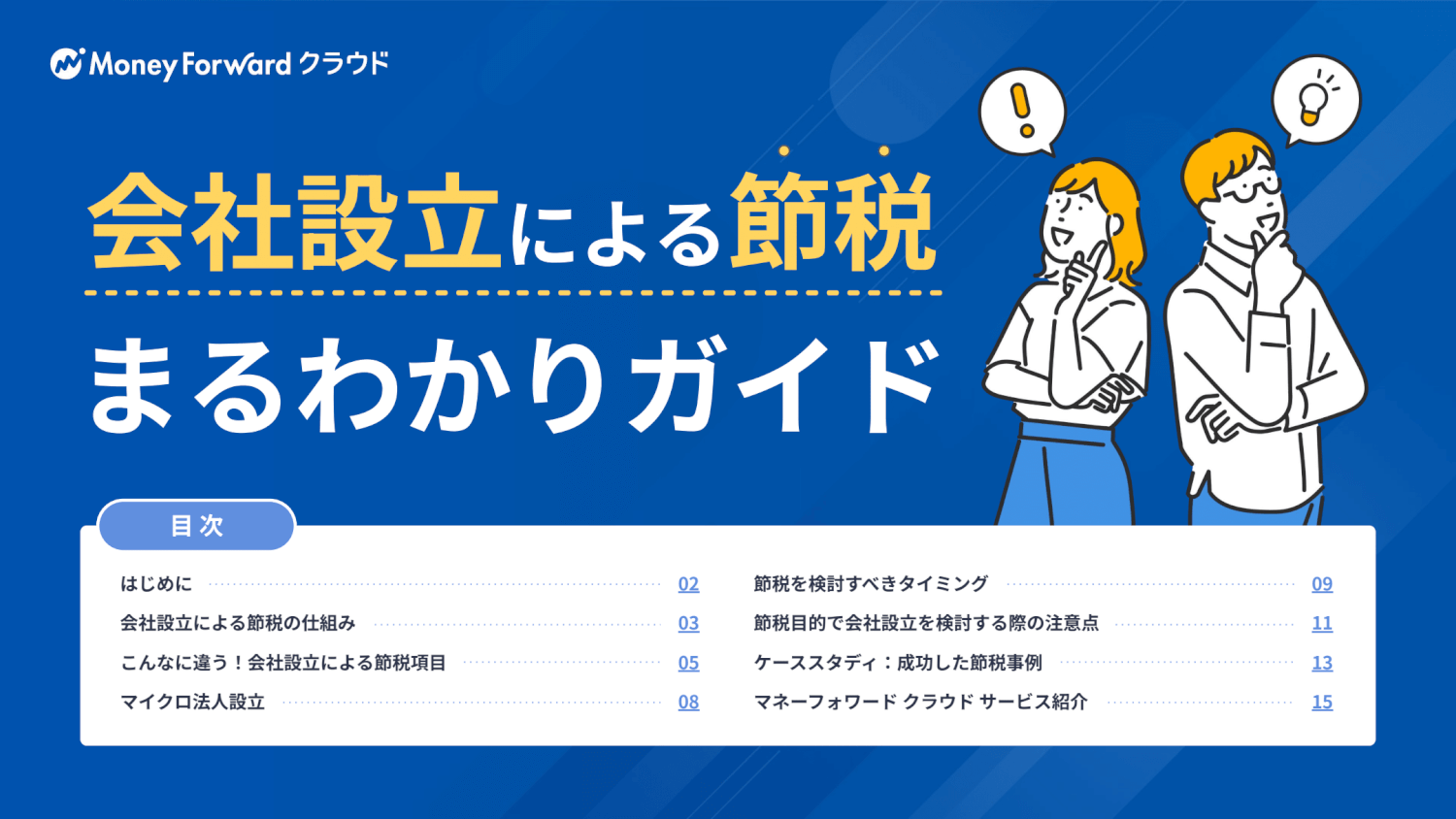
目次
フリーランスと税金の基礎知識
フリーランスとして働く場合、会社員とは異なり自分自身で税金の申告と納付を行う必要があります。所得が増えるほど税負担も大きくなるため、各種税金の種類や仕組みを理解したうえで、節税につながる行動をとることが重要です。ここでは、フリーランスが関係する主要な税金と特徴について整理します。
所得税・住民税を負担する仕組み
フリーランスが必ず支払う税金として、まず所得税と住民税があります。所得税は累進課税制度により、所得が増えるほど税率が高くなります。税率は5%から始まり、最大で45%に達します。さらに、所得税(最高45%)と住民税(約10%)に加え、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が課されるため、高所得者の合計税負担は最大で約55.9%に達します。
フリーランスは会社員のような年末調整はなく、原則として自身で確定申告を行う必要があります。確定申告で税額を自分で計算し一括納付する必要があるため、資金管理の面でも注意が求められます。
業種・売上規模により課税内容が変わる
フリーランスの業種によっては、個人事業税が課されることもあります。これは都道府県に納める税で、事業所得が年間290万円を超えた場合に発生し、対象業種は法律で定められています。加えて、消費税についても理解が必要です。前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じ、課税事業者として申告が必要になります。なお、2023年に始まったインボイス制度では、売上が基準以下でも適格請求書発行事業者に登録すると消費税の申告が求められるようになります。自身の売上規模や取引先の要請に応じた判断が欠かせません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
【基礎編】フリーランスの節税方法:経費と控除の活用
フリーランスがまず取り組むべき節税の基本は、必要経費と所得控除を正しく活用して課税所得を減らすことです。課税所得とは「収入-経費-控除」で算出され、これを小さくすることで所得税や住民税の負担が軽減されます。ここでは、経費の計上方法と所得控除のポイントを紹介します。
必要経費を正確に記録・活用する
必要経費とは、事業に直接必要な支出のことを指します。たとえば、業務用のパソコンやソフトの購入費、打ち合わせの交通費、通信費、書籍、広告費などが該当します。また、自宅を事務所として使っている場合には、家賃や光熱費の一部を「家事按分」として経費にすることも可能です。
経費は、支出を証明する領収書やレシートなどの記録が必要です。日々の支出を整理し、私的な支出と混同しないよう注意しましょう。また、青色申告を行っている場合には、「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用することで、設備投資を一括で経費に計上することもできます。たとえば、20万円のカメラをその年の経費として全額計上でき、課税所得の圧縮につながります。
所得控除をもれなく活用する
経費と並んで活用したいのが所得控除です。フリーランスも会社員と同様に、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、さまざまな控除が適用できます。確定申告で正しく申請することで、課税所得をさらに引き下げることが可能です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)は、控除額が大きくなる代表例です。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えると適用されます。原則として10万円を超えた場合に適用されますが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合に適用となります。上限は200万円です。
ふるさと納税では、2,000円の自己負担を除いた寄附金が控除対象となり、地域の返礼品も受け取れます。
また、青色申告をしている場合には「青色申告特別控除」が適用でき、条件を満たせば最大65万円の控除が可能です。こうした制度を組み合わせることで、フリーランスでも十分に節税が可能です。
【実践編】フリーランスの節税方法:青色申告と各種制度の活用
節税の基本を押さえたうえで、フリーランスがより大きな税負担軽減を目指すなら、青色申告や各種公的制度の活用が効果的です。ここでは、実践的な節税策として押さえておきたい5つの制度について解説します。
青色申告を活用して控除を受ける
青色申告は、正確な帳簿と申告を前提に税制上の優遇を受けられる制度です。最も大きなメリットは「青色申告特別控除」で、電子申告または電子帳簿保存を行えば最大65万円の控除が受けられます。事業所得が300万円なら、条件を満たせば65万円差し引いた235万円が課税対象となるため、大きな節税効果が期待できます。
さらに、青色申告をしていれば、赤字を翌年以降の所得と相殺できる「純損失の繰越控除」や、家族に対して給与を支払い経費にできる「専従者給与」などの制度も利用できます。
専従者給与を経費にできるのは青色申告者に限られ、かつ「生計を一にする配偶者や親族」であり「その事業に専ら従事していること」が要件となります。
また、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。青色申告を行うには、原則として事業開始から2ヶ月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
小規模企業共済に加入して将来に備える
小規模企業共済は、個人事業主のための退職金積立制度で、掛金は全額が所得控除となります。毎月7万円(年84万円)まで拠出でき、課税所得を大きく減らせます。廃業や65歳以降の退任時に共済金を受け取れ、退職所得扱いで税制上の優遇もあります。
将来の資金準備をしながら所得控除を得られるため、長期的な視点での節税策として有効です。ただし、途中解約では掛金の一部しか戻らないことがあるため、無理のない金額での積立が前提となります。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)を活用する
経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。掛金は全額を必要経費として計上でき、年間最大240万円の損金算入が可能です。解約手当金は12ヶ月以上の加入で原則8割、40ヶ月以上で全額戻るため、利益圧縮や税の繰延べに活用できます。
共済の本来の目的は連鎖倒産の防止ですが、好調な年の利益を圧縮したい場合などには、節税の一手として有効です。
iDeCoで老後の備えと節税を両立する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除となる年金制度です。フリーランスの場合、月額最大68,000円(年816,000円)まで拠出でき、その分所得税・住民税の軽減効果があります。さらに、運用益も非課税で積み立てられることから、長期的に大きな節税が期待できます。
ただし、原則60歳まで引き出せず、運用リスクや管理手数料もあるため、資金に余裕があり長期運用が前提となる人に適した制度です。
NISAを活用して資産運用を効率化する
NISA(少額投資非課税制度)は、投資による利益や配当に課税されない制度です。新NISAでは非課税期間が無期限となり、年間投資枠も拡大されました。具体的には、積立投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円と設定されており、合計で最大年間360万円を積み立てることができます。投資で得た利益に本来課される20.315%の税金が非課税になるため、資産形成を効率よく進められます。
iDeCoのような所得控除はないものの、いつでも資金を引き出せる点で柔軟性があり、余剰資金を有効活用する手段として活用価値があります。
フリーランスの法人化による節税効果とは
フリーランスとして所得が増えてきた場合、法人化(法人成り)を検討することは、節税の観点から有効な選択肢となります。法人化により税金の仕組みが変わり、さまざまな節税メリットを享受できる可能性があるためです。ここでは、法人化による主な節税ポイントと検討のタイミングについて解説します。
法人化による主な節税メリット
個人事業主は、自分への給与を経費にできませんが、法人化すれば代表者としての役員報酬を法人の経費(損金)にできます。その結果、法人の利益を圧縮でき、法人税の負担を軽減することが可能です。また、家族を役員や従業員にして適正な給与を支払えば、世帯内で所得を分散し、全体の税率を抑えることにもつながります。
さらに、法人税率は中小法人であればおおよそ20~25%で推移し、個人の所得税(最高45%+住民税)より低くなるケースが多くなります。また、赤字の繰越期間も個人では3年ですが、法人では10年と長いため、損失の活用余地も広がります。このほか、退職金制度や法人保険の活用、創業初期2年間の消費税免除(資本金要件あり)なども法人化ならではの利点です。(インボイス制度に対応するため適格請求書発行事業者に登録した場合は、設立初年度から納税義務が生じるため注意が必要です。)
ただし、社会保険の強制加入や設立・維持にかかるコストが発生する点も踏まえ、税金以外の要素も加味したうえで判断する必要があります。
法人化の適切なタイミング
法人化の目安としてよく挙げられるのが「課税所得が800万円を超えた頃」です。このラインを超えると所得税・住民税の合計負担が重くなり、法人化による税率の引き下げ効果が目立ってきます。
ただし、法人化の適否は、売上規模や経費率、家族構成、将来の事業方針などによっても異なるため、一概には決められません。検討する際は、税理士など専門家の助言を得ながら、収支や将来計画をもとに慎重に判断しましょう。法人化は節税だけでなく、経営の仕組みづくりとしても意味のある選択です。
フリーランスの節税制度を正しく活用しよう
フリーランスとして事業を続けていくうえで、税金の仕組みを理解し、適切な節税対策を行うことは欠かせません。必要経費や各種控除、青色申告などの基本的な制度から、小規模企業共済やiDeCo、法人化といった実践的な手段まで、節税の選択肢は多岐にわたります。税制や制度は毎年のように改正されており、情報を正しく把握し、自分に合った対策を選ぶことが、将来の安定した経営と資金繰りに直結します。今後も計画的に節税に取り組んでいきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
会社設立費用と新会社法のメリットとは
平成18年5月1日施行の新会社法により、資本金1円で会社設立ができるようになりました。開業前に準備する資金は以前と比べ、少額になりましたが、1円だけでは会社運用できません。 会社設立に係る費用には、どうのようなものがあるかを確認しながら、改…
詳しくみる会社法とは?基本的な規定や目的をわかりやすく解説!
会社法とは2005年に成立し、2006年に施行された法律で、会社に関するさまざまなルールがまとめられています。会社法とは具体的にどのような法律か、どのような会社が規定されているのか、株式会社についてはどのような規定があるのかなどについて、初…
詳しくみる札幌市で会社設立をお得に!準備をラクにする方法
札幌市での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる年収2000万円の節税策は?会社員・個人事業主別に対策を解説
年収2000万円という高水準の収入があるにもかかわらず、手取り額が期待より少ないと感じている方は少なくありません。 本記事では、会社員・個人事業主それぞれの立場で活用できる節税制度を整理し、合法的かつ効果的に手取りを最大化する方法を解説しま…
詳しくみる会社の実印とは?会社設立に必要なはんこの種類や選び方
会社の実印とは、会社の正式な意思であることを証明する印鑑のことを指します。この印鑑は法務局に登録され、法的な拘束力を持ちます。この記事では、どのような場面で会社実印が必要になるのか、印鑑の登録方法や作成方法、また、会社設立に必要なはんこにつ…
詳しくみる資本金が実際にはないのは違法?すぐに使ってもいい?
会社は設立時に株式を発行し、資本金を用意する必要があります。では、この資本金は戻ってくるお金なのでしょうか。また、すぐ引き出すことができる、使っていいお金なのでしょうか。さらに、資本金が足りない場合、見せ金でいいのかなどの疑問もあるでしょう…
詳しくみる


