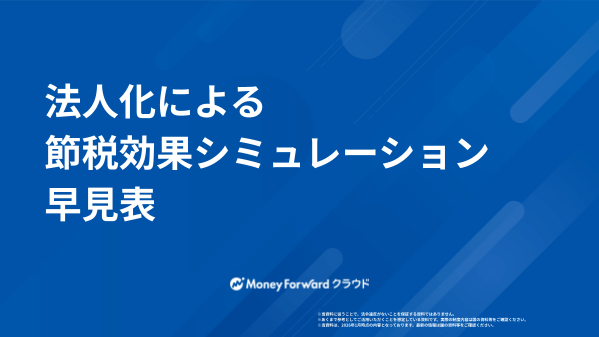- 更新日 : 2026年1月16日
年収いくらから法人化すべき?目安や年収別の節税効果の違いを解説
年収いくらから法人化するべきか悩む場合、課税所得900万円以上が判断基準です。課税所得900万円以上の場合、法人のほうが、個人事業主に比べると節税効果が期待できます。今回は、法人化する目安や年収別の節税効果の違いについて解説します。
目次
年収いくらから法人化すべき?
法人化を判断する課税所得の目安について確認していきましょう。
所得900万円以上で所得税が法人税を超える
所得税と法人税に注目すると、課税所得(収入 – 必要経費 – 所得控除)900万円以上で所得税率が法人税率を超えます。
- 所得税率:33%
- 法人税率:23.20%
所得税率は「超過累進課税」のため、個人事業主は収入増加と比例して税率が上がります。一方、法人税率は「比例課税方式」が採用されており、所得金額にかかわらず一律の税率が適用されます。課税所得900万円以上の場合は、法人のほうが節税効果は高めです。
なお、法人にかかる税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税の5種類です。全体の節税効果を確認し、法人化するのかを総合的に判断する必要があります。
売上1,000万円超で消費税の支払いが発生
インボイス制度の導入前、法人化の目安は課税売上高1,000万円でした。
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額です。1,000万円の課税売上高が法人化の目安になるのは、消費税の支払義務が発生するためです。1,000万円を超えた個人事業主は翌々年から消費税の課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)となり、課税事業者になる前と比べ、支払う税金が増えます。
従来、新規設立法人は免税事業者(消費税の申告や納付を免除される事業者)となり、2年間消費税の支払いが免除されていました。しかし、インボイス発行事業者になると、課税売上高に関係なく、消費税の支払義務を負うことになります。
参考:国税庁 基礎知識
参考:国税庁 インボイス制度について
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
【年収別】法人化による節税効果の違い
個人事業主・法人がそれぞれ負担する所得税・法人税は、以下の計算式で算出できます。
【個人事業主:所得税の計算式】
【法人:法人税の計算式】
法人化による節税効果を年収別に確認していきましょう。
参考:国税庁 No.2260 所得税の税率
参考:国税庁 No.5759 法人税の税率
所得800万円
所得800万円の場合の所得税・法人税は、以下のとおりです。
| 事業形態 | 税額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 800万円 × 23% – 636,000円 = 120万4,000円 |
| 法人 | 800万円 × 15% = 120万円 |
所得800万円の場合、個人事業主のほうが4,000円高いです。
所得1,000万円
所得1,000万円の場合の所得税・法人税は、以下のとおりです。
| 事業形態 | 税額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 1,000万円 × 33% – 1,536,000円 = 176万4,000円 |
| 法人 | (800万円 × 15%) + (200万円 × 23.20%) = 120万円 + 46万4,000円 = 166万4,000円 |
所得1,000万円の場合、個人事業主のほうが10万円高いです。
所得1,500万円
所得が1,500万円の場合の所得税・法人税は、以下のとおりです。
| 事業形態 | 税額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 1,500万円 × 33% – 1,536,000円 = 341万4,000円 |
| 法人 | (800万円 × 15%) + (700万円 × 23.20%) = 120万円 + 162万4,000円 = 282万4,000円 |
所得1,500万円の場合、個人事業主のほうが59万円高いです。
所得2,000万円
所得2,000万円の場合の所得税・法人税は、以下のとおりです。
| 事業形態 | 税額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 2,000万円 × 40% – 2,796,000円 = 520万4,000円 |
| 法人 | (800万円 × 15%) + (1,200万円 × 23.20%) = 120万円 + 278万4,000円 = 398万4,000円 |
所得2,000万円の場合、個人事業主のほうが122万円高いです。
事業計画書・創業計画書の作成には、テンプレートや作成例を活用すると便利です。
マネーフォワード クラウド会社設立に無料登録された方に、業界別の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例をプレゼントしています。140種類以上の中から、自由にダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。

法人化による節税のメリット
法人化による節税のメリットについて解説します。
役員報酬を経費として計上できる
法人化することで役員報酬を損金算入できます。
役員報酬とは、取締役や監査役等の役員に支払われる報酬です。個人事業主は事業主に給与を支払う事業形態ではありませんが、法人を設立すると会社と個人の資産は完全に分けて扱われるため、経営者は給与とは別に役員報酬を受け取れます。
役員報酬を損金算入できれば課税対象の所得が少なくなるため、法人税の税負担を軽減できます。ただし、役員報酬を経費として計上するには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかの要件を満たすことが必要です。
| 給与制度 | 概要 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 定期同額給与は、原則、事業年度を通じて毎月同額を支給する制度です。 |
| 事前確定届出給与 | 所定の時期に決められた金額を支払うことを定め、事前に税務署に届け出して支給する制度です。 |
| 業績連動給与 | 会社またはその会社と支配関係にある会社の業績に、役員の給与額を連動させる制度です。 |
参考:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
福利厚生費や退職金も経費になる
福利厚生費や退職金など経費として損金算入できる項目が増えるため、課税所得が少なくなり、法人税の税負担を軽減できるメリットがあります。
法人にのみ損金算入が認められている項目には、以下のようなものがあります。
退職金の損金算入時期は、株主総会の決議等で退職金額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則です。なお、退職金を実際に支払った事業年度に損金経理をした場合も損金算入が認められています。福利厚生の場合は、購入日等から1年以内に職場で提供されていれば、短期前払費用の取扱いとして損金算入することが可能です。
参考:国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期
参考:国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
参考:国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定
参考:国税庁 No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
参考:国税庁 短期前払費用の取扱いについて
給与所得控除が適用できる
給与所得控除を適用して課税所得を抑えると、経営者個人の所得税を所得控除できます。
給与所得控除とは、個人の所得を計算する際に給与収入額に応じて差し引ける控除です。給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて変わります。
【令和2年分以降】
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額 × 40% – 100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与所得控除は、給与収入にしか適用されません。
個人事業主は事業売上から必要経費を差し引いた課税所得に所得税がかかりますが、法人は経営者個人の所得である役員報酬に適用されます。法人化して役員報酬を支払うと、給与所得控除額の分だけ所得を減らせるため節税効果が期待できます。
家族への役員報酬で所得を分散できる
法人化すると経営者の役員報酬だけでなく、その家族の給与も経費計上できます。
家族の収入次第では、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が利用可能です。各控除を利用するには、以下の適用要件を満たす必要があります。
- 配偶者控除:配偶者の年間合計所得が48万円以下
- 配偶者特別控除:配偶者の年間合計所得が48万円を超える場合
- 扶養控除:年間の合計所得金額が48万円以下
控除の分だけ課税所得金額を抑えられるため、所得税の節税効果が期待できます。個人事業主は、配偶者・配偶者特別・扶養控除が適用されません。
参考:国税庁 No.1180 扶養控除
参考:国税庁 No.1191 配偶者控除
参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除
赤字を最大10年間繰り越せる
個人事業主の赤字の繰り越し期間は3年間ですが、法人化することで損失を最大10年繰り越せます。
損失を繰り越すとは、翌期の利益から損失を相殺することです。翌期以降に高い利益が出た場合、損失を相殺することで課税所得を減らすことが可能です。法人税の税額は課税所得から算出されるため、支払う納税額を低く抑えられます。
翌期以降に赤字が出た場合は損失を相殺できないため、節税効果は得られません。
法人化による節税のデメリット
ここからは、個人事業主が法人化するデメリットについて解説します。
赤字でも法人住民税がかかる
法人化すると赤字でも法人住民税が発生します。
法人住民税とは、法人が事業所を置く地方自治体に納める地方税です。赤字でも法人住民税がかかるのは、法人住民税が法人税割・均等割の税割で構成されているためです。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| 法人税割 | 法人税の金額で変動するもので、赤字の場合は全額免除されます。等しく税額を課す均等割と異なり、利益が高い法人ほど税額が高いです。 |
| 均等割 | 法人税の金額で変動しない金額が固定されており、必ず支払わなければいけません。均等割は、赤字に関係なく税金が発生してしまいます。 |
なお、均等割は資本金や従業員数をもとに、地域ごとに定められています。
参考:総務省 法人住民税
社会保険料を納める義務がある
法人化した場合、従業員数にかかわらず、事業者は社会保険に加入する義務があります。
社会保険とは、厚生年金保険・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など公的保険の総称です。各保険によって会社の負担割合は異なります。
- 厚生年金保険(会社と従業員で折半して負担する)
- 健康保険(会社と従業員で折半して負担する)
- 介護保険(会社と従業員で折半して負担する)
- 労災保険(会社が全額負担する)
- 雇用保険(業種によって異なる)
年収いくらにかかわらず個人から法人化する目安
個人事業主から法人化するメリットが多いケースについて確認していきましょう。
家族を従業員として雇う場合
法人化して家族に役員報酬を支払うと、所得が分散して経営者の所得税を節税できます。
家族経営の場合、法人化すれば家族に役員報酬を支給することが可能です。役員報酬には所得税が課税されますので、経営者一人にまとめて支払うと所得税の税率が上がります。家族に分散して一人ひとりの所得を下げることで所得税を抑えられます。
法人や大口案件を受注したいとき
仕事の依頼を法人に限定している企業は多いようです。
法人化には、基本的な情報が一般公開される商業登記が必要です。商業登記は登録した法人の概要を公示する制度で、会社の信用維持や取引の安全を確保する目的があります。法人は取引上の信頼性を担保できるため、依頼先として好まれます。
法人や大口案件を通してビジネスを展開したい場合は、法人化を検討しましょう。
事業成長に必要な資金調達を受けたいとき
法人化すると、資金調達方法の選択肢を増やせます。
出資を募れるのは個人事業主も同じですが、金融機関等の融資を受けたい場合、信用が高い法人のほうが審査は通りやすいです。ただし、融資は返済義務が生じるため、決められた期間内に借りた金額に対して元本と利息を返済しなければいけません。
事業承継や相続を円滑に進めたいとき
相続した財産に課される相続税は、資産額によっては税率が非常に高くなります。
個人間で直接相続しても、半分程度の資産しか渡せない場合があります。相続の対象となる資産を法人化すれば、資産の評価額を下げることが可能です。また、資産を資産管理会社に移し、法人株式に変えることで資産を分割しやすくなるのも利点です。
個人から法人化する流れや手続き
会社設立の流れ・手順は、以下のとおりです。
- 会社概要の決定
- 会社用の実印作成【任意】
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 会社設立登記
商業登記には会社の実印が必要でしたが、2021年に商業登記規則が改正されて、オンラインで登記申請した場合は印鑑届書の提出が任意になりました。
なお、会社設立後に必要な手続きには、会社の口座開設や法人設立届出書の提出等があります。従業員を雇う場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出が必要です。
法人設立の流れや手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事で確認してください。
法人化に役立つひな形・テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、法人化や法人登記に役立つひな形・テンプレートを無料提供しています。下記リンクからダウンロードできるため、業務を効率化したいなら、自社に合わせてカスタマイズしながら活用してみてはいかがでしょうか。
事業計画書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
法人化のデータから見る年収判断のポイント
年収による法人化の判断を検討する際、実際に法人化を選択した事業者の傾向を知ることは重要な参考情報となります。
個人事業主から法人成りを選択する事業者の増加傾向
マネーフォワード クラウドが実施した調査によると、会社設立者1,040名のうち57.8%が個人事業主として事業を行った後に法人成りしていることが明らかになりました。特に注目すべきは、設立1年以内の企業では68.5%、設立2~3年以内の企業では実に75.2%が個人事業主からの法人成りという結果です。
この傾向は、多くの事業者が個人事業主として事業基盤を固め、年収が一定水準に達した段階で法人化を選択していることを示しています。課税所得900万円という節税効果の分岐点を意識しながら、事業の成長に合わせて計画的に法人化を進める事業者が増加していると考えられます。
法人化のタイミングと年収の関係性
近年設立された企業ほど個人事業主からの法人成りの割合が高いという調査結果は、税制やインボイス制度などの制度変更に対応しながら、最適なタイミングで法人化を選択する事業者が増えていることを示唆しています。
年収による節税効果だけでなく、取引先との関係性、資金調達の必要性、事業承継の計画なども総合的に判断することが重要です。個人事業主として着実に事業を成長させ、年収が課税所得900万円に近づいた段階で、法人化のメリット・デメリットを慎重に検討し、適切なタイミングで法人成りを実行することが、多くの成功事例から見えてくる法人化の成功パターンといえるでしょう。
出典:マネーフォワード クラウド、先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】(回答者:会社設立の経験がある方1,040名、集計期間:2024年1月)
年収いくらから法人化するべきかは課税所得900万円以上が目安
個人事業主が法人化するタイミングは、課税所得900万円以上がひとつの目安です。
法人化することで、役員報酬を損金算入できたり給与所得控除が適用されたりなど多くのメリットがあります。一方で、すべての法人は社会保険への加入が義務付けられているうえに、赤字でも法人住民税が発生するなどの懸念点があるのも事実です。
全体の節税効果を確認し、法人化するのかを総合的に判断することが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
サラリーマンは会社設立で節税できる?合同会社がおすすめの理由やばれるリスクも解説
毎月の給与から天引きされる税金を見て、「もっと手取りを増やせないか」と感じているサラリーマンの方は多いのではないでしょうか。iDeCoやNISA、ふるさと納税といった節税対策の効果…
詳しくみる芸能人の法人化とは?個人事務所設立のメリット・デメリットや流れを解説
芸能人の中には売れっ子になったタイミングなどで、これまでお世話になった芸能事務所から独立して個人事務所または会社を立ち上げる方もいらっしゃいます。 本記事では、芸能人が個人事務所・…
詳しくみるバンドは法人化すべき?メリット・注意点、方法を解説
バンドを組んでいる活動中のミュージシャンの多くは、個人事業主として活動されていることでしょう。仕事がコンスタントに入り、安定した収入を得られるようになったタイミングで法人化を検討し…
詳しくみる海外FXで法人化は可能?法人口座の作り方やメリット・デメリットを紹介
FXで利益を安定的に得られるようになると、法人化を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、海外FXの場合、果たして法人化はできるのでしょうか。 この記事では海外FXで…
詳しくみる法人登記はどこでする?管轄法務局の調べ方、移転や複数登記する場合を解説
法人登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局またはその出張所などで行います。そのため、どの法務局へ申請するかは、会社の住所によって一律に決まります。企業の担当者にとって、会社設立準…
詳しくみる古物商の法人化で許可はどうなる?必要な手続きと注意点を解説
古物商を個人から法人化する場合、個人で取得した古物商許可をそのまま引き継ぐことはできません。個人と法人は法律上別人格として扱われるため、法人として新たに古物商許可を取得する必要があ…
詳しくみる