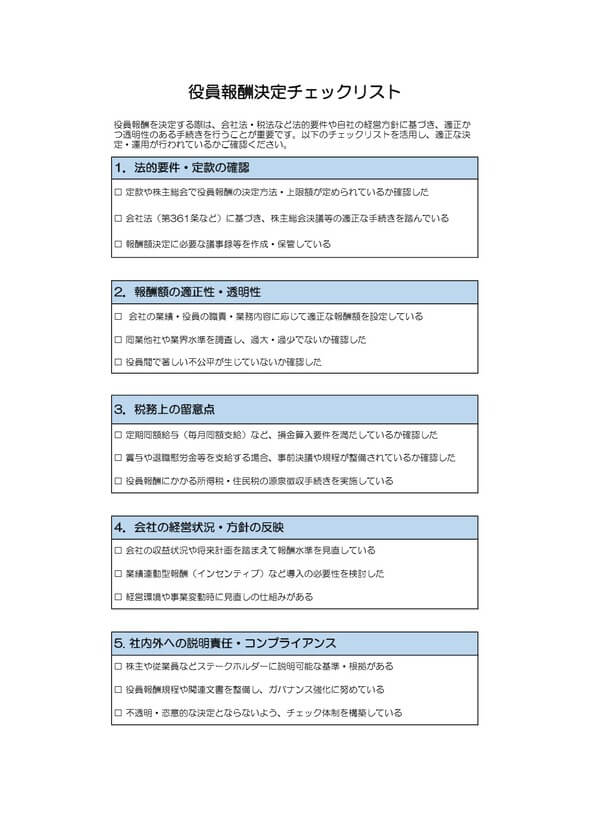- 作成日 : 2025年10月21日
一人会社の役員報酬(給料)はどう決める?ルールや節税効果を解説
一人会社の役員報酬は、会社の資金繰りと節税を左右する重要な決定です。金額や支払い方を間違えると、年間で数十万円損をすることもあります。相場がわからず、事業計画を立てにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、最適な役員報酬の決め方を、初めての方でも理解できるように順を追って解説します。計画的な資金準備のために、ぜひご活用ください。
目次
一人会社の役員報酬とは?給与との違い
一人会社の社長が自分に支払うお金が「役員報酬」です。これは、従業員に支払う「給与」とは性質が異なり、税務上のルールも大きく異なります。この違いを正しく理解することが、節税や適切な会社経営の基本となるでしょう。
役員報酬と給与の違い
役員報酬と従業員の給与の大きな違いは、経費(損金)として認められるためのルールの有無です。役員報酬は国が定めた税法上のルールを守らないと損金にできませんが、従業員の給与は原則として損金算入です。
両者の詳しい違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 役員報酬 | 従業員の給与 |
|---|---|---|
| 対象者 | 会社の役員(取締役など) | 会社の従業員 |
| 性質 | 経営委任契約に基づく報酬 | 雇用契約に基づく労働の対価 |
| 経費のルール | 一定のルール内でのみ経費になる | 原則として全額が経費になる |
| 変更の自由度 | 原則、年に一度しか変更できない | 雇用契約や労使協定に基づき随時変更できる |
役員報酬は従業員の給与と比べて、経費として扱うための制約が多いのが特徴です。
役員報酬はなぜ年に一度しか変えられない?
役員報酬が事業年度の途中で自由に変更できないのは、利益操作を防ぐためです。もし、期末の利益を見てから役員報酬を自由に決められると、多くの会社が利益をゼロにするために報酬額を調整し、法人税を不当に免れようとするおそれがあります。
そうした事態を避けるため、役員報酬は「事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その期中は原則として金額を変更してはならない」というルールが設けられています。これは、実質的に役員報酬の年額を期首に確定させるための決まりであり、これにより税の公平性が保たれているといえるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
一人会社の役員報酬が経費になる主な給与形態
役員報酬を経費として認めてもらうには、主に3つの「給与形態」があります。支払い方の種類と考えるとわかりやすいかもしれません。ただし、一人社長が実際に使うのは、このうちの「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の1つか2つに限られます。ご自身の会社に合った方法を選べるよう、それぞれの特徴をみていきましょう。
① 定期同額給与:毎月定額を支払う
定期同額給与は、毎月一定額を役員報酬として支払う方法です。事業年度の開始から3ヶ月以内に金額を決定し、その事業年度中は毎月同額を支給し続ける必要があります。
一度決めたら、原則としてその事業年度中は金額を変更できません。これにより、会社の資金計画が立てやすくなるという側面もあります。
出典:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
② 事前確定届出給与:賞与(ボーナス)を支払う
毎月の役員報酬とは別に、ボーナス(賞与)を出したい場合に使う給与形態です。
利益が出たときなどに臨時の報酬を受け取るために使われますが、届け出た通りの日付・金額で支払う必要があります。「いつ、誰に、いくら支払うか」を事前に計画し、株主総会などで決議したうえで、税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければなりません。1円でも、1日でもズレると経費として認められないため、計画的な利用が求められるでしょう。
③ 業績連動給与:業績に応じて支払う
会社の利益など、業績に応じて報酬額が変わる方法です。
これは主に上場企業など、客観的な業績指標を算定できる大企業向けの制度です。適用には厳しい条件があり、とくに「同族会社(特定の株主グループで株式の50%超を保有する会社)でないこと」が要件の一つです。一人社長の会社は、基本的にこの同族会社に該当するため、業績連動給与は利用できないと考えてよいでしょう。「こういう制度もある」と参考程度に知っておいてください。
一人会社の役員報酬の決め方4ステップ
最適な役員報酬額を導き出すための、詳しい手順を4つのステップで解説します。この流れに沿って進めることで、税金や社会保険料のバランスがとれた、適切な金額を設定しやすくなるのではないでしょうか。
会社の利益を予測する
役員報酬は会社の利益から支払われるため、自社の利益が年間でどれくらいになるかを予測します。
年間の売上高を見積もり、そこから売上原価、事務所の家賃、水道光熱費、通信費、広告宣伝費など、役員報酬以外の経費を差し引いて、最終的に残る利益額を算出します。
設立初年度で予測が難しい場合でも、事業計画に基づいた現実的な数字を立てることが大切です。
社長個人の必要額を出す
次に、社長個人が生活していくために、最低限必要な手取り額を計算します。
個人の家賃、水道光熱費、食費、通信費、保険料、貯蓄したい額などを合計し、1年間に必要な生活費を明確にしましょう。この金額が、役員報酬額を決めるうえでの下限の目安となります。この金額を大きく下回る報酬設定は、個人の生活を不安定にさせるため、原則避けるべきです。
社会保険料を把握する
役員報酬を設定するうえで、税金と同じくらい大きな負担となるのが社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)です。
社会保険料は、報酬額から算出される「標準報酬月額」に基づいて決定され、会社と個人がそれぞれ約半分ずつを負担します。報酬額が高くなればなるほど、会社と個人の双方の負担額が増えていきます。とくに設立したばかりの会社にとっては、この会社負担分が資金繰りに影響を与えることも少なくありません。報酬額を決める際は、社会保険料の負担額がいくらになるのかを必ず確認しましょう。
税金のバランス点を探す
最後に、法人税と、個人にかかる所得税・住民税のバランスを考えます。
役員報酬を高く設定すると、会社の利益が減るため法人税は安くなりますが、個人の所得税・住民税は高くなります。逆に、役員報酬を低くすると、個人の税負担は減りますが、会社の利益が増えるため法人税が高くなる傾向にあります。
この両者のバランスをとり、「会社が支払う法人税・社会保険料」と「個人が支払う所得税・住民税・社会保険料」の合計額が最も少なくなる点が、会社と個人を合わせた手残りを最大化するポイントといえるでしょう。
【年収別】一人会社の最適な役員報酬シミュレーション
役員報酬をいくらに設定すれば、会社と個人に一番お金が残るのでしょうか。ここでは、具体的なモデルケースで、手取り額を比較してみましょう。税金や社会保険料は人によって異なるため、あくまでも概算の参考値としてご覧ください。
シミュレーションの前提条件
シミュレーションは、以下の条件でおこないます。
比較表:役員報酬と手残り額
役員報酬や税金の計画は年単位でおこなうのが一般的なため、以下の表はすべて年額で記載しています。役員報酬額を3パターン設定した場合の、会社と個人の手残り合計額を比較します。
| 役員報酬額(年額) | 会社の手残り利益 | 個人の手取り額 | 会社+個人の手残り合計額 |
|---|---|---|---|
| 360万円(月30万円) | 約287万円 | 約282万円 | 約569万円 |
| 480万円(月40万円) | 約181万円 | 約371万円 | 約552万円 |
| 600万円(月50万円) | 約70万円 | 約452万円 | 約522万円 |
※上記は概算値につき実際の金額とは異なります。
最適解の考え方
上記の表を見ると、このモデルケースでは、役員報酬を年額360万円に設定した場合に、会社と個人の手残り合計額が最も多くなりました。
役員報酬を高くしていくと、社会保険料の負担が増えるため、合計の手残り額が減っていくのがわかります。役員報酬600万円のケースは、個人の手取りは増えますが、会社と個人全体で見ると約47万円も手残りが減ってしまいました。
もちろん、これはあくまで一つの例です。会社の利益水準や社長個人の状況によって最適解は変わります。大切なのは、ご自身の状況に合わせて、税金と社会保険料の総額がどう変化するのかをシミュレーションしてみることではないでしょうか。
一人会社の役員報酬設定の注意点とリスク
役員報酬の設定で失敗しないために、よくある注意点とリスクをまとめました。高すぎる・低すぎる場合の問題点も解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、適切な金額設定の参考にしてください。
高すぎる場合の問題点
役員報酬を高く設定しすぎると、社会保険料と個人の税金の負担が重くなり、結果として会社と個人の手残りが減ることがあります。
また、会社の利益に見合わない高額な報酬は、会社の資金繰りを圧迫する原因にもなりかねません。とくに、売上が不安定な時期に報酬を高く設定すると、赤字に陥るリスクも高まるでしょう。金融機関から融資を受ける際に、利益を圧迫するほどの役員報酬がマイナス評価につながることも考えられます。
低すぎる場合の問題点
一方で、役員報酬を低く設定しすぎることにも問題点があります。まず、社長個人の生活が不安定になるかもしれません。
また、会社の利益が多く残るため、法人税の負担が重くなります。利益をすべて設備投資や内部留保に回せるならよいですが、そうでない場合は、役員報酬として個人に移転したほうが、税率の違いから結果的に手残りが多くなるケースも少なくありません。個人の所得税は累進課税のため、税率のバランスを見ることが大切です。
役員報酬ゼロは可能か?
役員報酬をゼロに設定すること自体は、法律上可能です。設立直後で利益が見込めない場合や、他に収入がある場合などに選択されることがあります。
報酬ゼロのメリットは、社会保険料の負担がなくなることです。ただし、デメリットもあります。社会保険に加入できないため、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければなりません。また、法人に利益を残しても法人税は課税されるため、必ずしも節税になるわけではありません。さらに、金融機関からの融資審査・企業格付においては、役員報酬ゼロが代表者の返済能力への懸念と見なされる可能性も否定できないでしょう。
一人会社の役員報酬の見直しタイミング
会社の状況は年々変わります。一度決めた役員報酬を、いつ、どのように見直すべきか、会社の成長に合わせた考え方を解説します。役員報酬は、会社の成長を映す鏡のようなものであり、戦略的に見直していくべきものではないでしょうか。
報酬を変更できる期間
役員報酬の金額を変更できるのは、原則として「事業年度の開始から3ヶ月以内」です。この期間内に株主総会などで決議し、変更後の金額をその事業年度の終了まで毎月定額で支払い続けます。
この期間を過ぎてから金額を増減させると、変更した部分の金額は経費として認められないため、注意が必要です。たとえば、期中に増額した場合、増額した部分の金額は損金不算入となります。
利益が出た時の選択肢
事業が軌道に乗り、利益が安定して増えてきたら、役員報酬の増額を検討する良いタイミングでしょう。翌期の利益計画を立てたうえで、事業年度開始から3ヶ月以内に、適切な金額まで引き上げます。
ただし、利益をすべて役員報酬に回すのが最善とは限りません。将来の事業拡大や金融機関からの信用力強化のために、内部留保(利益剰余金)として会社に残すという選択肢もあります。会社の成長ステージや将来のビジョンをふまえて、報酬と内部留保のバランスを考えることが求められます。
役員報酬の変更に必要な手続き
役員報酬の金額を決定・変更するには、株主総会での決議が必要です。一人会社の場合、株主は社長自身なので、形式的な手続きのように思えるかもしれません。
しかし、税務調査などで決定の根拠を問われた際に、きちんと手続きを踏んでいることを証明するために、「株主総会議事録」を作成し、保管しておくことが大切です。議事録には、いつ、誰が、いくらの報酬を、いつから支払うことを決議したのかを明確に記載しましょう。
役員報酬は「会社+個人」の手残りで決める
役員報酬で最も重要なのは、税金や社会保険料を考慮し、「会社と個人、双方の手元に残るお金が最大になる点」を見つけることです。個人の手取りだけ、あるいは会社の利益だけに着目して決めるのではなく、全体最適の視点が欠かせません。役員報酬の決定は、年に一度の重要な経営判断といえます。本記事のステップとシミュレーションを参考に、あなたの会社にとって最適な報酬額を慎重に設定してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
古物商の法人化で許可はどうなる?必要な手続きと注意点を解説
古物商を個人から法人化する場合、個人で取得した古物商許可をそのまま引き継ぐことはできません。個人と法人は法律上別人格として扱われるため、法人として新たに古物商許可を取得する必要があ…
詳しくみる法人化で従業員はどうなる?メリット・デメリットや手続き、タイミングの目安など解説
個人事業主として事業を拡大されてきた方、あるいはその事業を支える従業員の方にとって、法人化は大きな転換期です。特に従業員を雇用している場合、その影響は多岐にわたり、事前にしっかりと…
詳しくみるピアノ教室の経営は法人化すべき?メリット・デメリットや方法を解説
ピアノ教室の法人化とは、個人事業主として運営しているピアノ教室を株式会社などの法人組織に移行することです。法人化のメリットとして、事業規模の拡大や社会的信用の向上、税務関連などがあ…
詳しくみる芸能人の法人化とは?個人事務所設立のメリット・デメリットや流れを解説
芸能人の中には売れっ子になったタイミングなどで、これまでお世話になった芸能事務所から独立して個人事務所または会社を立ち上げる方もいらっしゃいます。 本記事では、芸能人が個人事務所・…
詳しくみる【テンプレ付】役員の住所変更の法人ガイド!自分で行う手続きや費用まとめ
会社の代表権を持つ役員の住所が変更された場合は、変更の生じた日から2週間以内に、変更の日から2週間以内に法務局で法人登記の変更申請を行う必要があります。特に、代表取締役(株式会社)…
詳しくみる法人化や法人登記にはいくらかかる?会社形態別の費用を解説
会社を設立して法人化するには、株式会社で約20万~25万円、合同会社なら約6万~10万円の費用がかかります。これらの金額は、ご自身で手続きを進める場合に必要となる法定費用の目安であ…
詳しくみる