- 作成日 : 2025年9月16日
企業型確定拠出年金は節税にならない?節税効果や注意点を解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、老後資金を積み立てながら所得税や住民税、社会保険料の負担を軽減できる制度として注目されています。一方で、「節税にならない」と感じる人がいるのも事実で、背景には制度上の誤解や運用・受取の選択に関する課題があります。本記事では、企業型DCの正しい理解と節税につなげる活用法を解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
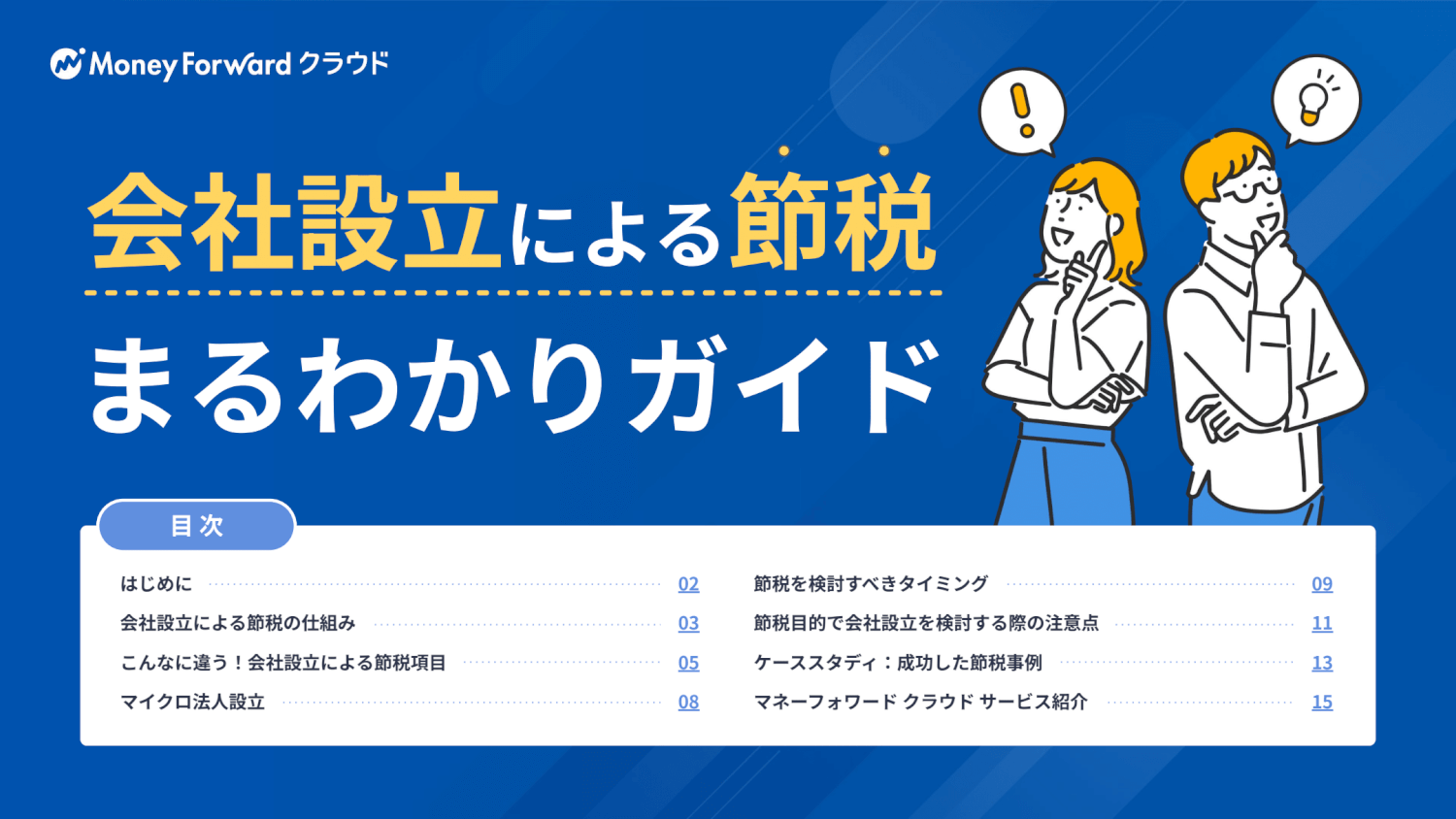
目次
企業型確定拠出年金の基本
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が従業員の老後資金づくりを支援するために導入できる年金制度です。ここでは概要を解説します。
拠出は企業または従業員の給与から
企業型DCでは、企業が毎月一定の掛金を従業員の専用年金口座に拠出します。また、企業の規約次第で、従業員が自らも掛金を上乗せできる「マッチング拠出」や、給与の一部を拠出する「選択制DC」などの仕組みも採用可能です。掛金は全額非課税で積み立てられ、所得税や住民税がかかりません。
運用は従業員の自己責任で行う
拠出された資金は、定期預金や投資信託、保険商品などの運用商品から従業員が自ら選んで運用します。運用益は非課税で再投資されるため、長期的な資産形成に有利ですが、運用成果次第では元本割れのリスクも伴います。
受け取りは60歳以降に開始
積み立てた資産は、原則として60歳以降に「一時金」または「年金」の形式で受け取ることができます。受取時には退職所得控除や公的年金等控除の対象となり、税負担が軽減される仕組みになっています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
企業型確定拠出年金は節税にならないと言われる理由
企業型確定拠出年金(企業型DC)は税制上の優遇がある制度ですが、人によってはその恩恵を実感できないケースがあります。「節税にならない」と言われる背景には、制度の仕組みと利用者側の状況が関係しています。ここでは代表的な理由を解説します。
運用益が少ないと節税メリットを実感しにくい
企業型DCでは、積立金の運用によって得られた利益が非課税になるという大きなメリットがあります。しかし、実際の運用益がほとんど出ていない場合、この非課税の恩恵はわずかになります。たとえば、定期預金や元本確保型商品での運用を選択していると利回りは低く、20.315%課税されるはずの利益額そのものが小さくなります。その結果、運用益に対する非課税メリットが薄く感じられ、「節税になっていない」と思われがちです。
もともとの税負担が小さいと効果が限定的
企業型DCの掛金は、給与からの拠出により課税対象の所得を圧縮することで所得税と住民税を減らす仕組みですが、もともとの課税所得が低い場合はその効果が目立ちません。たとえば、扶養控除や配偶者控除が適用されている人、非課税枠内の収入の人にとっては、企業型DCによる控除で減税される金額がもともと少なくなります。このため、DCを利用していても「節税できていない」と感じることがあるのです。
受け取り方によっては税優遇を活かしきれない
企業型DCは60歳以降に年金や一時金として受け取りますが、受け取り方によって税負担が変わるため、選択次第で節税効果が損なわれることがあります。
一括で受け取る一時金は退職所得となりますが、会社の退職金など他の退職所得と同じ年に受け取る場合、税金の計算に注意が必要です。退職所得控除額は、それぞれの勤続年数を通算して調整計算されるため、別々に受け取るよりも控除額が減り、結果的に課税対象額が増える可能性があります。
また、年金形式で受け取ると雑所得扱いとなり、他の年金と合算されて課税され、控除枠を超えると結果的に税負担が増すこともあります。誤ったタイミングや形式で受け取ると、制度本来の優遇を活かしきれず、期待した節税効果を得られない原因となります。
実は大きい!企業型確定拠出年金の節税メリット
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、節税効果が実感しづらいとされる場面もある一方で、制度としては優れた税制優遇を備えています。ここでは企業型DCがどのように節税に役立つのか整理します。
掛金が所得控除となり所得税・住民税が軽減される
企業型DCでは、企業が拠出した掛金は給与とみなされず、従業員の課税所得に含まれません。そのため、拠出額に対して所得税や住民税が一切課税されず、掛金分が丸ごと非課税となります。たとえば、課税所得500万円の人が年間24万円をDCに拠出した場合、所得税・住民税で約7万2千円が軽減されます。高所得者ほど適用される税率が高くなるため、節税効果はさらに大きくなります。また、企業側も拠出した金額を全額損金算入できるため、法人税の負担を減らすことができます。さらに、拠出額が社会保険料の対象から外れることにより、企業・従業員ともに保険料負担を軽減できる点も大きな特徴です。
運用益が非課税で再投資できる
企業型DCで積み立てた資金の運用中に得られる利息や投資信託の利益は、全額非課税で再投資されます。通常の金融商品であれば約20%の税金がかかる運用益も、確定拠出年金口座内では課税されません。この非課税効果は、長期運用において非常に大きく、特に複利運用によって資産が拡大するほど本来かかるはずだった税金分も含めて再投資できるという大きなメリットがあります。なお、理論上は年1.173%の特別法人税が存在しますが、1999年以降凍結されており、現在は実質的に運用益に税負担はありません。
受け取り時にも税制上の優遇がある
企業型DCの受け取りは60歳以降で、「一時金」または「年金」の形式を選ぶことができます。一時金で受け取る場合は退職所得扱いとなり、勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、控除額を超える部分も1/2課税という優遇が受けられます。年金で受け取る場合は雑所得扱いになりますが、公的年金等控除が適用されるため、一定額までは非課税になります。また、これらを併用して一部を一時金、残りを年金で受け取ることも可能で、双方の控除制度を組み合わせて税負担を分散することもできます。最適な受け取り方法を選ぶことで、引退後の税負担を抑えることが可能です。
社会保険料の負担も軽減できる
企業型DCの掛金は給与に含まれないため、健康保険料や厚生年金保険料の算定対象から外れます。たとえば、給与のうち毎月2万円をDC拠出に振り分けた場合、その分標準報酬月額が下がり、保険料負担が軽減されます。企業にとっても、給与として支給しないぶん会社負担の社会保険料が減少し、実質的な人件費の抑制にもつながります。この仕組みは在職中の可処分所得を増やす効果を持ちつつも、将来の年金受給額に影響するため、バランスを見ながら拠出を考える必要があります。
企業型確定拠出年金の注意点
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、節税効果が高い制度である一方、利用にあたってはいくつかの制約や注意点もあります。以下に主な注意点を解説します。
60歳まで原則引き出せない
企業型DCの積立金は、原則として60歳まで引き出すことができません。住宅購入や教育費など急な出費に対しても対応できないため、資金の流動性が低いという欠点があります。老後資金のための制度であることを踏まえ、無理のない範囲で拠出額を設定することが重要です。
運用リスクを加入者自身が負う
企業型DCでは、資産の運用を加入者が自ら行う必要があります。運用次第で将来の受取額が大きく変わる一方、元本割れのリスクも伴います。商品選びによっては利回りが期待できる一方で、安定性に欠ける可能性もあるため、金融リテラシーが求められます。
将来の年金額が減る可能性がある
企業型DCの掛金は給与とみなされず、社会保険料の計算対象から除外されます。そのため、給与の一部をDCに振り分けた場合、標準報酬月額が下がり、将来受け取る厚生年金がわずかに減る可能性があります。短期的な保険料削減と、長期的な年金額のバランスを考慮する必要があります。
他制度との併用に制限がある
企業型DCに加入していると、iDeCoなど他の確定拠出年金制度の利用に制限がかかることがあります。たとえば、iDeCoの掛金上限額が引き下げられたり、勤務先の規定によりiDeCoへの加入が制限されている場合もあります。併用を検討する際は、勤務先の制度内容や最新の法改正情報を確認することが不可欠です。
法人化した個人事業主が企業型確定拠出年金と併用できる節税方法
個人事業主は企業型確定拠出年金には加入できませんが、法人化すれば自社で制度を導入し、活用できるようになります。そのうえで、他の制度と併用することでさらに節税の幅が広がります。ここでは、企業型DCを導入した個人事業主が活用できる節税方法を紹介します。
iDeCoとの併用でさらなる控除を得る
法人化して企業型DCを導入した場合でも、一定の条件を満たせばiDeCo(個人型確定拠出年金)と併用することが可能です。確定給付企業年金(DB)など他の企業年金制度がない企業の場合、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金を合わせた拠出上限は、月額5万5,000円となります。
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となり、企業型DCと組み合わせることで、税負担をより効果的に軽減できます。ただし、企業規約の整備や、事業主証明書の提出が必要になるため、併用の際は制度運営と手続きに注意が必要です。
小規模企業共済で将来の退職金も準備
法人化後も中小企業の役員として「小規模企業共済」に加入することができます。これは退職金の積立制度で、掛金は月1,000円から7万円まで設定でき、全額が所得控除の対象となります。企業型DCと異なり、掛金は固定で運用リスクが少なく、受け取り時は退職所得として扱われるため、税制面でも優遇されています。企業型DCとは異なる性質の制度として併用することで、老後資金の分散や税負担の平準化に役立ちます。
中小企業退職金共済(中退共)の導入も検討する
従業員を雇用している法人であれば、中小企業退職金共済(中退共)の導入も有力な方法です。事業主が拠出した掛金は全額が損金算入でき、従業員に対する福利厚生としての側面もあります。
なお、中退共は従業員のための退職金制度であり、原則として経営者や役員自身は加入できません。あくまで従業員の福利厚生と、法人としての損金算入による節税の選択肢です。
経費として処理しながら、従業員の定着にもつながるため、企業型DCと併用すれば企業全体の節税と将来設計に貢献できます。
会社員が企業型確定拠出年金と併用できる節税方法
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している会社員でも、制度の条件に応じて他の節税制度を併用することが可能です。ここでは、企業型DCと組み合わせて活用できる節税手段を紹介し、会社員がより効率的に税負担を軽減する方法を解説します。
iDeCoとの併用で所得控除を拡充する
企業型DC加入者でも、企業の制度が併用を認めていればiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することができます。企業型DC加入者がiDeCoを併用する場合、iDeCoの掛金上限額は、勤務先の他の企業年金の加入状況によって異なります。企業型DCのみに加入している場合は月額2万円、企業型DCに加えて確定給付企業年金(DB)などにも加入している場合は月額1.2万円が上限となります。
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、企業型DCと合わせて活用することで控除額を増やすことができ、節税効果が拡大します。ただし、併用の可否は企業ごとの規約に依存するため、加入前に確認が必要です。
ふるさと納税で住民税・所得税の負担を軽減する
ふるさと納税は、会社員でも手軽に実践できる節税制度のひとつです。実質2,000円の自己負担で、寄付額の大部分が所得税と住民税から控除されます。企業型DCとは独立した制度であり、併用に制限はありません。ワンストップ特例制度を活用すれば、確定申告を行わずに控除を受けることも可能です。収入が高いほど控除上限額も上がるため、企業型DCと組み合わせれば、より大きな節税効果が期待できます。
生命保険料控除など他の所得控除も活用する
企業型DCによる節税に加えて、生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除などの各種所得控除も併用可能です。これらの制度はそれぞれ控除枠が決まっており、企業型DCと競合しないため同時に利用することができます。年末調整や確定申告の際に適切に申告することで、所得税や住民税の負担をさらに軽減することができます。
企業型確定拠出年金のメリット・デメリットを踏まえて賢く活用しよう
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、拠出・運用・受取の各段階で税制優遇を受けられる有利な制度です。個人・企業ともに所得税・住民税・法人税・社会保険料の負担を軽減でき、長期的な資産形成にもつながります。一方で、原則60歳まで引き出せない資金拘束、運用リスク、他制度との併用制限など注意点もあります。自分に合った拠出額や受取方法、他の控除制度との併用を計画的に行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
会社設立の相談は法務局ですべき?無料相談の範囲、予約から当日の流れなどを解説
会社を設立しようと決めたとき、多くの人が最初に直面するのが手続きに関する疑問です。その解決策として、登記を管轄する法務局の無料相談があります。 この記事では、法務局の登記相談窓口で何ができて、何ができないのか、相談を有意義なものにするための…
詳しくみる会社設立時の「資本金払込」とは?やり方と注意点
会社設立時の「資本金払込」は会社法34条に基づき、定款で定めた出資金額について、発起人が定めた銀行等の払込み取扱い場所(通常は発起人や設立時代表取締役名義の口座)に金銭を払い込む手続きです。 定款作成日よりも前に払込みがあったものに対しても…
詳しくみる京都府で会社設立する流れ・費用を抑えるコツ!税理士探しは必要?
京都府での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる家族信託で節税はできる?制度の仕組みと活用ポイントをわかりやすく解説
相続や贈与にかかる税負担をできるだけ抑えたいと考える中で、「家族信託」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。家族信託は、財産の管理や承継を円滑に行うための仕組みですが、使い方によっては節税にもつながる可能性があります。 本記事で…
詳しくみる合同会社(LLC)設立時に必要な印鑑は?法人印鑑の種類や費用などを解説
株式会社だけでなく、合同会社を設立する際も印鑑が必要です。電子定款を用いてオンラインで登記申請する場合は印鑑の提出(届出)が任意となり不要ですが、設立後に各種取引や申請などさまざまな場面で印鑑を使うため、あらかじめ作成しておいたほうがよいで…
詳しくみる家族で会社設立ガイド!メリット・注意点を解説
家族で会社を設立することは、絆を強めながら新たな事業チャンスを探る魅力的な方法です。しかし、スタートアップにおいてはメリットとともに注意すべき点もあります。 本記事では、家族を役員にするケースと従業員として雇うケースに分けて、それぞれのメリ…
詳しくみる


