- 作成日 : 2025年9月16日
マイクロ法人の節税効果は?設立のタイミングや注意点を解説
マイクロ法人は、節税や資産管理、社会的信用の向上といったメリットが得られる仕組みとして注目されています。副業による収入が増えてきた会社員や、高所得の個人事業主にとっては、税負担の軽減や経費の最適化といった効果が期待できます。一方で、法人設立や維持にはコストや手間がかかり、適切に運用しなければかえって負担が増すおそれもあります。本記事では、マイクロ法人の仕組みと節税効果、注意点を整理し、設立を検討すべきタイミングや条件について解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
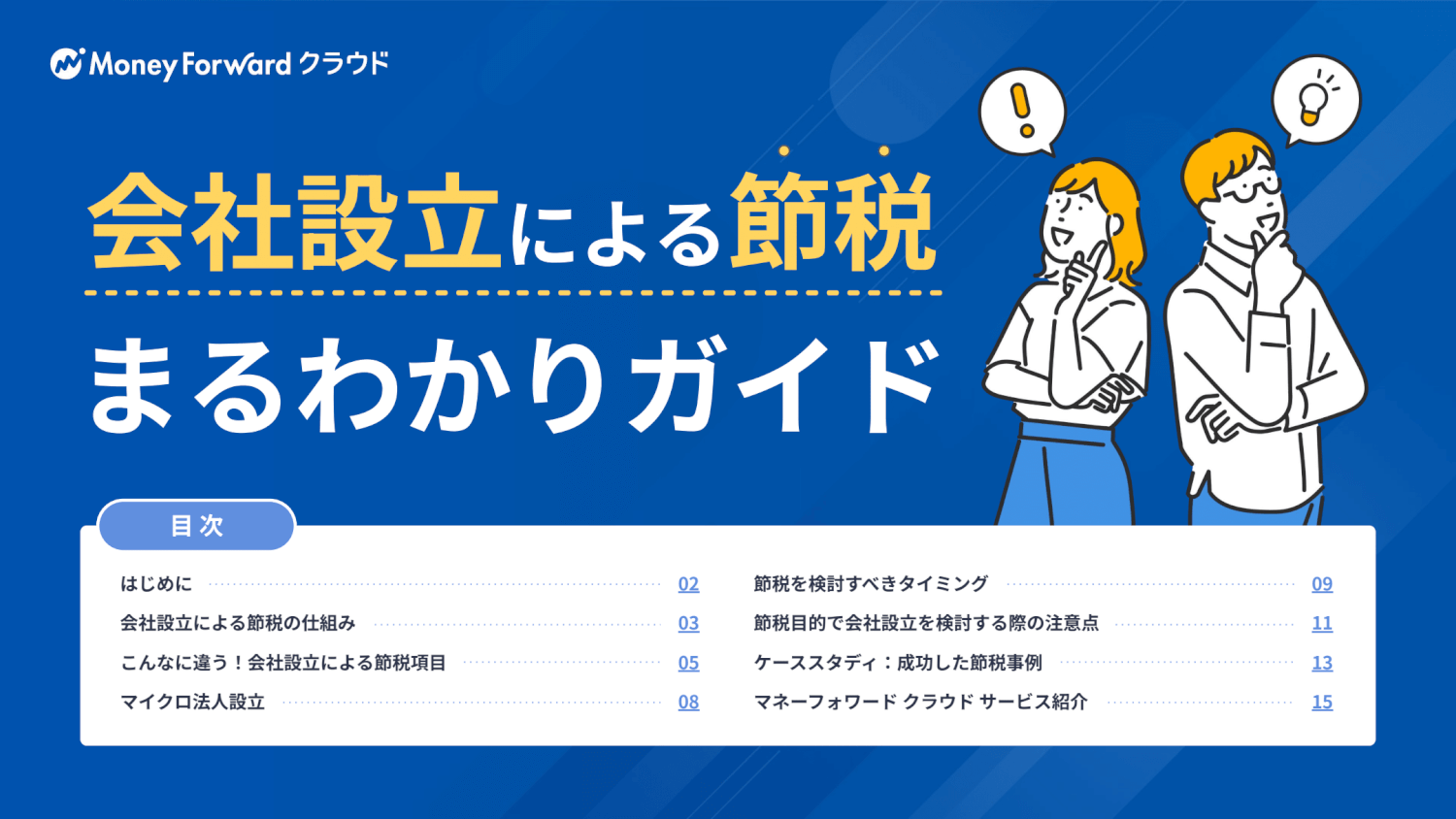
目次
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、個人やごく少人数で運営される小規模な法人を指す通称です。個人事業主や副業をしている会社員の間で、税金や社会保険料の負担軽減策として注目を集めています。近年の法人設立数の増加には、インボイス制度の開始など複数の要因が考えられますが、その中には節税を目的としたマイクロ法人の活用も一因として指摘されています。
マイクロ法人の定義
マイクロ法人は正式な法律用語ではないものの、一般的には一人で設立・運営できる「ひとり会社」を意味します。会社形態としては合同会社(LLC)や株式会社が選ばれることが多く、創業者自身が代表取締役を務め、他に役員や従業員を雇わないのが一般的です。こうした構成により、経営体制が非常にシンプルで固定費が抑えられる点が魅力です。
また、法人としての名義を持つことで、個人事業主のときよりも社会的信用を得やすくなります。これは取引先との契約や金融機関とのやり取りにおいて有利に働くことがあります。副業を始めたい会社員やフリーランスが、節税と信用力の両立を狙って法人成りする例も増えています。
副業としてのマイクロ法人と注意点
マイクロ法人の設立は適法であり、会社員が副業として法人を持つことも制度上は可能です。しかし、勤務先の就業規則で副業が禁じられている場合は、トラブルを避けるために事前の確認が必要です。
また、すでに個人事業として行っている事業をそのまま法人に移す場合には注意が求められます。同一の収益活動を個人と法人に分けて申告すると、税務当局から租税回避の疑いを持たれるおそれがあります。そのため、個人事業と法人の事業を明確に分け、売上・契約先・銀行口座・帳簿などすべてにおいて独立性を保つことが不可欠です。こうした運用を適切に行うことで、節税効果を活かしつつ、法的リスクを最小限にとどめることができます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
マイクロ法人を活用した節税のメリット
マイクロ法人は、個人で事業を行うよりも税務上の恩恵を受けやすい制度です。所得税や住民税、社会保険料の圧縮、消費税の免税、経費計上の柔軟性など、複数の節税効果が期待できます。収入が増えてきた個人事業主や副業を持つ会社員にとって、マイクロ法人は節税の強力な選択肢となり得ます。
所得税・住民税の負担軽減
個人事業主の所得には累進課税が適用され、最高で所得税45%、住民税10%、合計55%の税率がかかる場合があります。対して、法人税は中小企業であれば800万円以下の所得に対し軽減税率15%、800万円を超える部分に23.2%が適用されます。法人の方が一定以上の所得では税率が低く、税負担の軽減が見込めるのです。
高所得層では、法人化による節税効果が大きく現れる傾向があります。
社会保険料の負担軽減
法人の代表者は厚生年金と健康保険への加入が義務付けられますが、役員報酬を自分で設定できるため、報酬額を調整することで保険料を抑えることが可能です。ただし、この手法は近年行政から問題視されており、制度見直しの対象となっています。将来的なリスクも念頭に置きつつ、適切な報酬設計が求められます。
消費税の免税メリット
新設された法人は、原則として設立から2事業年度は消費税が免除されます(資本金1,000万円未満の場合)。そのため、個人と法人で売上を分散することで、どちらも免税事業者となれるケースがあります。
たとえば、個人で年収1,100万円ある事業主が、副業収入400万円分をマイクロ法人に移すことで、両者ともに免税対象となる可能性があります。ただし、消費税免税のみを目的とした法人設立は、税務調査で否認されるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。
また、2023年に導入されたインボイス制度の影響により、免税事業者のままでいると取引上の不利が生じる場合もある点には注意が必要です。
経費計上の幅が広がる
法人化することで、業務に関連する支出が経費として認められやすくなります。たとえば、自宅を社宅として会社が借り上げることで、法人側は賃料を経費として計上することができ、個人が賃料の一部を負担しているなど、一定の条件を満たせば、社宅としての使用に関して給与課税されずに済む場合があります。ただし、賃料の設定や契約内容には税務上のルールがあるため、適正な手続きを踏むことが重要です。さらに、業務に関連する出張では、一定の基準内であれば非課税扱いとなる「日当」を支給することで、従業員に対する実質的な補填を行いつつ、給与課税の対象とせずに済む場合もあります。
一方で、明らかに私的な支出を経費にすることは認められないため、経費の取り扱いには常に事業関連性を示せる根拠が求められます。
マイクロ法人による節税の注意点
マイクロ法人による節税は多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも少なくありません。ここでは、導入前に把握しておきたい注意点を解説します。
設立費・維持費などのコスト負担
法人設立には一定の初期費用がかかります。株式会社では約20〜25万円、合同会社でも約10万円が必要とされます。ただし、電子定款を利用すれば印紙代の負担が無いため、コストを抑えることが可能です。また、設立後も毎年支払いが発生する法人住民税(均等割)は、赤字や事業停止中でも最低7万円が課されます。また、役員報酬を設定すれば、健康保険や厚生年金の加入が必須となり、会社負担分を含めて社会保険料の支払いも発生します。
その他にも、バーチャルオフィスの利用料や会計ソフト、税理士報酬など、維持費が継続的にかかります。節税によって得られる効果よりも、こうした費用の方が上回る場合は、結果的に損をすることになります。法人化の前には、年収や事業規模に応じた費用対効果のシミュレーションが欠かせません。
事務手続きと管理業務の煩雑さ
法人を維持するためには、個人事業とは比べ物にならないほどの事務作業が求められます。決算書の作成、法人税・住民税・消費税の申告、各種届出といった税務手続きは毎年発生し、書類の整備や期限管理も必須です。
さらに、役員報酬の源泉徴収、社会保険の加入・変更手続きなど、日常的な管理業務も加わります。これらを自力で対応するのは現実的ではなく、税理士への依頼が一般的です。ただし、顧問料が発生し、資料提出や面談などの対応も必要になります。
本業を持ちながらマイクロ法人を運営するには、相応の時間的・精神的コストが伴います。管理業務に耐えうる体制があるかどうか、事前に検討しておくべきです。
税務上のリスク
節税目的で用いられるスキームの中には、税務上グレーと判断されるものもあります。たとえば、個人事業と法人で同一の業務を分けて行い、売上を人為的に分散させる方法は、税務署から「不自然な所得分割」として否認される可能性があります。
また、消費税の免税期間だけを狙った法人設立や、役員報酬を極端に低く抑えて高額な賞与で受け取るスキームも問題視されています。厚生労働省の審議会では、こうした手法が制度の不正利用として報告されており、今後の規制強化が予想されます。
これらの手法は一見すると節税効果が高いように見えますが、税務調査で否認されれば本末転倒です。マイクロ法人を活用する際は、合法かつ持続的に運用できる方法を採用し、節税目的が過度になりすぎないよう注意が必要です。
会社員・個人事業主がマイクロ法人の設立を検討すべきケース
マイクロ法人の設立は、特定の条件を満たす場合に節税効果を発揮します。誰にでも当てはまるわけではありませんが、一定の収入規模や副業状況にある人にとっては、有効な選択肢になり得ます。ここでは、会社員と個人事業主それぞれのケースに分けて、設立を検討すべき状況を解説します。
副業を持つ会社員
会社員で副業収入がある人にとって、マイクロ法人の設立は節税と信頼性向上の両面で効果が期待できます。副業の年収が500万円を超えるような場合は、個人の総合課税によって税率が上がり、手取りが減る傾向にあります。法人化すれば収入を法人に移すことで課税所得の分散が可能になり、税率の抑制につながります。
さらに、法人化によって経費計上の柔軟性が増すことも大きな利点です。たとえば、自宅を社宅として契約すれば家賃の一部を法人経費にできたり、通信費や出張費なども事業経費として処理しやすくなります。また、法人名義での契約や融資も進めやすくなり、ビジネスの信頼性も高まります。
ただし、会社員が法人を設立する場合、勤務先の副業規定に違反しないことが前提です。また、本業と競合するような事業を法人で営むことは、利益相反と見なされるリスクもあるため、事前の確認が欠かせません。
一定規模の収益がある個人事業主
個人事業主がマイクロ法人の設立を検討するべきタイミングは、課税所得が年間800万円を超える頃です。このあたりから所得税・住民税の負担が重くなり、法人化による定率の法人税(15~23.2%)への切り替えによって、税負担の軽減が期待できます。
また、社会保険料の面でも法人化のメリットがあります。個人事業主の場合、所得が増えるほど国民健康保険料・年金保険料が高額になりがちですが、法人化すれば役員報酬を調整して保険料をある程度抑えることが可能です。経費の取り扱いも法人の方が広く、家賃の社宅化や日当制度など、柔軟な節税スキームが実践できます。
加えて、2023年に始まったインボイス制度への対応としても法人化は有効です。適格請求書発行事業者としての登録により、取引先との関係維持にもつながります。
マイクロ法人設立の手続きの流れ
マイクロ法人は、会社設立の手順に従えば誰でも作ることができます。ここでは、合同会社または株式会社を前提に、設立に必要な基本的な流れと手続きについて解説します。
(1) 会社形態の選択と基本事項の決定
最初に、株式会社と合同会社のどちらを設立するかを選びます。コストや運営の自由度を重視する場合は合同会社、対外的な信用力を重視する場合は株式会社が適しています。そのうえで、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などの基本事項を決めます。マイクロ法人の場合、資本金は1円からでも設立可能です。
(2) 定款の作成と認証手続き
次に会社の憲法にあたる「定款」を作成します。合同会社は紙または電子で作成し、公証人の認証は不要ですが、株式会社は必ず公証人役場で認証を受ける必要があります。電子定款で作成すれば印紙代(4万円)が不要になるため、設立コストを抑えたい場合に有効です。
(3) 登記申請と各種届出
定款作成後は、資本金の払い込みを行い、登記に必要な書類(登記申請書、印鑑届出書、払込証明書など)を法務局に提出します。申請が受理されると登記が完了し、法人としての活動が正式に始まります。登記完了後には税務署・都道府県税事務所・年金事務所などへの各種届出も必要です。これらを正確に行うことで、マイクロ法人として適切に事業をスタートできます。
節税のためにマイクロ法人の活用を前向きに検討しよう
マイクロ法人は、節税や信用力向上を実現できる有効な手段です。副業で一定の収入がある会社員や、課税所得が増えてきた個人事業主にとっては、法人化によって大きな恩恵を得られる可能性があります。ただし、設立や維持には費用や手間がかかり、制度を誤用すれば税務リスクも伴います。自分の収入・事業規模・将来設計をふまえて、メリットとデメリットを整理しながら、必要に応じて専門家に相談し、マイクロ法人の活用を前向きに検討してみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
レンタル業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
これからレンタル業を始める方の中には、定款の作成に悩んでいる方もいるでしょう。定款は正しく作成しなければ、効力がありません。 定款には必ず記載しなければならない事項と、任意で記載する事項があります。本記事では定款への記載事項や、レンタル業の…
詳しくみる葛飾区でお得に会社設立!自分で簡単にできる!
葛飾区での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる運転資金とは?計算方法や種類、調達方法についてわかりやすく解説
事業を始める際、一番に考えなければならないのは運転資金についてです。事業のために絶対に必要な運転資金ですが、どのような種類の費用が運転資金と呼ばれるのでしょうか。 この記事では、運転資金とは何かを詳しくご紹介します。運転資金の種類だけでなく…
詳しくみるサラリーマン(会社員)が今すぐできる節税方法は?得する控除や制度を解説
サラリーマン(会社員)は会社での年末調整だけでなく、自ら税制を理解し活用することで、税負担を減らすことが可能です。基本的な所得控除はもちろん、ふるさと納税やiDeCo、新NISA、副業の経費処理など、応用的な制度まで幅広く存在します。これら…
詳しくみる三重県で会社設立をお得に依頼する方法!書類準備をラクにするには?
三重県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる売上なしの合同会社も税金がかかる?申告義務や赤字・休眠時の取り扱いも解説
合同会社は、売上がない状態でも法人住民税の均等割が発生し、税務申告の義務も原則として免除されません。適切な対応を怠ると、将来的なペナルティや不利益につながる可能性があります。 この記事では、合同会社で売上がない場合にかかる税金とかからない税…
詳しくみる


