- 作成日 : 2025年9月16日
マンション経営で節税するには?所得税・相続税・固定資産税を抑える仕組みや注意点を解説
マンション経営は、収益を得るだけでなく、さまざまな税金に対して節税効果を得られる投資手法としても注目されています。所得税・住民税をはじめ、相続税や固定資産税・都市計画税まで、制度をうまく活用することで税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、税制の仕組みを正しく理解せずに始めると、かえって損をするリスクもあります。本記事では、マンション経営で節税できる税の種類と仕組み、実践する際のポイントや注意点について解説します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
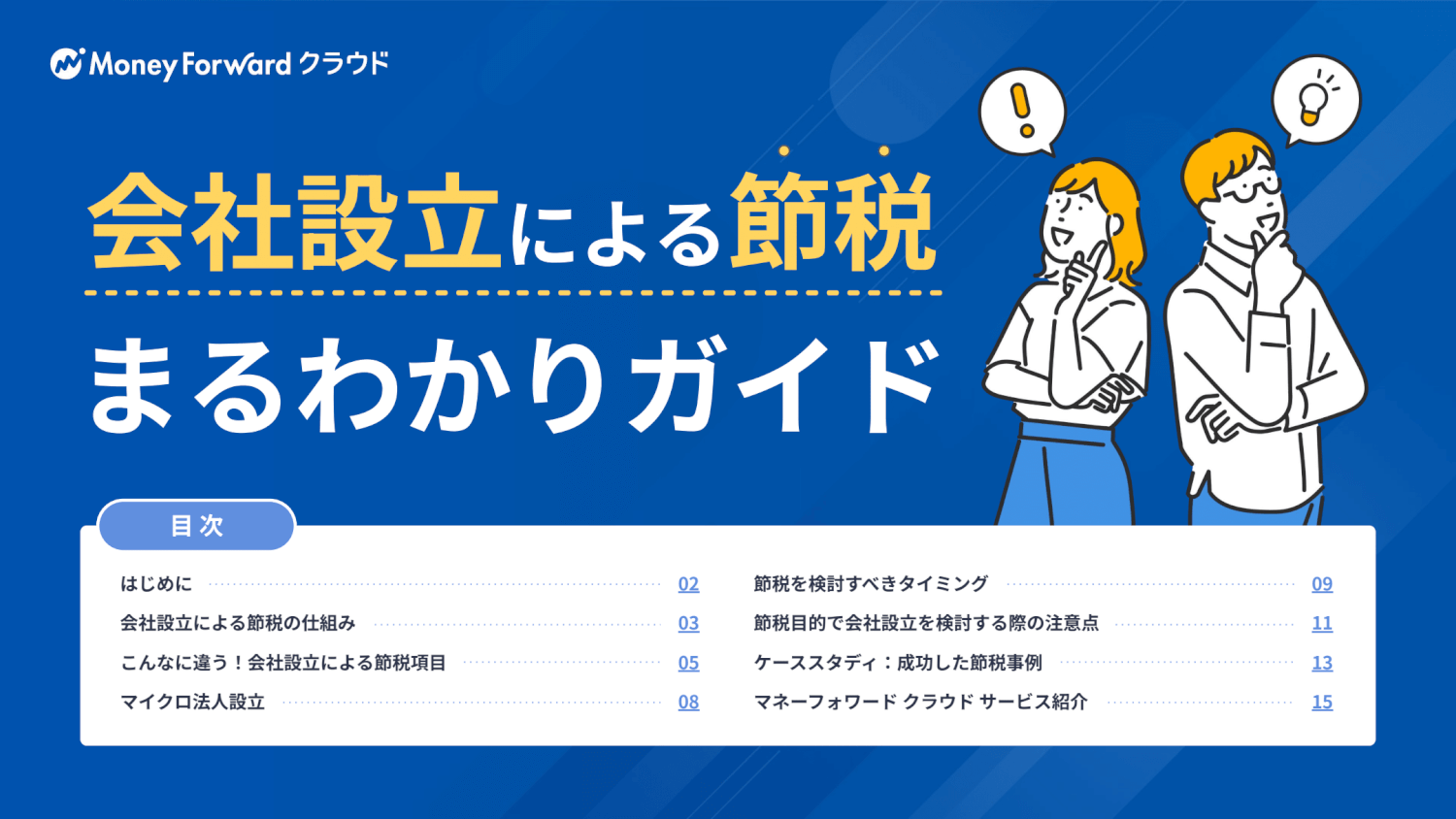
目次
マンション経営で節税できる税金の種類
マンション経営を行うことで節税できる主な税金は、所得税・住民税、相続税、固定資産税・都市計画税の3つに分類されます。
まず、所得税・住民税については、賃貸収入から減価償却費や必要経費を差し引くことで帳簿上の赤字を作り出し、本業の給与所得などと損益通算が可能になります。これにより課税所得が減り、税負担を軽減できます。
次に、相続税対策としては、現金で資産を持つよりも、賃貸用マンションなどの不動産に資産を組み替えることで、相続税評価額を圧縮しやすくなります。賃貸中の物件は評価減の対象となり、相続税を抑える手段として有効です。
最後に、固定資産税・都市計画税については、住宅用地に対する特例措置があり、更地と比べて税額が大幅に軽減される仕組みが用意されています。これら3つの税区分に対して、制度を適切に活用することでマンション経営による節税効果が見込めます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
マンション経営で所得税・住民税を節税するには
マンション経営では、不動産所得の赤字や減価償却の活用により、所得税や住民税の負担を軽減できます。帳簿上の赤字を他の所得と相殺することで税負担を抑えるこの仕組みは、給与所得がある会社員にとって有効です。
損益通算によって課税所得を圧縮する
不動産所得が赤字になると、その損失分を給与所得など他の所得から差し引けます。これを「損益通算」と呼び、課税所得を小さくできることで所得税・住民税が軽減されます。たとえば給与所得600万円の人がマンション経営で100万円の赤字を出した場合、他の所得と合算する「総所得金額等」を500万円として税額計算をします。ここからさらに給与所得控除や社会保険料控除などが差し引かれるため、最終的な課税所得は500万円よりも低くなり税金が減ります。
減価償却費で帳簿上の赤字をつくる
赤字を計上するうえで重要なのが減価償却です。建物の取得費用は法定耐用年数に基づいて毎年経費にでき、実際の支出を伴わずに経費化できます。これにより現金収支が黒字でも、帳簿上は赤字となる可能性があり、その赤字を損益通算に活用できます。
青色申告による追加の節税効果
一定の条件を満たせば、青色申告特別控除として最大65万円の所得控除が適用されます。帳簿を複式簿記でつけ、電子申告などを行うことでこの特典を得られ、より大きな節税効果が期待できます。家族への給与も経費にできるなど、制度の活用が節税につながります。
マンション経営で相続税を節税するには
マンション経営は、現金や有価証券を不動産に組み替えることで相続税評価額を圧縮し、結果として相続税の軽減につなげることが可能です。ここでは基本的な考え方と節税方法を解説します。
不動産評価額が下がる仕組みを活用する
相続税評価では、現金はそのままの額で課税対象になりますが、マンションなどの賃貸不動産は「貸家」「貸家建付地」として評価され、建物・土地の評価額がそれぞれ減額されます。賃貸マンションの敷地(貸家建付地)は、相続税評価額が減額されます。評価減の割合は自用地評価額に「借地権割合×30%(借家権割合)×賃貸割合」を乗じて計算されます。例えば借地権割合が70%で賃貸割合が50%の場合では10.5%減額されます。空室がある場合は賃貸割合が下がり、減額幅も小さくなります。
これにより、時価1億円の資産を賃貸マンションに組み替えるだけで、評価額が数千万円単位で下がることがあります。
実際の賃貸運用と継続性が前提
評価減を適用するには、実際に第三者へ賃貸していることが条件です。空室が多かったり、自己使用の形態になっていたりすると評価減の対象から外れる可能性があります。また、建物だけでなくその土地についても減額を受けるためには、相続時点で継続的に賃貸用として使われている必要があります。
事前準備は充分に
マンション経営を相続対策として活用するには、物件取得時の収益性の確認や初期費用、管理負担などを総合的に見極める必要があります。節税のために購入した物件で赤字経営が続くと本末転倒です。また、相続税申告時には適切な書類整備と評価計算が不可欠であり、税理士など専門家のサポートを受けることが安心です。
マンション経営で固定資産税・都市計画税を節税するには
毎年課される固定資産税・都市計画税は、マンション経営を行うことで大幅に軽減される可能性があります。住宅用地や新築住宅には、特例や減額措置が設けられており、更地で保有しているよりもマンションとして活用した方が有利になるケースがあります。
小規模住宅用地の特例で土地評価が6分の1に
マンション経営により土地を住宅用地として利用することで、「小規模住宅用地」としての課税特例を受けられます。これは、1戸あたり200㎡までの土地に対して、固定資産税の課税標準を評価額の6分の1、都市計画税を3分の1に減額する仕組みです。たとえば10戸の賃貸マンションであれば、最大2,000㎡分までこの軽減が適用される可能性があり、更地として保有するより圧倒的に税負担を下げることができます。
建物への課税と影響も考慮する
一方で、マンションを建てた後は建物自体にも固定資産税・都市計画税が課されます。構造がRC(鉄筋コンクリート)など耐火建築物で新築の場合、評価額が高くなり税額も大きくなる傾向があります。つまり、土地の税金が下がる一方で、建物分の税負担は増えるため、トータルでのシミュレーションが必要です。
新築住宅の固定資産税減額措置を活用する
賃貸マンションを新築する場合は、固定資産税の減額措置も有効です。一般の耐火建築物であれば、新築後5年間にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。さらに、長期優良住宅として認定されたマンションであれば、この期間が7年に延長されます。対象となるのは2026年3月末までに新築された物件です。新築後は申告が必要になるため、忘れずに市区町村へ届け出ることが大切です。
マンション経営を法人化する節税メリット
個人で行うマンション経営は節税効果がありますが、一定以上の収益が見込まれる場合は法人化することでさらに税負担を抑えることが可能です。法人税率の優遇や所得分散、経費計上の幅の広さなど、法人ならではの節税メリットを解説します。
法人税率の方が低くなる可能性がある
個人の所得税は累進課税で、最高税率は45%(住民税を含めると最大約55%)に達します。一方、法人税は所得800万円以下で15%、超過部分でも23.2%(別途地方税あり)と個人に比べて税率が一定かつ低く抑えられます。年間の不動産所得が900万円を超える場合、個人での納税額より法人の方が大幅に少なくなるケースが多く見られます。
所得分散で家族全体の節税が可能
法人化することで、家族を役員や従業員として雇用し、役員報酬や給与を支払うことが可能になります。この報酬は法人側の必要経費として計上され、同時に家族に分散された所得は個人の税率で課税されます。これにより一家全体での課税所得を引き下げ、税負担を効率よく分散することができます。
経費計上の幅が広がる
法人では、旅費交通費、役員報酬、出張手当、交際費、社宅費用など、個人では計上が難しい経費も適正に処理すれば法人の損金として計上可能です。法人が社宅を所有して役員に貸し付けた場合でも、一定条件を満たせば経費として認められ、家賃負担の軽減と節税効果の両立が期待できます。
欠損金の繰越期間が長い
個人事業では赤字の繰越は最大3年ですが、法人では最長10年間まで欠損金の繰越控除が認められます。赤字が出た年があっても、将来の黒字と相殺できるため、長期的な税負担の平準化が可能です。景気や賃貸需要の波に左右されるマンション経営にとって、この制度は大きなメリットです。
マンション経営を法人化する際のデメリット
法人化は節税や資産管理の面で有効な選択肢ですが、その一方でコストや手間、制度上の制限など注意すべき点も少なくありません。ここでは、マンション経営を法人化する際の注意点を解説します。
法人設立・運営にコストと手間がかかる
法人を設立するには、登録免許税・定款認証手数料などで約20万円前後の初期費用がかかります。設立後も、法人住民税の「均等割」として赤字でも年7万円程度の税負担が毎年発生します。さらに、決算・申告業務は個人より複雑で、税理士への依頼が必要になることも多く、その分の報酬も考慮が必要です。
社会保険料の負担が増える
法人化すると、役員報酬を受け取る自分自身も厚生年金・健康保険などの社会保険に加入する義務が生じます。これにより、個人事業時代より保険料の負担が大きくなるケースが多く、節税メリットが保険料によって打ち消されることもあります。報酬額の設定は慎重に行う必要があります。
不動産の移転コストがかかる
個人で所有していた不動産を法人に移すには、所有権移転登記が必要で、不動産取得税(原則4%)や登録免許税、司法書士報酬などのコストがかかります。また、不動産の譲渡益が生じる場合は個人に譲渡所得税が発生する可能性もあるため、慎重な試算が必要です。
銀行融資の難易度が変わる
個人名義でのマンション経営に比べ、法人名義での融資は金融機関の審査基準が厳しくなりがちです。設立直後の法人は実績がないため融資が通りにくく、個人保証や担保が必要になるケースもあります。法人化後の資金調達戦略も考慮しておく必要があります。
節税効果が限定的な場合もある
法人化によって得られる節税効果は、事業規模や収益状況によって異なります。たとえば年間の不動産所得が少ない場合は、法人化のコストと手間に見合う節税効果が得られない可能性もあります。節税目的で法人化する際は、専門家に事前シミュレーションを依頼し、実際の効果を確認することが大切です。
マンション経営による節税の注意点
マンション経営には、所得税・相続税・固定資産税などを抑える複数の節税手段があります。しかし、節税メリットだけを目的に投資判断を下すと、かえって経営が不安定になるリスクもあります。ここでは、マンション経営で節税を狙う際に意識しておきたい注意点を整理します。
赤字を前提にしすぎない
所得税の節税では、不動産所得を赤字にすることで給与所得などと損益通算できます。ただし、「赤字である」こと自体は経営上のマイナスです。たとえば、100万円の赤字で30万円の節税ができても、実際には70万円の損失となります。帳簿上の赤字が減価償却によるものなら問題ありませんが、空室増加や想定外の修繕費で現金収支までマイナスになると、本来の目的である収益確保が揺らいでしまいます。
空室と資産価値の低下に備える
賃貸経営では空室が続くと、収入が途絶え税負担どころではなくなります。また、エリアの需給悪化や老朽化により、資産価値が下がれば売却時の損失リスクも高まります。節税を目的に物件を取得しても、収益性のない物件であれば長期的には損失が拡大します。節税はあくまで副次的な利点と位置付け、立地や将来性、管理コストを見据えて慎重に判断する必要があります。
想定コストを過小評価しない
マンション経営では、取得時に不動産取得税(原則4%)、登録免許税、司法書士報酬、印紙税などの諸経費が発生します。事業規模(おおむね5棟10室以上など)に達すると個人事業税の課税対象となりますが、所得から年間290万円の事業主控除が差し引かれます。したがって、不動産所得が290万円を超えた場合に、その超過分に対して5%の税金がかかります。
こうした税金や手続きを見落とすと、想定よりも手残りが少なくなります。節税効果だけを追うのではなく、全体のキャッシュフローを見据えた経営計画が求められます。
マンション経営の節税効果を引き出すために制度を有効活用しよう
マンション経営では、所得税・相続税・固定資産税など複数の税目で節税できるチャンスがあります。損益通算や減価償却、小規模住宅用地の特例、法人化の活用など、制度を理解し適切に運用することで、税負担を抑えることが可能です。ただし、節税だけを目的とした投資にはリスクも伴います。収支計画や資産の収益性を見極め、節税メリットとコスト・リスクを総合的に判断することが大切です。専門家のアドバイスも得ながら、持続的な経営と節税の両立を目指しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
合同会社の設立は最短何日でできる?
できるだけ事業を早く立ち上げたいという思いで、合同会社の設立を急がれている方もいらっしゃるかと思います。この記事では最短でどれくらいの期間で合同会社を設立できるかについてご説明します。 すぐに会社を設立する必要がある、合同会社の設立に必要な…
詳しくみる建設業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
建設業の会社を設立する際は、定款の作成が必要です。定款とは会社の基本情報や規則を記載した文書であり、事業目的をはじめとして必ず記載しなければならない項目があります。事業目的は、許可を取得する予定の事業内容に沿って記載しましょう。 本記事では…
詳しくみるペットショップの定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
これからペットショップの起業を考えている方の中には、定款の作成で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。定款は普段あまり目にする機会もなく、いざ作成するとなると戸惑ってしまうでしょう。 定款には必ず記載しなければならない項目が定められていま…
詳しくみる住宅ローン控除で節税するには?条件・手続き・注意点を解説
マイホームの購入は人生の大きな節目ですが、同時に多額の費用を伴う一大イベントでもあります。そうした住宅取得を支援する制度として注目されているのが「住宅ローン減税」です。住宅ローンの年末残高に応じて、最大13年間にわたり所得税や住民税が控除さ…
詳しくみる法人登記情報の確認方法は?登記簿謄本や附属書類の取得・閲覧方法を解説
法人登記情報の確認方法は複数あり、状況に応じて選択できます。一般的には法務局の窓口で確認しますが、オンラインで申し込んで郵送で取り寄せたり、登記情報提供サービスで閲覧したりすることも可能です。また、登記事項証明書(登記簿謄本)だけでなく、登…
詳しくみる岩手県の会社設立をラクに・お得にする方法!起業情報まとめ
岩手県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる


