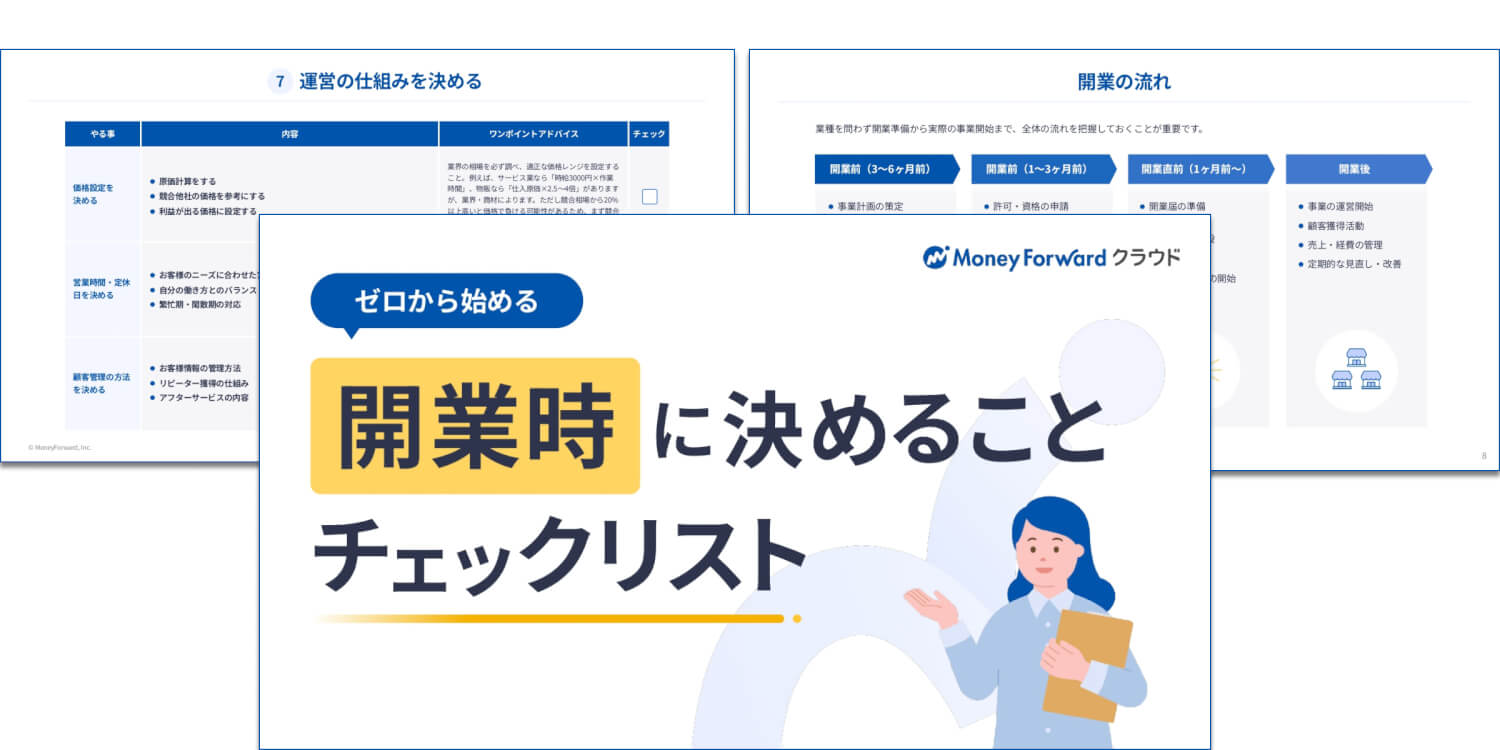- 更新日 : 2025年9月4日
フリーランスが開業届を出すメリットは?
フリーランスの個人事業主として仕事を開始する場合、自分次第でいつでも働き始められます。しかし「仕事を始めるにあたって開業届の提出は必要なのか?」「提出が必要な場合はどう書いたらいいのか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
そこで今回は、開業届の書き方について解説します。開業届についてしっかりと理解してスタートを切りましょう。
目次
フリーランスと開業届の関係性
フリーランスとして働く場合も開業届を提出することになります。まずは開業届とは何か、いつまでに提出するかについて理解しましょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。これにより税務署は開業の事実を知ることになります。
開業届を提出するタイミング
開業届を提出するタイミングは、事業の開始があった日から1か月以内とされています。提出期限が短いため、フリーランスとして働き始めたらすぐに準備にとりかかりましょう。
フリーランスと個人事業主の違い
フリーランスと個人事業主の関係について、まず明確にしておきましょう。
フリーランスは働き方を表す用語で、特定の企業や団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方を指します。一方、個人事業主は税法上の区分であり、個人で事業を営む人のことを指します。
つまり、フリーランスとして活動する人が開業届を提出すると、税法上は個人事業主として扱われることになります。開業届を出していないフリーランスも存在しますが、継続的に収入を得ている場合は、実質的には個人事業主と見なされる可能性があります。
重要なのは、年間の所得が一定額を超える場合、開業届の有無に関係なく確定申告の義務が発生することです。そのため、継続的にフリーランスとして収入を得る予定がある場合は、開業届の提出を検討することが賢明です。
フリーランスが開業届を出すメリット
開業届を提出することで得られる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
青色申告特別控除の適用
開業届及び青色申告承認申請書を提出する最大のメリットは、青色申告特別控除を受けられることです。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けることができ、所得税や住民税の大幅な節税効果が期待できます。
例えば、年間所得が300万円のフリーランスが青色申告特別控除65万円を適用した場合、課税所得は235万円となり、所得税だけでも数万円程度の節税効果があります。
屋号での銀行口座開設
開業届を提出することで屋号を登録でき、屋号名義での銀行口座開設が可能になります。これにより、事業用とプライベート用の口座を明確に分けることができ、経理処理が格段に簡単になります。
屋号口座を持つことで、取引先からの信頼度向上にもつながります。個人名よりも事業としての印象を与えることができるため、ビジネスの発展に寄与します。
事業所得としての損益通算
開業届を提出し、事業所得として申告することで、事業で発生した損失を他の所得と相殺できる損益通算が可能になります。これは特に事業開始初期において、設備投資などで赤字が発生する場合に有効です。
また、事業所得として認められることで、必要経費の範囲も広がります。事業に関連する支出を経費として計上できるため、課税所得を抑えることができます。
各種制度の利用
開業届を提出することで、小規模企業共済や経営セーフティ共済などの制度を利用できるようになります。これらの制度は節税効果があるだけでなく、将来の事業資金確保にも役立ちます。
フリーランスが開業届を出すデメリット
開業届の提出にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットも存在します。
配偶者控除の適用除外
開業届を提出し、個人事業主として、事業申告を行う場合、配偶者(納税者)が配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主(扶養親族)において、その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下であることやその他の要件を満たす必要があり、場合によっては、配偶者控除の適用除外になってしまう場合もあります。
これは、給与所得者の場合の給与収入103万円(所得48万円)の壁と同様の概念ですが、事業所得の場合は収入から必要経費を差し引いた所得で判断されるため、実際の収入額は異なります。
失業保険の受給制限
会社員からフリーランスになった場合、開業届を提出していると失業保険の受給ができなくなります。開業届を提出することで事業を開始したと見なされ、失業の状態ではないと判断されるからです。
詳しくはハローワークに相談することをお勧めします。
帳簿作成の義務
開業届を提出すると、青色申告・白色申告に関わらず、帳簿の作成と保存が義務付けられます。特に青色申告特別控除を受ける場合は、複式簿記による詳細な帳簿作成が必要となります。
これまで家計簿程度の記録しかつけていなかった場合、会計処理の負担が大きく増加する可能性があります。ただし、現在は会計ソフトの普及により、この負担は大幅に軽減されています。
フリーランスで開業届を出さないのは違法?出さないとどうなる?
所得税法229条では、開業届の提出について規定されています。しかし、開業届を出さなかったとしても具体的な罰則などはありません。ここからは開業届に関するよくある質問について回答とともにご紹介します。
フリーランスはいくらから開業届を出すべき?
開業届は収入、所得にかかわらず提出すべき書類です。そのため、事業を開始したら開業届を提出する必要があると考えましょう。
フリーランスで収入なしだが、開業届の提出は必要?
先述の通り開業届は収入、所得の有無にかかわらず提出しなければなりません。フリーランスで収入がなくても開業届の提出が必要です。
フリーランスで開業届を出してないときの確定申告はどうすればいい?
フリーランスで開業届を提出していなくても、確定申告は可能です。フリーランスとして行っている事業で所得を得ており、税金を納める必要がある場合は、確定申告をする必要があります。開業届を出してない場合でも、まずは確定申告を行いましょう。
フリーランスで白色申告のときに開業届の提出は必要?
フリーランスで白色申告のときも、開業届の提出は必要です。
フリーランスの開業届の書き方
開業届の具体的な記入方法と提出手順について説明します。
必要書類の準備
開業届の提出に必要な書類は以下の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印で可)
開業届の記入方法
開業届の主要な記入項目について詳しく説明します。
基本情報
提出日、納税地(住所地または事業所所在地)、氏名、生年月日、マイナンバーなどを記載します。納税地は住所地を選択するのが一般的です。
事業に関する情報
職業欄に具体的な業種を記入します。例えば「Webデザイン業」「システム開発業」「コンサルティング業」など、実際に行う事業内容を明確に記載しましょう。
フリーランスにおける職業欄の書き方も、それ以外の働き方と同じです。「フリーランス」などと働き方を記載するのではなく、フリーランスの美容師であれば「美容業」「美容師」など、フリーランスのカメラマンであれば「写真業」「カメラマン」などと仕事内容が分かるように記載します。
屋号は必須ではありませんが、事業用の名称を使用したい場合は記入します。屋号は後から変更も可能なので、現時点で決まっていなければ空欄でも問題ありません。
事業の開始等年月日は、実際に事業を開始した日付を記入します。すでに事業を開始している場合は開始日を、これから開始予定の場合は予定日を記載します。
フリーランスの開業届の提出方法
ここからは開業届の提出方法についてご紹介します。
オンラインで提出
開業届はe-TAXで提出することができます。e-TAXを利用すれば開業届を紙で印刷したり、税務署に行ったりする手間を省けるため、オンラインでの提出をおすすめします。
また、マネーフォワードでは、オンラインで簡単に開業届を提出できる「マネーフォワード クラウド開業届」を提供しています。書き方で迷いやすいポイントについて、選択肢などを用意しており、スムーズに提出できるでしょう。無料で使用できるため、ぜひご利用ください。
参考:税務署に行かず自宅からラクラク開業|マネーフォワード クラウド開業届
郵送で提出
紙で開業届を提出するときは、郵送でも提出が可能です。自身の所轄税務署を確認して投函しましょう。なお、開業届を郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。
持ち込みで提出
紙で開業届を提出するときは、税務署に持参することもできます。税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までのため、その時間帯であれば窓口に提出することが可能です。この時間に提出できない方は、税務署の時間外収受箱に投函すれば24時間365日提出できます。
なお、開業届を持ち込みで提出する場合は、本人確認書類の提示が必要となるため注意してください。
フリーランスの開業の手続き・流れ
フリーランスとして開業する際の全体的な手続きの流れを時系列で説明します。
事業準備段階
開業前の準備として、まず事業計画の策定が重要です。どのような事業を行うのか、ターゲット顧客は誰か、収益見込みはどの程度かなどを明確にしておきましょう。
事業用の銀行口座開設を検討している場合は、開業届提出前に金融機関の要件を確認しておくことをお勧めします。金融機関によっては、開業届の控えだけでなく、事業実態を証明する書類の提出を求められる場合があります。
開業届提出とその後の手続き
開業届を提出した後は、青色申告を希望する場合は青色申告承認申請書も併せて提出します。この申請書は開業から2ヶ月以内または青色申告を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書は、従業員を雇用する予定がある場合に提出が必要です。家族を従業員として雇用する場合も対象となります。
各種保険の手続き
国民健康保険と国民年金の手続きも重要です。会社員からフリーランスになった場合、健康保険の切り替え手続きが必要になります。国民健康保険への加入または任意継続被保険者制度の利用を検討しましょう。
国民年金については、第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。市区町村役場で手続きを行います。
会計処理の準備
帳簿作成の準備として、会計ソフトの選定と導入を行います。現在は多くのクラウド会計ソフトが提供されており、初心者でも使いやすい機能が充実しています。
銀行口座やクレジットカードとの連携機能を活用することで、取引の自動取り込みが可能になり、経理処理の負担を大幅に軽減できます。
フリーランスの開業費用
フリーランスとして開業する際に発生する費用について、項目別に詳しく説明します。
初期費用
開業届の提出自体は無料ですが、開業に伴って発生する初期費用があります。
事務用品・設備費
パソコン、プリンター、デスク、椅子などの基本的な事務用品が必要です。業種によって必要な設備は異なりますが、一般的には10万円から30万円程度の初期投資が必要になります。
ソフトウェア費用
会計ソフトの導入費用が発生します。クラウド会計ソフトの場合、月額1,000円から3,000円程度の費用がかかります。年間契約をすることで割引が適用される場合が多いです。
印鑑・名刺作成費
事業用の印鑑や名刺の作成費用が必要です。印鑑は数千円から1万円程度、名刺は100枚で2,000円から5,000円程度が相場です。
月次・年次費用
開業後に継続的に発生する費用についても把握しておく必要があります。
会計ソフト利用料
月額または年額で発生します。機能や利用者数によって料金が異なりますが、個人事業主向けのプランであれば月額1,000円から2,000円程度が一般的です。
各種保険料
国民健康保険料と国民年金保険料が発生します。これらは前年の所得に基づいて計算されるため、初年度は比較的低額になることが多いです。
税理士費用
確定申告を税理士に依頼する場合に発生します。自分で申告する場合は不要ですが、複雑な取引がある場合や節税対策を検討したい場合は、税理士への相談を検討しましょう。
経費として計上できるもの
開業に関連する費用の多くは、事業の必要経費として計上できます。
開業前に支出した費用についても、開業準備のために要した費用として「開業費」に計上し、任意の年度に償却することができます。これにより、開業初年度の税負担を軽減することが可能です。
事業で使用する設備や備品、ソフトウェアなどは減価償却または一括償却により経費計上できます。10万円未満の固定資産は、全額を取得年度の経費として計上することができます。
フリーランス開業成功のための重要なポイント
フリーランスとして開業し、継続的に成功するためには、適切な準備と計画的な事業運営が不可欠です。
開業届の提出は、フリーランスとして本格的に事業を開始する重要な第一歩です。青色申告特別控除をはじめとする税制上のメリットを最大限に活用し、適切な経理処理を通じて健全な事業運営を心がけましょう。
開業に伴う手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確実に進めることで、安心してフリーランス活動に専念できる環境を整えることができます。不明な点がある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
事業の成長とともに、新たな手続きや届出が必要になる場合もあります。常に最新の情報を収集し、適切な対応を取ることで、長期的に安定したフリーランス活動を続けることができるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
かき氷屋を開業したい!開店までの流れや必要な許可・資金を紹介
キッチンカーなどのビジネスモデルがよく見られるようになりました。かき氷屋も移動販売に向いたビジネスです。かき氷屋を開業したい場合、どのような販売許可や資格が必要で、どれくらいの開業…
詳しくみる経営コンサルタントとして起業・開業するには?資格や成功のコツを解説
経営コンサルタントとは、クライアントが抱える悩みに対して、専門知識を活かして解決手段や改善策を提案する仕事のことです。特別な資格は不要で、自宅でも開業できるため、個人での起業にもお…
詳しくみるイラストレーターは開業届の提出が必要?書き方やメリットも解説!
クライアントの要望に応じて、手書きやパソコンでイラストを作成し販売する「イラストレーター」を仕事にしている方がいます。イラストレーターは、報酬を得ていても趣味なのか仕事なのかあいま…
詳しくみる福井県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
福井県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する福井県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる公認会計士の独立・開業は難しい?年収や成功のコツを解説
公認会計士は専門性や需要が高い仕事であり、独立・開業は難しくありません。独立後は、税務業務やコンサルタントなど、さまざまな道があります。しかし、自身で仕事を獲得しなければならず、競…
詳しくみる広告代理店を起業するならネット広告がおすすめ?開業までの流れも解説!
これから起業したいという方に注目してもらいたいのが、「広告代理店」の開業です。インターネット広告など新しいビジネスモデルが確立しつつある広告代理店業界ですが、開業するためにはどのよ…
詳しくみる