- 作成日 : 2025年9月16日
節税は税理士に相談すべき?メリット・費用・選び方を解説
節税対策を考えるとき、税理士に相談するかどうかで効果や安心感は大きく変わります。税理士は、税務の専門家として最新の法令に基づいた節税方法を提案し、申告や手続きまでサポートしてくれる存在です。所得が増えてきた個人事業主や、副業や投資で複数の収入源を持つ会社員など、税務が複雑になるほど専門的な知識が求められます。
この記事では、税理士と連携して節税を進めるメリットや方法を紹介します。
「会社設立 節税まるわかりガイド」は、もうすでに無料ダウンロード済みでしょうか?会社設立による節税の仕組みや節税項目、マイクロ法人の設立方法などがまとまった、充実のガイドです。
無料登録で簡単にダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
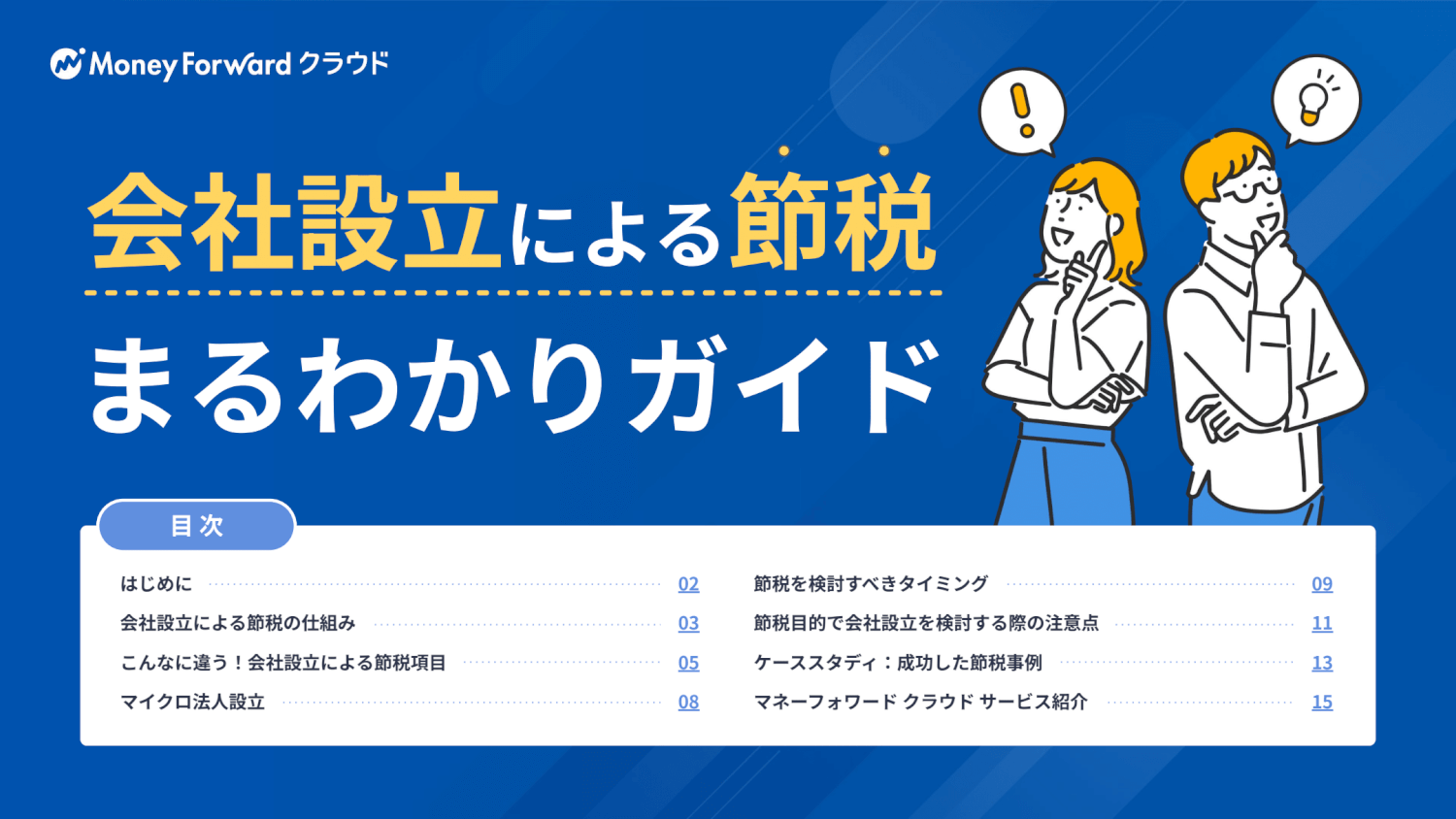
目次
節税対策で税理士に相談するメリットは?
節税について考える際、誰に相談すべきか迷う方も少なくありません。ここでは、税理士に相談することのメリットを解説します。
税理士は税務の専門資格を持つ唯一の国家資格者
税理士は、税務書類の作成や税務代理を法的に認められている唯一の資格者です。行政書士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーもお金や手続きに関する知識はありますが、税務申告の代理や税額計算の実務、および税務に関する相談業務は行えません。税制は毎年改正されるため、正確な申告と節税には税理士の専門知識が有効です。
公的相談窓口との違いは「実行支援力」
国税庁や市区町村の窓口では、基本的な税制度の案内や一般的な情報提供は受けられますが、個々の状況に応じた具体的な節税アドバイスや手続きの代行は行われません。税理士であれば、個人の収入構成や事業内容、家族構成などに合わせた節税戦略の提案が可能で、申告書の作成や提出まで一貫して対応してくれます。
自己判断での対応はリスクが高い
自己判断で節税を進めた場合、経費の取り扱いや控除の適用ミスによって、節税どころか後の追徴課税や税務調査の対象になるリスクもあります。税理士に相談すれば、税務上のグレーゾーンを避けつつ、適切な節税ができるよう助言を受けられるため、安心して対策を進めることができます。結果として、長期的に見れば報酬以上の節税効果が得られるケースも少なくありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
節税対策で税理士に依頼できる業務
税理士は、税務の専門家として節税対策に関するさまざまな業務を担います。ここでは、個人事業主や会社員が税理士に節税を相談した際に、どのような支援を依頼できるのか、代表的な業務内容を解説します。
確定申告の作成と控除の適用サポート
最も基本的な依頼内容は、所得税や法人税、消費税などの確定申告書の作成および申告手続きです。税理士は収支の内容や帳簿をもとに、正確に税額を算出し、各種控除や特例を漏れなく反映させることで、過不足のない税額を導きます。医療費控除、住宅ローン控除、青色申告特別控除、小規模企業共済等掛金控除など、複雑な制度の適用もスムーズに行えるため、申告ミスの防止にもつながります。
節税制度の提案と活用アドバイス
税理士は、顧客の収入や家族構成、事業内容に応じて、最適な節税制度を提案してくれます。たとえば、iDeCoやふるさと納税、経営セーフティ共済、小規模企業共済などの活用方法について、制度の概要、導入手順、効果の見込みまで丁寧に説明してもらえます。自身では気づきにくい制度も、税理士の提案によって活用できる可能性が広がります。
法人化(法人成り)のタイミングとシミュレーション
個人事業主が法人化を検討する際、税理士に相談することで、法人化による節税効果を具体的に数値で比較・試算してもらえます。所得税と法人税の違いや社会保険料の負担差、役員報酬の最適化による節税など、法人化のメリットとリスクを踏まえて、最適なタイミングと方法を判断する材料を提供してもらえます。
専従者給与や経費計上に関する助言
税理士は、家族従業員への給与支払いによる所得分散や、正当な経費の計上方法についても具体的に助言します。たとえば、青色事業専従者給与や役員報酬、家賃・光熱費の事業按分など、税務上のルールを遵守しつつ節税につながる処理をアドバイスしてもらえます。書類の保存方法や支払方法についても指導を受けられるため、税務調査への備えにもなります。
長期的な税務戦略や資産対策の相談
税理士には、節税だけでなく相続税・贈与税の対策や、不動産・退職金制度の活用など、中長期的な税務戦略も依頼可能です。将来の事業承継や資産移転を見据えたプランニングを行うことで、今後の税負担を見据えた対策が実現します。総合的な税務管理のパートナーとして、税理士は節税と資産保全の両面で強い支援を行います。
税理士に節税対策を依頼するのがおすすめなケース
税理士への依頼はすべての納税者に必要というわけではありませんが、節税の効果が高く、税務の複雑さも増す一定の状況では、専門家のサポートが大きな助けになります。ここでは、税理士に節税対策を依頼するのがおすすめなケースを解説します。
所得や利益が大きくなってきたとき
個人事業主で課税所得が年間500万円を超えると、所得税率が20%の段階に入り税負担が重くなるため、節税策の重要性が増してきます。
このタイミングで税理士に相談すれば、青色申告や専従者給与、法人化の判断など、所得圧縮につながる具体的な提案を受けることができます。法人においても利益が安定してきた段階で節税策の選択肢が広がるため、早めの依頼が有効です。
複数の収入源や控除項目がある場合
副業収入、不動産所得、株式や暗号資産の売却益などがある場合、税計算が複雑化しやすくなります。また、医療費控除や住宅ローン控除、iDeCo・小規模企業共済などの控除も組み合わせによって効果が大きく変わるため、制度に精通した税理士の判断が安心です。控除の適用漏れや計算ミスを防ぐという意味でも、税理士のサポートは大きな安心材料となります。
税理士に節税対策を依頼する場合の契約形態・費用相場
税理士へ節税対策を依頼する場合、契約内容や料金体系は事務所ごとに異なります。ここでは、税理士との契約形態の種類と、かかる費用の相場を紹介します。
スポット契約と顧問契約の違い
税理士への依頼には「スポット契約」と「顧問契約」の2つの形態があります。スポット契約は確定申告や決算申告など単発の業務を依頼する形式で、個人事業主や副業会社員によく利用されています。一方、顧問契約は月次の会計処理や節税アドバイス、経営相談など継続的な支援を受けたい方向けの契約です。会社経営者や継続的に収入があるフリーランスには顧問契約が選ばれる傾向があります。
節税対策にかかる税理士報酬の相場
スポット契約で確定申告のみを依頼する場合、所得や業務内容にもよりますが費用の目安は3万円〜10万円程度です。医療費控除や不動産所得、複数事業がある場合などは追加料金が発生することもあります。顧問契約の場合、個人事業主で月額1万〜3万円、法人で月額2万〜5万円程度が一般的です。これに加えて、決算期には10万〜30万円前後の決算報酬が発生するケースもあります。料金体系は提供する業務範囲によって異なるため、事前に見積もりを取り、業務内容と費用のバランスを確認することが大切です。
節税対策に強い税理士を選ぶポイント
税理士に依頼することで節税効果を最大限に引き出すことができますが、誰に依頼するかによって結果は大きく変わります。ここでは、節税対策に強い税理士を選ぶためのポイントを解説します。
節税に関する実績や提案力を確認する
節税に強い税理士を選ぶ際は、これまでの実績や具体的な提案力に注目しましょう。申告業務をこなすだけでなく、顧客ごとに合わせた節税方法を提案できる税理士が理想です。無料相談や初回面談の場で、青色申告の活用や法人化のタイミング、控除制度の提案など、どのような視点で節税を考えているかを尋ねてみるとよいでしょう。実績が豊富な税理士は、同業他社や似たような収入構成を持つ顧客の事例をもとに、実用的な節税策を提示してくれます。
業種やライフスタイルに合った知識があるか確認する
税務は業種や働き方によって大きく異なるため、自分の立場に合った経験を持つ税理士を選ぶことが重要です。たとえば、IT系フリーランス、不動産投資家、飲食業など、それぞれの業種で適用できる控除や経費処理には違いがあります。また、副業や資産運用をしている会社員なども、所得の種類ごとに異なる節税アプローチが必要です。面談の際には、自分の業種や収入構成を説明し、それに即したアドバイスがもらえるかを確認しましょう。
コミュニケーションと対応力を見極める
節税対策は一度で終わるものではなく、継続的な相談と調整が必要です。そのため、税理士との相性や対応スピード、コミュニケーションの取りやすさも大切な要素です。質問への回答が明確でわかりやすいか、必要なタイミングでアドバイスがもらえるかなど、信頼して任せられる関係を築けるかどうかを見極めましょう。定期的な面談や相談がしやすい体制を整えているかも確認ポイントになります。長く付き合えるパートナーとして、誠実で丁寧な対応ができる税理士を選ぶことが、安心かつ効果的な節税対策につながります。
節税対策に強い税理士の探し方
節税に力を入れたい場合、単に税務処理を代行してくれる税理士ではなく、節税の知識と提案力に優れた税理士を見つけることが重要です。ここでは、節税に強い税理士を効率よく探すための方法を解説します。
税理士紹介サイトやマッチングサービスを活用する
近年では、税理士を検索・比較できる専門の紹介サイトやマッチングサービスが多数存在します。これらのサービスでは、節税・法人化・相続など得意分野ごとに絞り込みができ、自分の目的に合う税理士を探しやすくなっています。口コミや実績の評価も見られるため、選定の参考になります。また、無料で複数人の税理士と面談できるサービスもあるため、初めて依頼する人にとって安心感があります。
自分と同業の経営者・事業主から紹介を受ける
信頼できる税理士を探すうえで、同業の知人や経営者仲間からの紹介も有力な手段です。すでにその業種での実績がある税理士であれば、業界特有の経費処理や節税方法にも精通している可能性が高く、実践的なアドバイスが期待できます。紹介であれば最初から相性の合う可能性も高く、長期的な信頼関係を築きやすい点もメリットです。交流会や経営者向けの勉強会などでも、有益な人脈が得られることがあります。
専門性や節税の実績をホームページやSNSで確認する
税理士の事務所ホームページやSNSでは、その税理士の専門分野や考え方、節税事例などが紹介されていることがあります。「iDeCoや法人化支援に強い」「飲食店・フリーランス特化」など、強みを明記している税理士は節税提案にも積極的な傾向があります。ブログやコラムを公開している税理士も多く、そこから知識の深さや説明の分かりやすさを判断することもできます。
節税を成功させるには、税理士と連携して進めよう
節税を効果的に進めるためには、制度の正しい理解と実務への落とし込みが不可欠です。税理士は複雑な税法を踏まえたうえで、状況に応じた節税方法を提案し、申告まで一貫して対応してくれます。自己判断だけでは見落としがちな制度や控除も、専門家のサポートがあれば適切に活用できます。納税負担を最小限に抑えたいなら、信頼できる税理士と連携して節税対策を進めることが有効です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
家族信託で節税はできる?制度の仕組みと活用ポイントをわかりやすく解説
相続や贈与にかかる税負担をできるだけ抑えたいと考える中で、「家族信託」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。家族信託は、財産の管理や承継を円滑に行うための仕組みですが、使い方によっては節税にもつながる可能性があります。 本記事で…
詳しくみる不動産業の会社設立で定款に記載する事業目的の書き方
不動産業で法人を設立する場合、法人設立登記が必要です。不動産業には、種々の形態がありますが、法人登記そのものについては共通事項もたくさんあります。 そこで、この記事では不動産業における法人設立の基礎ともいえる定款についてとりあげ、中でも「事…
詳しくみる会社設立登記で委任状が必要なケースは?|無料ひな形・テンプレート付き
会社設立をするならば、知っておきたいのが登記についてです。何の書類が必要なのか、そして、どうやって提出しないといけないのかは必ず押さえておきたいポイントといえます。そこで、今回は、書類提出時に疑問に挙がりやすい「委任状」にスポットを当て、ど…
詳しくみる合同会社の設立代行のおすすめは?メリットやデメリット、選び方を解説
合同会社の設立代行サービスは、複数の分野の専門家が事業として行っているため、サービスの範囲などを確認して自社に適した業者を選択するのがおすすめです。そもそも設立代行では、どのような専門家が、どのような手続きを代行してくれるのでしょうか。合同…
詳しくみる山形県で会社設立する際のポイント!サービス利用料0円
山形県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる千葉県でお得に会社設立をする方法!流れ・専門家探しのコツ
千葉県での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる


