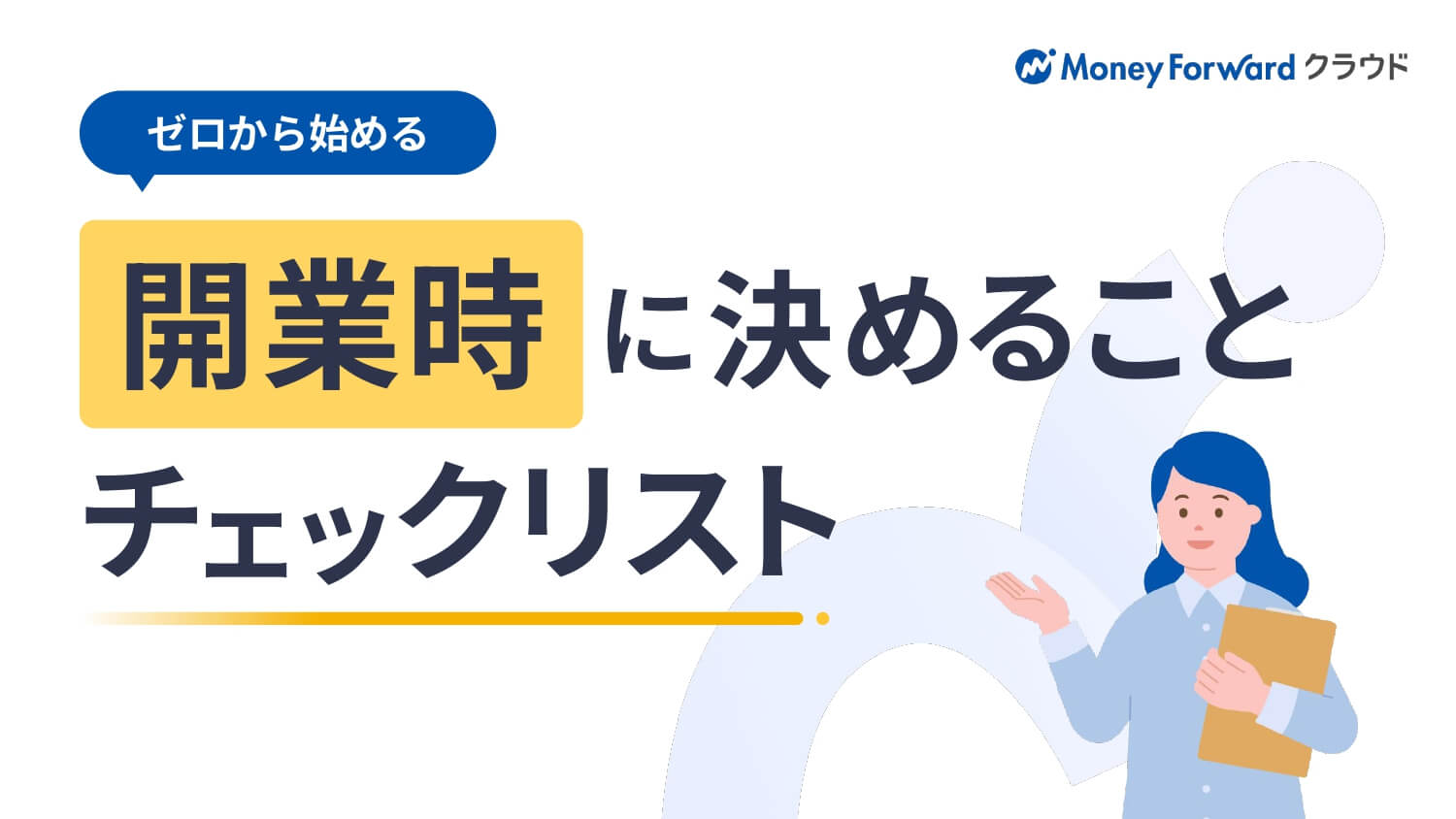- 更新日 : 2023年11月1日
仮想通貨投資で開業できる?必要な資格や税金対策・節税について解説
ビットコインなどの仮想通貨への投資額が増えると、税金対策として開業をした方がよいのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。仮想通貨投資もビジネスといえるほどの規模があれば開業できます。この記事では、仮想通貨投資の開業方法や税金についての注意点を解説していきます。
目次
仮想通貨投資で開業できる?
仮想通貨投資とは、ビットコインなどの暗号資産を購入して、購入時の価格よりも値上がりしたときに売却することで利益を得る投資手法です。結論からいうと、仮想通貨投資もすべてのケースではありませんが開業できる可能性があります。
まず、個人事業主の場合はビジネス規模(仮想通貨投資の年収300万円超が目安)であれば仮想通貨投資でも開業できます。
法人設立による開業は年収の目安などはありませんが、個人事業主で開業する場合と異なり、登記などの手続きの手間やコストがかかる点に注意が必要です。
なお、自身が仮想通貨に投資するのではなく、仮想通貨交換業登録を行い、仮想通貨の取引を提供する事業者として開業する方法もあります。
仮想通貨投資の開業に必要な免許や資格
仮想通貨への投資のみをビジネスとする場合は、開業に必要な免許や資格はありません。しかし、先述のように、仮想通貨が取引できる場所を提供する取引所を運営する場合は、仮想通貨交換業者の登録が必要です。
仮想通貨投資で開業する方法、流れ
仮想通貨投資の開業はどのような流れで行うのでしょうか。個人事業主で開業する場合と法人で開業する場合の2パターンを紹介します。
個人事業主で開業する流れ
後述しますが、個人事業主の仮想通貨投資による所得は、原則として個人事業主の所得区分である事業所得に該当しません。個人事業主で開業し事業所得として計上できるようにするためには、仮想通貨投資で一定以上の収入があることが求められます。
そのため、個人事業主での開業はすでに仮想通貨投資をやっていてある程度の収入がある人が対象になるでしょう。開業は以下の手順で行います。
- 仮想通貨投資の収入が300万円を超える
- 仮想通貨投資にかかわる帳簿書類を作成・保存しておく
- 税務署に個人事業の開業届を提出する
- 必要に応じて青色申告承認申請書を税務署に提出する
- 地方自治体に事業開始等申告書を提出する
法人で開業する流れ
法人は、法人税の計算で個人の所得のように所得区分が設けられているわけではないため、個人事業主のような仮想通貨投資の収入基準はありません。仮想通貨投資の年収300万円以下でも法人設立による開業ができます。
ただし、法人設立には登記のための初期費用がかかるほか、赤字でも法人住民税が発生することから、コスト面でのデメリットが生じる可能性があります。税金対策のためなら、仮想通貨投資である程度利益を出せるようになってから法人で開業するのが好ましいでしょう。
法人による開業は以下のような流れで行います。
仮想通貨取引での利益にかかる税金は?
仮想通貨取引の所得(利益から必要経費を控除した金額、法人の場合は益金から損金を控除した金額)にはどのような税金がかかるのでしょうか。個人事業主の場合と法人の場合に分けて解説します。
個人事業主の場合
個人の場合、仮想通貨投資による所得(譲渡などによる利益から必要経費を差し引いた額)は、原則として「雑所得」に区分されます。
しかし、先述のように、仮想通貨投資による年間収入が300万円を超え帳簿を作成・保存しているときは事業所得として申告することが可能です。(※会社員で継続的な事業として認められない副業は対象外となることもあります。)
事業所得は、雑所得と比べてさまざまなメリットがあります。青色申告の選択により最大65万円(電子申告または電子帳簿保存の場合)の青色申告特別控除を利用できるほか、所得の損益通算、翌年以降の純損失の繰越控除などができるためです。
例えば、赤字の場合、雑所得であれば赤字はなかったものとして切り捨てられますが、事業所得であれば赤字をほかの所得と相殺して課税所得金額を少なくできます。
なお、雑所得も事業所得も総所得金額を構成する所得です。総所得金額を構成するほかの所得金額を合算した金額から所得控除を行った課税所得金額に、所得税や住民税(約10%)がかかります。所得税は、以下の国税庁の速算表のように、課税所得金額ごとにより高い税率が適用される超過累進税率が適用される仕組みです。
引用:No.2260 所得税の税率(所得税の速算表より)|国税庁
法人の場合
法人を設立する場合、次のような税金がかかります。
- 法人税(原則23.2%、資本金1億円以下の法人で年800万円以下の部分は軽減税率が適用)
- 法人住民税(資本金や従業員数に応じた均等割+法人税割)
- 地方法人税(法人税の10.3%)
- 法人事業税(課税標準×所得額などで定められた法人事業税率)
- 特別法人事業税(法人事業税×特別法人事業税率)
上記のうち、仮想通貨投資の利益が赤字であっても発生するのが法人住民税です。均等割という仕組みで資本金と従業員数によって税額が固定されているため、利益がなくても支払いが生じます。
なお、法人については個人の所得税のように超過累進税率のような仕組みはありません。ある程度税率が固定されていることから、仮想通貨投資による利益が大きければ大きいほど、法人設立の方が税金面でのメリットは大きくなります。
仮想通貨の税金対策、節税方法や注意点
仮想通貨投資で開業したときの税金対策や注意点をいくつか紹介します。
利益確定の金額を抑える(個人の場合)
法人の場合、保有する暗号資産(活発な市場があるものに限る)は原則として時価で評価(期末時の価格で評価)することとされています。そのため、利益を確定させず持ち続ける方法は法人では効果がありません。
しかし、個人では有効です。個人(個人事業主)は、期末時に時価評価する必要がなく、利益確定時(譲渡の約定時など)に収益に計上すればよいためです。
たとえば、利益を確定させることにより、一段階高い所得税率が適用されるといった場面で使えます。ただし、利益の確定を調整する方法は、本来の投資の目的に合わず、売却のタイミングを逃すことでかえって投資に損失が生じる恐れもありますので注意が必要です。
ふるさと納税や各種控除を利用する(個人の場合)
事業の設備投資の税額控除がメインの法人と比べて、個人は利用しやすい税額控除(所得税額から直接控除するもの)や所得控除(課税所得の計算上合計所得金額から控除するもの)がいくつもあります。利用できる税額控除や所得控除は漏れなく利用して申告するのが個人の税金対策のポイントです。
代表的なものに、2,000円を超える地方自治体への寄附金額を所得控除できる「ふるさと納税」(※通常の寄附と異なり寄附の用途が指定できたり返礼品をもらえたりする)、住宅ローンを利用した一定の住居の取得で税額控除が適用される「住宅ローン控除」などがあります。
仮想通貨同士の損益を相殺する(個人の場合)
仮想通貨同士であれば、雑所得に該当する場合であっても損益通算ができます。例えば、ビットコインの利益50万円、イーサリアムの利益▲30万円であったとき、相殺して仮想通貨取引全体の利益20万円と計上できます。誤って利益ばかりを合算すると税金面で損をすることになりますので、複数通貨の取引や複数の取引所でのやり取りがあるときは、忘れずに損益と損失の相殺をしましょう。
給与所得を調整する(法人の場合)
法人の場合、役員に支払われる報酬(この場合、仮想通貨投資の開業のため法人設立をした人の報酬)は、給与所得に区分されます。給与所得は概算で給与所得控除が認められるのが特徴です。
まずは、役員報酬を給与所得控除の最低限度額の55万円を超える金額に設定して、そこから法人税や所得税とのバランスをみて調整するとよいでしょう。
なお、役員報酬を低く設定しすぎると内部留保が多くなり法人税額が増える一方で、役員報酬を高くし過ぎると個人の所得が増えて所得税額が多くなる特徴があります。複数パターンでシミュレーションをして、法人税額と所得税額を合算した額が小さくなるように調整するのがベストです。
ただし、役員報酬は損金算入に制限があります。頻繁に変更すると損金算入が認められなくなることに注意しましょう。
繰越控除や繰戻し還付を活用する
法人の場合、赤字は10年間の繰越控除が、個人の場合(※青色申告者に限る)は3年間の繰越控除が認められています。過去に赤字が発生して繰越控除できる額が残っている場合は本年度の所得金額と相殺できますので、漏れなく利用することをおすすめします。
なお、個人の場合は廃業する場合など繰戻し還付(過去申告した黒字で当年度の赤字を相殺すること)が適用できるケースは一部に限られますが、法人は廃業でなくても繰戻し還付を選択可能です。短期的な資金繰りを改善したいときは、繰越控除ではなく繰戻し還付を選択するのも方法のひとつでしょう。
仮想通貨投資の開業は個人と法人で異なる
仮想通貨投資の開業はできますが、個人事業主の開業と法人の設立では、税金面などで違いがあります。どちらを選択した方がよいかは仮想通貨投資の規模やほかの所得の関係もありますので、今回紹介した内容を参考に開業を検討してみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書の書き方<記入例付き>
個人事業主が従業員を雇用する場合には、税務署に提出が必要な書類があります。そのうちの1つが、「給与支払事業所等の開設届出書」です。 本記事では、個人事業主が「給与支払事業所等の開設…
詳しくみるクリニック開業の手順や必要な準備を解説
医師として収益を増やそうと考えた場合、独立して自身の診療所を開業するのも選択肢の一つです。今回は、内科や外科だけではなく、美容整形まで含めた「クリニック」を開業するにあたって準備す…
詳しくみる占い師は開業届の提出が必要?職業欄などの書き方も簡単に解説
仕事として収入を得て、占いを行うのが占い師です。収入を得るので原則、納税が発生します。そこで気になるのが、占い師に開業届が必要かどうかということです。実は、占い師には開業届が必要な…
詳しくみる居抜き物件とは?メリット・デメリットや開業までの流れ、契約にかかる費用などを解説
これから店舗やオフィスの開業を検討している方にとって、初期費用を抑える選択肢として居抜き物件があります。居抜き物件とは、前のテナントの内装や設備が残された状態で借りられる物件を指し…
詳しくみる屋台を開業するには?許可申請から出店場所、成功のコツまで徹底解説
自分のお店を持ちたいという夢を、比較的少ない資金で実現できる方法として屋台での開業が注目されています。しかし、手軽に見える一方で、食品を扱うための衛生管理や営業許可の取得など、事前…
詳しくみる不用品回収業の個人事業主として開業するには?必要な許可や確定申告も解説
不用品回収業を個人事業主として開業すると、古物商許可などが場合によって必要です。また、税務署に対して開業届の提出なども必要です。個人事業主として不用品回収業を始める際の手続きや許可…
詳しくみる