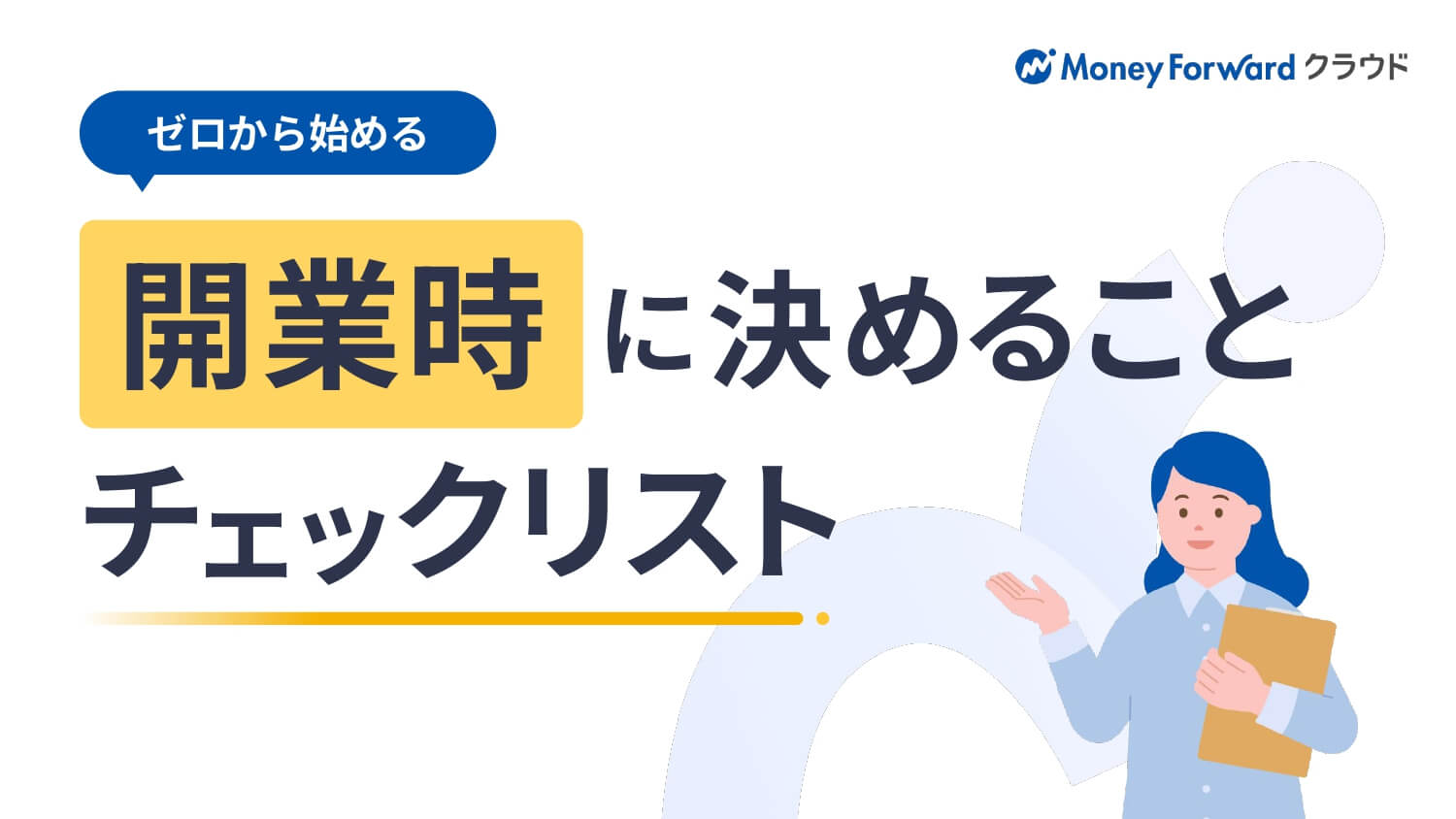- 作成日 : 2025年8月29日
塗装業で独立開業するには?失敗しない手続きや必要な資金、年収アップの秘訣まで解説
塗装職人として、独立開業を夢見ている方も多いのではないでしょうか。しかし、独立開業には「本当にうまくいくのだろうか?」という不安がつきものです。必要な手続きや資金、独立後の収入など、わからないことばかりで一歩を踏み出せずにいるかもしれません。
この記事では、塗装業の独立開業までのステップ、失敗を避けるための注意点、そして年収アップの秘訣まで分かりやすく解説します。
目次
塗装業の独立開業は儲かる?
まずは、塗装屋の独立後の年収の実態と、必要とされる経験年数の目安について見ていきましょう。
塗装屋の年収は400万〜1,000万円超
塗装屋として独立した場合の年収は、働き方や経営手腕次第で大きく変わりますが、平均的には500万円前後であり、努力や経営力次第では年収1,000万円を超えるケースもあります。
会社員時代と違い、売上が直接収入に結びつくのが独立開業の大きな魅力です。ただし、売上のすべてが収入になるわけではありません。売上から材料費、人件費(従業員を雇う場合)、車両の維持費、広告費、税金などの経費を差し引いたものが、最終的な自分の利益(所得)となります。
安定して高収入を得るためには、高い塗装技術力はもちろんのこと、継続的に仕事を受注できる営業力と、適切な価格設定やコスト管理といった経営能力が不可欠です。
塗装屋に必要な経験年数の目安は5年〜10年
「独立まで何年かかるのか?」という問いに、法律で定められた明確な答えはありませんが、一般的には5年〜10年の実務経験が一つの目安とされています。しかし、重要なのは年数そのものではなく、習得したスキルの質と幅です。
- 下地処理から中塗り、上塗りまで一連の工程を一人で完結できる技術力
- 現場全体を管理し、段取りを組むマネジメント能力
- お客様と円滑にコミュニケーションをとり、要望を正確に把握する折衝能力
- 材料費や人件費を考慮した、精度の高い見積作成能力
これらは最低限身につけておきたいスキルです。修行期間は、ただ塗装技術を磨くだけでなく、親方や先輩の仕事の進め方を経営者の視点で観察し、技術以外のスキルを吸収する貴重な時間と捉えましょう。
塗装業の独立開業に向けた具体的なステップ
独立の現実とリスクを理解したら、次はいよいよ具体的な準備です。周到な準備が、開業後の安定した経営を支えます。
1. 事業計画書の作成
まずは、自身の事業の設計図となる事業計画書を作成しましょう。提供するサービス内容、ターゲットとする顧客層、競合との差別化ポイント、料金設定、売上や利益の目標などを具体的に書き出します。
事業計画書は、資金調達の際に金融機関などに対して事業の将来性や返済能力を説明するための重要な書類となります。具体的で説得力のある計画を立てることが、円滑なスタートにつながります。
2. 開業資金の調達
事業の規模にもよりますが、独立開業に必要な資金は、初期費用と運転資金を合わせて300万円〜600万円程度が一般的です。
- 車両: 軽トラック、バン
- 道具一式: 刷毛、ローラー、マスカー、ヘルメット、安全帯
- 機材: 高圧洗浄機、コンプレッサー
- 材料費: 当面の塗料仕入れ費用
- その他: 事務所や倉庫の賃貸初期費用、広告宣伝費 など
これらに加え、開業後すぐには収入が安定しないことを見越し、最低でも3ヶ月〜半年分の生活費と運転資金を手元に用意しておくと安心です。自己資金で不足する場合は、日本政策金融公庫の創業融資や、地方自治体の制度融資の活用を検討しましょう。
3. 屋号の決定
屋号は、あなたのお店の顔です。顧客に信頼感を与え、覚えてもらいやすい名前を考えましょう。「ペンキ屋の独立で名前はどうするか」と悩む方は、以下のポイントを参考にしてください。
- 事業内容が伝わること
- 地域名を入れること
- 覚えやすく、言いやすいこと
- 他社と重複しないこと
4. 開業届の提出
個人事業として始める場合、事業を開始してから1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。
このとき、節税効果の高い「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出することを強くおすすめします。青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除など、税制上の大きな優遇が受けられます。手続きは国税庁のWebサイトからオンライン(e-Tax)でも可能です。
5. 建設業許可の確認
塗装工事は建設業の一種ですが、必ずしも「建設業許可」が必要なわけではありません。
ポイントは請負金額で、消費税を含んだ1件の工事の請負代金が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。個人の塗装屋として独立する場合、当面はこの範囲で活動することが多いでしょう。
しかし、将来的に公共工事の入札に参加したり、元請けとして大規模な工事を受注したりするには許可が必須になります。事業の拡大を見据えるなら、将来的な許可取得も視野に入れておきましょう。
6. 各種保険への加入
万が一の事故に備え、保険への加入は必須です。自分と事業、そしてお客様を守るために必ず手続きしましょう。
- 労災保険(特別加入制度)
一人親方でも加入できる国の保険です。加入には、労働基準監督署を通じた正式な申請手続きが必要です。 - 請負業者賠償責任保険
仕事中のミスで第三者に損害を与えた場合に備える保険です。補償範囲や補償金額は保険のプランによって異なるため、契約時にしっかり確認しましょう。
塗装屋の独立開業後の集客のコツ
どれだけ優れた技術を持っていても、お客様がいなければ事業は成り立ちません。ここでは、独立後に安定して仕事を受注するための集客のコツを紹介します。
人脈を頼りに最初の顧客を獲得する
独立当初は、前職の同僚や取引先、友人・知人など、これまでの人脈を頼りに仕事を紹介してもらうのが最も現実的です。一つひとつの仕事を丁寧にこなし、良い評判を広げてもらうことが次の仕事につながります。
また、地域の工務店やリフォーム会社などに挨拶回りをして、下請けの仕事をもらうのも有効な手段です。まずは着実に実績と信頼を積み重ねていきましょう。
地域の同業者や関連業者とのつながりを活用する
同業者はライバルであると同時に、重要なパートナーにもなり得ます。忙しくて手が回らない時に仕事を融通し合ったり、情報交換をしたりと協力できる場面は多々あります。地域の塗装組合や商工会などに加入し、人脈を広げることも有益です。
WebサイトやSNSを活用する
下請けだけでなく、利益率の高い元請けの仕事を獲得するには、インターネットの活用が不可欠です。
- Webサイト(ホームページ)
施工事例の写真やお客様の声を掲載し、技術力と信頼性をアピールします。無料のツールでも簡単なサイトは作成可能です。 - SNS(Instagram、Facebookなど)
日々の作業風景や、施工前後のビフォーアフター写真を投稿するのが効果的です。「#岡山市外壁塗装」のように地域名を含めたハッシュタグを活用し、近隣の潜在顧客に直接アプローチしましょう。
一人での独立開業が不安な場合の選択肢
「一人ですべてをこなすのは自信がない」と感じるなら、外部のサポートを活用するのも一つの選択肢です。
フランチャイズへの加盟
本部の知名度やブランド力を利用できるため、開業当初から集客面で有利に働くことがあります。経営ノウハウや研修といったサポートを受けられるメリットがある一方、加盟金やロイヤリティが発生し、経営の自由度が制限されるデメリットもあります。具体的な加盟金は数十万円〜数百万円、ロイヤリティは月商の数%程度が一般的です。
独立支援制度やコンサルティングの活用
塗装業界に特化した独立支援サービスや経営コンサルタントも存在します。事業計画の策定や資金調達、集客の仕組みづくりなど、専門家の視点から具体的なアドバイスを受けられます。費用はかかりますが、失敗のリスクを減らし、事業の成長を加速させるための投資と考えることができます。
塗装屋の独立開業に関してよくある質問
最後に、独立を考える方からよく寄せられる質問にお答えします。
塗装業の開業に必須の資格は?
塗装業を開業するにあたって、必須となる国家資格は特にありません。ただし、以下のような資格を保有していると、技術力の証明となり、顧客からの信頼獲得や公共工事の受注に有利に働きます。
- 塗装技能士(1級・2級): 塗装技術の高さを証明する国家資格です。
- 有機溶剤作業主任者: 溶剤を扱う現場での安全管理に必要な資格です。
- 足場の組立て等作業主任者: 塗装工事に不可欠な足場の組み立て作業に必要な資格です。
一人親方でも法人化すべき?
すぐに法人化(会社設立)する必要はありません。まずは個人事業主としてスタートし、年間の利益(所得)が800万円〜1,000万円を超えるあたりで法人化を検討するのが一般的です。法人化すると社会的な信用が高まる一方、社会保険への加入義務や経理業務の煩雑化といった側面もあります。税理士などの専門家に相談しながら判断しましょう。
確定申告はどうすればいい?
個人事業主は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間の所得と税金を計算し、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う義務があります。日々の売上や経費の記録をきちんとつけておくことが重要です。青色申告を行うためには複式簿記での記帳が必要になるため、会計ソフトを導入するとスムーズです。
塗装業での独立開業を成功させましょう
塗装業での独立開業は、大きな可能性を秘めた魅力的な挑戦です。その成功は、事前の入念な準備と、独立後も学び続ける姿勢にかかっています。
本記事で解説した、事業計画、資金準備、開業手続き、そして集客戦略といった各ステップを一つひとつ着実に実行していくことが、あなたの夢を現実に変えます。目の前の一軒一軒の塗装に心を込め、お客様からの信頼を積み重ねていくことが、何よりも確かな経営基盤となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
鹿児島県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
鹿児島県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する鹿児島県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始を…
詳しくみるダイニングバーの開業資金はいくら?店舗の運営費用や必要な資格も解説!
美味しい料理やお酒を提供するダイニングバーを開業したいと思っている方は多いのではないでしょうか。 この記事ではダイニングバーを開業する方法や実際に店舗として出すための段取り、開業時…
詳しくみる仙台市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
仙台市で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する仙台市内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる久留米市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ
久留米市で開業届を提出する際は、久留米市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、久留米市の管轄税務署…
詳しくみる和歌山市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
和歌山市で開業届を提出する際は、和歌山市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、和歌山市の管轄税務署…
詳しくみる株トレーダーは開業届を出すべき?個人事業主と認められないケースも解説
本業・副業を問わず、株式投資を行っている「株トレーダー」や「デイトレーダー」の方は、投資で利益が出た際には所得税を計算し納税しなければなりません。この場合、トレーダーであっても「開…
詳しくみる