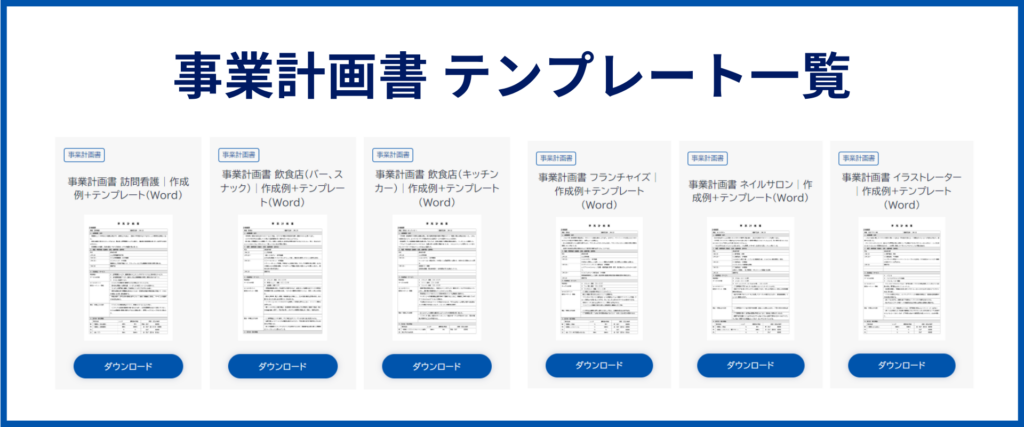- 更新日 : 2023年12月4日
個人事業主や一人親方でも建設業許可を取得できる?法人との違いも解説
建設業に従事したい場合、「会社に所属して従業員として働く」「会社を設立して代表者として働く」などの方法が一般的に考えられます。
また、これらの働き方以外に、個人事業主、一人親方として働くという方法もあります。個人事業主や一人親方が経営業務の管理責任者や専任技術者として建設業の許可を得る際の条件、手続きや必要書類についてご紹介します。
そして、将来事業を大きくしたいと考えている方は、個人事業主のままでいること、そして法人化することのメリット・デメリットについても押さえておきましょう。
目次
個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得できる?
まず、個人事業主(一人親方)であっても、建設業許可を取得できることは知っておいてください。特に、500万円(材料費含む・消費税込)以上の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要になるため、一人親方でも取得しておいたほうがビジネスチャンスが広がるといえるでしょう。
個人事業主のまま建設業許可を取得するメリット・デメリットとは?
個人事業主のままで建設業許可を取ることは可能です。では、個人事業主が建設業許可を取得するメリット、そしてデメリットを確認しておきましょう。
個人事業主のまま建設業許可を取得するメリット
個人事業主(一人親方)のまま建設業許可を取得するメリットは次の通りです。
- 法人に比べ、必要な経費が少ない
従業員が4人以下の個人事業主であれば、事業主として社会保険へ加入する義務がありません。なるべく経費を抑えたいというのであれば、個人事業主かつ従業員数が少ない状態で建設業許可を取るのがお得といえます。
また、各種手続きを行政書士などの専門家に依頼する場合、同じような手続きであっても、法人として依頼する場合より、個人で依頼するほうが費用を抑えられるケースが多々あります。
個人事業主のまま建設業許可を取得するデメリット
個人事業主のまま建設業許可を取るデメリットについても知っておきましょう。
- 仕事を取れないおそれがある
小さい会社、個人事業主が仕事をする場合、下請け業者として元請け業者から仕事を受注することがほとんどでしょう。ただし、法人のみに限定して仕事を依頼するという元請け業者もあります。個人事業主であったばかりに仕事を取れなかったということもあり得ますので注意が必要です。
- 仕事を取れないおそれがある
- 事業主が事業をやめた場合、後継者に建設業許可が引き継がれない
個人事業主本人が取得した建設業許可は、その人が事業をやめた場合や亡くなった場合、後継者に引き継ぐことができません。
- 事業主が事業をやめた場合、後継者に建設業許可が引き継がれない
後継者を立てるつもりがない場合は問題がないのですが、子どもなどの後継者がいる場合には、後継者が改めて建設業許可を取得する必要があります。その際は書類準備の手間や費用がかかるため要注意です。
- 法人化する場合は改めて建設業許可を取る必要がある
個人事業主が法人化する場合、すでに取得していた建設業許可は引き継がれません。改めて法人として建設業許可を取得する必要があります。
会社設立(法人化)して建設業許可を取得するメリット・デメリットとは?
ご参考のため、個人事業主のままではなく、会社設立(法人化)して建設業許可を取得するメリット・デメリットも把握しておきましょう。
会社設立(法人化)して建設業許可を取得するメリット
会社設立して建設業許可を取得するメリットは以下の通りです。
- 信用を得やすい
法人の規模が小さい場合、下請けとして仕事をする機会が多くなるでしょう。ただ、法人にしか仕事を依頼しないという元請け業者もあります。法人になっていることで信用を得やすく、仕事を増やすことが可能になります。
- 信用を得やすい
- 融資を受けやすい
金融機関からの融資を希望する場合、個人事業主に比べて法人のほうが信用度が高く、融資を受けやすい傾向があります。事業拡大を希望するならば、法人のほうが有利といえるでしょう。
- 融資を受けやすい
- 建設業許可の引き継ぎができる
個人事業主の場合は後継者に建設業許可の引き継ぎができませんが、法人の場合は引き継ぎ可能です。家族で建設業を経営しており、子どもに事業継承を行いたい場合でも、個人事業主に比べスムーズに引き継げます。
会社設立(法人化)して建設業許可を取得するデメリット
会社設立して建設業許可を取得するデメリットは次の通りです。
- 会社設立手続きが煩雑
会社設立時には、さまざまな書類の準備や定款の作成等が必要です。日常業務をこなしつつ、準備を進めることを面倒に感じる方もいるかもしれません。また、登記の際には費用がかかります。司法書士等の専門家に設立手続きを依頼することもできますが、この場合も費用がかかります。
- 会社設立手続きが煩雑
- 経費がかかる
法人になれば、社会保険への加入義務が生じます。従業員分も負担することになりますので、その分経費が増えることを覚悟しておく必要があります。
個人事業主が建設業許可を取得するための条件・必要書類は?
個人事業主が建設業許可を取得するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を置く
- 専任技術者を置く
建設業許可を取得するためには、上記の条件を満たすことはもちろんですが、請け負った契約を確実に履行する誠実性が求められます。また、一定の資金があることも条件です。具体的には次の条件のいずれかを満たす必要があります。
建設業許可申請は都道府県、2つ以上の都道府県で営業したい場合は国土交通大臣(都道府県経由)に提出します。ただ、条件や書類の準備が煩雑になるため、できれば行政書士などの専門家の手を借りながら手続きを行いましょう。
なお、建設業法の改正を受け、2020年(令和2年)10月1日から、法人の事業所(一人社長の場合も含む)や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は健康保険・厚生年金保険に加入していなければ、新規に建設業許可を取得できません。
個人事業主が経営業務の管理責任者になるための要件・必要書類は?
建設業許可を得るためには、経営業務の管理責任者になる必要があります。要件や必要書類を確認しましょう。
以下のいずれかに該当する人が経営業務の管理責任者として認められます。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること
申請の際は次の書類が必要です。
これらの経営経験、常勤性を証明する確認資料が必要になります。
個人事業主が専任技術者になるための要件・必要書類は?
個人事業主が専任技術者になるための要件を確認しましょう。なお、専任技術者は一般建設業と特定建設業とで要件が異なりますので注意してください。
はじめに一般建設業と特定建設業の主な違いを把握しておきましょう。
一般建設業:元請けとして仕事を受けた場合の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
特定建設業:元請けとして仕事を受けた場合の工事代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
その他、専任技術者の要件も一般建設業より特定建設業のほうが厳しくなります。
一般建設業の場合
一般建設業の場合は以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する
- 10年以上の業務経験を有する
- 国家資格者
- 複数業種に係る実務経験を有する
申請時に必要な書類は以下の通りです。
- 指定学科を卒業した証明
- 実務経験期間分の工事請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金を証明する通帳
- 保有国家資格の合格証明書
これらの現在の常勤性を証明する資料と技術者としての要件を証明する資料が必要になります。
また、提出書類は都道府県により若干異なる場合があります。
特定建設業の場合
特定建設業は一般建設業の場合より要件が厳しくなります。下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 国家資格者
- 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、元請けとして4,500万円以上の工事で2年以上の「指導監督的実務経験」があること
また申請時には、特定建設業許可の専任技術者要件を満たす確認資料と特定建設業許可の専任技術者になるべき者の「専任」の確認資料が必要になります。
建設業向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
建設業許可の申請手続きを確認した上で、法人成りを検討しましょう
個人事業主、一人親方であっても建設業の許可は取得できます。個人事業主であれば、経費が抑えられるといったメリットがあります。ただし、下請けを法人に限定している元請けからの仕事を受けられない、子どもなどの後継者に建設業許可の引き継ぎができないといったデメリットも忘れてはなりません。
個人事業主として建設業許可を取った後、法人化することもできますが、その際は再度建設業許可を取得する必要があります。また、法人化に伴い煩雑な手続きや諸費用もかかります。
今後事業の拡大を考えているのならば、法人化を検討する価値は大いにあるでしょう。その際は、必要な申請手続きについてもしっかり把握しておきましょう。
よくある質問
個人事業主でも建設業許可は取れる?
取得可能です。なお、500万円(材料費含む・消費税込)以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業主が建設業許可を申請する際の主な要件とは?
「経営業務の管理責任者を置く」「専任技術者を置く」ことが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業主の建設業許可を後継者に引き継ぐことはできる?
引き継ぎは不可です。改めて後継者が建設業許可申請を行わないといけません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
中小企業診断士の資格取得後に独立開業するには?フリーランスのキャリアパスを解説
「中小企業診断士の資格は取ったけれど、本当に独立して稼げるのだろうか?」 「開業準備は何から始めればいい?」このような不安や疑問を抱えていませんか? 実は、中小企業診断士の資格取得…
詳しくみるエステサロンは開業届の提出が必要?書き方や保健所への届出も解説!
個人事業としてエステサロンを開業する際、税務署に「開業届」を提出する必要があるか疑問に思う方もいるでしょう。所得税の届出の1つである「開業届」は、いつ、どのタイミングで提出すべきな…
詳しくみる静岡県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
静岡県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する静岡県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる青森県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
青森県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する青森県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみるバーの開業に必要な準備・資格は?店舗の設備資金など費用についても解説!
新型コロナウイルスのパンデミック発生から4年目を迎えた今、世界でも夜の街へ人が戻り始めてきました。日本でも、東京や大阪などの都市部を中心に夜のにぎわいが戻りつつあります。そんなアフ…
詳しくみる岐阜市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
岐阜市で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する岐阜市内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる