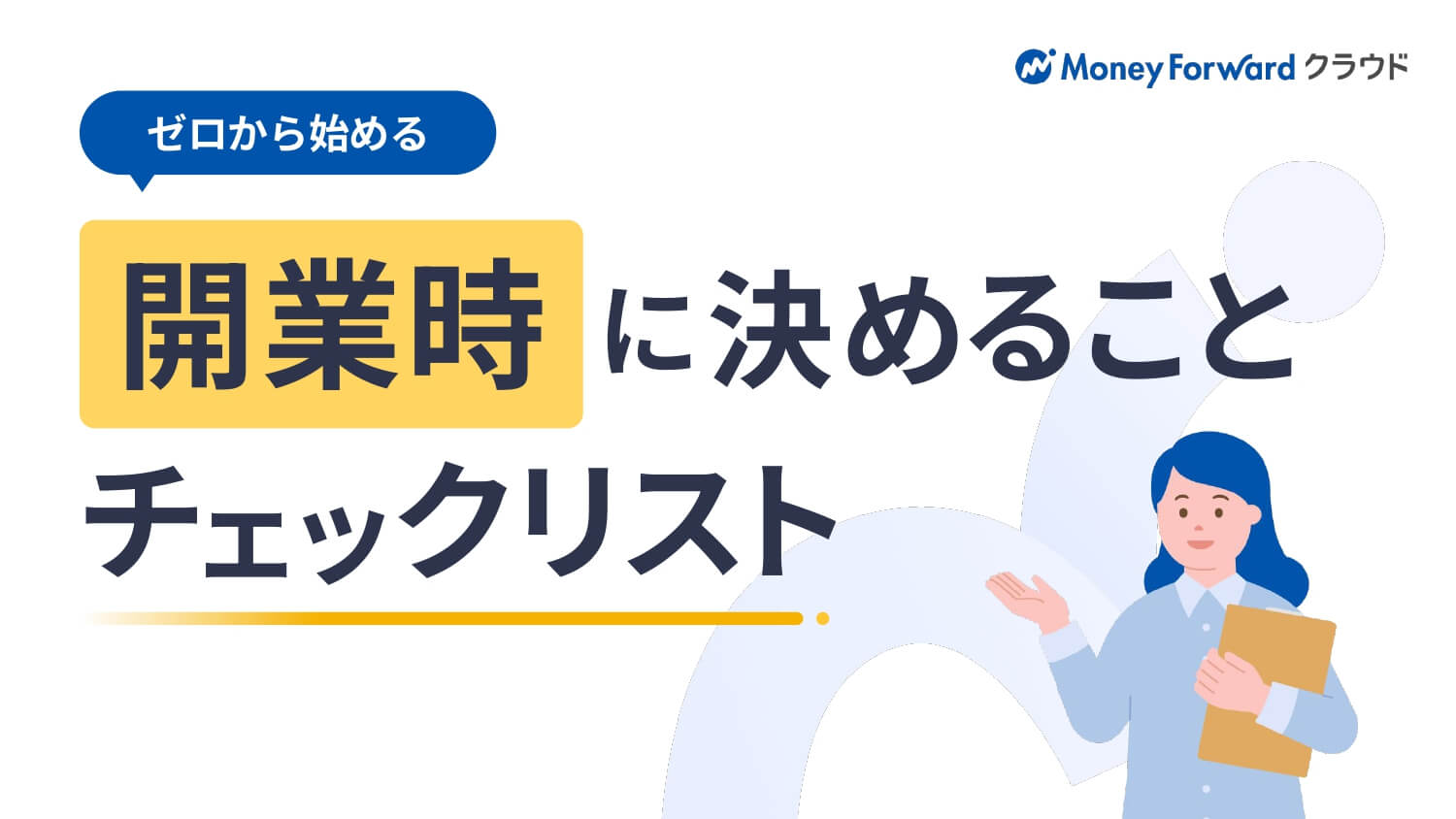- 作成日 : 2023年1月27日
ケーキ屋の開業方法は?必要な営業許可や資金、手続きを解説
個人事業主としてケーキ屋の開業を考えた場合、まずはどの程度の資金が必要なのかを考える必要があります。また、営業許可や開店までの手続きについても把握しておかなければなりません。
この記事では個人事業主がケーキ屋の開業をするまでの手続きや資金について解説します。開業資金の目安、そして儲けについてもご紹介しますので参考にしてください。
目次
ケーキ屋を開業する上で押さえるべきポイント
まず、知っておいてほしいのが、個人経営のケーキ屋や小さな焼き菓子屋の開業を取り巻く環境は非常に厳しいという点です。
同じような店はすでにたくさんある中で、開業し経営を続けるためには以下の点を確認しておく必要があります。
- 開店資金はいくらかかるのか、どうやって準備するのか?
- 開業までの手続きは何をすればいいのか?
- 儲けはどの程度出るのか?
ケーキ屋は憧れだけで始められる仕事ではありません。開業前、そして開業後の負担を少しでも軽減するためにも、必要な点は押さえておきましょう。
ケーキ屋の開業資金の目安
ケーキ屋の開業を考えるならば、初めに考えないといけないのが「資金」についてです。開業までにかかる資金、開業後にかかる資金を見ていきましょう。ここでは、次の業態で開業した場合の資金をそれぞれご紹介します。
- 店舗を借りて開業する場合
- 自宅で開業する場合
初期費用
開業前にかかる資金です。トータルの費用は内装・外装のレベル、店舗の場所により異なりますが、一般的な例で見ていきましょう。
| 店舗にかかる費用 | 保証金:家賃の6~10カ月分程度 仲介手数料:家賃の1カ月分 |
| 内装・外装にかかる費用 | 500万~1,000万円程度 |
| 設備・調理機器に関する費用 | 500万円前後 |
【店舗を借りる場合】
店舗を借りて開業するのであれば、家賃がかかります。また、保証金や仲介手数料、場合によっては礼金が必要です。保証金は家賃の6~10カ月程度ですので、家賃が15万円であれば、保証金は90万~150万円ということになります。まずは一括でこの金額を支払えるかを確認しましょう。
また、内装や外装、設備・調理機器に関する費用も準備してください。設備については初めのうちは中古でそろえるのもよいでしょう。費用を抑えたいのであれば、内装や外装も必要最低限の工事で済ませることを考えてください。状態がよい物件があれば、居抜き物件を借りるのもおすすめです。
【自宅で開業する場合】
「自宅でお菓子屋さんを開きたい」という方も多いのではないでしょうか。自宅の空いたスペースで開業する場合、家賃等はかかりません。そのため、月々の家賃のほか保証金や仲介手数料は節約できます。
しかし、設備・調理機器については店舗を借りる時と同様に費用がかかります。できるだけコストを抑えたい方は中古機器にするなどしてなるべく費用を抑えるようにしましょう。
また、居住スペースを店舗に改装する場合は内装・外装工事費用がかかる点にも注意が必要です。空調設備や清掃しやすい内壁を整える必要があります。また、立地場所によっては駐車場も整備する必要もあるでしょう。なお、駐車場の整備費用は200万円以上かかることもあります。
ランニングコスト
設備の費用、内装や外装に関する費用だけでなく、ランニングコストについても考えておかなければなりません。開店後数カ月は儲けが出ない可能性が高いため、事前に資金を準備しておきましょう。
ランニングコストとしてかかる費用は以下の通りです。
これらの中には、家賃や光熱費、人件費、保険料のように毎月必ず支払いが生じるものもあります。最低でも毎月数十万円はかかると見ておく必要があるでしょう。
開業資金の調達には補助金の支援や融資もおすすめ!
ケーキ屋開業までにかかる費用は数千万円程度かかることもあります。「とてもこんな金額を準備できない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで考えないといけないのが資金の調達方法です。開業資金の調達方法には以下のようなものがありますので確認しておきましょう。
【日本政策金融公庫の融資】
これから開業を検討している人、および事業開始後おおむね7年以内の人のための融資制度です。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、返済期間は設備資金の場合、20年以内、運転資金の場合は7年以内です。
その他、独自の補助金を用意している自治体もありますので調べてみてください。なお、融資や補助金の申請時には創業計画書や事業計画書などの提出が求められます。自分だけでは作れないという場合は、行政書士等の専門家の力を借りることも検討しましょう。
ケーキ屋開業の手続きの流れ
資金や店舗がそろっても、すぐにケーキ屋を開店できるわけではありません。必要な手続きがいくつもありますので押さえておきましょう。
開業に必要な書類
ケーキ屋を開業する場合に必要な書類は以下の通りです。
【融資を受けたい場合】
- 創業計画書
- 事業計画書
融資を受けたい場合は上記の書類を作成し、金融機関や日本政策金融公庫などに提出する必要があります。
【個人事業主としてケーキ屋を開業する場合】
- 開業届
個人事業主となる場合は、開業届を管轄の税務署に提出する必要があります。開業から1カ月以内に提出する決まりです。また、その際は「青色申告」「白色申告」を選択しなければなりません。
【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理についての書類】
個人で営むケーキ屋の場合、HACCP(衛生管理手法の一つ)の考え方を取り入れた衛生管理についての書類を保健所に提出します。具体的には以下の書類です。
- 衛生管理計画①
- 衛生管理計画②
- 記録簿
これらは菓子製造許可証を申請するのと同時に提出します。
申請の手続き
ケーキ屋開業までに必要な各種申請手続きを簡単に把握しておきましょう。
- 食品衛生責任者取得
- 飲食店営業許可の取得(イートインスペースを作る場合)
- 菓子製造業許可の取得
- 開業届の提出
詳しくは別途ご紹介します。
営業許可を取得する
ケーキ等の販売のみの場合は必要ありませんが、イートインスペースを設置するのであれば、「飲食店営業許可」の取得が必要です。「菓子製造業許可」の申請と同時に申請してください。
ケーキ屋は儲かるのか?
ケーキ屋の開業自体に問題がなくても、考えないといけないのが、きちんと利益が出るのかということです。事前に平均年収や成功するポイントなどを確認しましょう。
ケーキ屋の平均年収
ケーキ屋オーナーの年収は非常に幅があります。人気店のオーナーであれば、1,000万円以上の場合もありますが、平均は600万円ほどです。
ただし、店の立地、人気、経営手腕によって年収には個人差が出てきます。誰もが600万円ほど稼げるとは限りません。予想よりも収入が低くなってしまうという可能性も大いにあります。
ケーキ屋として成功する(失敗しない)ためのポイント
ケーキ屋として成功するためには以下の点を押さえておきましょう。
- 初期費用をかけすぎない
中古の調理機器、設備等を上手に活用しましょう。
- 初期費用をかけすぎない
- こだわりすぎない
「一等地でないといけない」「きれいなビルのテナントに入りたい」など、こだわりすぎると費用が余計にかかります。
- こだわりすぎない
- 生活費は確保する
保有する全ての資金を店舗経営につぎ込むことは避けましょう。儲けが予想よりも出ない時のために生活費は確保してください。
- 生活費は確保する
- ケーキ製造の技術だけでなく、経営も学ぶ
技術があっても、経営が下手であれば失敗する可能性が高くなります。ケーキ製造の技術のほかに経営についても学んでおきましょう。
ケーキ屋開業に必要な資格や営業許可
ケーキ屋開業に必要な資格・許可を見ておきましょう。
食品衛生責任者
開業の際は「食品衛生責任者」の資格が必要です。都道府県単位で行われる6時間ほどの「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで取得できます。ただし、調理師、栄養士、製菓衛生師の免許保有者は講習会の受講は不要です。免許保有者は申請のみで資格が取得できます。
菓子製造許可・飲食店営業許可
ケーキ製造を行う場合は「菓子製造許可」の申請が必要です。また、菓子製造・販売だけでなく、イートインスペースも作るのであれば、「飲食店営業許可」の申請も行ってください。飲食店営業許可は販売のみの場合は不要です。
ケーキ屋経営の確定申告
個人事業主としてケーキ屋を経営するのであれば、確定申告が必要です。
ケーキ屋経営で確定申告が必要な場合とは?
確定申告は、個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)、土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計が所得控除額を超えた場合に行います。基本的に事業を営んでいるのであれば確定申告は必要と考えておきましょう。
確定申告の方法
確定申告は対象となる年の翌年2月16日~3月15日の間に行います。確定申告書に必要事項を記載し、管轄の税務署に提出してください。
提出の方法は以下の通りです。
- 電子申告
- 郵送・持参で申告
確定申告についての詳細は以下もご覧ください。
設備や確定申告についてしっかり理解した上で、ケーキ屋を開業しよう!
個人がケーキ屋を開業する場合、最も不安に思うのが開業資金ではないでしょうか。なるべく節約したいのであれば、中古の機器を選び、内装・外装工事は複数の会社から見積もりを取って納得した上で決定するようにしましょう。
また、開業までには食品衛生管理者、菓子製造業許可や飲食店製造許可など必要な免許や許可がいくつもあります。開業に間に合うように、余裕を持ったスケジュールで申請することを心がけてください。
よくある質問
ケーキ製造販売スペースとイートインスペースを作りたい場合にはどの許可を取ればいい?
菓子製造業許可と飲食店営業許可を取ってください。詳しくはこちらをご覧ください。
食品衛生責任者講習は誰でも受けなければいけない?
調理師、栄養士、製菓衛生師の免許保有者は講習会の受講は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
弁理士の独立開業ガイド|廃業率や失敗しないためのポイント、経営者の年収まで解説
弁理士としてキャリアを積む中で、独立開業は大きな選択肢の一つです。自身の裁量で専門性を追求し、努力次第で勤務時代を大きく上回る収入を得られる可能性は、多くの弁理士にとって魅力的でし…
詳しくみる藤沢市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
藤沢市で開業届を提出する際は、藤沢市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、藤沢市の管轄税務署に提出…
詳しくみる弁護士が独立開業するには?年収やポイントを解説
弁護士のキャリアにおける大きな選択肢の一つ、「独立開業」。ご自身の専門性を活かし、より地域や社会に貢献したいと考える一方で、収入面や経営面の不安から、なかなか一歩を踏み出せないでい…
詳しくみるおにぎり屋を開業するには – 必要な手続きや費用、資格も解説!
手軽に利用できるなど、さまざまな理由でテイクアウトサービスを利用する人も増えています。おにぎり屋さんもテイクアウトに適したビジネス形態です。自身でおにぎり屋を開業しようと思った場合…
詳しくみるグループホームを開業するには?必要な資格・費用や資金調達方法を解説!
障害がある方や認知症など、支援が必要な方の住まいである「グループホーム」の開業を検討する際は必要な申請や資格を確認しなければなりません。また、資金をどう調達するかについても考える必…
詳しくみる盛岡市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
盛岡市で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する盛岡市内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる