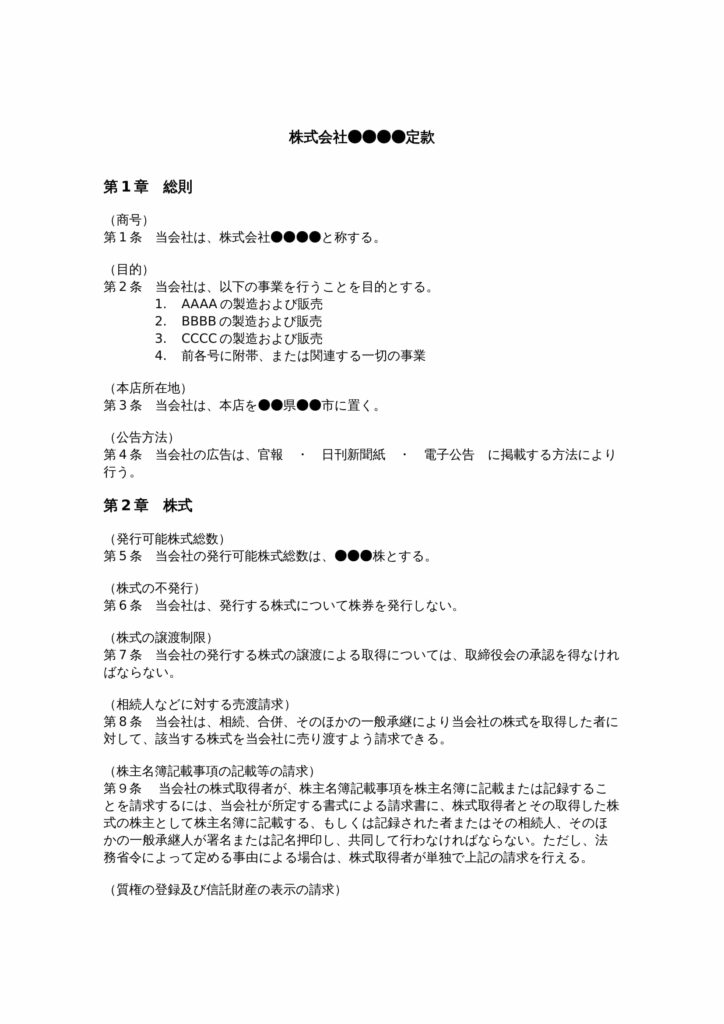- 更新日 : 2025年11月25日
法人登記の印紙代はいくら?0円や半額にする方法も解説
法人登記の際には、収入印紙でも納付することができる「印紙代」と呼ばれる費用が発生します。この印紙代には、主に「定款の印紙税」と「登録免許税」があり、それぞれ性質が異なります。
特に、会社設立時にかかる紙の定款作成での印紙税4万円は、電子定款を活用すれば0円にできます。 そのため、これから会社を設立する方は、紙の定款で手続きを進めるよりも、オンラインの電子定款を利用する方が設立費用を大きく節約できるでしょう。
また、法人登記にかかる「登録免許税」は、自治体の「特定創業支援等事業」を利用し、証明書を添えて申請すれば、半額に抑えることが可能です。
この記事では法人登記にかかる費用の内訳から、印紙代を安くする方法、会社形態別の総額までわかりやすく解説します。
目次
法人登記の印紙代とは?
会社設立時の法人登記で支払う「印紙代」には、主に「定款の印紙税」と「登録免許税」の2種類があります。これらはいずれも国に納める税金ですが、定款の印紙税は紙の定款を作成する場合に収入印紙で納付し、登録免許税は登記申請時に法務局へ納付します。
定款の作成で発生する「印紙税」
会社設立時に「定款」を紙で作成する場合に課される税金です。印紙税法にもとづき、4万円分の収入印紙を定款に貼り付けて納付します。ただし、電子定款は課税文書に該当しないため、印紙税は不要(0円)です。
そのため、紙の定款で手続きを進めるよりも、オンラインで電子定款を利用する方が、設立費用を大きく節約できます。
参照:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
登記手続きで納める「登録免許税」
登録免許税は、会社の設立や役員変更、本店移転といった登記手続きそのものに対して課される国税です。登録免許税法にもとづき、資本金の額などに応じて税額が決まります。
この税金は、紙の申請書を提出する場合に限り収入印紙で納付できますが、オンライン申請ではキャッシュレス納付が基本で、金融機関窓口での現金納付も可能です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
【会社形態別】法人設立時の印紙代はいくら?
会社設立時にかかる印紙代や登録免許税は、株式会社か合同会社かによって金額が異なります。電子定款を利用した場合の法人登記費用は、株式会社で約20万円〜、合同会社は6万円〜が目安です。
株式会社の設立費用
株式会社を設立する場合、定款の印紙税と登録免許税に加えて、公証役場で定款の認証を受けるための手数料が別途必要です。
株式会社の設立にかかる法定費用は、紙の定款で作成すると最低でも約24万2,000円〜、電子定款の場合は約20万円〜になります。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 定款の印紙税 | 4万円 | 電子定款の場合は0円 |
| 登録免許税 | 資本金の額 × 0.7% (最低15万円) | 資本金が約2,143万円以下の場合、一律15万円。特定創業支援等事業の証明書を提出すると半額(0.7%→0.35%、最低15万円→7.5万円)に軽減 |
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 資本金の額によって変動。一定要件を満たす場合は1万5,000円 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 1ページ250円で計算 |
【具体例】登録免許税の計算
登録免許税は「資本金の額 × 0.7%」または「15万円」のいずれか高い方の金額となります。
- 資本金が1,000万円の場合
10,000,000円×0.7%=7万円 →最低税額の15万円を納付 - 資本金が3,000万円の場合
30,000,000円×0.7%=21万円 →計算額が最低額を上回るため、21万円を納付
合同会社の設立費用
合同会社は、株式会社と異なり公証役場での定款認証が不要です。そのため、認証手数料や謄本手数料がかからず、設立費用を低く抑えられます。
紙の定款で作成した場合でも、合同会社の設立費用は最低10万円からとなります。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 定款の印紙税 | 4万円 | 電子定款の場合は0円 |
| 登録免許税 | 資本金の額 × 0.7% (最低6万円) | 資本金が約857万円以下の場合、一律6万円。特定創業支援等事業の証明書を提出すると半額 (0.7%→0.35%、最低6万円→3万円)に軽減 |
合同会社の場合も、電子定款を利用すれば定款の印紙税4万円は不要になり、設立費用をさらに圧縮できます。
法人登記の印紙代を安く抑える方法は?
法人登記の印紙代は、電子定款を利用することで印紙税4万円を0円にでき、さらに「特定創業支援等事業」を活用すれば登録免許税を半額にできます。 これら2つの制度を組み合わせることで、法人登記にかかる費用を大幅に抑えることが可能です。
特に会社設立時には大きな節約につながるため、事前に制度の内容を確認しておきましょう。
印紙税4万円を0円にする電子定款
法人登記の際にオンラインで電子定款を利用すると、定款にかかる印紙税4万円が0円になります。電子定款は、PDF形式で作成した定款に電子署名を付与する方法で、印紙税法上の「課税文書」に該当しないと定められています。そのため、紙の定款で必要だった4万円の印紙税が不要になります。
電子定款の作成に必要なもの
電子定款を自分で作成するには、以下を準備します。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)
- ICカードリーダライタ(PCでカードを読み取る機器)
- PDF作成ソフト(Adobe Acrobatなど)
- 電子署名用ソフト(JPKI利用者ソフトなど)
これらを使って作成した定款(PDF形式)に電子署名を付与します。準備が難しい場合でも、会社設立支援サービスや会計ソフト会社では、電子定款の作成を支援している場合があります。会社設立を考慮すると、代行サービスを利用する方が立ち上げまでスムーズになるケースも多いでしょう。
登録免許税を半額にする特定創業支援等事業
市区町村が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受け、発行された証明書を添付して設立登記を申請すると、設立時の登録免許税が半額になる制度があります。
この制度を利用することで、登録免許税は以下のとおり減額されます。
- 株式会社:最低15万円から7.5万円に減額
- 合同会社:最低6万円から3万円に減額
制度の概要と対象者
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法にもとづき、市区町村が商工会・金融機関・民間事業者などの支援機関と連携して、創業者を支援するサポート制度です。対象となるのは、主に以下の創業者です。
- これから事業を始める方
- 創業後5年未満の個人事業主または法人
- 自治体の窓口で相談:
まずは創業を予定している市区町村の商工担当課などで、制度の詳細を確認します。 - 支援事業への参加:
自治体が指定するセミナーの受講や、専門家による個別相談などの支援を受けます。 - 証明書の交付申請:
支援の修了後、自治体へ申請し「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付してもらいます。 - 登記申請時に提出:
会社の設立登記を申請する際に、この証明書を法務局へ提出することで、税額が減額されます。
登録免許税は、経費計上が可能
会社設立時に支払う登録免許税は、会計上「創立費」という勘定科目で経費計上が可能です。創立費は繰延資産として任意償却できるため、支払った際の領収書や納付書の控えは必ず保管しておきましょう。
参照:産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要|中小企業庁
会社設立後も特許免許税の印紙代は必要?
会社設立後も、役員や本社所在地、事業目的などに変更が生じた場合は、その都度、変更登記を申請しなくてはなりません。この変更登記にも1万円〜6万円程度の登録免許税がかかります。どのような手続きにいくらかかるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
| 変更登記の種類 | 登録免許税額 | 備考 |
|---|---|---|
| 役員変更(就任・退任・重任など) | 3万円 | 資本金の額が1億円以下の会社は1万円 |
| 本店移転(管轄内) | 3万円 | 同一の法務局の管轄内での移転 |
| 本店移転(管轄外) | 6万円 | 異なる法務局の管轄への移転(旧本店所在地・新本店所在地で各3万円) |
| 目的変更 | 3万円 | 事業内容の追加・変更 |
| 商号変更 | 3万円 | 会社名の変更 |
| 増資(募集株式の発行) | 増加した資本金の額 × 0.7% (最低3万円) |
これらの費用のほかに、登記手続きを司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。一般的に数万円程度の報酬がかかりますが、自分で登記手続きを行うことで、専門家への報酬分を節約することも可能です。ただし、登記内容に不備があると補正や再申請が必要になるため、手続きに不安がある場合は司法書士への依頼を検討すると安心です。
登記申請書と定款への収入印紙の貼り付け方は?
法人登記を申請する際に、紙で作成した定款や紙の申請書で登録免許税を納めるには、税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付ける必要があります。購入場所や貼り付け方には決まりがあるため注意しましょう。
登記申請書への収入印紙の貼り付け方
登録免許税を納付するための収入印紙は、登記申請書(または収入印紙貼付台紙)の所定の欄に貼り付けます。この際、貼り付けた収入印紙には絶対に消印(割印)はしないでください。
消印は法務局の職員が行います。申請者が押印してしまうとその収入印紙は無効扱いとなり、再購入が必要になるため気をつけましょう。
定款への収入印紙の貼り付け方
紙で作成した定款には、印紙税4万円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。これは登録免許税と異なり、必ず消印が必要です。
- 貼り付け場所:定款の表紙の裏面など余白部分に貼り付けます。
- 消印の方法:収入印紙と定款の用紙にまたがるように、発起人全員(または代理人)の印鑑を押します。この消印によって、印紙の再利用を防ぎます。
もし収入印紙を誤って貼り付けた場合や、登記申請が却下された場合でも、所定の手続きを行えば印紙税の還付を受けられる可能性があります。
収入印紙のおもな購入場所
収入印紙は、郵便局や法務局内、コンビニエンスストアなどで購入できます。高額な収入印紙は取り扱いがない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
- 郵便局:最も確実な購入場所。ほとんどの額面の収入印紙を取り扱っています。
- 法務局内の印紙売りさばき所:登記申請の直前に購入できるため便利です。
- 金券ショップ:額面より安く購入できる場合がありますが、在庫や取扱額面が限られることがあります。
- コンビニエンスストア:200円など低額の収入印紙のみの取り扱いがほとんどです。
法人登記の印紙代を理解して設立費用を最適化しよう
法人登記で必要となる印紙代は、主に「定款の印紙税」と「登録免許税」の2つです。定款の印紙税4万円は電子定款を利用すれば0円にでき、設立時の登録免許税も特定創業支援等事業を活用すれば半額に抑えられます。
株式会社であれば約20万円から、合同会社であれば約6万円からと、会社形態によっても設立費用は大きく異なります。
設立後も、役員変更などの登記手続きでは登録免許税が発生します。そのため、費用についての正しい知識は不可欠です。これらのポイントをふまえ、自社に合った方法で賢く費用を管理し、円滑な事業スタートにつなげましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主の法人化で合同会社を選ぶメリットは?手続きの流れをまとめて解説
合同会社を選択して法人化すれば設立費用を抑えられ、比較的自由度の高い経営が実現できるでしょう。個人事業主が法人化で合同会社を選ぶことには、このようにいくつかのメリットがありますが、…
詳しくみるネイルサロンは法人化すべき?売上目安としない方がいいケース
ネイルサロンは法人化することで経費の幅が広がったり、融資を受けやすくなったりするメリットがあります。ただし、個人事業と法人ではさまざまな違いもあるため、法人化する際には注意が必要で…
詳しくみる法人化しないデメリットは?個人事業主のままで得するケースや経費計上について解説
個人事業主は事業規模が大きくなっても、法人化しない方がいいケースもあります。あえて個人事業主のままでいることで得するケースや、経費計上など法人化する方が得するケースについてまとめま…
詳しくみる軽貨物運送で法人化すべきタイミングは?メリット・デメリットや必要な手続きを解説
軽貨物運送事業の法人化を検討すべきタイミングは、事業規模を拡大しようとするときと所得金額が増えたときです。事業が軌道に乗ると、売上や利益の増加を目指すのは自然なことであり、法人化は…
詳しくみる部活の法人化とは?メリット・デメリットや成功事例を解説
部活の法人化とは、学校の部活動を運営するための法人を立ち上げることです。一般社団法人として法人化するケースがあり、近年では大学の部活動が法人化する事例も見られます。 本記事では、部…
詳しくみる法人化で後悔する理由とは?節税にならないケースやあえて法人化しない選択肢も解説
法人化(法人成り)は、節税や社会的信用の獲得といった大きなメリットがある一方で、準備不足のまま進めると「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが後を絶ちません。 この記事では、法…
詳しくみる