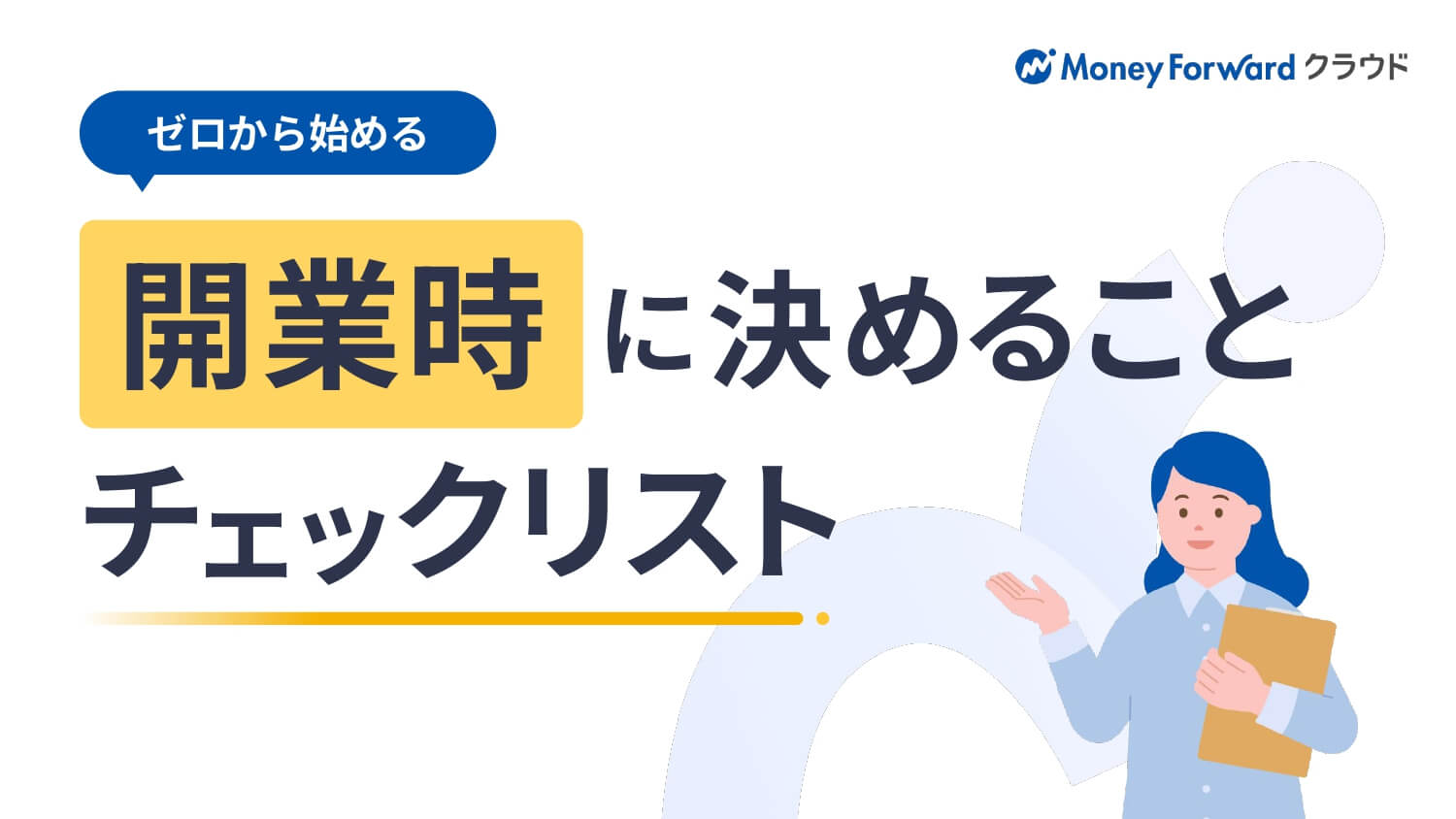- 作成日 : 2025年9月16日
就労継続支援B型で開業するには?事業計画から指定申請、つぶれるリスクまで解説
近年、多様な働き方を支える社会的な需要の高まりを受け、就労継続支援B型事業所の開設に関心が集まっています。障害のある方が自分のペースで働き、社会参加を実現するための重要な拠点ですが、その開業には専門的な知識と周到な準備が求められます。
この記事では、就労継続支援B型で開業するまでの具体的な流れ、必要な資格と人員配置、開設費用の詳細、そして活用できる補助金について詳しく解説します。
目次
そもそも就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスの一つです。障害や難病のある方が、雇用契約を結ばずに、軽作業などの生産活動を通じて就労訓練を行います。自分の体調や能力に合わせて比較的自由に働ける点が特徴で、利用者は生産活動への対価として工賃を受け取ります。社会貢献性が高く、地域社会に不可欠な存在としてその役割が期待されています。
就労継続支援B型の役割
就労継続支援B型事業所の主な役割は、障害のある方々へ就労の機会を提供し、その対価として工賃を支払うことです。しかし、その意義は単なる作業場所の提供にとどまりません。利用者が日中の活動拠点として通い、仲間との交流を通じて社会的なつながりを育む場でもあります。地域社会の一員として孤立することなく、自己肯定感を高めながら生活リズムを整える、こうした多面的な支援を通じて、利用者の自立した生活を支えるという重要な社会的使命を担っています。
A型や移行支援との違い
就労継続支援サービスにはA型とB型があり、他に就労移行支援というサービスもあります。
- A型との違い
A型は事業者と利用者が雇用契約を結び、原則として最低賃金が保障される働き方です。一方、B型は雇用契約がないため、利用者は自分のペースで通所し、作業内容や時間を調整しやすい環境が提供されます。 - 就労移行支援との違い
就労移行支援では、一般企業での就職を実現するために、職業訓練や就職活動の支援を中心に行います。利用期間は原則2年と定められています。B型は、すぐに一般就労することが難しい方へ、長期的な視点で働く場を提供します。
B型事業所の開設を検討する際は、この非雇用型という特性と役割を深く理解し、利用者に寄り添った事業モデルを構築することが成功への第一歩です。
就労継続支援B型の開業は儲かる?
就労継続支援B型は福祉制度を基盤に運営される事業であり、「儲かるのか」という問いは適切ではありません。「経営が継続できるかどうか」や「安定した運営が可能か」と言い換える方が制度の趣旨に即しています。
就労継続支援B型の収益は、主に国保連を通じて国から支払われる訓練等給付費と、事業所での生産活動収入で成り立っています。
訓練等給付費
事業所の最も大きな収入源は、訓練等給付費です。これは、利用者一人ひとりへのサービス提供に対して支払われる公的な報酬で、事業所の定員や職員の配置体制、利用者の利用日数などによって単価が決まります。
安定した収益を得るには、利用定員に対する稼働率を高く維持することが基本です。また、手厚い人員配置や専門職員の配置、利用者の工賃向上に向けた取り組みなどを行うことで、基本報酬に上乗せされる各種加算を算定でき、これが収益向上に直結します。
生産活動収入
もう一つの収入が、利用者が行う生産活動から得られる売上です。パンの製造販売、部品の組み立て、ウェブサイト制作、データ入力など、事業所ごとに多様な活動が行われています。
この生産活動で得た収入から、原材料費などの経費を差し引いた分が、利用者の工賃として支払われます。魅力的な商品やサービスを開発し、販路を拡大することで生産活動収入を増やすことは、利用者の工賃向上と経営の安定化につながります。
就労継続支援B型事業所の開設に必要な資格・要件は?
就労継続支援B型事業所を開設するには、障害者総合支援法で定められた人員基準を満たす必要があります。特に専門性が求められる役職があり、それぞれの要件を正確に把握しておくことが不可欠です。
| 職種 | 配置基準・役割 | 主な資格・要件 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所に1人 事業所全体の運営管理(職員のマネジメント、収支管理、行政手続きなど) | 特になし ただし、社会福祉主事任用資格や社会福祉事業での実務経験が求められる場合がある。 |
| サービス管理責任者 (サビ管) | 定員60人以下:1人以上(管理者が兼務可能) 個別支援計画の作成、サービス品質の管理など、支援の中心的な役割 | 一定の実務経験に加え、指定の研修の修了が必要。 |
| 職業指導員 | 1人以上 生産活動における専門的な技術指導や助言 | 特になし |
| 生活支援員 | 1人以上 日常生活の相談、健康管理のサポート | 特になし 介護福祉士や社会福祉士などの有資格者は歓迎される。 |
なお、職業指導員と生活支援員は、常勤換算方法で、その合計数が前年度の利用者数を10で割った数以上であることが基本となります。
就労継続支援B型を開業するまでのステップは?
事業所の開業は、思い立ってすぐにできるものではありません。法人設立から行政への指定申請まで、計画的に進めるべき多くの段階があります。
1. 法人設立と事業計画の策定
最初のステップは、事業の土台となる法人を設立することです。株式会社、合同会社、NPO法人など、それぞれの特性を理解し、自身の目指す事業形態に合った法人格を選びます。
同時に、事業の理念、サービス内容、収支見込みなどを詳細に記した事業計画書を作成します。事業計画書は、後の資金調達や指定申請において、事業の実現可能性を示す重要な書類となります。明確で説得力のある計画を練り上げましょう。
2. 物件選定と人員確保
次に、事業の拠点となる物件を探し、設備基準を満たしているかを確認します。都市計画法や建築基準法、消防法などの関連法規もクリアする必要があるため、専門家の助言を得ながら慎重に選定を進めましょう。
並行して、管理者やサービス管理責任者をはじめ、必要な人員の確保に動きます。特に一定の実務経験が求められるサービス管理責任者は、採用が難航することもあるため、早めに募集を開始することが成功のポイントです。
3. 指定申請と審査
全ての基準を満たす見込みが立ったら、管轄の自治体(都道府県または指定都市)の担当部署と事前協議を行います。ここで書類の不備や計画の問題点を指摘してもらい、修正を重ねます。協議を経て正式な申請書類を提出し、受理されると、現地調査を含む審査が行われます。
審査を無事に通過すれば、指定通知書が交付され、晴れて事業を開始することができます。申請から指定までは数ヶ月を要するため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。
就労継続支援B型の開設費用はいくらかかる?
就労継続支援B型の開業にかかる費用は、物件の規模や立地、事業内容によって大きく変動しますが、一般的に初期投資として500万円から1,000万円以上が必要となるケースが多いです。
初期費用
- 法人設立費用:約10万円~30万円(合同会社か株式会社かによる)
- 物件取得費:約100万円~(敷金、礼金、仲介手数料など)
- 内装工事費:約200万円~(物件の状態や規模による)
- 備品購入費:約100万円~(事務用品、パソコン、作業機材、送迎車両など)
運転資金
開業後すぐに収益が安定するわけではないため、数ヶ月分の運転資金を準備しておくことが不可欠です。人件費、家賃、水道光熱費、消耗品費など、少なくとも3〜6ヶ月分の運営費を確保しておくと、安心して事業をスタートできます。
就労継続支援B型で活用できる補助金・助成金は?
事業所の開設や運営にかかる経済的な負担を軽減するため、国や自治体は様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらを活用することで、初期投資や運営コストを抑えることが可能です。
- 創業支援系の助成金・補助金
各自治体が独自に設けている、新規事業立ち上げを支援する助成制度 - 設備整備の補助金
バリアフリー化のための改修費用や、生産活動に必要な機械の導入費用の一部が補助される制度 - 人材採用・育成の助成金
厚生労働省が管轄する人材開発支援助成金や、特定の条件を満たす従業員を雇用した場合に支給される助成金など - 民間財団の助成金
公益財団法人などが公募する助成金
補助金や助成金は、公募期間が短かったり、申請手続きが複雑だったりすることが多いです。また、補助金は原則として後払いのため、一時的な立て替え資金が必要になる点に注意しましょう。常に最新の情報を確認し、必要であれば行政書士や社会保険労務士などの専門家への相談も有効です。
就労継続支援B型で失敗しないための運営戦略は?
残念ながら、すべての事業所が順調に運営できるわけではありません。失敗の主な原因は、利用者が集まらないことによる収益不足、人材の確保・定着の失敗、そして生産活動の不振です。
これらのリスクを避けるためには、開業準備の段階から明確な戦略を持つことが重要です。
- 地域のニーズを捉えた差別化
ITスキルやデザイン、農業、eスポーツなど、特定の分野に特化することで、他の事業所との差別化を図り、独自の強みを打ち出します。 - 安定した利用者確保のための営業活動
地域の相談支援事業所やハローワーク、特別支援学校などへ地道に足を運び、信頼関係を築くことが、安定した利用者紹介につながります。 - 魅力的な生産活動と工賃向上
利用者がやりがいを感じられ、かつ収益性の高い生産活動を企画することが重要です。企業からの下請けだけでなく、自主製品を開発して販路を開拓するなどの努力が、工賃向上と経営の安定につながります。
就労継続支援B型の開業を成功に導きましょう
就労継続支援B型事業所の成功には、明確なビジョンと準備が欠かせません。事業の基本理念を確立し、資格を持つ人材を確保し、詳細な資金計画を立て、行政手続きを着実にクリアしていく必要があります。特に、開設費用を抑えるための補助金・助成金の活用や、安定経営の基盤となる収益構造への深い理解は、事業の持続性を大きく左右します。本記事が、皆さまの開業準備を進めるうえで少しでもお役に立てれば幸いです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
中小企業診断士の資格取得後に独立開業するには?フリーランスのキャリアパスを解説
「中小企業診断士の資格は取ったけれど、本当に独立して稼げるのだろうか?」 「開業準備は何から始めればいい?」このような不安や疑問を抱えていませんか? 実は、中小企業診断士の資格取得…
詳しくみる新潟県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
新潟県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する新潟県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる新規開業を成功させるには?自己資金なしの融資や開業届などの必要書類についても解説
新規開業は、資金調達や複雑な手続きなど、多くの不安がつきものです。「自己資金がなくても事業は始められるのか」「融資の審査は厳しいのではないか」「開業届の手続きはどうすればいいのか」…
詳しくみるサンドイッチ屋として独立開業する方法は?キッチンカーのメリットや必要資金も解説
18世紀後半にイギリスの第四代サンドイッチ伯爵にちなんで名付けられたとされる「サンドイッチ」。日本へは明治時代に伝わり、第二次世界大戦後のパン食文化の広がりとともに一般化しました。…
詳しくみる皮膚科を開業するには?必要な資格や資金、手続きの流れなどを解説
皮膚科医として経験を積み、専門知識を深める中で、「自身のクリニックを持ち、理想とする医療を提供したい」と考える先生方も多いことでしょう。地域に根ざし、患者さん一人ひとりと向き合い、…
詳しくみるフリーランス・個人事業主必見!家事按分を活用して生活費を経費にするための5つのポイント
フリーランス・個人事業主になると、様々な税金の負担が大きく感じるようになります。そのような時には、普段使っているお金の一部を費用として仕分けられる家事按分を活用した節税がおすすめで…
詳しくみる