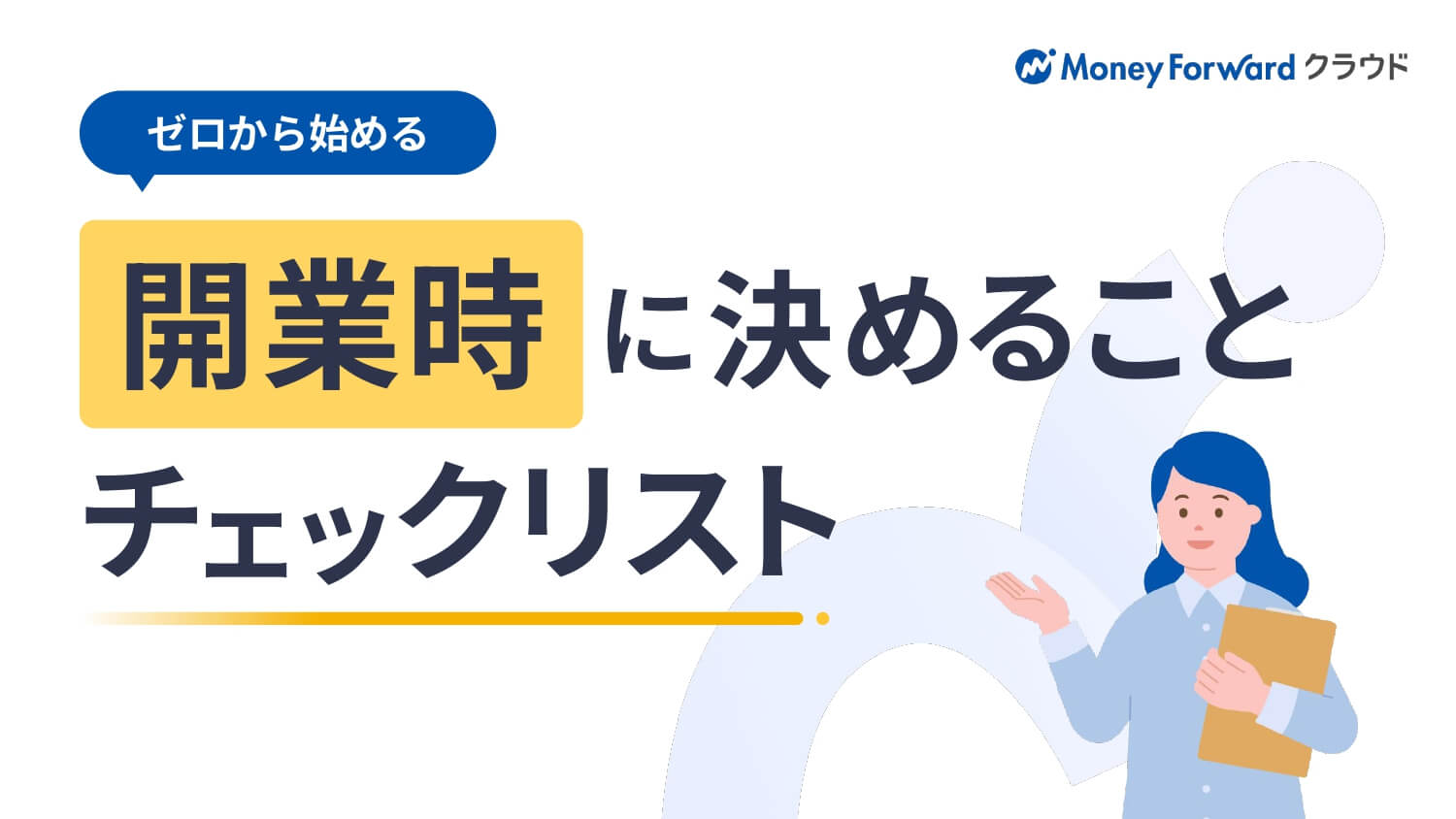- 作成日 : 2025年9月16日
児童発達支援事業所を開設するには?必要な資格や立ち上げ手順、助成金なども解説
近年、発達に特性のある子どもたちへの支援ニーズは高まり続けており、社会的意義の高い児童発達支援事業所の開業を志す方が増えています。子どもたちの成長を支えるやりがいのある仕事である一方、「本当に事業として成り立つのか」「児童発達支援事業所は儲かるのだろうか」といった収益性に関する不安や、「放課後等デイサービスの経営は厳しい」という声も聞こえてきます。
この記事では、児童発達支援事業所の開業を具体的に検討している方へ向けて、事業の収益モデルや経営の現実、開業までの具体的なステップ、必要な資格や施設基準、そして資金調達に役立つ助成金に至るまで詳しく解説します。
目次
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
児童発達支援事業所の開業を考える際、よく似たサービスとして放課後等デイサービスが挙げられます。両者は障害のある子どもや発達に課題のある子どもを支援する障害児通所支援サービスという点で共通していますが、対象となる子どもの年齢が明確に異なります。
- 児童発達支援
主に小学校に就学する前の障害のある子どもが対象です。日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練など、幼児期の発達支援を中心に行います。 - 放課後等デイサービス
就学児(小学生・中学生・高校生)が対象です。学校の授業終了後や休業日に、生活能力の向上のための訓練や、社会との交流促進などを行います。
児童発達支援事業所の収益モデル
児童発達支援の主な収入源は、国や自治体から支払われる訓練等給付費です。この給付費は利用者一人あたりの単価が決まっており、提供したサービスの対価として約9割が支払われ、残りの約1割を利用者が負担します(ただし、生活保護世帯や住民税非課税世帯では、自己負担が免除される場合があります)。
したがって、児童発達支援の収益モデルは、利用定員を安定的に満たし、サービスの稼働率を高く保つことで成り立ちます。さらに、専門職員の配置や支援内容に応じて設定されている各種加算を取得することで、さらなる収益向上も見込めます。
児童発達支援事業所の経営は厳しいと言われる理由
安定した収益モデルがある一方で、児童発達支援の経営は厳しいという声も少なくありません。その背景には、以下のような要因が挙げられます。
- 人材の確保難と人件費の高騰
専門性の高い人材の確保は容易ではなく、採用競争の激化は人件費の高騰に直結します。 - 制度改正のリスク
数年ごとに行われる法改正により、報酬単価が変動する可能性があります。 - 競争の激化
ニーズの高まりとともに事業所数も増加しており、近隣に競合事業所が増えれば利用者獲得の競争が激しくなります。
質の高い療育と安定した運営を両立させるための、確かな経営手腕が求められるのです。
児童発達支援事業所の経営者の年収
児童発達支援事業所の経営者の年収は、事業所の規模や運営状況によって大きく変動します。開業初期や定員10名程度の小規模な事業所の場合、経営が軌道に乗るまでは経営者の役員報酬を十分に確保できないケースも珍しくありません。まずは事業所の経営を安定させ、確固たる収益基盤を確立することが最優先となります。
児童発達支援事業所を開設するための手順
児童発達支援事業所の開業には、法令で定められた基準を満たし、行政から指定を受けるための周到な準備が不可欠です。ここでは、開業までの具体的な流れを解説します。
1. 事業計画の策定と法人格の取得
まず、事業の理念や提供するサービス内容、収益予測などを盛り込んだ事業計画書を作成します。児童発達支援事業所を運営するには、株式会社、合同会社、NPO法人などの法人格が必要です。個人のままでは開業できないため、事業計画と並行して法人設立の手続きを進めます。この段階で、事業の骨格を固めることが大切です。
2. 物件の選定と確保
事業計画に沿って、児童発達支援事業所の施設基準を満たす物件を探します。指導訓練室や相談室、事務室などの必要なスペースを確保できるか、建築基準法や消防法に適合しているかなどを確認し、賃貸契約または購入を行います。利用者の通いやすさや周辺環境も考慮すべき点です。
3. 資金調達の実行
初期費用が高額になりやすいため、自己資金だけですべてを賄うのは難しいケースがあります。その場合、作成した事業計画書をもとに、日本政策金融公庫からの創業融資や、地方自治体の制度融資などを活用して資金を調達しましょう。助成金の活用も視野に入れ、余裕を持った資金計画を立てることが大切です。
4. 人員の採用と育成
児童発達支援事業所の施設基準で定められた人員を確保します。特に、管理者や児童発達支援管理責任者は事業運営の中核を担うため、早期の採用が求められます。児童発達支援の開業に必要な資格要件を確認し、有資格者を募集・採用するとともに、質の高いサービスを提供するための研修体制を整えることが重要です。
5. 指定申請書類の準備と提出
事業所を管轄する自治体(都道府県または市町村)の担当窓口に、指定申請を行います。申請には、事業計画書、法人の定款、従業員の資格証の写し、施設の平面図など、多数の書類が必要です。提出期限や要件は自治体によって異なるため、事前にウェブサイトや窓口でしっかりと確認し、不備のないように準備を進めましょう。多くの場合、本申請の前に複数回の事前協議が求められます。
児童発達支援事業所を開設するための要件
児童発達支援事業所を開設するには、法令で定められた基準をクリアしなければなりません。
人員配置基準
開業にあたり、経営者自身に特定の資格は必須ではありません。しかし、現場で働く専門職には以下の通り資格や配置人数に定めがあります。
- 管理者
事業所全体を統括する責任者です。 - 児童発達支援管理責任者(児発管)
子ども一人ひとりの個別支援計画を作成・管理する、事業所の要となる専門職です。一定期間の実務経験と指定の研修修了が必須で、1名以上の配置が義務付けられています。 - 児童指導員または保育士
子どもたちに直接指導を行う専門職です。保育士、児童指導員(社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許保持者など)の資格を持つ人が該当します。利用者数がおおむね10人以下の場合は2名以上の配置が必要です。
施設基準
施設に関しても基準が設けられています。
- 指導訓練室
子どもたちが活動するメインの部屋。利用者一人あたりの面積基準(例:おおむね3㎡以上)が定められている場合があります。 - 相談室
- 洗面所・トイレ
- 事務室
これらの設置に加え、消防法や建築基準法といった関連法規を遵守することも当然求められます。
児童発達支援事業所の立ち上げに活用できる融資・助成金
開業資金は、多くの創業者にとって大きな課題です。自己資金に加えて、公的な融資や助成金・補助金を上手に活用することで、初期投資の負担を軽減し、経営を安定させることができます。
日本政策金融公庫の融資
政府系の金融機関である日本政策金融公庫は、民間金融機関に比べて創業者への融資に積極的です。新規開業・スタートアップ支援資金や、女性、若者/シニア起業家支援資金など、様々な融資制度が用意されています。低金利で長期の返済計画が立てやすい点が大きな魅力です。
自治体の補助金・助成金
国だけでなく、事業所を開設する都道府県や市区町村が、独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。例えば、施設の改修費用や備品購入費用の一部を補助する制度などです。これらの情報は自治体のホームページや窓口で確認できます。
助成金や補助金は、申請期間が限られていたり、募集枠が少なかったりすることが多いです。また、事業開始後に申請できるもの、着工前に申請が必要なものなど、条件は様々です。公募要領を熟読し、スケジュールを正確に管理することが成功の鍵となります。
児童発達支援事業所の開業で、社会貢献と事業継続性の両立を
児童発達支援事業所の開業について、収益性という現実的な視点から、開設の具体的な手順、そして各種基準や資金調達の方法まで解説しました。児童発達支援事業所は、子どもたちの未来を支えるという大きな社会的使命を担っています。しかし、その崇高な理念を継続していくためには、安定した経営基盤を築くことが不可欠です。本記事で得た知識が、あなたの事業を成功に導くための確かな土台となることを願っています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
塗装業で独立開業するには?失敗しない手続きや必要な資金、年収アップの秘訣まで解説
塗装職人として、独立開業を夢見ている方も多いのではないでしょうか。しかし、独立開業には「本当にうまくいくのだろうか?」という不安がつきものです。必要な手続きや資金、独立後の収入など…
詳しくみるトリミングサロン開業のポイント!ペット業界は儲かる?必要資格は?
社会情勢の影響から在宅時間が長くなったこともあり、癒しを求めて新たにペットを飼い始めたという人が増えました。同時にペットサロンや犬のトリミングサロンの需要増も期待できます。これから…
詳しくみる家事代行サービスを開業するには開業届が必要?書き方やメリットも解説
高齢化社会や働き方改革に伴う女性の社会進出などにより、家事代行サービスの需要が増えています。家事代行サービスは準備を適切に行えば、比較的成功しやすい事業のひとつです。自身で独立開業…
詳しくみる高崎市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
高崎市で開業届を提出する際は、高崎市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、高崎市の管轄税務署に提出…
詳しくみるエステサロンを開業するには?手続きや資金、成功のための準備を解説
エステサロンを開業したいと考えていても、開業資金や運営資金、保健所などの許可申請や必要な資格についてなど、準備について全くわからないという方もいるのではないでしょうか。そこで、今回…
詳しくみる開業届に印鑑(ハンコ)は不要!個人事業主に必要な印鑑まとめ
令和3年4月以降、個人事業を始めた時に税務署に提出する開業届には印鑑の押印が不要になりました。それでも事業を開始するにあたって、「新しいハンコも準備したほうがよいのでは?」と考える…
詳しくみる