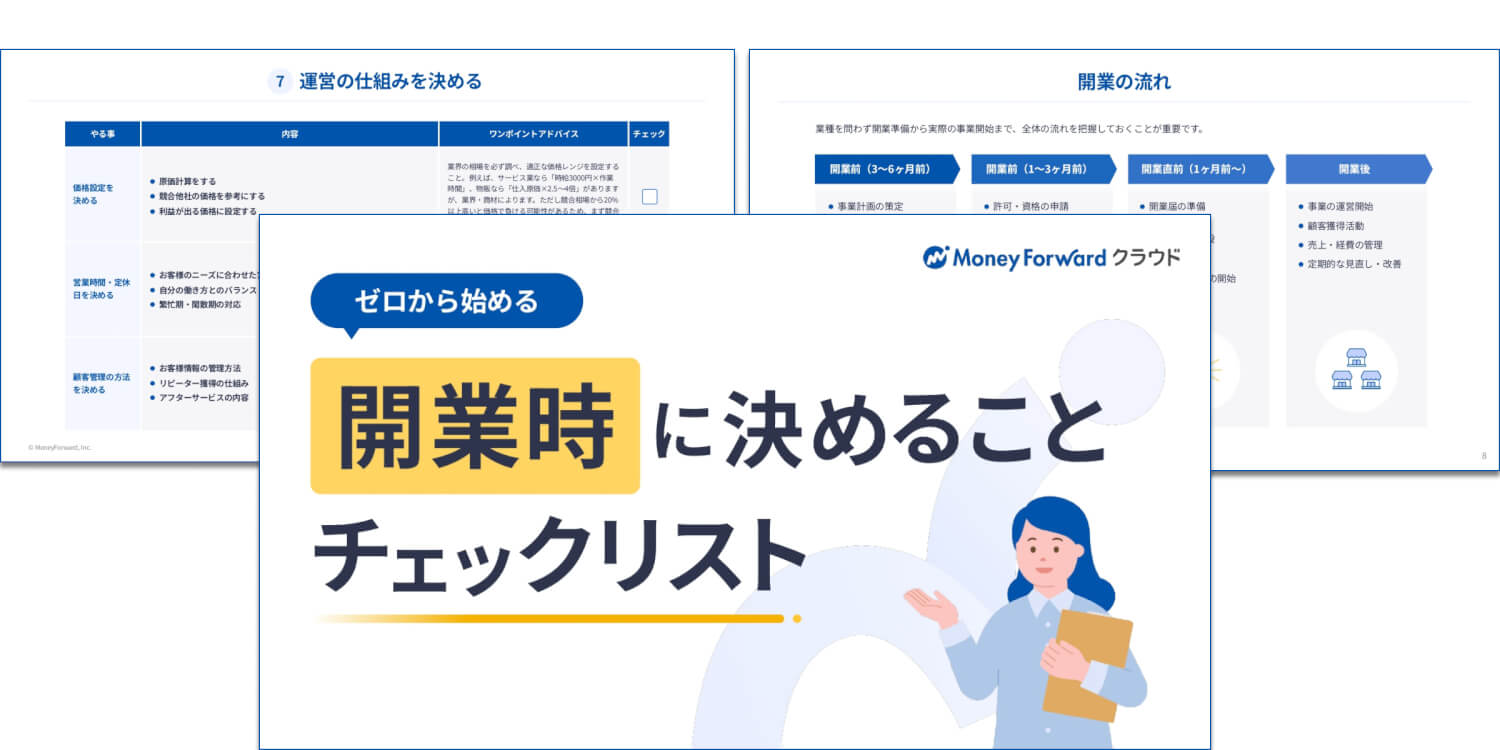- 作成日 : 2025年3月3日
個人事業主に顧問弁護士は必要?メリットや依頼業務・費用について解説
個人事業主は事業上のトラブルを個人で抱えるため、顧問弁護士をつけることで法的リスクを軽減できます。契約書チェックや債権回収など幅広いサポートを受けることで、安心して本業に専念できるのが大きなメリットです。
ここでは、個人事業主に顧問弁護士は必要かどうか、また依頼できる業務や費用などについて解説します。
目次
個人事業主に顧問弁護士が必要な理由
業務上の責任を一人で負う個人事業主は、法的な問題や闘争などが起こった場合のダメージが法人よりも大きくなりがちです。そのため、できるだけ顧問弁護士と顧問契約を締結するのが望ましいといえます。
以下では、個人事業主こそ顧問弁護士を持つことが重要とされる理由を解説します。
個人事業主はトラブルリスクを1人で負う
会社組織であれば、契約トラブルや労務トラブルが起きても、法人が訴えられるため、経営者個人の資産や名誉にまでいきなり影響が及ぶケースは限定的です。ところが、個人事業主は事業主本人が当事者となるため、万一裁判で敗訴すれば個人の自宅や預金が差し押さえられたり、社会的ダメージを負ったりするリスクもあります。
特に大きな金額の損害賠償を請求された場合、一度のトラブルで経営が傾く恐れもあるでしょう。顧問弁護士がついていれば、契約締結時やクレーム対応時に法的リスクを事前に洗い出し、問題が大きくなる前に対処できる可能性が高まります。
個人で法改正に対応するのが難しい
最近ではフリーランスや個人事業主の働き方が増え、国や自治体による新たな制度や法改正が頻繁に行われています。フリーランス新法など、個人事業主の取引条件の適正化に向けた新たな動きもありますが、これらの情報を常にウォッチし、具体的にどのような改正が行われ、自分の事業にどう影響するのかを判断するのは容易ではありません。
法の専門家である弁護士であれば、最新の情報を常に把握しており法改正のポイントを抑えているため、必要な契約見直しや実務対応をサポートし、法的リスクの大幅な軽減が期待できます。
個人事業主にとって顧問弁護士は、リスク回避とビジネスの安定化のために必須といって過言ではないでしょう。
個人事業主が顧問弁護士に依頼できる業務
顧問弁護士というと大手企業のみが利用するイメージを持たれがちですが、個人事業主でも十分に活用できる幅広いサービスがあります。特に契約書関連やトラブル対応は、事業の信頼性向上とリスク低減に大きく寄与します。
ここでは、個人事業主が顧問弁護士に主に依頼できる業務について解説します。
契約書のリーガルチェックや作成
個人事業主にとって契約書は、取引先やクライアントとの関係を規定する重要な文書です。自分で契約書を確認する、または作成する場合、法律に照らしたチェックが不十分だと、後のトラブルに発展するリスクがあります。
顧問弁護士に依頼すれば、以下のようなポイントで適切なサポートを受けられます。
- 契約書に不利な条項がないか、あるいは重要な条項が抜け落ちていないかの確認
- 必要に応じた修正・加筆で、個人事業主を守るための条文整備
- 新たにサービスを立ち上げる際の利用規約やプライバシーポリシーなどの作成支援
とりわけ、インターネットサービスを提供する個人事業主にとっては、利用規約やプライバシーポリシーの整備は社会的信用を高めるうえでも必須といえます。
取引先とのトラブル対応
取引先との契約不履行や料金未払いなどのトラブルが発生した場合、当事者同士で交渉を続けると感情的になり、話が平行線をたどることが少なくありません。
その点顧問弁護士に相談すれば、法的観点から冷静なアドバイスを受けつつ、交渉の方針を決められます。必要に応じて弁護士が代理人として動いてくれるため、個人事業主自身が余計なストレスを抱えずに済む点は大きな利点です。専門家に任せることで、自身で対応して不利になるリスクを軽減することにもつながります。
さらに、問題が起こった際の内容証明郵便の作成や送付、裁判手続きへの移行のタイミングなども的確に見極めてもらえます。
債権回収
個人事業主にとって、納品・提供したサービスの報酬が支払われない事態は経営を圧迫する重大な問題です。顧問弁護士なら、未払い報酬を効率的かつ適法に回収するための手順を提案してくれることが期待できます。
顧問弁護士による法的な対応となると相手方にもプレッシャーがかかり、早期解決のきっかけとなる可能性が高いといえるでしょう。
顧客からのクレーム対応
個人事業主が直接顧客対応を行うケースでは、クレーム処理が予想以上に時間と労力を要することがあります。クレームが長期化すると、事業主自身のメンタルにも大きなダメージを受けるほか、事業に支障をきたす可能性があります。
顧問弁護士のサポートを受けることで、事実関係の確認や損害賠償の範囲など法的根拠に基づいた対応が可能となり、感情的なこじれを回避できます。結果として、迅速かつ適切にクレーム処理を行い、本業に集中できる環境を保てるでしょう。
個人事業主が顧問弁護士に依頼するメリットと注意点
顧問弁護士を活用することで、法的トラブルの発生を防ぎ、スピーディーな事業運営が実現しやすくなります。ただし、弁護士と長期契約を結ぶにあたって、注意しておくべき点も存在します。
それぞれ、見ていきましょう。
メリット
弁護士と顧問契約を結ぶと予約なしで気軽に法的な相談できる環境が整い、ちょっとした疑問や不安にも迅速に対応してもらえるため、日常的な法務トラブルの予防につながります。
また、万が一トラブルが発生した場合でも、事前に適切なアドバイスを受けることで問題が大きくなる前に対応できるでしょう。さらに、法改正や業界特有の規制など、常に変化する法的環境においても、顧問弁護士が最新情報をもとに適切な対策を提案してくれるため、個人事業主は安心して本業に専念できる環境が整います。
注意点
個人事業主は、顧問弁護士に業務上の詳細な情報を提供する必要があります。顧客情報や取引先データなど機密性の高い情報を扱うため、契約前に守秘義務やセキュリティ対策をしっかり確認しましょう。また、契約書において、月額の顧問料でどこまで対応してもらえるのか、追加料金が発生する業務は何か、解約条件はどうなっているのか、といった点は必ず明確にします。
法的には問題がなくても、コミュニケーションの齟齬があるとスムーズに相談しにくくなります。契約前に対応の雰囲気や方針などを確認しておくと安心です。
個人事業主が顧問弁護士を選ぶポイント
顧問弁護士を選ぶ際には、個人事業主としての業務内容や規模、将来的な展望などを踏まえたうえで、相性の良い専門家を探すことが大切です。単に「知名度が高い」「費用が安い」というだけで選ぶのではなく、以下のポイントをチェックしましょう。
専門分野と実績
弁護士にも、それぞれ専門とする分野があります。個人事業主が顧問契約を結ぶ際には、特に企業法務(ビジネスに関わる法律問題)の経験があり、個人事業主や中小企業のサポートに慣れているかどうかをチェックしましょう。
また、法律事務所全体としての実績、評判も考慮し、業界特有の課題に対する知見を持つ弁護士を選定する必要があります。
相談のしやすさと対応の迅速さ
個人事業主は人員的にも限られており、トラブルが起きたときに迅速に相談できる体制がないと大きな損失につながりかねません。メールや電話での相談に対して素早く対応できるか、休日や夜間の緊急対応は可能かなどを事前に確認すると安心です。
また、法的事項を分かりやすく噛み砕いて説明し、必要に応じて社内用の資料を作成してくれるなど協力的な弁護士なら、より良いでしょう。
費用対効果
顧問契約は毎月定額で支払う形が一般的ですが、その金額に含まれる範囲を明確に確認しておきましょう。契約書のチェックや電話相談は月額料金に含まれるものの、交渉や訴訟対応は別料金というケースもあります。追加料金がどの程度発生するのかを把握したうえで、自身の事業規模や予想されるリスクと照らし合わせ、納得できる費用対効果が得られるかどうかを判断することが大切です。
なお、顧問弁護士への支払いは経費計上が可能です。経費として計上することで、法的リスクを抑えるメリットを得つつ所得税や住民税の節税効果も期待できるでしょう。ただし、必要以上に高い顧問料を設定してしまうと、キャッシュ・フローを圧迫する恐れがあるため、バランスを見極める必要があります。
個人事業主が顧問弁護士に依頼する費用相場
一般的に個人事業主向けの顧問料は、月額3万~5万円程度が相場とされています。ただし企業規模や取り扱う案件の複雑さ、リーガルチェックの頻度などによって変動する場合もあります。
個別の契約の内容によって費用相場は変わってくるので、自身が納得できる価格であるかどうかで判断することをおすすめします。
顧問弁護士にかかる費用の勘定科目と仕訳
顧問弁護士への報酬は、主に「支払手数料」「支払報酬料」「業務委託費」「支払顧問料」のいずれかの勘定科目で処理しますが、一般的には「支払手数料」が最も多く使用されています。
なお、弁護士法人への支払いは源泉徴収が不要ですが、個人の弁護士に対する支払いの場合は源泉徴収をしなければなりません。
弁護士法人へ顧問料として月額11万円(税込)を支払う場合は、以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 110,000円 | 普通預金 | 110,000円 | 顧問料支払い |
源泉徴収が必要な個人の弁護士と月額3万3,000円(税込)で顧問契約をしている場合の仕訳は、次のようになります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 33,000円 | 普通預金 | 29,937円 | 弁護士への顧問料支払い |
| 預り金 | 3,063円 | 源泉所得税 | ||
源泉所得税は、後日納付するため「預り金」として計上します。
個人事業主にとって顧問弁護士は心強い存在
個人事業主は、自分で事業運営を行いながら法務リスクまで管理しなければならないため、知らず知らずのうちに大きな負担がかかります。
しかし、顧問弁護士のサポートを受ければ、契約やトラブルのリスクを軽減しつつ最新の法改正にも対応可能となり、安心して事業に集中できます。費用はかかるものの得られるメリットは大きいため、可能であれば信頼できる相性のいい弁護士を探してみることをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主が納める税金は?会社設立とどっちが得?法人税との違いをシミュレーションで比較
個人事業主が納める主な税金に、所得税、個人住民税、個人事業税、消費税があります。法人税は法人が納める税金で、所得税と比較されやすい税金の種類です。この記事では、税金面を中心に、個人…
詳しくみるドッグランを開業する方法は?開業資金や必要な資格・許可などを解説!
ドッグランを開業する際に必要な資格や許可を知りたいと思った方はいるのではないでしょうか。資格や許可以外にも開業するためにどのくらいの資金が必要か知りたい方もいるでしょう。 この記事…
詳しくみる訪問美容師は開業届の提出が必要?書き方もわかりやすく解説
高齢者や要介護者の元に訪問して髪を切るなどの仕事をする訪問美容師は、法人ではなく個人で事業として行っている場合が多いです。 では、個人事業主の訪問美容師は、開業届を提出する必要はあ…
詳しくみる開業届は代理提出できる?必要書類・持ち物や書き方も解説!
個人事業主が開業すると開業届を作成して、税務署に提出する必要があります。しかし、本業が忙しい場合など、なかなか開業届を提出できないこともあるでしょう。「開業届を代理提出できればよい…
詳しくみる三重県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
三重県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する三重県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみるフリーランスのための保険活用法
フリーランスには2つの大きな課題があると言われています。それは「収入の安定化」と「傷病時の保障」です。特に「傷病時の保障」の選択肢はとても限られています。 一般に企業へ就職すると、…
詳しくみる