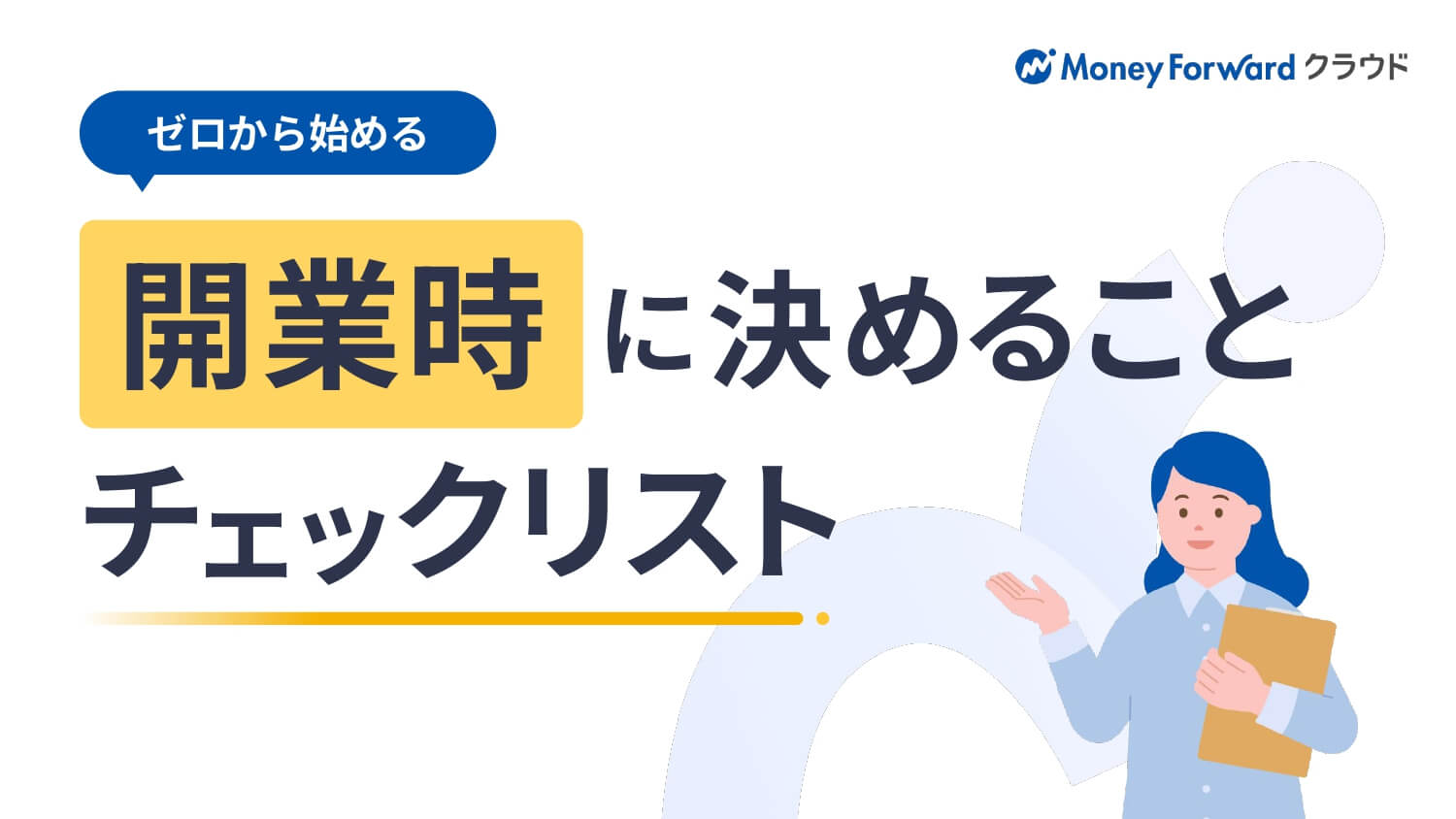- 更新日 : 2025年9月19日
個人事業主がホームページ(webサイト)を持つメリットは?記載内容や活用方法を解説
個人事業主にとって、ホームページの活用は事業成長の大きなカギとなります。SNSは手軽に情報を発信できますが、投稿が流れてしまいやすく、商品の詳細や料金体系などを体系的に伝えるには不向きです。一方でホームページがあると見込み客や既存顧客に対して信頼性のある情報提供が可能になり、集客や成約率の向上にもつながると中小企業庁の調査でも示されています。。
本記事では、個人事業主がホームページを持つメリットや作成時の注意点、さらに上手な活用方法を解説します。
目次
個人事業主がホームページ(webサイト)を持つメリット
個人事業主がホームページを持つ主なメリットとしては、以下の4点が挙げられます。
- 顧客の獲得につながる
- 信用度が向上する
- 名刺やポートフォリオとして利用できる
- 集客費用を抑えられる
詳しく見ていきましょう。
顧客の獲得につながる
ホームページは見込み顧客からのアクセスを得るために不可欠な手段といえます。SNSでは手軽に発信ができる一方で、タイムラインが流動的で、投稿の鮮度が落ちると閲覧されにくくなる場合が少なくありません。
一方、ホームページは一度検索エンジンに評価されれば、継続的に検索結果で上位表示される可能性があります。実際に、Googleの調査でも「検索経由のユーザーは購入意欲も高い傾向にある」ことが示されており、安定してホームページを訪問してもらえるようになると顧客獲得にも直結しやすくなります。
また、実店舗を持たない個人事業主にとって、ホームページはバーチャル店舗のような役割も担います。オンライン上の窓口が整っていれば、時間的・地理的な制約を超えて全国各地から問い合わせを受けられるチャンスが広がります。
信用度が向上する
ホームページの存在は、ユーザーからの信頼性向上にも貢献します。SNSは誰でも気軽に作れる反面、ユーザーの側に「この個人や企業は本当に信頼できるのか」という疑問が生じかねません。一方で、独自ドメインのホームページを開設していると、事業者としての公式な情報を明示できるため、ユーザーの安心感が与えやすいのが特徴です。。
特に、サービス内容や運営者情報、過去の実績などをわかりやすい形でまとめられていると、初めて訪れたユーザーにも信用を得やすくなります。企業規模の大小にかかわらず、「ホームページをきちんと持っている=しっかりした運営者」という印象を与えられるのは、対外的な信用度を高めるうえで非常に重要です。
名刺やポートフォリオとして利用できる
個人事業主のホームページは、インターネット上の「デジタル名刺」としての役割も担います。対面での営業活動が中心であっても、後から詳細な説明を送りたい場合や、直接会う機会を作れない相手に情報を見せたい場合などに、ホームページのURLを案内すればスムーズにサービスの概要を伝えられるでしょう。
また、クリエイターやコンサルタント、士業など専門性が高い業種の場合は、過去の制作事例や実績をポートフォリオとして整理できるのは大きな強みです。SNSでは伝えきれない詳細な情報も、ホームページなら自由に掲載できるため、利用者が自分のニーズに合ったサービスを提供できる事業者なのかを判断しやすくなります。
その結果、商談や契約成立までのステップの短縮できる可能性があり、営業効率の向上に繋がります。
集客費用を抑えられる
ホームページでの集客は、従来のオフラインの広告に比べるとコストを抑えやすい傾向があります。名刺やチラシ、看板などでは印刷費やデザイン費が継続的に発生しますが、ホームページの更新は比較的低コストで行えるのが魅力です。
ホームページを持つこと自体でサーバー代やドメイン費用など一定のランニングコストはかかりますが、一度整備しておけばコンテンツを継続的に活用できます。また、集客を強化したい時期には積極的に更新し、落ち着いている時期には基本的な運用を続けるといった柔軟なスタイルが可能です。自身の予算やスケジュールに合わせて柔軟に活用できるため、固定費が膨らむリスクを抑えつつ集客を図れる点は大きな利点でしょう。
個人事業主の集客におけるホームページ(webサイト)とSNSの違い
SNSは手軽に始められ、投稿が拡散されれば多くのユーザーに瞬時にアピールできる利点があります。しかし、SNSはあくまで特定のプラットフォームに依存しており、運営元の方針変更やアルゴリズムの更新によって情報の届き方が左右されるリスクも避けられません。
さらに、アカウントの凍結など予期せぬ事態に見舞われれば、それまで築いてきた顧客やフォロワーとのつながりを一瞬で失う可能性もあります。これに対して、独自ドメインで開設したホームページは運営者自身が管理権限を持ち、プラットフォームへの過度な依存がない点が大きな強みといえます。
また、SNSではタイムラインやフィードの流れが速く、新しい情報が次々と更新されるため、過去の投稿が埋もれていきます。それに対してホームページのコンテンツは、サイト構造を適切に設計しておけば古い記事やページであっても探しやすく、検索エンジンからの流入が長期間に見込めるというメリットがあります。
こうした違いを踏まえると、個人事業主としての公式情報やサービス内容はホームページでしっかりと発信し、SNSは補助的に使う形が理想的です。
個人事業主がホームページ(webサイト)を作成する方法
個人事業主がホームページを作ろうと思ったとき、制作手段は大きく分けて「自作」と「外注」の2つがあります。どちらを選択するかは、予算やスキル、制作にかけられる時間などで変わってきます。ここでは、それぞれの方法の特徴を紹介します。
WordPressなどの作成ツールを利用して自作する
ホームページ作成ツールの定番といえるのが、WordPressです。WordPressは無料で使えるオープンソースのCMS(コンテンツ管理システム)であり、初心者でもわかりやすいマニュアルが用意されているため、導入のハードルは高くありません。初期費用が抑えられ、デザインの自由度も高く、豊富なプラグインを利用できる点も魅力です。
また、WordPress以外にも、WixやJimdoなど、デザイン済みのテンプレートを活用できるサービスとして知られています。こうしたツールを活用すると、専門的なプログラミングの知識がなくても比較的簡単にホームページの作成できるのが特長です。
プロに外注する
外注でホームページを作る場合は、制作会社やフリーランスのWebデザイナー・エンジニアなどに依頼する形が一般的です。プロに任せることで、クオリティやデザイン性の高いサイトを実現できるだけでなく、集客効果を高めるための戦略的なアドバイスを得やすい点が利点といえます。
また、自分が不得意な分野を専門家に任せることで時間と労力を節約でき、本業に専念しやすくなるのも魅力といえるでしょう。
ただし、外注には一定の制作費用が必要になるほか、サイトの更新や改修を行う度に追加コストが発生する場合があります。そのため、依頼する前に、制作会社が担当する範囲と、自分で管理する部分を明確に決めておくことが大切です。
個人事業主のホームページ(webサイト)に記載する内容
ホームページには、必要な情報をバランス良く掲載することが大切です。最低限記載するべき項目としては、以下が挙げられます。
- サービス内容
- 実績
- 料金
- プロフィール
- 顧客の声
- 問い合わせフォーム
- プライバシーポリシー
それぞれについて、見ていきましょう。
サービス内容
提供しているサービスや商品の紹介ページは、ホームページの中核となる部分です。詳細をわかりやすくまとめるだけでなく、他社との違いや強みなどを示すことが大切です。
また、抽象的な表現にとどまらず、具体的な作業内容やサポート範囲などを明記することで、ユーザーの理解が深まり、興味を持ってもらうきっかけになるでしょう。
実績
これまでに手掛けたプロジェクトや成果を紹介することも重要です。実績を示すことで、訪問者は自分の目的や要望とマッチしているかを判断しやすくなります。
さらに、受賞歴や評価を受けた事例などがあれば、強力なアピール材料になります。多様な事例を掲載すれば信頼感が増し、訪問者に「この事業主なら任せられる」という安心を与えられるでしょう。
料金
訪問者にとって、料金は大きな関心事です。料金表やサービス内容ごとの費用は、できるだけ明確に示しておきましょう。
完全オーダーメイドの案件であれば、「ヒアリング後にお見積もり」という形が基本になりますが、おおよその価格帯や算定基準を明記しておくと納得感が得られやすいでしょう。また、単に価格の安さを強調するだけでなく、サービスの質と料金が見合っていることをアピールする工夫も大切です。
プロフィール
事業者自身の経歴などを詳しく紹介することは、依頼を検討している人に安心感や信頼感の向上につながる効果が期待できます。どのような経験や資格を持ち、なぜこのビジネスを始めたのかなどをストーリー性を持って書くと、訪問者から共感を得やすくなるでしょう。
特に士業などの専門職であれば、学歴や資格取得の経緯、資格取得後の活動などで専門性の高さを効果的に訴求することも可能です。
顧客の声
ユーザーにとって第三者の声は非常に参考度が高く、サービス利用を検討する際の判断材料になります。実際にサービスを受けた顧客の感想やレビューを積極的に掲載することで、サービスの価値や信頼性を証明できるでしょう。
ただし、顧客の個人情報保護には配慮が欠かせません。実名を掲載する場合には必ず同意を得るなど、個人情報保護の観点を示すことが重要です。
問い合わせフォーム
問い合わせ手段としてメールアドレスだけを載せるケースもありますが、専用フォームを用意することでユーザーは連絡を取りやすくなります。必要事項を入力して送信するだけの仕組みにしておけば、問い合わせのハードルを下げられるでしょう。
また、フォームの設置にあたっては、セキュリティ対策としてSSL証明書を導入しているサーバーを利用するなど、個人情報が暗号化される仕組みを整えることが求められます。そうすることでユーザーに安心して利用してもらえるようになります。
プライバシーポリシー
個人情報保護法に基づき、個人情報の取り扱い方法を明示することはホームページ運営者としての責務です。フォーム経由で取得した情報については、どのように保管し、どの目的で利用するのか、さらに第三者への提供の有無などを明記する必要があります。
また、アクセス解析ツールを利用している場合も、その旨やCookieの使用状況を記載し、利用者に対して透明性を確保することが求められます。
個人事業主が選ぶべきホームページ(webサイト)の種類と構成
個人事業主がホームページを作成する際には、目的に合ったサイトの種類を選び、業種に応じた構成を考えることが大切です。そうすることで効果的に信頼獲得や集客につなげられます。ここでは4つの代表的なタイプと、それぞれに適した業種や作成ポイントを解説します。
名刺代わりのシンプルなプロフィールサイト
営業先や問い合わせの際に「自分が何者であるか」を伝えるための基本的なWebサイトです。費用や運用負担を抑えながら、最低限の信頼感を伝えられます。
- トップページ(顔写真・キャッチコピー・理念)
- プロフィール(経歴・資格・実績)
- 業務内容の簡単な紹介
- お問い合わせフォーム
- フリーランス全般(デザイナー、イラストレーター、ライターなど)
- 士業(行政書士、社労士など)
- カウンセラー、セラピスト
- 講師・研修講師など
作成のポイント
最小構成でも「誰に、何を提供しているか」が明確に伝わることが重要です。顔写真・実績・連絡手段の3点を必ず盛り込み、デザインはシンプルかつ清潔感のあるものを選ぶと信頼性が高まります。
ブログ型・オウンドメディア型サイト
知識やノウハウを発信しながら、検索エンジンやSNS経由で見込み客を集める形のWebサイトです。中長期的に集客やブランディングを築きたい人に適しています。
- トップページ(最新記事一覧・サービス紹介)
- ブログ(カテゴリ別に整理)
- プロフィール・活動の背景
- お問い合わせフォーム・メルマガ登録導線
- コンサルタント(経営、Web、健康など)
- セラピスト・スピリチュアル系サービス
- 士業(税理士、弁理士など専門知識が強みの職種)
- 情報商材、教育コンテンツ提供者
作成のポイント
定期的に記事を更新できる体制と、ターゲットが検索しそうなキーワードを設計することが不可欠です。単なる日記ではなく、読者の課題解決を意識した内容にすることで価値が高まります。SNSとの連携やメルマガへの誘導もセットで考えると効果的です。
商品販売向けEC型サイト
物販やデジタルコンテンツ、チケット販売など、決済が発生する事業に適したWebサイトです。商品紹介や購入導線の作り方が、そのまま集客や売上に直結します。
- 商品一覧/カテゴリページ
- 商品詳細(説明・画像・レビュー)
- カート/決済導線
- 特商法表示/利用規約/FAQ
- ハンドメイド作家、イラスト・グッズ販売
- 自作コンテンツ販売(PDF教材、講座、電子書籍など)
- 小規模ブランドのアパレルや雑貨販売
- 飲食のテイクアウト・通販など
作成のポイント
商品写真の品質が売上を左右する最大の要素です。プロらしい見せ方を意識して送料・返品条件などを明確にすることで信頼性がアップします。さらに、BASEやSTORESを使えば、初期費用を抑えて簡単にスタートできます。
サービス業向けの予約・問い合わせ特化型
個別サービスや時間制のビジネスを行う事業主にとって、予約や問い合わせをスムーズに受けるための導線を整えたサイトです。ユーザーが「気になった瞬間に行動できる仕組み」を備えることが重要になります。
- サービス案内・料金表
- カレンダー付き予約システム
- お客様の声・施術実績・導入事例
- プロフィール・理念・FAQ・問い合わせフォーム
- 美容・整体・鍼灸・パーソナルジム
- カウンセラー、コーチ、占い師
- フリーランス講師、家庭教師
- 写真・映像撮影、出張サービス系全般
作成のポイント
予約や問い合わせのハードルを下げる工夫(例:無料相談、LINE連携)が有効です。さらに、口コミやビフォーアフター画像といった第三者の声を積極的に掲載すると信頼性が高まります。加えて、フォームや予約ツールはスマホ対応が必須です。
ホームページ(webサイト)運用にかかるコストと無料で始める方法
ホームページは作って終わりではなく、運用に継続的なコストと労力が発生します。このセクションでは、一般的なWebサイト運用コストの内訳と、無料〜低コストで始める方法をわかりやすく解説します。
一般的にかかるホームページ(Webサイト)運用コスト
個人事業主が自前のホームページを持つ場合、以下のような費用が一般的に発生します。
ドメイン取得費・更新費(年間1,000〜3,000円程度)
独自ドメインはブランディングや信頼性の面で大きなメリットがあります。「yourname.com」や「business.jp」など、覚えやすいURLは名刺やSNSにも活用でき、ほぼ必須といえるでしょう。ドメインの価格は「.com」や「.jp」などの種類で異なりますが、年間1,000〜3,000円程度が目安です。
サーバー費用(年間6,000〜15,000円程度)
レンタルサーバーを使う場合、初期費用+月額数百円〜1,500円程度がかかります。WordPressを使いたい場合は「エックスサーバー」「ロリポップ」「ConoHa WING」などが定番です。安価であっても、安定稼働やSSL対応は必須条件です。
制作費・外注費(10万〜50万円)
自作であれば無料ですが、制作を外注する場合、テンプレートデザインを利用したシンプルな単一ページサイトであれば5万円程度から可能なケースもありますが、オリジナリティを出し複数ページで構成するなら10万円~50万円程度が一般的な相場です。戦略設計やコンテンツ作成も含めるとさらに高額になります。
保守・更新管理費(任意で月額5,000〜20,000円)
WordPress等のCMSで作成した場合、セキュリティ更新やバックアップのために保守契約を結ぶケースもあります。作業内容によりますが、専門業者に依頼する場合、月額5,000円~20,000円程度が一般的な相場です。
無料・低コストで始める方法
コストを抑えたい個人事業主や副業初心者には、無料〜低価格で使えるサービス活用が有効です。
無料ホームページ作成ツールを使う(初期・月額0円〜)
「ペライチ」「Wix」「Jimdo」などのサービスを使えば、専門知識がなくてもドラッグ&ドロップでホームページを作成可能です。
無料プランでも1ページ完結型のWeb名刺として十分機能します。
ただし、独自ドメインでない(例:〇〇.wixsite.com)ことや、広告表示、機能制限がある点には注意が必要です。
Google サイトの活用(完全無料)
Googleアカウントがあれば誰でも利用できる「Google サイト」は、ビジネス情報やプロフィール、問い合わせフォームの設置など最低限の要素を簡単に構築できます。SEOやデザイン性には限界がありますが、初期段階のWebプレゼンスとしては効果的です。
noteやブログサービスを代用する(初期・月額費用ゼロ)
文章中心であれば「note」「はてなブログ」「アメブロ」などを活用し、自己紹介、実績、サービス案内、問い合わせ導線などを設置することも可能です。読者との接点を作る場として運用しつつ、ホームページの代替としても機能します。
格安ノーコードツールで有料運用を始める(月額500〜1,000円)
海外製の「Carrd」など一部サービスでは月額数百円から独自ドメインが利用できます。国内で人気の「STUDIO」などでは月額1,000円前後から独自ドメインや高度なフォーム機能が使えるプランを提供しています。低コストで本格運用を始めたい人に向いています。
個人事業主がホームページ(webサイト)を作成する注意点
ホームページは「一度作って終わり」ではなく、継続して運用することで効果を発揮します。目的やターゲットを明確にし、こまめな更新作業や法的要件の遵守、セキュリティ対策などに気を配りながら運営を継続することが重要です。
ここでは、作成時に注意すべきポイントを解説します。
目的とターゲットを明確にする
ホームページを作成する際には、どのような目的を達成したいのかを明らかにする必要があります。たとえば、新規顧客の獲得なのか、既存顧客とのコミュニケーションを重視するのか、あるいはブランディングが目的なのかで、設計やコンテンツの方向性が異なるでしょう。目的を定めたうえで、想定するターゲット層も設定することが欠かせません。
さらに、年齢層や居住地、興味・関心など、ある程度絞り込むことでサイトのデザインや文章のトーンも考えやすくなります。
継続的な更新と運用を行う
ホームページを放置すると、検索エンジンからの評価が下がり、集客効果が薄れてきます。また、掲載内容が古くなってしまうと、ユーザーから見ても「このサイトはすでに運営されていないのでは……」と不安を与えかねません。
定期的に、商品情報やお知らせなどを更新することで、新鮮な情報を維持し、検索結果での上位表示を維持しやすくなります。新たな実績やサービス内容の変更があれば積極的に反映させ、常に最新情報を提供する姿勢を持つことが大切です。
法的要件とセキュリティ対策を遵守する
ホームページを持つ個人事業主には、特定商取引法や個人情報保護法などの法令を遵守する必要があります。特に、インターネットを介して商品販売や有料サービスの提供を行う場合は、販売業者の名称や所在地、連絡先、販売価格などをわかりやすく表示しなければなりません。
さらにユーザーから個人情報を収集する際には、どのように情報を管理し、目的外で使わないかを明確に示すことが求められます。
セキュリティ対策の面でも、脆弱性を悪用されてサイトが改ざんされる事例などが報告されており、注意が欠かせません。WordPressなどを利用している場合は、こまめなシステム更新を行い、不要なプラグインを放置しないよう心がけましょう。加えて、SSL(TLS)を導入して通信を暗号化することも、ユーザーの安全と安心につながります。
個人事業主がホームページ(webサイト)を活用する方法
ホームページは、「作る」ことが目的ではありません。作成後集客ツールとして運用し、事業に貢献できるよう育てていく必要があります。ここでは、ホームページ作成後どのように活用していけばよいか、具体例を紹介します。
オフラインツールとの連携
名刺やフライヤー、封筒などの紙媒体にホームページのURLやQRコードを掲載すると、オフラインからオンラインへの誘導がスムーズになります。また、イベントやセミナーで配布する資料にもホームページへのリンクを掲載しておけば、帰宅後にアクセスしてもらえる可能性が高まるでしょう。
SNSとクラウドソーシングの活用
SNSは短期的な情報発信や拡散に優れ、フォロワーとの交流にも適しています。ホームページに書ききれない日常的なトピックやリアルタイムの進捗状況、キャンペーン情報などをSNSで発信し、詳細はホームページで確認してもらう流れを作ると効果的です。
SNSからホームページへの導線を用意し、サービス申し込みやお問い合わせにつながります。クラウドソーシングを利用する個人事業主は、プロフィールや提案文にホームページを記載しておくと信頼性が高まります。
継続的な情報発信と分析
ホームページを通じた集客を安定的に続けるためには、継続的な情報発信が欠かせません。新サービスの開発ストーリーやユーザー事例、イベントレポートなど、有益なコンテンツを更新していくことが大切です。検索エンジンだけでなく、リピーターの訪問も増え、長期的なファンを築ける可能性が高まります。
さらに、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを導入し、閲覧数が多いページや流入経路を把握する習慣をつけるとよいでしょう。データに基づいてサイト構成やコンテンツの方向性を見直すことで、より効果的な改善施策を打ち出せます。
競合と差をつけるホームページ(Webサイト)の印象アップ術
ホームページは、訪問者が最初に触れる「事業の顔」です。サービス内容が競合と似ていても、「見た目」や「レイアウト」で印象に大きな差が生まれます。ここでは、専門知識がなくても実践できる印象アップの方法を紹介します。
色使いとフォントで“らしさ”を演出する
配色は訪問者の感情にダイレクトに作用します。たとえば、士業やコンサル業であれば信頼感を与えるブルー系、美容や子育て支援ならやさしさを演出するピンクやベージュ系など、自身の業種やターゲットに合った色を選ぶことが大切です。
また、フォントも印象を左右します。手書き風や装飾の多い書体は印象的ですが、可読性が下がりやすいため、本文には「Noto Sans JP」「游ゴシック」「Hiragino」などの読みやすいフォントを選びましょう。タイトルと本文で書体や太さを変えることで、視線誘導も作りやすくなります。
写真と余白で“プロ感”を出す
文章がいくら良くても、暗くて解像度の低い画像が並んでいると信頼感を損なってしまいます。自然光で撮影した明るい写真を使用し、人物は笑顔・背景の整ったものを選ぶと好印象です。
さらに、ページ内に十分な余白(スペース)を儲けることで、内容が整理されて見え、見やすさや読みやすさが向上します。余白を恐れず、「情報を詰め込みすぎない」ことが、結果的に洗練されたデザインにつながります。
無料ツールで見栄えを底上げする
デザインに自信がなくても、「Canva」を使えば簡単にオリジナルのバナーや画像を簡単に作成可能です。テンプレートを活用すれば、配色やレイアウトも自然と整った仕上がりになります。
また、「Unsplash」や「Pexels」などのフリー素材サイトを活用すれば、無料で高品質な画像が手に入ります。文章が中心のサイトでも、適度にアイコンや図解を差し込むことで、情報が視覚的に整理され、読者の集中力を保てます。
うまく活用すればホームページは強力な営業ツールになる
ホームページの作成は、信用度の向上、安定した顧客獲得の経路、ポートフォリオとしての活用など、多くのメリットを得られます。また、SNSやオフラインツールと組み合わせると相乗効果も期待できるでしょう。
ただし、ホームページは作成して終わりではなく、常に最新の情報を発信し、継続的に運営していく必要があります。事業の特性に合わせて適切に活用し、ビジネス拡大のチャンスを逃さないようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
精神科を開業するには?必要な費用や許認可、流れを解説
精神科医が地域密着型の診療を目指して独立・開業するのは、理想の医療実現への大きな一歩です。 しかし、いざ開業となると、「どれくらいの費用がかかるのか?」「どのような手続きや許認可が…
詳しくみるホステスは開業届の提出が必要?個人事業主向けに書き方を解説!
バーやラウンジで接客をするホステスは個人事業主になるのか?という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。個人事業主かどうかは、店側との契約形態や業務上の指示の有無などによって変わり…
詳しくみる個人事業主に代表者印は不要!作成がおすすめの印鑑や購入費用の会計処理について解説
個人事業主の中には、代表者印を作るべきか迷っている人もいるでしょう。個人事業主の場合は法人登記しないため、代表者印の作成は不要です。 本記事では、個人事業主に代表者印が必要なのかに…
詳しくみる1,000円カットで開業するには?儲かる仕組みや経営方法を解説!
昨今の物価上昇などの影響もあり、1,000円~1,200円程度の低価格でカットできる理髪店や美容室を利用する人が増えています。その需要の波に乗って、1,000円カット店を開業したい…
詳しくみる福山市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
福山市で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する福山市内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる横須賀市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
横須賀市で開業届を提出する際は、横須賀市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、横須賀市の管轄税務署…
詳しくみる