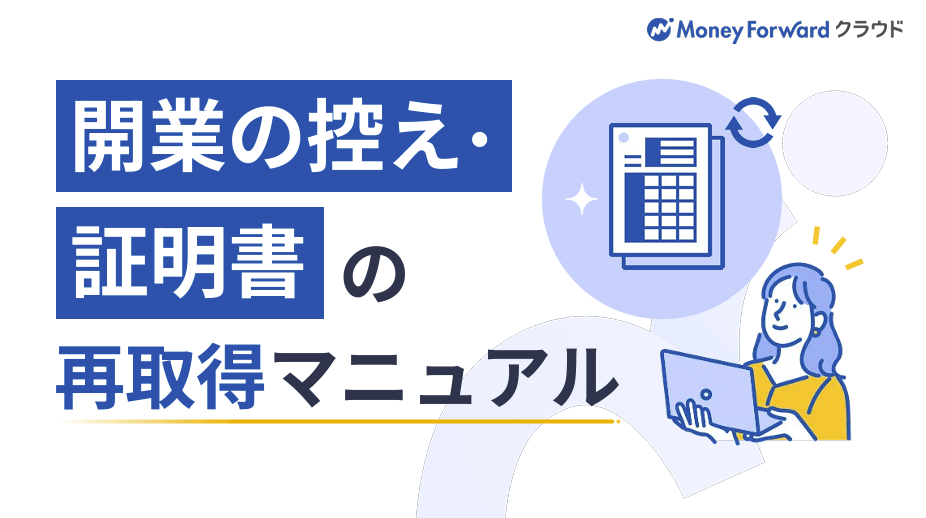- 更新日 : 2025年12月29日
【2025年改正対応】開業届の証明書が必要な時どうする?入手・控えの再発行方法を解説
2025年1月から、国税庁の運用変更により、申告書等(開業届を含む)の控えに対する収受日付印の押なつが行われなくなりました。これにより、個人事業主が開業届の提出事実をどのように確認・証明するかについて、従来と異なる運用が求められるようになっています。
これまで銀行口座開設や補助金申請の際には、収受印付きの控えが「開業届の証明書」として利用されてきましたが、今後は提出先の要件に応じて別の方法で提出事実を示す必要があります。
本記事では、開業届の提出事実が求められる場面ごとの対応策や、収受印の代わりとなる証明手段、電子申請(e-Tax)の活用方法について解説します。
目次
開業届の証明書(控え)とは?
開業届は、個人事業主が税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。その控え(提出者が保管する写し)は、事業を開始したことを証明する書類として重要な役割を果たしてきました。
法人の場合は登記簿謄本など公的な登録記録がありますが、個人事業主にはそれがないため、開業届の控えが開業の事実を示す代表的な公的書類の一つといえます。
例えば、屋号名義の銀行口座を開設する際や事業用クレジットカードの申し込み、事業資金の融資を受ける場合、小規模企業共済への加入手続きなど、各種場面で「開業届の証明書」として控えの提出や提示を求められることがあります。このように、開業届の控えは個人で事業を始めたことを第三者に示す大切な役割を担っていました。
従来の運用:開業届の控え受領と収受印の仕組み
2025年1月以前の運用では、開業届を提出すると税務署から控えに受領印(収受日付印)を押してもらうことができました。窓口では開業届の原本とコピーを持参すれば、その場で収受印が押された控えを受け取れました。郵送でも、コピーと返信用封筒を同封すれば印が押された控えが返送され、証明書として保管できました。
一方、e-Taxで電子申請した場合には紙の控えは発行されず、代わりに「受信通知」がメッセージボックスに届き、提出の証拠となりました。以前は紙提出が主流で、収受印付きの控えを確実に入手・保管することが基本的な手続きとされていました。
2025年制度改正:収受印廃止と開業届控え運用の変更
令和7年(2025年)1月から、税務署に提出する各種書類の控えに対する押印が廃止され、これまで一般的だった「収受印付きの開業届控え」は発行されなくなりました。この制度改正は、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化を推進する流れの一環とされています。控えの取り扱いが大きく変わったことで、提出先の要件に応じて、どのように提出事実を確認・保存するかを整理しておく必要があります。
開業届の控えに収受印が押されない仕組みに変更
2025年以降、開業届を紙で提出した場合でも、控えに収受印は一切押されなくなりました。従来のように、税務署窓口で原本と控えを持参したとしても、返却される控えに印が入ることはありません。郵送で提出した場合も同様で、返信用封筒とともに控えを送付しても、押印された控えは返ってこないことになります。現在は国税庁のQ&Aで示されているとおり、提出日付と税務署名が記載されたリーフレットが返送されることがありますが、将来的にはそのリーフレットも廃止される可能性があります。
参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
制度変更の背景は行政のデジタル化方針
この運用変更の背景には、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))があります。e-Taxの利用者は年々増加しており、税務署側としても書類管理や受付の効率化を求められる状況にあります。このため、控えへの押印という手間のかかる対応を廃止する判断がなされました。
今後は提出者が証明方法を自ら用意する必要がある
収受印がなくなったことで、開業届の提出日や提出済みの証明をどう残すかが課題となります。これまでは収受印付き控えがその役割を果たしていましたが、今後は提出者が自ら提出記録を残す必要があります。
e-Taxを利用すれば受信通知という電子データが得られ、それが証明になります。紙で提出する場合は、提出日を自身で記録したうえで、提出済みの控えや税務署からの返送書類を保管しておくことが、提出事実を確認する手段として有効とされています。
収受印廃止後に開業届の提出済みを証明する方法は?
開業届の控えに収受印が押されなくなったことで、提出した事実をどう証明すればよいかという疑問が多く寄せられています。
国税庁ではこの点に対応するため複数の代替手段を用意しており、状況に応じて有効な方法を選ぶことができます。ここでは、収受印の代わりとして使える3つの方法について解説します。
(1)e-Taxによる受信通知と電子申請等証明書
e-Taxを利用して開業届を電子申請した場合、提出後すぐに「受信通知」がメッセージボックスに届きます。この通知には、申請者の氏名や受付番号、受付日時などが記載されており、それ自体が開業届の提出を証明する記録として使うことができます。受信通知を必要に応じて印刷して保管しておくと便利です。期間を経過するとメッセージボックスから削除されますので注意してください。
より正式な証明書が必要な場合には、「電子申請等証明書」の交付をe-Tax上から請求できます。これは、提出した事実を税務署が証明する公式な文書で、無料で発行されます。PDF形式で交付されるこの証明書は、銀行や自治体への提出資料として利用できるようです。
なお、発行を受けるにはマイナンバーカードなどの電子証明書を用いた認証が必要となりますが、収受印付きの控えの代替手段として提出履歴を電子的に証明できるため、活用が広がっています。
参考:電子申請等証明書の概要はどのようになっていますか。| e-Tax
(2)申告書等閲覧サービスを使った提出記録の確認
紙で開業届を提出し、控えを受け取らなかった、あるいは紛失してしまった場合には、「申告書等閲覧サービス」を活用する方法もあります。このサービスでは、自分が過去に提出した開業届の内容を税務署の窓口で閲覧することが可能です。利用にあたっては、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を提示する必要があります。
閲覧時には書類のコピーをもらうことはできませんが、スマートフォンなどでの写真撮影や、内容の手書き記録が認められています。内容や提出日付を確認する目的であれば十分な手段と言えるでしょう。すぐに証明が必要な場合や、提出した事実の確認だけで問題がないケースにおいては、このサービスが手軽な解決策となります。
(3)保有個人情報開示請求による開業届控えの再発行
どうしても開業届の正式な控えが必要な場合には、「保有個人情報の開示請求」を行い、税務署に対して正式な写しの交付を申請する方法があります。この手続きでは、所定の申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を添付したうえで提出します。手数料として収入印紙300円分(オンライン請求では200円)が必要になります。
交付申請を行ってから30日以内で決定通知が届き、その後、窓口で受け取るか、郵送で送ってもらうかを選べます。郵送を希望する場合は、返信用封筒と郵送料が別途必要です。再発行される控えには収受印は付きませんが、税務署が保有する正式な記録の写しであり、行政機関や金融機関などで証明資料として利用されることが多い書類です。時間と手間はかかるものの、確実な方法として覚えておくと安心です。
参考:開示請求等の手続|国税庁
開業届の提出済みを証明する3つの方法の比較表
上述した3つの証明手段を比較して表にまとめました。
| 項目 | (1)e-Tax受信通知・電子申請等証明書 | (2)申告書等閲覧サービス | (3)保有個人情報開示請求(控えの再発行) |
|---|---|---|---|
| 主な用途 | 電子的に提出した証明・銀行や補助金提出用の公的証明 | 提出済みか内容を確認したい場合 | 収受印が不要でも「正式な控え」を求められる場合 |
| 証明力・信用度 | ◎ 高い信用度がある(多くの場面で公的証明書として扱われる) | △ 内容の確認には十分。証明力は弱い | ○ 税務署が保有する正式記録の写し → 高い信用度 |
| 取得方法 |
| 税務署窓口で申請・閲覧 | 税務署に開示請求(郵送・窓口・オンライン) |
| 取得手段の種類 |
| 開業届の内容をその場で閲覧(写真撮影可) | 開業届の写しを交付(収受印は付かない) |
| 提出日が証明できるか | ◎ 明確に証明できる(受付日時入り) | ○ 内容・提出日を確認可能 | ◎ 提出記録に基づくため確実 |
| 取得費用 | 無料 | 無料 |
|
| 必要書類 |
| 本人確認書類(運転免許証等) | 本人確認書類・開示請求書・収入印紙等 |
| 取得までの期間 | ◎ 即時(電子データすぐ発行) | ○ 当日その場で閲覧可能 | △ 最大30日(決定通知後に交付) |
| 書類の形態 | PDF形式(電子データ) | 紙の閲覧のみ(コピー不可だが撮影可) | 紙の写しを交付(正式記録に基づく) |
| 提出先での利用可否 | ◎ 多くの場面で利用される | △ 内容確認程度の扱い。提出書類としては弱い | ○ 多くの行政機関・金融機関で証明書として利用されている |
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
銀行・自治体・金融機関ごとの提出書類の受け入れ基準は?
2025年の収受印廃止により、多くの手続きで「開業届の証明書」として何を提出すればよいかが分かりづらくなっています。提出先ごとに必要書類の運用が異なるため、ここでは、主な提出先の傾向を整理しつつ、最終的には各機関の案内に従う必要があることを前提にまとめます。
メガバンク・ネット銀行での屋号口座開設
銀行では、収受印廃止後も開業届の控え(印なし)を基本資料として受理するケースがあります。三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行などのメガバンク、楽天銀行・住信SBIネット銀行などのネット銀行も、国税庁の案内に沿って収受印付き控えの提出を前提としない運用に切り替えつつあり、提出する方法が案内されています。より確実に審査を通したい場合には、e-Tax提出時の受信通知や電子申請等証明書(PDF)を併せて提示することで、提出日・受付事実が明確になりスムーズです。
紙提出で控えが手元にない場合は、開示請求で取得した控えの写しも有効な証明資料として扱われるケースがあります。
自治体の補助金・助成金制度
自治体の補助金申請では従来「税務署の受付印付き控え」が求められましたが、収受印廃止後は電子申請等証明書を代替書類の一つとして位置づける自治体が増えています。自治体によっては要項が更新されていない場合もあり、印付き控えの提出を求められることがありますが、制度変更を説明し電子申請等証明書を提示することで受理されるケースもあるようです。
紙提出での提出事実確認が必要な場合には、税務署窓口での申告書等閲覧サービスで撮影した記録が参考資料として扱われることもあります。
政策金融機関(日本政策金融公庫など)の創業融資
日本政策金融公庫などの政策金融機関は事業実態の確認が厳格なため、証明力の高い書類が求められます。収受印廃止後は、証明力の高い書類の一例として、電子申請等証明書を求める案内が行われているようです。紙提出で控えを紛失した場合には、税務署が正式記録に基づいて発行する保有個人情報開示請求による控えの再発行が有効です。
融資審査では書類の不備が遅延につながるため、提出資料は事前に確認しましょう。
クレジットカード(法人・個人事業主向け)発行
ビジネス用クレジットカードの発行でも、開業の実態確認として開業届控えの提出を求められます。多くのカード会社は制度変更を把握しており、収受印なしの開業届控えでも受理される場合がありますが、審査の厳しいカードほど電子申請等証明書を併せて提出する方が安心です。なお、e-Tax提出の場合の受信通知のみで認められるケースもあるようです。実際にどの書類が必要かは、各カード会社の申込要項・問い合わせ窓口で事前に確認するほうがスムーズです。
共済加入(小規模企業共済・国保組合など)
小規模企業共済や各種国保組合では、加入要件として事業の実態が確認できる書類が必要です。開業届控えの写しは基本として受理されますが、制度変更により印なしの控えでも受理されるケースがあります。正式な証明を求められた場合は電子申請等証明書が有効とされることが多く、紙提出の場合に控えがないときは開示請求による写しが代替資料として有効です。共済によってルールが異なるため、事前の確認が安心です。
契約時(取引先・決済サービス・士業契約など)
取引先との業務委託契約、キャッシュレス決済業者への登録、税理士との契約などでは、開業の事実を示す書類が求められることがあります。多くの場合、開業届の控え(印なし) で対応できますが、提出先が厳格な場合は電子申請等証明書を提出すると信用性が高まります。紙提出で控えが紛失している場合は、申告書等閲覧サービスの記録、または開示請求による控えの正式な写しが代替資料として利用可能です。ただし、どの書類が認められるかは各事業者の判断によるため、事前の確認が不可欠です。
開業届をオンラインで電子申請する方法(e-Tax利用)は?
開業届を提出するにあたって、2025年以降は電子申請(e-Tax)の利用がますます注目されています。収受印の廃止により、紙提出の控えが証明として使いづらくなった今、自宅で完結できる電子申請は便利な手段です。ここでは、初めての方でも安心して使えるよう、e-Taxを用いた開業届の提出手順を解説します。
ステップ1:マイナンバーカードやICカードリーダーの準備
まず、e-Taxで開業届を提出するには、マイナンバーカードに格納された公的個人認証の電子証明書を用いて電子署名を行う必要があります。このカードに内蔵されている電子証明書を使って、e-Taxにログインし、電子署名を行うためです。パソコンを使用する場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーの用意も求められます。NFCに対応したスマートフォンでも、対応アプリを使用すればマイナンバーカードの読み取りが可能です。
ステップ2:e-Taxにアクセスしてログイン
事前準備が整ったら、国税庁のe-Taxソフト(Web版)にアクセスします。初めての方は、画面の案内に従って利用者識別番号(ID)を取得し、アカウントを作成してください。すでにIDをお持ちの場合や、マイナンバーカードでログインできる環境がある場合は、そのままログインが可能です。ログイン後は、トップページにある「申告・申請・納税」メニューから、「個人事業の開業・廃業等届出書」の入力フォームを選びます。このフォームが、電子的に開業届を提出するための専用画面です。
ステップ3:開業届の必要事項を入力する
フォームに進んだら、氏名、住所、生年月日、職業、開業日、事業内容、屋号などの情報を入力していきます。基本的には紙の開業届と同じ項目で構成されているため、あらかじめ内容を整理しておけばスムーズに進められます。青色申告を希望する場合は、申請欄で「する」を選択することを忘れないようにしましょう。通常は添付書類は必要ありませんが、税務署から指示があった場合には、案内に従ってファイルを添付してください。すべての入力内容を確認したら、送信に進みます。
ステップ4:電子署名の付与と受信通知の保存
開業届の入力が完了したら、マイナンバーカードを使って電子署名を付け、データを送信します。送信が正常に完了すると、e-Taxのメッセージボックスに「受信通知」が届きます。この通知には提出者の情報や受付番号、提出日時などが記載されており、正式な提出記録として保存しておくことが大切です。受信通知はダウンロードできますので、必ず自身のパソコンに保存しておきましょう。証明資料として将来必要になる可能性もあるため、バックアップの保管をおすすめします。
電子申請等証明書の取得方法
より公的な証明が必要な場面では、「電子申請等証明書」を取得することも検討しましょう。これは、e-Taxで行った電子申請の事実を税務署が正式に証明する文書であり、申請者の名義と提出日時などが明記されたPDFファイルとして交付されます。手数料はかかりません。ただし、電子申請等証明書の取得にはマイナンバーカード方式での対応が必要です。
e-Taxのメッセージボックスから請求でき、申請後しばらくすると、電子的にダウンロードできる形式で受け取ることができます。この証明書は、銀行口座開設や補助金申請など、正式な提出記録が必要な場面で役立ちます。
開業届の提出前でも“開業済みであることを証明”する方法は?
開業届を提出する前でも、銀行口座の開設やサービス契約などで「すでに事業を開始していること」を求められる場合があります。その際は、事業の実態を示せる資料を組み合わせることで、開業前でも一定程度、事業を行っていることを説明できます。以下では、開業届未提出の状態でも有効とされる方法をまとめます。ただし、これらを「証明」と認めるかどうかは提出先の裁量によるため事前に確認するほうが望ましいでしょう。
事業活動を示す書類を提示する
実際の取引が確認できる書類は、開業済みであることを示す強い根拠になります。取引先との契約書、請求書、領収書、見積書、納品書などが挙げられます。物販であれば仕入れ伝票や在庫管理の記録、サービス業であれば顧客とのやり取り、注文内容の記録なども有効です。また、事業用のWebサイト、SNSアカウント、ネットショップの販売ページ、広告運用の履歴なども事業活動の証拠として評価されます。これらを複数提示することで、開業届が未提出でも事業実態を示すことができます。
事業に関連する契約書類を利用する
事務所や店舗の賃貸借契約書、事業用スマートフォンの契約、クラウドサービスの利用契約など、事業運営に必要な契約書類も証明として役立ちます。契約書に事業内容が記載されている場合や屋号で契約している場合は証明力が高まります。銀行や決済サービスでは、これらの契約書類と合わせて事業説明書の提出を求められることもあります。
開業届の提出予定を説明し補足資料を付ける
開業届未提出でも、「提出予定であること」を説明し、事業内容・開業予定日・提供サービスなどをまとめた説明書を補足資料とともに提出する方法も有効です。この際、前述した事業活動を示す書類や契約書類を添付しておくと、開業準備が進んでいることをより明確に示せます。
なお、開業届は原則として事業の開始などの事実があった日から1か月以内に提出することとされていますが、提出が遅れた場合でもそれ自体を理由とした罰則はありません。ただし、青色申告承認申請書の期限など他の手続きに影響することがあるため、可能な限り早めの提出が望ましいでしょう。
収受印廃止後も対応できるよう、開業届の証明と提出方法を知っておこう
開業届は、個人事業を始めたことを示す大切な書類です。2025年から控えへの収受印が廃止され、証明の方法が変わりましたが、e-Taxの受信通知や電子申請等証明書、税務署の閲覧サービスや個人情報開示請求を活用すれば、提出事実を確認できます。屋号付き口座の開設や融資申請といった場面でも、こうした代替手段で対応できます。これからは自分で提出記録を残す意識を持ち、適切な方法で備えておきましょう。
よくある質問
開業届の控えが必要になる場面とは?
屋号で銀行口座を作る場合や、法人用のクレジットカードを作る場合、事業資金の融資を受ける場合などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届の控えを確認するには?
税務署の窓口に行けば、申告書等閲覧サービスにより、自分が過去に提出した開業届を無料で閲覧できます。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届を再提出して控えをもらう方法も?
保有個人情報開示請求書を提出して開業届の控えをもらうには1カ月程度がかかることがありますが、開業届を再提出すればすぐに入手することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
開業届の書き方の関連記事
新着記事
養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説
Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…
詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説
Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…
詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説
Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…
詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説
Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…
詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説
Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…
詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説
Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…
詳しくみる