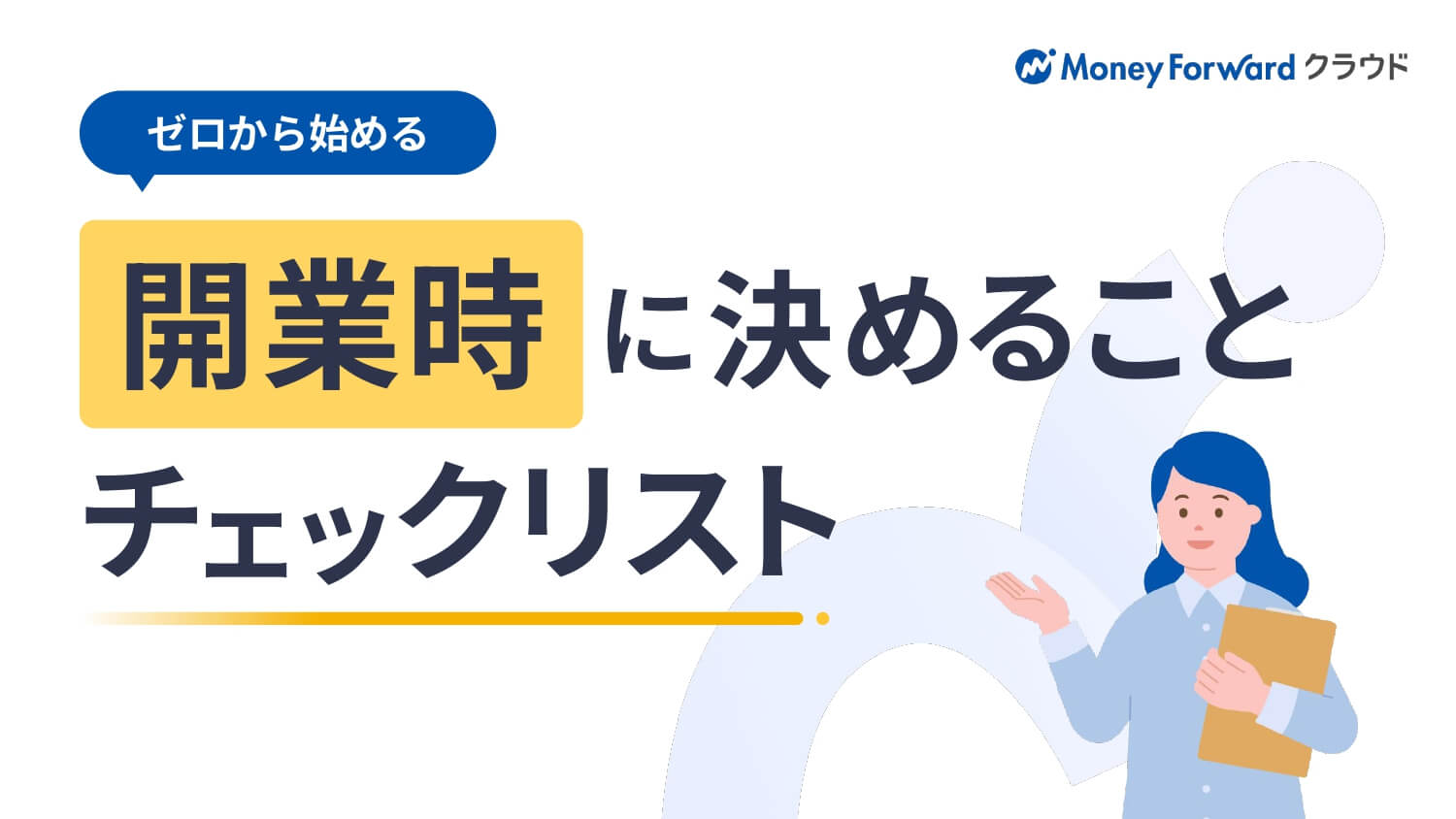- 更新日 : 2025年7月25日
開業届はどこでもらえる?国税庁サイトや無料の開業届ソフトで手に入れよう
開業届は、個人事業主が事業を始めるにあたって税務署に提出する書類であり、事業の開始日から1月以内に税務署に提出します。この届によって税務署は事業者を把握し、課税に関する連絡等を行えるようになります。
取引先と業務委託契約を結び、個人事業主になった場合もこの開業届の提出が必要です。期限内に提出するようにしましょう。
目次
開業届はどこでもらえる?
開業届は基本的に屋号や事業概要を簡潔に記載するもので、紙の申請の他、電子申請でも提出できます。
国税庁のホームページ
最も手軽な開業届の入手先は国税庁のホームページであり、下記のリンク先にて[申請書様式・記載要領]に掲載されているPDFファイルをダウンロードして、入手します。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」
ダウンロードしたファイルは、自宅やコンビニのプリンターなどで印刷し、必要事項を記入・捺印のうえで所轄の税務署へ持参または郵送で提出できます。
なお、以前は副本(控え)を同時に提出すれば、収受印付きの返却を受け取る運用がありましたが、2025年1月以降は紙提出であっても収受印の押印は原則廃止されています。そのため、控えを証明書類として使用する場合は、提出済であることがわかるように写しを手元で保管するか、e-Taxでの電子申請+受付通知の保存を行う方法が推奨されます。
国税庁では銀行などに対して、融資や補助金の申請時などに収受印の押された申告書等(開業届も含む)の控えの提出を求めないよう要請しています。
ただし、まだ銀行口座の開設や補助金申請で開業届の証明が必要になる場合も考えられます。そこで、書面で開業届を提出した場合は、次の方法で提出年月日を証明します。
- 税務署配布のリーフレットを一緒に提出
税務署に開業届を提出する際には、提出日や税務署名を記載したリーフレットが希望者に配布されます。ただし、当分の間の対応となります。郵送で開業届を提出する場合に、リーフレットの配布を受けるためには、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。 - 保有個人情報の開示請求
税務署が保有している個人情報について、税務署の窓口またはオンラインで開示請求を行います。ただし写しの交付の場合は1カ月程度かかるので、余裕を持った対応が必要です。
制度変更後は、提出方法に応じた控えの取り扱いに注意しておきましょう。
開業届には、開業のタイミングで考えるべき「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」についても記載欄があるため、よく読んで対応しましょう。特にインボイス制度の経過措置と密接にかかわるため、課税事業者選択届出書について気になる場合は、税務署に確認してください。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7ご参照)|国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
マネーフォワード クラウド開業届
マネーフォワード社の「クラウド開業届」で処理をするのも手早い方法です。マネーフォワードIDの登録があれば、次の3ステップで開業届の印刷または電子申告ができます。
- 書類作成の準備:いくつかの質問に答える
- 情報の入力:フォームに沿って情報を入力する
- 書類の提出:提出前には何度でもやり直せます
参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」
税務署
開業届の用紙は、最寄りの税務署窓口で直接受け取ることができます。印刷環境がない方や、記入方法に不安がある方にとっては、職員に相談しながら取得・提出できる、最も安心かつ確実な方法です。税務署の窓口には「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式が常備されており、無料で取得できます。
受付時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時までです。初めて開業する方でも、その場で記入方法や添付書類の確認ができるため、手続きをスムーズに進められます。どうしても平日に窓口へ行けない場合は、税務署に設置されている「時間外収受箱」に投函すれば、夜間や休日でも提出が可能です。
また、「税務相談チャットボット」なども準備されているため、試してみるのもよいでしょう。
事業開始等申告書とは?どこでもらえる?
事業を始めた事実を税務署だけではなく、都道府県の税事務所にも届けましょう。所得税等の国税の管轄は税務署ですが、事業税などの地方税の管轄は税事務所です。
事業開始等申告書?名称は地域でさまざま
税務署の開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)は対象が国税です。事業税が課税される場合には地方税の開業届も提出する必要があります。
東京都などでは、開業届は「事業開始等申告書」と呼ばれます。また、大阪府では「事業開始・変更・廃止申告書」、愛知県では「開業事務所等設置報告書」となっており、都道府県により呼称は異なります。
なお、いずれも個人事業税の課税対象となる事業を開始等した場合や、事務所等を設置等した場合に申請が必要な書類です。
都道府県のホームページや税事務所で入手
各都道府県のホームページにおいて、「個人事業税」等で検索してみましょう。また、税事務所窓口で「事業開始の申告書」と言えば紙の申請書を入手できるでしょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人が事業を始めたことを税務署に届け出るための書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業届出書」と言います。
個人事業を開始した人が開業届を税務署に提出することで、税務署は提出者が個人事業主として開業したことを把握します。税務署は申告や納税に関する情報を個人事業主に通知したり、申告・納税できているかを管理したりします。
一般的に、会社員は毎月の給与から所得税が天引きされますが、個人事業主は1年間の収入をもとに所得税を自分で計算し、確定申告と納税を行います。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となるため、税務署への開業届の提出は納税者本人が行います。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に提出します。開業日があいまいでも問題ありません。開店日や勤め先を退職して独立した日など、本人が「開業した」と考える日を開業日にします。
開業届は期限を過ぎて提出しても、罰則などはありませんが、遅くとも事業を開始した年には提出しましょう。
開業届の提出方法は?
開業届の提出方法には、以下の3つの方法があります。
① 窓口提出(税務署へ直接持参)
所轄の税務署へ印刷した開業届を2部(提出用・控え用)持参し、窓口で提出します。
- メリット:その場で職員に確認してもらえるため、記入ミスの防止につながります。
- 注意点:控えの提出証明が必要な場合は、代替となる電子的な受付通知や提出書類のコピー保管、リーフレットの受け取りなどで代用します。税務署の受付時間は通常、平日午前8時30分から午後5時までで、混雑する場合もあります。
② 郵送提出
記入済みの開業届を2部印刷し、返信用封筒と切手を同封して所轄の税務署へ郵送します。
- メリット:税務署に直接出向く必要がありません。
- 注意点:控え(副本)を返送してもらうためには、返信用封筒・切手の同封が必要です。返送される控えには印が付かない可能性がありますが、当分の間は提出日や税務署名が記載されたリーフレットの返送を受けることができます。証明書類として必要な場合は、提出証拠の保管方法を別途検討してください。
③ e-Tax(電子申請)
国税庁のe-Taxシステムを利用して、開業届をオンラインで提出します。
開業届は事業所と自宅、どちらの税務署に提出する?
開業届を提出する際、「事業所と自宅が異なる場合、どちらを管轄する税務署に出せばよいのか?」が気になるかもしれません。税務署への提出先を誤ると、開業手続きが無効になったり、再提出を求められたりすることがあるため、事前に正しく理解しておくことが大切です。
自宅で事業を行う場合は自宅住所が基準
開業届は、納税地を所轄する税務署に提出します。納税地は一般的に住所地になるため、フリーランスや個人事業主が自宅で作業を行っている場合は、自宅がそのまま納税地となります。この場合、自宅住所を管轄する税務署が開業届の提出先になります。
開業届は「事業所の所在地」管轄の税務署に提出することも可能
住所地のほかに事業所がある場合は、事業所の所在地を納税地にすることができます。その場合、開業届は事業を行う「事業所の所在地」を基準に、その住所を管轄する税務署に提出します。たとえば、自宅とは別に事務所や店舗、アトリエなどの拠点を構えている場合、その事業所の住所を納税地にできます。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届の控えが必要となる場面ともらう際の注意点
開業届の提出控えは、さまざまな手続きや申請において事業の実態を証明する重要な役割を果たします。現在は、税務署窓口や郵送による紙提出でも収受印が原則廃止されているため、控えの取得・保管方法には注意が必要です。
青色申告の承認申請時
青色申告を希望する場合は、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。開業届の控えは、提出済みであることの確認や、税理士との相談時に内容を参照する資料として活用されます。申告制度の特性上、記帳ルールや提出期限に厳格な運用があるため、開業届の控えは厳重に保管しておくことが重要です。
銀行口座の開設
屋号付きのビジネス口座を開設する際、多くの金融機関で「開業届の控え」の提出が求められます。ただし、国税庁では銀行などに、融資や補助金の申請時などに収受印の押された申告書等の控えの提出を求めないよう要請しています。そのため、収受印の押された開業届の控えの提出が求められることも少なくなるでしょう。
従来は収受印付きの控えが基準とされていましたが、現在は電子申請で取得した控えPDFや、提出済みを証明する受付通知・受信通知(e-Tax)を代用するケースが増えています。紙で提出した場合でも控えに印が付与されないため、開業届提出の際に受け取った受付日付や税務署名の記載があるリーフレットなど、事前に金融機関に使用可能な書類形式を確認することをおすすめします。
融資や補助金申請時
創業融資や補助金申請などでは、開業日・業種・所在地といった事業の基礎情報を裏付ける書類として開業届の控えが求められることがあります。電子申請ならPDF控えと受付通知を組み合わせることで対応可能です。提出先の要件に合わせて控え形式を準備しておくことが、審査通過の一助になります。
取引先との契約や信頼性の証明
新たな取引先と契約する際、事業が正式に届け出られていることを確認する目的で、開業届の控えの提示を求められることがあります。特に法人や公的機関との取引では、信頼性を証明するための基本資料となるため、提出形式(PDF、電子受付通知など)についてあらかじめ確認し、すぐに提示できる状態にしておくと安心です。
控えをもらう際の注意点
2025年以降、税務署に紙で開業届を提出しても、原則として収受印付きの控えは発行されません。ただし当分の間、希望者には開業届の提出日や収受した税務署名を記載したリーフレットが配布されるので、忘れずに受け取りましょう。
電子申請(e-Tax)を活用すれば、提出控え(PDF)や受付完了通知を取得・保存することができ、各種手続きに使用できます。紙で提出する場合も、提出した内容のコピーや提出日、提出先を記録し、必要に応じて提出済証明の発行依頼や電子控えの保存を検討しましょう。
開業届を電子申請したら控えをもらえる?
電子申請(e-Tax)で開業届を提出した場合でも、控えを取得することは可能です。提出後には「申告書等送信票(控え)」や「受付完了通知」「受信通知」などがPDF形式で発行されるため、これらをダウンロード・保存しておけば、提出証明として利用できます。印刷すれば紙の控えとしても活用可能です。
2025年1月以降は、紙で提出した場合でも収受印付きの控えが原則廃止されているため、電子申請で得られる控えが重要視されることも多くなるでしょう。そのため、今後はe-Taxを利用した提出とPDF控えの保管が実務の主流となっていくかもしれません。
控えは、融資申請や屋号付き銀行口座の開設、補助金・助成金の申請など多くの場面で必要になります。電子控えを確実に保存し、必要に応じてプリントアウトして提出できるようにしておくことが、開業後のスムーズな事業運営につながります。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
開業してから事務所設立までの流れ
会社を設立して事業を立ち上げるときには、事務所を用意する他にも設立登記、届出など実にさまざまな手続きが必要になります。今回は、事務所を手に入れる方法から開業して事業を開始するまでに…
詳しくみる郡山市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
郡山市で開業届を提出する際は、郡山市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、郡山市の管轄税務署に提出…
詳しくみる個人タクシーを開業するには?必要な条件、資金、失敗を防ぐコツを解説
一般社団法人全国個人タクシー協会によると、2023年4月30日時点で日本全国に2万6788人の個人タクシー事業者が存在しています。また、個人タクシー事業者の平均年齢で、64.8歳と…
詳しくみる前橋市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
前橋市で開業届を提出する際は、前橋市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、前橋市の管轄税務署に提出…
詳しくみる個人事業主SEとは?開業までの流れや経費、確定申告のやり方について解説
個人事業主SEは収入の増加や自由度の高さなどのメリットがありますが、収入の不安定さなどのデメリットもあります。本記事では、個人事業主SEの業務内容や平均年収、働き方、検討すべきタイ…
詳しくみる店舗開業に必要な準備は?必要な資格や流れを解説
店舗を開業することは、多くの人にとって夢の実現であると同時に、大きな挑戦でもあります。成功する店舗開業には、入念な準備と適切な手続きが不可欠です。この記事では、店舗開業を成功させる…
詳しくみる