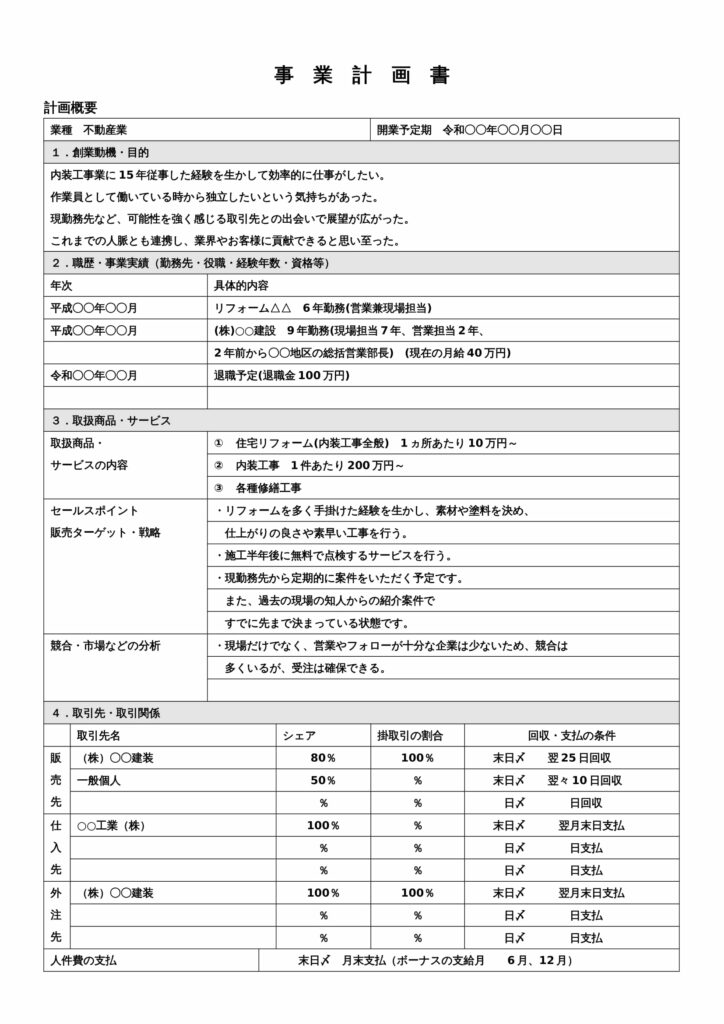- 更新日 : 2025年11月25日
宅建業(宅地建物取引業)の許認可とは?不動産の会社設立で必要なこと
宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、事業所の所在地に応じて都道府県知事または国土交通大臣からの許認可(免許)が法律で義務付けられています。
これは、宅地・建物の売買や交換、その賃貸を含む取引の「代理・媒介」を反復継続して業として行う事業を適正化し、消費者保護と公正な取引環境を確保するための制度です。
初めて不動産業を開業される方は、「どの免許区分に当たるのか」「どの条件を満たせばよいのか」といった疑問を抱きやすいでしょう。
この記事では、宅建業の許認可(免許)の種類から取得条件、申請手順、更新手続きまでを詳しく解説します。
目次
宅建業の許認可(免許)はなぜ必要?
宅建業の免許は、宅地や建物の売買・交換・賃借の「代理」または「媒介」を、反復継続して事業として行う場合に必要です。これは宅地建物取引業法に基づき、消費者保護と取引の公正確保のために定められています。まずは、どの行為が宅建業に当たるのかを理解しましょう。
そもそも宅建業とは何か
宅建業(宅地建物取引業)とは、上記の代理・媒介を継続的に行う事業を指します。典型例は次のとおりです。
- 自社で仕入れた宅地・建物を不特定多数に販売する行為(自ら売主)
- 売主と買主の間に入り、売買の仲介(媒介)を行う行為
- 貸主と借主の間に入り、賃貸借の仲介(媒介)を行う行為
宅建業免許が不要なケース
すべての不動産取引に免許が必要なわけではありません。
自社が所有する物件を自ら貸主として賃貸する行為(いわゆる大家業)は、代理・媒介に当たらないため原則として免許不要です。
一方、自己物件の売却については注意が必要です。たとえば特定の相手(グループ会社等)への売却であっても、転売目的で取得した物件の処分、区画分譲、広告で広く買主を募る販売など、行為全体の事業性(反復継続性・取得経緯・販売態様)が高いと判断されれば、宅建業に該当し免許が必要となる場合があります。
宅建業免許と宅建士資格の違いは?
不動産会社の設立を考える際、宅建業免許は事業者(法人・個人事業主)に対する許可であり、宅地建物取引士(宅建士)は個人の国家資格です。
宅建士は重要事項の説明(35条)や契約書への記名(37条)などの独占業務を担い、各事務所で従事者の5分の1以上の専任の宅建士の配置が免許要件とされています。つまり、事業の許可(免許)を、人の資格(宅建士)が支える構造です。
| 項目 | 宅建業免許 | 宅建士(宅地建物取引士)資格 |
|---|---|---|
| 対象 | 法人または個人事業主(宅地建物取引業を営む者) | 個人(不動産取引に従事する者) |
| 法的根拠 | 宅地建物取引業法(第3条~) | 宅地建物取引業法(第16条~) |
| 性質 | 不動産取引業を「業」として行うための行政上の許可(免許) | 不動産取引に必要な専門知識と実務能力を証明する国家資格 |
| 目的・役割 | 宅地建物取引業を適法・公正に営むための制度(消費者保護・取引安全) | 重要事項説明・契約書記名押印等の独占業務を通じて取引の適正を担保 |
| 取得方法 | 行政庁へ申請→書類審査・適格性審査(欠格要件・事務所要件等) | 国家試験合格→登録申請→宅建士証交付 |
| 有効期限 | 5年(更新時に再審査・手続要) | 登録は永久(宅建士証は5年ごとに更新講習が必要) |
| 免許・登録権者 | 都道府県知事(1都道府県内のみ)/国土交通大臣(2都道府県以上) | 各都道府県知事 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
起業アイデアを磨く!自己分析3点セット
「やりたいことはあるけれど、ビジネスとして成立するか不安」という方へ。
自分の強み・価値観・市場ニーズを掛け合わせ、唯一無二のアイデアに昇華させる自己分析メソッドを3つのシートにまとめました。
経営スキル習得の12か月ロードマップ
「経営を学びたいが、何から手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?
本資料では、財務・マーケティング・組織作りなど多岐にわたる経営スキルを、12か月のステップに凝縮して体系化しました。
副業アイデア辞典100選
「副業を始めたいけれど、自分に何ができるか分からない」そんなあなたにぴったりの厳選100アイデアを公開!
スキルを活かす仕事から未経験OKなものまで、市場の需要や収益性を網羅しました。パラパラと眺めるだけで、あなたのライフスタイルに最適な働き方が見つかるはずです。
1から簡単に分かる!起業ロードマップ
起業に興味はあるけれど、複雑な手続きや準備を前に足踏みしていませんか?
準備から設立までの流れを分かりやすく図解しました。全体像をひと目で把握できるため、次に何をすべきかが明確になります。
宅建業免許の種類とは?知事免許と大臣免許の違い
宅建業の免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、宅建業を営む「事務所」(本店・支店等)の設置状況でどちらを申請するかが決まります。免許の種類が異なっても、行える業務内容に違いはありません。
事務所の設置場所で決まる免許の種類
免許の種類は、宅建業を行う事務所(本店、支店など)の所在地によって区分されます。
| 免許の種類 | 事務所の設置状況 | 免許権者 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 | 事務所所在地の都道府県知事 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 |
例えば、東京都内のみに本店と支店を置く場合は「東京都知事免許」、東京都に本店を、神奈川県に支店を置く場合は「国土交通大臣免許」が必要になります。
知事免許から大臣免許への切り替え(免許換え)
事業拡大で別の都道府県に新たに事務所を設置する等により免許区分が変わる場合、既存の免許を返納し、新たな区分で免許を取得する「免許換え」が必要です。免許換えにより従前の免許は効力を失い、免許番号も新しいものになります。
参照:宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|東京都住宅政策本部
宅建業の許認可(免許)を得るための条件とは?
宅建業の許認可(免許)を得るには、宅地建物取引業法で定められた複数の要件をすべて満たさなければなりません。これらの要件は、事業の安定的な運営と消費者保護を目的としています。
1. 事務所の設置
宅建業を営むためには、継続的に業務を行える独立した形態の事務所を設ける必要があります。物理的な事務所の存在が必須で、単なる登記上の本店所在地だけでは認められません。
一般的な要件は以下のとおりです。
- 物理的な区画:他の法人や個人のスペースとパーテーションなどで明確に区切られ、独立性が保たれていること
- 継続的な使用権限:自社所有または賃貸借契約などに基づき、継続して使用できる権限があること
- 業務に適した設備:電話、机、帳簿保管設備、複合機、接客スペースなど、宅建業務を継続的に行うのに必要な設備を備えること
2. 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所には、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置することが義務付けられています。宅建士は、その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事する必要があります。
- 常勤性:当該宅建業者の事務所の営業時間中、通常勤務できる状態にあることをいいます。
- 専任性:当該宅建業者の宅建業務に専ら従事し、他の業務に支障を及ぼさない状態を指します。
3. 欠格要件に該当しないこと
宅建業免許の申請者(法人の場合はその役員等、個人の場合は本人)は、宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないことが免許取得の前提条件です。欠格要件は、宅建業の公正性・信用維持の観点から、刑事罰・行政処分・暴力団関係・経営能力・心身状態など多岐にわたります。
主な欠格要件は以下のとおりです。
- 不正手段により免許を取得した者/業務停止命令に違反し免許を取り消され、その日から5年を経過しない者/取消処分を受けた法人の旧役員等で取消しから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 宅建業法、暴力団対策法、風営法、破産法、刑法など一定法令違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員が事業活動を支配している者
- 破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者
4. 営業保証金の供託または保証協会への加入
宅建業者は、宅地建物取引業法第25条に基づき、取引の相手方(消費者等)が損害を被った場合に備えた弁済措置をとらなければ、営業を開始できません。これは免許通知を受けた後、営業開始前までに行う手続きです。弁済措置には次の2通りの方法があります。
| 措置 | 概要 | 主たる事務所(本店) | その他の事務所(支店) |
|---|---|---|---|
| 営業保証金を供託 | 事務所ごとに一定額の「営業保証金」を法務局に供託する方法 | 1,000万円 | 1カ所につき500万円 |
| 保証協会に加入 | 指定保証協会(※)に加入し、代わりに「弁済業務保証金分担金」を納付する方法 | 弁済業務保証金分担金:60万円 | 1カ所につき30万円 |
多くの事業者は、初期費用を抑えられる保証協会への加入を選択します。保証協会に加入する場合、上記の分担金以外に入会金・年会費などの費用が別途かかります。
※ 指定保証協会とは国土交通大臣が指定した公益法人であり、2025年現在は以下の2団体
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(通称:ハトマーク)
- 公益社団法人 不動産保証協会(通称:全宅保証)
5. 代表者の常駐性
宅地建物取引業法自体には「代表者が事務所に常駐していなければならない」という条文は存在しません。しかし、宅建業法第5条(欠格要件)・第31条(業務の適正化)・第50条(報告義務)の趣旨に基づき、都道府県等の免許権者は「事務所運営の実質的管理体制」を審査対象としており、この中で「代表者が常勤して実質的に業務を統括しているか」が確認されます。申請先の自治体の要件を事前に確認することが大切です。
宅建業の許認可(免許)申請の流れと必要書類は?
宅建業の許認可(免許)申請は、事前準備から営業開始まで複数のステップを踏む必要があり、標準処理期間は一般におおむね100日と見込むのが安全でしょう。自治体や案件の内容により短くなる場合もありますが、計画的に進めましょう。
STEP1:事前準備
申請に先立ち、免許の要件を満たすための準備を整えます。
- 法人の設立(定款の事業目的に「宅地建物取引業」などを記載)
- 事務所の確保(独立性・使用権限・設備の要件を満たす。賃貸借契約の締結など)
- 専任の宅地建物取引士の確保(5名につき1名以上・常勤専任など)
STEP2:申請書類の作成
都道府県や地方整備局のウェブサイトから申請様式を入手し、必要事項を記入します。法人の登記事項証明書、役員・専任宅建士の身分証明書・登記されていないことの証明書、事務所の写真等、添付書類は多岐にわたるため、漏れなく準備します。
- 免許申請書/相談役・顧問・株主の名簿
- 身分証明書(役員・専任宅建士)/登記されていないことの証明書(役員・専任宅建士)
- 略歴書(役員・専任宅建士)/専任の宅地建物取引士証の写し
- 法人の登記事項証明書
- 事務所の使用権原書類(賃貸借契約書写し等)
- 事務所写真(外観・入口・内部 等)
STEP3:行政庁への申請と手数料納付
管轄の行政庁(知事免許=都道府県、大臣免許=国交省地方整備局)に提出し、所定の手数料を納付します。手数料は自治体や申請方式(紙/電子)で異なります。申請時には、所定の申請手数料(例:東京都では電子申請における新規・更新免許申請に係る手数料額は26,500円)を納付します。
オンライン申請(電子申請)も可能
申請方法は、従来、管轄の行政庁へ書類を持参または郵送するのが一般的でしたが、近年では行政手続きのデジタル化が進んでいます。2025年1月からは国土交通省のシステムを通じて、多くの自治体で宅建業免許の新規申請や更新などがオンラインで可能になりました。利用にはGビズIDの取得などが必要な場合があるため、申請先の行政庁のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。
STEP4:行政庁による審査
書面審査等により、要件充足が確認されます。標準処理期間は前述のとおりおおむね100日が目安です。
STEP5:免許の交付(通知)と営業保証金の手続き
免許通知(はがき等)受領後、営業開始前に次のいずれかを選択します。
- 営業保証金の供託:本店1,000万円/支店1か所500万円(供託所=法務局等)
- 保証協会へ加入:弁済業務保証金分担金 本店60万円/支店30万円(別途入会金等あり)
免許日から3か月以内に供託または分担金納付を済ませ、所定の届出を行わないと、催告・取消の対象となり得ます。
STEP6:免許証の交付と営業開始
供託または保証協会加入の手続き完了後、その旨を行政庁に届け出ることで、正式に免許証が交付されます。免許証を受け取った後、宅建業の営業を開始できます。
参照:宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|東京都住宅政策本部
宅建士以外にあると有利な不動産関連資格は?
宅建士は不動産取引の独占業務を担う必須資格ですが、関連資格を併せて備えることで、事業領域の拡張や提案力の底上げが図れます。賃貸管理やマンション管理を扱うなら、法令上の選任・配置義務に直結する資格要件の理解が不可欠です。
賃貸不動産経営管理士
賃貸アパート・マンション等の管理受託に関する専門知識を証明する有力資格。
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣登録が義務となります。そのうえで営業所・事務所ごとに「業務管理者」を1名以上配置しなければなりません。業務管理者の資格要件の一つとして、賃貸不動産経営管理士の保有が認められています。
賃貸管理業を事業の柱にする場合には、取得しておくとよいでしょう。
管理業務主任者
分譲マンションの管理組合と管理委託契約を結ぶ際の重要事項説明や契約書への記名など、独占業務を行える国家資格です。マンション管理業を営む場合、事務所ごとに一定数の設置が義務付けられています。
ファイナンシャル・プランナー(FP)
住宅ローンの組み方、税金、保険、相続など、顧客のライフプランに関わる資金計画のアドバイスを行う専門家です。不動産の購入は大きな資金計画を伴うため、FPの知識は顧客からの信頼獲得につながり、提案の質を高めます。
| 資格名 | 概要とメリット |
|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸住宅の受託管理に関する専門知識を証明する。業務管理者の要件の一つに位置づけ。 |
| 管理業務主任者 | マンション管理業で重要事項説明・契約書記名の独占業務。事務所ごとに専任者の設置義務(目安:管理組合30につき1名) |
| ファイナンシャル・プランナー(FP) | FP技能士=国家検定/AFP・CFP=民間認定。住宅ローン・税・保険を横断し提案の妥当性を補強できる。 |
宅建業免許の更新や変更手続きはどうする?
宅建業免許の有効期間は5年間です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります。期限を過ぎると更新申請は受理されず免許が失効するため、逆算したスケジュール管理が重要です。
5年ごとの免許更新
免許の有効期間は5年間。満了日の90〜30日前が更新申請の受付期間です。この期間外は更新できず、失効した場合は新規申請からやり直しになります。その間は宅建業を営めないため、社内の更新管理(期限アラートや担当者の二重チェック)を徹底しましょう。
変更があった場合の届出
免許取得後、商号・代表者・役員・主たる事務所や従たる事務所の所在地・専任の宅地建物取引士など、名簿登載事項に変更が生じた日から30日以内に「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を提出します。
自治体によっては免許証書換え交付申請(商号・代表者・所在地変更等)も併せて必要になるため、手引の様式・必要書類を確認してください。
なお、専任の宅建士が欠けた場合は、原則2週間以内に補充し、そのうえで30日以内に変更届を提出するのが各自治体手引に基づく運用目安です。不補充が続くと指導・業務停止等の行政処分の対象になり得ます。採用・異動の計画時点で代替要員の確保と届出の準備を並走させておきましょう。
宅建業の許認可(免許)取得は、計画的な準備が大切
宅地建物取引業の許認可(免許)を得るには、法律で定められた人的・物的・財産的要件をすべて満たす必要があります。事務所の確保や専任の宅建士の設置といった準備から、申請書類の作成、営業保証金の供託まで、計画的に進めることが大切です。
免許の種類は事業所の設置場所で異なりますが、どちらも公正な不動産取引を支える制度です。有効期間は5年で、事業を続けるには更新手続きが求められます。近年は電子申請も普及しつつあるため、最新情報を確認して手続きを進めるとよいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
塗装業に許認可は不要?開業の流れや建築業許可が必要な金額・条件を解説
塗装業を開業する際には、必要な資格や許可はありません。そのため、誰でも始めることが可能です。ただし、クライアントの信頼を得たいのであれば塗装技能士や有機溶剤作業主任者など資格を取得…
詳しくみる1番儲かるキノコは?収益性が高い品種や起業の流れを解説
Point1番儲かるキノコは? 最も儲かるキノコは、価格ではなく再現性と需要が高い品種です。 安定需要はシイタケ 高単価なら国産キクラゲ 栽培再現性が収益を左右 菌床シイタケを直販…
詳しくみる歯科医は儲かる仕事?年収・収益構造・失敗しない経営戦略を解説
Point歯医者は「儲かる職業」と言える? コインランドリー事業計画書は、創業目的・市場調査・収支見通しを具体的に記載します。 平均年収は約1,100万円 保険診療は安定収入 自費…
詳しくみる保証業に許認可は必要?家賃債務保証業の登録制度の要件からメリットまで徹底解説
現在、「保証業」全般を横断して義務づける共通の免許制度はありません。一方で、賃貸住宅の入居者の家賃債務を対象とする保証については、国土交通省所管の任意登録制度(家賃債務保証業者登録…
詳しくみる起業と創業と開業の違いってなんだろう?意味や使い方について解説
起業と創業、開業の違いが分からなくなった人もいることでしょう。これらの言葉は「新しく事業を始めること」という共通の意味を持ちますが、それぞれでニュアンスの違いがあります。この記事で…
詳しくみる一般社団法人で儲かることは可能か?収益を上げるポイントや注意点を解説
一般社団法人はビジネスの器として非常に優秀であり、その特性を正しく理解すれば収益性の高いモデルを構築することが可能です。 「一般社団法人はボランティア団体だから儲からない」「利益を…
詳しくみる