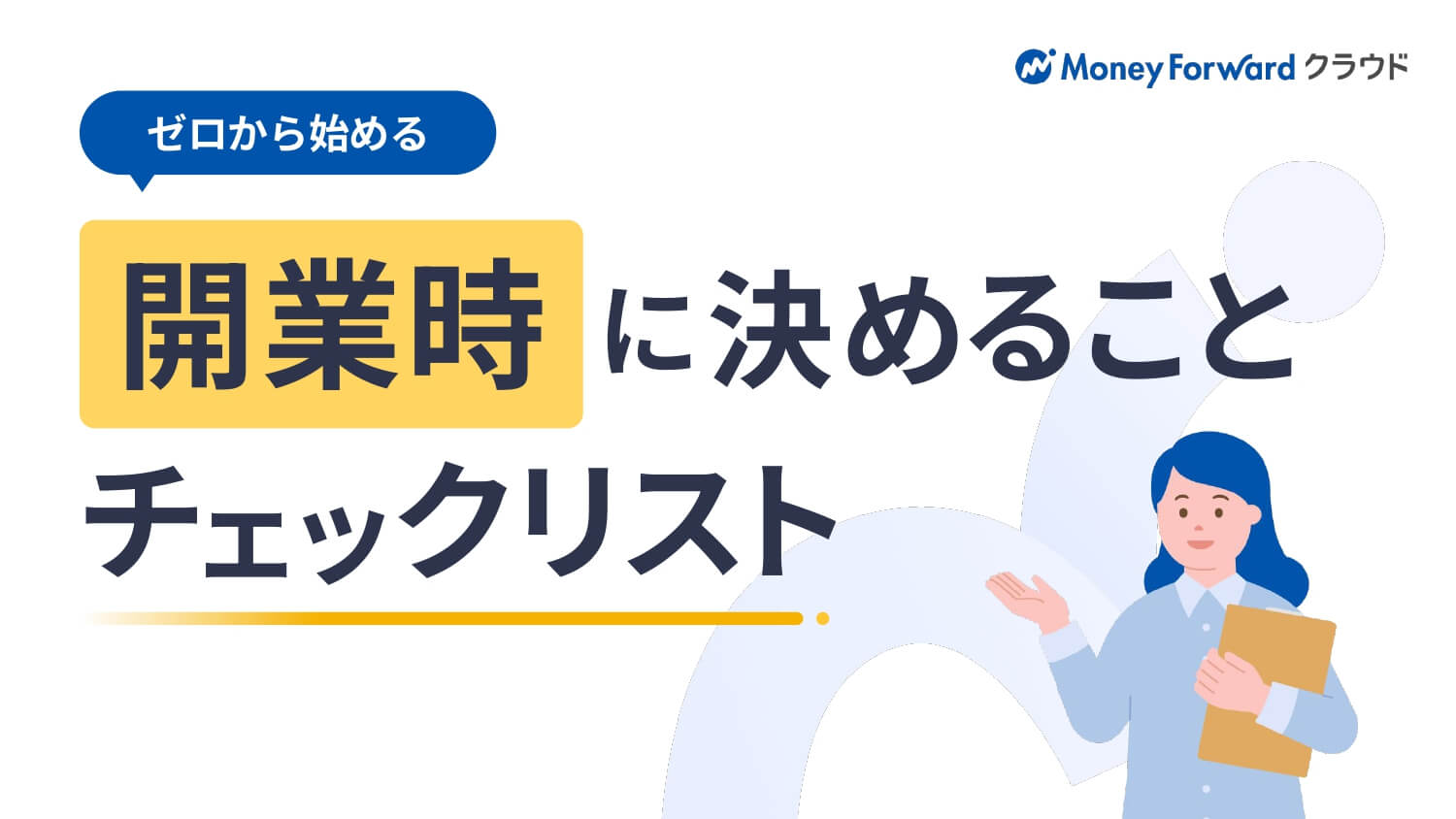- 更新日 : 2025年10月15日
【会社を辞める前に】フリーランスになるために必要な手続きまとめ
会社から独立し、フリーランスとして働くためには様々な準備が必要です。資金の用意、役所への様々な書類の提出、仕事をする上で必要な備品を揃えることなど、やらなければならないことはたくさんあります。
フリーランスとは、いわゆる「個人事業主」です。それはつまり、会社を経営すると同時に、営業も事務手続きも備品管理もすべて一人でこなさなければならないということです。
そこで今回はフリーランスとしての生活を滞りなくはじめ、スムーズに仕事を開始するために必要な手続きをまとめました。独立をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
フリーランスになるために必要な手続き
会社を辞め、フリーランスとして新たに歩みだす場合、いくつかの手続きを行う必要があります。
1.開業届を出す
新たに事業を始めた時、事業を廃止する時に開業届が必要になります。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、開業時のほかに事務所を新設、増設、移転した際にも必要になります。この書類は「納税地」を管轄する最寄りの税務署に提出します。
開業届は個人事業を行う方は全員提出する必要があり、提出期限は開業日から1ヶ月以内となっていますので忘れないようにしましょう。
参考:独立・開業の第一歩!「開業届」の書き方と抑えておきたい3つのポイント
2.国民年金の手続き

フリーランスになったら国民年金保険料を自分で払う必要があります。これは居住している市区町村役場で支払いの手続きを行います。手続きの際には、年金手帳を忘れずに準備しましょう。もしも年金手帳を紛失してしまっていた場合は、年金事務所で手続きを行う必要があります。
3.国民健康保険に加入する
多くの場合、これまで勤めていた会社の健康保険・雇用保険・厚生年金保険から脱退し、国民健康保険に加入することになります。これは居住している市区町村役場で必要な手続きを行います。
また、国民健康保険に加入する代わりに2年間に限り、任意で前の会社の健康保険に継続して加入したままでいることも可能です。しかし、この場合は会社が負担してくれていた分の保険料も払う必要があるため、これまで支払っていた額の2倍となるので注意が必要です。
4.青色申告承認申請書を提出する

Photo by bfishadow
フリーランスになったらしっかりと1年間の収支を記録して確定申告をしなければなりません。その際には白色申告よりも控除額の大きい青色申告を選ぶと節税できます。また、青色申告をするためには青色申告承認申請書を用意する必要があります。
確定申告は2月から3月の間に提出する必要があります。例年ほぼ同じ時期ですが、若干受付の開始日と終了日が異なるので注意が必要です。また、開業をした最初の年は、開業日から2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。これは先の開業届と一緒に提出することもできるので、一緒に用意しておくと手間を省くことができます。
お金に関する準備
一人で働いているうちは経理事務も自分で行う必要があります。お金に関するトラブルを起こさない為にも、以下の準備を忘れないようにしましょう。
1.仕事用の口座をつくる
確定申告や、自身の売り上げなどを把握しやすくするためにも、プライベート用と仕事用の2種類の口座を用意するようにしましょう。特に、自宅を事務所として利用する場合は光熱費やインターネットプロバイダの料金なども経費とできるため、仕事用の口座から引き落とされるようにしておくと節税にもなります。
2.クレジットカード・ローンを申し込む

Photo by Sean MacEntee
フリーランスになると会社員と比べて新しくクレジットカードを作ったりローンを組むことが比較的難しくなります。できるだけ会社員のうちにこれらの手続きを澄ましておくと後々楽になります。
3.売上計画を立てる
独立する前にはしっかりとフリーランスで生活していくための計画を練るようにしましょう。特に売上計画はしっかりと立てておいた方がいいでしょう。毎月必要な経費からどの程度の貯金が必要なのかを把握しておくだけでも違います。見切り発車で独立してしまうと思わぬ苦労をすることになりかねません。ここはじっくりと計画を立てるようにしましょう。
参考:来年こそ思った通りの1年に!計画を“確実に”実現するために必要な3つのこと
4.複式帳簿をつける

青色申告をする場合、複式簿記をつける必要があります。ですが複式簿記を作成するためにはある程度の専門知識が必要です。事前に勉強するのも一つの方法ですが、青色申告ができる青色申告用の会計ソフトを利用すると楽にできます。
もし資金に余裕があるのならプロである税理士に依頼すると安心です。もしくは、会計ソフトを利用して入力だけ自分で行い、残りをプロに依頼することでコストを下げられる場合もあります。なるべく自分の手を煩わさせない方法を選びましょう。
備品をそろえる
勤めていた時は会社が用意してくれていた様々な備品も当然、フリーランスは自分で用意する必要があります。
ここでは独立してから慌てないように、最低限そろえておきたい備品を紹介します。
1.名刺
フリーランスにとって人脈作りは非常に重要です。特に、企業などの団体に所属していないので自分が何をしているのかがわかる名刺を常に持ち歩くようにしましょう。
参考:
・名刺作成サービス徹底比較!(作成シミュレーションあり)
・フリーランスの名刺管理フリーソフト徹底比較!
2.印鑑
普通に生活する分には印鑑は1つあれば十分ですが、フリーランスとして活動する場合は屋号印が便利です。また、領収書や請求書などの書類を作成する時のために住所印、請求書在中印もあると便利です。
参考:
・覚えておきたいビジネス印鑑の種類と社印の押し方まとめ
・個人事業主必見!デザイン名刺作成・印刷サービス10選
3.契約や書類整理のための備品

ビジネスを行うためには様々な書類が必要になります。これらをしっかり管理するためのファイルやバインダーは常に余裕を持った量を用意しておきましょう。また、郵送する際などクリアファイルが足りなくなるといちいち買いに行くのは大きな手間です。常に必要になるものは余裕をもって数を揃えておくようにしましょう。
また、契約書や請求書など同じフォーマットを使いまわせる書類は事前にひな形を用意しておくと楽に作業ができます。独立する前に一度、どの様な事務用品が必要になるかシミュレーションしておくといいでしょう。
4.通信環境整備
どんなに優秀な方でも連絡がつかないと仕事になりません。通信環境はしっかりと用意しておきましょう。
電話やメールは当然ながら、日本ではまだファックスを利用した取引も多く行われているのでファックスも受信できるようにしていると安心です。
また、外での打ち合わせや取材などの時のために、持ち運び可能なサブパソコンやタブレットなども用意しておくと仕事がしやすくなります。
おわりに
フリーランスになると様々な事を自分でする必要があります。特に今回紹介したような備品の用意や書類手続きは企業だと経理や総務が代わりにやってくれている場合が多く、普通に会社に勤めている間はあまり意識しない部分です。
独立したら身の回りの準備が忙しくて仕事どころじゃない、などということになっては本末転倒です。そうならないようにするためにも、独立する前にできることは極力準備をしておくようにしましょう。
よくある質問
フリーランスになるために必要な手続きは?
「1.開業届を出す」「2.国民年金の手続き」「3.国民健康保険に加入する」「4.青色申告承認申請書を提出する」の手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
お金に関する準備は?
「1.仕事用の口座をつくる」「2.クレジットカード・ローンを申し込む」「3.売上計画を立てる」「4.複式帳簿をつける」の4つです。詳しくはこちらをご覧ください。
独立してから最低限そろえておきたい備品は?
「1.名刺」「2.印鑑」「3.契約や書類整理のための備品」「4.通信環境整備」などが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
個人事業主・フリーランスの関連記事
新着記事
店舗を存続させる!事業計画立案のポイントと実務
株式会社hacomonoと共催セミナー「店舗を存続させるための事業計画立案のポイントと実務」を開催しました。本記事は、株式会社ナレッジラボ 税理士/中小企業診断士 大道 智之による…
詳しくみる里親手当で儲かる?制度の仕組み・支給額・費用・税金を解説
Point里親手当で生活が楽になったり、儲けが出たりする? 里親手当は、子どもの養育費を補助する制度であり、儲かる仕組みではありません。 養育費の実費補助 利益目的は不可 融資を意…
詳しくみる本店移転の手続きはどう進める?登記から各種届出までわかりやすく解説
Point本店移転では、何をどの順番で行う必要がある? 本店移転は、社内決議→登記→各機関届出の順で行う法定手続きです。 登記は移転日から2週 費用は3万〜6万円 登記後に届出必須…
詳しくみる墓参り代行は儲かる?仕事内容・料金相場・起業のポイントを解説
Point墓参り代行は、儲かるビジネス? 墓参り代行は、高単価で副業から収益化しやすいサービスです。 1件5千〜1.5万円 月数件でも黒字可 初期費用が少ない 月12件・単価1万円…
詳しくみる納税証明書(その1)とは?その2との違い・取得方法・請求時の注意点を解説
Point納税証明書(その1)は、どんな場面で必要になる? 納税証明書(その1)は、国税の納付状況を証明する公式書類です。 納付額と未納額を記載 融資・補助金で必須 税務署が発行 …
詳しくみる社会福祉法人を設立するメリットは?事業内容・他法人との違い・設立手順を解説
Point社会福祉法人には、どのような強みがある? 社会福祉法人は、公的支援と税制優遇を受けながら福祉事業を安定運営できる法人です。 補助金で施設整備可 税負担が大幅に軽減 社会的…
詳しくみる