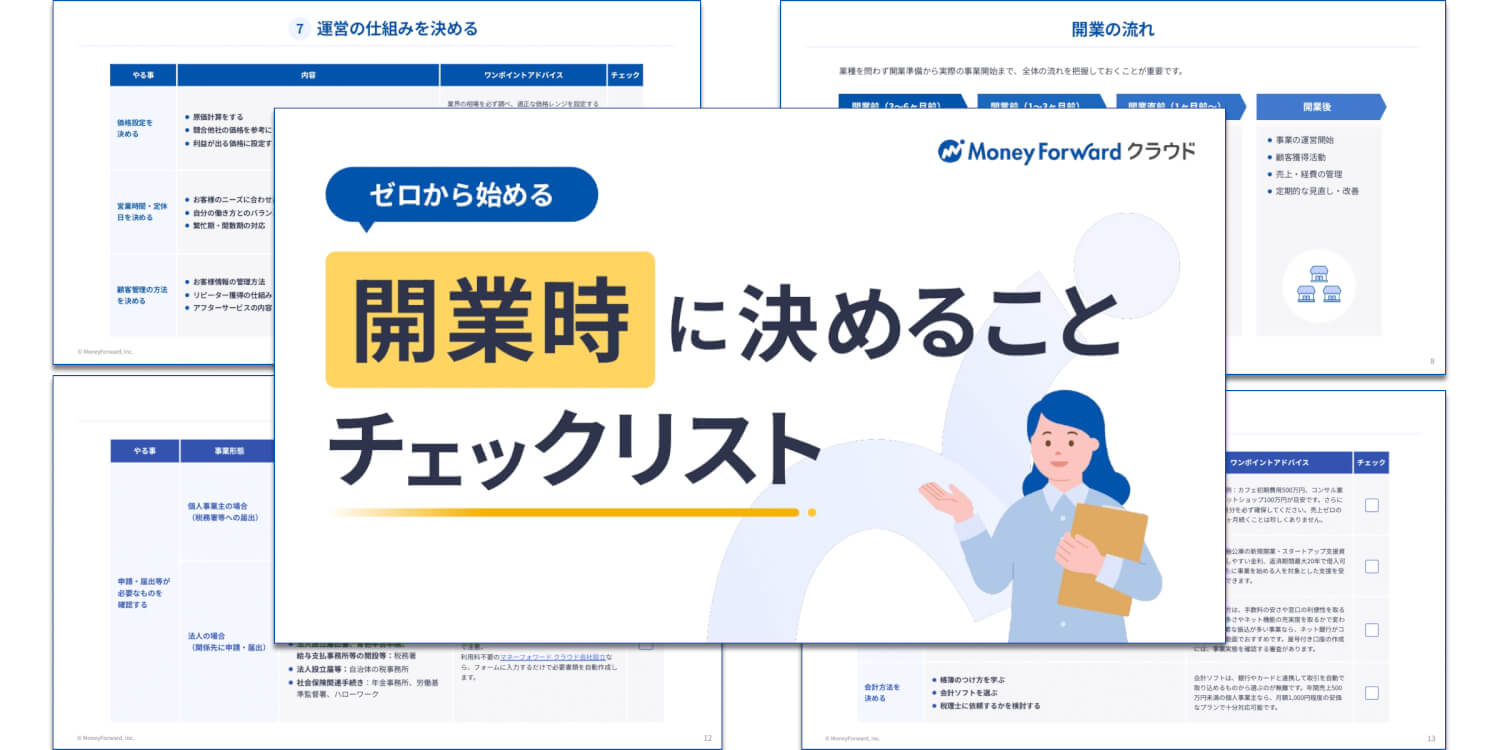- 作成日 : 2025年9月16日
登録販売者は独立開業できる?ドラッグストアの開業やフランチャイズ加盟などの方法を解説
医薬品販売の専門家である登録販売者の資格を活かして、いつかは自分の店を持ちたいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的にどうすれば開業できるのか、資金はどのくらい必要なのか、不安や疑問も尽きないはずです。
この記事では、登録販売者が独立開業するための具体的な方法、店舗管理者になるための要件、開業までのステップ、そしてビジネスを成功させるための秘訣を解説します。
目次
登録販売者は独立開業できる?
登録販売者は、独立して自分の店を開業することが可能です。ただし、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づき、医薬品を販売する店舗には、店舗の責任者である店舗管理者を置くことが法律で義務付けられています。そのため、自身が店舗管理者になるか、店舗管理者として雇用できる登録販売者を確保する必要があります。
そもそも登録販売者とは
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類・第三類医薬品の販売を担う専門資格です。薬剤師不足の解消や、地域住民のセルフメディケーション推進の観点から、その重要性は年々高まっています。ドラッグストアや薬局だけでなく、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、活躍の場は広がっています。
登録販売者が店舗管理者になるための要件
店舗管理者となるには、単に試験に合格するだけでは足りず、一定の実務経験と研修の修了が必要です。2023年4月の制度改正により要件が緩和され、以下の基準が適用されています。
- 実務経験の期間:過去5年以内に通算1年以上かつ合計1,920時間以上の勤務実績があること
- 追加的な研修:厚生労働省が定める「資質向上のための外部研修」を修了していること
これらを満たすことで、店舗の責任者(管理者)として自らの店舗を持つ、または管理者として勤務することが可能になります。
登録販売者の多様な独立開業方法
登録販売者の独立開業には、いくつかのスタイルがあります。それぞれの特徴を理解し、自身の経験や資金状況、目指すビジネスモデルに合った方法を選択することが重要です。
1. ドラッグストアを開業する
最も一般的な開業方法です。第二類・第三類医薬品を中心に、健康食品や日用品などを幅広く取り扱うことで、地域の健康を支える拠点となります。
- メリット
立地選定から品揃え、店舗デザインまで自由度が高く、自分の理想とする店舗づくりを追求できます。地域住民との信頼関係を構築できれば、安定的な顧客基盤を築くことが可能です。 - デメリット
競合が多く差別化が不可欠です。また、店舗取得費・内外装工事・商品仕入れなどで初期投資が高額になりやすく、資金調達のハードルも大きくなります。
2. コンビニエンスストアのフランチャイズに加盟する
近年、第二類・第三類医薬品を取り扱うコンビニエンスストアが増えています。大手フランチャイズチェーンに加盟して開業する方法です。
- メリット
大手ブランドの集客力と確立された経営ノウハウを活用できるため、比較的低リスクで開業が可能です。本部からのサポートも期待できます。 - デメリット
加盟金やロイヤリティが発生します。また、経営の自由度が低く、本部の経営方針に従う必要があります。
3. 漢方薬局や相談薬店を開業する
漢方薬やサプリメントなど、特定分野に特化した相談型の販売スタイルです。他店との差別化がしやすいのが特徴です。
- メリット
専門知識を活かしたカウンセリング販売が可能で、顧客一人ひとりと長期的な信頼関係を築けます。利益率の高い商品を取り扱える可能性があり、固定客を確保できれば安定経営につながります。 - デメリット
漢方やサプリメントに関する専門知識や継続的な学習が必要です。また、仕入れルートの確保や専門性のアピールが課題となります。
4. ネット販売(医薬品EC)に特化する
インターネットを利用して第二類・第三類医薬品を個人販売する方法です。
- メリット
店舗の立地に左右されず、全国の顧客をターゲットにできます。店舗運営コストを抑えられる可能性があります。 - デメリット
薬機法上、医薬品のネット販売を行うには許可を受けた実店舗の設置が必須です。また、ネット集客や物流管理、セキュリティ対策など、オンライン特有のノウハウが求められます。
5. その他の独立・起業アイデア
店舗を持つだけでなく、登録販売者の知識を活かして、以下のような形で独立することも考えられます。
- 健康や医薬品に関するWebライター
- ヘルスケア領域のコンサルタント
- 健康をテーマにしたセミナー講師
自身の興味や得意分野に合わせて、柔軟な働き方を選択できるのも登録販売者の強みです。
登録販売者が独立開業するまでの流れ
登録販売者としてドラッグストアなどを開業するには、周到な準備と計画が必要です。夢を実現するための具体的なステップを解説します。
1. 事業計画書の作成
まず、どのような店にしたいのか、具体的なコンセプトを固めます。例えば、特定の健康相談に強みを持つのか、美容商品を充実させるのか、地域密着型で高齢者向けのサービスを手厚くするのかなど、他店との差別化を意識した計画が重要です。事業計画書には、以下の内容を盛り込みましょう。
- 店舗のコンセプトとターゲット顧客層
- 提供する商品やサービスの詳細
- 競合店の分析
- 売上予測や収支計画などの詳細な財務計画
2. 資金調達
開業スタイルや店舗の規模によって大きく変動しますがドラッグストアの開業には相応の資金が必要です。主な内訳は、物件取得費、内外装工事費、什器・備品費、医薬品や商品の仕入れ費用、当面の運転資金などです。
自己資金だけで不足する場合は、融資を受ける必要があります。日本政策金融公庫では、無担保・長期返済・固定金利など、創業者にとって有利な条件で融資を受けられる場合があります。審査では事業計画書の実現性が厳しく評価されるため、綿密に作成することが不可欠です。
3. 開業地の選定
店舗の立地は、売上に直結する非常に重要です。以下の点を考慮し、慎重に選定しましょう。
- 商圏分析
店舗周辺の人口、年齢層、世帯構成などを調査します。ターゲット顧客が多く住むエリアを選びます。 - 競合調査
周辺にどのような競合店があるか、その店舗の強みや弱みを分析します。 - 視認性とアクセス
店舗が顧客の目に付きやすいか、車や公共交通機関でのアクセスは良いか、駐車場は確保できるかなどを確認します。
4. 店舗の設計・施工
薬機法および関係法令で定められた構造設備基準を満たす店舗設計が必要です。具体的には、医薬品を陳列・保管するための清潔な棚やショーケース、第一類医薬品や要指導医薬品を保管する鍵付き設備、購入者に説明や相談を行うための情報提供スペースを備えることが義務付けられています。また、温度・湿度管理が可能な環境整備や、手洗い設備を含む衛生管理体制も求められます。内装・外装工事業者と相談しながら、法令を遵守しつつ、顧客にとって利用しやすいレイアウトを設計することが重要です。
5. 許認可の申請
医薬品を販売するには、薬機法に基づき、店舗ごとに所在地を管轄する保健所を通じて店舗販売業許可を取得する必要があります。申請の際には、申請書のほか、店舗の平面図、店舗管理者(登録販売者または薬剤師)の資格証明書類、賃貸借契約書の写しなどが必要です。特に店舗の構造設備が法令基準を満たしているかが審査対象となるため、工事を開始する前に図面を持って保健所へ事前相談に行くことが推奨されます。
6. 従業員の採用・教育
一人で店舗を運営する場合を除き、従業員の採用が必要です。薬機法上、店舗には店舗管理者(薬剤師または一定の要件を満たす登録販売者)を常駐させることが義務付けられています。自身が常時店舗に立てない場合には、代わりに勤務できる登録販売者を確保しなければなりません。
採用後は、厚生労働省の指導に基づき、登録販売者に対して継続研修を行うとともに、一般従業員にも接客対応や医薬品知識に関する教育を実施することが求められます。店舗のコンセプトに沿ったマニュアルを整備し、接客や販売時の適正な情報提供ができる体制を構築することが、法令遵守と顧客の信頼確保につながります。
7. 医薬品・商品の仕入れ
医薬品を仕入れる際は、必ず「医薬品卸売販売業の許可」を持つ卸売業者と契約する必要があります。複数の卸売業者から見積もりを取り、価格や品揃え、配送条件を比較検討して契約先を決定しましょう。仕入れや販売に関する記録は薬機法に基づき作成・保存義務があるため、伝票や納品書は適切に管理する必要があります。
医薬品以外の商品についても、それぞれの仕入れルートを確保しますが、健康食品や化粧品の取り扱いには、関連法令の遵守が求められる点に注意が必要です。
8. 開業準備とマーケティング
開業に向けて、最終的な準備を進めます。
- 備品・システムの導入
レジ(POSシステム)、パソコン、電話、陳列棚、買い物かごなどの備品を揃えます。 - 商品の陳列
仕入れた商品を店頭に並べ、顧客が手に取りやすい魅力的な売り場を作ります。 - マーケティング活動
開店を地域住民に知らせるため、チラシのポスティング、ウェブサイトやSNSでの告知、プレオープンイベントなどを計画・実行します。
登録販売者が独立開業に成功するためのポイント
夢の開業を実現し、長く地域に愛される店を続けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 明確なコンセプトと事業計画
どのような顧客に、どのような価値を提供したいのか、店舗のコンセプトを明確にすることが成功の第一歩です。そのコンセプトに基づき、売上予測や資金計画を含んだ詳細な事業計画を立てましょう。
2. 徹底した市場調査と立地選定
開業するエリアの人口動態、競合店の状況などを徹底的に調査し、自身のコンセプトに合った立地を選ぶことが極めて重要です。漢方やサプリメントに特化する、子育て世代向けの品揃えを強化するなど、他店にはない強みを打ち出して差別化を図りましょう。
3. 医薬品知識以外の経営スキル
独立開業するということは、一人の経営者になるということです。医薬品に関する専門知識はもちろん、経理、財務、労務、マーケティングといった経営全般の知識を学ぶ必要があります。
4. 顧客との信頼関係の構築
登録販売者の大きな強みは、顧客の健康相談に乗り、適切なアドバイスができることです。一人ひとりの顧客と真摯に向き合い、丁寧なコミュニケーションを重ねることで信頼関係を築くことが、リピーターの獲得、ひいては安定した経営につながります。
5. 継続的な学習
医薬品や健康に関する情報は日々更新されます。常に最新の知識を学び、顧客に提供し続ける姿勢が、専門家としての信頼を高めます。また、経営に関するトレンドや新しい販売手法などにもアンテナを張り、自身の店に取り入れていく柔軟性も大切です。
登録販売者の独立開業についてよくある質問
最後に、登録販売者の独立開業についてよくある質問とその回答をまとめました。
実務経験なしの場合は独立開業できない?
登録販売者試験に合格しただけでは、直ちに店舗管理者になることはできません。薬機法上、店舗には必ず「店舗管理者」を配置する必要があり、その要件として実務経験(過去5年以内に通算1年以上、1,920時間以上)と厚労省指定の研修修了が求められます。実務経験がない場合は「研修中の登録販売者」として薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者の下で勤務し、経験を積むことが必須です。独立開業を目指すには、まず管理者要件を満たすことが第一歩となります。
漢方の知識は必須?
必須ではありません。ただし、第二類・第三類医薬品の中には多くの漢方薬が含まれており、専門的な説明やアドバイスができる登録販売者は顧客から高く評価されます。漢方の知識は法令上の義務ではありませんが、他店との差別化やリピーター獲得につながる「強み」として大いに役立ちます。
将来的に登録販売者は必要なくなる?
セルフメディケーションの推進に伴い、登録販売者の役割はむしろ高まっています。確かに「AIやネット販売で不要になるのでは」という意見もありますが、薬機法上、第二類・第三類医薬品の販売には登録販売者または薬剤師の関与が必須です。そのため、地域の健康相談窓口としての存在意義は今後も継続し、むしろ少子高齢化社会において需要は増すと考えられます。
地域に信頼される登録販売者を目指して
登録販売者としての独立開業は、決して簡単な道ではありません。しかし、明確なビジョンと周到な準備があれば、その夢を実現させることは十分に可能です。
管理者要件の正しい理解から始まり、自分に合った事業モデルの選択、そして着実な資金計画と許可申請の実行が、成功へのステップとなります。この記事で得た知識を踏まえ、あなた自身の強みを活かした店舗作りを目指してください。地域の人々から信頼される専門家として、新たなキャリアを築き上げる一歩となるはずです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
探偵業をはじめるには開業届が必要?書き方や警察への届出も解説!
探偵業とは、依頼者からの求めに応じて、特定個人の所在や行動について情報を収集し、依頼者に報告する仕事です。「探偵業法」という法律によって、仕事内容の定義や業務を営む条件などが決めら…
詳しくみる開業準備に必要なこととは?オープン前までにすることリスト
創業は個人・法人関係なく用いられる言葉であるのに対し、開業は主に個人事業主が事業を始める際に用いられます。開業にあたり、創業融資や助成金を利用した資金調達、店舗物件選定、印鑑の作成…
詳しくみるハンドメイド作家は開業届の提出が必要?メリットや書き方を解説
ハンドメイド作家は、自分の作品を販売して収入を得ます。収入を得ているということは、税金の支払いが発生します。ハンドメイド作家は原則、申告や納税をする必要がありますがそこで気になるの…
詳しくみる山形県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
山形県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する山形県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…
詳しくみる東大阪市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
東大阪市で開業届を提出する際は、東大阪市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、東大阪市の管轄税務署…
詳しくみる声優は開業届の提出が必要?書き方や確定申告についても簡単に解説
映画やアニメーションなどの声優で生計を立てている方がいます。個人事業主として声優業を営む場合、税務署に対して「開業届」を提出する必要はあるのでしょうか?適切な税務手続きを行うことで…
詳しくみる