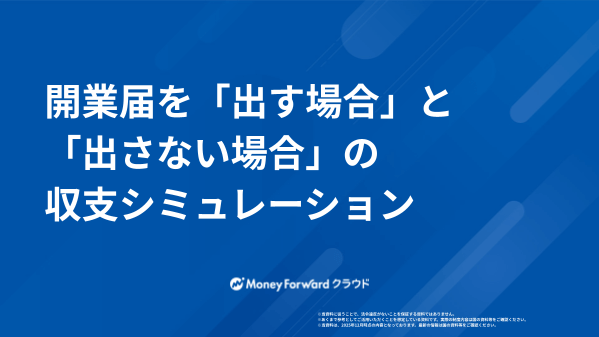- 更新日 : 2025年12月10日
開業届を出すデメリットと、出さないデメリットを比較解説!
個人で事業を行って収入を得ているけれど、「開業届を出していない」という人もいるでしょう。継続して事業を行う場合、本来は開業届の提出が必要です。また、開業届を出さないことで、デメリットになることもあります。
本記事では、開業届を出さなかった場合にどうなるかを説明しますので、参考にしてみてください。
目次
開業届を「出す」デメリット
開業届を「出す」デメリットは、主に以下の3つです。
記帳の義務が発生
開業届を出して個人事業主となったなら、日々の取引を帳簿に記載しておき、なおかつ帳簿を保存しておかなければなりません。白色申告の個人事業主であっても、記帳や帳簿の保存義務はあります。記帳の手間が発生することは、デメリットとも考えられます。
失業保険がもらえなくなる
会社を辞めて雇用保険の失業給付(失業保険)を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。
失業保険は、再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです。個人事業を開始した場合にはハローワークに申告しなければならず、無申告で失業保険を受給すると不正受給となり、厳しい処分を受けることになります。
社会保険の扶養を出なければならなくなる
配偶者の社会保険の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主となった場合、扶養を出なければならないことがあります。ただし、具体的にどういう場合に扶養から外れるかは、加入している社会保険によって変わります。開業届を出していても、収入が少ない場合には、扶養に入ったままでいられるケースもあります。
開業届を「出さない」デメリット
開業届を出さなくても罰則はありませんが、開業届を出さないと困るケースがあります。以下、開業届を出さない具体的なデメリットについて説明します。
青色申告ができない
青色申告とは、事業を行う人が税務署の定める方法で正しく記帳を行えば、さまざまな税務上のメリットを受けることができる制度です。青色申告の大きなメリットと言えるのが、青色申告特別控除です。要件をみたしていれば、最大で65万円を所得から控除でき、その分税金が安くなります。また、青色申告では赤字を最長3年間繰越でき、黒字になった年の税金を安くすることもできます。
青色申告をするには、事前に税務署に申請して承認を受けなければなりません。青色申告承認申請をするには、開業届を提出していることが前提になります。開業届を出していない場合には、青色申告承認申請書を受け付けてもらえません。
\青色申告承認申請書も簡単に作れる/
屋号での口座開設ができない
個人事業主が銀行で事業用の口座を開設した際、口座名義は個人名になります。ただし、銀行によっては、個人名に屋号を付け加えた口座を開設できますが、銀行から開業届の控えを求められることが多く、開業届を出していないと屋号での口座開設は難しいでしょう。
クレジットカードを作れない
安定した給与をもらえる会社員と違い、個人事業主はクレジットカードの審査に通りにくくなっています。個人事業主としてクレジットカードの申し込みをすると、事業を行っている証明として、開業届の控えを求められることがあります。開業届を出していないと、クレジットカードを作れない場合もあるかもしれません。
小規模企業共済に加入できない
小規模企業共済は、個人事業主が退職金代わりになる共済金を積み立てられる制度です。小規模企業共済に加入するには確定申告書の写しの提示が必要ですが、まだ確定申告していない初年度から加入するには開業届の写しを提出しなければなりません。
補助金・助成金の申請ができない
事業を開始するときには、補助金や助成金をもらって資金調達できることがあります。開業時に補助金や助成金の申請をする場合、開業届が必要になるケースが多くなっています。開業届を出さなければ、補助金・助成金等の申請もできないということです。
初めてでも安心!簡単3ステップで個人事業主の開業手続きがラクラクに。
>マネーフォワード クラウド開業届(利用料無料)
開業しても開業届を出さないとどうなる?
所得税法では、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を開始したときには、その事実があった日から1カ月以内に開業届を提出しなければならない旨が定められています。すなわち、事業を開始した人は、開業届を出す義務があるということです。
しかし、開業届を出さないとどうなるのでしょうか?
開業届を出さなくても罰則はない
個人で事業を開始したら開業届を出す義務がありますが、もし開業届を出さないまま事業を行っていても罰則はありませんし、税務署に出すように言われることも通常はありません。
開業届を出さずに事業を行っている人も現実にいることでしょう。
ただし、罰則がないからと言って、開業届を出さなくてよいというわけではないことは理解しておきましょう。開業届の提出は、任意ではなく、義務的なものです。
参考:所得税法第二百二十九条
開業届を出す目的
開業届を出さなくても罰則はなく、税務署から出すように言われることもないのなら、一体何のために開業届を出すのでしょうか。詳しくは後述しますが、開業届を出していないと、青色申告ができなかったり、屋号での銀行口座を開設できなかったりと、不便なことがあります。そういった、開業届を出さないと困るケースがあるため、多くの人は開業届を出しているのです。
開業届を出していなくても確定申告は必要
もちろん、開業届を出さなかったからといって、事業で得た所得を申告しなくてもいいわけではありません。開業届を出す・出さないにかかわらず、事業所得も含めた所得をきちんと確定申告する必要があります。開業届を出さなくてもペナルティーはありませんが、必要な確定申告をしていなければペナルティーがありますので注意しましょう。
初めてでも安心!簡単3ステップで個人事業主の開業手続きがラクラクに。
>マネーフォワード クラウド開業届(利用料無料)
確定申告ソフトを使えば青色申告が簡単になりますので開業届とあわせてぜひご覧ください。
>マネーフォワード クラウド確定申告を無料で始める
開業届を出さなければならない人と出さなくても大丈夫な人
個人で事業を開始したときには、開業届を提出しなければなりません。以下、どのような人が開業届を出さなければならないのか、出さなくても大丈夫な人はいるのかについて説明します。
フリーランスや副業でも基本的には出さなければならない
開業届を出さないといけないのは、事務所や店舗を構えて自営業をしている人だけではありません。フリーランスであっても、開業届を出す必要があります。会社員が副業で事業を行う場合でも、継続して事業を行う予定なら、開業届を出さなければなりません。出さなくても罰則はありませんが、提出は義務付けられています。
フリーランスや副業の場合でも、開業届を出すことにより、青色申告ができるようになります。青色申告特別控除を受けられたり、赤字を繰り越したりできれば、税金を抑えることができます。フリーランスや副業で開業届を出していない人は、出すことを検討しましょう。
継続した収入でなければ出さなくてもいい
なお、収入が一時的なものの場合には、開業届を出す必要はありません。例えば、フリマアプリやネットオークションで不用品を売って収入を得たけれど、継続的に利益を得るつもりではない場合には、開業届の提出は不要です。これは、一度だけ頼まれて原稿を書き、原稿料をもらった場合なども同様です。開業届を出すかどうかは、反復・継続して収入を得ている(事業)かどうかが基準になります。
初めてでも安心!簡単3ステップで個人事業主の開業手続きがラクラクに。
>マネーフォワード クラウド開業届(利用料無料)
継続して事業を行うなら開業届を出そう
個人で事業を開始したら、開業届を出す必要があります。フリーランスであっても、開業届を提出する義務はあるので、未提出の人は今からでも提出しましょう。開業届を提出することで、青色申告ができるようになるので、節税にも役立ちます。
よくある質問
開業しても開業届を出さなくてもいい?
開業届を出さなくても罰則はありませんが、だからといって開業届を出さなくてよいというわけではありません。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届を出さないとどんなときに困る?
青色申告ができない、屋号での口座開設ができない、クレジットカードを作れないといったデメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届を出すことにデメリットはある?
記帳の義務が発生することや、失業保険がもらえなくなること、社会保険の扶養を出なければならなくなる場合があることなどです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
開業届のメリット・デメリット の関連記事
新着記事
養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説
Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…
詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説
Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…
詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説
Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…
詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説
Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…
詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説
Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…
詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説
Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…
詳しくみる