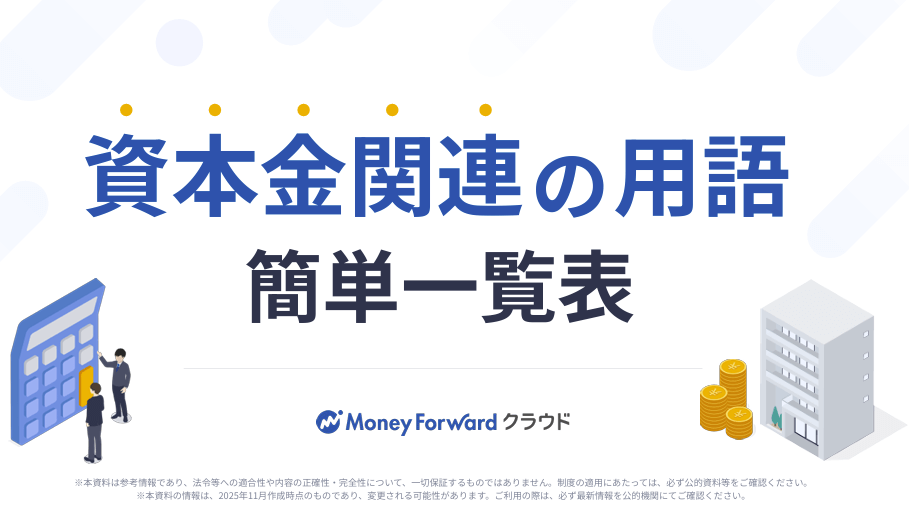- 更新日 : 2025年12月23日
資本金、資本準備金、資本剰余金をわかりやすく解説!
資本金、資本準備金、資本剰余金は、いずれも貸借対照表の純資産に記載される勘定科目です。しかし、それぞれの役割や意味が曖昧なまま、混同されてしまうことも少なくありません。
この記事では、資本金、資本準備金、資本剰余金それぞれの内容について、会社法を織り交ぜながら解説するとともに、実際の仕訳を見ながら財務会計の側面から理解できる内容となっています。
※条文の但し書きや除外規定の一部は便宜上割愛しています。
資本金とは?
資本金とは、株式会社が事業を行うための基礎となる財産であり、株主が会社へ払い込んだ財産のうち、資本金として計上された金額によって構成されます。会社の信用力や財務基盤を判断する上で重要な指標であり、会社法上も厳格に位置づけられています。以下では、資本金の定義と法律上の扱いについて解説します。
資本金は株主が会社に払い込んだ財産額
資本金は、会社法第445条第1項において「設立又は株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払い込み又は給付をした財産の額」と定義されています。
参考:会社法 第四百四十五条 (資本金の額及び準備金の額)|e-GOV
これは、会社が事業を続けるための土台となる財産を確保するための仕組みであり、会社が持つべき財産の目安を示すものです。また、会社が事業で得た利益は、資本金とは別に「利益剰余金」として計上されるため、企業が成長しても資本金が自動的に増えるわけではありません。
資本金の額は、企業の経営状況にかかわらず原則として固定されており、これを「資本不変の原則」と呼びます。資本金は任意に減らすことはできず、減資を行う際には会社法に基づく所定の手続きが必要になります。
資本金の増減には株主総会の決議が必要
資本金の変更には株主総会の承認が不可欠であり、増資の場合は普通決議で足ります。増資は会社の財務基盤を強化し、将来の配当拡大へもつながる可能性もあることから、資本金の減少に比べると比較的簡易な手続きが認められています。
一方、資本金を減額する場合は株主への影響が大きいため、原則として株主総会における特別決議が求められます。さらに、会社債権者保護手続きを経なければならず、公告や催告を行い、債権者に異議を申し立てる機会を与えることが義務づけられています。
このように、資本金は会社の信用を支える重要な財産であることから、その増減には慎重な手続きが求められています。
新株発行で1,000万円の払い込みを受けた場合の仕訳例
会社が新株を発行し、株主から現金の払い込みを受けた場合、その金額は会社の財産となり、資本金として計上されます。たとえば、会社が1,000万円の払い込みを受けた場合、会社の資産である現金預金が増える一方で、その対価として会社の純資産である資本金が同額増加することになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 10,000,000円 | 資本金 | 10,000,000円 |
※上記は、払込額の全額を資本金として計上した場合の仕訳例です。
資本金についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
会社設立時に決めることチェックリスト
「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。
図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。
補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド
補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。
「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。
法人成り手続きまるわかりガイド
初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。
多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド
マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。
先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。
資本準備金とは?
資本準備金は、企業が株主から出資を受ける際に、資本金として計上しなかった部分の金額を指し、会社の純資産を構成する重要な勘定科目です。以下では、資本準備金の定義と法的な位置づけについて解説します。
資本準備金は、株主からの出資金のうち資本金に計上しなかった残額
資本準備金とは、新株発行などを通じて株主から払い込まれた出資金のうち、資本金に計上しなかった部分の金額を意味します。多くの企業は設立時や増資時に株主から資金提供を受けますが、そのすべてを資本金に組み入れる必要はありません。出資金の一部を資本金に、残りを資本準備金に区分することで、会社の資本構成を柔軟に設計できます。なお、資本準備金は利益とは異なり、企業の持続的な運営を支えるための純資産として扱われる点が特徴です。
資本準備金の上限や計上方法は会社法で定められている
会社法第445条第2項では、「払込みに係る額の2分の1を超えない額は資本金としないことができる」と規定されています。これは、株主から受け入れた出資金のうち、半額までは資本金に含めないことができるという意味です。その結果、出資金のうち少なくとも半分以上は資本金に振り分けられることになります。また、同条第3項では「資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない」と定められています。つまり、資本金に含めなかった部分は、必ず資本準備金として振り分けられます。
参考:会社法 第四百四十五条 (資本金の額及び準備金の額)|e-GOV
これにより、資本金と資本準備金の区分が明確となり、企業の財務状況を外部に対して透明に示すことができます。なお、資本準備金は原則として自由に使用できる資金ではなく、配当や減資により取り崩す場合には、会社法に基づく所定の手続きが必要となります。
新株発行で1,000万円の払込みを受け、最低限度額を資本金として計上した場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金預金 10,000,000円 | 資本金 | 5,000,000円 | |
| 資本準備金 | 5,000,000円 | ||
資本金を大きいほど財務基盤がしっかりしている印象を与え、取引先や金融機関からの信用を得やすくなる一方、外形標準課税の対象となるなど税負担が増える場合もあるため、信用面と税務面のバランスを考えた適切な水準の設定が重要です。
資本剰余金とは?
資本剰余金は、企業が株主との資本取引によって得た剰余金を指し、利益剰余金とは異なる性質を持つ純資産項目です。以下では、その定義と法的取り扱いについて説明します。
資本剰余金は利益剰余金を除く剰余金で、資本取引を通じて発生する
資本剰余金とは、企業の剰余金のうち「利益剰余金以外の部分」を指し、企業の通常の事業活動ではなく、株主との資本取引を通じて発生するものです。たとえば、新株発行時に払い込み額が資本金として計上した金額を超えた場合、その超過部分が資本剰余金となります。また、自己株式の売却差益や、資本準備金を取り崩した際の増加分も資本剰余金に含まれます。
このように、資本剰余金は会社の利益ではなく、資本構造に関わる性質を持つ純資産であり、企業の財務基盤を支える役割を果たします。
配当の原資となり、取り崩しには会社法の手続きが必要
会社法第453条では、「株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる」と規定されており、剰余金であれば利益剰余金だけでなく、資本剰余金も配当原資として利用できます。ただし、資本剰余金が十分でない場合には、資本準備金を取り崩して資本剰余金へ振り替える必要があります。
この取り崩しには、場合によっては債権者保護手続きなどの会社法上の手続きが求められます。これは、会社財産の減少が債権者へ不当な影響を及ぼさないよう配慮するための制度です。
参考:会社法 第四百五十三条 (株主に対する剰余金の配当)|e-GOV
資本剰余金を原資とする配当の基本的な仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| その他資本剰余金 | 50,000,000円 | 未払配当金 | 50,000,000円 |
実際に株主に配当を支払ったときの仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払配当金 | 50,000,000円 | 現金預金 | 50,000,000円 |
なお、一定の条件を満たした場合は、準備金を計上する必要があるため注意しましょう。
資本剰余金が多い企業・少ない企業の特徴は?
資本剰余金の多寡は、企業の資金調達方法や財務戦略の傾向を反映するため、財務分析において重要な指標となります。企業がどのように資本を調達し、どの程度株主との資本取引を行ってきたかを読み解くことで、その企業の事業スタイルや成長段階を把握することができます。
資本剰余金が多い企業は、外部資金を積極的に活用する傾向
資本剰余金が多い企業は、新株発行による増資を積極的に行ってきた企業であるケースが多く見られます。新株発行時に払い込み額が資本金を上回った部分は資本剰余金として計上されるため、結果的に資本剰余金が厚くなります。また、資本政策として外部投資家からの資金調達を重視している企業や、高い成長戦略を採用しているスタートアップ企業なども該当します。
財務分析において資本剰余金が多い企業は、株主からの資本流入が活発で、財務基盤が比較的強固であると評価される一方、増資による希薄化リスクや株主還元方針の影響も考慮する必要があります。
資本剰余金が少ない企業は、財務戦略は保守的な傾向
資本剰余金が少ない企業は、増資をあまり行わず、主に利益剰余金や内部留保を基盤に経営を行う傾向があります。成熟企業や家族経営の企業などは、外部からの資本調達に依存しないため、資本剰余金が少なくなる傾向があります。この場合、財務分析では株主持分の構成比を確認し、資本政策が保守的であることや内部資金の活用方針を読み取ることができます。ただし、資本剰余金が少ないことは必ずしも弱点ではなく、過度な希薄化を避け、安定した利益成長に注力している企業である可能性もあります。
分析にあたっては、資本剰余金の多寡だけで判断するのではなく、企業の成長段階や資本政策全体を総合的に評価することが重要です。
資本剰余金の取り崩しと債権者保護手続きの流れは?
資本剰余金の取り崩しは、企業の純資産を減少させるため、会社法に基づき慎重な手続きが求められます。特に資本準備金を取り崩す場合は、原則として債権者保護手続きが必要とされており、適切な手順を踏まなければ法令違反となる可能性があります。以下では、取り崩しのプロセスを解説します。
① 取締役会による取り崩し方針の決議と株主総会での承認
資本剰余金の取り崩しを行うには、まず取締役会で取り崩す金額・理由・使途を決定します。資本準備金を取り崩す場合は会社財産が減少するため、株主総会での特別決議が必要とされます。株主総会では、取り崩しによる配当原資の確保や財務戦略上の必要性が説明され、出席株主の3分の2以上の賛成を得て承認されます。この段階で承認されて初めて、法的手続きを進めることが可能となります。
② 公告・催告による債権者保護手続きの実施
資本準備金を取り崩す場合、会社法により債権者保護手続きが義務づけられています。まず官報に公告を行い、債権者に対して一定期間(通常1か月以上)異議を述べる機会を与えます。必要に応じて、日刊紙などへの掲載を併用することもあります。また、把握している債権者には個別に通知を行います。債権者から異議が提出された場合、会社は弁済・供託・担保提供など、適切な措置を講じなければなりません。
これらの対応が完了するまで、資本準備金の取り崩しは効力を生じません。
③ 債権者保護手続き完了後の取り崩し処理と財務諸表への反映
異議申し立て期間が終了し、必要な措置をすべて終えた時点で、取り崩しが正式に有効となります。その後、資本準備金を資本剰余金へ振り替え、必要に応じて配当原資として利用するための記帳処理を行います。この取り崩しにより企業は配当や財務政策に柔軟性を持つことができますが、純資産の減少は財務健全性に影響するため、適切な判断と透明性のある開示が必要となります。
資本金、資本準備金、資本剰余金の違いを理解しましょう
資本金の金額そのものは財務諸表上で勝手に大きくなるものではなく、増資や減資を行うには、株主総会や取締役会の決議を経なければならないことが、会社法上で明確に規定されています。
また、会社法上は資本金が5億円以上の会社は大会社と定義されていますが、法人税法上は資本金が1億円以下の会社を中小企業と定義し、中小企業として各種の優遇措置を受けることができます。ただし、大法人の100%子会社などの場合には、中小企業の優遇税制の適用ができないケースがあるため注意が必要です。
よくある質問
資本金とは?
会社財産を確保するための基準となるものです。詳しくはこちらをご覧ください。
資本準備金とは?
資本金の1/2を超えない額を準備金として積み立てておくことができるものを資本準備金といいます。詳しくはこちらをご覧ください。
資本剰余金とは?
資本剰余金は資本金と資本準備金の資本取引から生じた余りの金額のことをいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新着記事
店舗を存続させる!事業計画立案のポイントと実務
株式会社hacomonoと共催セミナー「店舗を存続させるための事業計画立案のポイントと実務」を開催しました。本記事は、株式会社ナレッジラボ 税理士/中小企業診断士 大道 智之による…
詳しくみる里親手当で儲かる?制度の仕組み・支給額・費用・税金を解説
Point里親手当で生活が楽になったり、儲けが出たりする? 里親手当は、子どもの養育費を補助する制度であり、儲かる仕組みではありません。 養育費の実費補助 利益目的は不可 融資を意…
詳しくみる本店移転の手続きはどう進める?登記から各種届出までわかりやすく解説
Point本店移転では、何をどの順番で行う必要がある? 本店移転は、社内決議→登記→各機関届出の順で行う法定手続きです。 登記は移転日から2週 費用は3万〜6万円 登記後に届出必須…
詳しくみる墓参り代行は儲かる?仕事内容・料金相場・起業のポイントを解説
Point墓参り代行は、儲かるビジネス? 墓参り代行は、高単価で副業から収益化しやすいサービスです。 1件5千〜1.5万円 月数件でも黒字可 初期費用が少ない 月12件・単価1万円…
詳しくみる納税証明書(その1)とは?その2との違い・取得方法・請求時の注意点を解説
Point納税証明書(その1)は、どんな場面で必要になる? 納税証明書(その1)は、国税の納付状況を証明する公式書類です。 納付額と未納額を記載 融資・補助金で必須 税務署が発行 …
詳しくみる社会福祉法人を設立するメリットは?事業内容・他法人との違い・設立手順を解説
Point社会福祉法人には、どのような強みがある? 社会福祉法人は、公的支援と税制優遇を受けながら福祉事業を安定運営できる法人です。 補助金で施設整備可 税負担が大幅に軽減 社会的…
詳しくみる