
法人税申告書の別表20とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表20は、法人の退職年金等積立金に関わる法人税の申告書です。この記事では、別表20の概要や別表20の書き方を説明していきます。 法人税申告書の別表20とは 別表20…
会計業務における最新情報と基礎知識が分かる

法人税申告書の別表20とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表20は、法人の退職年金等積立金に関わる法人税の申告書です。この記事では、別表20の概要や別表20の書き方を説明していきます。 法人税申告書の別表20とは 別表20…

法人税申告書の別表19とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務別表19は、法人税や地方法人税の中間申告に関わる書類です。内国法人の場合と、外国法人の場合で様式が異なります。この記事では、別表19の概要や社内で作成する場合の書き方、作成にあたっ…

法人税申告書の別表17とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書を作成する際、必要に応じて添付するのが「別表」です。しかし、どの別表を使ったらいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は法人税申告書別表17に…

法人税申告書の別表16とは?作成目的やポイントを解説
会計業務法人税申告書別表16は、主に減価償却の償却限度額(法人税法上の損金に算入できる限度額)に関する明細書で構成されています。今回は、別表16の種類や各種明細書の作成目的、別表16を作成…

法人税申告書の別表15とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表15は、法人の交際費等に関する明細を示した書類です。この記事では、別表15の種類、別表15の各項目と書き方、別表15作成時の注意点まで解説していきます。 法人税申…

法人税申告書の別表14とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表14は、寄附金や株式などに関連した明細書で構成されています。この記事では、別表14の種類、社内で申告書を作成する会社向けに代表的な明細書の書き方、作成時の注意点を…

法人税申告書の別表13とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表13は、圧縮記帳にかかわる申告書です。この記事では、別表13の種類、別表13のうち代表的な書類の書き方、別表13作成時の注意点を解説していきます。 法人税申告書の…

法人税申告書の別表12とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人が法人税を申告する場合「法人税申告書」を提出します。法人税申告書には必要に応じて別表を添付しますが、業種や申告内容によって提出する別表が異なります。 今回は、別表の一つ「法人税…

法人税申告書の別表11とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表11は、引当金にかかわる書類です。この記事では、法人税申告書を社内で作成したいと考えている企業向けに、別表11の種類や書き方、作成にあたっての注意点を解説します。…

遊休資産とは?会計・税務処理や放置のデメリット、処分ポイントを解説
会計業務事業で利用するために取得した機器や土地が、何らかの都合で休止している状態の会社は少なくないとされています。 これらの機器や土地は遊休資産と呼ばれ、固定資産税の対象となります。 本記…
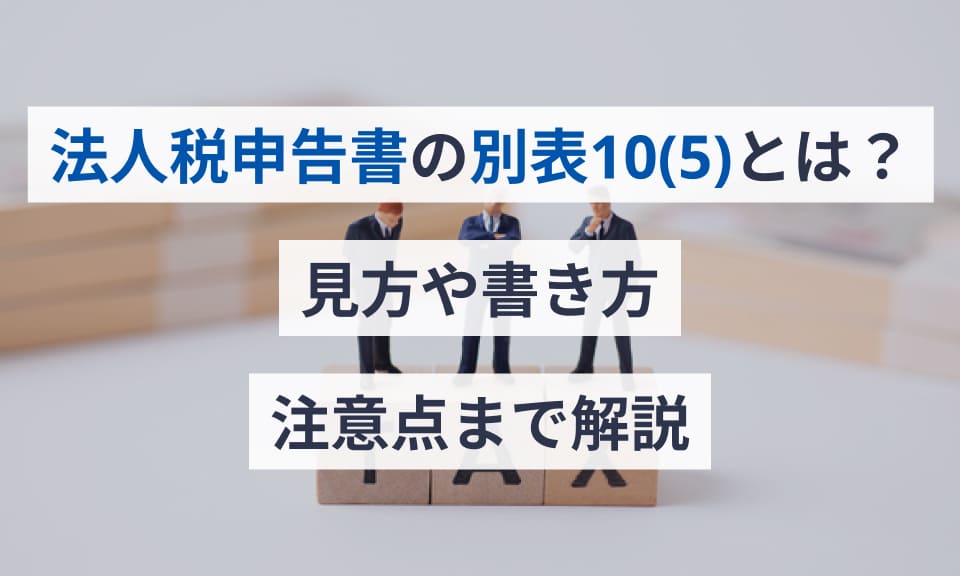
法人税申告書の別表10(5)とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の添付書類は別表1から別表20までと数多くの種類があります。さらに、別表10を見てみると(1)から(11)までの書類があります。ただし、別表10の各書類はどの法人でも使…
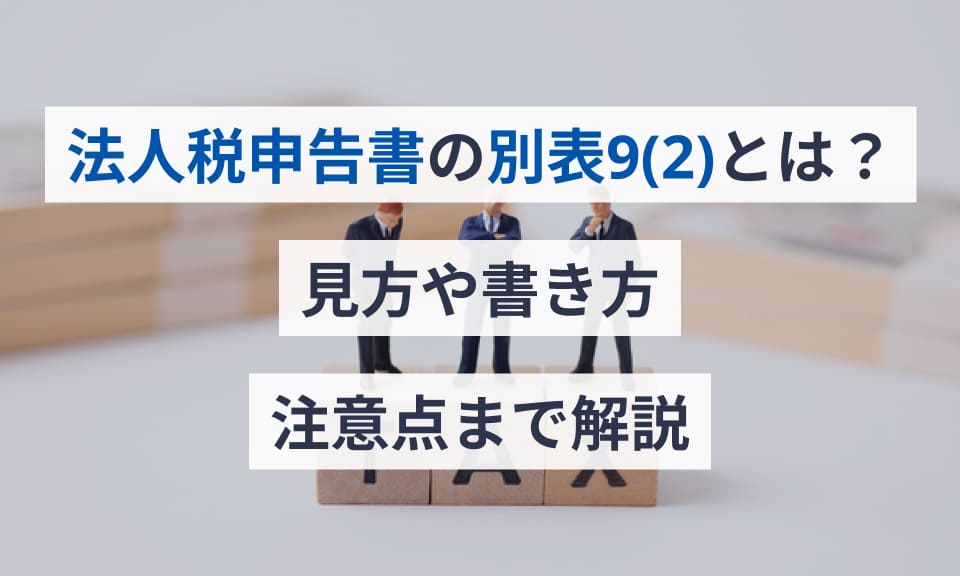
法人税申告書の別表9(2)とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人が確定申告をする際に提出するのが「法人税申告書」です。そして法人税申告書を提出する際は、必要に応じて「別表」を添付します。 別表の種類は1から20までありますが、今回は別表9に…
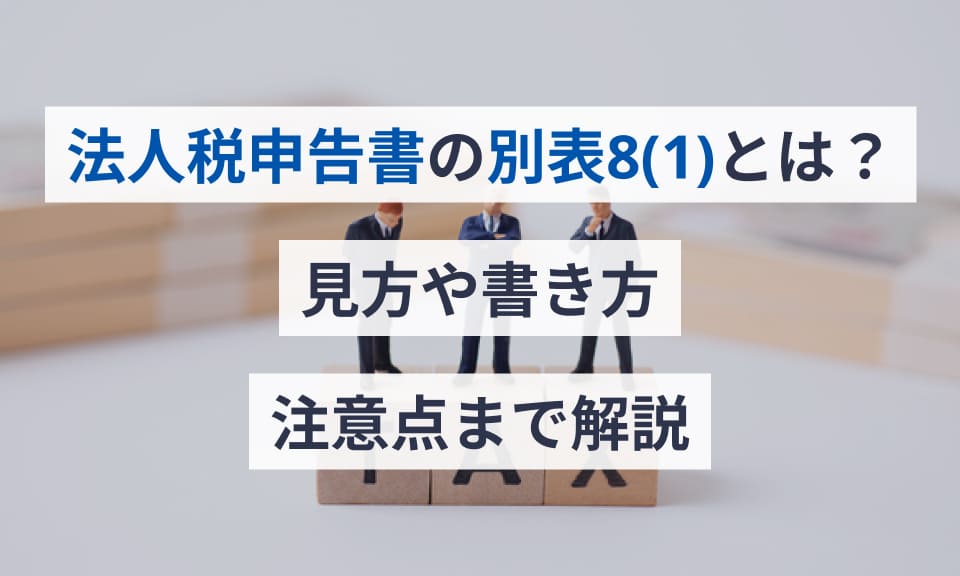
法人税申告書の別表8(1)とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務関連会社がある場合、その法人から配当金などを得ることがあります。その際の処理についてご存じでしょうか。どのように処理するかで法人税額が変わってきますので、しっかりと理解しておきたい…
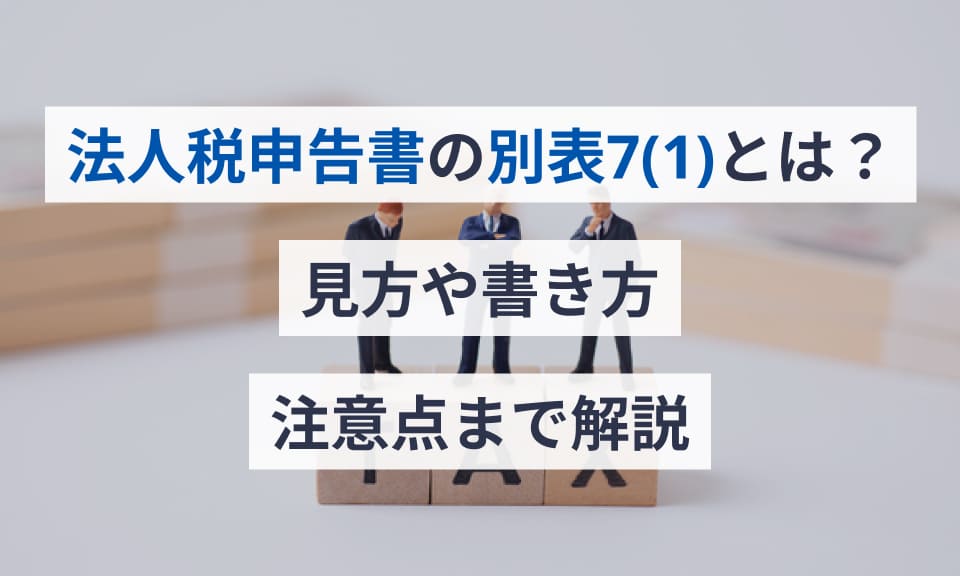
法人税申告書の別表7(1)とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務企業を経営していると、欠損金を出してしまうことは珍しくありません。しかし、欠損金が出てしまったとしても、青色申告ならば赤字分を次の年度以降に繰り越すこともできます。 本稿では、欠損…
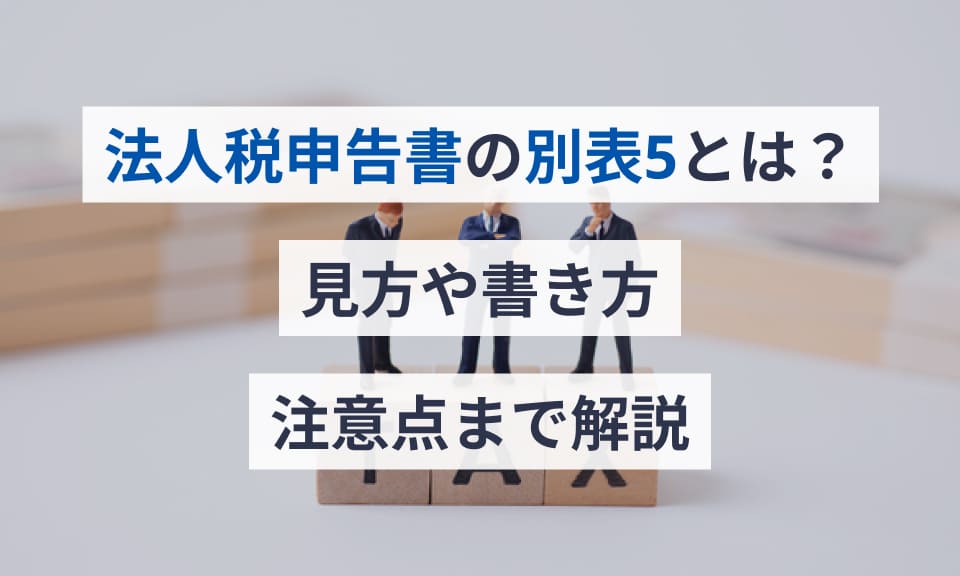
法人税申告書の別表5とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務別表5は、利益積立金額の計算に関する申告書です。別表5を自社で作成する場合どのように作成していけばよいか、別表5の書き方と注意点を紹介します。 法人税申告書の別表5とは 法人税申告…

法人税申告書の別表6(1)とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税の納税申告をするためには「法人税申告書」の作成が必要です。しかし、法人税申告書は別表の種類も多いため、何を使ったらいいのか迷う場合も多いのではないでしょうか。 そこで、本記事…

法人税申告書の別表4とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表4は、所得の計算を示す書類です。法人税の基礎となる所得金額を求める書類で、法人税申告を行う法人は作成・申告の必要があります。今回は、別表4の役割や書き方を紹介しま…

法人税申告書の別表3とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表3は、該当する法人が記載・提出する必要のある申告書です。特定同族会社に該当する場合、土地の譲渡利益金額がある場合に作成します。今回は、別表3の種類や書き方を紹介し…

法人税申告書の別表2とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表2は、同族会社に関連する判定を記載する書類です。判定結果を記載するだけなく、なぜその判定に至ったのかまで詳細を記載します。今回は、別表2の役割や各項目の書き方につ…

法人税申告書の別表1とは?見方や書き方、注意点まで解説
会計業務法人税申告書の別表1は、法人税申告の全体像がわかる申告書類のひとつです。法人申告書を社内で作成する場合どのように作成していくべきか、別表1の種類と入手方法、書き方を紹介します。 法…
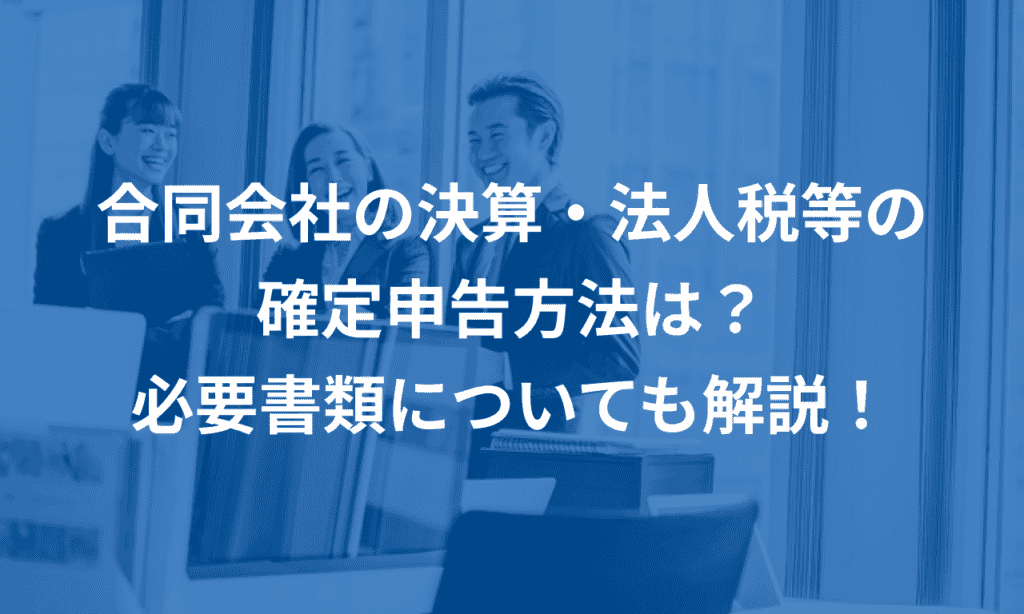
合同会社の決算・法人税等の確定申告方法!自分で可能?いつ行う?
会計業務合同会社の決算・法人税等の確定申告は自分でもでき、まずは帳票整理・記帳を行い、決算書類の作成を行います。その後、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」「消費税(免税事業者を除く。)…

税務における連結納税のメリットは?グループ通算制度との違いも解説
会計業務連結納税は、一つの親会社とその子会社群が、個別に税金を計算・納付するのではなく、グループ全体として統一的に税金を計算し納税する制度です。複数の会社にわたる税務処理を一本化し、税務管…

連結決算における持分法を適用するメリットは?会計処理もわかりやすく解説
会計業務持分法とは、会社が他の会社の一部の株式を所有している場合に使用される会計方法です。 企業が連結財務諸表を作成するために必要なものとなり、特に経営陣は子会社や関連会社を含めたグループ…

子会社の赤字が連結決算に与える影響は?事例や対処法を解説
会計業務赤字を出している子会社の会計処理にお悩みの方もいるのではないでしょうか。赤字の子会社を抱えていると、連結決算において不利になります。グループ全体の損益を連結させて納税する方法はある…

持株比率別に連結決算時の会計方法を解説|持分法適用会社との違いも紹介
会計業務連結決算では、連結子会社と関連会社の区別、それぞれの会計方法に関する正しい知識が不可欠です。 本記事では、連結決算時の会計方法を持株比率別にお伝えします。持分法を適用するメリットと…

海外子会社と連結決算を行う際の会計処理|換算処理やポイントも解説
会計業務近年、大企業だけではなく中小企業およびベンチャー企業でも投資やM&Aによる海外進出が増加しています。しかし、海外子会社を会計上適切に管理できていない企業も多いのが現状です。…

中小企業には連結決算の義務はある?メリットやデメリットを解説
会計業務連結決算は、基本的に多くの子・関連会社を抱える大企業が行うべき会計処理方法です。しかし、最近は企業規模を問わずM&Aや海外進出などで国内外に子会社を持つ動きが高まっていることにとも…

連結決算で親子会社間に決算期のずれがある場合は?わかりやすく解説
会計業務連結決算において親・子会社間で決算期がずれている場合、一定の期日を境に対応が異なることをご存知ない企業の方も多いのではないでしょうか。原則として決算日は統一することが推奨されますが…

中間決算や連結決算とは?期間別・対象の会社数別に種類を紹介
会計業務決算は、一定の期間内における損益や財政状況、キャッシュの流れの把握に重要な業務です。中間決算や連結決算など数種類に分類され規定や法的な義務が異なるため、それぞれの違いを正確に把握し…

出荷伝票とは?テンプレートをもとに書き方や注意点を解説
会計業務出荷伝票とは、商品などを取引先などに引き渡す際に使用する伝票です。商品や商品を入れるダンボール箱などに貼り付けて使うことがあります。出荷伝票の必要性や納品書との違い、書き方について…

連結決算の対象となる条件は?義務付けられている親会社の定義も解説
会計業務連結決算業務をスムーズに行うには、どのような会社が対象になるかを理解しておくことが重要です。一部の会社においては連結決算が義務付けられており、適切な会計処理が求められます。 連結決…

連結決算の対象となる株式保有率は?子会社と関連会社の違いも解説
会計業務子会社の株式保有率によって連結決算の対象となるケースが異なりますが、一般的に重要性の高い子会社が連結決算の対象となります。 本記事では、連結決算の対象となるケースや子会社・関連会社…

消費税集計表とは?書き方や活用方法をテンプレつきで紹介
会計業務消費税の申告前に納税すべき金額を概算するには、消費税集計表が便利です。消費税集計表を作成する前に、3つの税率を理解することや経理方式の確認、会計ソフトへの正確な仕訳入力などが必要で…
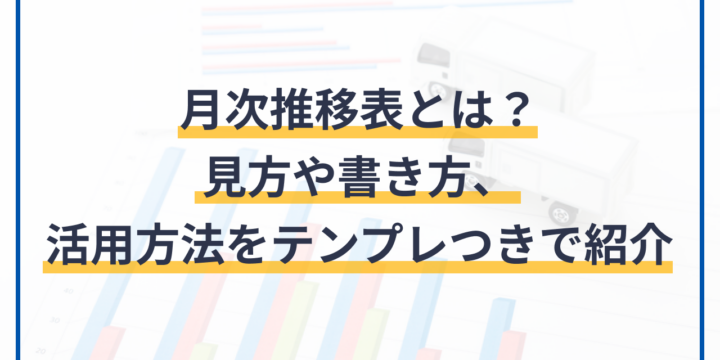
月次推移表とは?見方や書き方、活用方法をテンプレつきで紹介
会計業務月次推移表とは、月ごとの業績や資産の状況について、他の月と比較して傾向や変化を把握できるものです。うまく活用することで将来に活かせるでしょう。 本記事では月次推移表の作り方や読み方…

お会計票とは?種類や伝票の保管期間についてテンプレをもとに解説
会計業務お会計票は伝票のひとつで、主に店舗など顧客から直接注文を受ける場で使われます。さまざまな種類があり、業務の内容や性質によって使いやすいものを選ぶことが可能です。 本記事では、お会計…

クレジットカード管理表の書き方をテンプレをもとに解説
会計業務事業で発生する経費を現金で支払う場合は、立替や領収書の確認、支払いなどの対応が必要です。しかし法人向けクレジットカードであれば、このような事務処理を削減できます。 ただし、むやみに…

未払金台帳とは?買掛金との違い、テンプレートを基に書き方を解説
会計業務未払金台帳は未払金を管理する台帳です。未払金とは営業外の単発的な取引から発生する費用のことです。未払金台帳をつけることで、支払のミスを防止したり、資金繰りに役立てたりできます。紹介…

将来キャッシュフローとは?計算方法と現在価値との違い
会計業務将来キャッシュフローとは、ある企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローの総額です。企業価値を算定する際に用いられます。将来キャッシュフローを現在価値に割り引いたものが、その企業…

自己資本利益率(ROE)とは?目安や計算方法をわかりやすく解説
会計業務自己資本利益率(ROE)は、企業の経営効率を見る指標です。今回は、自己資本利益率の計算の仕方や数値でわかること、目安や業界ごとの平均、自己資本比率との関係などについて解説していきま…
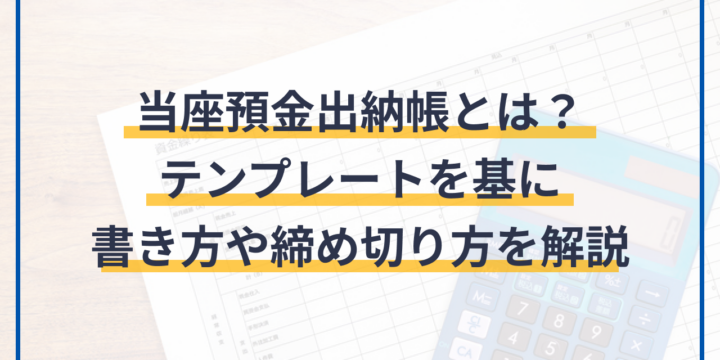
当座預金出納帳とは?テンプレートを基に書き方や締め切り方を解説
会計業務当座預金出納帳とは、当座預金の増減を記帳する補助簿です。現金出納帳や小口現金出納帳と似ていることから、違いや書き方がわからない方もいらっしゃるでしょう。 本記事では、当座預金出納帳…

減価償却明細書とは?テンプレートを基に書き方や注意点を解説
会計業務減価償却明細書とは、企業が保有する資産の減価償却状況を一覧にした帳簿を指します。個々の固定資産の減価償却の流れを記載した固定資産台帳とは別の帳簿です。 減価償却明細書があると「少額…

連結決算における相殺処理の必要性|ケース別の仕訳や子会社の基準も紹介
会計業務連結決算を行うにあたって、必要性や状況に応じた相殺方法がわからない方もいるのではないでしょうか。連結決算は、親会社と子会社すべてをひとつの大きな組織として見た際のお金の流れが理解で…

連結決算の対象となる子会社の基準は?例外や行うことをわかりやすく解説
会計業務上場企業の場合は子会社を含む経営全体を把握するために、連結決算が不可欠です。一定の条件下で報告が義務付けられており、中小企業・非上場でも一概には要否を判断できません。違反すると罰則…

買掛金元帳とは?書き方や管理方法の注意点(テンプレート付き)
会計業務買掛金元帳は、仕入先元帳とも呼ばれる総勘定元帳の補助簿です。買掛金の発生時と支払時に記入します。仕入先ごとに買掛金の動きを記録するため、1件の仕入先につき1つの帳簿を使用しなければ…

開始貸借対照表とは?会社設立時の会計や作り方の注意点(テンプレート付き)
会計業務会社で作成する財務諸表の1つに貸借対照表があります。特に、設立時に作成する貸借対照表を開始貸借対照表といいます。開始貸借対照表はなぜ必要で、また、どのように作成したら良いのでしょう…

直接原価計算とは?全部原価計算との違いや計算のポイント
会計業務直接原価計算とは製造費用を変動費と固定費に分け、変動費で原価計算をする方法です。一方で変動費・固定費ともに製造原価とする方法を、全部原価計算と呼びます。どちらも原価計算方法の手法で…

車両管理台帳はどう作成する?書き方や、記入例を解説
会計業務車両管理台帳は、使用責任や整備点検義務などを果たすために、使用中の車両情報や使用状況などを管理するための台帳です。作成するメリットには、コストを削減できる点やリスクを軽減できる点が…

日繰り表で日次の資金管理をするには?テンプレをもとに作り方を解説
会計業務資金繰り表のひとつである日繰り表は、勘定科目などを各取引ごとで残高がわかるようにした書類です。作成することで、将来の資金の流れをある程度予測できるようになります。 ひな形やテンプレ…

売掛金元帳とは?書き方や記入例を解説
会計業務「売掛金の管理に手間がかかる」とお悩みの場合には、売掛金元帳が便利です。取引先ごとの売掛金の発生・回収状況を把握でき、売掛金がいくら残っているかもすぐにわかります。この記事では、売…

事業における収支計画書とは?テンプレをもとに書き方や記入例を解説
会計業務収支計算書とは、事業によって生じる収入と支出を算出し、どの程度の金額が手元に残るかを示す書類です。借入金も収入として考えるため、実際に使える金額を具体的に把握できます。 この記事で…

仕入帳の書き方は?作成義務の有無や記入例を解説
会計業務仕入帳とは、仕入によって発生するお金の流れを記載する書類です。仕入先や単価、数量など、仕入にかかわる情報はすべて記載します。仕入帳があることでお金の流れを時系列に把握しやすくなりま…

建設業の工事完了報告書とは?書き方やテンプレートを紹介
会計業務工事完了報告書とは、主に建設業者が工事の完了を報告する書類です。契約どおりに進んだことを確認する目的で、元請けなどから提出を求められることがあります。 雛形やテンプレートを活用すれ…

金種表とは?書き方や無料テンプレートを紹介
会計業務金種表とは、現金残高や申請する金額を紙幣・硬貨の種類別に記入する表のことです。小口現金管理や、銀行預金の入出金などさまざまな場面で使う機会があります。 金種表をかんたんに作成するに…

棚卸表とは?申告の必須項目や書き方をテンプレート付きで解説
会計業務在庫管理書類の1つに「棚卸表」があります。確定申告においても必要とされる重要な書類ですが、どのように作成すべきなのでしょうか。また、棚卸表を作成するメリットはどこにあるのでしょうか…

預り証とは?記載項目や書き方をテンプレート付きで解説
会計業務物品や金銭を預かった際、その証拠書類として預り証を発行します。預り証の書き方には明確なルールはないため、記載内容や書き方で迷う人も多いでしょう。本記事では、預り証に記載すべき項目や…

製造原価報告書とは?作成義務や計算方法について解説
会計業務製造業において作成される財務諸表の1つに「製造原価報告書」があります。製造業者は必ず作成する書類ですが、法令上作成の義務はあるのでしょうか。また、計算方法はどのようなものなのでしょ…

仮払法人税等とは?計上の流れや仕訳まで解説
会計業務仮払法人税等とは、中間申告で支払った法人税等を一時的に計上する勘定科目です。決算で確定した納税額から控除し、残った金額を未払法人税等の勘定科目で仕訳します。 本記事では仮払法人税等…

減価償却費を月割りで計算する方法は?具体例と共に紹介
会計業務減価償却費は資産の価額に償却率を掛けて計算し、耐用年数で償却するものです。しかし、取得の時期は1年の途中であることも多く、正確に計算するためには月割り計算が必要です。 減価償却費の…

資本取引・損益取引区分の原則とは?具体例から解説
会計業務資本取引・損益取引区分の原則は、「資本取引と損益取引をはっきりと区別しなければならない」とする企業会計の原則です。大企業から中小企業に至るまでさまざまな企業において、会計上守るべき…

保守主義の原則とは?具体例から解説
会計業務保守主義の原則は、企業会計原則の7つの一般原則のうち6つ目の原則で、一定の状況下において保守的な会計を行うことを要請するものです。今回は、保守主義の原則の意味や必要性、具体例や行き…

正規の簿記の原則とは?具体例から解説
会計業務企業会計の重要な原則の一つに「正規の簿記の原則」があります。 正規の簿記の原則とは、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならな…

明瞭性の原則とは?具体例から解説
会計業務明瞭性の原則は、企業会計原則の一般原則の4つ目に示されている原則です。どのような内容の原則なのか、その必要性と具体例もあわせて解説していきます。 明瞭性の原則とは? 企業会計原則、…

継続性の原則とは?正当な理由の具体例の解説
会計業務法律ではないものの、すべての企業が従わなければならない基準として、企業会計原則が定められています。継続性の原則は、企業会計原則の一般原則に定められている7つの原則の中のひとつです。…

法人税とは?税率の計算や節税方法などを解説
会計業務法人税とは、法人が事業によって得た所得に対して課税される国税です。株式会社や有限会社などの普通法人と、協同組合などは法人税を納めなければなりません。 この記事では、法人税の概要と種…

追徴課税とは?計算方法や対象期間の解説
会計業務確定申告を忘れていた場合や正しい税額を納付していない場合は、税務調査により追徴課税の徴収を受ける可能性があるでしょう。また、追徴課税の内容によってはペナルティーとして、本来納めるべ…

新収益認識基準とは?適用範囲や導入時の注意点を解説
会計業務収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)が2021年4月から適用されるようになりました。原則として全ての企業が対象となっていますが、中小企業に関しては、従来通りの会計処理を継続し…

借方と貸方の違いとは?考え方や覚え方を解説
会計業務複式簿記の知識は経理を行ううえで必須の知識といえます。しかし借方や貸方、貸借対照表や損益計算書など、慣れない言葉が多く登場して戸惑っているのではないでしょうか。 本記事では、借方と…

駐車場経営で経費にできるもの・できないものまとめ
会計業務これから駐車場経営を始めようと考えている人は、どのような支出が経費に計上できるか知りたいのではないでしょうか。初期費用や運営費用、撤去費用といったように、場面ごとで必要になる経費に…

貸倒引当金戻入とは?仕訳から解説
会計業務貸倒引当金戻入は前期に計上していた引当金を減らす場合に用いる勘定科目です。戻し入れる際の会計処理は、貸倒引当金の計上方法によって異なります。似た勘定科目が何度も出てくるので、仕訳時…

不動産投資で経費にできるもの・できないものまとめ
会計業務不動産投資でかかった費用には、経費にできるものとできないものがあります。実際に経費として計上が可能な費用について具体的に例を挙げて紹介するので、ぜひ参考にしてください。経費計上する…

社用車を経費にする方法まとめ
会計業務法人名義で購入した社用車は、経費に計上できます。ほかにも社用車にかかるガソリン代や保険料、車検費用といった費用も経費計上が可能です。経費にする方法は、ローンを利用した購入やリース契…

社宅を経費にして節税する方法をわかりやすく解説
会計業務社宅に関連する費用は経費に計上でき、節税ができます。しかし、社宅に関する費用のすべてを経費にできるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりません。 本記事では社宅を経費にするメ…

一人親方が経費にできるもの・できないものまとめ
会計業務一人親方が独立した当初に直面する大きな問題が確定申告です。売上額は請求書で確認できても「何を経費に入れればよいのか」といった、疑問や不安を抱く方もいるでしょう。今回は、一人親方が経…

フリマアプリで購入した物を経費にする方法は?仕訳まで解説
会計業務メルカリなどのフリマアプリで事業に関する商品を購入した場合、経費計上が可能です。領収書やレシートが発行されない場合には、それに代わるものを保管する必要があります。 本記事ではフリマ…
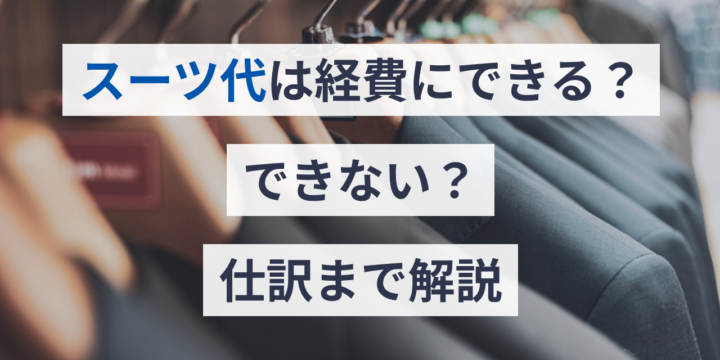
スーツ代は経費にできる?できない?仕訳まで解説
会計業務経費に含めてよいものかどうか迷う費用のひとつが、スーツ代です。スーツ購入費用を経費に入れられるかの基準は、一言でいうと事業に必要かどうかです。業務用に購入したスーツの費用は経費に入…

ゴルフで経費にできるものは?仕訳と勘定科目まとめ
会計業務状況によってはゴルフコンペに要した費用を経費に含めることが可能です。事業と関わりがあると明確に説明できる場合のみ経費算入できます。取引先がいないゴルフコンペは営業活動ではないため、…
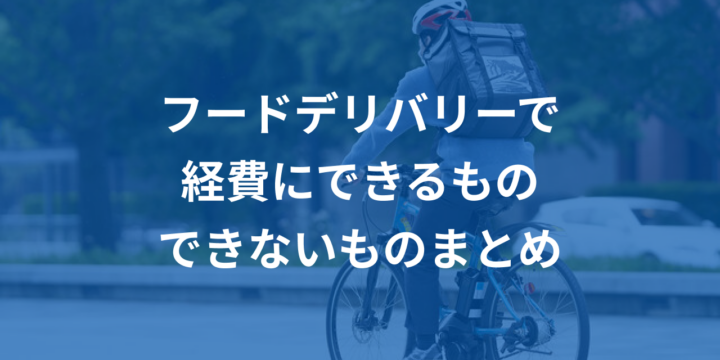
フードデリバリーで経費にできるもの・できないものまと
会計業務ウーバーイーツ配達員が収入を増やすためには、稼働回数を増やすほかに税金対策も重要です。フードデリバリーでは、自転車の購入費やガソリン代、通信費、駐輪場代などを経費として計上できます…

アパート経営で経費にできるもの・できないものまとめ
会計業務アパート経営では管理修繕費や通信費、新聞書籍代などさまざまな費用を経費にできます。 事業に関係しているかどうかが基準になるため、プライベートな支出や税金の一種は経費とは認められませ…

YouTuberが経費にできるもの・できないものまとめ
会計業務自宅で自分の好きな動画を撮影して収益が得られるYouTuberは、非常に人気のある職業のひとつです。事業を営んでいる経営者でもあるため、経費についての理解は不可欠です。 動画撮影に…

旅費交通費とは?交通費との違いや仕訳の解説
会計業務業務上で発生する従業員の移動にともなう費用は、「旅費交通費」や「交通費」といった勘定科目を使って仕訳を行います。旅費交通費と交通費にはどのような違いがあり、具体的にどのような費用を…

商品輸入時の仕訳と会計処理を解説
会計業務昨今、副業を始める人が増えている中で、海外から商品を輸入仕入れし、日本国内で商品を販売する輸入業が注目を集めています。人気商品は多岐にわたるため個人でも参入しやすい一方、輸入による…

出張時の日当の仕訳に使う勘定科目を解説
会計業務従業員や役員などの出張に対し会社から規定に応じた出張手当を支給することがあります。出張時の日当は経費として精算できますが、どのような勘定科目で会計処理をするのが適しているのでしょう…

減損とは?計算方法や会計フローの解説
会計業務年次決算において、資産価値を正しく認識するために欠かせないのが減損です。減損は決算に大きな影響を与える可能性があります。経理や財務に関わる人であれば、基本的な考え方は理解しておきま…

原価率とは?計算方法や目安の解説
会計業務会社が利益を出していくには、売上に対する原価の割合を表す原価率について把握しておくことが大切です。特に飲食店では、原価率に加え、食材などの原価に人件費を加えた割合を見て経営判断する…

利益率とは?出し方の計算方法や目安の解説
会計業務売上高に対する利益の割合を利益率といいます。利益率は、売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、売上高税引前当期純利益率、売上高当期純利益率の5種類に分類されます。会社が…

【2024年版】IT導入補助金とは?補助対象や申請方法を解説
会計業務IT導入補助金とは、中小企業等を対象として、業務効率化、DX化のために必要となるソフトウェアやITサービスなどの導入費用の一部を補助する制度です。経済産業省などによる国の制度である…

当座借越とは?一勘定制と二勘定制の違いを解説
会計業務企業は銀行との間で契約を結ぶことで口座残高を超えた金額の小切手を振り出せるようになります。当座借越の仕訳方法は一勘定制と二勘定制に分かれることが特徴です。 一勘定制と二勘定制では使…

資本的支出と収益的支出とは?違いをフローチャートで解説
会計業務固定資産の修理・改良等に費用を支出したとき、その支出により価値や耐久性が増加したと認められる場合、資本的支出となります。一方、通常の維持管理または原状回復である場合は収益的支出です…

差入有価証券とは?仕訳から解説
会計業務有価証券を金銭貸借等の担保として提供する際は、差入有価証券勘定を使用します。差入有価証券の仕訳を行う際は、時価ではなく帳簿価額を記載します。 預り有価証券や保管有価証券は時価で記載…

強制評価減とは?わかりやすく解説
会計業務強制評価減は取得原価と期末時点での時価に著しい乖離が見られる場合に、強制的に帳簿価額を下落させる会計処理です。それぞれの資産区分に応じて強制評価減を行う要件があるのが特徴です。 今…

永久差異と一時差異の違いとは?例から解説
会計業務永久差異と一時差異には、その差異が永久的に解消されないのか、将来的に解消され得る性質のものかという違いがあります。一時差異は費用と損金、収益と益金の認識時期が異なるために生じるもの…

その他資本剰余金の配当にかかる会計処理・税務処理を解説!
会計業務事業の元手となる財産は財務諸表上で「株主資本」とされます。株主資本は「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」に分けられますが、その中の「資本剰余金」は「資本準備金」と「その他資本剰余…

特許権の会計処理と償却方法を仕訳まで解説
会計業務特許権の耐用年数は8年間で、その間に償却することになります。特許権を購入したときなどには、適切に会計処理を行わなくてはいけません。具体的にどのように会計処理を行うのかについて、仕訳…

貸倒実績率とは?計算方法をわかりやすく解説!
会計業務会計処理、特に期末における決算整理仕訳では、貸倒引当金の計上の要否を検討します。貸倒引当金とは、取引先が倒産等で支払い不能となった状態などに備えて、事前に損失額を予測して計上してお…

最終仕入原価法とは?棚卸資産の評価方法をわかりやすく解説!
会計業務最終仕入原価法とは、事業年度における最終の仕入価格を期末棚卸資産の評価に適用する方法を指します。会計基準における棚卸資産の評価方法に含まれませんが、法人税法上は、ほかの評価方法を選…

荷為替手形とは?仕組みや仕訳をわかりやすく解説
会計業務荷為替手形とは運送中の商品の引渡請求権を表章する運送業者発行の運送証券(貸物引換証、船荷証券などの有価証券)が担保として添付された為替手形のことです。 また、代金は第三者である取引…

手許商品区分法の仕訳と会計処理をわかりやすく解説
会計業務手許商品区分法は手許にある商品とない商品を区分して処理する方法です。受託者に商品の販売を任せる委託販売や、試用期間を設けてから販売につなげる試用販売のときに用いられます。 手許商品…

セール・アンド・リースバック取引の会計処理と仕訳をわかりやすく解説
会計業務保有する不動産の有効活用を進める企業も増えてきています。セール・アンド・リースバック取引による不動産の有効活用と資金調達も、不動産有効活用の方法のひとつです。この記事では、セール・…

会計とは?業務内容や経理との違い、効率化の手法を解説
会計業務企業の経理担当者や財務担当者などにとって、会計はよく耳にする言葉のひとつかもしれません。一般でも、国の歳入・歳出について一般会計と言ったり、マイナス面では企業の不正会計で「会計」と…

外貨建有価証券の会計処理をわかりやすく解説
会計業務個人、法人に限らず、ネット上で証券口座を開き有価証券を売買しやすい時代になりました。証券会社の中には、米国株式や中国株式など、海外の銘柄を広く扱っているところもあります。会計処理上…

退職給付会計の過去勤務費用とは?算出方法をわかりやすく解説
会計業務過去勤務費用は、退職にともない支給する退職給付に関連するものです。過去勤務費用は退職給付においてどのような性質の費用を表すのでしょうか。この記事では、過去勤務費用の概要と算出方法、…

金利調整差額とは?認められない場合もわかりやすく解説
会計業務会計処理上、企業の所有する有価証券は4つに区分されます。4つの区分のうち、金利調整差額が関係してくるのは、満期までの保有を目的に所有する債券とその他有価証券に区分される債券です。こ…
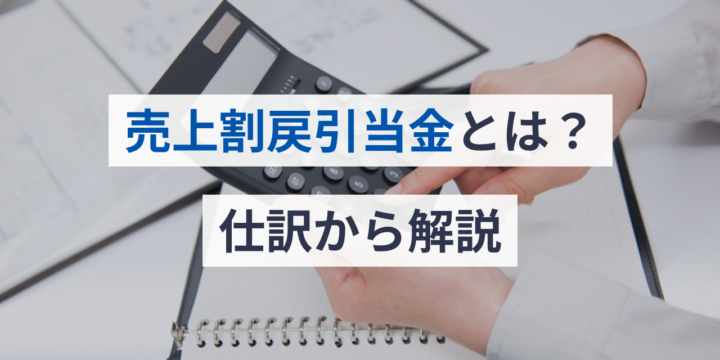
売上割戻引当金とは?仕訳から解説
会計業務製造業や卸売業において、一定額または一定数量の売上を達成した販売店などに対して、顧客との契約に基づき売上代金の一部控除を行うことを「売上割戻」と言います。また、売上割戻に対する引当…

営業外支払手形と営業外受取手形を仕訳から解説
会計業務手形を活用すれば、資金を準備できないときでも、仕入や有価証券の購入などを行うことが可能です。企業が扱う手形は、取引の事由に応じて、支払手形(受取手形)と営業外支払手形(営業外受取手…

見本品とは?仕訳や会計処理を解説
会計業務見本品とは無償で提供される商品や製品のことです。取引先や顧客に製品のよさや特徴を理解してもらうために、実際に使用したり手にとったりできるものを意味します。 見本品は会社の在庫品とし…

仕切精算書とは?書き方や会計処理の解説
会計業務委託販売を依頼している受託先から仕切精算書という書類が送られてきて、どのような処理をすべきか分からず、困っている方はいるかもしれません。また、委託先に仕切精算書を送付すると知って、…
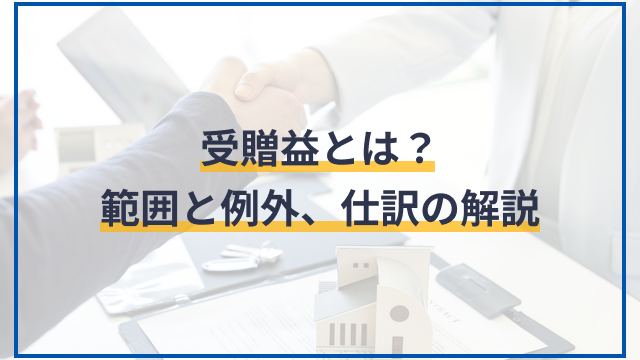
受贈益とは?範囲と例外、仕訳の解説
会計業務受贈益とは特別損益の1つで、無償または低額で資産を譲り受けた際に使う収益勘定です。無償で資産を受け取った場合でも、法人税の対象となるため会計処理を実施する必要があります。 しかし、…

預金科目の種類とは?普通預金以外の銀行の口座科目を解説!
会計業務銀行の預金科目は普通預金以外にも、さまざまな種類があります。定期預金や当座預金などはよく知る科目でも、通知預金・別段預金などはあまり馴染みがないかもしれません。通常よりも高い金利で…

リース会計基準とは?改正に伴う影響は?
会計業務設備を調達したい会社(借手)に代わってリース会社(貸手)が新規購入して貸借する取引のことをリース取引といいます。このリース取引に関する基準などを定めた「リース会計基準」が、2008…

工事原価と4つの構成要素をわかりやすく解説
会計業務建設業では、工事原価といって、工事ごとに原価計算を行い、完成工事高(収益)との対応を行ったのちに、利益を計算します。それでは、工事原価にはどのようなものが含まれるのでしょうか。この…

仕入戻しとは?仕訳から解説
会計業務「仕入戻し」とは注文した商品に何らかの問題があり、返品をする際に使う勘定科目です。どのように返品のやりとりをしたのか残すためにも、仕入戻しを勘定科目に取り入れて仕訳をすることが大切…

割賦販売の会計処理と仕訳方法のまとめ
会計業務割賦販売は、主にパソコンや車などの高額な商品の代金を分割払いで契約する販売方法です。本記事では、割賦販売をしたときの仕訳の書き方やポイントを解説します。また、平成30年度の税制改正…

新株予約権とは?会計処理やメリット・デメリットの解説
会計業務あらかじめ決められた条件や金額によって、株式会社の発行する株式を取得できる権利を「新株予約権」といいます。新株予約権を株式会社が発行した場合、または取得した場合、どのように会計処理…

子会社株式の減損処理や評価損について解説
会計業務会社が保有する有価証券は、会計処理上、時価評価するもの、時価評価しないものに分類されます。時価評価しない有価証券は、取得原価(取得時の取得価額)などで評価しますが、時価が大きく下落…

子会社株式とは?わかりやすく解説
会計業務「子会社株式」とは企業が保有する資産の1つで、他の企業の議決権を行使するためのものです。子会社に該当すれば、運営方針や人事などで決定権を得られます。しかし、子会社に該当する基準は意…

資本連結の考え方や仕訳を基本から解説
会計業務実質的な支配関係がある会社を企業グループとし、ひとつの組織体として行う決算を連結決算といいます。連結決算では、投資と資本の相殺消去など一連の処理である資本連結を行い、企業グループ全…
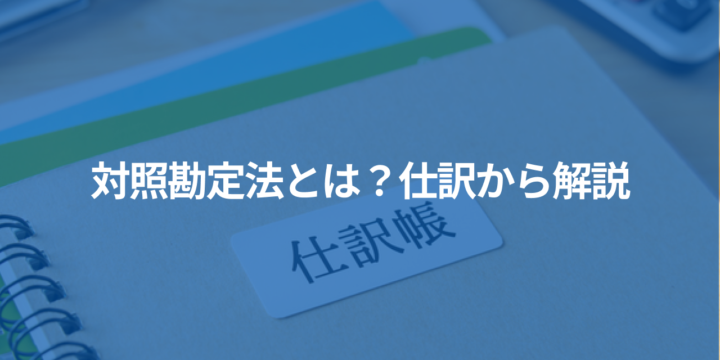
対照勘定法とは?仕訳から解説
会計業務対照勘定法は、実施された取引の内容を忘れないようにするための備忘記録として、特殊な仕訳を用いて帳簿に記録する方法です。この記事では、具体的にどのような仕訳を行うのか、対照勘定法の概…

決算とは?行う理由や時期、業務の流れ、必要書類について解説!
会計業務健全な経営を図るため、また、株主などのステークホルダーへの会計責任を果たすために、会社は「決算」を行います。この記事では、なぜ決算が必要なのかという理由から、決算の時期、決算業務の…

賃上げ税制とは?令和4年度税制改正による変更点やメリットをわかりやすく解説!
会計業務賃上げ税制(賃上げ促進税制)は、従業員の給与引き上げを支援する制度です。所得拡大税制に代わる税制で、令和4年度の税制改正大綱において、賃上げ税制のさらなる見直しが盛り込まれました。…

共益費とは?管理費や家賃との違いや勘定科目について解説!
会計業務賃貸オフィスなどを契約する際、家賃とは別に、共益費がかかることがあります。なぜ、契約によって共益費が発生するのでしょうか。この記事では、共益費の概要と管理費や家賃との違い、共益費を…

税制改正大綱とは?令和4年度の中小企業に関する改正ポイントを解説!
会計業務令和3年12月24日、令和4年度税制改正大綱が閣議決定されました。今後、国会での審議や本会議での可決で改正法が成立する見込みです。令和4年度税制改正大綱で柱とされたのが、成長と分配…

二重責任の原則はなぜ必要か?
会計業務監査に関わる仕事を担当している人であれば、「二重責任の原則」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。二重責任の原則は、日本の監査制度を信頼できるものにするために欠かせないルール…

単一性の原則とは?形式多元や二重帳簿についてもわかりやすく解説!
会計業務単一性の原則とは、異なる形式の財務諸表であっても、単一の会計帳簿により作成することを明記したものです。信頼できる財務諸表を作成するためには、単一性の原則を必ず守らなければいけません…

真実性の原則とは?意義や目的、相対的真実についても解説!
会計業務真実性の原則は、企業会計において真実な報告を求めるものであり、企業会計原則の一般原則に記された会計の根本的なルールです。本記事では、会計・経理の担当者に向けて真実性の原則を分かりや…

重要性の原則とは?金額での判断基準や適用例についてもご紹介
会計業務本記事では、企業会計の基本的なルールのひとつ「重要性の原則」について、具体的に解説します。重要性の原則とは、重要性の乏しいものに関する例外的な会計処理を認める規定です。重要性の原則…

商標権の会計処理や仕訳方法まとめ
会計業務商標権とは商品やサービスに商標となる目印をつけて独占できる権利です。商標権を得ると、自社の商品に使われるデザインや文字などを保護できます。 商標登録をする際に支払った費用は、固定資…

転リース取引とは?会計処理と仕訳の解説
会計業務さまざまなビジネスの方法がある中で、転リース取引を行っている事業者は少なくありません。しかし、転リース取引は、通常のリース取引と会計処理が異なります。そこで、転リース取引の概要や会…

フルペイアウトの意味とは?リース取引の基本まで紹介
会計業務会計処理上、リース取引は主に「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分けられます。ファイナンス・リース取引に該当するには、「解約不能」と「フルペイア…

未渡小切手とは?仕訳から解説
会計業務未渡小切手とは、取引先に渡す予定で振り出したにもかかわらず、渡せないままになっている小切手のことです。本記事では、未渡小切手が見つかった場合の対処方法や、混同されがちな未取付小切手…

電子記録債権の会計処理とは?仕訳の解説
会計業務新しい金銭債権である「電子記録債権」は、発生時と譲渡時、決済時にそれぞれ会計処理をする必要があります。どのような勘定科目が使えるのか、具体的な仕訳例も紹介しつつ解説するので、ぜひ参…
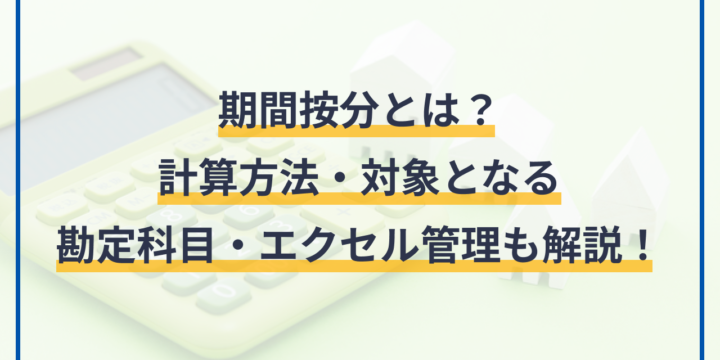
期間按分とは?計算方法・対象となる勘定科目・エクセル管理も解説!
会計業務月次処理や決算など会計処理をしていく過程で「期間按分」が必要になるケースがあります。「期間按分」とは、一定の基準に基づいて収益や費用を対応する期間それぞれに按分する計算方法を指しま…

修繕引当金と特別修繕引当金とは?
会計業務修繕引当金や特別修繕引当金は、決算整理仕訳で計上される勘定科目です。日常的に使用される勘定科目ではないため、扱い方がよく分からない経理担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、…

短期前払費用の特例とは?仕訳や要件を具体例から解説
会計業務短期前払費用の特例を詳しく知らなくても、前払いしている費用を即座に費用計上しているという経理担当者は多いのではないでしょうか。実は、この会計処理は「短期前払費用の特例」という特例を…
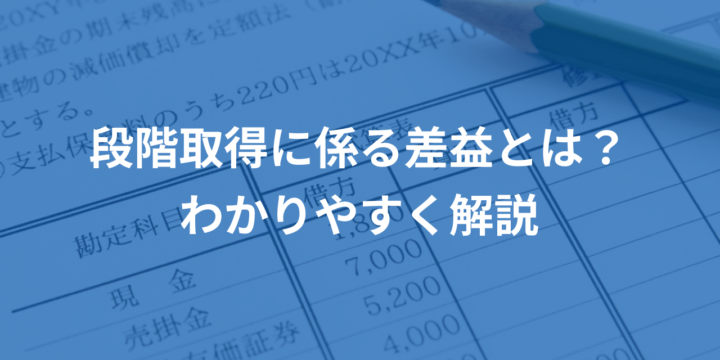
段階取得に係る差益とは?わかりやすく解説
会計業務連結財務諸表を作成するための会計処理には、子会社への投資と、資本の相殺消去をする処理が必要になります。このとき、子会社株式を一括して取得(一括取得)する場合と、複数回にわたって段階…
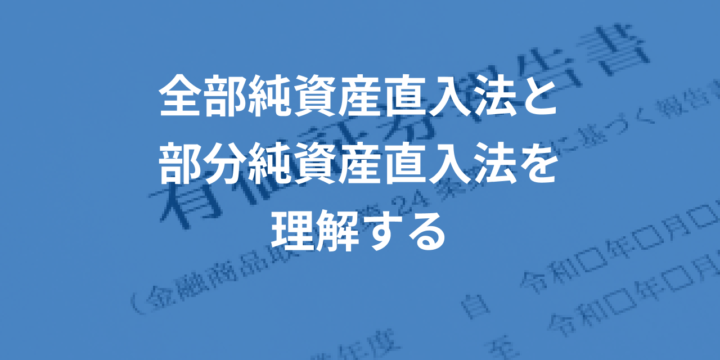
全部純資産直入法と部分純資産直入法を理解する
会計業務その他有価証券を時価に評価替えするときの方法は「全部純資産直入法」と「部分純資産直入法」の2つがあります。有価証券の取得原価と時価に差額がある場合、その他有価証券評価差額金を会計処…

積送品とは?仕訳から解説
会計業務積送品とは委託販売のために発送した商品のことです。委託販売の際に積送品として振り替えをすることによって、商品在庫の管理や委託先への発送状況などの確認ができます。 そこで今回は、積送…

帳簿の締め切りとは?書き方と流れを解説
会計業務決算期にすべての帳簿の記載が終わったら、当期の記入と次期の記入を区別するために帳簿の締め切りを行わなければなりません。 帳簿の締め切りには4つの流れがあります。収益、費用の各勘定の…

流動性配列法と固定性配列法とは?
会計業務貸借対照表には資産や負債、資本金が勘定科目としてよく使用されます。その科目を配列する方法が、流動性配列法と固定性配列法です。 2つの配列法は上に来る項目が反対になっており、流動性が…

本支店会計とは?本店集中計算制度と支店分散計算制度の仕訳を解説
会計業務複数の支店を持つ企業では、支店の採算性をみるために「本支店会計」を用いることがあります。本支店会計には「本店集中計算制度」「支店分散計算制度」があるため、それぞれの意味と使い方の理…

財務とは?業務内容をわかりやすく解説
会計業務日頃関わりのない人にとって財務は、何をやっているのかよく分からない仕事だという印象があるかもしれません。本記事では財務に馴染みのない人に向けて、財務の業務内容や会計や経理との違いを…

ペーパーレス化とは?導入方法のポイントやメリットを解説
会計業務近年は多くの企業でペーパーレス化の動きが加速しています。そもそもペーパーレス化がどういったものなのか、その意味や目的を理解していない方も多いでしょう。 そこで、本記事ではペーパーレ…

通貨代用証券とは?一覧と仕訳の解説
会計業務通貨代用証券に該当するものには他人振り出しの小切手や郵便為替証書、送金小切手などがあります。これらの言葉は聞いたことがあっても、「通貨代用証券」という用語に馴染みがない人は多いので…

費用性資産と貨幣性資産をわかりやすく解説
会計業務資産は「費用性資産」と「貨幣性資産」に分類することができます。言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような資産が費用性資産と貨幣性資産に該当するのか、把握できていない方も多いでし…
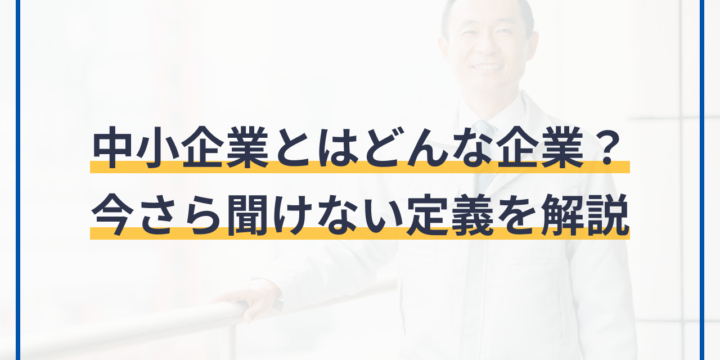
中小企業とはどんな企業か?今さら聞けない定義を解説
会計業務日本の企業のほとんどが中小企業であることを知っていても、中小企業の定義を明確に答えられない人も多いのではないでしょうか。 しかし中小企業であるかどうかは軽減税率措置を始め、企業を経…

中小企業の人数とは?法律上の定義と助成金の利用要件
会計業務「中小企業」という言葉は普段何気なく使っていますが、法律的な定義があるため勝手に判断することはできません。 また、中小企業が対象の各種助成金にも人数要件が定められていることが多いた…

中小企業の定義は法律によって異なる
会計業務中小企業は大企業に比べて経営基盤が安定していないことから、優遇措置や補助金の支給など、さまざまな支援が受けられます。 しかし、これらの支援を受けるには、それぞれに定められた「中小企…

役務収益と役務原価の仕訳方法とは
会計業務商品売買に限らず、近年では、多種多様のサービスを提供する企業も増えてきました。「役務収益」や「役務原価」は、モノを販売するのではなく、サービスを商品として提供したときに使われる勘定…

利息法について計算方法まで解説
会計業務利息法とは、償却原価法の中の一つで、債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を債券の帳簿価格に対し、実効利子率になるように各期の損益に配分する方法のことです。この記事では利息法…

連結税効果会計をわかりやすく解説
会計業務グループ会社で連結財務諸表を作成する際には、親会社と子会社の財務諸表を単純に合算するだけではなく、親会社と子会社間の取引で生じた取引や債権債務・未実現利益を消す、貸倒引当金の修正を…

貸倒金とは?仕訳例をわかりやすく解説
会計業務貸倒金とは、取引先から売掛金や貸付金、未収入金などの回収ができなくなった場合の損失を計上する勘定科目です。貸倒引当金とは異なり、損失が確定した場合に計上します。 債務者が支払い免除…

EMS料金支払の仕訳と消費税の取扱を解説
会計業務EMS(国際スピード郵便)を送る際、注意したいのが消費税の支払いです。EMSの支払いは国内郵便と同じ勘定科目で仕訳しますが、輸出免税取引で消費税がかからないため、課税取引にしないよ…

インプレストシステムの仕訳方法まとめ
会計業務インプレストシステムとは、小口現金制度のひとつです。1週間または1カ月という期間を決め、まとまった現金を各部署の小口現金係に支給します。日常業務で発生する経費を各部署が備えることで…

電話加入権は償却できる?会計処理や仕訳の解説
会計業務固定電話を使用している場合に発生するのが、電話加入権です。電話加入権は、簡単にいうと、電話回線を引くための負担金のことです。では、電話加入権が発生した場合の会計処理はどうなるのでし…

特殊商品売買の基本と仕訳をわかりやすく解説
会計業務特殊商品売買とは、商品売買の中でも通常とは異なる販売、購入形態をとる売買をいいます。 「特殊な商品」の売買ではなく、商品販売形態、購入形態などが一般と異なるものです。 この記事では…

立替金とは?仕訳方法をわかりやすく解説
会計業務立替金とは会社内外に関わらず、取引先や従業員などが本来負担すべき金銭を一時的に会社が立て替えた際に仕訳処理するための勘定科目です。立て替えは一時的なものとし、相手から返済してもらう…

売上戻り高の意味と仕訳例まで徹底解説
会計業務「売上戻り高や売上値引き、仕入れ戻しなど、似ている名前の用語が多くて違いがよく分からない」という経理担当者は多いのではないでしょうか。本記事では、これらの勘定科目の意味の違いや仕訳…

入金伝票とは?書き方や仕訳方法をわかりやすく解説
会計業務経理経験がある人でも、初めて入金伝票を手にすると戸惑うことがあるかもしれません。この記事では、初めて入金伝票を取り扱う人向けに入金伝票の書き方や仕訳方法を解説します。入金伝票は仕訳…

法人事業税の税率や計算方法について解説!
会計業務法人が納付する税金には法人税や法人住民税、特別法人事業税などのいくつかの種類がありますが、その中で法人事業税とはどのような税金なのか詳しく解説します。申告する際の税率や計算方法、外…

役員報酬とは?給与との違いや相場・決め方などを解説
会計業務役員報酬とは、取締役や監査役といった役員に支払う報酬を指します。役員報酬は従業員に支払う給与とは異なり、一定のルールを厳守しなければ損金に計上することはできません。この記事では、役…

委託買付と受託買付を仕訳から解説
会計業務「委託買付」は、手数料を支払って他者に商品の購入を委託することを指します。一方の「受託買付」は、商品の購入を委託された受託者側からみた場合の買付業務のことを指します。立場が異なるた…

超過累進税率を踏まえた所得税・相続税・贈与税の計算方法
会計業務所得税や相続税、贈与税の計算では、一律の税率は用いません。「超過累進税率」を使って計算を行います。所得税など一部の税金の計算に使われる超過累進税率とはどのようなものなのでしょうか。…

リース投資資産の仕訳やリース資産との関係を解説
会計業務リース取引において、リース期間終了後、貸し手に支配権が戻るリース物件を、「リース投資資産」といいます。リース投資資産の処理は、リース業を行っている会社なら押さえておきたい業務です。…

外貨建取引と外貨建取引等会計処理基準について解説
会計業務一般的な商取引では、取引金額は「円建て」で行うのが通常です。しかし、海外の企業との取引では「ドル建て」「ユーロ建て」といったような外国通貨で行うこともあります。今回は外貨建て取引と…

現金取引を仕訳例からわかりやすく解説
会計業務法人や個人事業主が作成する帳簿書類の中には、「現金出納帳」または「現預金出納帳」と呼ばれる帳簿があります。現金出納帳は、すべての現金取引を記録した帳簿です。事業を行うにあたって、現…

工事未払金の使い方や仕訳、未成工事支出金との関係
会計業務建設業会計では、一般の商業簿記で使われる勘定科目とは別に、特殊な勘定科目が使われます。「工事未払金」も、建設業会計で用いられる勘定科目の一種です。工事未払金はどのような場面で使われ…

商品保証引当金の意味や仕訳、製品保証引当金との関係
会計業務修理や返品交換などの商品保証は、問題となる事象が発生したときにのみ保証が行われます。必ずしも発生する性質ではないことから、これまでの商品保証を行った傾向をもとに、合理的に見積もれる…

純額表示と総額表示の違いをわかりやすく解説
会計業務2021年4月1日から「収益認識に関する会計基準」が適用されたことによって、収益の表示方法が変更されました。強制適用を受ける上場会社や大会社などでは、これまでの収益認識の仕訳を会計…

自己振出小切手の使い方や仕訳方法
会計業務自己振出小切手はそれほど登場頻度が高くないため、まだ出会ったことがないという人も多いでしょう。自己振出小切手という名前だけ見ると難しく感じられますが、実際は自分が振り出した小切手が…
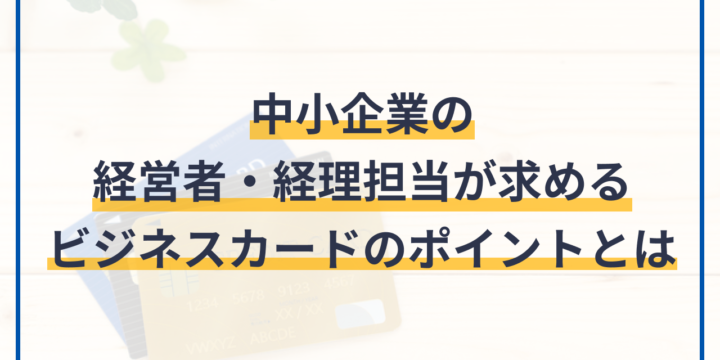
中小企業の経営者・経理担当が求めるビジネスカードのポイントとは
会計業務法人の経理作業にはビジネスカードの活用が便利ですが、実際に導入、利用する際にはどのようなポイントが意識されているのでしょうか? 30名以下の企業の法人経営者・経理担当の方に、ビジネ…

当座預金と普通預金の違いは?メリット・デメリットまで解説!
会計業務金融機関に金銭を預ける預貯金は、個人だけでなく法人も広く利用しているサービスです。事業を営む法人や個人事業主は、普通預金や定期預金以外に当座預金も利用できます。事業者向けの当座預金…

売価還元法とは?棚卸資産の評価方法や原価法、計算方法も解説
会計業務主に販売を目的として所有する事業用の財産を、棚卸資産といいます。棚卸資産は貸借対照表上に記載される科目で、適切に評価するために毎期末どのくらい在庫があるか、価格の下落で損が生じてい…

仕入割戻とは?会計処理、仕訳例、税務上の扱いを解説
会計業務仕入割戻とは、一定期間に多額もしくは大量の仕入れをした際に代金の一部が返還されることです。価格が事後に下がるため、仕入高から控除する処理を行います。税務上の取り扱いでは、算定基準が…

非支配株主に帰属する当期純利益とは?わかりやすく解説!
会計業務連結決算で子会社が完全子会社でない場合に必要となる「非支配株主に帰属する当期純利益」ですが、いまいち概念が分からないという人も多いのではないでしょうか。実際に苦手意識を持つ人も多い…

評価勘定とは?代表的な勘定科目の貸倒引当金や評価勘定法などをわかりやすく解説!
会計業務評価勘定とは、ある勘定科目を評価する目的で使用する勘定科目のことです。具体的に、どのような勘定科目を指すのでしょうか。この記事では、評価勘定の概要や評価勘定に含まれる代表的な科目、…

未払法人税等とは?計上方法や勘定科目、仕訳例まで徹底解説!
会計業務決算日時点における税金の未払い額を表す勘定科目に「未払法人税等」があります。法人税の確定申告は、決算日よりも後になりますので、法人税などを納める企業であれば、通常は未払法人税等の計…

負ののれんの発生原因から仕訳、会計処理など解説
会計業務経営基盤の強化や後継者問題解決の方法として、M&Aが注目を浴びるようになりました。M&Aとは企業買収や企業合併のことで、広義では資本業務提携や技術などの業務提携を含みます。M&Aに…

社債とは?株式との違いや種類、リスクや銘柄まで簡単に解説!
会計業務事業の拡大を図りたいとき、新事業を立ち上げたいとき、事業の成長スピードを上げたいときなど、企業はさまざまな場面で資金が必要になります。資金調達の方法として代表的なのが、株式の発行で…

土地再評価差額金とは?会計処理の方法を仕訳例を用いて解説
会計業務上場企業の財務諸表を見ると、貸借対照表の純資産の部に「土地再評価差額金」が記載されていることがあります。「土地再評価差額金」がどのような勘定科目なのか、知らない方は多いでしょう。計…
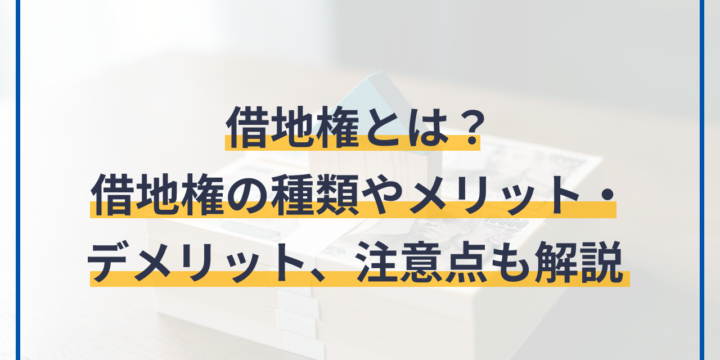
借地権とは?借地権の種類やメリット・デメリット、注意点も解説
会計業務建物の建設は、所有する土地にはもちろん、借りた土地に行うことも可能です。このうち、土地を借りて建物を建てる場合、借主を保護するための権利である借地権が発生します。具体的に借地権とは…

分記法とは?三分法や総記法との違いや仕訳例を解説・簿記3級受験者必見!
会計業務簿記には分記法や三分法、総記法とよばれる記帳方法があり、仕訳方法によってメリットとデメリットが異なります。仕訳方法の種類を知ることは簿記の第一歩です。この記事では主に分記法の基本に…

単利・複利とは?計算式は?合計積立金額をシミュレーションしよう
会計業務金融商品には、単利で計算するものと複利で計算するものがあります。どちらで計算するかによって、殖えるお金も異なるため、単利と複利の計算式の違いを理解しておくことが大切です。 本記事で…

売上原価対立法とは?三分法や分記法との違いから仕訳例までわかりやすく解説!
会計業務商品売買時に仕訳する際の記帳処理方法には、「売上原価対立法」「三分法」「分記法」などがあります。売上原価対立法は、商品売買を「商品」「売上」「売上原価」の3つの勘定科目で仕訳する点…

洗替法(洗い替え方式)とは?切放法との違いや売買目的有価証券の仕訳例など徹底解説!
会計業務簿記で資産負債の帳簿価額(簿価)を評価計上する際の方式として「洗替法」「切放法」「差額補充法」があります。 売買目的有価証券や貸倒引当金(大企業では廃止)などを評価替えする際に用い…

長期前払費用とは?仕訳例や勘定科目、前払費用との違いまで解説!
会計業務長期前払費用とは、前払費用のうち一定のものです。 この記事では、勘定科目として長期前払費用と仕訳するのはどのような場合なのか、繰延資産とはどのように違いがあるのか等、保険料などの例…

通知預金とは?メリットや定期預金との違いについてわかりやすく解説!
会計業務通知預金とは、まとまった資金を短期間預けるための預金です。普通預金よりも金利が高めの場合もありますが、同程度の利率ことも多く、利息にあまり差はありません。解約する際のルールや廃止の…

消費税とは?計算方法や使い道を分かりやすく解説
会計業務消費税は、商品やサービスの販売・提供に対してかかる税金で、年金、医療費、介護、少子化対策などに使用されている税金です。 消費税の計算は、標準税率10%の場合は【商品価格×1.1】で…

消費税を徹底解説!10%になって何が変わった?軽減税率とは? #2
会計業務2019年10月に消費税率は10%まで引き上げられました。また、同時に日本では初めてとなる軽減税率の制度も導入され、一部の品物の消費税は8%のまま据え置かれることに。これにより全て…

諸掛の意味と仕入諸掛・売上諸掛の仕訳を解説
会計業務諸掛とは、商品に対して係る保険料や運送料などの費用を指します。諸掛には「売上諸掛」と「仕入諸掛」の2種類があり、それを自社と取引先のどちらが負担するかで使う勘定科目が異なるのです。…

その他有価証券とは?仕訳とその他有価証券評価差額金について解説
会計業務有価証券は大きく分けて4つのグループに分かれます。「売買目的有価証券」「満期保有目的債券」「子会社株式・関連会社株式」の3つに該当しない有価証券を「その他有価証券」としてまとめてい…
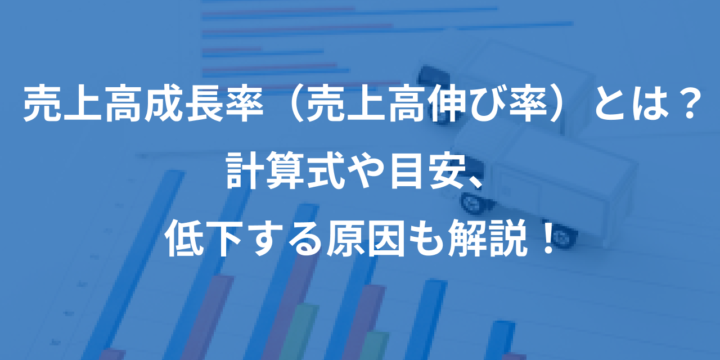
売上高成長率・売上高伸び率の計算式や目安を解説!
会計業務売上高成長率(英語表記:Sales Growth Rate)とは「売上高伸び率」とも呼ばれ、企業の売上がどの前期と比較してどの程度伸びているかを表す指標のことです。売上高成長率やそ…

営業外損益とは?営業損益や特別損失との違いを解説
会計業務損益計算書で見る「営業損益の部」「営業外損益の部」「特別損益の部」の項目。この3つの項目の特徴とそれぞれの違いを正確に理解できると、経営への貢献度の高い経理担当者になれるかもしれま…

正常営業循環基準とは?一年基準との違いや具体例についてわかりやすく解説!
会計業務正常営業循環基準とは、正常な営業サイクルにおける資産や負債を、流動資産や流動負債とする基準のことです。ifrsにおける英語分類では「Normal operating cycle r…

後入先出法とは?廃止理由やメリット、計算例などわかりやすく解説!
会計業務後入先出法とは在庫金額の計算方法の一つで、「新しく仕入れた商品から出庫して売れたことにし、古く仕入れた商品は在庫として残る」という考え方に基づいて在庫を計上する方法のことです。 後…

売上高販管費率とは?目安や計算式についてわかりやすく解説!
会計業務売上高販管費率とは、その名のとおり、販管費が売上高に占める比率のことを言います。 経費削減策の中でも、販管費の削減がまず取り沙汰されるでしょう。この記事では、その目安や計算式を含め…

資本金とは?企業の平均額やランキングを調査
会計業務新たに会社を設立する場合、必要となるお金が「資本金」です。「資本金」という言葉自体は、耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、細部にわたってきちんと理解している方は少ないかもし…

期末商品棚卸高とは?計算方法や仕訳例を解説
会計業務期末商品棚卸高は、期末時点での商品の在庫の額を表します。棚卸資産として決算書にも記載される価額です。では、期末商品棚卸高はどのように算出するものでしょうか。この記事では、期末商品棚…

仕入割引は損益計算書の勘定科目!仕訳方法や割戻・値引との違いとは?
会計業務割引と聞くと、日常使いされている商品代金の値引きを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、会計用語の「仕入割引」は、買掛金を支払期日より前に支払うことで、商品やサービスの価格を一部減…

個別法とは?原価法の棚卸資産評価方法のひとつ!仕訳例までわかりやすく解説
会計業務商品や製品などを取り扱っている事業者は、期末になると商品や製品などの棚卸しをする必要があります。棚卸しとは、簡単にいうと、期末に事業者が所有している商品などがいくらなのかを評価する…

期首商品棚卸高とは?仕訳や消費税区分を解説
会計業務期首商品棚卸高は、簿記の学習でも決算処理としてよく出てくる勘定科目です。 この記事では、期首商品棚卸高の仕訳、消費税の取扱、原価の計算方法などについて解説します。 期首商品棚卸高と…

償却資産申告書とは?対象の資産や書き方、固定資産税の納付までわかりやすく解説
会計業務土地や建物を所有しているとき、地方自治体から固定資産税が課税されることはよく知られているかと思いますが、これ以外に土地や建物以外の事業用の償却資産がある場合に、固定資産税として償却…

融通手形とは?仕組みや危険性についてわかりやすく解説!
会計業務融通手形とは、どのような仕組みなのでしょうか? 簿記の教科書にもあまり出てこない融通手形。ほとんどの場合には、資金調達のために利用するのですが、使い方によっては危険を伴います。 こ…

買掛債務とは?未払金と買掛金の違いや具体的な仕訳もわかりやすく解説
会計業務買掛債務とは何をさすのでしょうか? この記事では、未払金や買掛金といった買掛債務について解説し、企業が抱える支払の問題に対し、「買入債務回転期間」というキーワードから考えてみます。…

機能別分類と形態別分類との違いやIFRS適用時の表示方法を解説
会計業務原価計算を行う場合に重要なのが、発生原価をどのように分類するのかということです。原価計算には大きく分けて5つの分類方法があり、その中で重要となるのが機能別分類と形態別分類です。 機…

事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は?
会計業務経営者など役員に対する報酬や賞与は、一般社員の給与とは異なり、税務上の規定に従って支給されなければ損金算入できません。役員報酬は金額が大きくなりがちなため、損金算入として扱わなかっ…

伝票とは?種類を徹底解説 請求書との違いや項目もわかりやすく解説
会計業務「伝票(でんぴょう)」をうまく活用することで、経理業務の効率化や正確な記帳実施につながります。しかし、ひと口に伝票と言っても多種多様な書式が存在しており、記載内容や使用状況がそれぞ…

決算時に在庫を減らした方が良い理由とは?在庫と決算書の関係性
会計業務製品の加工や販売をするために、必要な商品を仕入れて在庫の確保を行う企業も多いでしょう。適正な在庫を保有しておくことで、品切れ防止や大量購入による単価コストの削減といったメリットが得…

消費税などの税金は決算書のどこに反映される?
会計業務一口に税金と言っても、さまざまな種類があります。 ただでさえ種類の多い税金が、決算書のどこに反映されるのかは、複雑でわかりにくいでしょう。 税金と決算書の関係は、3パターンに分類す…

時価ヘッジとは?繰延ヘッジとの違いや仕訳方法、税効果会計についてわかりやすく解説
会計業務資金調達や投資方法が多様化するなか、様々な金融商品の取引を行う企業も多くなりました。金融商品にはリスクが付きものですが、このリスクを可能な限り回避させるために、先物取引やオプション…

収支報告書とは?書き方を部活・飲み会など具体例別に紹介!無料テンプレートも
会計業務収支報告書とは、企業や団体などの組織や、飲み会や部活動などの集まりでの収支を記録した書類です。決算報告書よりも簡潔な内容とすることが多いですが、お金の出入りや運営状況の判断材料にな…
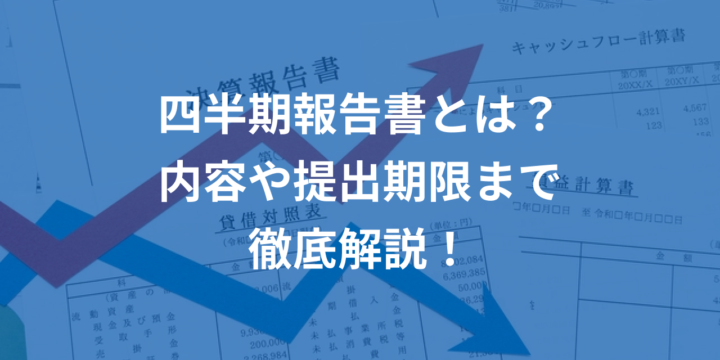
四半期報告書とは?内容や提出期限を解説
会計業務有価証券報告書はニュースやSNSなどで話題になることがあり、ご存じの方が多いと思います。ただ、実際に上場企業の決算書を探してみると、有価証券報告書よりも四半期報告書の方が目に触れる…
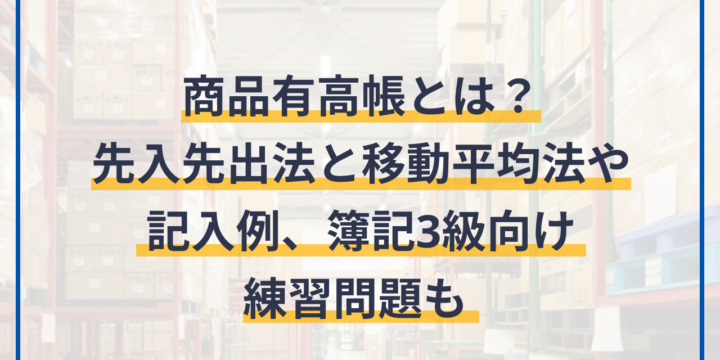
商品有高帳とは?先入先出法と移動平均法や記入例、簿記3級向け練習問題も
会計業務企業が商品を仕入れて販売する過程の中で、出荷するまでの間、一時的に商品が社内に滞留する状態があります。これを「在庫」と呼びます。「在庫」がいまどれくらい手元に残っているかを把握する…

手形要件とは?不備があった場合はどうなる?一覧でまとめて解説
会計業務手形は、一定の期日に決められた金額を支払うことを約束する決済方法です。企業間のやりとりで使用される場面もあり、名称を聞いたことのある方も多いと思います。 しかし、実際どのように取り…

売掛債権とは?未収入金との違いや管理・回収方法までわかりやすく解説
会計業務事業をしていく上で重要となるのが、売掛債権です。せっかく売上をあげても、売掛債権をしっかり管理しておかないと、キャッシュが不足するなどの事態に追い込まれる可能性があります。 そこで…
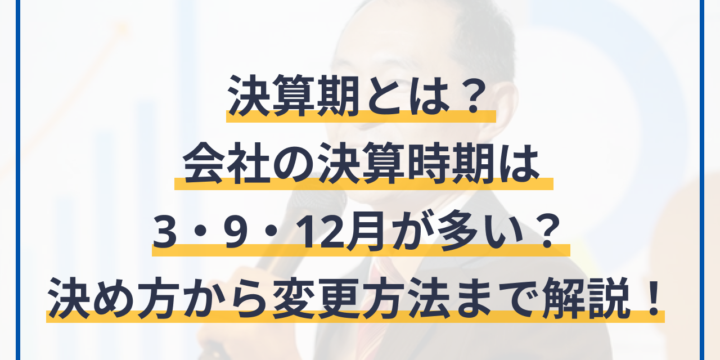
決算期とは?会社の決算時期は3・9・12月が多い?決め方から変更方法まで解説!
会計業務法人には個人と違って「事業年度」があり、自社の定款に事業年度を記載するのが一般的です。事業年度の最終日が決算日となり、決算日の次の日から新たな事業年度が始まります。 3月決算の法人…

特別損益とは?特別損失と特別利益として計上される具体例とともに解説
会計業務損益計算書において、企業が通常行っている業務で得た利益である経常利益に、特別利益を加え、特別損失を差し引いて税引前当期純利益を計算します。この経常利益の次の段階における、特別利益と…

後発事象とは?監査上の取り扱いや重要な後発事象の開示および修正について
会計業務決算書には、対象となる事業年度についての内容が記されています。 しかしながら、決算の翌日に財務諸表の内容を大きく変えるようなできごとが発生したときはどうしたらよいのでしょうか? 決…

先入先出法での棚卸資産の評価・商品有高帳の記入例 移動平均法との違いも解説
会計業務決算においてその事業年度の売上原価を求めるには、今までに仕入れた商品や製品が期末にどれだけ残っているかを調査しなければなりません。 多くは、商品や製品が実際にある倉庫などで物理的に…

貸倒懸念債権とは?判定基準や貸倒引当金の算定方法について
会計業務売掛金などの債権が将来、回収不能となるリスクに備えるために設定されるのが、貸倒引当金です。しかし、将来に回収不能となるリスクの大きさは、債権ごとに異なります。そこで債権をリスクの高…

損益法とは?財産法との違い、計算式、メリット・デメリットをわかりやすく解説
会計業務一定期間にどれだけの利益(損益)を得ることができたかを把握することは、企業にとって必要不可欠です。実は、一定期間の損益を計算する方法はひとつではなく、損益法と財産法の2つがあり、一…

年金資産とは?わかりやすく解説|計算方法や仕訳例
会計業務企業にとって、従業員の退職金の資金を用意することは重要です。自己資金を貯めておいたり、外部の年金制度に拠出したりすることなどで、将来の退職金支払いに備えます。 企業会計においても、…

売上台帳とは?エクセル無料テンプレート・書き方・手書きの方法
会計業務売上台帳は、売上に関連する取引を記録するための帳簿の一種です。売上台帳には、商品やサービスの販売によって生じた収入の詳細(販売された商品やサービスの種類、数量、販売価格、販売日、顧…

決算短信とは?概要と読み方を徹底解説
会計業務決算短信(けっさんたんしん)とは、企業の財務情報や経営状態がまとめてある書類のことです。投資家にとっては非常に有益な情報源であり、証券取引所でも重要情報として扱われています。しかし…

売上高経常利益率とは?計算方法や業種別目安を解説
会計業務売上高経常利益率は、売上高に対する経常利益の割合のことです。売上高経常利益率を把握することで、本業以外の収益や費用を含めた会社全体の収益力が把握できます。この記事では、売上高経常利…
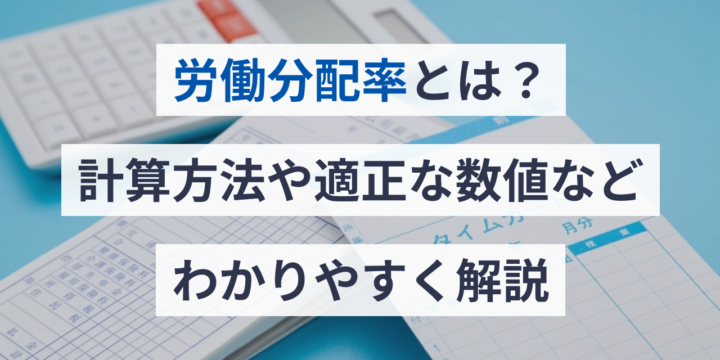
労働分配率とは?計算方法や適正な目安をわかりやすく解説
会計業務付加価値に占める人件費の割合を表す「労働分配率」は、人件費が適正な水準かどうかを判断するために使われる経営指標です。 人件費は従業員への投資であり企業が成長するためには増やすべきで…

送料にかかる消費税や軽減税率を解説
会計業務モノやサービスを消費したときにかかる消費税は、普段の生活の中で関わることが多くさまざまな場面で課税されます。 身近な税金であるだけに課税対象や税率など仕組みを正しく理解しておくこと…

公会計とは?新地方公会計制度や企業会計との違い、勉強法までわかりやすく解説
会計業務公会計(こうかいけい)とは、国や地方公共団体(地方自治体)における会計基準・会計処理の方法です。企業会計とは異なる目的と概念を持っていますが、あまり耳慣れない方も多いのではないでし…

飲食店の損益計算書の見方、作り方を例から解説
会計業務「損益計算書ってそもそもなに?」「どうやって作ればいいの?」 この記事では、そのような疑問がある方向けに損益計算書を飲食店に特化して、わかりやすく説明していきます。 結論から言うと…

売上計上の時期はいつ?計上時期の原則や税務調査で注意すべきポイントを解説
会計業務売上計上の時期は、会社の規模や業種、取り扱う商品やサービスによってさまざまです。 実現主義や発生主義などのさまざまな用語があり、迷うこともあります。 そこで、この記事では売上計上の…

個別注記表とは?記載例と注意点を徹底解説!
会計業務注記表には、個別注記表と連結注記表とがあります。個別注記表とは、会社個別の注記事項を記載した書類で、貸借対照表や損益計算書のような決算書に関連するものです。会社法の会社計算規則によ…

貸借対照表の現金・預金で見るべきポイントとは?
会計業務会社の会計期間1期分の財務状況を示す表が、貸借対照表です。貸借対照表は、表示科目を「資産」「負債」「純資産」の3つの部に分けて表示します。「資産」のうち、1番上にくる表示科目が「現…

未払金とは?未払費用や買掛金との違いや決算時に未払計上する仕訳例を解説
会計業務未払金は貸借対照表における負債の部に分類される勘定科目の1つです。似た勘定科目に「未払費用」や「買掛金」などがあり、間違って認識しやすい勘定科目ともいえます。 言葉は似ていても、そ…

決算での利益調整は違法になる?ならない?
会計業務利益調整というと、利益操作や不正などの粉飾決算をイメージすることが多いと思います。また、不正と利益調整は似ていることもあり、区別がつきにくい側面があります。 しかし、利益調整は合法…

法人決算を自分で(税理士なしで)やる手順を簡単に紹介!
会計業務法人決算とは、事業年度ごとに決算書類を作成することを指します。決算書類には貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などが含まれており、これらの書類から法人の経営状態や信用度な…

雑収入とは?雑所得や事業所得との違い、個人事業主の確定申告での注意点など
会計業務個人でも法人でも、よく使う勘定科目に「雑収入」があります。この雑収入とはどのようなときに使う勘定科目なのでしょうか。また、個人の場合は似たようなものに「雑所得」があり、混同されるこ…

販売費及び一般管理費とは?内訳の一覧や区分分析方法をわかりやすく解説
会計業務販売費及び一般管理費とは、商品やサービスの販売に関連する費用や一般管理業務で必要な経費をします。いずれも会社が本業を営む上で必要な費用です。この記事では、販売費及び一般管理費の仕訳…
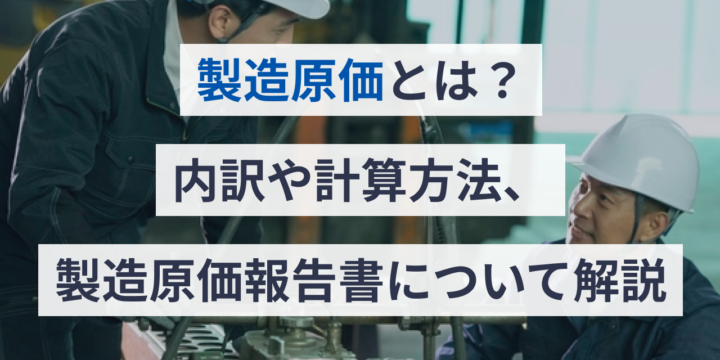
製造原価と売上原価との違い、内訳や計算方法、報告書について解説
会計業務製造原価とは、製品を作る際にかかった原価の合計を表しますが、英語では”Manufacturing cost”などといい、また当期製品製造原価となると英語では”Cost of pro…

未実現利益・未実現損益の消去と連結会計の仕訳を解説
会計業務未実現利益とは、連結会計で使われる用語で未実現損益ともいい、連結グループの観点で実現していない収益や費用のことを意味しています。 この記事では、そもそもの未実現利益から連結会計の未…

災害損失とは?特別勘定や会計処理について解説
会計業務被災された事業者は災害損失だけでなく、復旧費用も負担しなければいけません。 そのような事態のため税金面で特別の優遇制度があります。 この記事では、優遇制度を受けるために必要な事項で…

金融商品会計基準についてじっくり解説
会計業務金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)は、現金預金や有価証券、オプション取引など、金融商品の会計処理について示された会計基準です。金融商品の会計処理の基礎となる内容で、幅広い…

固定負債とは?流動負債との違いや貸借対照表での勘定科目の具体例を紹介
会計業務固定負債の「負債」という文字から借金をイメージする方も多いかもしれません。しかし、会計上の負債は借金だけでなく、未払金や買掛金など返済義務のあるもの全てを含んでいます。 貸借対照表…

販売促進費とは?広告宣伝費や交際費との違い、勘定科目の仕訳例を解説
会計業務販売促進費とは、商品やサービスの販売による売上増加や、ブランド力向上のための支出です。しかし、広告宣伝費や交際費との違いがわかりにくいことから「どの勘定科目を使うのが正解なのか」と…

予算管理とは?目的から手順・ポイントまで解説
会計業務予算管理の実施は、経営上の問題点の抽出や、経営の方向性ならびに業務改善の方向性を決めるためには非常に有効です。 しかし、適切な予算編成や業績の分析を行うには、予算管理の目的を理解し…

小口現金出納帳とは?書き方・記入例、現金出納帳との違いをわかりやすく解説
会計業務日常的に現金出納帳を利用している方でも「小口現金出納帳」は利用したことがない方も多いでしょう。どちらも決算書類として利用するための重要度の高い帳簿です。 小口現金出納帳を作成する目…

流動資産とは?主な種類とチェックポイント
会計業務簿記上における「資産」には種類があり「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3つで構成されています。中でも流動資産については、その意味や対象を正しく理解できている方は意外と多くないか…

資金繰り分析と資金繰り表や貸借対照表を使った方法を解説
会計業務資金繰りのイメージは、入金や出金を予測するために資金繰り表を作成することではないでしょうか。資金繰り表は、項目が細かく複雑な計算が必要だと思いがちですが、大きくざっくりと見ることが…

棚卸しとは?目的や評価金額の計算をわかりやすく解説
会計業務棚卸しは、商品の在庫が実際にどのくらいで、状態はどうか確認するために必要なもので、会計処理にも影響します。年に数回棚卸しを行うこともあれば、業種によっては月末の度に実施するなど、手…

印紙が必要な契約書の種類と金額まとめ
会計業務契約書をはじめ、一部の文書には印紙税が課されるため、収入印紙を貼りつけ、消印しなくてはなりません。ただし、収入印紙による印紙税の納付は、必ずしも印紙税の範囲に含まれる文書に必要なわ…

印紙が必要な契約書の種類と金額まとめ #2
会計業務契約書をはじめ、一部の文書には印紙税が課されるため、収入印紙を貼りつけ、消印しなくてはなりません。ただし、収入印紙による印紙税の納付は、必ずしも印紙税の範囲に含まれる文書に必要なわ…

会計システムとは?主な種類と機能について
会計業務企業の会計業務は、適切な会計処理に加え、債権債務の管理や経営に合った管理が必要など、複雑です。多くの企業では、複雑な会計処理を効率良く済ませられるようにするため、会計システムが用い…

売上債権とは?種類や管理・回収方法、売上債権回転期間と回転率の計算方法も解説
会計業務企業間の取引においてしばしば登場するのが「掛取引」「手形取引」です。信用に基づき代金の決済を繰り延べる取引形態ですが、信用取引により発生した売上にかかる債権のことを「売上債権」と呼…

為替換算調整勘定とは?例から解説
会計業務為替換算調整勘定は為替差損益と似ているようで、実は違う勘定科目です。 この記事では、連結会計や外貨建会計基準の基本的な部分を中心に、為替換算調整勘定の基本的な内容や具体例、税効果に…

売上債権回転率とは?計算式や目安と平均、売上債権回転期間の求め方まで解説
会計業務経営指標の一つに「売上債権回転率」があります。 さて、この指標はどのような時に役に立つのでしょうか? この記事では、売上債権回転率の計算式や値の目安、平均値、さらには売上債権回転期…

売掛金管理でエクセルや会計ソフトを使う方法
会計業務売掛金管理をする方法はさまざまです。 どのような管理表が求められるのか、また、エクセルや会計ソフトで売掛金管理をするにあたっての注意点などをご説明します。 売掛金管理とは?なぜ重要…

予実管理とは?目的・必要性とポイントを解説
会計業務会社の経営者にとって、会社の経営がうまくいっているのかどうか判断することは、必要不可欠です。会社の経営状態の判断材料として重要となるのが「予実管理」です。ここでは、予実管理の意味や…

税務会計とは?財務会計、管理会計、企業会計との違い、法人税の計算方法
会計業務会計にはいくつもの種類があり、財務会計や管理会計に並んで税務会計があります。 税務会計は、主に所得税や法人税の税金計算のために行われる会計で、財務会計とは目的が違います。 この記事…

手形売却損とは?仕訳例からわかりやすく解説
会計業務お金の代わりとして使えるのが手形です。手形は金融機関に売却することで、早期に現金化できます。ただし、満期日前に現金化すると割り引かれてしまうため注意が必要です。この割引料を「手形売…

前払金の仕訳例と前払費用との使い分けを解説
会計業務「前払金(まえばらいきん)」や「前渡金(まえわたしきん)」とは、購入した商品やサービスなどの代金について、その一部のみを支払った際の仕訳に使う勘定科目です。 事業を営む上では欠かせ…

売上債権回転期間とは?計算式や意味、目安と平均、長期化の理由を解説!
会計業務売上債権回転期間とは何を表す期間でしょうか? 熟練した入金担当者になると、売上債権回転期間については知らなくても、顧客の状況や入金状況について熟知している場合がありますが、売上債権…

記帳には会計ソフトを使うべき?色々な方法がある
会計業務「会計処理」には多くの時間と手間を要します。しかし「会計処理」は事業をうまく運営し、税金の計算を正確に行うための大切な作業の1つです。 会計の精度は、事業の発展や拡大に大きく影響し…

前期損益修正益・前期損益修正損とは?仕訳から解説
会計業務法人の決算は文字通り「一年間の計算を決する手続き」であり、専門部署の方々が時間と労力をかけてじっくり精査するものです。それでもなお、処理の間違いが起こるケースがありますが、修正を要…

受取手形とは?決済、回収時の仕訳・勘定科目や売掛金との違いをわかりやすく解説
会計業務現金での取引は、確実ではあるものの、企業間取引においては柔軟性の高い取引とはいえません。期限に柔軟性をもたせ、現金の代わりに利用されているのが「手形」です。 手形には、約束手形と為…

有価証券売却損とは?仕訳例や勘定科目の説明、計算方法を紹介
会計業務有価証券売却損は、有価証券を売却して損が出た時に使う勘定科目です。 また、似た勘定科目で投資有価証券売却損という勘定科目もあります。 この微妙な違いを、ご存じでしょうか。 この記事…

棚卸資産回転率(回転期間)とは?高い程いいの?計算や経営分析方法を解説
会計業務小売業の利益を上げるためにカギとなるのが棚卸資産回転率の指標です。 例えばスーパーでは、商品を仕入れて棚に並べ、売り切れになるまでのことを1回転といいます。一定の期間でこの回転が何…

当座資産の解説と当座比率の求め方や流動資産との違い
会計業務当座資産とは、会社の貸借対照表から「当座比率」を算出する際に必要です。当座比率を求めることで、企業の短期債務の支払能力を示す指標にすることができます。つまり、企業の安全性分析のため…

ROA(総資産利益率・総資本利益率)とは何の指標?目安や計算方法、ROEとの違いも
会計業務会社が作成した貸借対照表、損益計算書などの決算書は、経営分析で活用できます。経営分析の代表的な指標が、ROAやROEです。このうち、ROAは総資産利益率や総資本利益率といわれ、資産…
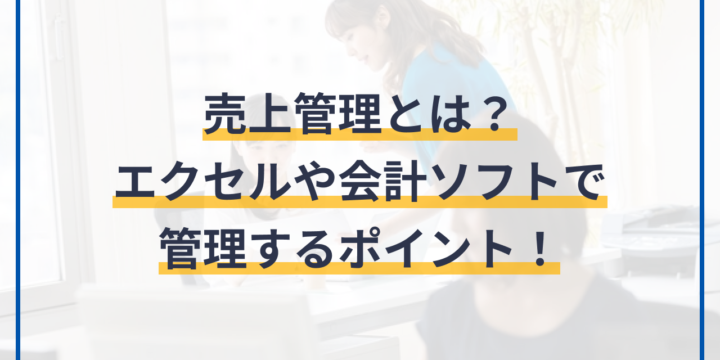
売上管理とは?エクセルや会計ソフトで管理するポイント
会計業務売上を管理する方法については、エクセルで売上管理表を作成したり、会計ソフトの機能を利用したりする方法があります。 取引のしかたや会社の規模にもよりますが、売上管理においてポイントと…

先日付小切手とは?小切手との違いや仕訳方法まで解説!
会計業務金融機関との当座預金契約を結んだ企業のみが振り出すことのできる小切手ですが、そのなかでも「先日付小切手」は企業の信用力が試されるものです。今回は「小切手」と「先日付小切手」の違いと…

退職給付会計とは?退職給付債務の計算や会計基準をわかりやすく解説
会計業務退職給付会計は、会計処理のなかでも専門用語の頻出度や計算の複雑さから、理解が難しい会計処理と言われています。 しかし、目的はシンプルです。 最終的に「退職給付引当金」と「退職給付費…

益金とは?益金不算入制度とは?徹底解説
会計業務益金(えききん)は、収益や収入といった用語と似通っていますが、同じ意味ではありません。 経営者や経理担当者は、益金や益金算入・不算入について理解しておかなければ、決算や税申告の際に…

覚書に収入印紙は必要か不要か?かかる金額は?
会計業務様々な契約の場面では、契約書以外に「覚書」の作成が必要となる場合があります。その際、「覚書に収入印紙は必要か」「覚書に貼る収入印紙の金額が分からない」といった点で困る方も多いのでは…

環境会計とは?どんな企業が導入しているの?
会計業務環境に配慮した経営が国際的な注目を集めるなか、環境会計の導入を推進する動きがあります。 環境会計を導入することで、将来の経営コストの削減や企業のブランドイメージ力の向上が見込めるか…

掛取引とは?仕訳の具体例と健全な割合を解説
会計業務掛取引(かけとりひき)とは、簡単にいうと後払いのことです。 個人に置き換えると、買い物でクレジットカード払いをするのとほぼ同じです。後日口座から引き落とされるものの、財布の現金を減…

資産とは何か?個人や会社、会計学上の資産について簡単に解説
会計業務資産とは会計学上、会社の経済主体に帰属する用益潜在力と定義されています。わかりやすく言うと、会社が持っている財産のことです。財産にはお金や商品の他、使用している機械や建物も含まれま…

賞与引当金とは?仕訳例とともに会計処理方法や税務上の取り扱いを紹介
会計業務「賞与引当金」は、決算時、適正な期間損益計算により財務諸表を作成するときに必要な勘定科目です。名称どおり、発生する可能性が極めて高い翌期の「賞与」に備え、引当金として計上します。こ…

決算整理仕訳とは?やり方やポイントをわかりやすく解説!
会計業務企業は年に1回決算をする必要があり、決算作業の一つに決算整理仕訳の作成があります。 決算整理仕訳は、簿記のやり方に従って、減価償却費の計上や貸倒引当金の繰入、売上原価の計算・仕訳な…

支払サイトとは?長いと良いの?意味や計算方法、決め方を解説
会計業務支払サイトとは、掛取引や手形とセットで使われるビジネス用語です。 個人で例えると、クレジットカードの請求金額が確定してから、口座引き落としの日までのことです。長すぎると何を買ったか…

わかりやすくて簡単な会計ソフトを比較する15のポイント
会計業務会計ソフトとは、伝票作成や総勘定元帳などの会計処理を効率よく行い、データとして管理するためのソフトウェアです。さまざまな会計ソフトがありますので、自社に合った会計ソフト選びが重要な…

企業結合に関する会計基準とは?徹底解説
会計業務企業結合会計は、M&Aの様々な取引を分類して会計処理が行われます。 この会計基準を理解するためには、M&Aの各取引に加えて、会計基準独特の分類の仕方を知らなければいけません。 そこ…

株主資本比率とは?計算方法から目安まで解説
会計業務株主資本比率は、企業の財務安定性を測る指標のひとつです。企業の経営が安定しているかどうかを見るのに重要な目安となります。この記事では、株主資本比率はどのような計算式で求めるのか、株…

役員退職慰労金とは?計算方法と功労加算・税金面の注意点や支給手続きを解説
会計業務取締役や監査役などの役員が退職した場合に、会社は役員退職慰労金を対価として支給することができます。 この役員退職慰労金については、支給する側にもされる側にも様々なメリット・デメリッ…

売買目的有価証券とは?時価評価の仕訳方法や有価証券評価損益の法人税の取扱
会計業務売買目的で所有している有価証券を「売買目的有価証券」といいます。 売買目的有価証券は時価評価が必要で、期末には「有価証券評価損益」科目を使って、仕訳をする必要があります。また、会計…

出張費とは?相場や旅費交通費との違いを詳しく解説
会計業務経理担当者にとって出張費の精算業務は、負担の大きい業務の1つといえるでしょう。申請内容にミスがあり、確認するべき経費が多いと、時間や手間を取られるためです。 また、出張手当と旅費交…

自己株式とは?取得・消却のメリットや制限、手続きをわかりやすく解説
会計業務上場企業では、比較的頻繁に行われている自己株式の取得や消却ですが、中小企業でも自己株式の取得や消却を行う会社が増えてきました。それは、自己株式の取得や消却にさまざまなメリットがある…
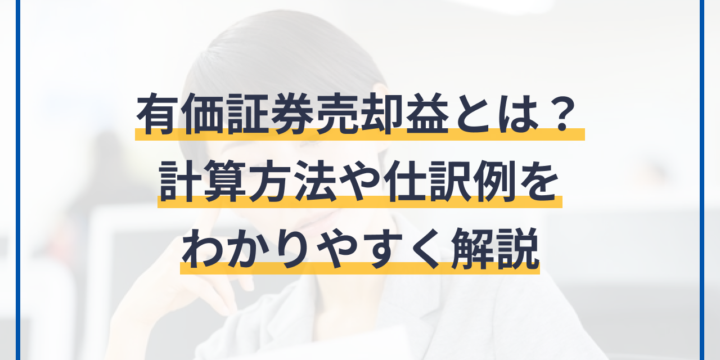
有価証券売却益とは?仕訳の方法や勘定科目の種類、計算方法を解説!
会計業務「有価証券売却益」とは文字通り、有価証券を売却益したときに使う勘定科目です。 ただし、仕訳を行う上では「そもそも有価証券とは何か」を理解しておく必要があります。 一般的な有価証券と…

固定資産の定義とは?種類や金額基準、償却方法や節税対策を解説
会計業務会社を正しく経営していくためには「固定資産」への理解は必要不可欠です。しかし、経理の実務経験がなければ、そもそも固定資産について学ぶ機会は少なく、内容まですべてを理解している方の方…

約定日とは?申込日・受渡日との違いや基準を解説
会計業務約定日(やくじょうび)、受渡日(うけわたしび)、申込日など日付に関する用語については、わかっているようでも案外あやふやな部分があるかもしれません。特に金融商品に関係するものは特殊な…

株主資本とは?自己資本・純資産との違い
会計業務「株主資本」「自己資本」「純資産」、それぞれについての違いを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。場合によっては、同じ意味として扱われているこの3つの用語ですが、正確に…

内部留保(社内留保)とは?!企業を守る資産で会社の強さをあらわす!
会計業務近年では、企業の内部留保がニュースで取り上げられることがあります。 労働組合などからは、内部留保せずに人件費の賃上げを要求する一方、経営陣は将来に備えて内部留保を行いたいと考えてい…

貢献利益の意味と限界利益との違いや計算方法、損益分岐点の求め方
会計業務貢献利益とは、会社の経営状況を判断する重要な指標の1つです。広義には、限界利益と貢献利益は同じと考えられますが、狭義では限界利益と貢献利益の考え方は異なります。また、損益分岐点とも…

前受金とは?仕訳例から、前受収益・仮受金との違いまで解説!
会計業務決算書の負債の部に表記される勘定科目の中に「前受金」というものがあります。商品の販売引き渡しや役務提供が完了する前に受け取った金銭を、前受けとして処理する際に使用する勘定科目です。…

会計処理って具体的に何?業務の流れや経理処理との違い
会計業務経理に配属されると「経理処理」や「会計処理」という言葉を聞くことが多いと思います。 これらの用語に厳密な定義はありませんが、経理の業務の1つに会計処理があります。 この記事では、会…

会計ソフトのランニングコストはどんなものがある?削減するには?
会計業務個人・法人を問わず、経営を行っていく上で決して無視できないのが、帳簿や会計の存在です。昨今では情報データの多さやその利便性から会計ソフトを使用して会計処理を行うことが当たり前になっ…
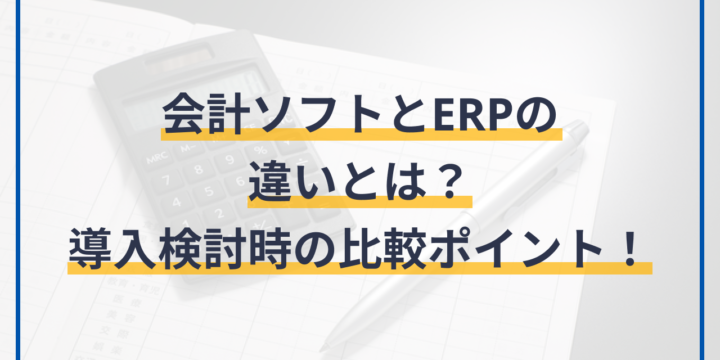
会計ソフトとERPの違いは?導入検討時の比較ポイント
会計業務これまでは「経理なら会計ソフト」といったように、効率化したい業務ごとにシステムを導入する形が一般的でした。しかし現在は、システム単体でなく複数のシステムを統合したERPの導入が増え…

法人税法とは?概要や目的、税効果会計をわかりやすく解説
会計業務法人税は、法人の所得に対し課税される国税であり、法人税法に規定されています。 法人税の節税にあたっては、損金に関してだけでなくバランスの取れた法人税法の理解が必要です。 ここでは、…

会計ソフトのバックアップはどうするのが正解?手法とポイントまとめ
会計業務会計ソフトデータのバックアップを取ることは、経理作業のリスクマネジメントとして非常に有効です。 しかし、なかには「バックアップを取ったことがない」という経営者や個人事業主も多いでし…
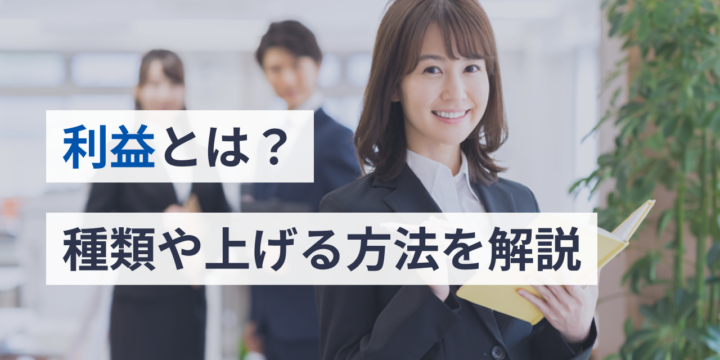
利益とは?種類や上げる方法を解説
会計業務利益とは収益から費用を差し引いたもののことで、利益を上げることが目的の一つとなる企業にとって、重要な経営指標です。また、損益計算書では売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利…

有価証券報告書とは何かをわかりやすく解説!提出義務がある記載要綱とは
会計業務有価証券報告書とは 有価証券報告書とは、株式を発行する上場企業などが開示する企業情報をいいます。開示される情報は、企業の概況、事業の状況、財務諸表などです。有価証券報告書を略して「…

仕掛品の意味や半製品との違い 棚卸資産での計上方法や読み方まで解説
会計業務製造業における工業簿記や商的工業簿記の決算では、仕掛品の計上は非常に大きな意味を持っています。 この記事では、仕掛品、半製品などの棚卸資産の意味やそれぞれの違い、計上方法などを…

移動平均法による評価方法をわかりやすく解説
会計業務企業の利益を把握するうえで、売上原価管理は無くてはならない業務のひとつです。棚卸資産の原価を正しく把握できていなければ、利益の数字が不正確となり経営判断や戦略に大きな影響を及ぼすで…
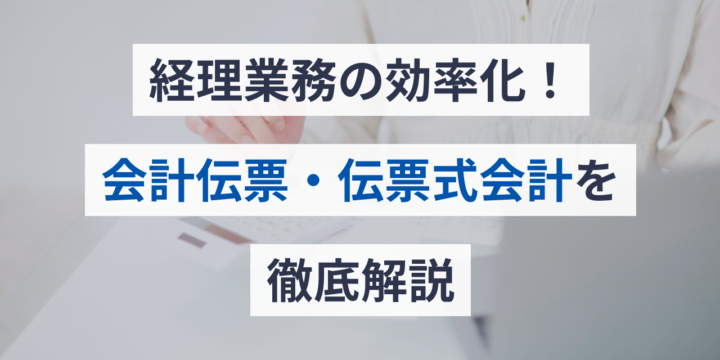
会計伝票・伝票式会計を解説!会計ソフトで経理を更に効率化しよう
会計業務「伝票」と聞くと、紙のイメージが強い方も多いでしょう。 伝票式会計の歴史は古く、紙と現金を前提としているといっても過言ではありません。 近年では、電子化・キャッシュレス化になってい…

事業報告書とは?作成方法や書き方・雛形・記載例についてわかりやすく解説
会計業務「事業報告書」とは一体どんなものでしょうか。ある程度のイメージはできるけど「具体的には?」「事業報告を詳しく知りたい」という方に向けて、この記事では事業報告書について詳しく解説して…

中小企業・零細企業が会計ソフトを比較するための13のポイント
会計業務従業員が増え、会計処理も増加すると、いよいよExcelや紙ベースでは管理が難しくなってきます。経理業務効率化のため会計ソフトの導入を考えている中小企業もあるでしょう。 しかし、会計…

2024年版-会計ソフトは無料で導入できる?
会計業務会計ソフトにはさまざまな会社のものが販売されており、自社にとって向いているものと向いていないものがあります。そこで利用したいのが、無料で導入できる会計ソフトです。 ただし、無料で導…

大企業・上場企業が会計ソフトを比較するための11のポイント
会計業務企業のバックオフィス業務には欠かすことのできない「会計ソフト」。 資本金が5億円以上、負債が200億円以上である大企業や上場企業は、公認会計士や監査法人の会計監査を受けなければなり…

支払明細書とは?意味や書き方、領収書・請求書との違い、無料テンプレートも
会計業務支払明細書というと、クレジットカードを使用した際などに発行されるものが思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、会社同士の取引でも支払明細書を発行することがあり、さらには領収書や請求…

売上高とは?意味や定義、営業利益や純利益との違いをわかりやすく解説
会計業務経営に関する参考書や株式のニュースなどで「売上高」や「営業利益」「純利益」という単語を見聞きする人も多いかと思います。なんとなくイメージはついても、具体的に説明をできる人は少ないの…

利益剰余金とは?仕訳例やマイナスになる理由をわかりやすく解説
会計業務経営や経理の上で「利益剰余金」という言葉を見聞きする人は少なくないでしょう。しかし、利益剰余金についてなんとなく理解しているけれども詳しくは分からない人、当期純利益との関係や仕訳に…

債務超過とは?純資産がマイナスになったら倒産?意味や解消方法について
会計業務債務超過(さいむちょうか)は、過去に日本のペッパーフードサービスや米国の航空会社ボーイングなどの大企業も陥った財務状況です。 「倒産しそうな危険な経営状態なのでは」というイメージは…

個人事業主が会計ソフトでクレジットカード決済する際の仕訳と注意点まとめ
会計業務今や個人事業主でも給与所得者でもクレジットカードの利用は日常となっています。 会計ソフトを利用した場合には、銀行口座と連携して会計仕訳を自動起票してくれる機能がありますが、クレジッ…

約束手形の仕組みとは?小切手との違いやメリット、仕訳方法
会計業務会社を経営していると「約束手形」「不渡手形」「裏書手形」「為替手形」「受取手形」「支払手形」など、『手形』というキーワードが付く取引を目にすることが多いのではないでしょうか。今回は…
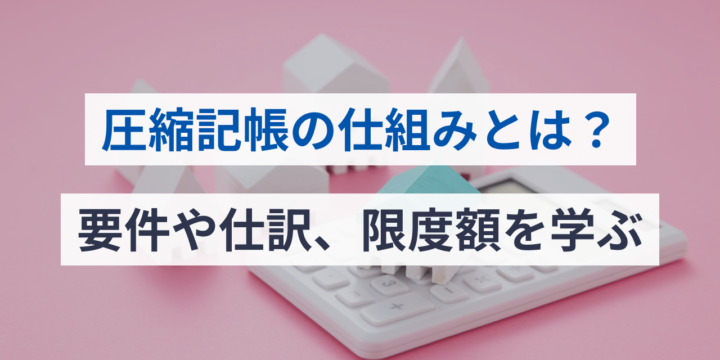
圧縮記帳の仕組みとは?要件や仕訳、限度額を学ぶ
会計業務圧縮記帳とは、一定の要件のもとで固定資産を取得した場合の「課税の繰り延べ」です。圧縮記帳について、適用要件、限度額、直接減額方式や積立金方式といった処理方法から具体的な仕訳までを簡…

会計ソフト導入のメリット・デメリットを徹底解説
会計業務会計ソフトは経理・会計業務の効率化に用いられるツールです。日常のデータ入力から決算、財務諸表作成までを簡単に行えて、業務の効率化・生産性向上が図れます。 この記事では会計ソフト導入…

会計ソフトにCSVファイルをインポートするポイント・注意点
会計業務多くの会計ソフトには、CSVファイルからデータをインポートする機能があります。CSVファイルインポート機能を使えば、エクセルで作成した表や他のソフトのデータを取り込むことができます…

剰余金とは?配当・処分の流れと仕訳方法
会計業務剰余金は、貸借対照表の純資産の部のうち、株主資本を構成する要素のひとつです。 この剰余金は、会社法上と会計上では少し意味が異なります。では、それぞれはどのような意味をもつのでしょう…

繰延資産とは?償却方法や仕訳例をわかりやすく解説
会計業務費用でありながら資産のような性質を持つものを繰延資産と言います。一時的な出費であるものの支出効果は長期にわたって継続し、数年をかけて費用化することが認められています。 繰延資産を計…

為替手形とは?仕組みや仕訳例、印紙税の金額などを解説
会計業務為替手形という手形がありますが、通常の約束手形や工業手形とは何が違うのでしょうか。今回は為替手形という手形独特の仕組みと流れと項目を説明した上で、為替手形を理解するために必要な、支…

流動比率と当座比率とは?目安や計算式、両者の違いを解説
会計業務会社の財務状況把握のために用いられる指標のうち、安全性を示す指標として流動比率と当座比率があります。流動比率は流動負債に対する流動資産の割合、当座比率は流動負債に対する当座資産の割…
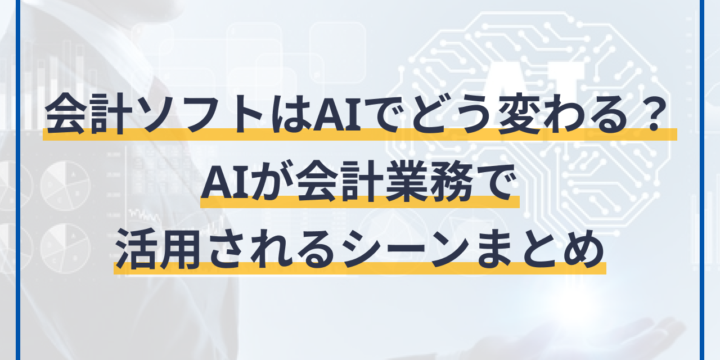
会計ソフトはAIでどう変わる?AIが会計業務で活用されるシーンまとめ
会計業務AIは近年、めざましく技術が進み、様々な分野で利用されてきています。会計ソフトにおけるAI導入も、すさまじいスピードで進んでいます。 AIは会計ソフトの様々な機能を自動化し、より使…

会議費とは?接待交際費との違いは?損金算入の特例や上限、仕訳方法も紹介
会計業務法人の経費の中には、勘定科目の取り扱いを間違えると、法人税に大きな影響を与えかねないものがいくつかあります。そのひとつが「会議費」です。会議費は、接待交際費などのほかの経費と性格が…

資産除去債務とは?会計基準と仕訳の具体例を解説
会計業務建物など有形固定資産の取得にともない、将来建物を解体する義務などが生じた見積もり可能なものを資産除去債務といいます。 財務諸表に有形固定資産の除去に関する将来の負担を反映することは…

総資産回転率(総資本回転率)の目安は? 計算方法をわかりやすく解説
会計業務総資産回転率(総資本回転率)という用語をご存じでしょうか?財務分析では総資産という言葉がつく比率が数多くあります。この記事では、その中でも重要な指標である総資産回転率について、基本…

固定長期適合率とは?計算式と目安、改善方法まで
会計業務固定長期適合率は、固定資産と自己資本と固定負債の合計額との割合を示す数値です。固定資産が安定した資金で賄えているかを表し、会社の財務状況が安定しているかどうかの判断に用いることがで…

安全性分析のための5つの指標~企業の決算書を分析して安全性を確認
会計業務企業の財務についての分析の中で、安全性分析という言葉を聞くことがあります。安全性分析とは一体どのようなものなのでしょうか。ここでは、安全性分析とは何かという点と併せて、その分析に使…

安全余裕率とは?計算式や損益分岐点との関係を解説
会計業務会社の経営状態を確認するためには、さまざまな指標を確認する必要があります。その1つが安全余裕率です。安全余裕率は、損益分岐点比率とも関係のある重要な指標です。そこで、ここでは安全余…

純資産とは?総資産との違いや内訳、見るべきポイントを解説
会計業務「純資産」とは、企業が所有する資産の総額から負債の総額を差し引いたものです。組織の実質的な経済的価値を表しており、財務状態の健全性を評価するのに用いられます。本記事では純資産と総資…

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?掛金や、加入資格、メリット・デメリット
会計業務経営セーフティ共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために創設された制度です。 共済への掛金は法人の損金や個人事業主の必要経費として処理されるため、節税対策としても効果的だといわ…

減資とは?意味とメリット・デメリットをわかりやすく解説
会計業務新聞やニュースで、よく企業が減資を行ったということを耳にします。実は、法人にとって減資をすることは、重要な意味を持ちます。なぜなら、減資をすることで、さまざまなメリットを得ることが…

EBITDAとは?計算式や意味をわかりやすく解説
会計業務M&A(企業の合併や買収)をする際に、相手企業の価値を判断する指標としてEBITDAがあります。日常の実務において、EBITDAという言葉を使うことは滅多にないかと思います…

EDINETとは?有価証券報告書等の開示書類がデータ化され検索も可能!
会計業務EDINETは、金融庁が公開している有価証券報告書などを開示閲覧するシステムです。 気になる企業の有価証券報告書の閲覧やダウンロードが簡単にでき、同業他社などの状況を知る目的などに…

会計監査っていつ何をやる?目的や担当者が準備すべき資料を解説
会計業務会計監査は、会社法の要件を満たした大会社が受ける監査のことです。 特に監査を行う人を会計監査人といいます。 では、会計監査はどのようなことを行うのでしょうか。そのために経理担当者は…
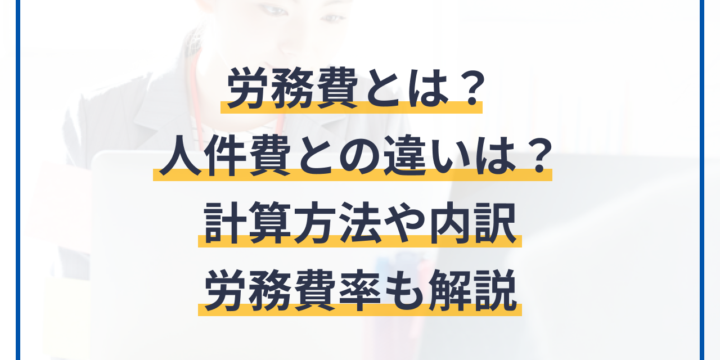
労務費の意味や人件費との違い、計算方法や内訳、労務費率まで解説
会計業務労務費は製品の製造と密接な関わりがあり、利益にも大きな影響を与える費用です。そのため、きちんと把握・管理した上で適切な値とする必要があります。 この記事では労務費について人件費との…

借入金とはどんな勘定科目?種類や仕訳まで解説
会計業務法人が事業を続けていくなかで、仕入や費用の支払いのや企業の成長への投資のためなど、さまざまな理由で金融機関などからお金を借りることがあります。融資を受けたお金のことを「借入金」とい…

営業キャッシュフローとは?見るべきポイントは?マイナスでも大丈夫?
会計業務「営業キャッシュフロー」とは、財務諸表の一種である「キャッシュフロー計算書」の重要な項目の1つです。企業のキャッシュフローのうち、「営業取引」から生じた現金収支を表します。 営業キ…

税引前当期純利益(税引前利益)とは?求め方や意味を解説
会計業務損益計算書には様々な段階での利益が計上されています。それでは税引前当期純利益とは、どのような利益を表しているのでしょうか。ここでは、税引前当期純利益の計算方法とその性格、損益計算書…

繰越欠損金とは?期限や税効果会計の適用方法・控除限度額
会計業務繰越欠損金という言葉だけは知っているけれど、実はどのようなものかわからないという方も多いと思います。今回は、青色申告の承認を受けている法人も、これから青色申告の承認を受ける法人も、…

経常利益とは?計算方法や他の利益との違い
会計業務経常利益とは、企業が通常行っているすべての業務で得た利益のことです。営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いて算出されます。投資家や金融機関が企業を評価する際にも重視される…

会計業務とは?業務内容と流れを解説 経理・財務との違いも
会計業務「会計業務」と、「経理」や「財務」との違いについて、なんとなく認識している人が多いのではないでしょうか。この記事では、その「なんとなく」を明確にわかりやすく解説します。会計業務の基…

固定比率とは?計算式や目安、改善方法までわかりやすく解説
会計業務「固定比率」とは、会社の長期的な支払能力を表す指標です。一般的な目安は「100%以下」になることが望ましいですが、業種によってはこの数字が参考にならない場合もあります。そこで今回は…
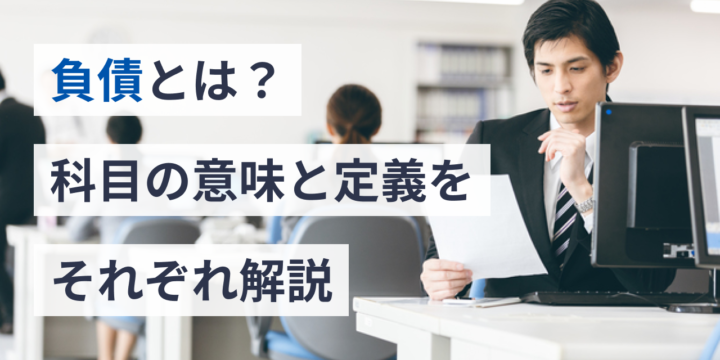
負債とは?科目の意味と定義をそれぞれ解説
会計業務一般的な負債の定義は、債権者に対する支払義務を表します。しかし、会計上、貸借対照表の貸方(右側)に表示される負債は異なる意味も含みます。会計上の負債とは何でしょうか。この記事では、…

繰延税金資産とは?取り崩しや回収可能性、仕訳について解説
会計業務繰延税金資産とは、将来の期間にわたって税金の負担が軽減されることを見込んで、会計上で計上される資産です。これは、損失や一時的な差異が発生した場合に、未来の税金の支払いを減らすための…

固定費と変動費の違いとは?求め方や削減方法を紹介!
会計業務「固定費」と「変動費」は、勘定科目とは異なった費用の分類方法です。この記事では、経営分析をするにあたって必要な考え方である「固定費」や「変動費」について、その求め方を解説します。 …

企業会計原則とは?基礎となる7つの一般原則や覚え方を解説
会計業務企業会計原則とは、会計時に守らなければならい基準のこと。公正な会計処理を行うために作られおり、決算書(財務諸表)の監査をするときにも使われています。この記事では基礎となる7つの一般…
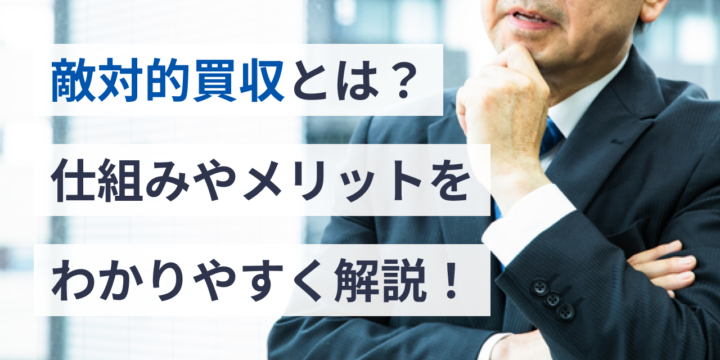
敵対的買収とは?M&A戦略における仕組みやメリットをわかりやすく解説!
会計業務M&Aのひとつに「敵対的買収」という方法があります。敵対的買収といえば、株式会社ニッポン放送の株式を巡る、株式会社ライブドア(当時)と株式会社フジテレビジョンによるやり取りが有名で…

不良債権とは?回収方法や会計処理の手順を解説
会計業務一般的に「不良債権」とは、銀行などの金融機関が行った融資について、経営悪化などを理由に回収できなくなった、あるいは回収の可能性が困難になったものを表します。しかし、回収しなければな…

【法人向け】会計ソフトの基本機能を一覧で解説!企業会計に必須
会計業務経理業務の効率化、資金繰りや経営戦略の上で、会計ソフトはほぼ必須なツールとなっています。法人成りや事業拡大にともない会計ソフトの導入を検討している、あるいは現在使っている会計ソフト…

当期純利益とは?計算式・求め方や意味をわかりやすく解説
会計業務会社の決算書や経理でよく使われる言葉の1つに「当期純利益」があります。当期純利益とは、簡単にいうと会社に残った最終的な利益のことです。 この記事では、当期純利益について計算方法や意…

営業利益とは?計算方法や経常利益との違いをわかりやすく解説
会計業務会社の利益を知ることができる決算書類として損益計算書があります。収益・費用・利益が記載されており、英語の「Profit and Loss Statement」を略して「P/L」とも…

売上高営業利益率とは?計算方法や業種別目安を解説
会計業務売上高に対する営業利益の割合を売上高営業利益率といいます。利益率の指標は他にもありますが、売上高営業利益率とはどのような違いがあるのでしょうか。売上高営業利益率の業種別目安、売上高…

損益分岐点をエクセルで作成!計算方法とグラフの作り方
会計業務会社の経営状況を分析する方法に、損益分岐点を利用する方法があります。損益分岐点は、どのくらいの売上を上げていかなければならないか、売上とコストのバランスを見るのに便利です。 この記…

会計ソフトの費用相場は?税理士に依頼する価格と比較!費用を安く抑える方法も!
会計業務確定申告にて「税理士には頼んだ方がいいの?」「会計ソフトは必要?」といった疑問がある方に向けて、「なるべくコスパの良い方法」を解説していきます。 結論から言うと、かかる時間も考慮し…

税効果会計とは?目的や手順、適用時の注意点を解説
会計業務税効果会計は、主に上場企業で用いられる会計手法で、会計上の収益・費用と税務上の益金・損金の認識時点が異なる場合に、法人税その他所得を課税とする税金を適切に期間配分することにより、損…

粉飾決算とはなぜ起こる?手法と見抜き方、罰則を解説
会計業務テレビや新聞で「粉飾決算」という言葉を見たことはないでしょうか。粉飾決算とは「赤字決算を不正な会計処理で黒字決算に見せかけること」を指します。黒字決算を赤字決算に見せかける「逆粉飾…

売上原価とは?計算方法や業種ごとの違いを解説
会計業務一般に「原価」と聞くとピンとくる人も、「売上原価」と聞くと原価との違いに考え込む場合があります。 損益計算書で売上の次に表示される売上原価は、財務情報として非常に重要性が高く、いわ…

自己資本とは?他人資本との違いをわかりやすく解説
会計業務自己資本とは、企業が安定した経営をするために必要な資金のうち、返済する必要がない資金の調達源泉を指します。自己資本を増やすことは、安定した会社経営を行なう上では欠かせない要素となり…

自己資本比率とは?計算方法や業種ごとの目安
会計業務企業を評価する観点として、「安全性」が挙げられます。企業の総資本に占める自己資本の割合を自己資本比率といいます。ここでは、貸借対照表から求める自己資本比率の見方や目安について解説し…

資金繰りを改善して資金ショートを防ぐための方法・考え方
会計業務皆さんは黒字倒産という言葉をご存じでしょうか?売上も好調で利益も出ている黒字企業が資金繰りの悪化により資金ショートを起こし倒産してしまうことを指します。たとえ黒字企業であっても運転…

借金返済の減額に活用できる補助金とは?資金繰りに困ったら会計事務所に相談しよう!
会計業務中小企業及び個人事業主(以下、中小企業)にとって、資金繰りは最も重要な経営課題の1つと言えます。 今回は、中小企業が借金返済の減額をしたい場合に、条件を満たせば、借金返済を減額する…

サッカー界の「脱税ベストイレブン」!? 大会の裏でちらつく“お金の疑惑”
会計業務6月14日に開幕した、4年に1度のサッカーの祭典。日本代表は、初戦で強豪コロンビアを相手に見事勝利を収め、セネガルにも善戦。残す対戦相手はすでに予選敗退が決まっているポーランドで、…

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を使った資金繰り対策を検討しよう
会計業務新型コロナウイルス感染症の拡大が止まりません。国や地方自治体は、相次いで外出規制の要請を行い、町はかつてのにぎわいを失いました。地域に密着した事業活動を展開する中小企業は大打撃を受…

法人税や社会保険料が1年猶予!厳しい今を乗り切るために
会計業務新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態宣言が発令され、テレワークへシフトする企業や、やむ無く営業を自粛している飲食店なども多いでしょう。今回は厳しい今を乗り切るために、新型コ…

コロナ支援金の「課税・非課税」 なぜ持続化給付金は課税対象なのか考えてみよう
会計業務新型コロナの感染拡大から約半年が経ちました。僕のもとには今もなお、持続化給付金や家賃支援給付金に関する質問が届きます。 すでに申請を済ませ、無事に入金されたという方も多いと思います…

建設業会計の特徴とは?仕訳や勘定科目の具体例を簡単に解説!
会計業務建設業は、商品やサービスを提供する一般的な業種と異なり、特殊な受注形態を持っています。そのため、会計処理にも特殊な処理や判断が求められ、複数の工事を請け負っているとさらに処理が煩雑…

【2020~2021年度】コロナによる固定資産税の猶予・減免 対象者や申請方法は?
会計業務毎年4~6月頃は「固定資産税の納期」と記憶している事業者も多いことでしょう。ところが、2020年は新型コロナウイルスにより経営難に陥り、納税どころではないという事業者が少なくありま…

会計ソフトのセキュリティが心配…安全性を徹底解説!
会計業務ほとんどの企業では、利便性の高さなどから会計ソフトを導入していることと思います。これまでは、パソコンにインストールして使用するインストール型、あるいは表計算ソフト(Excel)を使…

クラウド会計ソフトとは?コスト、特徴、メリット・デメリット等を解説
会計業務会計業務の効率化のために、クラウド型会計ソフトの導入を検討してみましょう。 クラウド型会計ソフトはデータがクラウドに保存されるため、場所を選ばずに作業ができます。また、常に最新の状…

美容室の会計業務を解説!おすすめの会計ソフトは?
会計業務「本業が忙しく会計業務に時間をかけたくない」「毎月の仕訳入力が面倒くさい」という方向けに、この記事はクラウド型会計ソフトで会計業務を効率化するための方法を解説しています。 結論から…

税理士とのやりとりを効率化!クラウド型会計ソフトでデータ共有
会計業務この記事では、顧問税理士とのやりとりを少しでも効率化したい、面倒なやりとりを無くしたい、データを共有したいという方に向けて、現状の問題点とクラウド型会計ソフトで解消できることを説明…

会計ソフトを導入しても税理士は不要にならない、その理由を解説
会計業務この記事では「確定申告が不安で税理士に依頼するかどうか悩んでいる方」、「税理士費用が高いと感じている方」に向け、会計ソフトを使えば税理士は不要になるかどうかを説明していきます。 帳…

<中小企業向け>新型コロナ給付金・助成金・補助金・資金繰りタイプ別の支援策まとめ
会計業務新型コロナウイルス感染症の急速な広がりを受けて、国は相次いで支援策を打ち出しています。ウイルスの拡大も急速であれば、支援策も急拡大しています。このため、中小企業にとっては、自社にと…
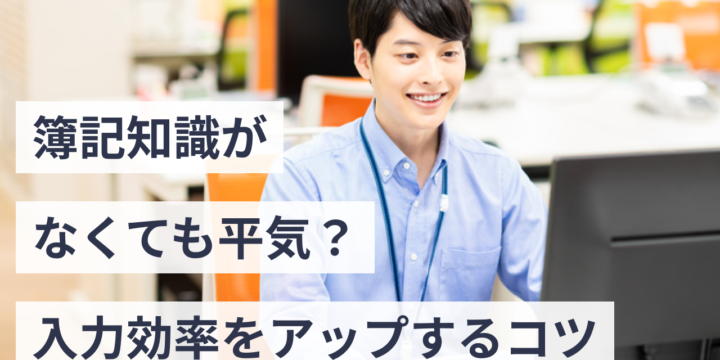
簿記知識がなくても平気?会計ソフトで作業の入力効率をアップするコツ
会計業務会計業務というのは、面倒で時間もかかるものです。ずっと手書きの帳簿やExcelの帳簿をつけている方は、「会計ソフトを導入した方が時間を節約できるのではないか?」と考えることも多いの…

会計ソフトは毎年バージョンアップが必要?クラウド型とインストール型を解説!
会計業務会計ソフトは、仕訳データを入力することで帳簿類など、必要な書類の多くを自動で作成してくれるので便利です。企業や個人事業主で、会計ソフトを利用されている方も多いでしょう。 それでは、…

テレワーク実現のための助成金とは?クラウドツール導入にも使える!
会計業務テレワークの導入にはある程度、導入費用がかかります。テレワークの導入にあたり費用面が障害となる企業様も少なくありません。また、テレワークは働き方を大きく変えることから、導入に不安を…
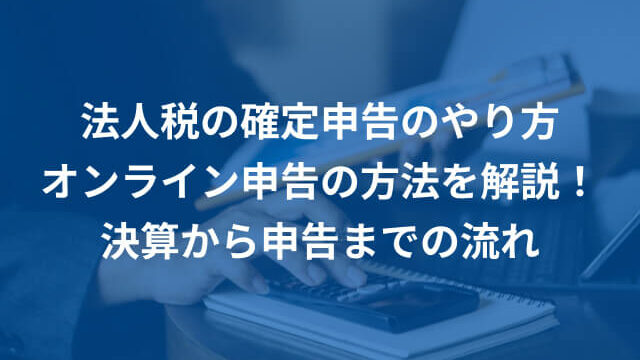
法人税の確定申告のやり方・オンライン申告の方法を解説!
会計業務法人の確定申告は、企業がその事業活動から得た所得に対して納めるべき税金を申告する義務のことを指します。企業は会社法に基づき、毎事業年度ごとに決算を行い、決算書を作成後、必要な承認を…

2024年版-会計ソフト一覧!比較ポイントやおすすめ製品も紹介
会計業務この記事では、代表的な会計ソフト(経理ソフト)や、会計ソフトの種類、主な機能、初心者向けの使い方などを解説します。 会計ソフト探しでよくある疑問・悩み 【法人の方】貸借対照表や損益…

会計ソフトの乗り換えはいつがベスト?互換性にも注意!
会計業務使用している会計ソフトの使用感、機能に限界を感じ、会計ソフトを乗り換えたいと感じている個人事業主、また経理担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。乗り換えの壁となるのが、互換…
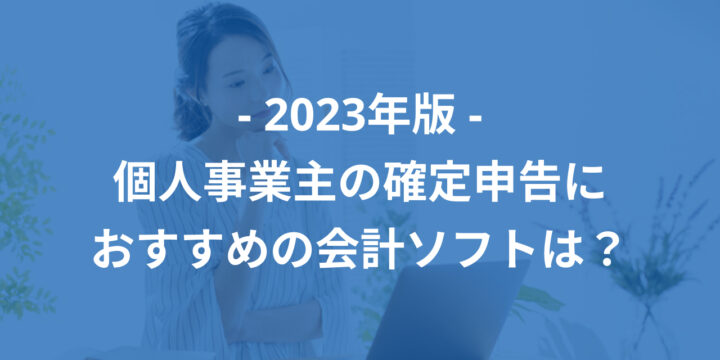
2023年版- 個人事業主の確定申告におすすめの会計ソフトは?比較ポイントを解説
会計業務個人事業主やフリーランスの方が会計ソフトを選ぶ際は、「確定申告機能付きのソフト」を選ぶことが一般的です。そのため、「個人事業主向けの会計ソフト」=「確定申告ソフト」として、理解して…

税務調査とは?流れや必要書類、対応方法の解説
会計業務事業を営む個人や法人、あるいは資産家や相続があった個人などに対して、税務署や国税庁による税務調査が行われることがあります。「怖い」「重いペナルティを科せられてしまう」というイメージ…

税務調査対象に選ばれにくい申告のポイント
会計業務事業を行っている法人や個人などの納税者を対象に、税務署や国税局による税務調査が行われることがあります。対象に選ばれると調査のための準備をしなくてはならないため、通常の業務への影響も…

消費税の課税事業者とは?対象となる取引や計算方法、必要な届出書とは?
会計業務消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。 事業者に負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービス、役務提供などの価格に含まれており、最終的に商品を消費、あるいは…

簡易課税制度とは?消費税額の計算方法やメリットデメリットの解説
会計業務簡易課税制度は、要件を満たせば「みなし仕入率」を使って消費税額を計算できる制度を指します。事務作業が楽になるメリットがある一方、還付が受けられない点や原則課税よりも納税額が増えるこ…
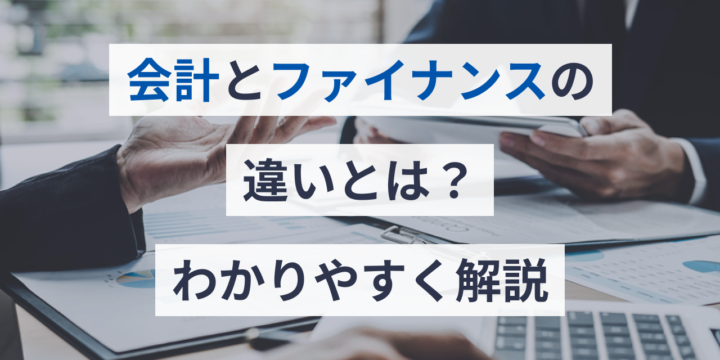
会計とファイナンスの違い
会計業務「会計」と「ファイナンス」は会社経営を行う上で極めて重要な要素ですが、両者の違いを明確にわかっていない人も多いのではないでしょうか。 そこで、この記事では会計とファイナンスの違いに…
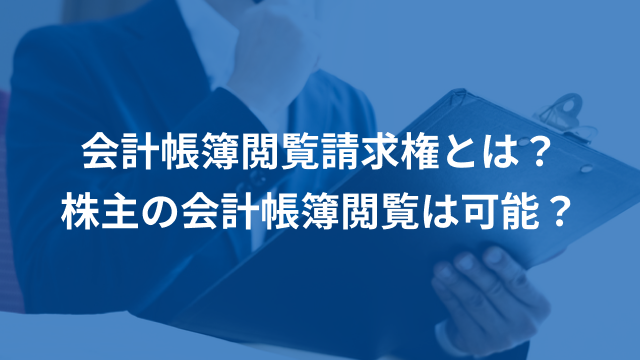
会計帳簿閲覧請求権とは?株主の会計帳簿閲覧は可能?
会計業務会計帳簿は経営状況を把握したり経営戦略を検討したりする際に活用され、会社にとって非常に重要な書類です。しかし、一定の条件を満たした株主は、会社のオーナーとして会社に会計帳簿の閲覧や…

社会保険・労働保険に関わる手続きが電子申請義務化! 準備はできていますか?
会計業務令和2年4月1日より、社会保険・労働保険に関わる手続きの一部において、電子申請で行うことが義務付けられます。まずは、一定規模以上の企業に限ってスタートを切ることになりますが、いずれ…

増税時に注意しておきたい! 消費税転嫁対策特別措置法まとめ
会計業務令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられました。消費税を払う側は増税により負担が大きくなり、また事業者間取引では、増税分を払いたくない買い手による買いたたき等が生じる可能性が…

勘定残高の確認方法と決算締めの流れ
会計業務期末になると資産の棚卸が必要だといわれますが、棚卸の方法は複数あり、どのように評価するのが適当なのかよくわからない場合も多いでしょう。 この記事では勘定残高の締め処理が必要となる背…

決算修正の方法と注意点 – 前年度修正損益は必ず申告
会計業務当年度の決算書を作成する際、すでに確定している過年度の決算書に誤りが見つかる場合があります。この記事では、決算修正(過年度修正)の具体的なやり方と、決算修正の結果によって生じる可能…

支払調書とは?書き方や提出義務、期限について解説
会計業務支払調書とは法定調書のひとつです。法定調書とは、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のことです。法定調書の種類は多く、全部で60種類あります。この記事では支払調書の概要…
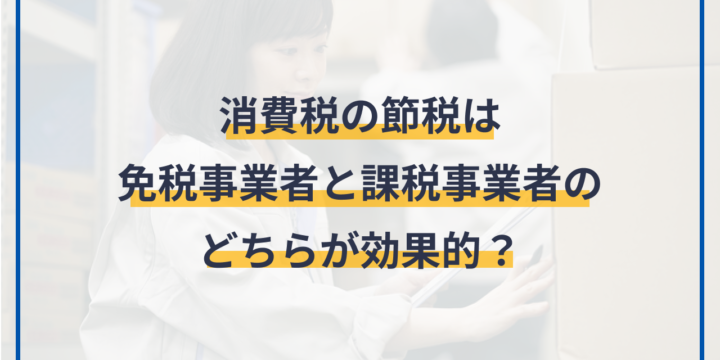
消費税の節税は免税事業者と課税事業者のどちらが効果的?
会計業務「消費税を節税する際に気を付けることは?」 「増税や軽減税率はなにか関係がある?」 「インボイス制度の免税事業者と課税事業者の違いは?」 この記事ではこんな疑問を持つ方に向けて、消…

消費税における「切り捨て」とは? 法人が行う消費税の計算・納税方法を解説
会計業務消費増税や軽減税率に対応した結果、消費税の端数が生じた経験はありませんか? 端数処理は、切り上げ、切り捨て、四捨五入などが考えられますが、どれが適切なのか判断しかねる方も多いと思い…
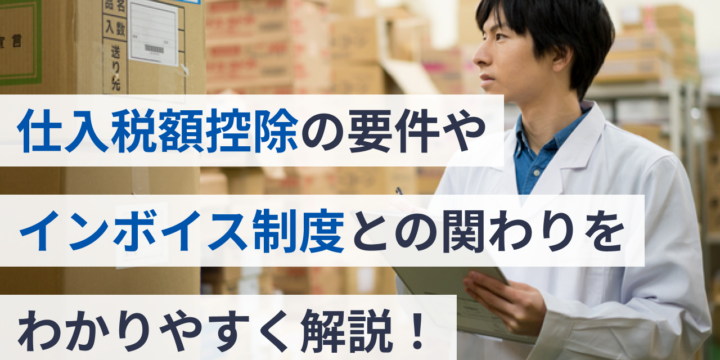
仕入税額控除とは?意味やインボイス制度での変更点をわかりやすく解説
会計業務仕入税額控除は、課税事業者にとって納税額を大きく左右するポイントです。 計算方法を間違えるとキャッシュフローが悪化し、経営に支障をきたす場合もありますので注意が必要です。 本記事で…

複式簿記を成り立ちから理解しよう
会計業務簿記の技術は何世紀にもわたって世界中で普及してきました。 一見すると複雑なようにも思えるこの技術が会計に役立つのはなぜなのでしょうか。 この記事では複式簿記と単式簿記の違いをはじめ…

管理会計における意思決定プロセス
会計業務経営上の意思決定採決を進めるには、管理会計によって作成されたデータが必要です。管理会計のデータに基づく意思決定は、根拠が明確なため結果分析も容易です。 本記事では、意思決定のプロセ…

連結決算とは?連結財務諸表の作成手順から連結修正まで解説!
会計業務企業グループ全体の経営状況を知るためには、連結貸借対照表や連結損益計算書といった連結財務諸表が必要です。これらは個別財務諸表を合わせることで作られますが、ただ合算するだけでは正確な…

ROEとROAとは?違いや目安、分析方法の解説
会計業務財務指標の中で、似ているものにROEとROAがあります。どちらも投資家が注目する指標で、企業分析に役立ちます。しかし、計算方法や分析の方法は異なるため、両者の概要と違いを理解してお…
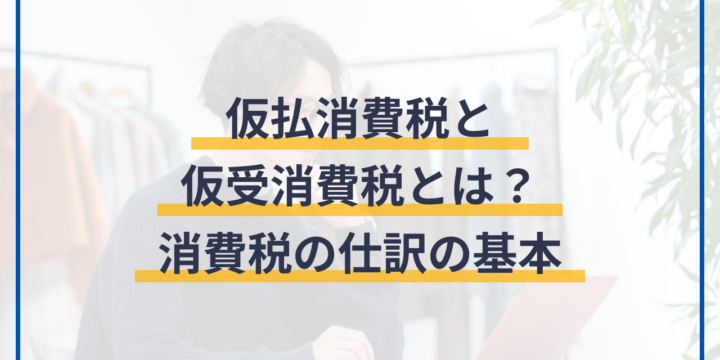
仮払消費税と仮受消費税とは?消費税の仕訳の基本
会計業務仮払消費税とは、経理処理を税抜方式でおこなっているときに使う勘定科目です。仕入れや経費にかかった消費税について用います。仮受消費税との違いや帳簿に記載するときの仕訳例、消費税に関す…

消費税の中間納付とは?計算方法や仕訳の解説
会計業務消費税の中間納付とは、課税期間の途中で分割して税金を納める制度です。前年の納税額が48万円を超える企業や法人が対象で、期限までに中間納付をしない場合は延滞税が生じます。 中間納付の…

免税事業者は消費税を請求していいのか?
会計業務間接税である消費税は、事業者が消費者から預かって納税するものです。ところで、事業者の中には消費税の納税を免除されている免税事業者があります。消費税の納税義務のない免税事業者は、消費…

消費税還付の仕組みと還付される条件まとめ
会計業務事業者は、商品やサービスを提供し消費者から消費税を受け取りますが、一方で事業者も仕入れをしたり備品を購入したりするので他の事業者に消費税を支払います。 消費税は、基本的に受け取った…

発生主義・現金主義・実現主義の違いは?青色申告での注意点も解説
会計業務企業会計原則に示される会計の基準は、会計処理をする上での基本的なルールです。 しかし、企業会計原則に直接的に「発生主義とは」「現金主義とは」などの記載があるわけではありません。 こ…

会計ソフトの摘要欄に書くべき内容と活用方法
会計業務標準的な会計ソフトには、借方と貸方に仕訳を入力できるよう、勘定科目や補助科目、金額の欄が設けられているほか、取引内容を記入できるよう摘要欄が設けられています。この「摘要欄」にはどの…

資金繰り表とは?作り方をわかりやすく解説
会計業務健全な会社経営を行っていくためには、「資金繰り表」を適切に作成することが重要です。資金繰り表の必要性は認識しているものの、具体的にどのように作成すればよいか、わからない方も多いので…

貸借対照表の書き方を簡単に解説!エクセル作成も対応
会計業務会社は決算の際に「貸借対照表」を税務署に提出します。 この「貸借対照表」には決算日の会社の財政状態が表されており、記載事項には会社の純資産(資本)、そして、それを導き出すための資産…

キャッシュフロー計算書の作り方!直接法と間接法どちらが良い?
会計業務キャッシュフロー計算書(C/F)を作成するには、財務諸表の収集・営業活動によるキャッシュフローの計算・ 投資活動によるキャッシュフローの計算・財務活動によるキャッシュフローの計算な…

現金出納帳とは?会計ソフトで作れる?書き方の基礎知識をわかりやすく解説
会計業務現金取引はほぼ毎日のように行われるため、現金の管理が重要になってきます。 現金出納帳は、家計簿のようにカンタンに作成することができ、現金の管理に非常に役立ちます。 この記事では現金…

出納簿ってどんなもの?帳簿の役割と書き方まとめ
会計業務出納簿とは事業活動で発生した取引について、勘定科目ごとに記録した帳簿のことです。科目ごとに帳簿が異なり、「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」などがあります。 それぞれの…

中小企業におすすめ会計ソフトの選び方・種類と比較方法
会計業務初めて会計ソフトを導入する場合や、今まで使用していた会計ソフトを更改したい場合、どの会計ソフトを選べばいいのかについて悩んでいませんか? 新たに会計システムの導入を検討する際はまず…

法定調書とは?知っておきたい法定調書の基礎知識
会計業務「法定調書」と聞いてどのようなものをイメージするでしょうか。 法律に定められた書面だということは言葉からわかると思いますが、どのような書面なのかといわれるとピンとこない方も多いはず…

総勘定元帳とは?作成する目的やエクセルでの作り方を解説
会計業務総勘定元帳とは、企業が行うすべての取引について勘定科目ごとに分けて管理するための帳簿です。 総勘定元帳とは何のためにあるのか、勘定ごとに記帳することで何がわかるのかなどを明らかにし…

法人の決算準備のためにしておくべきことまとめ
会計業務年度末が近づいてくると、やはり気になる決算処理。ただでさえ忙しい年度末に、決算手続きをして確定申告に納税…と毎年頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。 法人決算のために準備…

決算月はいつにする?決算月の決め方とポイント
会計業務日本では決算月を3月と定めている会社が多いですが、これは国や市区町村の会計年度が4月から3月までであることにならったものです。会社の決算月について、何月にしなければならないという決…

財務分析の方法・やり方を解説!必要指標とそれぞれの計算方法
会計業務財務分析とは、決算書などを見ながら、企業の現状や問題点を把握することです。企業の現状や問題点を把握することで、改善点がわかり、今後の経営戦略を立てるのに役立ちます。 財務分析は、企…
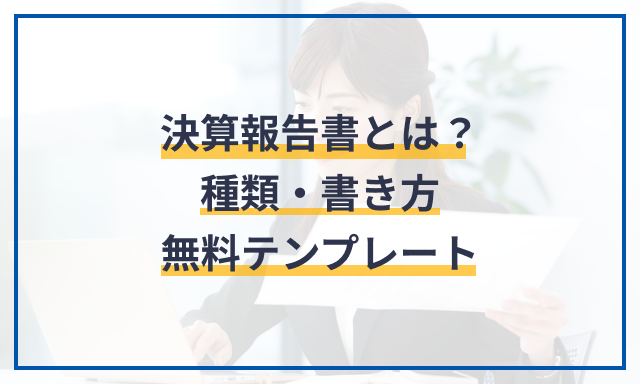
決算報告書の種類は?書き方・無料テンプレート
会計業務決算報告書とは、企業が年度末に作成する財務状況や経営成績をまとめた書類で、法人税法、会社法、金融商品取引法などの法律によって作成が義務付けられています。 1年間の事業年度が終わると…

2024年版 – 損益計算書と貸借対照表の違いと見方
会計業務損益計算書と貸借対照表は、決算において作成を求められる重要な財務諸表です。そのためには、2つの帳票の関係を正しく理解し、作成することが重要です。また、財務諸表をはじめとする帳簿や書…

損益計算書(P/L)とは?項目別の見方やポイント一覧・事例をわかりやすく解説
会計業務損益計算書(P/L)は、1年間の経営成績を示す決算書であり、構成要素を財務分析に利用するなど、経営戦略を立てる上で重要な書類です。損益計算書は、会社の経営状況を把握する決算書の中で…

予実管理とは?目的、予算管理の進め方、エクセルでの作成方法のポイント
会計業務企業経営にぜひ役立てたいプロセスの一つに予実管理があげられます。予実管理とは、経営管理のための手法の一つで、あらかじめ設定した予算と実際の業績を比べて原因を分析・改善していく予算管…
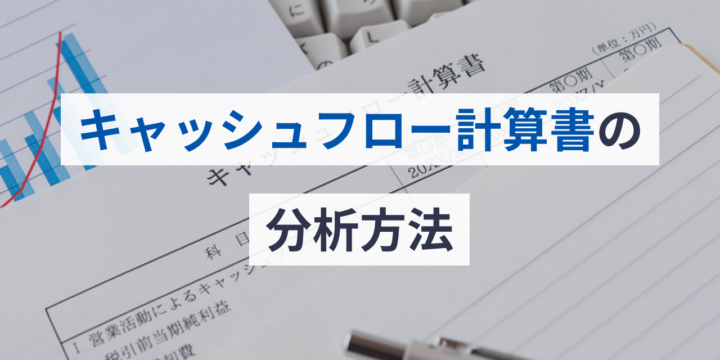
キャッシュフロー計算書の分析方法
会計業務手元にキャッシュがなければ黒字でも倒産する可能性があるため、会社にとってキャッシュの状況を把握することは非常に重要です。この記事ではキャッシュフロー計算書の概念や見方、キャッシュフ…

キャッシュフローとは?キャッシュフロー計算書(C/F)の読み方を解説
会計業務キャッシュフロー(C/F)は、一定期間における企業や個人の現金および現金同等物の流入と流出の差額のことです。 企業にとって資金の状況を把握するのは非常に重要です。適切に資金の状況が…

仕訳帳とは?書き方や記入例、帳簿付けの流れを解説
会計業務仕訳は日々の事業活動を記録しておくために欠かせない、大切な作業です。仕訳帳に記入することで、ひとつひとつの取引によって生じる勘定科目の増減について後からでもチェック可能にできます。…
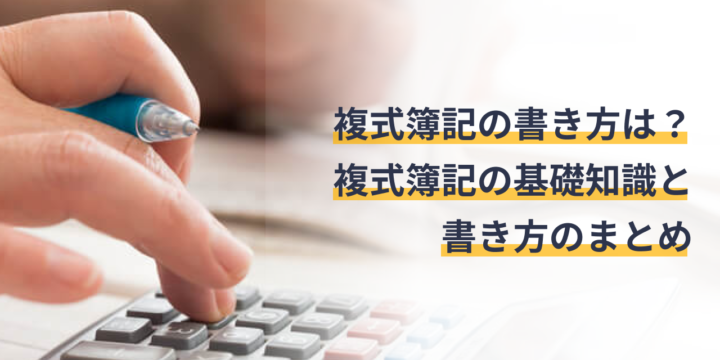
複式簿記の書き方を正しく理解していますか?複式簿記の基礎知識と書き方まとめ
会計業務複式簿記の書き方、ご存知ですか? 個人事業主はもちろん、たとえ小規模にしても経営者であれば、また、社会人であれば、複式簿記の書き方の基本は知っておきたいものです。 ここでは、複式簿…

管理会計とは?財務会計の違いから企業会計を解説
会計業務会計とは、経済活動による収支を認識して記録し、利害関係者に対して報告をするまでの行為全般を指します。会計は管理会計と財務会計の2つに大きく区分されており、会計の目的に応じて処理方法…

会計帳簿とは?保存期間・書き方・エクセルテンプレ13種類
会計業務会計帳簿とは、企業が行う経済活動が取引として漏れなく記録される必要があり、期末に決算書を作るために必要になる、大切なものです。 会計帳簿には主要簿と補助簿の2つの種類があります。 …
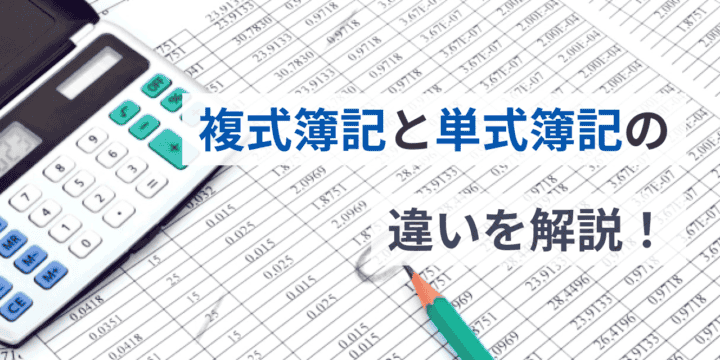
複式簿記と単式簿記の違いを解説!
会計業務今回は簿記について説明します。簿記には「単式簿記」と「複式簿記」があります。 会計や簿記は難しいところもありますが、知っておくと業績を把握する力や決算書を読み取る力が上がります。ぜ…

【これは軽減税率?】ぶどう狩りや梨狩り。その場で食べると軽減税率の対象外ってほんと?
会計業務2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…
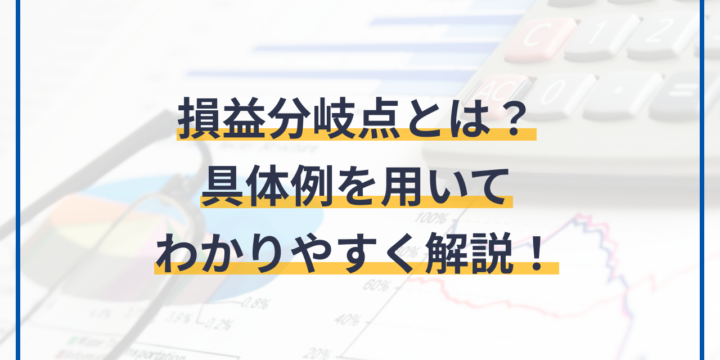
損益分岐点とは?具体例でわかる計算方法
会計業務経営をするうえで、利益を出すためにはたくさん販売することが基本になりますが、どれくらい販売すれば黒字になるのか、その数値目標を持つことはとても重要なことです。今回は、黒字化のために…

帳簿とは?主要簿・補助簿の種類と意味は?書き方や簡単な記帳方法をわかりやすく解説!
会計業務帳簿とは 帳簿とは、事業の取引や資産や負債、お金の流れなどを記録した帳面や台帳のことです。厳密にいうと、会社の経理などで作成される会計帳簿(会計簿)のことですが、一般的に帳簿と呼ば…

試算表とは?作り方・無料エクセルテンプレート
会計業務試算表(T/B :trial balance)は、月次・年次など会計期間の区切りで、総勘定元帳(General Ledger)に記載されている全ての勘定科目の残高を一覧表にまとめた…

消耗品費と雑費の使い分けは?仕訳の方法や注意点をわかりやすく解説
会計業務消耗品費と雑費の違いをご存じでしょうか。 実は、それぞれの科目には明確な定義や区別がないため、使い分けようとすると感覚的な判断になりがちです。 そこでこの記事では、消耗品費と雑費の…

法定実効税率とは?計算方法をわかりやすく解説
会計業務法定実効税率とは所得に対して課税される法人税、住民税、事業税の表面税率を使って所定の方法で計算される総合的な税率のことを指します。表面税率(もしくは合計税率)とは、法律が定めている…

国際会計基準(IFRS)とは?日本の会計基準との違いや導入メリット
会計業務現在、欧州連合(EU)では、連結財務諸表における国際会計基準(IFRS/International Financial Reporting Standards)の適用を上場企業に義…

【これは軽減税率?】バーガーとドリンクのセット。ドリンクだけ店内飲食する場合、消費税はどうなる?
会計業務2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

【これは軽減税率?】キッチンカーで買った食事。近くのベンチで食べるなら消費税どうなる?
会計業務2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

損益分岐点分析・CVP分析とは?計算方法や経営への活用法をわかりやすく解説
会計業務損益分岐点分析(CVP分析)で求める指標は、財務分析の中でも基本的な指標の1つです。事業活動を行う上で、損益分岐点の考え方を知り、損益分岐点を分析する力を付けることは非常に重要です…
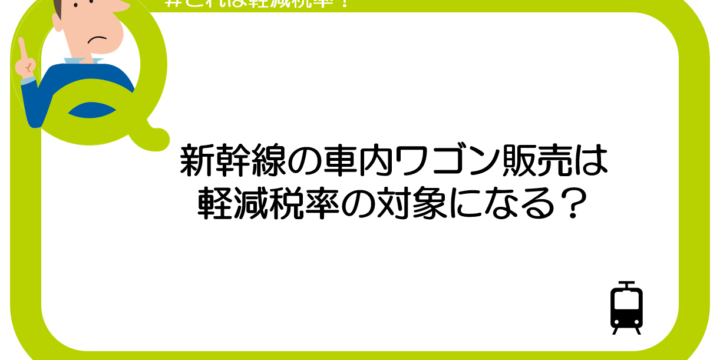
【これは軽減税率?】新幹線の車内ワゴン販売は軽減税率の対象になる?
会計業務2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

これでわかる「キャッシュレス・ポイント還元」の利用方法から会計処理まで
会計業務2019年10月1日の消費税率引き上げと同時に、キャッシュレス決済を行うと最大5%還元される「キャッシュレス・ポイント還元事業」が始まりました。キャッシュレス還元を活用すれば、増税…

【これは軽減税率?】会議室までサンドイッチ配達。消費税8%と10%の分かれ道は「給仕」
会計業務2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

消費税増税にともなうキャッシュレス決済でポイント還元!活用するには?
会計業務2019年10月1日より、消費税率が2%引き上げられ、10%になります。この消費税増税によって懸念されるのが、需要の変動。こうした需要変動を抑制するために、消費税増税とともに実施予…

【これは軽減税率?】「宅配ピザ」と「UberEatsでピザ配達」で消費税は変わる?
会計業務2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

【これは軽減税率?】医薬部外品の栄養ドリンクは消費税10%…トクホや健康食品は?
会計業務2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

【これは軽減税率?】レストランで残った食事。パックに詰めて持ち帰ったら?
会計業務2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…

融資とファクタリングは何が違う?マネフォの資金調達サービス担当者に聞いた
会計業務こんにちは、Money Forward Bizpedia編集部です。いきなりですが、マネーフォワードにはマネーフォワードファイン株式会社、MF KESSAI株式会社というグループ会…

消費税引き上げに伴う経過措置とは?
会計業務平成31年(2019年)10月1日より消費税が8%から10%に上がりますが、消費税引き上げ前に契約した商品の引き渡しが消費税引き上げ後に行われた場合、引き上げ前の税率(8%)と引き…
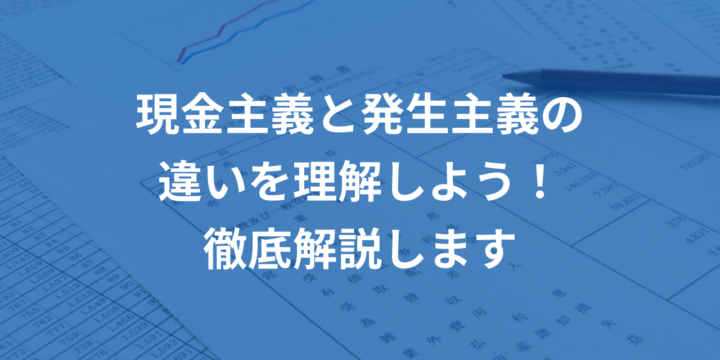
現金主義と発生主義の違いを理解しよう
会計業務企業の基本的な会計ルールである企業会計原則には、「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない」と示さ…

飲食業以外の事業者も確認すべき「軽減税率の3つのポイント」
会計業務軽減税率が導入され、現在では消費税率が8%と10%の2種類になっています。軽減税率8%の対象が主に「飲食料品」ということもあり、飲食店やスーパー、コンビニなどの支払いで2つの税率が…

持ち帰りとイートインスペース利用、軽減税率の適用基準や罰則は?
会計業務2019年10月、消費税が10%に上がるにともない、生活に密接にかかわる飲食物については、そのほとんどが現行の消費税のまま8%に据え置かれる、軽減税率の措置が取られることが決まって…

販売者は気をつけたい!軽減税率の値引きの話
会計業務2019年10月1日より、消費税が8%から10%へと引き上げられます。 これと同時に軽減税率が導入され、一部の商品は8%で据え置きとなります。そのため事業者は、取り扱う商品によって…

通販 ・ECサイトは軽減税率にどう対策するべき?
会計業務消費税増税にともなう軽減税率の対策は、通販・ECサイトも例外ではありません。顧客とその場で直接取引をする実店舗での対策とは異なってきますが、異なる2つの消費税で運用しなければならな…

食品を含んだ一体資産は軽減税率の対象になる?判断基準は?
会計業務2019年10月、8%から10%への消費税引き上げにともない、一部を現行の消費税にとどめる軽減税率の措置が実施されます。 一定の条件を満たした飲食物を中心としたものの譲渡(顧客への…

売上総利益(粗利益)とは?計算方法や他の利益との違い
会計業務会社の経営状態や財務状況を見るために使う「財務諸表(決算書)」。その中でも「損益計算書(PL)」は会社の経営成績を示し、経営判断の重要な指標に用いられます。会計期間における費用と収…

起業したらいつ税理士をつける? 契約タイミングの目安は「1年間の売上」
会計業務起業した方から、「どのタイミングで税理士をつけたらいいですか?」と質問されることがあります。その質問に答える前に、税理士紹介サービスを手掛ける私がまずお伝えしているのは「税理士をつ…

固定資産税はどう抑える?「オフィス形態別」に負担を比較解説
会計業務春はなにかと出費が多い時期です。5月以降はさらに追い打ちをかけるように固定資産税や自動車税などの納税ラッシュが始まります。今回は、経営者なら知っておきたいオフィスの固定資産税に着目…

「親身な税理士」を見極めるポイント。報酬の安さで決めるのはハイリスク
会計業務確定申告を依頼したい方、税金で損したくない方、今の税理士に不満があり別の税理士に乗り換えたい方――税理士を探す理由は人それぞれですが、みなさん口を揃えて「親身に相談に乗ってくれる税…

「税理士が何も提案しない」当然の理由 上手に付き合うコツは?
会計業務社長と話をしていると、「うちの税理士は何も提案してくれない……」という不満を聞くことがあります。こう聞くと「怠慢な税理士がいるんだなぁ」と思う方もいるかしれませんが、本当にそう言え…

【解説】2019年度税制改正大綱のポイントは「車と住宅」 仮想通貨にも初めて言及
会計業務自民、公明両党が12月14日、2019年度(平成31年度)の税制改正大綱を発表しました。今回の改正は、2019年10月の消費税率10%への引き上げにともなう駆け込み需要と反動減を抑…

“良い税理士”を見極めるたった一つのポイント 「近所」「紹介」の落とし穴も
会計業務この記事の読者の中に、税理士を探している方がいるかもしれません。中には知人の紹介やネット検索を頼りに検討している方もいるかもしれないですね。 一昔前と変わり、今はターゲットや専門分…

日産を「年収1000万円」の家計に例えたら分かる、監査法人がゴーン氏不正を見逃した理由
会計業務カルロス・ゴーン氏の逮捕劇から10日が経ちました。日産自動車の有価証券報告書に、自身の報酬を約50億円過少に記載した疑いが持たれているゴーン氏。世界を股に掛けるカリスマ経営者のスキ…

日大生逮捕のサークル、納税しなくていいの? 「毎月会費3万円」で荒稼ぎ
会計業務日本大学の男子学生2人がサークル仲間からバッグを奪ったとして、強盗容疑で逮捕された事件。報道各社は、彼らが幹部を務めるインカレイベントサークルの悪質な運営実態を次々と報じています。…

消費税の軽減税率 調味料なのに「みりんは適用対象外」なワケ
会計業務2019年10月1日、いよいよ消費税が10%に引き上げられます。 消費税は所得の多さに関係なく、すべての人に等しくかかる税金です。そのため低所得者の負担増の懸念から、増税と同時に、…

大坂なおみ選手の活躍で知りたい、日本とは全然違う「アメリカ・ファーストな税金事情」
会計業務2018年9月の全米オープンテニスにおいて、日本人初のグランドスラムを達成した大坂なおみ選手。日本への凱旋帰国後のトーナメントでも大活躍ですが、税金はどのようになっているのでしょう…

〇億円超えは当たり前!? すごい収益力「夏の甲子園」の税事情に迫る
会計業務第100回の記念大会である夏の甲子園が、8月21日に大阪桐蔭(北大阪)の2回目の春夏連覇で感動のフィナーレを迎えました。特に今年は異常気象とも言える酷暑の中、悲願達成へ東北勢の期待…

謎多き「お祭り屋台」の税事情 納税義務はあるの?
会計業務東京の靖国神社で7月13日~16日の間、夏の訪れを告げるお祭り「第72回みたままつり」が開催されました。 みたままつりと言えば、近年話題になったのが「屋台の出店中止」。一部参拝客の…

創業期の事業を「早く」「大きく」する『財務』のチカラ 6.資金調達力の育て方
会計業務起業家は、「財務」を知ることで、もっと事業を発展させることができます。この連載では、起業家が創業からもつべき「財務」の視点・考え方について、シリーズでお伝えしていきます。 第4回、…

役員報酬ランキング1位の外国人に「破格退職金」 日本で高額退職金が少ないワケ
会計業務東京商工リサーチが5月29日、上場企業の役員報酬額のランキングを発表しました。最高額は、ソフトバンクグループのニケシュ・アローラ元副社長で、103億4,600万円。巨額報酬もさるこ…

元TOKIO山口達也さんの降板続々… 芸能人の不祥事、賠償金の会計処理は?
会計業務ジャニーズ事務所が5月6日、TOKIOのメンバー山口達也さんとの契約解除を発表しました。急展開に悲鳴をあげているのが、緊急対応を迫られているテレビ局やCMスポンサー企業です。一部ス…

税理士に聞く、2018年度の税制改正で押さえるべきポイント
会計業務政府は2017年12月、2018年度税制改正大綱を閣議決定しました。今回の税制改正にともない、個人では基礎控除や給与所得控除等の見直し、法人では賃上げした場合の法人税の税額控除の改…

月間100万PVの人気ブロガー「ヒトデ」が税理士から法人化を学ぶ!
会計業務今年も年末調整の季節がやってきました。 個人事業主の方なら、誰もが「税金ってこんなに高いのか!」と驚いた経験があるのではないでしょうか。 今回のスペシャルゲスト、月間100万PVを…

創立費と開業費の会計処理について
会計業務会社の創立と開業準備にかかる費用である創立費と開業費は、繰延資産として資産計上でき、償却方法としてはいつでも必要経費として償却することができる、任意償却が適用されます。創立費、開業…
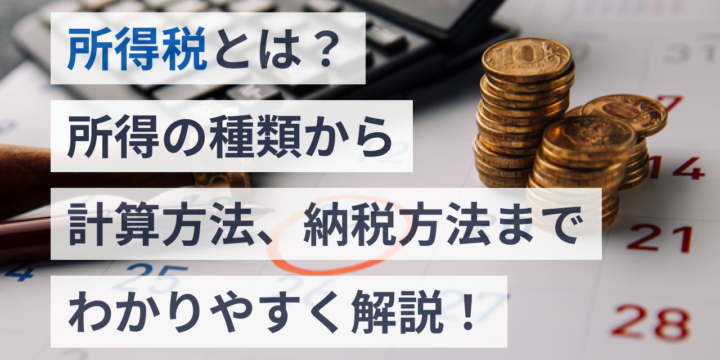
所得税とは?所得の種類から計算方法、納税方法までわかりやすく解説!
会計業務会社からもらった給料や、自分の事業で稼いだお金、アパートの家賃収入など、収入全般に対しては所得税が課税されます。所得税は収入の種類によって税率や計算方法が異なるため、収入の種類が多…

私的整理における主な3つの借金返済の減額手法ってどんなもの?
会計業務個人事業主や中小企業が借金の返済に困り、再建する場合において、法的整理は民事再生や会社更生などの裁判所が関与した上で法律に基づいて行われる手続きであり、私的整理はそれ以外の手続きを…

借金返済の減額を金融機関に相談する際の3つのポイント
会計業務事業用の資金として、金融機関から借金(借入れ)をしている法人や個人事業主の方も多いと思います。借金をした時のスケジュールどおり返済している場合は問題になりませんが、経営には不測の事…

ヘッジ会計でリスク回避!メリットと仕組みを解説
会計業務企業としてリスクの少ない投資活動や安定した資産管理を望むなら、ヘッジ会計について知っておきましょう。 ここでは、企業の会計・財務担当者が知っておきたいヘッジ会計の概要や適用条件など…

法人事業概況説明書の提出は義務!記載内容と書き方を解説
会計業務法人は確定申告の際に、確定申告書とは別にいくつかの添付書類を提出しなくてはなりません。例えば貸借対照表や損益計算書などの財務諸表、勘定科目内訳明細書などです。 この添付書類の中に「…

原価計算とは?計算方法や目的、種類などの基本知識と仕訳例を解説!
会計業務原価計算は難しいという先入観はありませんか?一度にあまり多くの計算方法を学ぼうとせず、基礎的なところから始めましょう。ビジネスの最前線の問題も、基本的なしくみの理解なしでは語れませ…

原価管理は重要? 原価管理の目的と経営改善への活用方法とは
会計業務これまでは、製造業や飲食店といった特定の業種で行われてきた原価管理ですが、業種にかかわらず原価管理を活用する企業が増えてきました。 そこで今回は、原価管理を行うことの目的やその活用…

固定資産税を滞納したらいったいどうなる?
会計業務固定資産税は土地家屋を所有している人が、その土地・家屋の価格をもとに算定した税額を納める税金です。滞納した場合は、延滞金がかかります。さらに、悪質な場合は財産を差し押さえられること…

課税証明書とは?課税証明等請求書の書き方と役所での発行・取得方法
会計業務課税証明書は住民税額を証明するための書類で、そこから転じて所得の証明などに利用される書類です。 そのため課税証明書が「非課税証明書」「所得証明書」という書類の役割も兼ねている自治体…

ものづくりを行う中小企業が抱える課題とは?ものづくり企業への支援策を紹介
会計業務戦後の混乱期以降から現在に至るまで日本経済の基盤を支え続けてきたのが、自社の技術を突き詰めて新しい製品を開発、製造している「ものづくり企業」です。ものづくり企業には大企業も存在して…

中小企業でも社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければいけない?
会計業務マイナンバーの導入などをはじめとして、さまざまな取り組みが見られる社会保険ですが、中小企業の中には未加入のところも見られます。 今回は、中小企業でも社会保険に加入する必要があるのか…

中小企業のための安心できる取引先とは?年商だけで信用してはいけない!?
会計業務メディアで企業の規模を表す際によく用いられる「年商」ですが、これが何を意味するかはご存知でしょうか。 年商が1億円を超えているからといって、必ずしもその企業がそれだけの利益をあげて…

税理士資格はどう役に立つ?試験の概要と仕事内容
会計業務会社員として働いていても税理士資格の取得は大幅なスキルアップにつながり、独立することも可能です。ここではこの税理士資格を取得するための試験の概要と、試験を受けるために必要な資格、そ…
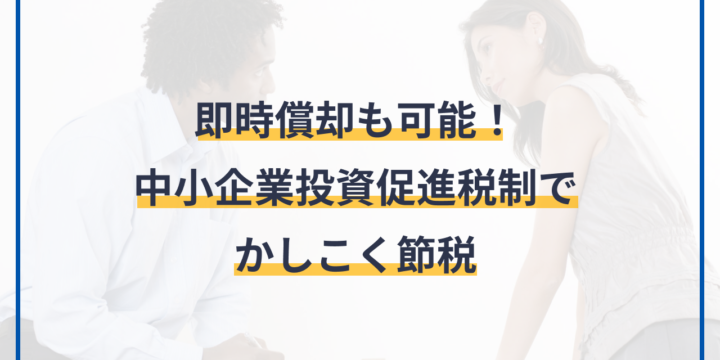
即時償却も可能!中小企業投資促進税制でかしこく節税
会計業務「中小企業投資促進税制」という制度をご存知ですか?この制度は、設備投資をおこなう中小企業の利益率アップを図るために導入された減税策です。条件が合えば、より高い節税効果が期待できる即…

中小企業の役員報酬についての税務上のポイント
会計業務中小企業の役員報酬は、適正な額にすることが大切です。少なすぎると役員のやる気がそがれる一方、多すぎると税務上の経費に算入できずに法人税を多く支払うことになってしまいます。 この記事…

中小企業の事業承継をM&Aで行う際の実務フローと注意点
会計業務中小企業の経営者がリタイアし、事業承継を行う際には、これまでは経営者の子供や経営の中枢を担ってきた社員が事業を継ぐ形で行うことが一般的でした。 しかし、日本全体の景気の低迷などによ…

中小企業の課題とは?課題解決のための支援策を解説
会計業務中小企業は、どのような会社であっても何かしらの経営課題を抱えています。実際に中小企業を経営している方は、自社の課題に対して対応することが精一杯であり、ほかの中小企業の現状について見…

中小企業は資本金をいくらに設定したら良いのか
会計業務会社を設立する際に決定する資本金ですが、いくらに設定するべきなのでしょうか。 そもそも資本金とは何かということから、中小企業としての税的な優遇を受けるための基準となる資本金の額など…

納税充当金とは?仕訳から確定申告書での表記方法まで解説
会計業務経理に携わる方は、法人税の申告書について、会計と税務の差異を表す法人税の確定申告書の「別表4」や、納税状況を表す法人税の確定申告書の「別表5-2」については、意味がわかるようにして…

中小企業の経営戦略を立案する基本フロー
会計業務経営資源に限りのある中小企業が市場で勝ち抜くには、経営戦略を立てることが大切です。 ここでは、中小企業が経営戦略を立案し実行するために必要な環境分析や、具体的な戦術を策定する基本フ…

中小企業の税制上の優遇措置
会計業務中小企業は法人税の税率が大法人に比べて軽減されていることは、すでにご存じのことでしょう。これ以外にも、中小企業に対するさまざまな税制上の優遇措置があります。 この記事では、中小企業…

中小企業で退職金を準備する方法
会計業務退職金を支払うためには、多額の資金を準備しなければなりません。そのため、中小企業では単独で退職金制度をもつことが難しいものです。 そこで、中小企業の従業員や小規模企業の経営者の退職…

仕入高
会計業務仕入高とは、事業で販売する商品や、その商品を作るための原材料を仕入れるための費用を計上するために利用します。 今回は、仕入高を計上する際に気をつけなければいけないことや、特に間違い…

リース債務
会計業務「リース債務」は、リースした物品に対するリース料などのことを指す勘定科目です。リースを行った際には、このリース債務をはじめとしたリース会計と呼ばれる処理を行う必要があり、その際に気…

中小企業の人手不足にどう対応する?経営者が知っておくべき3つの道
会計業務景気回復に伴って浮き彫りになってきた中小企業の人手不足問題。 ここではその現状を解説するとともに、企業が取るべき3つの対応策、すなわち「攻め」の採用活動、女性雇用促進、外国人雇用促…

数字で読み解く! 日本の中小企業の状態とは
会計業務経済白書などの調査から判明した実際の数字から、これからの日本経済を引っ張っていく中小企業の実情を読み解いていきます。 中小企業の数は? みなさんは、日本にはどれほどの中小企業が存在…

中小企業向けの会計ルールを知っておこう
会計業務中小企業の場合、決算は法人税の申告や会社法の規定で仕方なく行うことが多いものですが、経営管理や対外的な信用の面からも、一定のルールに則った決算を行うことは大切です。 この記事では、…
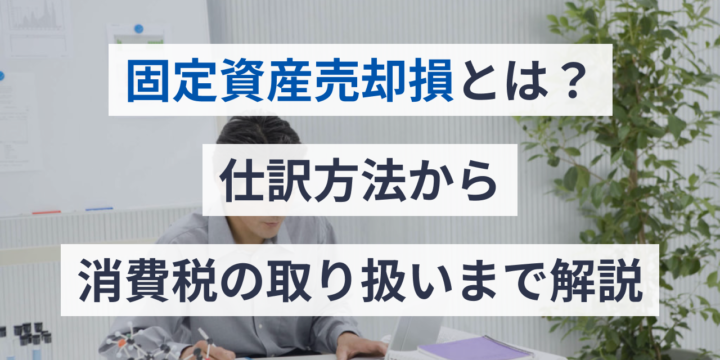
固定資産売却損とは?仕訳方法から消費税の取り扱いまで解説
会計業務固定資産を売却した際に発生することがある固定資産売却損。どのようなケースで発生し、会計処理はどのように行えば良いのでしょうか。 ここでは、固定資産売却損の基本的な概要や仕訳方法につ…

販売手数料とは?仕訳の区分と消費税の計算に注意!
会計業務同じ費用であっても、性質によって処理方法が異なる勘定科目は押さえておく必要があります。特に販売手数料については、処理方法を誤ってしまうと法人税や消費税に影響がでてしまいます。 今回…

退職給与引当金とは?損益算入は廃止!具体例と計算方法
会計業務今回は、退職給与引当金の意味から具体的な計算方法、さらには税務的にはどのように取扱われているのかを紹介していきます。 退職給与引当金を計上する意味は? まずは、退職給与引当金の意味…

地代家賃とは?消費税法上の取り扱い・仕訳や計算方法も解説
会計業務地代家賃はその名のとおり「地代」「家賃」を管理するための勘定科目ですが、一見すると地代家賃に分類できそうでも、実は地代家賃ではないというケースもあります。 ここではそのような間違い…

権利金とは?計算方法や仕訳方法、税務上の取り扱いをわかりやすく解説
会計業務新しい事務所や店舗などを賃貸借する場合に、敷金や保証金、さらには仲介手数料など、様々な支払い項目が発生します。その中でも特に経理として注意しておくべきなのは、権利金の処理方法ですね…

特別償却準備金とは?メリットから仕訳方式まで解説!
会計業務特別償却準備金は特別償却をするために積み立てるお金を指します。これを理解するためには、そもそも「特別償却とはどんなものか」を理解する必要があります。 ここでは特別償却の定義や会計上…

保険積立金とは?保険別に会計処理を解説!
会計業務保険積立金とは、生命保険や損害保険の保険料のうち、満期返戻金など貯蓄性がある部分の保険料を計上するための勘定科目です。貸借対照表の資産の部の投資その他資産として表示されます。 保険…

損害保険料とは?契約期間ごとの仕訳・積立保険の計上方法を解説
会計業務損害保険料勘定は、主に商品や事務所などの事業用資産に対する損害保険料を計上するための勘定科目です。損益計算書の販売管理費の内訳として表示されます。 損害保険料とは 損害保険は、火災…

リース料とは?リース取引のメリット・デメリットを解説!
会計業務購入とリースの違いなどからリース取引のメリット・デメリットについて、あるいは具体的なリース料の処理方法についてご紹介していきます。 リース取引とは?メリット・デメリットを紹介 まず…

雑給とは?給与との違いは?定義の解説から仕訳例まで紹介
会計業務雑給という勘定科目は、それ自体の理解は難しくありません。しかしこれを理解するためには「給与」について理解が必要です。ここでは雑給の定義や仕訳について解説するとともに、法律における給…

繰り越しヘッジ損益とは?デリバティブの定義から解説!
会計業務繰延ヘッジ損益勘定は、先物取引やオプション取引といったデリバティブについて、期末時点での時価評価による差額を翌期以降に繰り延べるときに使用する勘定科目です。 財務諸表では、貸借対照…

償却債権取立益とは?貸倒引当金戻入益との違いに注意!
会計業務償却債権取立益勘定は、前期以前に回収不能であるとして貸倒処理した債権が当期に回収できた場合に、その金額を収益として計上するための勘定科目です。財務諸表では、損益計算書の営業外収益と…

割引手当とは?種類や不渡手形になるまでのプロセスを解説
会計業務販売代金を現金ではなく約束手形で受け取った場合に「受取手形」で仕訳を起こすことは良く知られていますが、「割引手形」や「裏書手形」、「不渡手形」がどういった種類の手形であるのか意外と…

開業償却費とは?償却方法や確定申告との関係まで解説!
会計業務開業費償却勘定は、開業時に繰延資産として計上した開業費を取り崩して費用にするときに使用する勘定科目です。財務諸表では、損益計算書の営業外費用として表示されます。 開業費・開業費償却…

未収入金とは?売掛金・未収収益との違いに注意
会計業務未収入金は、営業活動以外の取引による未回収の金額を計上するための勘定科目です。財務諸表では、貸借対照表の資産の部に表示されます。 未収入金は営業活動以外の取引による未回収の金額を計…

減損損失とは?計算方法や会計処理の方法、認識と測定や財務諸表への影響を解説
会計業務減損損失とは、企業が行った固定資産などの投資額と将来キャッシュフローを比べたとき、損が出ている場合の損失額のことです。投資の失敗は、投資家などの外部関係者に影響を与えるため、財務諸…
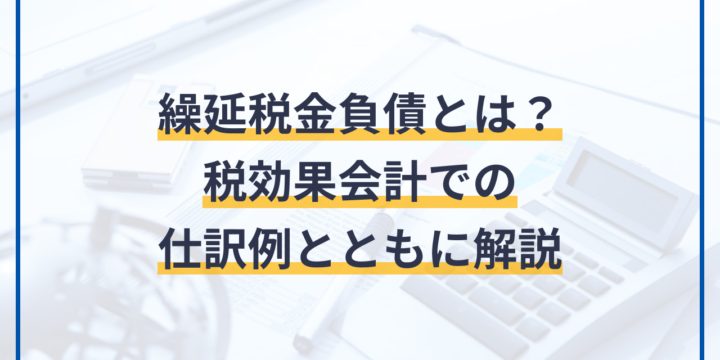
繰延税金負債とは?税効果会計での仕訳例とともに解説
会計業務繰延税金負債は、税効果会計を適用している場合に使用する勘定科目で、会計上の損益と税務上の所得の差を調整するためのものです。財務諸表では、貸借対照表の負債の部に表示されます。 繰延税…

2024年版 – 一括償却資産とは?仕訳から解説
会計業務一括償却資産とは、通常の減価償却ではなく、取得価額を3年間で均等償却できる一定の資産のことです。財務諸表では、貸借対照表の資産の部の固定資産として表示されます。 法人だけではなく、…

投資有価証券とは?保有目的で仕訳が変わるのか
会計業務一般的に「投資有価証券(とうしゆうかしょうけん)」とは、社債や国債、株式などの金融商品のうち、長期間にわたって保有されるものを指します。さまざまな種類の投資有価証券がありますが、「…

利益準備金とはどんな勘定科目?計上しなければならない理由を解説
会計業務利益準備金とは法定準備金の1つであり、会社法によって規定されているものです。剰余金を株主に配当する場合に、法務省令の会社計算規則で規定された計算方法で求めた額を利益準備金に回すこと…

仮受金の仕訳はどうする?財務諸表での位置付けと取り扱い
会計業務仮受金は誰から支払われたのか、あるいはどうして支払われたのかが不明な入金や送金を振り分けられる勘定科目です。 ここではこの勘定科目の定義や財務諸表での位置付け、そしてどのように扱う…

原材料に関する意外と知らない簿記のルール3選
会計業務原材料は仕入れて加工し、製品となったものを販売することによって初めて利益を上げることができます。 そのため原材料を仕入れただけでは利益を上げることができず、原材料ならではの簿記のル…

差入保証金の仕訳を理解しよう!具体例と考え方を解説
会計業務差入保証金とは敷金や営業保証金などを処理するための勘定科目です。以下では差入保証金の基本的な考え方と会計上・税務上の取扱ルール、敷金をはじめとする主な差入保証金について解説します。…

貯蔵品はこんなに便利!知って得する貯蔵品に関する知識まとめ
会計業務利益を生み出すために必要な費用は、基本的にすぐに消費することを前提に経理処理を行なうものです。 とは言え、購入したけれど例年通りに消費することができず、期末にたくさん余ってしまった…

研究開発費とは?定義や資産計上できるケースの解説
会計業務研究開発費とは新技術や新製品の発見に支出した試験研究費や、市場の開拓や資源開発のコストの記帳に用いる勘定科目です。 研究開発費に該当するか否かは、実質的に判断します。既存製品の改良…

繰越利益剰余金とは?貸借対照表での位置付けと仕訳のルール
会計業務貸借対照表の純資産の部に区分される繰越利益剰余金は、株主への配当額にも関わる勘定科目です。 ここではこの繰越利益剰余金が貸借対照表でどのような位置付けがされているのかを通じて、その…

締め日がポイント|退職時に損をしないための税金と社会保険料
会計業務退職してすぐに再就職しない場合、それまで自動で給与から天引きされていた税金や社会保険料は自分で支払わなければなりません。 税金や社会保険料は退職日を基準にそれぞれの締め日が決定する…

仮払金の仕訳はどうする?財務諸表での位置付けと取り扱い
会計業務交通費や旅費、内容不明分の仮処理など様々な支払いを振り分けられる仮払金。 ここではこの勘定科目の基本的な考え方をはじめ、財務諸表での位置付けや仕訳の方法など、実務に必要な知識につい…

役員報酬は変更できる?手続き方法と注意点を解説!
会計業務会社経営が順調な場合や経営状態が悪化した場合には、役員報酬を変更することがあります。しかし、役員報酬を変更する際には、税法上のルールに従って変更しなければなりません。 役員報酬を変…

資金収支計算書とは何か?おさえておくべき3つのポイント
会計業務「資金収支計算書」とは、社会福祉法人や学校法人が作成しなければならない財務諸表の1つです。 ここでは社会福祉法人に関する、 ・資金収支計算書の法的根拠 ・資金収支計算書の記載内容 …

「公益目的事業(公益事業)」に認定されるために知っておくべき3つのポイント
会計業務公益法人として会社を立ち上げるためには「公益目的事業(公益事業)」として認定される必要があります。 公益目的事業として認定されるためには、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関…

外交員報酬の税法上の扱いは?源泉徴収の方法について解説
会計業務保険の外交員や集金人、または電力計の検針人などを指す「外交員」に支払う外交員報酬は、税法上「給与」とは違う扱いを受けます。 ここでは外交員及び外交員報酬の定義を解説するとともに、税…

定額法の償却率は耐用年数がポイント|国税庁の質疑応答事例を用いて解説
会計業務定額法とは減価償却における償却方法の1つであり、減価償却によって購入した減価償却資産を費用化することで節税効果を期待することが可能となります。 減価償却方法を定額法とした場合は原則…

公課証明書とは?記載内容と取得方法について解説
会計業務公課証明書は固定資産の所有権の移転に伴う固定資産税の按分などに使用する書類です。 ここでは公課証明書にどのような情報が書かれているのか、どのようにすれば取得できるのかについて解説し…

国保計算を基本から理解するための3つのポイント
会計業務職場で社会保険に加入していない人や生活保護を受給していない人であれば加入が義務付けられている国民健康保険(以下、国保)。 ここではこの国保の保険料計算(以下、国保計算)の基本と、保…

郵便代について知っておきたいポイント3選
会計業務郵便代と一口に言っても、切手代やメール便、送料など、用途の異なるものが含まれています。そのため郵便代について仕訳を起こす際には、内容に応じた科目を選択する必要があります。 また郵便…

借り上げ社宅、税法上のメリット・デメリットは?
会計業務会社が提供する住宅に関する福利厚生の一環として、借り上げ社宅があります。 これは一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れて、その借り入れた賃貸物件を社員に貸し出す制度のことを指します…

天引きされた税金や保険料はどのように取り扱われているのか詳しく解説
会計業務毎月の給与から天引きされるものとして、 ・健康保険料 ・介護保険料 ・厚生年金保険料 ・雇用保険料 ・所得税 ・住民税 などがあり、これらは「保険料」と「税金」の2つに大別されます…

その他資本剰余金とは
会計業務「その他資本剰余金」とは、企業の財産のうち、事業の元手である株主資本の一部を表すものです。 ここでは、その他資本剰余金とはどのような場合に計上されるか、財務諸表ではどのように表示さ…

決算日はいつがオススメ?押さえておきたいポイント3選
会計業務決算日をいつにするのかという問題は、これから会社を設立する人にとって頭を悩ませる問題なのではないでしょうか。 多くの会社が採用している3月決算や12月決算に倣ったほうがいいのか、そ…

残業代計算、正しくできていますか?基本的な考え方を解説
会計業務残業代の計算は事業主なら誰もが頭を悩ませる問題です。支払う残業代が少ないに越したことはありませんが、計算を間違えて支払うべき残業代を支払っていないと、法的なトラブルにも発展しかねま…

収入印紙を金券ショップで買うことのメリット・デメリット
会計業務契約書や領収書に貼る収入印紙は郵便局や印紙売りさばき所で売られていますが、金券ショップで売られていることもあります。金券ショップでは額面より低い金額で売られているため、経費削減に役…

固定資産評価証明書はどのようなときに必要?
会計業務固定資産税の課税のために土地や家屋などの資産につけられる価格を、固定資産税評価額といいます。 固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書で確認できますが、公…

中小企業が受けられる補助金一覧 雇用調整助成金が受けられるのはどんな時?
会計業務中小企業は事業運営の中で、運転資金が十分にない為に活動に制限が出ることがあります。加えて資本金も少ない為に僅かな資金繰りミスにより倒産に陥る可能性を負っています。 しかしながら、条…

定額法と旧定額法の違いを理解しよう
会計業務定額法による減価償却方法は、税制改正前の「旧定額法」と、税制改正後の「定額法」の2種類があります。税制改正の影響を受けて、それぞれ償却率や計算方法が変更しています。 今回は定額法と…

所得割額と均等割額との合計で算出される住民税 その意味や計算方法を解説
会計業務会社に勤める方なら通常、「特別徴収」といって毎月給与から天引きされている住民税。住民税を特別徴収されていない方は、自治体から届く納税通知書で原則として年4回(6月、8月、10月、翌…
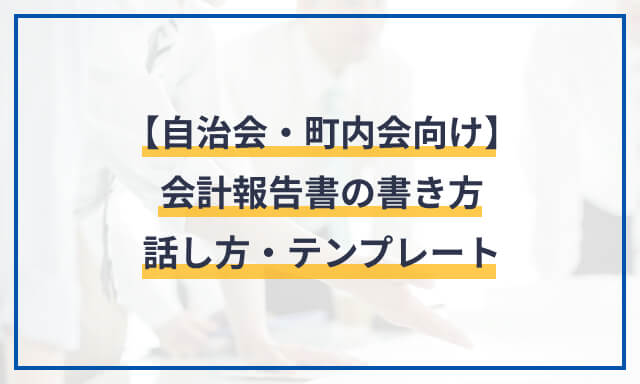
町内会等の会計報告書の書き方・話し方・テンプレート
会計業務自治会、町内会などの団体や地域活動を行っているコミュニティ団体で法人格を持たないものは「任意団体」に分類されます。任意団体の運営については、法律などで決められたルールがありません。…

【定率法の償却率】旧定率法と250%と200%の違いを徹底解説
会計業務平成19年度税制改正によって定率法の償却率が250%に引き上げられ、平成23年度税制改正によって200%に引き下げられました。 税制改正の影響を受けて、定率法による減価償却率がどの…

コンビニでも買える収入印紙についての知識
会計業務マイホームなどの高額なものを購入した時に収入印紙を貼った領収書をもらったことなどあるかと思います。収入印紙はもっと様々な場面で必要になります。 どんな場合に収入印紙を貼らなければい…

収入印紙を購入するうえで知っておくと便利な知識3選
会計業務契約書や領収書に貼られる収入印紙は、印紙税法という法的根拠に基づき、印紙税を納めるために使用するものです。 収入印紙と契約書がどのように関わっているのかを明らかにするためには、印紙…

財団法人とは?設立前に知っておくべきポイント
会計業務一般財団法人△△会、公益財団法人○○財団など世の中には多くの「財団法人」と名のつく団体があります。 そもそも財団法人とはどういった性質の団体なのか、あるいは「一般」財団法人「公益」…

地方法人税はなぜ創立された?その理由と申告・納付方法について
会計業務地方法人税とは、平成26年施行された税制度です。 この税制度の創設の理由と申告方法、納付の仕方について、基礎知識をご紹介します。 地方法人税はどんな税制度? 地方法人税と聞くと、地…

固定資産税はいくらかかるもの?知っておきたい課税額の計算方法
会計業務家や土地などの資産を所有している人にかけられる固定資産税。所有している人なら、実際にいくらかかるのか、知っておきたいところです。 ここでは固定資産税の計算方法を土地、家屋など、具体…

財務諸表に関する法的根拠まとめ
会計業務財務諸表と呼ばれる代表的なものとして、 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・キャッシュ・フロー計算書 の4つを挙げることができます。 それぞれの書類が持つ数字の意…

リバースチャージ方式とは?消費税法改正で課税方式が変わった!
会計業務平成27年(2015年)4月の消費税法改正では新しく「リバースチャージ方式」という課税方式が一部の取引に適用されることになりました。 ここではこのリバースチャージ方式の仕組みを解説…

ABC分析を極める!パレートの法則、ロングテール理論との関係は?
会計業務事業で取り扱う商品にも売れ筋のものとそうで無いものがあると思います。 人気の違う商品に、それぞれどれくらい手間をかけて管理すれば良いのかという疑問には、本稿で解説するABC分析が役…

法人税の申告期限は決算日の2か月後
会計業務法人税の申告期限は決算日の2か月後と定められています。決算日から2か月を過ぎているのに、株主総会を待ってから法人税の申告をする会社も多くみられますが、これは特例を適用していることに…

資金繰りは経営の必須項目
会計業務経営にかかわる数字のうち、経営者はどうしても売上高や利益に目が向きますが、資金繰りに目を向けることも重要です。資金繰りがおろそかになると、利益は出ているのに資金が不足して、事業の存…

固定資産税も軽減措置で減税!納期は?課税資産や納税義務者は?
会計業務税金には、所得に課税される税金(所得税、法人税など)や消費に課税される税金(消費税、酒税など)のほか、資産の所有に課税される税金もあります。この代表的な税金が固定資産税です。 本稿…

財務諸表とは?財務三表の読み方を初心者向けにわかりやすく解説
会計業務財務諸表とは、一般的に決算書といわれる書類のうち、金融商品取引法で上場企業などに作成が義務付けられている書類のことです。その中でも、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の…

無形固定資産と有形固定資産とは?違いや減価償却の解説
会計業務固定資産には、無形固定資産と有形固定資産があります。物理的な形態を持つか、持たないかが主な違いです。 無形固定資産には、ソフトウェアや特許権、有形固定資産には土地や建物などの種類が…

未償却残高はどのように算出するのか
会計業務みなさんは未償却残高という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 一言で言えばその資産に現在どれくらいの価値が残っているかを表している金額となります。 それでは試算表をみたときにどの数…

農業法人設立の流れとメリット 白色申告の農家が受けられる税金面の優遇措置とは
会計業務農業を営んでいるといっても個人事業主や農業法人など事業形態はさまざまですが、家族経営している農家が多いのではないでしょうか。 家族経営している白色申告の農家であったとしても農業法人…

「e-Gov」って何?その全容と活用法を知っておこう!
会計業務e-Gov(イーガブ「電子政府の総合窓口」)とは、政府が運営する行政情報のポータルサイトをいいます。 このe-Govを使えば、オンライン上で行政手続きを行うことができたり、政府の試…

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金を活用しよう!
会計業務「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」という制度があるのをご存じでしょうか。革新的なものづくりやサービスを創出するための補助金です。今回は、ものづくり・商業・サービス経…

W/R比率とは?日本の卸売構造の特徴を解説します
会計業務W/R比率という指数をご存じですか?W(wholesale/ホールセラー)は卸売業、R(retailer/リテイラー)は小売業のことで、W/R比率(wholesale /retai…

連結納税は得か損か?
会計業務連結納税とは、一企業ではなく、その企業が属するグループ全体に対して、法人税が課税される制度です。この制度を用いると、企業グループ内の各企業の黒字と赤字を通算して、「企業グループ=ひ…

非課税取引とは?消費税の非課税取引を徹底解説
会計業務消費一般に公正に負担をかけるという消費税の性格上、消費にあたらないものや配慮されるべきものは「非課税取引」となります。非課税取引は、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡など、多岐にわた…

みなし配当の課税関係
会計業務みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が利益配当であるとみなされるものをいいます。そのため、税務上は配当金と同様に取り扱い、法人の場合は益金…

グループ法人税制の注意点
会計業務2010年度に行われた税制改正の目玉として、新たに誕生した「グループ法人税制」があります。これは、会社の規模や資本金の大小を問わず、100%支配グループ内の場合強制的にすべての法人…

「自計化」って何だ?
会計業務会社を運営していると、本業への取り組みに注力するために、会計処理の全般を会計事務所に依頼するケースが多くあります。業績が順調に伸びていったり、経営方針上、業務内容が多岐にわたってい…
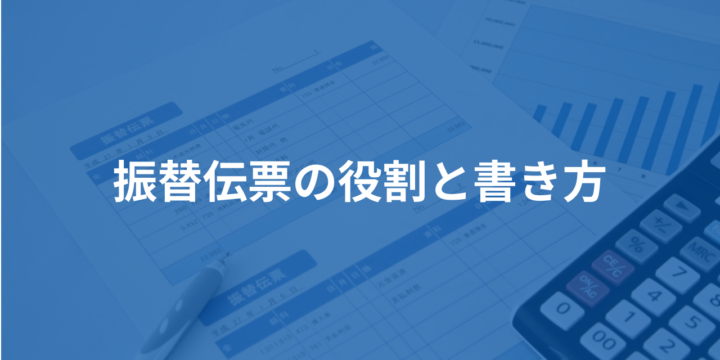
振替伝票の役割と書き方
会計業務業務で発生した金銭のやりとりは、すべて帳簿に記載しなければなりません。一般的に、こうした取引のすべてを日付の順番に従って記載した帳簿を仕訳帳と言います。 仕訳帳に記載されたすべての…

源泉分離課税とは?源泉分離課税の基礎を解説
会計業務分離課税制度(ある種類の所得を他の所得と分けて課税する制度)には申告分離課税と源泉分離課税があり、所得の種類によってどちらを適用するかが決定されています。その結果、確定申告が必要か…

国民年金基金の節税効果やデメリットについて
会計業務国民年金は、日本に住所がある20歳以上~60歳未満の方全員に加入が義務づけられている公的年金であり、老後の生活を支えるための大切な制度です。万一のための障害基礎年金・遺族基金年金も…

売上の計上基準の種類とは?
会計業務商売をしていく上で最初に決断しなければならないことのひとつに、どの時点で売上を計上するか、つまり、「売上の計上基準」をどれにするかというものがあります。 売上の計上基準をいったん採…

売掛金を回収するために知っておくべきこととは
会計業務「売掛金はきちんと回収できている」「売掛金は取り扱ってないから」と、根拠なく安心していませんか? 世間では「売掛金未回収」はよくあるトラブルで、対岸の火事ではありません。また、現在…

土地や建物にかかる固定資産税の計算方法
会計業務固定資産税とは、土地・建物などの所有者に課される税金で、市町村(東京23区だけは東京都)から送られてくる納税通知書に書かれた金額を4回に分けて支払います。ここでは、固定資産の概要や…

【予算計画の基礎】正しく経営するために予算計画を立てよう
会計業務事業計画を立てるうえで重要なのが予算計画です。予算とは、どのような目的で立てるものなのか、どの程度の頻度で見直していけばよいのかなどについて、気を付けたいポイントとあわせて解説しま…

キャッシュフローを改善するためのポイント
会計業務事業を継続していると、会社にはお金が出たり入ったりします。キャッシュフローとは、一定期間の活動の結果として会社に出たり入ったりするキャッシュということになり、実際に手にする現金の流…

会社解散における税務処理とは
会計業務業績が悪化し事業閉鎖に追い込まれてしまったり、会社を存続するメリットがなくなったり、事業の後継者がおらず、事業そのものが継続できなくなったなどの理由から、会社の業務を終了させること…

間接税と直接税との違いとは
会計業務税金の徴収方法には2種類あります。直接税と呼ばれる方法と、間接税と呼ばれる方法です。 直接税はその言葉どおり、納税者が直接税金を支払います。所得税や住民税、法人税や事業税、固定資産…

貸倒損失とは?計上される要件と仕訳の処理について
会計業務売掛金などの債権の回収ができなくなった場合に行うのが「貸倒損失」の処理です。貸倒損失を計上し、損失で処理します。しかし、貸倒損失の計上には税務上、さまざまな要件などがあります。そこ…

工事進行基準の会計処理方法について
会計業務工事進行基準の会計処理方法について 工事進行基準は、請け負った仕事の進み具合に合わせて段階的に収益を会計処理していく方法です。 商品・サービスと対価の提供がほぼ同時に行われる小売業…

役員賞与は税金が高くつく!?
会計業務ボーナスと呼ばれる賞与は、もらう側にとって仕事が評価された喜びを高め、モチベーション・アップにもつながります。一方で、支払う側にとっては、そのモチベーション・アップを業績に反映させ…

棚卸資産とは?原価法や低価法による評価方法
会計業務会社が所有する資産には様々なものがありますが、損益計算に大きく影響しながらも残高管理が難しい資産のなかに「棚卸資産」があります。今回は「棚卸資産」にはどのような種類があるのか、原価…

引当金の会計処理はどう考えればいいのか?
会計業務「引当金」についてご存知でしょうか? 引当金とは、将来に発生するであろう特定の費用又は損失に備えてあらかじめ準備しておく見積金額のことをいいます。 なお、発生する可能性が低い場合は…

中小企業経営者が知っておくべき節税対策とは?
会計業務法人という形態はとっているものの、実体としては個人事業主と変わらない規模の小さな中小企業や、起業して間もなく資金繰りに余裕がない中小企業にとって、税金の負担は死活問題といえます。 …

中小企業をサポートするための税制について
会計業務わが国の雇用や経済は中小企業によって支えられています。中小企業の活動はさまざまな措置でサポートされており、税法においても法人税法をはじめ租税特別措置法などの支援策が講じられています…

法人税申告書とは?初心者向けに書き方を解説!
会計業務法人税申告書とは、法人が事業年度ごとに行う税務手続きに関する書類のことです。法人は、所得に対して課せられる法人税の額を計算し、税務署に申告書を提出する義務があります。 法人税の申告…

自動車重量税はだれがいつ納付しているのか?
会計業務「自動車重量税」についてご存じでしょうか。自動車を所有している方なら、購入時や車検のときに請求書等で目にしたことくらいはあるかも知れませんが、「どのみち支払わなければいけないもの」…

消費税は輸入と輸出では扱いが違う?
会計業務グローバル社会の進展により、国際取引が頻繁に行われるようになりましたが、輸入や輸出をした場合、消費税はどうなるのか悩まれる方もいるかと思います。そこで、今回は、輸入や輸出をする際の…

決算賞与による節税対策|要件とメリット・デメリット
会計業務「利益が大幅に上がり、それに伴って税金も増えそうだ」といった場合に、決算賞与という節税方法があります。決算時に賞与が未払いであっても今期に損金と認められる決算賞与の要件、メリット、…

同族会社とは?判定要件を正しく理解するための基礎知識
会計業務ここでは、同族会社の定義、同族会社に対する3つの制限について説明いたします。 同族会社とは何か 会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保…

平均課税を正しく理解して節税対策に役立てよう!
会計業務所得税は、所得の種類によって固定の税率または超累進税率を乗じた税額の合計となっています。 固定税率とは、例えば、利子所得や株の譲渡などで得た所得に対するもので、それぞれ固定の税率が…

簡易課税は事業区分で決まる!節税対策として知っておきたい基礎知識
会計業務インボイス制度に登録した事業者は「原則(一般)課税方式」での納税が原則ですが、「簡易課税方式」という税額の計算方法もあります。加えて、当面の間は「2割特例」と呼ばれる経過措置も適用…

総合課税で損益通算するには?
会計業務税制上、収入は性質ごと区分されています。そして、その区分ごとに課税の方法も異なります。 例えば、会社員が受け取る給料は「給与所得」に分類されます。収入が給与所得だけの場合には区分を…

【公益法人会計基準とは】法人税が非課税になるのには理由があった
会計業務公益法人は税制面で優遇されています。法人なら支払うべき法人税がなぜ非課税になるのでしょうか? 公益法人は税制面で優遇されるため財務状況が厳しく審査されています。(これを公益法人会計…

消耗品費と雑費はどうやって線引きするか
会計業務消耗品費と雑費の違いについてご存知でしょうか。 消耗品費と雑費は使い分けを迷う方が多い科目です。 それぞれの科目の特徴、実務上の注意点をお伝えします。 消耗品費として経理処理する場…

逓増定期保険を節税の強い味方にする!
会計業務多くの法人が活用する逓増(ていぞう)定期保険は、一定期間を超えると死亡保障金額が徐々に増えていくタイプの定期生命保険です。 保険料の一部が損金として計上できるため、条件を満たせば節…

事業税の計算方法を正しく理解していますか?個人事業税と法人事業税の計算方法を解説
会計業務事業主が知っておくべき税金のひとつに「事業税」があります。 所得税は国に納める税金ですが、事業税は管轄する行政に納める地方税です。そして、事業税には「個人事業税」と「法人事業税」が…

寄付金控除は法人も受けられるか?
会計業務個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附をした場合には、所得控除を受けることができます。これを、寄附金控除と呼びます。また、政治活動関連への寄附金や認定NPO(特定非営利…

留保金課税で特定同族会社がとるべき対策は?
会計業務留保金課税制度は、特定同族会社が利益を留保することによる過剰な租税回避を防止するために制定されました。 本来、会社であれば、利益が出ればそれを配当という形で株主に分配しなければなり…

中古車の方がお得?社用車の節税対策とは
会計業務会社の資金繰りは、事業を運営する上で重要な要素のひとつです。 固定資産の購入は、会社の事業の運営・将来的な収益に結び付く投資であるため、減価償却による費用処理が認められています。社…

寄附金控除・損金算入の基礎知識
会計業務個人や会社などが寄附を行った場合、控除や一定限度額までの損金算入などを受けられます。 寄附金控除を受けることができたり損金に算入できたりする寄附金とはどのようなものを指すのか、寄附…

法人税法で認められる貸倒引当金限度額は?
会計業務中小企業者は会社が持つ売掛金や受取手形などの再建において、将来的に貸倒の発生が見込まれる損失額を法人税では損金として算入できます。 ただし、参入することができる金額はある一定の算式…

法人税で「繰延資産」を節税に活用できていますか?
会計業務法人税を確定申告するときに、繰延資産を上手く利用すると節税効果があることをご存知でしょうか。 繰延資産には、会社法上や税法特有のものなどさまざまな費用があり、支出の効果が及ぶ期間に…

法人税等調整額とは?仕訳事例でわかりやすく解説
会計業務法人税は、法人の各事業年度の所得に課される税金です。ここでいう法人の所得とは、会計上の利益(収益-費用)とは異なります。 法人が一般的に妥当とされる企業会計で計算した利益は、必ずし…

固定資産税の税率が下がる?知っておきたい軽減税率や優遇措置の基礎
会計業務固定資産税の税率は全国どこでも一律ですが、住宅用地としての土地使用の場合には軽減税率が適用されるなど、優遇措置が認められています。そこで、今回は、主な税制の優遇措置の内容とそれを受…

法人税で中間納付方法は3種類?理解しておきたい中間申告・納付のポイント
会計業務法人税の支払いに関しては、事業年度開始から6ヵ月経過時点を「中間」とし、事業年度の始めから「中間」点までの法人税を先に納めることとなっています。 納付期限は「中間」日より2か月以内…

仕入税額控除の対象とその計算方法
会計業務仕入税額控除は、課税事業者にとって納税額を大きく左右するポイントです。 計算方法を間違うとキャッシュフローが悪化し、経営に支障をきたす場合もありますので注意が必要です。 そもそも、…

補助元帳と補助記入帳の役割とは?
会計業務複式簿記における補助簿併用制は、「主要簿」と「補助簿」で構成されています。また、補助簿には、「補助元帳」と「補助記入帳」があります。 どちらも任意帳簿で義務付けられているものではな…

決算書とは?主な種類や見方をわかりやすく解説
会計業務決算書を見ると企業の経営状態や財務状況がわかります。しかし、見方がわからないと記載されている数字の意味が理解できないため、企業の経営状況を把握することができません。決算書の作成は税…

預金出納帳の書き方について
会計業務複式簿記において重要な「預金出納帳」とは、金融機関の口座別に入金・出金のすべてを記録していくための帳簿です。 ここでは、預金出納帳の役割、預金出納帳の書き方について解説します。特に…

株主資本等変動計算書の書き方の基礎
会計業務新会社法の施行により、株主資本等変動計算書が使われるようになりました。ここでは、株主資本等変動計算書の位置づけや、導入のいきさつについて説明します。また、株主資本等変動計算書の書き…

固定資産台帳とは?作成方法や記入例、見方を項目別に解説
会計業務固定資産を購入した場合に取得時の状況やその後の減価償却の状況を記録する固定資産台帳について、その役割や作り方、記入方法を解説します。 固定資産台帳とは 建物や車両などの固定資産を取…

クラウドが描く未来。東欧の小国エストニアから税理士が消えたわけ
会計業務確定申告のシーズンを終え、多くの人が会計の世界に触れ、改めて、確定申告は面倒だと感じた方も多いのではないでしょうか。実は、世界には確定申告をする必要がない国があります。 もちろん、…

【タカタ リコールに学ぶ】回収・無償修理した際の会計処理方法
会計業務トヨタ、ホンダを始めとする日欧企業が、タカタ社製のエアバッグに関して「不具合を起こす可能性がある」との理由によりリコールを発表しました。 本来リコールとは自主的に製品の回収や修理を…

エンジェル税制とは?個人投資家の確定申告手続きも解説!
会計業務エンジェル税制という制度があることをご存じでしょうか。 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するため、平成9年の税制改正で新設された税の優遇制度のことです。この制度を利…

外形標準課税の対象法人になるとどうなる?
会計業務外形標準課税は、行政サービスを受けている以上、黒字の企業も赤字の企業も費用を平等に負担すべきだという指摘に対応する形で生まれた法人事業税です。 外形標準課税は、企業間の不公平感をな…

損金の意味と法人税の計算に欠かせない損金算入・不算入を解説
会計業務企業が営業活動を行う際には、広告費や光熱費といった「費用・経費」が必ず発生します。会計上の「費用・経費」のことを法人税法上は「損金」と呼びますが、会計上の「費用・経費」と法人税法上…

損益計算書の借方と貸方の違いや減価償却費の扱いを解説!
会計業務簿記について勉強する時に、ごく初歩的な借方と貸方の違いがわからないことが理由で挫折してしまうことがあります。ですが、借方と貸方のルールさえ理解してしまえば、あとは少しずつ学んでいけ…

借方と貸方|貸借対照表の借方と貸方の違いをわかりやすく解説!
会計業務貸借対照表や借方、貸方と聞いただけで考えるのも嫌になってしまう方、簿記アレルギーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、そんな簿記アレルギーの方向けに、貸方と借方の違いを解…

法人税の資本金には超えられない壁がある?
会計業務法人税には資本金によって大きな壁があるといわれています。資本金がその壁を超えるか超えないかによって、毎年支払う法人税等に多額の差が出てくることもあります。「1,000万円の壁」と「…

合併の基礎知識|負債がある会社と合併したら、どうなるの?
会計業務会社活動の選択肢のひとつに、合併や会社を分割することで組織を再編するというものがあります。この中の、合併という方法は会社法によって規定されています。では具体的に合併するとはどういう…

上場予定の企業必見!絶対必要になる内部統制報告書とは
会計業務上場会社には様々な書類を提出することが求められています。そのうちのひとつに、金融商品取引法が定める内部統制報告書があります。 内部統制報告書とは、企業の財務報告に関する内部統制が有…

【保存版】すまいの給付金や失業給付金だけじゃない!8種の給付金一覧
会計業務消費税の増税や、相続税の改正など、税負担の増加に関する話はよく聞きます。しかし、実際にはこれらの負担増を軽減するために様々な給付金が用意されていることをご存知でしょうか? 有名な給…
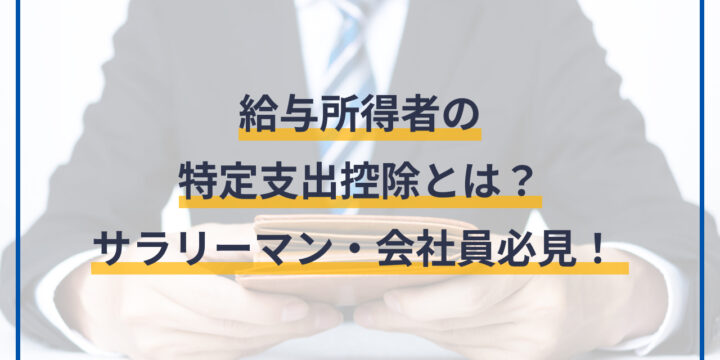
給与所得者の特定支出控除とは?サラリーマン・会社員必見!
会計業務サラリーマンであっても経費が控除される、特定支出控除という制度があります。その控除の範囲や条件が平成24年度(2012年度)、平成28年度(2016年度)に改正され、使いやすいもの…

手形とは?小切手との違いや種類、取引の流れを解説
会計業務手形とは、一定期間後に現金化できる証書のことです。現金化できる証書としては小切手もありますが、小切手はすぐに現金化できる点が異なります。手形の種類や取引の流れ、メリット・デメリット…

与信管理とは?調査方法やポイントをわかりやすく
会計業務一般企業の与信取引として代表的なのが、売掛金などによる掛取引です。与信取引のある企業では、与信管理をすることが、自社を連鎖破産から守る防衛策になります。今回は、与信管理の重要性やプ…

60年ぶりの農協監査制度改革!全中の監査権廃止で日本の農業の何が変わるのかを徹底解説!
会計業務2015年2月8日に、政府と全国農業協同組合中央会(以下、全中と表記)の間で全中がこれまで、全国各地にある700に上る地域農協に対して独占的に有していた監査権を廃止することで合意が…

企業の資産価値を測る6種のデューデリジェンスを解説
会計業務組織再編や、企業買収の際に話題に上がるデューデリジェンスという言葉があります。これは、6種類の視点からその企業の資産価値を測ることを指します。 買収や合併の際に行うデューデリジェン…

正しく理解していますか?事業税と事業所税の違いとは
会計業務事業税と事業所税は、言葉は似ているものの全く別の税金です。 事業税は、事業を営む個人には個人事業税として、法人には法人事業税として、所得や収入に応じて課せられる地方税のことです。個…

限界利益とは?計算方法や他の利益との違い
会計業務限界利益とは、売上から売上を増やすためにかけた費用である変動費を差し引いたものです。売上高に対する限界利益の割合を示す限界利益率とともに、事業の状態を把握する指標となります。 本記…

中小企業に大きな優遇!研究開発税制を活用して研究開発を促進せよ
会計業務「研究開発税制」という言葉を耳にしたことはありませんか? これは、国が成長力と国際競争力を高めていくことを目的に、研究・開発にかかった費用を法人税から控除するという制度です。つまり…

分割基準を正しく理解していますか?事業税の分割基準の基礎
会計業務事業税を払っている法人はたくさんあります。また、各地に事業所を展開している法人も多いでしょう。では、法人事業税はどこで払うのでしょう? 事業所のある各地に納めているのでしょうか? …

法人税で寄付金とみなされる行為にはどのようなものがあるか?
会計業務損金の予定が寄付金と扱われてしまうことがある 売掛金や貸付金などの債権が回収不能になった場合や、債権者が融資先である債務者に対する債権を放棄した場合などは、法人税計算の際に貸倒損失…

法人税とは?法人税の基礎知識
会計業務法人税とは、主に株式会社や協同組合などの法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得にかかる税金です。個人が利益を得たら所得税を税務署に申告・納税しますが、法人の場合は法人税を税務署…

通勤手当の非課税限度額の引き上げを解説
会計業務平成26年や平成28年度の税制改正により、交通用具に関する通勤費の非課税限度額が改正されました。平成26年改正は2014年4月より既に支給した通勤手当に対しても、遡って適用されるこ…
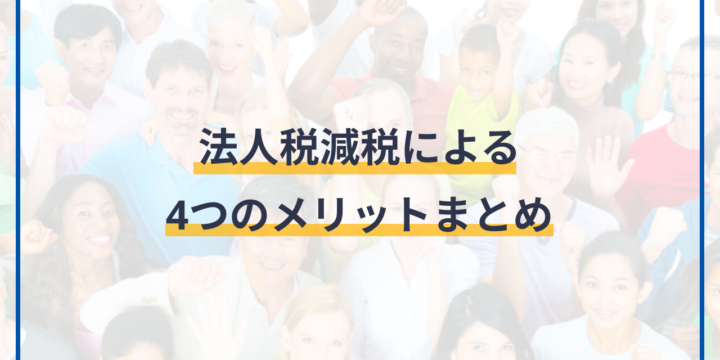
法人税減税による4つのメリットまとめ
会計業務日本経済の長期的な成長を目指す政策とされるアベノミクスのなかでも、法人税の減税は抜本的な税制改正のひとつとして注目を集めています。 国内における投資の活性化や企業の成長促進を目的と…

簡易課税の計算方法には基本と特例がある!
会計業務消費税の納税額は、簡易課税という方式と原則課税という方式のいずれかの方法で計算します。その1つである簡易課税方式は、仕入れや設備投資、経費など仕入れの際に支払った消費税の金額を計算…

赤字でも法人税がかかるって本当?費用と損金の違いを解説
会計業務法人税は会社の利益にかかる税金です。では、会社が赤字の場合はどうなるのでしょうか。当然法人税は支払わなくてよいはずです。ところが、実際には会社が赤字でも法人税を支払う場合があります…

時価会計の意味と時価の算定に関する会計基準の導入を解説
会計業務近年、企業の金融投資が増加する傾向にあります。金融投資の実体を財務諸表に色濃く反映させるために、金融商品を時価で会計処理するという「時価会計」が導入されました。 本記事では、「時価…
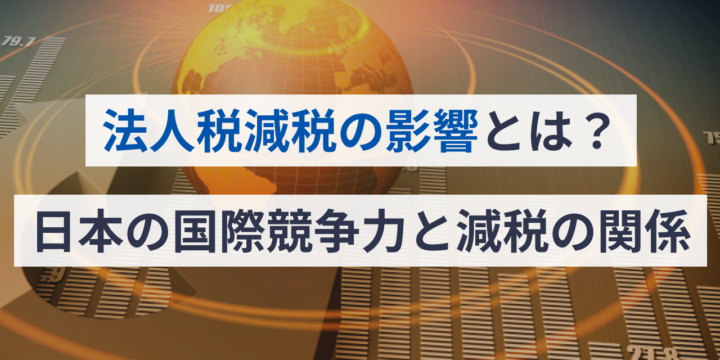
法人税減税の影響とは?日本の国際競争力と減税の関係
会計業務近年、法人税減税実施とその効果について、さまざまな論議がされています。法人税減税の主な目的は、海外企業の日本誘致を促進し、日本企業の国際競争力を高めることです。 この効果によって日…

法人税の計算方法を正しく理解していますか?意外とシンプルな法人税の計算
会計業務法人税は、株式会社や協同組合などの法人が各事業年度に得た課税所得に、一定の税率を乗じて計算します。 法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、比例税率(固定税率)ですが、法人の種類や…

使途不明金に要注意!注意すべきポイントと使途不明金の税務処理方法とは?
会計業務勘定科目には、給与賃金や水道光熱費はもちろん、旅費交通費のほか、さまざまな経費項目がありますが、曖昧でわかりにくい項目のひとつに、「接待交際費」があります。実際はどこまでが接待交際…

知っておきたい支払調書の提出義務者・期限・提出先
会計業務事業者は、所得税法で源泉徴収が必要とされている報酬等を支払った場合、原則的には支払いをした翌月に徴収した源泉所得税等を国に納付します。この報酬等について、1年間の支払金額・源泉徴収…

法人税の節税対策は?社宅や保険・車など効果的な方法10選を紹介
会計業務法人税は法人が事業を行ううえで必要な費用ですが、適切な費用計上によって節税に結びつく方法があります。法人税を節税すれば、法人の利益を増やすことが可能です。この記事では、法人税の効果…

社内連絡から会計まで!中小企業の業務効率化クラウドサービス6選
会計業務最近では様々なクラウドサービスが登場しています。ファイル保管、データ共有、社内の情報共有、スケジュールの共有をはじめ、財務会計、業務支援といった企業内部の業務効率化ができるサービス…

10%増税に備えよう!消費税転嫁対策特別措置法まとめ
会計業務消費税が5%から8%に上がってから、間もなく1年が経過しようとしています。さらに、平成31年10月には10%に引き上げられる予定です。今回は、増税に備えて特に関連性の高い「消費税転…

買い替えの方がお得!?中小企業投資促進税制を使って賢く設備投資!
会計業務中小企業にとって、設備投資は大きな負担として両肩にのしかかります。しかし、一方で既存の古い設備のままでは生産性が向上しません。そういったジレンマを抱える方も多いのではないでしょうか…

日本のお財布、一般会計と特別会計ってなに?
会計業務ニュースで耳にしたことがあっても、実は詳しくわからない言葉って多くありませんか? ここでは、そんな言葉の一つである「一般会計」と「特別会計」についてわかりやすく解説します。 一般会…

源泉徴収票を退職者に渡す際の注意点
会計業務退職手当や退職一時金などを支払った会社は、 退職者に対し、退職後1ヵ月以内に「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」を交付します。税法上、退職所得は給与とは別の方法で算出され、「退…

支払調書の発行義務はあるのか?
会計業務書籍等の通販で有名な企業、Amazonが支払調書の送付を停止しました。「企業は必ず支払調書を発行するものだ」、「みんなが発行しているから必要なものだ」と思っていませんか? 結論から…
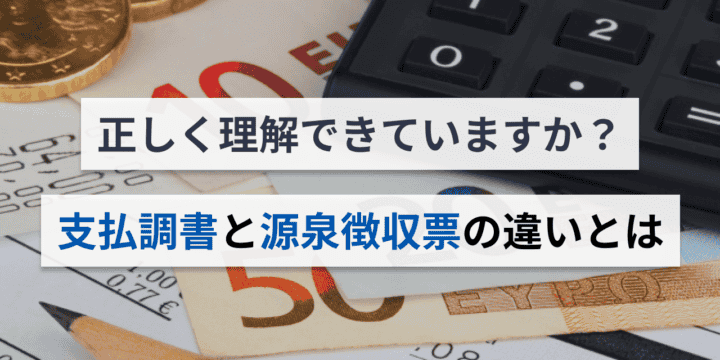
正しく理解できていますか?支払調書と源泉徴収票の違いとは
会計業務支払調書と源泉徴収票とはどう違うのでしょうか。いずれも所得金額とこれに対応する税額を示す法定調書の一種です。 支払調書と源泉徴収票の仕組みについてご紹介します。 法定調書について …

税金を滞納するとどうなる?
会計業務日本に住んでいるかぎり、法律の定めるところにより私たちには納税をしなければならないという義務があります。税金を納付期限までに支払わなかった場合、どのようなことが起きるのでしょうか。…
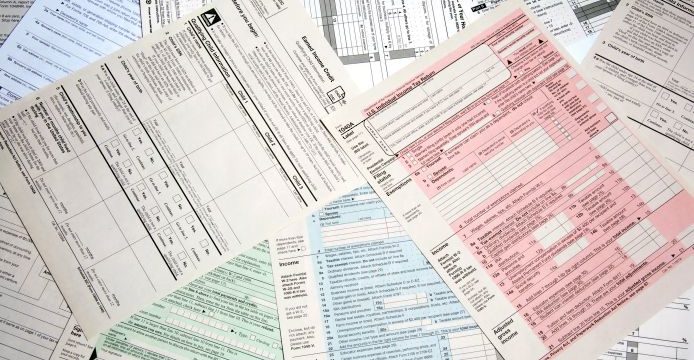
税金の種類にはどのようなものがある?
会計業務日本の税金にはさまざまな種類がありますが、税金の分類や体系などはあまり知られていません。個人や法人が支払うべき税金の正しい知識を得ることは、適切な節税にもつながります。今回は、直接…

初詣のお賽銭は課税対象?神社で学ぶ宗教法人と税金
会計業務あけましておめでとうございます。Bizpediaでは、今年もみなさまに有益な情報を発信できますように努める所存でございます。 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げ…

日本ITソフトウエア企業年金基金に加入するメリットまとめ
会計業務毎月の給与などで年金分の金額を引かれるように、全ての国民には年金を払う義務があります。年金は65歳になって初めて受け取ることができる制度です。 今回はその年金基金の中でも、日本IT…

日本でも「Google(グーグル)税」はあり得るのか?日本の多国籍企業の租税回避の対策を追う!
会計業務2015年4月にイギリスがGoogle(グーグル)税を導入することが話題となっています。また、スペインでは実際にグーグル税の影響を受けて、GoogleNewsのスペイン版の閉鎖が決…

契約書の収入印紙を節約する「第7号文書」に関する節税術
会計業務収入印紙の節約方法については、前回の『プロが教える!簡単に契約書の「収入印紙代」を節約できる3つの方法』の記事でもご紹介しました。 今回は更なる応用編として「第7号文書」という書類…

会計初心者に捧ぐ!基礎から学べる目的別「会計本」まとめ
会計業務書店に行くと会計コーナーや税務コーナーにはたくさんの関連書籍が並んでいます。 とりあえず手に取ってみますが、 「なにを説明しているのかさっぱりわからない…」 「こういう内容の本は持…

納税の期限と方法まとめ!法人ならチェック必須の10の税金
会計業務起業したときに必ず頭に入れないといけないのが「法人における税金」について。責任ある企業として活動していくためには納税の義務は避けて通ることはできません。みなさんは納税の期限や方法に…

領収書のオリジナルデザイン作成におすすめの2つのサービス
会計業務日々の企業活動の中で、頻繁に発行する機会がある書類の一つに領収書があります。みなさんの会社の領収書は市販のものでしょうか?それともオリジナルデザインによるものでしょうか? こちらの…

プロが教える!契約書の「収入印紙代」を簡単に節約できる3つの方法
会計業務「この契約書にはこの金額の収入印紙」普段、何気なく契約書に決まった額の収入印紙を貼っていませんか? 契約金額が高額であったり、同一の契約書を大量に作成したりする場合、収入印紙の額は…

契約書に収入印紙が貼られていない場合は無効なの?
会計業務ビジネスの場において契約書はとても重要です。せっかく成立した商談も無効な契約書を作ってしまっては水の泡となってしまいます。 一方、契約書の種類によって必要な収入印紙の額も200円~…

役員報酬の決め方の注意点と知っておくべき3つの制度
会計業務例えばあなたが起業した場合、自らが経営者となり、会社の役員となります。特にこれまで会社員だった方は、自分の適正なお給料はいくらにすれば良いのだろうか?と悩んでしまう方も少なくないの…

この依頼はどっち?具体例でわかる税理士と公認会計士の違い【5つの質問付き】
会計業務街中でよく「◯◯会計事務所」「◯◯税理士事務所」「◯◯公認会計士事務所」といった看板を目にしたことがありませんか? 税理士や公認会計士は普段の生活であまり関わることがないため、それ…

貸借対照表/バランスシートとは?読み方・見方を初心者向けに解説
会計業務会社の財政状況を表す「貸借対照表(バランスシート)」は、会社のいち会計期間の経営成績を表す「損益計算書」と同時に作成される、決算書の一種です。 企業の資産、負債、純資産の三つの要素…

役員報酬を確実に損金扱いするための3つの注意点
会計業務法人会計において、金額の大きさからも特に重要度が高いものの1つとして「役員報酬」と「役員退職金」が挙げられます。 いずれも金額が決して少なくない額であるため、きちんと手続きを踏まな…

黒字倒産とは?原因や回避方法の解説
会計業務黒字倒産とは、商品やサービスの販売で利益が出ているにもかかわらず、決済資金が不足して支払いが滞り、倒産してしまうことです。決して珍しいものではなく、倒産する企業は高い割合で黒字倒産…

法人住民税とは?計算方法や納付時期を解説
会計業務法人住民税とは、事業所のある自治体に納める地方税です。個人の住民税と同じく、都道府県民税と市町村民税に分かれています。計算方法やほかの税金との違い、納付時期についてまとめました。ま…

収入印紙の取り扱いに注意!印紙税を納める際に気をつけたい3つのこと
会計業務「印紙税」や「収入印紙」と聞いて、すぐにピンとくる方はどのくらいいらっしゃるでしょうか? 「領収書で必要になるもの」くらいしか思い当たらない方も少なくないのではないでしょうか。たし…
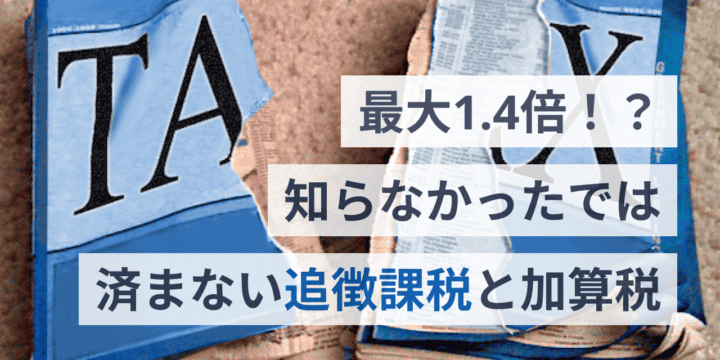
最大1.4倍!?知らなかったでは済まない追徴課税と加算税
会計業務追徴課税という言葉を聞いたことがある方は多いかと思います。しかし、追徴課税に関して、具体的にどういう状況のときに課税されるかまでご存知の方は少ないのではないでしょうか? 追徴課税は…

売掛金のトラブルを未然に防ぐ!貸し倒れを避けるための正しい対処法とは?
会計業務はじめに 企業規模を問わず、事業を行う上でキャッシュフローの管理は、財務面で最も重要な活動の1つと言えるでしょう。損益計算書の売上高、純利益は実際のお金の流れを表しておらず、自社の…

海外での販路開拓や拠点設立の強い味方!海外ビジネス戦略推進支援事業とは
会計業務はじめに 海外展開をしたいけれど「資金に余裕がない」や「どう展開していけばいいかわからない」などの悩みを抱えている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか?そんな悩みや課題を…

「社長、本当に有効な節税方法知ってますか?」 税理士・服部先生が読み解くスタートアップの節税テクニック
会計業務リソース、ノウハウが不足しがちなベンチャー企業やスタートアップにとって、お金に関する悩みが尽きることはないかと思います。その中でも、節税対策について頭を悩ませている経営者も少なくな…

話題の販売促進費用補助制度を徹底解説!
会計業務販売促進費用補助制度とは? スタートアップ経営者、起業家の方で、新規ユーザーや新規顧客の獲得、ないしは自社サービスの認知拡大に頭を悩ませている方は少なくないでしょう。その際、広告を…
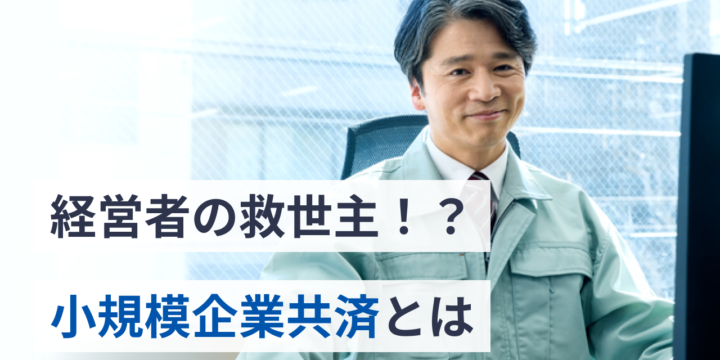
経営者の救世主!?「小規模企業共済」とは
会計業務老後への不安。 年金制度の破綻が叫ばれている中、若年層から中高年までの幅広い層において、そんな漠然とした不安を抱えている方も少なくないと思います。老後の生活資金として年金の積み立て…

「資本性ローン」とは?資金調達における注目の新制度
会計業務はじめに 起業家、または経営者にとって「資金調達」はとても重要なテーマです。資金繰りに悩んでいる起業家や経営者は決して少なくないでしょう。 昨今のスタートアップにおいては、VC(ベ…