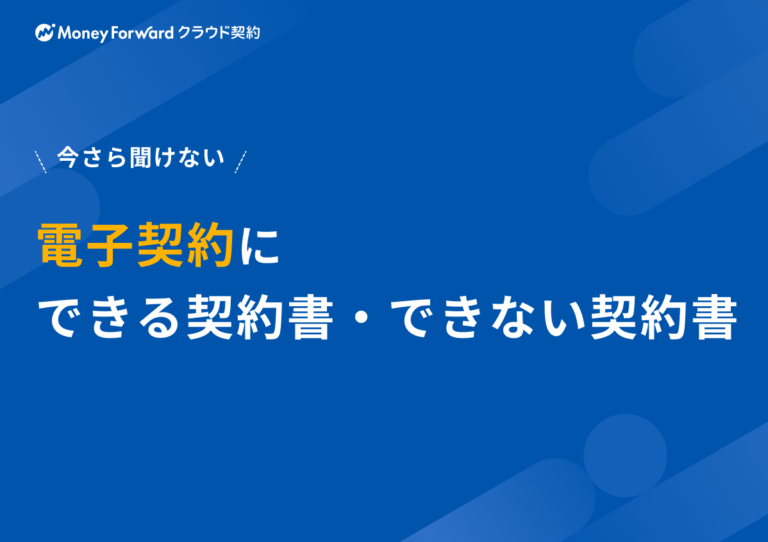- 更新日 : 2025年3月6日
雇用契約書を電子化して工数削減!電子化の方法や要件、注意点は?
契約書など、さまざまな書類を電子化する流れが進んでいます。従業員を雇うときに交わす雇用契約書についても同様です。電子化を進めると工数を削減でき、業務効率の向上が図れるなど、得られるメリットも大きいです。
ただし注意すべき点もあります。ここで雇用契約書を電子化するための要件、注意点についても説明していきます。
目次
雇用契約書は電子化しても良い
雇用契約書とは、使用者となる会社と労働者となる方との間で交わす、雇用契約に基づいて作成される契約書です。雇用契約書は、電子データとして作成・交付することができます。
雇用契約書について、詳しくはこちらでも説明しています。
契約書は、当事者間で定めたルールを明確にし、客観的にその内容を示すために利用される書類です。雇用契約書には労働条件などが記載され、誰とどのような条件で雇用契約を交わしたのかを明らかにできます。
ただ、契約自体は原則として意思表示が合致するだけでも成立するため(民法第522条、労働契約法第6条参照)、雇用契約書を作成する義務はありませんが、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認することが求められます(労働契約法第4条第2項)。雇用主と被雇用者の双方が同意したことを証明する書類として、雇用契約書を用意した方が良いでしょう。
なお、雇用にあたって交付が法的に求められているのは「労働条件通知書」です(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第4項)。 労働基準法では労働条件通知書に関しても、原則としては書面での交付が必要としつつ、労働者が希望したときにはメールやSNSなどを使って労働条件を明示しても良いと規定されています(労働基準法施行規則第5条第4項)。
雇用契約書を電子化する際の要件
作成した雇用契約書について、労働基準法では「5年間」の保存義務を課しています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
しかし同法第143条第1項では「第109条について、当分の間、5年間とあるのは3年間とする」と規定されており、2025年1月の執筆時点においてはこの経過措置が適用されています。
そして国税関係書類の保存について規律する電子帳簿保存法では、電子的にやり取りされた取引情報の保存について、「電子取引」という区分で保存要件を定めています。
契約書を保存するときに求められるのは①真実性の要件と②可視性の要件です。
- 契約書にタイムスタンプを付与する
- 契約書の訂正や削除を行ったとき、その記録が残るシステムを利用する(または訂正や削除ができないシステムを利用する)
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける
②可視性の要件について
- 保管場所にPC・ディスプレイ・プリンタなどを備え付けて、速やかに、明瞭に、整然と内容を確認できるようにしておく
- システムの概要書を備え付ける
- 契約書を作成した日付などの情報から契約書が検索できるようにしておく
雇用契約書を電子化するメリット
雇用契約書を電子化することには、次のようなメリットがあります。
- 業務効率が上がる
押印するために出勤する、移動するといった手間をなくせる。雇用契約を交わす相手方としても、わざわざ会社に出向く、あるいは郵送されてくる書面を待ち、署名押印などを施して返送するなどの手間がなくなる。 - コストが削減できる
ペーパーレスとなることにより用紙を購入するコストが不要になる。また、契約書を書面として作成すると印紙税が課税されるが、電子化することで印紙代も不要となる。雇用契約書はもともと必要ではないが、実際には作成するケースが多い。契約書の電子化ができるシステムを備えておくことで、その他の書類作成に関して印紙税をカットできるようになる。また、郵送などにかかる費用も不要となる。 - スペースが節約できる
紙の契約書を保管する場合、スペースを取ってしまう。一方、電子化する場合、物理的なスペースが不要となる。 - 閲覧制限をかけやすい
電子化しておけば、システム上でアクセス権限を付与することで、閲覧の制限をかけやすい。
雇用契約書を電子化する方法
雇用契約書を電子化するにあたっては、以下の2つの方法が一般的です。
- 電子契約サービスを利用する
- PDF化して電子メールで送付する
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
電子契約サービスを利用する
電子契約サービスは、クラウドベースで契約書を作成、署名、管理するシステムです。企業が提供するプラットフォームを利用することで、契約書はオンラインで署名され、契約の成立が即座に確認できます。
この方法では、電子署名の本人確認やタイムスタンプの付与など、法的効力を保つためのセキュリティ対策が取られています。さらに、契約書はクラウド上に保管され、簡単に検索・参照が可能でメリットが多い方法といえます。
PDF化して電子メールで送付する
PDF化して電子メールで送るのも、雇用契約書を電子化するひとつの方法です。比較的手軽にできますが、法的効力を確保という点においては注意が必要です。
この場合、電子署名ソフトウェアなどを使用して署名を付与する流れになりますが、改ざん防止措置や保存要件を自社で整備しなければなりません。
雇用契約書の電子化にあたり準備が必要なもの
雇用契約書を電子化するには、以下の3点が必要です。
- 電子証明書
- 電子署名
- タイムスタンプ
電子証明書
電子証明書は、契約当事者の本人性を証明するオンライン上の身分証明書です。第三者機関である認証局から発行され、紙の契約における実印の押印と印鑑証明書に相当する役割を果たします。
電子証明書により、なりすましや改ざんを防止し、契約内容の信頼性を確保が可能です。
電子署名システム
電子署名は、契約書に対する合意の意思表示を電子的に行うための仕組みです。署名者の本人性と文書の非改ざん性を証明する機能を持ち、紙の契約書における署名や押印に相当します。
電子署名により、契約内容が確かに契約者の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
タイムスタンプ
タイムスタンプは、電子文書がある特定の時点で存在し、その時点以降に改ざんされていないことを証明する技術です。時刻認証局から発行される時刻情報とハッシュ値を組み合わせることで、契約締結時点での文書の存在と完全性を保証します。
電子契約サービスなら一括で契約締結・保存まで可能
電子署名やタイムスタンプなどの雇用契約書の電子化に必要なものは、電子契約サービスを利用することで一括して導入できます。
ほとんどの電子契約サービスではこれらの機能が統合されており、法的要件を満たした安全な契約の締結から保管までをワンストップで実現します。さらに、契約書の検索や閲覧、承認プロセスの管理など、契約管理に必要な機能も備わっています。
電子契約サービスを導入して雇用契約書を電子化する流れ
雇用契約書の電子化のために、電子契約サービスを導入する際の流れを紹介します。
導入前の準備
電子契約サービスの導入に先立ち、現状の課題分析と目標設定が不可欠です。まず、現在の雇用契約業務における作業時間やコストを可視化しましょう。
紙の契約書作成から保管までの工数を測定し、電子化による改善効果を試算します。また、法務部門や人事部門と連携し、電子化に関する法的要件の確認や、社内規程の整備も行います。
電子契約サービスの選定・導入
電子契約サービスの選定では、セキュリティ基準や運用性、コストなど多角的な視点での検討が必要です。特に雇用契約では、労働基準法で定められた記載事項の確実な明示や、個人情報の適切な保護が求められます。
また、人事システムとの連携可能性や、データの長期保存機能なども重要な選定基準になります。
運用開始
本格運用の開始にあたっては、小規模な運用から始め、実際の業務フローにおける課題を抽出します。この際、従業員からのフィードバックを収集し、必要に応じてマニュアルの改訂や運用ルールの調整を行います。
電子契約の運用が軌道に乗った後も、継続的な改善活動が重要です。定期的に利用状況や効果測定を行い、必要に応じて運用ルールの見直しや、システムの機能追加を検討します。また、法改正や社会情勢の変化にも柔軟に対応できるよう、運用体制を随時アップデートすることも大切です。
雇用契約書を電子化する際の注意点
書面の場合、署名押印により本人性を担保していますが、電子化した契約書に従来のやり方で署名押印をすることはできません。
そこで、電子署名により真正性と非改ざん性を、タイムスタンプにより契約書作成の時期と非改ざん性を確保することが大事です。契約書等の電子化を支援する専用ツールを導入すれば、会社側が特別な技術を備えていなくても、電子署名やタイムスタンプは付与できます。
また、契約書の電子化導入に向けてワークフローを調整しておく必要があります。どのような手順で契約書を作成するのか、作成後のデータの取扱いなど、問題なく運用ができるような体制を整えておきましょう。
なお、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねるケースもありますが、この場合は労働条件通知書にかかるルールが適用されるので要注意です。労働条件通知書は本来書面で交付すべき書類ですので、会社側の裁量で電子化してはいけません。契約相手(労働者側)の、電子化してメール等で交付することに関する意向を確認しておきましょう。
SNSやSMSを使って労働条件を明示することも禁止されてはいませんが、法律で想定されているのは、PDFとしてファイルにまとめた労働条件通知書を送信する手段としての利用です。
LINE上で「契約期間は○○」「就業場所は○○」などとチャット形式でテキストを送るのではなく、PDFファイルを送るようにしましょう。
労働条件の通知や保存要件に注意して雇用契約書の電子化を進めよう
雇用契約書は電子化することが可能です。電子化することで業務効率を上げることができ、コストの削減や省スペースなどのメリットが得られます。
電子化した雇用契約書には電子署名やタイムスタンプを付与して真正性や非改ざん性を確保することが大事です。専用のツールを導入して対応しましょう。
一方で、労働条件通知書としての役割も兼ねる場合には、法令に準拠して電子化しないといけません。労働者の希望を受けた上で、必要な事項を漏れなく記載するように気を付けましょう。
よくある質問
雇用契約書は電子化できますか?
雇用契約書は電子化できますが、雇用契約書兼労働条件通知書とするときは、労働者の希望を受けている必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用契約書を電子化する際の要件はありますか?
電子帳簿保存法に従い、真実性と可視性が確保できる形で電子化する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
電子契約の後文・文言の書き方は?ひな形の変更方法や文例を解説
後文(こうぶん)とは、契約書や電子契約の末尾に記載された文章を指します。後文には、契約当事者の情報や契約の成立日、契約締結や保管の方法などが記載されています。電子契約の場合、紙の契約書と同じ後文は使えません。本記事では、紙の契約書の後文を電…
詳しくみる電子契約とは?仕組みやメリット、法的有効性について解説
電子契約とは、電子文書で作成した契約書に電子署名を行うことで成立する契約です。電子契約を導入することで、契約を迅速に進められるだけでなくコスト削減も可能です。 本記事では、電子契約の仕組みやメリット、法的有効性といった電子契約の全体像を解説…
詳しくみる電子契約をPDFで行う方法は?作成・送信・返信のやり取り、保管を解説
企業の総務担当者にとって、契約書の管理は重要な業務の一つです。ここ数年、電子契約が普及し、PDF形式での契約書のやり取りが一般的になっています。電子契約は、業務効率の向上やコスト削減に寄与するだけでなく、法的にも有効です。 本記事では、PD…
詳しくみる電子契約の当事者型とは?立会人型との違いやメリット・デメリットを解説
電子契約システムは、当事者型と立会人型に大きく分けられます。契約方式によって手続きの流れや証拠力において異なるため、どちらが自社に適しているかを正しく判断することが必要です。 本記事では、電子契約の当事者型について詳しく解説します。 電子契…
詳しくみる合意締結証明書とは?電子契約での活用方法や記載事項を解説
近年、多くの企業や個人が契約業務の効率化とコスト削減を目指し、電子契約システムを導入しています。この新しい契約形態は利便性が高い一方、「法的に有効なのか」「締結の証拠は?」といった不安の声も聞かれます。 このような背景のもと、電子契約の信頼…
詳しくみる電子署名とタイムスタンプの違いは?仕組みや無料で付与する方法を解説
電子署名とタイムスタンプは、目的や役割、有効期限などに違いがあります。電子署名やタイムスタンプについて、電子契約の締結に必要な理由や、付与する方法がわからない方もいるでしょう。 この記事では、電子署名とタイムスタンプの役割や、無料で付与する…
詳しくみる