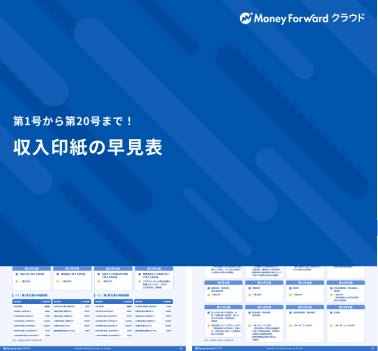- 更新日 : 2025年3月10日
収入印紙の金額は全部で31種類ある!郵便局・コンビニで買える印紙を解説
収入印紙とは、国に納める税金や手数料などを支払う目的で使用する証票のことです。1円や2円など少額のものから、最大で100,000円のものまで、全部で31種類あります。
本記事では、収入印紙の種類や購入できる場所や収入印紙が必要な書類と種類などについて解説します。
目次
収入印紙とは
収入印紙とは、印紙税などの納税のために使用する証憑のことです。
経済取引にともなって領収書や契約書などを作成する場合には、印紙税法に基づいて印紙税という税金が課せられます。収入印紙には紙幣のように金額が記載されており、納税金額分の印紙を書類に貼付することで、納税したことの証明となります。
収入印紙の金額は1円〜10万円で31種類ある
収入印紙の額面は、31種類です。その種類は、次で記載したように1円、2円……から最大で10万円のものまであります。
収入印紙の額面は、次のとおりです。
- 1円、2円、5円
- 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
- 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
- 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
- 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
- 100,000円
納税する際は、この31種類の中から必要に応じて額面を組み合わせて使用することになります。たとえば、1,500円であれば、1,000円と500円の組み合わせが一般的です。また、金額の組み合わせは不問であるため、手元に未使用の100円×5枚がある場合は、1,000円1枚を購入して、100円×5枚と組み合わせて1,500円とすることも問題ありません。
次項では、収入印紙を購入できる場所と種類について解説します。どこでも買えるわけではないため、注意しましょう。
収入印紙を購入できる場所と種類
収入印紙を購入できる場所としては、郵便局や法務局のほか、役所やコンビニなどがあります。ここでは、購入可能な場所と買える種類について解説します。
郵便局はすべての額面の収入印紙が購入できる
郵便局では、基本的に31種類すべての収入印紙を購入できます。ただし、郵便局の規模によっては取り扱っていない額面もあるため、事前に確認しておくようにしましょう。とくに、50,000円以上の収入印紙の取り扱いがない場合が多いようです。
50,000円以上の収入印紙を購入したい場合は、以下で紹介する他の施設の利用も検討しましょう。
郵便局で収入印紙を購入する際のポイントは、次のようなものがあります。
- 全国にあり、施設数が多い
- 平日9:00~17:00で施設を利用できる
- ほぼすべての種類の収入印紙を購入できる
なお、ゆうゆう窓口がある郵便局であれば、24時間収入印紙を購入可能です。
法務局もすべての額面の収入印紙が購入できる
収入印紙は、法務局でも購入可能です。法務局では、収入印紙の貼り付けが必要な登記関連などの書類を提出する機会があるため、収入印紙の売り場が設けられています。
法務局でも、基本的にはすべての額面の収入印紙を購入可能です。ただし、前述した郵便局のように施設数が多くないため、近くに法務局がある場合には候補となるでしょう。
市区町村の役所は一部の額面を購入できる
市区町村の役所でも収入印紙を購入することが可能です。
ただし、すべての市役所で販売しているわけではありません。さらに、販売している額面も役所によってそれぞれです。地域や規模などによって変わってきくるため、事前に自分の住んでいる役所で収入印紙の取り扱いがあるのか確認することをおすすめします。
また、役所は郵便局と同じく、平日しか営業していません。あわせて、営業時間の確認もしておきましょう。
コンビニは200円のみ購入できる
コンビニでも収入印紙を購入できます。ただし、コンビニでは購入可能な収入印紙の額が200円に限定されるため、それ以外の金額の収入印紙も必要な場合には、郵便局や法務局などに行くようにしましょう。
なお、すべてのコンビニで取り扱いがあるわけではないため、事前に確認しておくと安心です。
金券ショップや通販で購入できることも
収入印紙は、金券ショップや通販でも購入可能です。これらのサービスを利用するメリットとしては、額面より安い金額で購入できる可能性がある点が挙げられます。
金券ショップや通販では、利用しなかった収入印紙が販売されているため、通常よりも安価で購入することが可能です。しかし、必ずしも欲しいタイミングで出品されているわけではないことには、注意しましょう。
収入印紙が急ぎで必要な場合は、他の手段で購入することをおすすめします。
収入印紙が必要な書類と種類
収入印紙の貼り付けが必要な書類と種類について解説します。
領収書に貼る収入印紙の種類
商品の販売やサービスの提供を行った際に、領収書を発行するかと思います。領収書は税制上、印紙税額第17番文書と呼ばれ、やり取りした金額が大きいものについては収入印紙の貼り付けが義務付けられています。
領収書に収入印紙の貼付が必要なのは、受取金額が5万円を超える取引が行なわれたケースです。必要な収入印紙の額面は、取引の金額に応じて次の表のように変わります。
領収書に貼る収入印紙の金額表
| 領収書の記載金額 | 収入印紙の額面(税額) |
|---|---|
| 5万円未満 | 不要 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円以上200万円以下 | 400円 |
| 200万円以上300万円以下 | 600円 |
| 300万円以上500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円以上1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円以上2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円以上3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円以上1億円以下 | 2万円 |
参考:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
契約書に貼る収入印紙の種類
契約書の種類によって、収入印紙の貼り付けを求められることがあります。収入印紙の貼り付けが必要なのは、次のような契約書です。
- 不動産の売買や賃貸
- 土地の貸借権
- 債務保証
- 投資信託
- 業務委託
- 請負 などの契約書
不動産譲渡等に関するものや業務の請負に関する契約書では、契約金額にしたがって収入印紙の税額が変動するため注意が必要です。とくに不動産取引の契約では、高額になることもあるため、印紙税の金額を事前に確認しておくようにしましょう。
なお、投資信託や債務保証の契約書に貼付する収入印紙の額面は、基本的に200円です。
契約書に貼る収入印紙の金額表
契約書に貼付が必要な収入印紙の金額は、文書の種類と契約金額によって決まります。
印紙税法上、文書の種類は第1号から第20号までに分類されていますが、日常的な契約として特に使用頻度が高いのが第1号と第2号です。今回は、この2種類に課税される印紙税について説明します。
第1号文書の印紙税
第1号文書は、不動産売買契約、土地賃貸借契約、金銭貸借、運送契約の4つの契約に関する契約書において適用されます。
| 契約金額 | 収入印紙の額面(税額) |
|---|---|
| 1万円未満 | 不要 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 記載なし | 200円 |
参考:印紙税額|国税庁
1号文書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間、不動産譲渡に関する契約書には、印紙税の軽減措置が適用されます。
第2号文書の印紙税
第2号文書は、工事請負契約、広告契約、映画俳優専属契約などの、主に請負契約における契約書に適用されます。
| 契約金額 | 収入印紙の額面(税額) |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 記載なし | 200円 |
参考:印紙税額|国税庁
2号文書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間、建設工事の請負に関する契約書には、印紙税の軽減措置が適用されます。
手形に貼る収入印紙の種類
約束手形や為替手形などの手形にも収入印紙を貼る必要があります。手形とは、仕入れなどの際に一定金額の支払いを約束するために発行するものです。
現在は銀行口座による振替が採用されていることが多いため、約束手形、為替手形が使われるケースは多くありません。
なお、手形に金額の記載をしない場合は非課税となり、金額を記載する場合は金額に応じて収入印紙の額が変動します。10万円以下であれば非課税ですが、10万円以上100万円以下の取引では200円の収入印紙が必要です。
取引額が高額になるほど必要な収入印紙の金額も高くなるため、手形を発行する際には税額もあわせて確認しておきましょう。
他にも法人登記や株券の発行など様々な書類に収入印紙が使われている
収入印紙は、他にも法人登記や株券、社債などの書類にも貼り付ける必要があります。一例としては、次のような書類が挙げられます。
- 株式会社の定款の原本、保険証券
- 登録免許税や受験手数料、交付手数料など
国家試験の受験手数料や不動産登記の登録免許税などの場合は、専用の書類に収入印紙を貼付します。
収入印紙の金額は消費税の税抜価格が基準になる点に注意
契約書に印紙を貼る際、一定の条件を満たした場合には、契約の消費税抜きの金額を基準として印紙税が計算されます。
具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り、消費税額を除いた金額が印紙税の課税対象となります。
(1)消費税額が明確に区分記載されている
「110万円(うち消費税額10万円)」のように記載されている場合です。
(2)税込価格と税抜価格の両方が記載されていて、消費税額が明らかにわかるとき
「税込110万円(税抜100万円)」のように記載されている場合です。
上記に該当する場合には、100万円をもとに印紙税額が計算されます。
ただし、「110万円(消費税額等10%を含む)」や「110万円(税込)」などといった表記は、消費税額が明確ではないため、税込金額である110万円が印紙税の課税対象額となります。
さらに、この取り扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、請負に関する契約書、金銭または有価証券の受取書の3種類のみに適用されます。
契約書を作成する際は、消費税額を明確に区分記載する、または税込価格と税抜価格の両方を記載することで、印紙税を過剰に納めてしまうことを防ぎましょう。
収入印紙の貼り方
収入印紙の貼り方には法的な決まりはありません。そのため、該当書類の空白部分であればどこに貼り付けても有効になります。
市販の領収書など、あらかじめ収入印紙の貼り付け枠が印刷されている場合は、そこへ貼りましょう。貼り付け枠がない場合は、表題部分の左右の空白に張り付けるのが一般的です。複数枚収入印紙を張る場合は上下/左右に並べて貼りましょう。
また、同時に「消印」も行ってください。消印とは、収入印紙の上に捺印する印、署名のことです。印紙を貼った人間が誰であるかを表すほか、印紙が使用済みであることも示すものになります。
消印を施す際の注意点としては、印影が収入印紙と書類にまたがるように押印することです。誤った消印の押し方をした場合、過怠税の支払いが生じる恐れがあるため、あわせて正しい消印の押し方も理解しておきましょう。
収入印紙の種類を把握して適切に貼り付けよう
収入印紙の種類は、1円から100,000円まで31種類が存在します。収入印紙が必要な書類や必要な金額は書類によって異なるため、まずは必要な金額を把握するようにしましょう。
収入印紙を貼り付ける際は、組み合わせは問いません。また、貼り付ける場所にも規定はないため、本記事で紹介したように表紙や表題部分の左右いずれかの空白に張り付けましょう。
金額ミスや貼り付けミス、消印ミスなどを起こさないように、慎重に対応してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
契約書コピーの効力は?契約書の「収入印紙代」を簡単に節約できる3つの方法
「この契約書にはこの金額の収入印紙」普段、何気なく契約書に決まった額の収入印紙を貼っていませんか? 契約金額が高額であったり、同一の契約書を大量に作成したりする場合、収入印紙の額は馬鹿になりません。しかし、これらの収入印紙はちょっとした工夫…
詳しくみる収入印紙はどこで買える? 購入場所や注意点を解説
契約書や領収書で使用する収入印紙は、コンビニや郵便局など日常生活のさまざまな場所で購入できます。 一方で、購入時はキャッシュレス決済が使えないなどの注意点もありますが、電子契約であれば印紙の貼り付けが不要なため、経費削減と効率的な契約締結が…
詳しくみる解約合意書に印紙は不要?一部解約や変更の場合、必要な場合を解説
解約合意書は契約の消滅を証明する文書であるため、原則として印紙税は不要です。また、解約合意書への印紙の貼付は、金額によって必要な場合があり、印紙を貼る場所や、印紙税の負担者については注意が必要です。ここでは解約合意書に印紙は不要なのかどうか…
詳しくみる印紙税法とは?収入印紙が必要な契約書と金額、電子契約の場合を解説
契約書を作成する際に印紙税法に従って収入印紙を貼付しなければならないケースがあります。この記事では印紙税法の内容や収入印紙が必要となる契約書の種類や金額について解説します。最近普及してきている電子契約においても収入印紙が必要となるか否かにつ…
詳しくみる売買契約書に印紙は必要?金額はいくら?貼り方やどちらが負担するかを詳しく解説
課税文書の売買契約書には、収入印紙(印紙)が必要です。ただし、契約書の種類や記載されている金額などによって、印紙税額が異なることや印紙なし(非課税)になることがあります。 また、印紙を貼る際は割印を忘れずにしましょう。本記事では、売買契約書…
詳しくみる機密保持契約書に印紙は不要?必要な場合や秘密保持契約との違いを解説
機密保持契約書は、印紙税法の課税文書に該当しないため、印紙を貼る必要はありません。印紙なしが基本です。しかし、印紙が必要となる場合もあるため、注意してください。どんな場合に印紙が必要なのか、金額はいくらか、どちらが負担するか、貼る場所はどこ…
詳しくみる