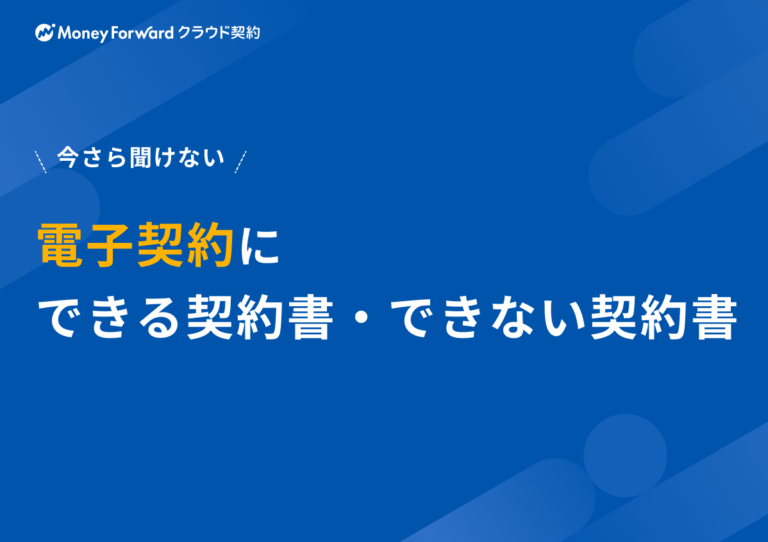- 更新日 : 2025年3月6日
借用書は電子契約にできる?電子化のメリットや注意点を解説
借用書は、電子契約化することが可能です。法律により、必ずしも紙の書類で作成せずとも、電子契約の中で作成した電子ファイルで借用書としての効力が認められます。
この記事では、借用書の基礎知識、借用書の記入必須事項、電子化のメリット・デメリットと注意点について解説します。一読すれば、借用書の電子化のイメージがつかめるでしょう。
目次
借用書は電子契約にできる
借用書は、民法第587条の2により、電子契約での締結が可能です。同条は、書面でする消費貸借について規定しており、4項に「消費貸借契約が電磁的記録(電子契約)によってされた場合は、書面によってされたものとみなす」と記載されています。借用書も消費貸借契約において交わされる書面なので、同条を適用して電子契約化が可能であるといえます。
したがって、消費貸借契約において交わされる借用書も、当事者双方が合意していれば電子契約によって締結できます。
なお、電子契約については以下の記事でくわしく解説しています。
借用書とは
借用書は、例えば金銭貸借契約などを締結した際に、借主が借金の返済を約束するために作成し、貸主に渡す書面です。金銭に限らず、物品の賃借においても発行されます。
作成する目的
借用書を作成する目的は、「貸し借りの内容を明確にする」「借主に返済義務をしっかりと意識させる」「トラブル発生時の証拠とする」などです。
「借りたお金をいつまでに返す」という約束は、口頭だけでも成立します。しかし、後になって「言った」「言わない」のトラブルになることもあります。
そこで、借用書という書面を作成し、返済金額や日時などを明確に書き記すことで、借主に返済義務をきちんと意識させ、万が一トラブルが発生した時もすぐに解決できるようにします。
法的な効力
借用書は、必要事項を記載し、適切な方法で作成されていれば法的な効力を有します。法的な効力を有するということは、借主の返済義務の根拠となるのです。
借用書で記入すべき必要事項は以下の通りです。
- タイトル(「借用書」など)
- 貸主の氏名・名称
- 借入金額・借入日
- 返済期日・返済方法
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失条項
- 借用書の作成日
- 借主の氏名、住所
最低でも上記の点は記載しましょう。もし、必要事項の記載がなかったり、不適切な方法(脅しなど)で作成されたりした場合は無効となる可能性があります。
金銭消費貸借契約書との違い
借用書と金銭消費貸借契約書の違いは、金銭消費貸借契約書が契約当事者双方の手元に保管される書面であるのに対し、借用書は借主側が貸主のために1通だけ作成する書面である点です。
金銭消費貸借契約書は、文字通り金銭消費貸借契約締結における当事者間の合意内容をまとめた書面です。したがって、貸主と借主の分の2通を作成し、双方が署名押印して保管します。
一方、借用書は、記載事項自体は金銭消費貸借契約書とほぼ同じですが、借主が1通作成し、それを貸主に渡す性質の書面です。
借用書を電子化するメリット
借用書を電子化するメリットとして、主に以下の3つのメリットがあります。
- 契約業務の効率化
- 郵送代や印紙代などのコスト削減
- 改ざん防止などセキュリティレベルの向上
以下、この3つのメリットについて詳しく説明します。
契約業務の効率化
借用書を電子化すると、紙で作成する際にかかる一連の作業の手間や時間が削減され、業務を効率化できるメリットがあります。
紙で借用書を作成する場合、印刷や製本、封入、宛名書き、郵送などの処理が必要です。一連の作業を終えるまでには一定程度の時間や人手も要します。
契約業務の電子化をすれば、借用書の印刷や製本などの必要がなく、オンラインで済ませられます。また、リアルタイムでステータスを確認できるため、記載事項の抜けや漏れを確認しやすくなります。相手に送付する際もメールで送ればよいので、郵便局に持っていくなどの手間を省けます。
郵送代や印紙代などのコスト削減
郵送代や印紙代などのコスト削減につながるのも電子化のメリットです。紙で借用書を作成すると、相手に送るための郵送費がかかります。また、紙の借用書は原則として印紙税法上の課税文書に該当するため、借入額によって決められた額の収入印紙の貼付が必要です。
借用書を電子化すれば、オンライン上で一連の手続きができるため、郵送費や印紙代がかかりません。多くの書類を郵送することを考えると、郵送費や印紙代がかからないだけでも大幅なコスト削減につながります。
改ざん防止などセキュリティレベルの向上
書面の改ざん防止など、セキュリティレベルが向上する点もメリットです。紙の借用書では、印刷したものを他部署や他社などの手に渡った際、内容の改ざんが行われるリスクがあります。当事者にとって不利益となる内容に改ざんされる恐れもあるでしょう。また、紙の借用書を動かすことで、外部に情報が漏れてしまう危険性もあります。
電子化をすれば、閲覧権限を厳しく設定するなど、セキュリティシステムが整った中で借用書を管理できます。セキュリティレベルが高ければ、内容を改ざんされたり、外部の人に見られたりといったリスクが大幅に削減できます。
借用書を電子化する際の注意点
借用書を電子化する際は、効力が無効とならないように注意すべきポイントがいくつかあります。
以下では、借用書の電子化で注意すべきポイントを3つ解説します。
保存形式の注意点
借用書を電子化した場合は、電子帳簿保存法の規定に従った保存形式を守らなければなりません。
まず、電子化した借用書を明瞭に読める状態にしておくため、ディスプレイやプリンターを備え付けなければなりません。また、借用書が真正なものであると証明するために、電子署名法の規定に従い署名する必要があります。
さらに、取引の日付・金額・取引先などですぐにデータを検索できるようにしておくことも求められます。
保存期間の注意点
借用書を電子化した場合は、紙の場合と同様に保存期限は7年間です。保存場所は、書面の作成ややりとりが行われた納税地です。
保存の際は、いざという時のためにバックアップデータをとっておきましょう。バックアップデータの保存については法律で決められているわけではありませんが、データの紛失や消失が起きた時のための対策として推奨されています。
バックアップデータの保存場所は、納税地にあるデバイスからアクセスできれば、パソコンのサーバー内やクラウドサービス上でも保存が可能です。
電子契約システムの導入が必要
借用書を電子化する場合は、電子契約システム上で一連の作業を行うため、当該システムを社内に導入する必要があります。
自社で電子契約システムを構築できる場合は別ですが、そのような経験のない会社であれば、他社が提供する電子契約システムを導入するとよいでしょう。
借用書を電子化する方法
借用書を電子化する方法を解説します。手順は大きく分けて3つあり、いずれも電子契約システム上で一元化できる作業です。
書面をPDFファイルに変換する
借用書を作成したら、まずはPDFファイルに変換します。PDFファイルにするのは、データ形式を統一して管理しやすくするためと、使用しているアプリやソフトに関わらずオンライン上で閲覧しやすくするためです。また、契約内容の書き換えをしにくくする目的もあります。
書面を電子契約システムに取り込む
借用書をPDFファイルに変換したら、電子契約システムに取り込みましょう。電子契約システムは、契約の電子化におけるさまざまな業務をパソコンやオンライン上で作業できるシステムです。
システム上で管理することで、契約内容の確認やメールでの通知、電子署名や保管といった一連の業務を一元化できます。
電子契約システム上で借用書を作成する
書面を電子契約システムに取り込んだら、同システム上で借用書を作成します。作成の際は、特定の人だけがアクセスや書き換えできるようセキュリティを設定しておきましょう。
システム上で借用書を作成したら、電子署名をします。一連の作業を終えたら相手方にメールなどで通知し、確認してもらいます。
マネーフォワード クラウド契約なら借用書も電子化できる
マネーフォワード クラウド契約であれば、借用書を電子化できます。また、金銭消費貸借契約に関する一連の業務もスムーズに電子化することが可能です。
特に、以下の3つの点から電子化をサポートします。各ポイントについて紹介します。
紙の書面と電子契約をまとめて管理
マネーフォワード クラウド契約であれば、電子契約はもちろん、紙の契約書もまとめて管理できるため、効率的に業務を進められます。
また、他社の電子契約サービスから受領する電子ファイルやデータも、自動で取り込むことが可能です。書類の保管場所を確保したり、ファイリングの作業をしたりといった手間と時間を削減できます。
電子化業務をワンストップで完結
マネーフォワード クラウド契約では、借用書の作成からシステムへの取り込み、署名、保存、管理までを一括して完結させることが可能です。「借用書を電子化したいが、何をどのように進めればよいかわからない」という場合でも、一からサポートします。
また、1つの画面で一連の作業を完結できるため、電子化に慣れない方でも使いやすいメリットがあります。
借用書の管理・保存
マネーフォワード クラウド契約では、電子システム上に契約管理に必要な情報をまとめて管理・保存できます。
また、過去の借用書も絞り込み検索が可能です。相手方の名称や借入額、返済日といった項目から絞り込めます。絞り込み項目は自由にカスタマイズ可能です。
さらに、電子化した書面ごとに閲覧権限を付与できるため、セキュリティ面も安心です。
借用書の電子化でコスト削減を実現
借用書は、電子化できることが法律で認められています。借用書を電子化すれば、書類の印刷や郵送といった作業の手間が省けたり、印紙代が節約できたりするなどのメリットがあります。電子契約システムで業務を一元化すれば、大幅なコスト削減が期待できるでしょう。
また、借用書にまつわるさまざまな手間やコストを軽減できるため、業務効率化にもつながります。電子契約化を進めたいがどのようにすればよいかわからないという場合は、しっかりサポートしてくれる電子契約システムの導入を検討してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
電子契約を変更契約するには?書面と電子の変更方法について解説
ビジネスにおいて、一度締結した契約について、後から内容を変更したいという状況は決して少なくありません。特に近年、多くの企業で導入が進んでいる電子契約においても、こうした変更の必要性は当然発生します。 「電子契約の場合、どのように変更すれば良…
詳しくみるIT重説実施に関する同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
宅地建物取引業者などが「IT重説」を行う際には、相手方から同意書を取得する必要があります。法律の規制内容を踏まえて、ひな形をもとに、適切な形式の同意書を準備しましょう。本記事では、IT重説の実施に関する同意書の書き方や、同意書を作成する際の…
詳しくみるクラウド型の契約書管理システムのおすすめは?メリット、デメリットや比較ポイントを解説
契約書管理をクラウド上で行うと、法改正に自動で対応できる、管理コストを抑えられる、リモートアクセスができるなどのメリットがあります。料金体系・操作性・機能・サポート・セキュリティなどを総合的に考慮して、導入するクラウド型の契約書管理システム…
詳しくみる土地売買契約書の電子契約の流れは?電子化する方法やデメリットも解説
2022年5月の宅建業法改正により、土地売買契約書の電子契約が全面的に解禁されました。相手方の承諾を得れば、重要事項説明書から契約書まで、ほぼすべての書類を電子化して契約を締結できます。 本記事では、土地売買契約書の電子化に関する法的根拠か…
詳しくみるWordで電子署名する方法は?手書きやMacでのやり方、法的効力を解説
Wordで電子署名をする方法には、デジタルIDを利用した方法や手書きの署名を挿入する方法があります。WindowsとMacのそれぞれで異なる手順が必要な場合もあり、法的効力についても理解しておくことが重要です。 本記事では、Wordでの電子…
詳しくみる電子サインとは?電子署名との違いや作り方、導入までの流れをわかりやすく解説
電子サインとは、従来は紙の書類で行っていた同意や承認、本人証明などの認証を電子上で行うプロセス、および電子形式で記録したもののことを広く意味するものです。ペーパーレス化が進む近年のビジネスシーンにおいて、電子サインの導入は重要です。本記事で…
詳しくみる